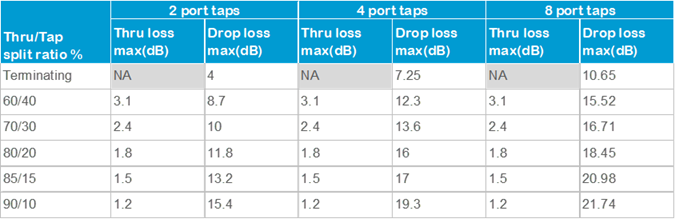2.1.1 HFC�P�[�u���`���Z�p�̍��x��
2.1.2 DVB-C2�i���x�ȃf�W�^���L���e���r�W�������������j
2.2.3 ���`���ւ̃}�C�O���[�V����
2.3.1 �����P�[�u�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p
2.4 �V����FTTH�\�z�\�����[�V����
2.4.2 ���z���^�b�v��p�����A���C�[�u���A�[�L�e�N�`���R�l�N�^�\�����[�V����
2.4.3 MDU�ł̃R�l�N�^�\�����[�V�������p
2.5.1 BWA�iBroadband Wireless Access�j�F
��2�� �C���t���Z�p
2.1�@ HFC�`���Z�p
2.1.1�@ HFC�P�[�u���`���Z�p�̍��x��
�ʐM���x�̍������̂��߂ɕK�v�ȋZ�p�Ƃ��āAHFC�`���H�̍��x���A�ϒ��E�������Z�p�̍��x���A�����̋Z�p���̗p����DVB-C2�i���x�ȃf�W�^���L���e���r�W�������������j��DOCSIS 3.1�ADOCSIS4.0�ɂ��ċL�q����B
2.1.1.1�@ HFC�`���H�̍��x��
(1) HFC���x���i������HFC�j
HFC���x���́A������HFC�Ƃ��Ă�A���Z�����i1�Z�����̉ƒ��100�����x�܂Ō��炷�j�Ɠ����`���ш��1GHz���x�܂ōL�ш扻���邱�Ƃł���B�������Z�����E�L�ш扻��HFC���\������o�����A���v�̌����ɂ��A�ʐM���x�̌����CN�䓙�̓`�����\�̌��オ���҂ł���B
���Z�������s�����߂ɁA���m�[�h�ȉ��̑o�����A���v��0���邢��1�Ƃ��iNODE 0/NODE+1�Ƃ��Ă��j�A���P�[�u���̋����������A�����P�[�u���̋��������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���Fiber Deep�Ƃ��Ă��B�܂��A�����P�[�u���i���g����1/2��ɔ�Ⴕ�Č����ʂ���������j�̋������Z���Ȃ邽�߁A1GHz�ȏ�̎��g���܂ŒʐM�Ɏg����悤�ɂȂ�BDOCSIS 3.0�̉�����g����108�`1002MHz�ADOCSIS 3.1�̉�����g����258�`1218MHz�iMUST/�K�{�j���邢��108�`1794MHz�iSHOULD/�����EMAY/�C�ӂ��܂ށj�ƂȂ��Ă���i�ڍׂ�2.1.3�@DOCSIS 3.1�Q�Ɓj�B
2.1.1.2�@ �ϒ��E�������Z�p�̍��x��
�]���A�P�[�u���̕����ƒʐM�iDOCSIS 3.0�ȑO�j�̕����w�́AITU-T����J.83�ɏ�������QAM�ƒZ�k�����[�h�E�\����������RS�i204�A188�j�������Z�p��p���Ă����B�ŋ߁A�������Z�p�ɂ�BCH�u���b�N�����ƒᖧ�x�p���e�B�`�F�b�N�����iLDPC�j���p�����Ă���B���̌������Z�p��p����ƁACN��Ŗ�7dB�̉��P���ʂ�����A���݂�64QAM�̏��vCN���256QAM�����p�ł��邱�Ƃ���A��1.33�{�̓`�����\�ƂȂ�B����ɁADVB-C2�����DOCSIS 3.1�ł́A4096QAM���̑��l�ϒ����K�肳��Ă���B
�܂��A�ʐM�̍������iDOCSIS 3.0�j������̓`���e�ʊg��̂��߂ɁA�V���O���L�����AQAM�̕����̃`���l�����{���f�B���O������@�����邪�A�ŐV��Wi-Fi��DVB-C2�ADOCSIS 3.1�ł�OFDM���g���āA�A������`���l���̊Ԃ̋ш�ɂ������g�ߍ��ނ��Ƃœ`���e�ʂ̊g�傪�s���Ă���B
�����OFDM��BCH�{LDPC�������������̗p���A�ϒ��̑��l���ɂ�鍂�����`���\�Ƃ����B����BCH�{LDPC�����������́A���B�̕����K�i�iDVB�FDigital Video Broadcasting�j�̉q���E�n��E�P�[�u���̑��ł���DVB-S2�EDVB-T2�EDVB-C2����{�̉q�������̍��x�������ɍ̗p����A�ʐM�ł�DOCSIS 3.1�ɍ̗p����Ă���B�܂��AOFDM�ɂ��`���́ADVB-C2�ADOCSIS 3.1��EPoC�ō̗p����AOFDM�̃}���`�L�����A�����̓��������āA6MHz�ш�̘g���ĔC�ӂ̑ш�����R�Ɏg�p�\�ȋK�i�E�d�l�ƂȂ��Ă���B
�@ OFDM
���s�̃V���O���L�����AQAM�����ł́A6MHz�Ȃǂ̕����ш敝�ɐM���ш�𐧌����邽�߂Ƀ��[���I�t���Ɉˑ����Ă������AOFDM�ł͒��������T�u�L�����A�𖧂ɓ`�����邽�߁A�K�[�h�o���h���}�s�ȓ����������A�ш�d�l�������ǂ��Ȃ�B�܂��A�`���H�̔��˂���g�������̕�ɍۂ��Ď�M���ŗp������g�`�����ɂ����āA�V���O���L�����AQAM�����ł͊�M�����Ȃ��u���C���h�����̂��߂�1024QAM�ȏ�̑��lQAM�͎�������ł��邪�AOFDM�ł̓p�C���b�g�M���iContinual pilot��Scattered pilot�j����Ƃ����g�`�����ɂ����4096QAM�ȏ�̑��lQAM�������\�ƂȂ��Ă���B
����ɁAOFDM�̃T�u�L�����A��6MHz�ш�̘g���ĔC�ӂ̑ш�܂Ŋg��i�ш�A���j�ł��i6MHz�ш�Ԃ̃K�[�h�o���h���s�v�j�A����Ȃ�ш�d�l�������ǂ��Ȃ�B�܂��A6MHz�ш���Ɋ��g�������݂���ꍇ�A���s�̃V���O���L�����AQAM�����ł͂��̃`�����l���͎g�p�ł��Ȃ��������i��������`�����l���j�AOFDM�ł͂��̊��g�������݂�����g�������݂̂�����āA����ȊO�̕����ŃT�u�L�����A��p���ă`�����l�����̈ꕔ��L�����p�ł���B
DOCSIS 3.1��EPoC�ł́A6MHz�ш�̘g���ĔC�ӂ̑ш�i1MHz�P�ʁj�ŁA�����̕�����ʐM�Ŏg�p����Ă���ш������ė��p�\�ƂȂ��Ă���B�܂��A���Ɖ���̑o�����̒ʐM���p�ш���A����ш�i���10�`55MHz�A����70�`770MHz�j����A�V�K�ш�1�i���5�`65MHz�Ɖ���76�`1000MHz�j��V�K�ш�2�i���5�`204MHz�A����268�`1218MHz�j�Ȃǂ̎��R�ȑш�ŕύX�\�ƂȂ��Ă���B�������A���p�ш�̕ύX�ł́AHFC���\�����Ă���o�����A���v�̏��/���蕪�����g����ύX����K�v������B
�A BCH�{LDPC�������Z�p
���݂̃f�W�^�������ł́A�Z�k�����[�h�E�\����������RS�i204�A188�j��p���Ă��邪�A�ŋ߂ł�BCH�������p�u���b�N�����ƒᖧ�x�p���e�B�`�F�b�N�����iLDPC�j���p�����Ă���B
BCH�������p�u���b�N�����Ƃ́A�J���ҁiBose�EChaudhuri�EHocqenghem�G�{�[�Y�A�`���h�[���A�{�b�P���W�F���j�̖��ɗR������u���b�N�����������iBCH�̂ق��A�n�~���O������[�h�E�\����������������j�ł���A�u���b�N�P�ʂɓ���̐������������g���ē����p���e�B�r�b�g��t�����ē`������B�Ⴆ�ABCH�i15�A11�j�ł͐�����������G(x) = x4 + x + 1 ��p���āA�f�[�^���i���r�b�g���j��11�r�b�g�A�璷�r�b�g����4�r�b�g��1�r�b�g�̌��������ł���B�ᖧ�x�p���e�B�`�F�b�N�����iLDPC�FLow-Density Parity-Check�j�́A�p���e�B�`�F�b�N�����̈��ł���BLow-Density�i�ᖧ�x�j�Ƃ́A�������ɑ���1�����r�b�g�������Ȃ��Ƃ������Ƃł���AParity-Check�ł́A�r�b�g��̈��P�ʂ̒��ɂ���1�̐����A������������`�F�b�N���邱�ƂŌ��肷�邱�Ƃɂ���BLDPC�́A���ɑa�Ȍ����s��ɂ���`���ꂽ���`�����ł���B�a�ȍs��Ƃ́A�s�����1�̐������ɏ��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�����s�����1�̐������Ȃ����Ƃ́A���Z�ʂ����Ȃ����Ƃ��Ӗ������������邱�Ƃ��e�ՂɂȂ��Ă���B
���̋Z�p��p����ƁA��q�iDVB-C2���} 2‑1���邢��2.1.3�@DOCSIS 3.1���} 2‑8�j�Ŏ����悤�ɁA�����`�����x�ŏ��vCN�䂪��7dB���Ȃ�Shannon���E�l�܂�2dB�Ɣ����Ă���B
DVB-C2�ł́A�������̃u���b�N��������2��ޗp�ӂ���Ă���A������������Normal Code�i�������\�͂��������x���ʑ�j�ƕ��������Z��Short Code�i�������\�͂����܂荂���Ȃ����x���ʏ��j����������Ă��邪�A�ʏ�Nomal Code���g�p����B
DOCSIS 3.1�i����j�ł́A�ʐM�ŗ��p����ۂ̒x���ʍ팸�̂��߂�DVB-C2�ɂ�����Short code�݂̂�p���ALDPC����������8/9�݂̂Ƃ��āA�n�[�h�E�F�A�̕��G����������Ă���i��q���} 2‑6�Q�Ɓj�B
2.1.2�@ DVB-C2�i���x�ȃf�W�^���L���e���r�W�������������j
DVB�́A���B�̃f�W�^�����������̕W�����g�D�A����т����ō��肳�ꂽ�W���K�i���w���ADVB�K�i�Ă͉��B�ʐM�W��������iETSI�FEuropean Telecommunications Standards Institute�j�ɒ�o����A���B����̋K�i�ƂȂ�BDVB�W���K�i�́A���B�ȊO���܂ߑ����̍��ō̗p����Ă���A�����K�iDVB-C�́A�O�N1993�N�ɐ��肳�ꂽDVB-S����ɁA1994�N�ɐ��肳�ꂽ�B���{�̃P�[�u���d�l�ł�������Q�Ƃ��AJ.83�gAnnex C�h�Ƃ��ċK�i������Ă���B���Ȃ݂�DVB-C�͓�����J.83�gAnnex A�h�Ƃ��ċK�i������Ă���B
DVB-C2�́A��2����f�W�^���P�[�u���K�i�Ƃ���2009�N�ɋK�i�����������A���N2010�N�Ɏ��p�������ɒ��肵���B2011�N11���ɂ́A����LSI�̏o�ׂ��J�n����Ă���B�܂�2013�N2���ɕ]�����������{���A���̌��ʂ������ċK�i�����ŏI�łƂȂ��Ă���B���̌�2013�N6���ɂ́A���B�̎��ƎҁiKabel Deutschland�j�ɂ����āADVB-C2�ł̎����������J�n���ꂽ�i�����F1024QAM�A��������3/4�j�B
DVB-C2�̑傫�ȓ����Ƃ��āA�L�����A�`��������OFDM���̗p�������ƂƁA������������LDPC���̗p�������Ƃ���������B�����́A�q���K�i��DVB-S2/�n��g�K�i��DVB-T2�ō̗p���ꂽ���̂����̂܂܁ADVB-C2�ł��̗p�������̂ł���B
�������s�K�i�ł́A�ϒ������̓V���O���L�����A��64QAM/256QAM�ł��邪�ADVB-C2�̓}���`�L�����A��OFDM�����ł���A�ш���ɕ����̃T�u�L�����A�𗧂āA���ꂼ��16QAM����4096QAM�܂ł̑��lQAM��I���\�ł���B�������́A�]����Reed-Solomon�����ɑւ��ADVB-C2�ł͓������Ƃ���LDPC�A�O�����ɂ�BCH���̗p���Ă���BLDPC����������2/3����9/10�܂ł�5��ނ�����B
�M���ш敝�́A�ő�l�Ƃ���8MHz��6MHz����I���ł���悤�ɂȂ��Ă���B���̍ő�ш敝�ɂ�����L�����A���̍ő�l��8MHz��6MHz�Ƃœ���3408�Ƃ��Ă���A�L�����A�������炷���Ƃɂ��ш敝��C�ӂɌ��炷���Ƃ��\�ł���B�L�����A���̍ő�l��8MHz��6MHz�Ƃœ����ł���̂ŁA�L�����A�Ԋu��8MHz�̏ꍇ��2.23kHz�A6MHz��1.67kHz�ŌŒ�ƂȂ�B
DVB-C2�̓`��������DVB-C����ь��s�����K���K�i�ł���J.83 Annex C�Ɣ�r�����\ 2‑1�Ɏ����A���\��r�Ƃ��ď��vCN��Ɠ`�����x���} 2‑1�Ɏ����B
�\ 2‑1�@DVB-C2��DVB-C�̕�����r
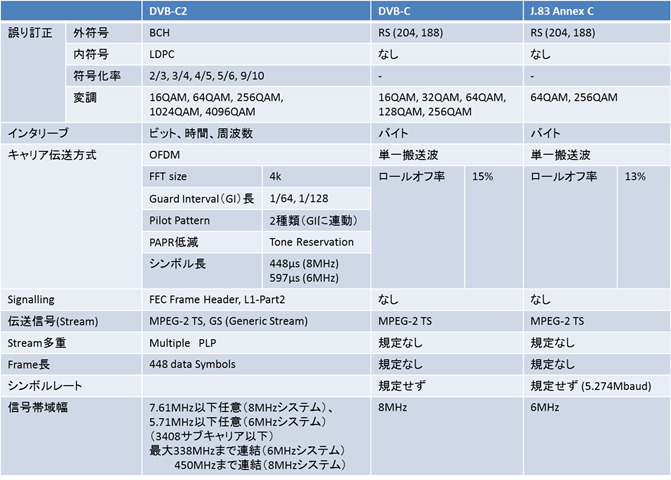
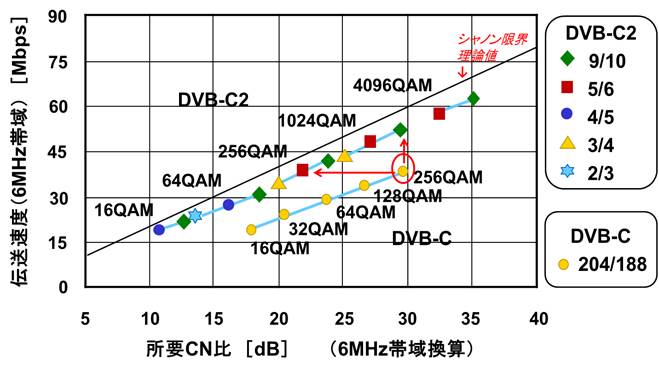
�} 2‑1�@DVB-C2��DVB-C�Ƃ̐��\��r
�} 2‑1�́ADVB-C2�̓������悭�\�����̂Ƃ��ėp��������̂ł���B�����Ŏ������V���m�����E�́AShannon�������ʐM�ɂ�����`���e�ʂ̗��_���E�l�ł���A���s��DVB-C�i6MHz���Z�j�͗��_�l�ɑ��Ă܂��u���肪���邪�ADVB-C2�͗��_���E�ɂ��Ȃ�߂Â������`��������B�����Ă���B
����̉^�p�ŗp�����Ă���64QAM�Ə��vCN�䂪�����ꍇ�A3�����̓`�����x��������B���s��256QAM�̓`�����x���g���������A���vCN�䂪���������^�p�ł��Ȃ��ꍇ�ł��ADVB-C2�ɂ����Ă�256QAM/��������4/5�ł�7dB�ႢCN��ł��\�ł���B�܂�����256QAM�^�p���\�ȏꍇ�AC2�ł�1024QAM/��������9/10���g�p�ł���B
ITU-T���ەW�����ɂ����ẮA������P�[�u���`�������̗v������J.381�Ɋ�Â��`�������̎d�l�K��Ƃ��āADVB-C2�ɏ�������V�K����J.382��2013�N12���Ɋ��������ꂽ�B�Ȃ�2017�N10���̎��_�ɂ����ẮA�{�������̗p�������i�͓��{�����ł͎s�̂���Ă��Ȃ��B
2.1.3�@ DOCSIS 3.1
DOCSIS�iData Over Cable System Interface Specification�j��HFC��ō����f�[�^�T�[�r�X����邽�߂̃V�X�e���d�l�ŁA���̏��Łi1.0�Łj�͕č��P�[�u�����{��1997�N3���ɍ��肵���B���̌�AQoS�@�\�̒lj��i1.1�ŁA1999�N4���j�A���ϒ������̒lj��ɂ����g�����p�����ib/s/Hz�j�̉��P�i2.0�ŁA2001�N12���j�A�`���l���{���f�B���O�@�\�̒lj��i3.0�ŁA2006�N8���j�Ƃ������������d�ˁA2013�N10���ɂ͍ŐV��3.1�ł������[�X����Ă���B
DOCSIS 3.1�́AOFDM��LDPC�̗̍p�ɂ��DOCSIS 3.0�ɔ�ׂĎ��g�����p������3���ȏ���シ��Ƌ��ɁAHFC�̏�����g�����ő�1.8GHz�܂Ŋg�����邱�Ƃɂ��`���e�ʂ̔���I�Ȋg���}���Ă���B���Ȃ킿�A�W���I�Ȑݔ��\���ʼn���5Gbps�A���1Gbps�̓`���e�ʂ̎������������Ă���B�܂��A�]���̃V���O���L�����AQAM�ϕ��������萔�����邱�Ƃɂ��DOCSIS 3.0�Ƃ̋������\�Ƃ��Ă���̂������ł���ADOCSIS 3.0�Ƃ͐���̈قȂ�Z�p���̗p���Ă���ɂ��ւ�炸DOCSIS 3.1�ƌď̂��Ă��鏊�Ȃł���B[1]
DOCSIS 3.0��3.1�ł̑傫�ȈႢ�́A�\ 2‑2�Ɏ����悤�ɁA�`���������V���O���L�����AQAM����OFDM�ɂȂ������ƁA���͂Ȍ����������ł���LDPC�̓����ɂ��ő命�l�ϒ�������4096QAM�i�I�v�V�����ł�16384QAM�܂Łj�Ƃ������ƁA�܂��AOFDM�̗̍p�ɔ�����6MHz�̃`�����l���T�O��P�p���A�ő�192MHz�i����j�A96MHz�i���j���V�X�e��������̍ő���g���ш敝�Ƃ����_���ł���B
�\ 2‑2�@DOCSIS 3.0/3.1��r
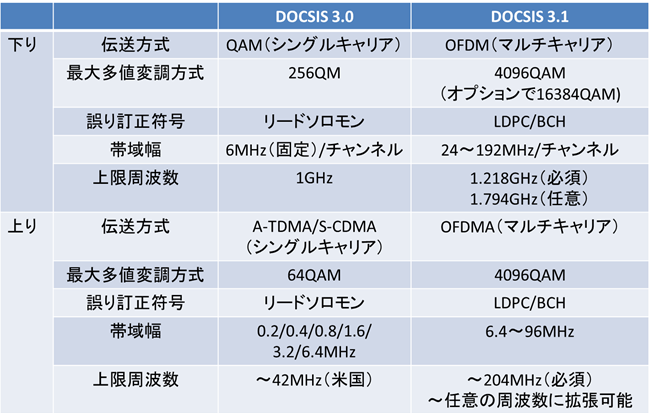
DOCSIS 3.1���p������g�����Ɏ����B����ш�́A3.0���p����108�`258MHz���g���ш�i�����j�A258�`1218MHz��K�{�Ƃ��A�����1218�`1794MHz���g���ш�i�C�Ӂj�Ƃ��Ă���B����5�`204MHz��K�{�Ƃ�����ŁA204MHz�ȏ�̑ш�͏�������߂��ɔC�ӂɊg���\�Ƃ��Ă���B
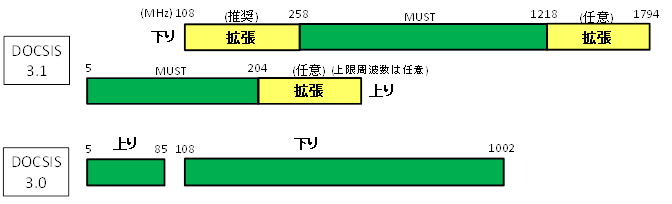
�} 2‑2 �@DOCSIS 3.1/3.0�̎��g��
DOCSIS 3.1�ɂ���e�ʉ��́A�`�������̍��x���ɉ����A���̂悤��HFC�ш�̊g����O��Ƃ��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���A�ȉ��̉ۑ�ւ̑Ή����K�v�ƂȂ�B
�E�g���ш�ʼn^�p���̖����V�X�e���Ƃ̊Ԃ̔튱�E�^���ւ̑Ή�
�E���E����̑ш�ύX�ɔ������p������̒u��
�܂��A���l�ϒ���p���邽�߂ɂ͎�M�[�ɂ�����CN��̉��P���K�v�ƂȂ�A���̂��߂ɃP�[�u�����f���iCM�j�������ґ���̋��E�_�ɒu������iGateway Architecture�Ə̂���j�AHFC�̏��Z����������������̊g��iFiber Deep���ƌď́j���̕���ɂ��`���HCN������P���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
DOCSIS 3.1�̉��肨��я��d�l�T�v�����ꂼ���\ 2‑3�A�\ 2‑4�Ɏ����B
�\ 2‑3�@DOCSIS 3.1�d�l�T�v�i����j
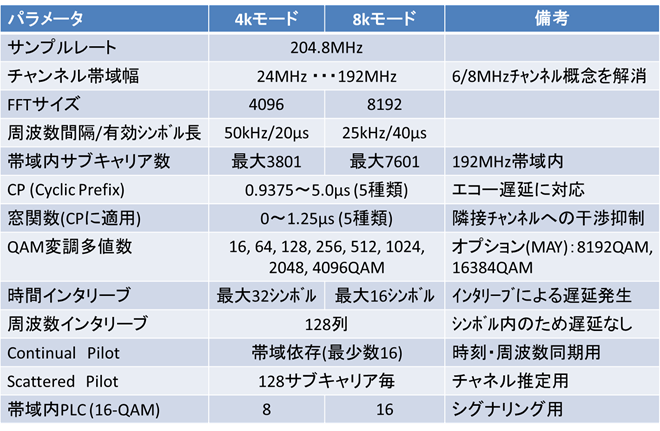
�\ 2‑4�@DOCSIS 3.1�d�l�T�v�i���j
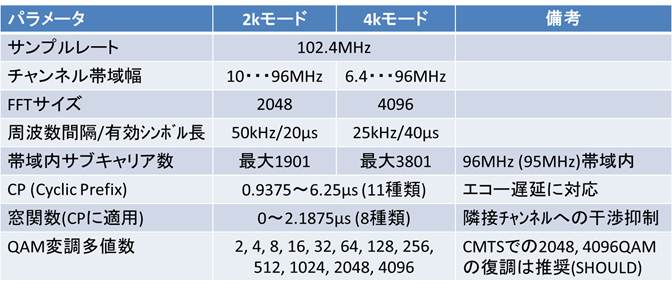
�\ 2‑3�A�\ 2‑4��2k/4k/8k���[�h��FFT�T�C�Y�������A���E���肻�ꂼ���2��ނ�FFT�T�C�Y���K�肳��Ă��邪�A���ۂ̉^�p���ɍ��킹�ēK��FFT�T�C�Y��I�����邱�Ƃ����߂���B�Ⴆ�A����8k���[�h�ł̓T�u�L�����A�̎��g���Ԋu��25kHz�ƂȂ�A4k���[�h��50kHz�ɔ�ׂĂ�肫�ߍׂ������g���̉�����\�ƂȂ�B�܂��A�V���{�����͒���������ɏq�ׂ�K�[�h�C���^�[�o���iCyclic Prefix�FCP�j�̕t�^�ɂ��`���e�ʒቺ�̉e�������Ȃ��ł��邪�A���̔��ʃC���p���X���̃m�C�Y�̉e�����₷���Ȃ�A�����l�����ׂ��_�ł���B
�Ȃ��A����4k���[�h�ł�4096�{�̃T�u�L�����A����������邪�A192MHz�̑ш���ɔz�u�����͍̂ő��3801�{�ŁA���[��295�{�͓d�͂�^����ꂸ�A���p����Ȃ��i�} 2‑3�j�B���̏�Ԃ̃T�u�L�����A��Excluded�i���O�j�T�u�L�����A�ƌĂԁB�ш����QAM�`�����l����z�u������A����̑ш�ɑ��݂��銱�g�������ꍇ�ɂ��Y������T�u�L�����A��Excluded��Ԃɂ���B
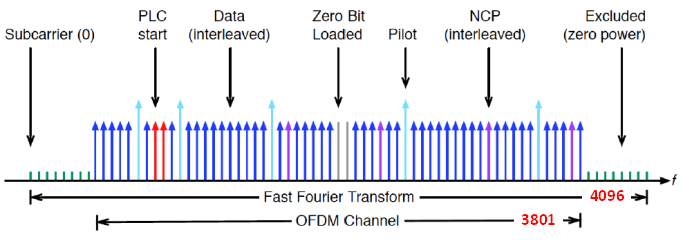
�} 2‑3�@DOCSIS 3.1�̃X�y�N�g����
DOCSIS 3.1�̃V�X�e���v�����} 2‑4�Ɏ����B���E���苤�ɁA��Ɏ�����OFDM�e2�`�����l���Ƌ��ɁA����͏]����QAM�`�����l��24�A����QAM�`�����l��8���������邱�ƂƂ��Ă���B�����āACMTS�iCable Modem Termination System�j��S-CDMA���[�h�̏�������T�|�[�g���邱�Ƃ𐄏����Ă���B
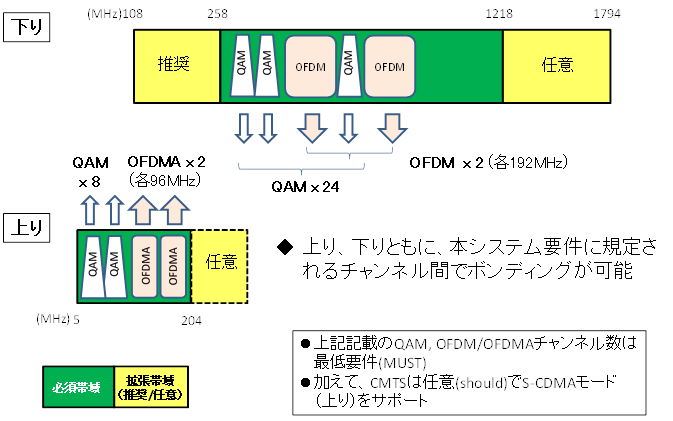
�} 2‑4�@DOCSIS 3.1�̃V�X�e���v��
2.1.3.1�@ DOCSIS 3.1��PHY�i����j
DOCSIS 3.1�̉���PHY�@�\�̃u���b�N�}���} 2‑5�Ɏ����B
�M���̓f�[�^��i���j�ƃV�O�i�����O�@�\��S��PLC�iPhysical Layer Signaling Channel�j�ɕ������A���ꂼ�ꂪ�������iFEC�j�AI/Q�A�X�N�����u���A�C���^�[���[�u���̏������o�č������ꂽ��A�t�t�[���G�ϊ��iIDFT/IFFT�j�ɂ����OFDM�T�u�L�����A����������A�K�[�h�C���^�[�o���iCP�j����ё������t�������B
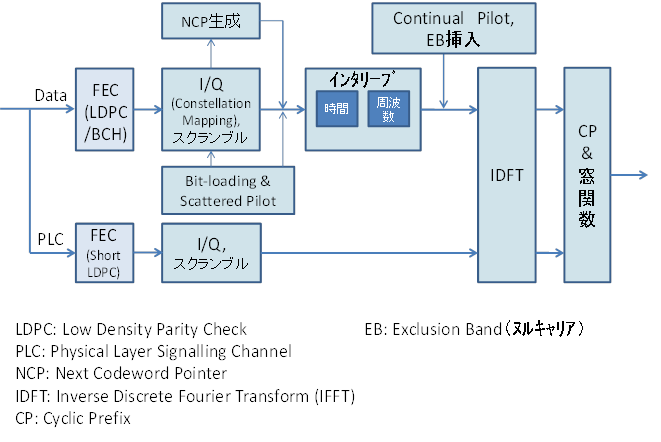
�} 2‑5�@DOCSIS 3.1����PHY�@�\�u���b�N�}
�ȉ��A�e�@�\�ɂ��ĊT������B
(1) FEC�i����j
DOCSIS 3.1�̉���ł��} 2‑6�Ɏ����悤�ɁA�����������iFEC�j�Ƃ��ĊO����BCH�A������LDPC��p���Ă���B����͊�{�I�ɂ�DVB-C2�d�l��6.1��[2]�Ɠ��l�ł��邪�ADVB-C2�ł�64800�r�b�g�̕�������Normal Code�Ƃ��ėp����̂ɑ��āADOCSIS 3.1�ɂ����ẮADVB-C2�ł�Short code�ƌĂ��16200�r�b�g�̕������݂̂�p���ALDPC����������8/9�݂̂Ƃ��āA�ʐM���p���̒x���팸�ƂƂ��Ƀn�[�h�E�F�A�̕��G����������Ă���B
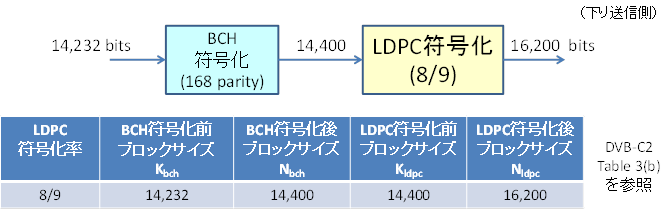
�} 2‑6�@DOCSIS 3.1����FEC
(2) ���l�ϒ������i����j
�`���V�X�e���ł́A�ʏ�A�`���H��CN��ɍ��킹�Č������̕��������Ƒ��l�ϒ��̑g���������邱�Ƃɂ��`�����\�̍œK����}�邱�Ƃ��������ADOCSIS 3.1�ł͕����������Œ肵�A���̑���ɔ��`�ϒ��i128QAM�A512QAM�A2048QAM�j����э����ϒ��imixed modulation�j��p���邱�Ƃɂ��`���HCN�ւ̑Ή����s���Ă���B���̓_��DVB-C2�ɂ͂Ȃ�DOCSIS 3.1�̓����ł���B
���`�ϒ��̗�Ƃ���512QAM�̃R���X�e���[�V�������} 2‑7�Ɏ����B
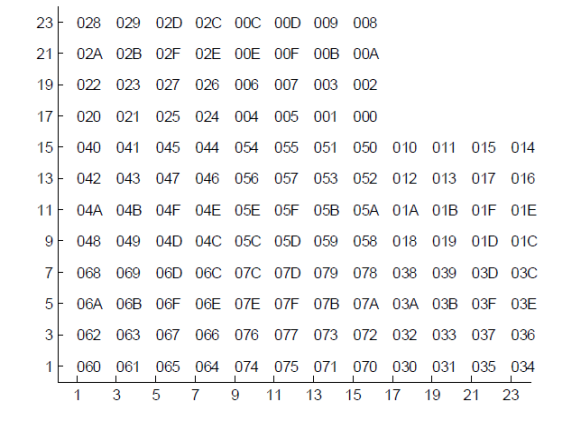
�} 2‑7�@���`�ϒ��̗�i512QAM�j
�����ϒ��́A512/1024QAM�A1024/2048QAM�A2048/4096QAM�̂悤�ɈقȂ鑽�l�ϒ������g������A���Ԏ���ō��݂����ėp���邱�Ƃɂ��A���ԓI�ȏ��vCN���m�ۂ���Z�p�ł���B
DOCSIS 3.1�ł́A�ʏ�̑��l�ϒ��ɔ��`�ϒ�����э����ϒ��������邱�Ƃɂ�菊�vCN��̗��x�igranuality�j��1.5dB���݂Ŏ������Ă���B
�} 2‑8�ɕϒ������i�`���e�ʁj�Ə��vCN��̊W�������B
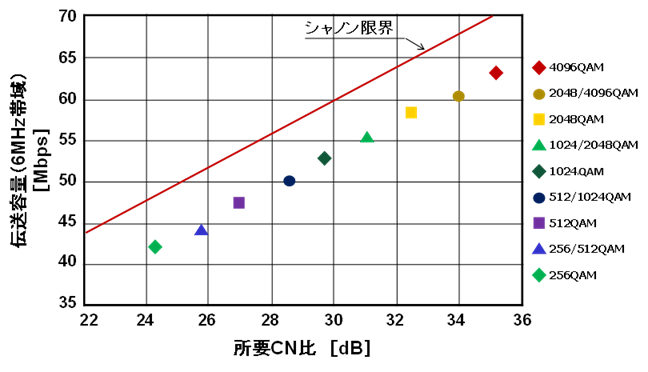
�} 2‑8�@�ϒ����l���Ə��vCN��̊W
(3) �ϒ��v���t�@�C��
DOCISIS 3.1�ł́A��M�_�œ�����CN��ɍ��킹��OFDM�T�u�L�����A�̕ϒ����l�����w��ł���B�����ϒ����l����L����T�u�L�����A�̏W�܂��ϒ��v���t�@�C���iprofile�j�ƌĂсAA����P�܂ł�16��ނ��K�肳���BProfile A��CM�����������o�^����ۂɗp����boot profile�ł���B
�v���t�@�C�����} 2‑9�̂悤�Ɏ��g���i�T�u�L�����A�j�����Ǝ��Ԏ������Ƀu���b�N������AA���珇�Ԃɑ��M�����i�}�ł�A����D�܂ł̃v���t�@�C�����L�ځj�B��M����CM����M���ׂ��T�u�L�����A�͂����ꂩ�̃v���t�@�C���Ɋ܂܂�A�v���t�@�C�����ꏄ����܂ł͎��̃f�[�^�͎�M�ł��Ȃ��B����āA�v���t�@�C���̌J��Ԃ��������`���x���ilatency�j�ƂȂ�B
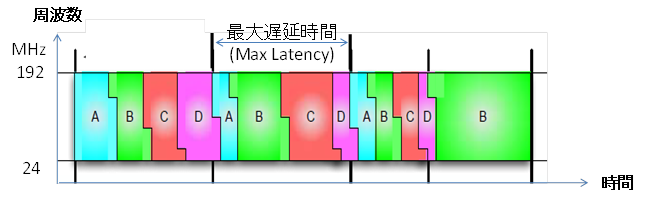
�} 2‑9�@�ϒ��v���t�@�C��
(4) PLC
PLC�iPhysical Layer Link Channel�j�́ACMTS����CM��OFDM�`�����l���̕ϒ����l�����̃p�����[�^��ʒm����V�O�i�����O�`�����l���ł���B
PLC���} 2‑10�Ɏ����悤�ɘA������6MHz�ȏ�̑ш悪�m�ۂł�����g���т�4k���[�h��8�{�A8k���[�h��16�{�̃T�u�L�����A�Ƃ��Ĕz�u�����i���ɑS�ш敝��400kHz�j�BPLC�̍ł����g���̒Ⴂ�T�u�L�����A��1MHz�̐����{�̎��g���ɔz�u���邱�ƂƂȂ��Ă���A�C�j�V�����C�Y����CM��1MHz���Ƃɑш���X�L��������PLC��T���B
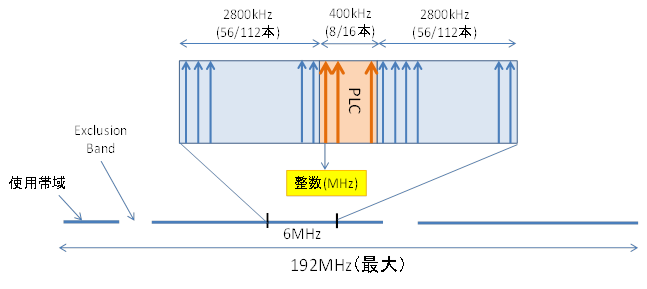
�} 2‑10�@PLC�z�u�}
�} 2‑11�Ɏ����悤�ɁAPLC�̓v���A���u��8�V���{���ƃf�[�^120�V���{���i���v128�V���{���j�̌J��Ԃ��ō\������A�v���A���u������BPSK�A�f�[�^������16QAM�ϒ��Ɛ�p��LDPC�i384�A288�j��p����B
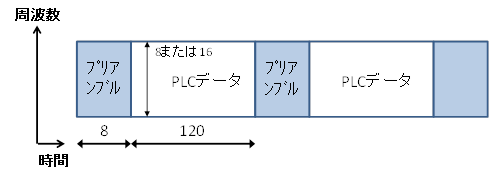
�} 2‑11�@PLC�̍\��
(5) CP����ё���
DOCSIS 3.1�ł́A�x���g�ɂ�銱��ጸ����CP�A����ё��M�X�y�N�g�����̑ш�O�������������P���鑋�����d�l������Ă���B
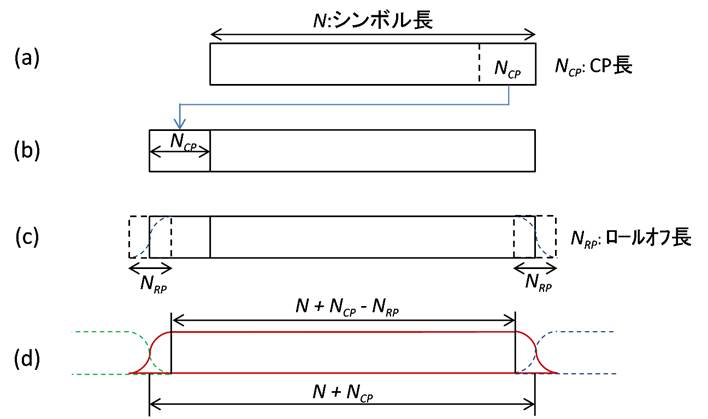
�} 2‑12�@CP�Ƒ���
CP�̓K�[�h�C���^�[�o���iG/I�j�Ƃ��Ă�A�} 2‑12 (a)(b)�Ɏ������悤�ɁA����`������V���{���ɕt������邽�ߓ`���e�ʂ��������邪�AHFC���̔��˓��ɂ���Đ�����x���g�̉e���y���ɗL���ł���BDOCSIS 3.1�̉���ł�CP���iNCP�j�Ƃ���0.9375�A1.25�A2.5�A3.75�A5.0µs��5��ނ��K�肳��Ă���BCP�l���傫���قǁA�����x���ɑΉ��\�����A�`���e�ʂւ̉e�����傫���Ȃ�BCP�Ɠ`���e�ʂ̊W���} 2‑13�Ɏ����B����4k���[�h�ł̓V���{������20µs�ƒZ�����߁ACP�̒l�ɂ���Ă͗e�ʂ��傫���ቺ���邱�Ƃ��킩��B
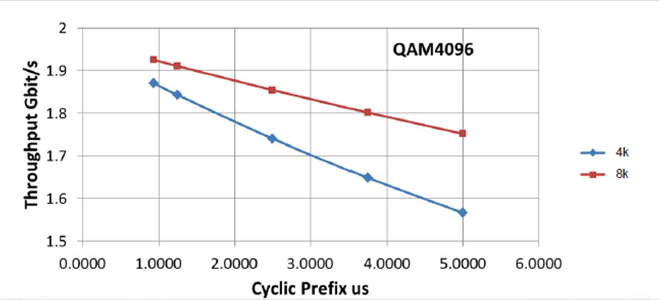
�} 2‑13�@CP�Ɠ`���e�ʂ̊W
����̑����́A�} 2‑12 (c)�Ɏ����悤�ɁA��`�V���{���̗��[��raised cosine�����|�����킹�A���Ԏ���łȂ��炩�Ȍ`��ɂ�����̂ŁA���[���I�t���iNRP�j�ɂ��K�肳���BNRP�͉�������ł�0�i�����Ȃ��j�A0.3125�A0.625�A0.9375�A1.25µs��5��ނ����p�\�ł���i�������ANCP��NRP�j�B���[���I�t�����ݒ肷��قǁA�V�X�e������я��O�ш�iexclusion band�j�̗��[�ɂ����Ď��g���̈�ŋ}�s�ȑш�O���������������邽�߁A�אڂ�QAM�M�����ւ̉e����ጸ���A��葽����OFDM�T�u�L�����A���^�p�\�ƂȂ�B�������A�} 2‑12 (d)�Ɏ������悤�Ƀ��[���I�t���̔����͗אڂ̃V���{���Əd�Ȃ邽�߁A�V���{���Ԋ����������錇�_������B
DOCSIS 3.1�̓`���e�ʂ��ő剻���邽�߂ɂ́A�^�p����HFC�̓�����אڂ̑��̃T�[�r�X�̉^�p�ɍ��킹��NCP��NRP�̒l���œK�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
2.1.3.2�@ DOCSIS 3.1��PHY�@�\�i���j
(1) �~�j�X���b�g
DOCSIS�̏��ɂ����āACM�Ɋ����Ă��鑗�M�g���~�j�X���b�g�iMinislot�j�ƌĂԁB�eCM�́A1��̑��M�^�C�~���O���Ƃ�1�܂��͕����̃~�j�X���b�g�������Ă��A�o�[�X�g��̑��M�g�𑗐M����BDOCSIS 3.1�̃~�j�X���b�g�́A���Ԏ�K�V���{���A���g����Q�T�u�L�����A���\�������i�} 2‑14�j�B�\ 2‑5�Ɏ����悤�ɁA�V���{����K�̓��[�h�iFFT�T�C�Y�j����уV�X�e���̑ш敝�ɂ��ő�l���K�肳��A�T�u�L�����A��Q�̓��[�h�ɂ����i8�܂���16�j�ł���B
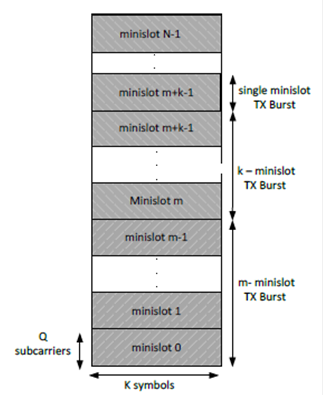
�} 2‑14�@DOCSIS 3.1�̃~�j�X���b�g�\���}
�\ 2‑5�@DOCSIS 3.1�~�j�X���b�g�p�����[�^
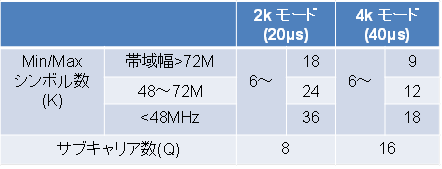
�~�j�X���b�g���̃T�u�L�����A�͂��ׂē����ϒ���p���邪�A���M�^�C�~���O���Ƃɕϒ����l����ύX�\�ł���B
(2) FEC�i���j
DOCSIS 3.1���FEC�́A����ƈقȂ�AQC-LDPC�iQuasi-Cyclic LDPC�j��p����BQC-LDPC�͊ȈՂȌJ��Ԃ��s��𗘗p������̂ŁACM�̃n�[�h�E�F�A���ȑf�����邱�Ƃ��\�ł���B���FEC�̃p�����[�^���\ 2‑6�Ɏ����B
�\ 2‑6�@DOCSIS 3.1���FEC
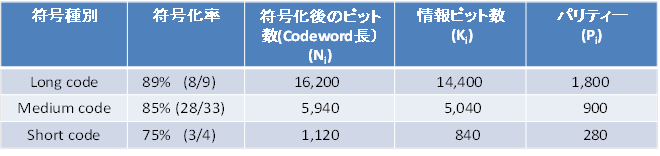
CM��CMTS����ʒm�����grant�i���M���j�Ɋ�Â��A�~�j�X���b�g�߂Ă������A���̎��A�ŏ���Long�R�[�h���g���A�c��r�b�g��Long�R�[�h������Ȃ�����Medium�R�[�h��p���A�Ō��Short�R�[�h�Ń~�j�X���b�g�����B
2.1.3.3�@ �`�����l���{���f�B���O
�} 2‑4��DOCSIS 3.1�̃V�X�e���v���Ɏ�����OFDM�`�����l���ԁAQAM�`�����l���ԁA�����OFDM/QAM�`�����l���ԂŃ{���f�B���O���\�ł���B
����Ń`�����l���{���f�B���O���s�������̍ő�e�ʁiMAC�e�ʁj���\ 2‑7�Ɏ����B�������AOFDM��4�V�X�e���i192MHz�~4�j�ȏ�^�p���邽�߂ɂ͈�ʂ�HFC�ш�̊g�����O��ƂȂ�B
�\ 2‑7�@����`�����l���{���f�B���O���̍ő�e�ʁiMAC�e�ʁj
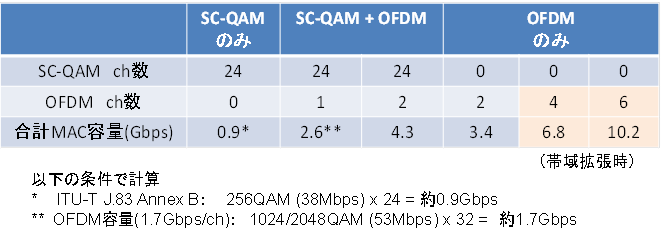
���ł��AOFDMA��QAM�`�����l���Ԃ̃{���f�B���O���\�ł���B
���̏ꍇ�ATaFDM�iTime and Frequency Divising Multiplexing�F���Ԏ��g���������d�j��p����OFDMA/QAM�`�����l���������ш�����p����B����́A�} 2‑15�Ɏ����悤�ɁAQAM�`�����l���̑��M�~�j�X���b�g��OFDMA�̃t���[���������A�����QAM�`�����l�������p���Ȃ����g����OFDMA�~�j�X���b�g�������Ă邱�Ƃɂ�莞�Ԏ�����ю��g�����őш�����p����Z�p�ł���B
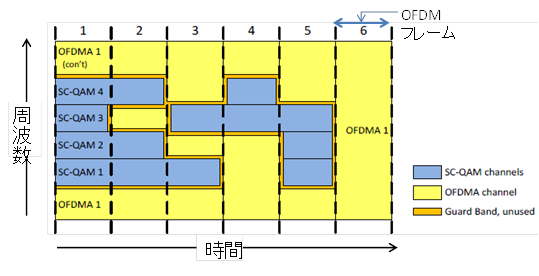
�} 2‑15�@���`�����l���{���f�B���O��TaFDM
2.1.4�@ DOCSIS 4.0
HFC�l�b�g���[�N�W�����A��Gbps�̏㉺�Ώ̑��x�̃T�[�r�X�����������@�Ƃ��āA�C�O�̃P�[�u���ƊE�ł�2�̈قȂ�A�v���[�`���o�������B
ž Full Duplex�iFDX�jDOCSIS�iNode + 0 �̍\���ł̂ݑΉ��\�j
ž ���g�����d�iFDD�jDOCSIS��1.8GHz�܂ŃX�y�N�g���g���iESD�j
�iNode + 0 �ȊO�̍\���ł��Ή��\�j
���̎�@�̑��ႪCATV�֘A�x���_�̍����������A�����̗̂v����s�ꉻ�����̕s�m��������ݔ��������S�O�����鎖�Ԃɔ��W���Ă������B���̎��Ԃ����������邽�߁A�č�CableLabs�ł̓x���_����щ���e�ЂƂƂ��ɑI�����̖��m���Ɠ����i�߁ADOCSIS 4.0�̎d�l��V���ɍ��肵�Ă���B
DOCSIS 4.0�ɂ����ẮA���Ɏ����悤�ɋZ�p�I��{�����s����B
ž FDX �� 1.8GHz FDD�̗��@�\���T�|�[�g
ž ����MAC (�� D4.0 MAC) �v����P��d�l��
ž ����PHY (�� D4.0 PHY) �v����P��d�l��
ž DOCSIS 4.0�����̂́A���ׂĂ̗v�����T�|�[�g
ž �P�[�u�����f���iCM�j�p�����̂̐v�ɉe����^����v����`������
Ø ����: OFDM 5ch�A �P��L�����AQAM�@32ch
Ø ���: OFDMA 7ch�A A-TDMA 4ch�i�I�v�V������8ch)
Ø FDX�� 1.8GHz FDD�̗��v����`���T�|�[�g
2.1.4.1�@ FDX�iFull Duplex�j�V�X�e��
DOCSIS 3.1�ł͉���10Gbps�A���1Gbps�����E�Ƃ���邪�A�č�CableLabs�ł͏��E����Ώ̂�10Gbps�T�[�r�X���\�Ƃ���FDX�iFull Duplex�j����������ADOCSIS 4.0�ŋK�i�����ꂽ�B����܂ł�DOCSIS 3.1�Ƃ͈قȂ�A����ш�͂��̂܂܂ɁA���ш�g�����\�ł���BFDX�ł�108�`684MHz�Ԃŏ��E�����OFDM�M�����Ɏg�p����B���̂��߁A�M���Ԋ����L�����Z������Z�p�i�G�R�[�L�����Z�����O�j���K�{�ƂȂ�B���͓���CM�������CM�ɑ��Ă����łȂ��A�m�[�h�o�R�����邽�߃G�R�[�L�����Z�����O��FDX�ɂƂ��ĕK�{�̋Z�p�ł���B
�} 2‑16��CMTS�ACM���ꂼ�ꂩ�猩��FDX�`�����l���̎g�����ƐM���Ԋ��̊T�O���A�} 2‑17��FDX�V�X�e���ԁA�����V�X�e���ւ̊��������B
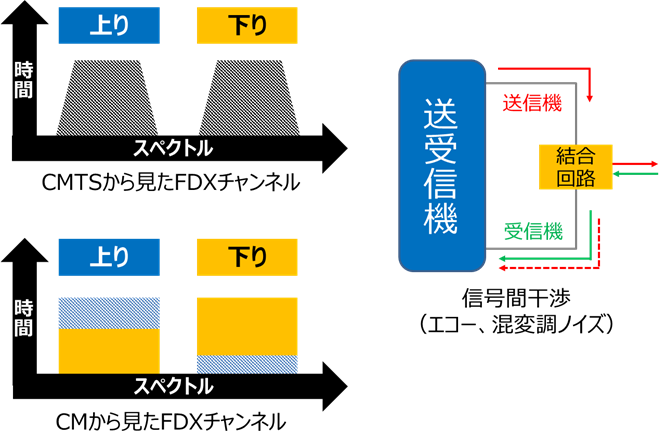
�} 2‑16�@FDX�ł�TDD�Z�p�̎g�����ƐM���Ԋ��̊T�O
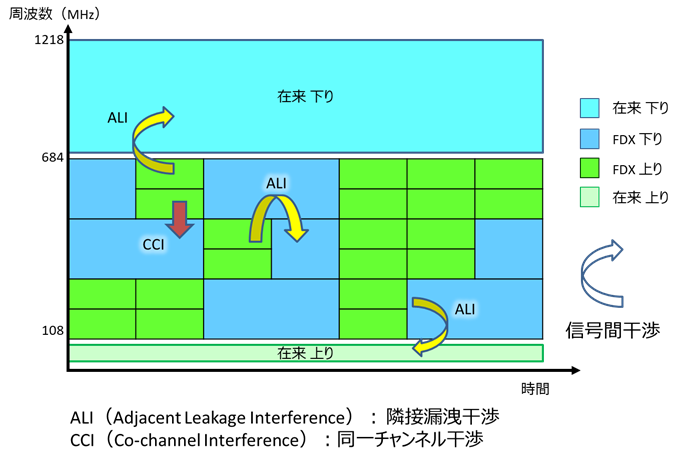
�} 2‑17�@FDX�V�X�e���ԁA�����V�X�e���ւ̊���
�} 2‑18��FDX�P�[�u�����f���iCM�j�ɂ����銱�̏������B
���̏܂��ADOCSIS 4.0�ł͈ȉ��̎菇�ɂ��FDX�̎��g�������Ɗ��������s���B
i) ����CM�̏��Ɖ����FDX�ш�i108�`684MHz�j���̈قȂ���g���������Ă�B
ii) CM�̏�著�M�M���ɕt������ш�O�X�v���A�X�M���̎��g�̎�M�@�ւ̉�荞�݁i�אڃ`�����l���ւ̘R��E���j�̓G�R�[�L�����Z���ŏ�������B
iii) CM�̏��M��������CM�̉���M����M�Ɋ����邩�ۂ������O�Ɍ����A������CM�̃O���[�v�����O���[�v�iIG�j�ƒ�`����B����CM�����M���́A����CM��������IG���̑���CM�ɁA�������g��������p�Ɋ����ĂȂ��B
iv) CMTS���} 2‑16�ɂ������悤�ɏ펞�A�S�ш�����E���蓯���ɗ��p����̂ŁA�G�R�[�L�����Z���Ŋ�����������B
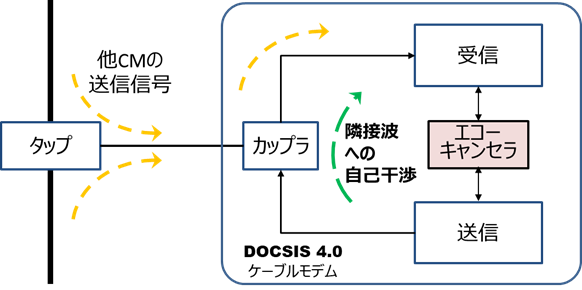
�} 2‑18�@FDX CM�ɂ����銱��
FDX��CM�͔�FDX��DOCSIS 3.1 CM�Ƃ̍��݉^�p���\�ƂȂ��Ă���B�} 2‑19��DOCSIS 3.1�V�X�e����FDX�̕��p�������B���̐}�́AFDX�m�[�h�ɂ�����108MHz�`204MHz�őS��d�ʐM���ł��邱�Ƃ������Ă���B
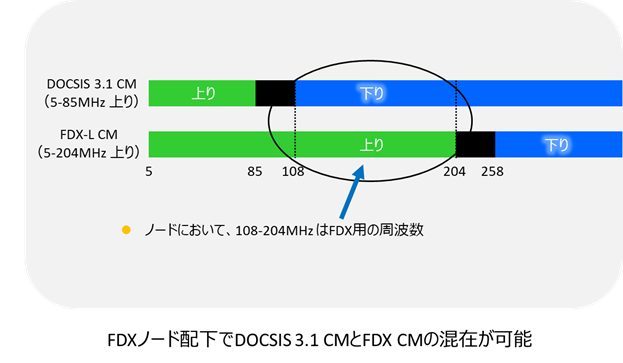
�} 2‑19�@DOCSIS 3.1�V�X�e����FDX�̕��p
2.1.4.2�@ FDD�iFrequency Division Duplexing�j�V�X�e��
�} 2‑20��DOCSIS 4.0�ɂ�����1.8GHz �ш�g��FDD�ɂ�����㉺�������g���������B
�����g����684MHz�܂Ŋg���\�ŁA684�`834MHz�̃K�[�h�o���h������ŁA834�`1218MHz�܂ł�384MHz��1794MHz�܂ł�576MHz�A���v960MHz�ш敝��������g���Ƃ��ė��p����B
�Ȃ��������g��������������A�K�[�h�o���h�ш敝���傫���Ȃ�_�ɒ��ӂ��K�v�ł���B
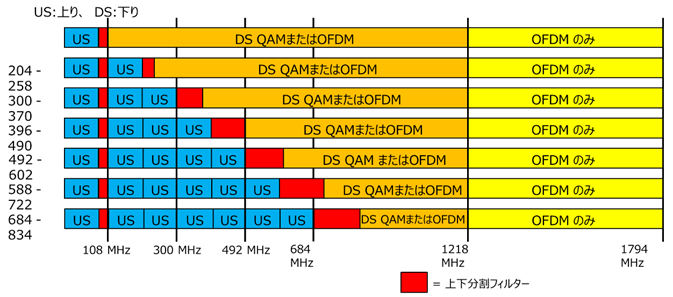
�} 2‑20�@DOCSIS 4.0�ɂ�����1.8GHz�ш�g�� FDD�pCM�̏㉺�������g���̗�
2.2�@ ���`���Z�p
2.2.1�@ ���`���̎d�g��
���`���̌`�Ԃ́A���t�@�C�o���w�b�h�G���h����ǂ��܂ŕ~�݂��邩�ɂ���đ傫��4�ɕ�������B�} 2‑21�̂悤�Ɍ��m�[�h�܂ł�HFC�iHybrid Fiber Coaxial�j�A���o�̓~�j�m�[�h�܂ł�FTTC�iFiber To The Curb�j�A�e�Z�˂܂ł�FTTH�iFiber To The Home�j�A�W���Z��̋��p���܂ł�FTTB�iFiber To The Building�j�ƌĂԁB
HFC�́A���O�`���H�����P�[�u���Ɠ����P�[�u���ō\�������B�����P�[�u����Ԃɂ�5�`7�i�̑����킪�ڑ������BFTTC�́A���O�`���H�����P�[�u���Ɠ����P�[�u���ō\������AHFC�̃l�b�g���[�N�`�ԂƂ̍��͏��Ȃ����A�����ґ�̋߂��ɍ��o�̓~�j�m�[�h��ݒu���A�����P�[�u����Ԃɑ������u���Ȃ������ł���BFTTH�́A���O�`���H�����ׂČ��P�[�u���ō\������A�ˌ��Z�˂̂悤�ɂ��ꂪ�_��Z�˂ւ̕~�݂ƂȂ�����ł���BFTTB�́A���O�`���H�����ׂČ��P�[�u���ō\������邪�A�W���Z��̂悤�Ɍ����ւ̈�������_��Z�˂܂ł͌����̓����P�[�u�����̊��ݔz���œ`����������ł���B
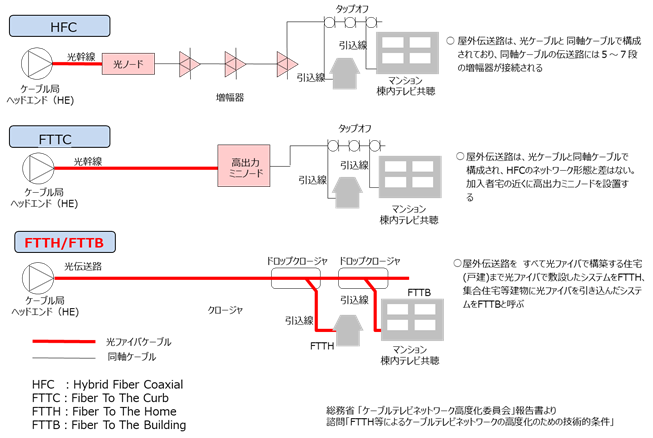
�} 2‑21�@���`���̌`��
���`���ɂ����ẮA�} 2‑22�Ɏ����Ƃ�����t�@�C�o1�c�̏�ɁA�Е����̕����Ƒo�����ʐM��g�����d���ē`������B�g�p����g���͕�����1,555nm�A�ʐM������1,490nm�A���1,310nm�ł���B�P�[�u���e���r�ǂł͕����ƒʐM��ʂɂ���2�c��p���邱�Ƃ��������A���̏ꍇ�ł��g���͓����ł���B
�����̐M���́A�d�g�Ɠ������ϒ��g�ł���A���̓_�͓����P�[�u���ł̓`���M���Ɠ����ł��邪�AFTTH�ł͓`�����g���ш悪2~3GHz�ƍL���ABS��110�xCS��IF�`�����\�ł���B�ʐM�̐M���́A�g1�h�g0�h�̃f�W�^���f�[�^�ł���B
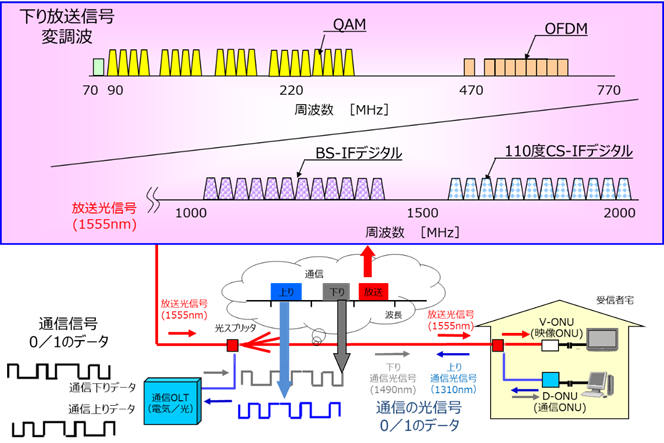
�} 2‑22�@FTTH�ɂ���������ƒʐM�̑��d��
���`�����\������@��́A�Ǔ����u�̒ʐMOLT�iOptical Line Terminal�j�ƁA������u��D-ONU�iData-Optical Network Unit�j�ł���B
�܂��A�����p�ɂ́A�Ǔ����u�Ƃ��ēd�C�E���ϊ����u�iRF���ϒ���j���A������u�Ƃ���V-ONU�iVideo-Optical Network Unit�j������B���`���͂����@���PON�iPassive Optical Network�j�����̓`���Z�p���g���čs����i�} 2‑22�Q�Ɓj�B
OLT����ONU�ւ̉�������ʐM�ɂ́ATDM�iTime Division Multiplexing�F���������d���j�Z�p���p������BTDM�͕�����ONU�ւ̐M�����A���ԓI�ɏd�Ȃ�Ȃ��悤�ɑ��d�����ē`������Z�p�ł���B����M���͌��X�v���b�^�ŕ��ꓯ���PON�Ɍq���邷�ׂĂ�ONU�ɓ����M�����]�������B���̂��ߊeONU�ւ͑���ONU���̃f�[�^���]�������B�eONU�͎��Ȉ��Ẵf�[�^�����𒊏o���A����ONU���f�[�^�͔p������B
ONU����OLT�ւ̏������ʐM�ɂ́ATDMA�iTime Division Multiple Access�F�����������ڑ��j�Z�p���p������B����ONU����̏��M�������X�v���b�^�ō��g����邽�߁A�eONU����̐M�����������ɑ��M���ꂽ�ꍇ�A�`���H��ŏՓ˂��N�����\��������BTDMA��ONU�̃f�[�^���M�^�C�~���O�Ƒ��M�ʂ𐧌䂵���M���̏Փ˂�������鑽�d���Z�p�ł���i�} 2‑24�Q�Ɓj�B
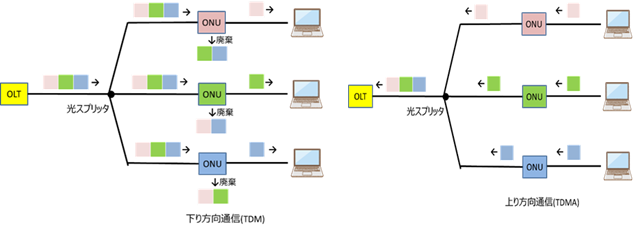
�} 2‑23�@PON�ɂ��o�����ʐM
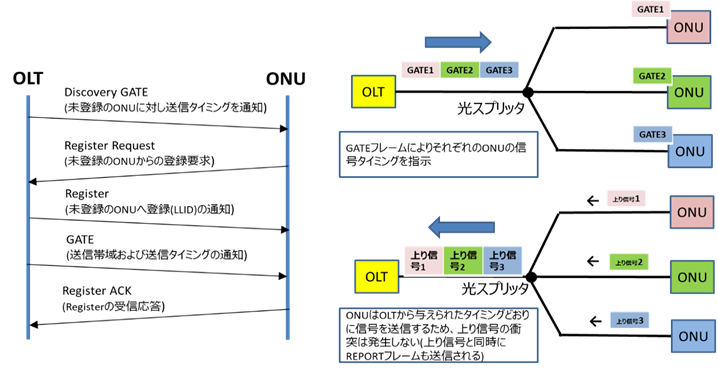
�} 2‑24�@���M���Փˉ��
E-PON�iEthernet-PON�j�ł́AONU��PON�ɐڑ�������OLT�͂���ONU�������I�ɔ������AONU��LLID�iLogical Link ID�j��t�^���ĒʐM�����N�������I�Ɋm������B���̋@�\��P2MP�f�B�X�J�o���ƌĂԁBP2MP�f�B�X�J�o�����ɁAOLT�͊Y��ONU�Ƃ̊Ԃ�RTT�iRound Trip Time�F�t���[���������ԁj������s���A�܂�ONU��OLT�Ƃ̎����������s���BRTT���肨��ю��������͂��̌������I�ɍs���A���H�����̕ω��Ȃǂɂ��Y�����������ꍇ�ɂ͐���������B
�Ȃ��A�V�X�e�����ł���20km�ȓ���ONU�����݂��邽�߁A����20km�̌����B���Ԃ͌��t�@�C�o���̔g���Z�k���ɂ���Ė�0.1ms�ɂȂ�A���̉������Ԃ���RTT��0.2ms���x�ȉ��Ɛ��������B
������ONU����̏��M�������X�v���b�^�ō������Փ˂��Ȃ��悤��E-PON�ł�OLT���i�ߓ��̖����߁A�eONU�ɑ��đ��M����ʒm����B����ɂ��eONU����̏��M�������ԓI�ɕ������Փ˂��������B�i�} 2‑24�Q�Ɓj
���M���̒ʒm�́A��̓I�ɂ́uGATE�v�ƌĂ�鐧��t���[����OLT����eONU�֑��邱�Ƃɂ���������BGATE�t���[���ɂ́A����ONU�ɑ��鑗�M�J�n�����Ƒ��M�ʁi���̎��_����ǂꂾ���̏��M���𑗂��Ă悢�Ƃ������j�����e����Ă���ONU�͂��̎w���ɂ��������ď��M���̑��M���s���B
�Ȃ��AIEEE802.3ah�ł͊eONU�ւ̏��M�����M�����@�͋K�肳��Ă��邪�A�eONU�ւ̑ш�̊����i���M�J�n�����Ƒ��M�p�����Ԃ̌v�Z�j���@�ɂ��Ă͋K�肳��Ă��Ȃ��B
2.2.2�@ ���`���̍��x��
PON�̒ʐM�����͕W��������Ă���A����܂ŁAITU-T�ɂ��G-PON�iGigabit PON�j��IEEE�ɂ��E-PON�iEthernet PON�j�̕W�������i�߂��Ă������A�����ɉ����V���Ȓc��(25GS-PON MSA, �č�CableLabs, Open XR optics Forum)�ł��W�������s����悤�ɂȂ����B
ITU-T�͍��ۓd�C�ʐM�A���̒ʐM����̕W�������肷��@�ւł���BIEEE�ithe Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.�j�͓d�C�H�w�E�d�q�H�w�Z�p�̊w��ł���AIEEE802.3��ŃC�[�T�l�b�g�i���`�����܂ށj�̕W�������肵���B25GS-PON MSA(Multi-Source Agreement)�́AITU-T���W��������������25Gbps�̋K�i�����肷�邽�߂ɑn�݂��ꂽ�c�̂ł���BOpen XR optics Forum�ƕč� CableLabs �̓R�q�[�����gPON�̕W�������s���Ă���B
���`���K�i�̐i�����} 2‑25�Ɏ����B
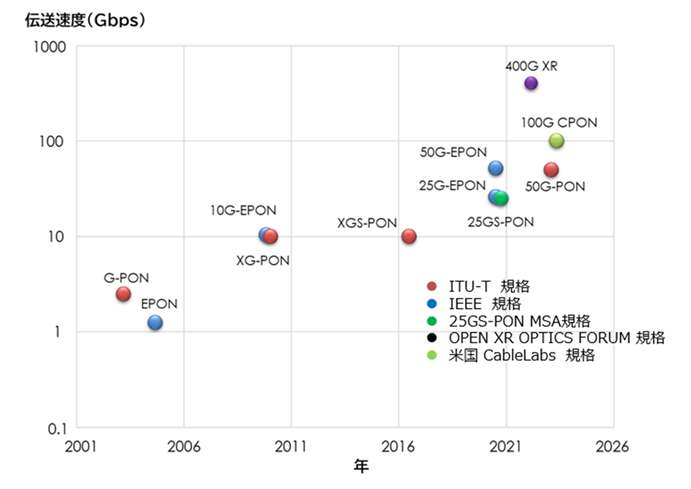
�} 2‑25�@���`���K�i�̐i��
2.2.2.1�@ ITU�W��G-PON��IEEE�W��E-PON
G-PON�́AG-PON�ȑO��B-PON�iBroadband PON�j�Ƃ̐�������ۂ��������������̂ł���A���܂ł̒ʐM�̊�{�ł���d�b�ԂƂ̐���������8kHz�œ��������Ă���B�܂��A�ϒ�GEM�iG-PON Encapsulation Method�j�t���[����ATM�Z�����܂Ƃ߂�GTC�iG-PON Transmission Convergence�j�t���[���i125��s�F8kHz�Œ�j�ō\������A�d�b�A�f�[�^�A��p���Ȃǂ̒ʐM�T�[�r�X�����e���邱�Ƃ��ł���B
E-PON�́A���܂ł̓d�b�ԂƂ̐��������IP�ԂƂ̐��������Ƃ�A�C�[�T�l�b�g�iEthernet�j�t���[���̂܂܂œ`������B���݂͍��������ꂽGE-PON�iGigabit Ethernet-PON�j�����p����Ă���B
���`���K�iG-PON��GE-PON�Ȃ�тɂ��̍������ł���10G-EPON��XG-PON�̓`���t���[���Ȃǂ̊T�v��\ 2‑8�Ɏ����B�X��10Gbps���̕W�����T�v��\ 2‑9�Ɏ����B
�\ 2‑8�@G-PON��E-PON�̊T�v

����AIEEE�ł́A2004�N��1G-EPON�iIEEE802.3ah�A����1Gbps�^���1Gbps�j�A2009�N��10G-EPON�iIEEE802.3av�A����10Gbps�^���10Gbps�j���W�������ꂽ�B�܂��A2020�N��25G-EPON(IEEE802.3ca�A����25Gbps�^���25Gbps)��50G-EPON�iIEEE802.3ca�A����50Gbps�^���50Gbps�j���W�������ꂽ�B
�\ 2‑9�@Over10G PON�̕W�����T�v

�`�����x�ɂ��āAE-PON�ł́A�����x�ϒ��œ`���\�Ȃ悤�ɃC�[�T�l�b�g�t���[���̒��������i�g1�h�Ɓg0�h�����p�x�Ɉˑ��j��ጸ����8-10�ϊ���p�����B���̂��߁A���`�����x�͋K�i�i����1.25Gbps/���1.25Gbps�j��0.8�{�i����1Gbps/���1Gbps�j�ƂȂ��Ă���BG-PON�̓`�����x�́A����/���̑g�����i����/���F1244.16Mbps/155.52Mbps�A1244.16Mbps/622.08Mbps�A1244.16Mbps/1244.16Mbps�A2488.32Mbps/155.52Mbps�A2488.32Mbps/622.08Mbps�A2488.32Mbps/1244.16Mbps�A2488.32Mbps/2488.32Mbps�j�ƂȂ��Ă���i�Q�ƁFTable 1/G.984.2 – Relation between parameter categories and tables�j�B������GEM�t���[����GTC�t���[���̃w�b�_�[�����̃��X�͊܂܂Ȃ��������x���L�ڂ��Ă��邪�ACTC�_�E���X�g���[��38880Byte�ŁAGTC�t���[���w�b�_�[�iONU���ʼnρFONU��64�Ɖ���j548Byte��CEM�t���[���w�b�_�[5Byte���l�����Ă��A�e�t���[���w�b�_�[�͖�1.4%�ł���B�܂��AG-PON�̓C�[�T�l�b�g�A���O�����ATM�iAsynchronous Transfer Mode�j�Ԃ��p�������p�ł���ȂǑ����̋@�\��L���Ă���B
���̂悤��G-PON�̓C�[�T�l�b�g�t���[���̂܂܂œ`������E-PON�Ɣ�r����ƁA�ʐM���x�E�������E���Ƃ��ɗD��AE-PON�Ɠ���2004�N�ɕW��������Ă���ɂ�������炸�A�����̒ʐM���Ǝ҂ɂ͍̗p����Ȃ������B���̗��R�Ƃ��āA��L�̂悤�ȋ@�\�̑�������J�����Ԃ��������Ƃ�A���i�������ƂȂ�Ɨ\������h�����ꂽ�ƌ�����B
2.2.2.2�@ PON�̌��g���ɂ���
���t�@�C�o�̌��g���́A�`���������ጸ�ł���悤�Z�p�J������A1980�N�ɖ�1300�`1700nm�Ł|0.5dB/km�ȉ����K�i������č����Ɏ����Ă���B���̓��A�ʐM�p�iPON�j�ɂ͏��1310nm�i1260�`1360�j�A����1490nm�i1480�`1500�j���A�����p�i����̂݁j�ɂ�1555nm�i1550�`1560�j�������Ă�ꂽ�B���ɁAONU�ɓ������锼���̃��[�U�ł́A���i�����\�ȃt�@�u���E�y���[�E���[�U�iFabry-Perot lasers�F�t�@�u���E�y���[���U��i���ˋ��̊ԁj�ɕ����߂��Ĕ������錴���j�������̔g���Ŕ�������Ƃ����������l���A1260�`1360 nm�ƍL���g���̈悪�ݒ肳�ꂽ�B
���̌�A�������iG-PON��10Gbps�j�����ɍۂ��āA�uEnhancement band�v���lj��K�肳�ꂽ�B����ɂ��A��L��1260�`1360nm��Regular�Ƃ��ADFB lasers�iDistributed Feedback lasers�F���z�A�Ҍ^���[�U�F�����̃��[�U���\������N�^��P�^�����̂̂���N�^�����̂̉�܊i�q�ɂ���ĒP��g���݂̂��������錴���j��ΏۂƂ���Reduce�g���i1290�`1330nm�j��CWDM���̔g���I�����[�U��Ώۂɂ���Narrow�g���i1300�`1320nm�j�������Ă�ꂽ�B���̌��ʁA1Gbps��G-PON�ŏ���DFB laser���g�p����A10Gbps��XG-PON�ŏ��g����1270nm�i1260�`1280�j���g���ē`�����邱�Ƃ��ł��AOLT���ł�G-PON Reduce�g����XG-PON�ŏ��g���Ƃ�WDM�t�B���^�ŕ����ł��邱�ƂƂȂ����BE-PON��Fabry-Perot laser���g�p����G-PON�ł�1260�`1360nm�Ɠ����g���ш���g���\�������邽�߁AOLT����̎w����ONU�̏�蔭�������ԕ������䂷��TDM���K�v�ƂȂ�B
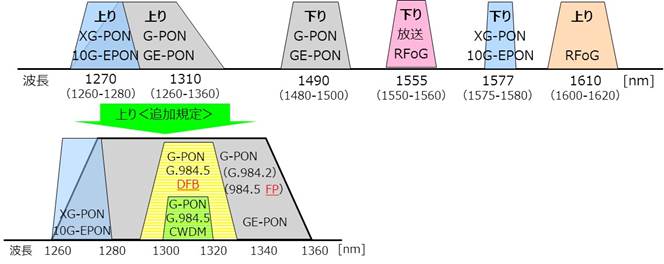
�} 2‑26�@G-PON��E-PON�̌��g��
2.2.2.3�@ PON�@��̑��ݐڑ����ɂ���
��L�̂Ƃ���PON�̒ʐM�����́A�`���t���[���`���Ȃǂ̃f�[�^�����N�w�ƌ��g���̕����w�Ȃǂ̕W�������i�߂��e�퐻�i�����p����Ă������A�@��\�����菇�Ȃǂ̎d�g�݂����߂Ă����ʑw�̕W�������ڍׂɂ͍s���Ă��Ȃ��������߁A���А��i�Ƃ̑��ݐڑ����ł��Ă��Ȃ��B������������ׂ��AITU-T��IEEE�ł���Ȃ�W���������Ƒ��ݐڑ��������i�߂��Ă���B���̗����\ 2‑10�Ɏ����B
�\ 2‑10�@ PON�W��������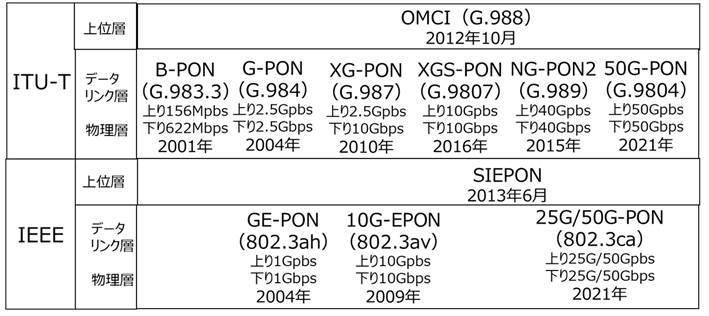 �@
�@
G-PON�ł́AG.984.4�ŁAOLT��ONU�̓�����Ǘ����䂷�邽�߂̃C���^�t�F�[�X���K�肳��Ă͂������A�v�Ɏg���郌�x���ŊǗ�����菇�Ȃǂ��ׂ����K�肵���K�C�h���C��G.Imp.984.4�iImplementer�fs Guide for ITU-T Rec. G.984.4�j�����肳�ꂽ���Ƃɂ�葊�ݐڑ����\�ƂȂ����B�܂��AG-PON��XG-PON�̗��W����ΏۂƂ���G.988�iONU management and control interface (OMCI) specification�j�����肳��A���̗��W���̉ƒ�[���ł���ONU������\�ƂȂ����B�܂��A���̑��ݐڑ����̊m�F�̂��߂ɁABroadband Forum�iBBF�j�ő��ݐڑ��������s���Ă���ABBF�̃z�[���y�[�W�ɂ͂��̔F�v���O������A���ݐڑ��ł������i�iONU�j������Ă���BBBF�̐ڑ������͈ȉ��̎d�l���K�肳��Ă��邪�A���ݐڑ������d�l�Ɋ�Â��F��̎��т͂Ȃ��B
Ø �K���������d�l�iBBF.247 G-PON ONU Certified Products�j
ITU�W���d�l�ɑ���ONU�̓K������F�肷�鎎��
Ø ���ݐڑ������d�l�iTR.255 GPON Interoperability Test Plan�j
�قȂ�x���_��OLT-ONU�Ԃ̑��ݐڑ������m�F���鎎�����K��
GE-PON�ł́AIEEE��P1904.1 Working Group���ݒu����ASIEPON�iStandard for Service Interoperability in Ethernet Passive Optical Networks�j�ƌĂ��GE-PON�̑��ݐڑ����̂��߂̌������i�߂��A2013�N6���ɕč��ł̃P�[�u���e���r���p��ΏۂƂ���Package A�i�P�[�u���j�A���{��NTT�d�l����{�Ƃ���Package B�i���{�j�A�����s����ӎ�����Package C�i�����j���d�l�����ꂽ�B���݂�Package���ƂɔF�v���O�������������Ă���BPackage A���������Ă����č��ł́ADOCSIS�P�[�u�����f���^�p�̃o�b�N�I�t�B�X�̊e��T�[�o�Ȃǂ�PON�ł����p�ł���DPoE�iDOCSIS Provisioning of EPON�j���č��P�[�u�����{�Ŏd�l�����ꂽ�B���̐���R�}���h��Package A�Ɛ������Ă���B�����DPoG�iDOCSIS Provisioning of GPON�j���d�l�����ꂽ�BDPoE�́A�e��@�킪�F����āA�č��P�[�u�����{�̃z�[���y�[�W�Ō��\����Ă���B�܂��APackage B�i���{�j�́ANTT�𒆐S�Ƃ����ʎВc�@�l���ʐM�l�b�g���[�N�Y�Ƌ���iCIAJ�j�������ǂƂȂ��ĕ������[�J�[��10G-EPON�@��̑��ݐڑ�������i�߂Ă���B
���{�P�[�u�����{�ł́A�كx���_��OLT-ONU�Ԃ̑��ݐڑ����������邽�߁A�����̃P�[�u�����ƎҌ�����E-PON���ݐڑ��^�p�d�l�iJLabs SPEC-027 1.1�Łj�����肵���i�} 2‑27�j�B�܂����d�l�ɑΉ������F�莎�����A2017�N8�����J�n�����B
PON���ݐڑ��̊K�w�ł���A�����w�ƃf�[�^�����N�w�ɂ��ẮAIEEE 802.3ah�AIEEE 802.3av�̋K�����������B��ʑw�ł���^�p/�Ǘ�/�����e�i���X�w�ł�DPoE/SIEPON Package A���瑊�ݐڑ��ɕK�v�ȃR�}���h���K�肵�Ă���B
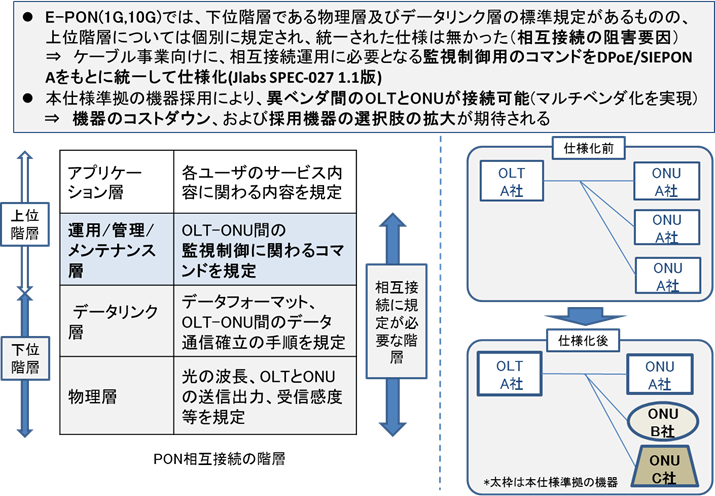
�} 2‑27�@E-PON���ݐڑ��^�p�d�l
�܂��AG-PON�ɂ��Ă����ݐڑ��^�p�d�l�ɂ��Č������s�����B
G-PON�����ʊK�w�ɂ͍��ەW��������A�����@��Ԃ̐ڑ����͍����������̃��[�����͕K�v�ł���B��ʊK�w�ɂ����ʋK�i�͂��邪�A�ʂ̍��ڂ̗̍p�ۂ̓x���_�̎d�l�ɂ�邽�߁A���ݐڑ��͎��Ǝ҂̗v�]�ɂ��A���Ǝ҂ƃx���_���������ČʂɑΉ����Ă����B�]���āA��ʊK�w�̓��A�^�p/�Ǘ�/�����e�i���X�w�̕K�v�ȊĎ�����p�R�}���h�ꂷ�邱�Ƃ��L�v�ł���B
G-PON���ݐڑ��̊K�w�ł���A�����w��TC�w�ɂ��ẮAG.984�A G.987�A G.9807�A G.989�̋K�����������B��ʑw�ł���^�p/�Ǘ�/�����e�i���X�w�ł�OMCI�iG.988�j���瑊�ݐڑ��ɕK�v�ȃR�}���h���K�肷��BE-PON���ݐڑ��d�l�Ƃ̑傫�ȑ���̓��C��3�Ɋւ���Ď��@�\���lj�����Ă��邱�Ƃł���B�Ȃ�G-PON���ݐڑ��^�p�d�l�iJLabs SPEC-036 1.0�Łj��2017�N12��21���Ɋ������A�F���t��2018�N1�����J�n�����B
2.2.2.4�@ GE-PON��10G-EPON�̍��݉^�p
EPON��1G��10G�̍��݉^�p�̂��߂̃C���[�W��} 2‑28�Ɏ����B���[�U1��1Gbps�̑o�����ʐM�A���[�U2��10Gbps�̑o�����ʐM�A���[�U3�͏��1Gbps�A����10Gbps�Ƃ��Ă���B�w�b�h�G���h�ɂ͏��1Gbps�Ɖ���10Gbps�̐M���𐧌䂷��OLT�������āA����͕ʔg���i1Gbps��1490nm�A10Gbps��1577nm�j�Ń��[�U���ONU�ցA����1Gbps��10Gbps�Ƃ������g���ƂȂ邽�߃��[�U1����3�̏��M����ʂ̎��ԂŊ��蓖�Ă鎞����������s���B���̎���������͓������l�b�g���[�N���[�U���X�v���b�^�j�ɐڑ����Ă��郆���[�U��Ɠ����ł���B
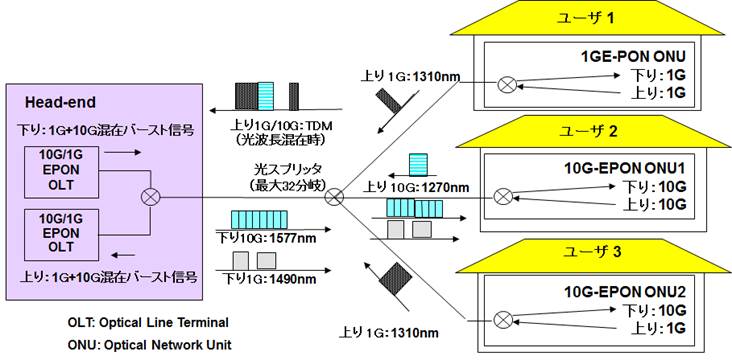
�} 2‑28�@GE-PON��10GE-PON�̍��݉^�p
2.2.2.5�@ ����Ȃ鍂�����ɂ���
NG-PON1�iNext Generation-PON 1�j��GE-PON�Ƃ̋����i���X�v���b�^���x�[�X�Ƃ��������l�b�g���[�N�p����j��v�������Ƃ��Č�������AXG-PON�iITU-T G.987�j�ƂȂ��Ă���B
����Ȃ鍂�����i40Gbps���x�j��ڎw��NG-PON2�iNext Generation-PON 2�j�ł́A���������Ƃ̋�����v�������Ƃ����V�Z�p�𗘗p����B2014�N12��ITU-T G989.2��TWDM-PON�iTime and Wavelength Division Multiplex - PON�j��PtP WDM-PON�iPoint-to-Point Wavelength Division Multiplexing – PON�j��2�������K�肳�ꂽ�B
TWDM-PON�iTime and Wavelength Division Multiplex - PON�j�̌��g���̈�́A��肪1500-1550nm�A���肪1580-1600nm�ŁA�e�g����10Gbps��4�g�������Ă�i�} 2‑29�Q�Ɓj�B
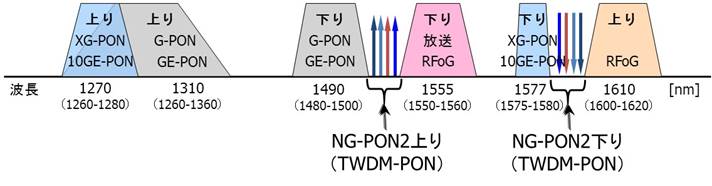
�} 2‑29�@����Ȃ鍂�����i40Gbps�jNG-PON2�̌��g��
���̌��`���ɂ����Ĕg�����d�`��������̔g���Ԋu�́ADWDM�ł͌����g�����ƂɋK�肳��Ă���A193.1[THz]�𒆐S��12.5GHz�A25.0GHz�A50.0GHz�A100GHz�E�E�E�Ԋu�̎��g���i1�A600nm�t�߂̔g���ł́A50GHz�Ԋu�͖�0.4nm�Ԋu�A100GHz�Ԋu�͖�0.85nm�Ԋu�A200GHz�Ԋu�͖�1.7nm�Ԋu�j�ł���BCWDM�ł͔g���𑽏d�E��������t�B���^�̒��S�g����20nm�Ԋu�ŋK�肳��Ă���B�Ȃ��ADWDM��ITU-T G.694.1�ŁACWDM��ITU-T G.694.2�ŋK�肳��Ă���B
2.2.3�@ ���`���ւ̃}�C�O���[�V����
2020�`30�N�ɂ͓����P�[�u���ł̒ʐM���x�����E�ɒB���A�ʐM�T�[�r�X��HFC��DOCSIS����FTTH��PON�Ɉڍs����ƌ����Ă��邪�A�����i�K�I�ɍs�����߂ɗL���ȕ����Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�@HFC���x���i������HFC�Ƃ��Ă�鏬�Z�����E1GHz���x�ւ̑ш�g��j
�A�@RF�{PON�i�ʐM�T�[�r�X�����P�[�u����GE-PON�ɐ�ւ���j
�B�@RFoG�i�`���l�b�g���[�N�݂̂���������j
�C�@PON��HFC�̍��݁i����j�^�p
������g�ݍ��킹�ē`���ݔ��̓����������邱�Ƃ��\�ł���B
���̂ق��č��ł́ADPoE�iDOCSIS Provisioning of EPON�j���d�l������Ă��邪�A�����ł͇@�`�C���ꂼ��̕����ɂ��Đ�������B
2.2.3.1�@ HFC���x��
HFC���x����DOCSIS3.1���厲�Ƃ�����̂ł���B�iDOCSIS�̋L�q�Q�Ɓj
�} 2‑30�̂Ƃ���AHFC���x�������̐ݔ��\�z�ɂ́A�ʐM�p�ǐݔ���CMTS����щƒ�[����CM���A����DOCSIS��3.0����3.1�ɕύX����K�v������B
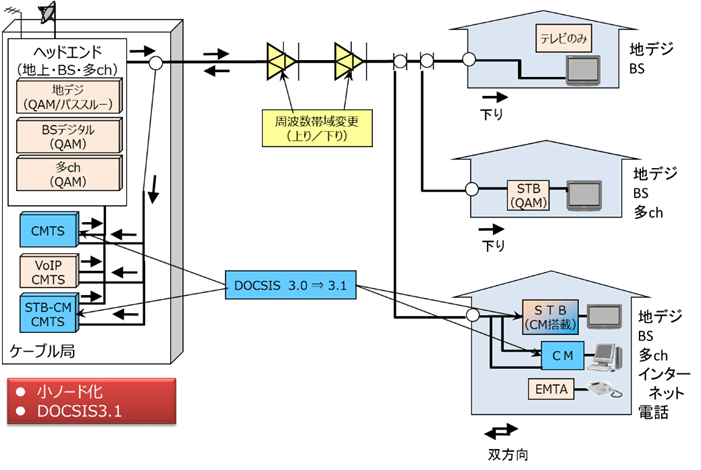
�} 2‑30�@HFC���x�������iDOCSIS 3.1�j
2.2.3.2�@ RF�{PON
RF�{PON�V�X�e�����} 2‑31�Ɏ����悤�ɁA���t�@�C�o�P�[�u����V���ɕ~�݂��ADOCSIS�̃Z���^�[�ݔ������[���ݔ��͎g�킸�ɁAGE-PON�ɂ��ʐM�T�[�r�X���s�������ł���B�ʐM�T�[�r�X�ɂ́A����M���Ɍ��g��1490nm���A���M���Ɍ��g��1310nm��p���A�ǂɐݒu�����OLT�Ɖƒ�ɐݒu�����ONU�Ƃ̊Ԃł́AEthernet�t���[���`���̐M����ONU����Ȃǂ̏���t�����A���̋���ŒʐM����B�������AHFC�l�b�g���[�N�ł���܂Ŏg�p���Ă�������[���iCM����STB�ACM�AEMTA�j�����p�ł��Ȃ��Ȃ�B
�����T�[�r�X�i����M���j�ɂ͌��g��1555nm��p����B���`���̎��g���ш悪�L�����Ƃ���BS-IF�M���̃p�X�X���[�ɂ��ĕ������\�ł���B�f���͍��܂łǂ���W���Z����̓����P�[�u�����g����B
RF�{PON�����iFTTH�j�̒lj��ݔ��Ƃ��ẮA�ǐݔ��̒ʐM�pOLT�ƕ����p�����M�@�EFTTH�`���H�i���t�@�C�o�j�E�ƒ�p�̒ʐM�pD-ONU�ƕ����pV-ONU��lj�����K�v������B
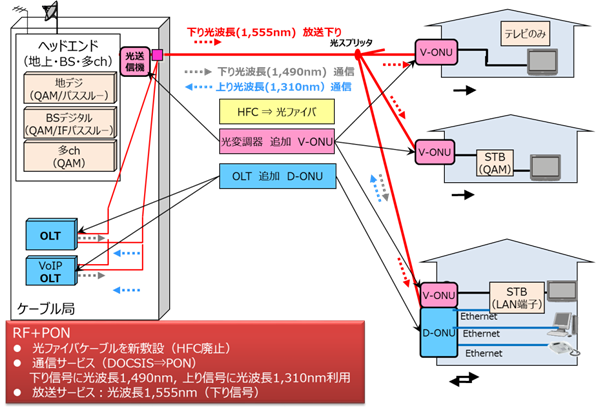
�} 2‑31�@RF�{PON�V�X�e��
2.2.3.3�@ RFoG
RFoG�V�X�e���́A���t�@�C�o�P�[�u����V���ɕ~�݂��邪�ADOCSIS�̃Z���^�[�ݔ������[���ݔ������̂܂܊��p����B���������ĒʐM�ݔ��̓�����������FTTH����i�߂邱�Ƃ��ł����߁ARF�{PON�V�X�e���ւ̈�̈ڍs��i�ƈʒu�t���邱�Ƃ��ł���B
�������A�ʐM�T�[�r�X�̍���̍��������v�ɑΉ�����ɂ́A�o������100Mbps���邢�͂���ȏ�̓`�����x���K�v�ł���A����ɂ�RFoG�͓K���Ă��Ȃ��BPON�̒ʐM���ŏ����瓱������K�v������B
RFoG�V�X�e�����} 2‑32�Ɏ����悤�ɁA�����P�[�u���̉�����̐M�����e�X���Ɋ��蓖�Ă�B����M���ɂ͌��g��1555nm���A���M���ɂ͌��g��1610nm���g���B
RFoG�����i�`���HFTTH�j�ɕK�v�Ȑݔ��Ƃ��ẮA�ǐݔ��̌�����M�@�AFTTH�`���H�i���t�@�C�o�j�A�ƒ�[����R-ONU�ł��肷�ׂĒlj�����K�v������B
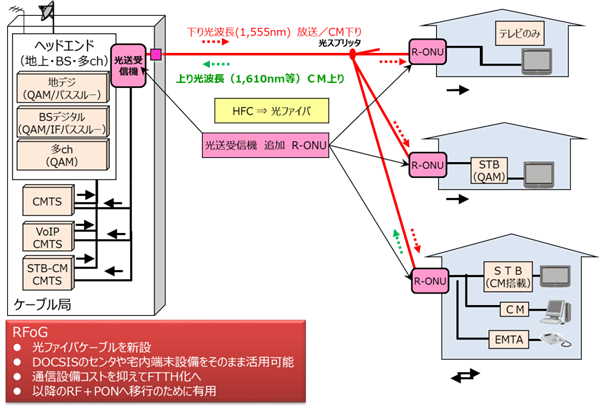
�} 2‑32�@RFoG�V�X�e��
2.2.3.4�@ HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h
HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h�V�X�e���́A�����T�[�r�X��HFC�ŁA�ʐM�T�[�r�X��FTTH�iPON�j�Œ���V�X�e���ł���B
�Ȃ��AHFC�̓����A���v�ւ̋��d�@�\���c�邱�Ƃɕt�����ăP�[�u��Wi-Fi�̉��O�A�N�Z�X�|�C���g�ւ̋��d�@�\���c�邱�ƂɂȂ�B
HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h�V�X�e����} 2‑33�Ɏ����B
HFC�{PON�i�f���A���t�B�[�h�j�����ɕK�v�Ȑݔ��́A�����p�ɂ͊����̃w�b�h�G���h�ݔ��AHFC�`���H����щƒ���̃e���r�ł���lj���v���Ȃ����A�ʐM�p�ɂ͋Ǒ���OLT�AFTTH�`���H�i���t�@�C�o�j�A�ƒ�[����D-ONU�ł��肷�ׂĒlj�����K�v������B
PON�ɂ���ĒʐM����������������ł��邽�߁A�o����STB��CM�����^����LAN�[�q�Ή��^�ɕύX����K�v������B�������A������DOCSIS�ɂ��o����STB�ւ̒��p������ꍇ�ɂ́A�o����STB�̕ύX�͕K�v�Ƃ��Ȃ��B
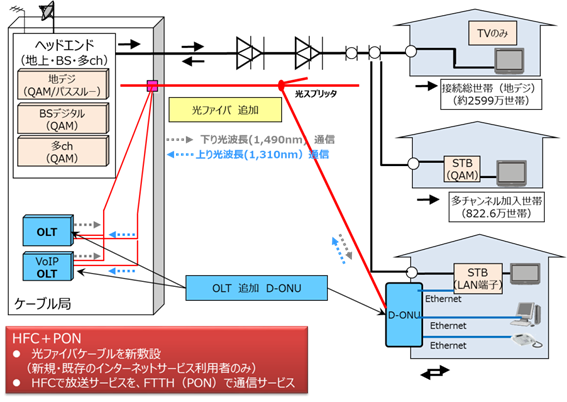
�} 2‑33�@HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h
�f���A���t�B�[�h�����́AHFC�̍��x���i���Z�����j�p����ꍇ�ƕ��p���Ȃ��ꍇ�ƂňႢ������̂ŁA���ꂼ���} 2‑34����ѐ} 2‑35�Ɏ����B
���Z�����p�����ꍇ�ɂ́A���m�[�h��OLT������Ȃǂ��Ē���ݒu���\�ɂȂ�AOLT�����e���邽�߂̃T�u�Z���^�������炷���Ƃ��ł���B�܂��AOLT-ONU�Ԃ̋������Z���Ȃ���t�@�C�o�ɂ�鑹��������i���g��1,310nm�ɂ�����10km�Ŗ�5dB�j�B�������AOLT�̒���ݒu�ɂ��Ă͓d�����ˏ����ɂ��B
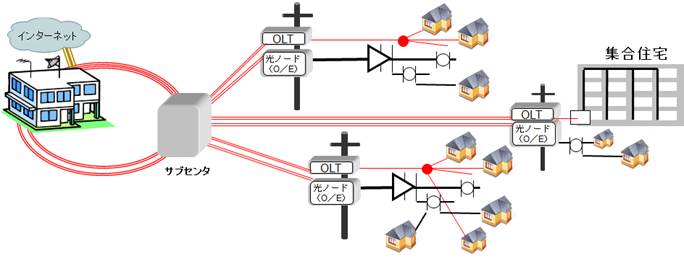
�} 2‑34�@���Z�������p�̃f���A���t�B�[�h
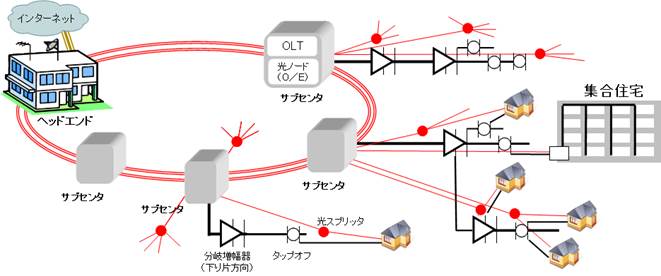
�} 2‑35�@���Z�������p�̂Ȃ��f���A���t�B�[�h
2.2.3.5�@ HFC����FTTH�ւ̍��x�������̑I��
HFC�ARFoG�AHFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h�ȂǁAHFC����FTTH�ւ̍��x�������̑I���ɍۂ��l�����ׂ��v�_��\ 2‑11�Ɏ����B
�\ 2‑11�@HFC����FTTH�ւ̍��x�������̑I��

![]()
��\�̓K���̂���G���A�Ɋւ��⑫����B
�@ HFC�����iDOCSIS 3.1�j�͊����̕����iRF�j�ɍ��킹�ĒʐM��DOCSIS 3.1�ɍ��x����������ł���ADOCSIS�̋ǐݔ�CMTS�Ɗe�ƒ���ɂ���CM�̌������K�v�ł���B�ʐM�̍��������}��邽�߁A�������p�\��HFC�n�悩�C���^�[�l�b�g���嗬�̒n��ɂ����ēK����L����B
�A RFoG�����i�`���HFTTH�j�͓`���H�݂̂�FTTH����������ł���A�����̕����iRF�j�ƒʐM��DOCSIS�͂��̂܂܂Ƃ��A�ǐݔ��̖��[�iFTTH�`���H�̋��E�j�Ɍ�����M�@���A�e�ƒ�[�iFTTH�`���H�̋��E�j��R-ONU��lj�����݂̂ł���̂ŒʐM�̍������͐}��Ȃ��B�V��������HFC�n��ł��C���^�[�l�b�g���嗬�ł͂Ȃ��n��ɂ����ēK����L����B
�B HFC�{PON�i�f���A���t�B�[�h�j�����͕�����������HFC�Œ��ʐM��PON�iFTTH�j�ŐV�K�\�z��������ł���A�ǐݔ���OLT���A�`���H��FTTH���A�e�ƒ�[�iFTTH�`���H�̋��E�j��D-ONU��lj�����K�v������BPON�ɂ��ʐM�̍��������}��邽�߁A�ĕ������[�U���嗬��HFC�n��ł����ĐV�K�C���^�[�l�b�g���[�U�̊l�����邢�̓C���^�[�l�b�g������]�̍����n��ɂ����ēK����L����B
�C RF�{PON�����iFTTH�j�͈�ʓI��FTTH�����ł���A�ǐݔ���OLT�ƕ����p�����M�@���A�`���H��FTTH���A�e�ƒ�[�iFTTH�`���H�̋��E�j��D-ONU��V-ONU��lj�����BPON�ɂ��ʐM�̍������ƕ����iRF�j�̒��}��邽�߁A�V��������HFC�n��ł��C���^�[�l�b�g���嗬�̒n��ɂ����ēK����L����B
2.3�@ �W���Z��ɂ����铏���`���Z�p
2.3.1�@ �����P�[�u�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p
��ˌ��ďZ��ɂ��ẮAHFC�`���H�̑ш�g����PON���ɂ��1Gbps�̍���������������悤�Ƃ��Ă��邪�A�W���Z��̒ʐM�������ɂ��Ă͌��ߎ�ƂȂ��@���Ȃ��A���ꂪ�W���Z��䗦�̍����n��ɂ����������x�点��v���ƂȂ��Ă����B
�P�[�u���`���H�̒ʐM���x�̍������̂��߂ɂ��AHFC�`���H�ł́A������DOCSIS 3.0��ϒ��E�������Z�p�����x������DOCSIS 3.1������AFTTH�`���H�ł�ITU-T�W����G-PON��IEEE�W����E-PON�����邱�Ƃ͐�q�̂Ƃ���ł���B
FTTH�ɂ��`���H�̍������́A�W���Z����ɂ����Ă���Ɍ��������������������邱�Ƃ����z�ł���A���̂��߂ɂ͊e�ƒ�܂Ō��t�@�C�o�Œ��ڐڑ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�����̏W���Z����ɂ͓����P�[�u�����z������Ă��錻����A���݂̔z�Ǔ�����Ċe�˂܂Ō��t�@�C�o��z������͍̂���ł���B�܂��A�W���Z����ł̓c�C�X�g�y�A�P�[�u���i�d�b���j�̗��p���\�����A�P�[�u�����Ǝ҂�����e����ł��铯���P�[�u���ɂ�鍂�����̉\��������A�����L�����p���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B���܂ł̋Z�p�ŁA�W���Z����̔z���ɂ��̗p�ł���W���Z����̒ʐM�Z�p��r��
�\ 2‑12�Ɏ����B
�Ȃ��������̗��R�œ����P�[�u���𗘗p�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�d�b���ɂ�鍂���ȓ����ʐM���������p�\�ł���B
�\ 2‑12 �@�W���Z����̍ݗ��ʐM�Z�p��r
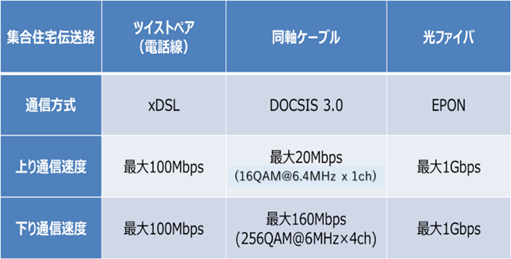
���܂ł̓����P�[�u���𗘗p����DOCSIS 3.0�́A�����`���A�o�����`���A����`���A���������P�[�u���𗬗p�\�Ȃǂ̗��_�͂��邪�A�ш�̊m�ہi���ɏ��ш�̊m�ہj����/���葬�x�̋ϓ����ɓ�_������B
�����ŁA�Ώۂ̏W���Z����ł�HFC���ɂ��o����������Ă���O��ŁA�܂��A�W���Z��܂ł�PON���p���Ȃǂœ`�����邱�ƁA�W���Z��ŏ��/����M�����I�[�i��藬���G�����팸�j���邱�ƁA��������M���ȊO�̐M���͂Ȃ����ƁA���ш�͑S�ш�W���Z����ŗ��p�\�ł��邱�Ƃ�O��ɁADOCSIS 3.0�ADOCSIS 3.1�AC-DOCSIS���p��EoC�iEthernet over Coax�A�����P�[�u�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p�j�ȂǏW���Z������Z�p�ɂ��Ă��̓K�ۂ�����������������B
���̌��ʁAC-DOCSIS���p��EoC�͊����[���i�P�[�u�����f���j�����p�\�ł��邱�Ƃ�A����ш�i���10�`55MHz/����70�`770MHz�j�ł��A���100Mbps�i64QAM�~4ch@6.4MHz�j�A����300Mbps�i256QAM�~8ch@6MHz�j���\�ł��邱�Ƃ͕��������B�ڍׂ��ȉ��ɐ�������B
2.3.1.1�@ C-DOCSIS
EoC�́A�L�`�ɂ�Ethernet�M�����P�[�u�����ɓ`������Z�p���Ӗ����A�d�͐����p��HP AV��d�b�����p��Home PNA������̔h���Z�p������Ɋ܂܂�邪�A�{�߂ł͏�艺��̎��g���ш���Ďg�p���A�P�[�u���e���r�Ƃ̐e�a��������C-DOCSIS�ɂ��ďq�ׂ�B
C-DOCSIS�́A2014�N8��29����C-DOCSIS System Specification�gcm�|SP�|CDOCSIS- I01-140829�h�Ƃ��ĕč��P�[�u�����{�ɂ�菉�ł����J���ꂽ�B���̌�A��2�ŁiI02�j��2015�N3��5���Ɍ��J����Ă���B�܂��ADOCSIS 3.0 Operations Support System Interface Specification�iCM-SP-OSSIv3.0�j�̍ŐV�ŁiI25�j���������s����AAnnex S Additions and Modifications for Chinese Specification���lj�����Ă���B
C-DOCSIS�́gChina DOCSIS�h��gCabinet DOCSIS�h�Ƃ��Ă�A�W���Z��̒ʐM�������̂��߁A�W���Z���MDF�����ɐݒu����CMTS�ƁA�����̓����P�[�u���o�R�Ŋe�ƒ�̃P�[�u�����f���Ƃ��ʐM���s�������ł���BCMTS�����^���������ɂ������̂�CMC�iCable Media Converter�j�ł���A�P�[�u���ǂɐݒu�����CMC�𐧌䂷�鑕�u��CMC�R���g���[���ƌĂԁB���̗��p����} 2‑36�Ɏ����B
C-DOCSIS�ł́A�P�[�u�����f���ƊǗ����u�i�v���r�W���j���O�j���͌��݂̂��̂����̂܂ܗ��p���Ȃ���A�W���Z��ɐV����CMC��ݒu�E�������邱�Ƃɂ�荂�������\�ƂȂ邽�߁A�^�p���S�����Ȃ��B�W���Z��̓��������łȂ����㓙�ɂ��ݒu�\�ȋ@�킪���i���i���FHuawei MA5633�j����Ă���B�����M���́A���ϒ��킩����t�@�C�o�ɂ���ē`�����A�W���Z����⒌��̑��u��CMC�o�͂�DOCSIS�M���ƍ������邱�Ƃ��\�ł���B
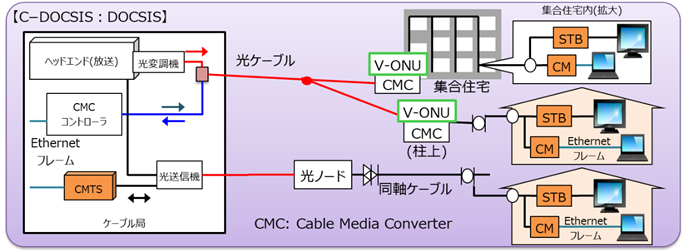
�} 2‑36�@C-DOCSIS�̗��p��
�����ɂ́ACMC�R���g���[����CMC�̋@�\���ǂ̂悤�ɕ��S�E�������邩�ɂ��AC-DOCSIS�ɂ͎���3��ނ�����B���̃A�[�L�e�N�`���̊T�O���} 2‑37�Ɏ����B
Type 1�iMini CMTS�j CMTS�̂قڂ��ׂĂ̋@�\�������[�g���ɒu���B
Type 2�iRemote MAC-PHY�j CMTS��MAC�w�ȉ��̋@�\�������[�g���ɒu���B
Type 3�iRemote PHY�j CMTS��PHY�w�̋@�\�݂̂������[�g���ɒu���B
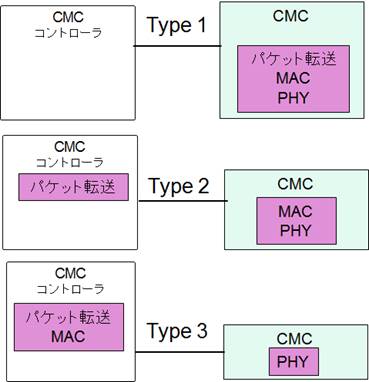
�} 2‑37�@C-DOCSIS��3��ނ̃A�[�L�e�N�`��
�����[�g����CMC�́AType 1���ł����G�ō����AType 3���ł��ȈՂň����ɂȂ邱�Ƃ��z�肳��邪�A�ێ�E�^�p���܂߂Ă̑������f���K�v�ł���B
2.3.1.2�@ C-DOCSIS�̃P�[�u���ǂł̎��؎���
���{�P�[�u�����{�̏W���Z��ʐM����������WG��CNCI�Ő��i����@�iHuawei MA5633�j��p����C-DOCSIS�̎��؎������s�����B�����œ���ꂽ�ʐM���x�̑��茋�ʂ��\ 2‑13�ɁA�����n���}���} 2‑38�Ɏ����B���̎����ł͏��65�`80Mbps�A����280�`360Mbps�������Ă���B
�\ 2‑13�@�W���Z��i���Z�҂Ȃ��A�������ȂǂƂ��ė��p�j�ł̒ʐM���x���茋��
|
|
�M������ |
���茋��:�ʐM���x |
|
���M�� |
SCDMA�F6.4MHz�~3�g�{3.2MHz�~1�g�@�S64QAM |
80Mbps |
|
ATDMA�F6.4MHz�~2�g�{3.2MHz�~2�g�@�S64QAM |
65Mbps |
|
|
����M�� |
8MHz�iAnnex A�j�~8�g�@�S256QAM |
360Mbps |
|
6MHz�iAnnex B�j�~8�g�@�S256QAM |
280Mbps |
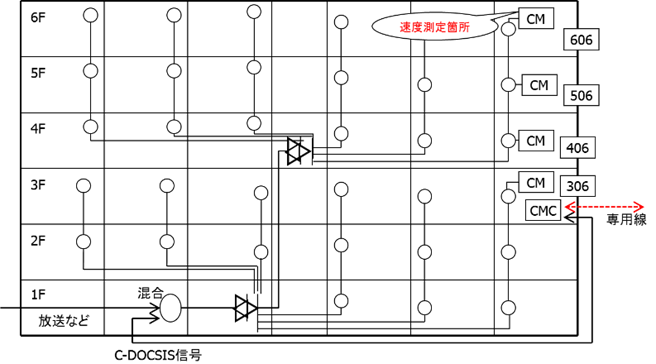
�} 2‑38�@�W���Z��i���Z�҂Ȃ��A�������ȂǂƂ��ė��p�j�ł̎������v�}
���p�����i�߂��Ă���C-DOCSIS�ȊO�ɂ��A�W���Z��ɂ�����`���ɂ͗��p�\�Ȍ�����������������̂ŁA�������Љ��B
2.3.1.3�@ Home PNA over Coax/G.hn
Home PNA�́A���X�͉ƒ���̓d�b�����𗘗p���郁�K�r�b�g�N���X�̓`�������Ƃ��ĊJ������A���̌�J�����ꂽG.hn���M�K�r�b�g�N���X�̑��x�ɑΉ����Ă���B�`���}�̂Ƃ��Ă͓����P�[�u�������p�\�ł���A�W���Z������\�����[�V�����Ƃ��Đ��i����������Ă���B
�{���ł͗������̊T�v����яW���Z������\�����[�V�����ɂ��ĉ������B
�@ Home PNA 3.1 over Coax
Home PNA�iHome Phoneline Networking Alliance�j�͉ƒ���̓d�b���𗘗p��������`���𐄐i����c�̂Ƃ��Đݗ�����A2001�N��ITU-T����G.989.1�����肳�ꂽ�i���̌�A2005�N��G.9951�ɉ��́j�B�����P�[�u���𗘗p�\�ȋZ�p�K�i��Home PNA 3.1 over Coax�ƌĂ�A2007�N1����ITU-T G.9954��v2�Ƃ��Ċ��������ꂽ�B�ϒ������Ƃ���QAM�������͒�V���{�����[�g�ł�FDQAM�iFrequency Diversity QAM�j���̗p���A�ő�`�����x320Mbps��������B
�\ 2‑14��Home PNA�̐i�W�A�܂��} 2‑39��Home PNA 3.1�iG.9951�j�̃X�y�N�g�����[�h�������B
�\ 2‑14�@Home PNA�̐i�W
|
�K�i |
ITU-T���� |
���莞�� |
�����w���x |
���l |
|
Home PNA 1.0 |
- |
1998�N |
1Mbps |
|
|
Home PNA 2.0 |
G.9951 |
2001.2 |
32Mbps |
������G.989.1 |
|
Home PNA 3.0 |
G.9954 |
2005.2 |
128Mbps |
|
|
Home PNA 3.1 |
G.9954 |
2007.1 |
320Mbps |
�����ɑΉ� |
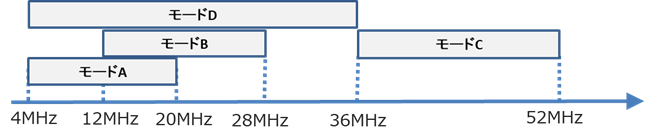
�} 2‑39�@Home PNA 3.1�iG.9954�j�̃X�y�N�g�����[�h
�A G.hn
G.hn�ihn: home network�j�́AHome PNA�̃M�K�r�b�g�ł̈ʒu�t���ŁA�������̓����P�[�u���A�d�b���A�d�͐��Ƃ���3�̊����z���𗘗p�ł��铝��I�ȓ`�������̊m����ړI�ɍ��肳�ꂽ�Z�p�d�l�iITU-T�����Q�j�̑��̂ł���B���̂��������w��ITU-T G.9960�iUnified high-speed wireline-based home networking transceivers - System architecture and physical layer specification�j�ɋK�肳��Ă���BG.hn�������w���x�͍ő�2Gbps���x�i200MHz�ш���g�p�����ꍇ�j�ł���A����d�ʐM�iTDD�j���s���B
G.hn�֘A��ITU-T�����Q�̈ꗗ���\ 2‑15�ɁA�܂��A�����P�[�u���𗘗p����ꍇ�̎g�p���g���͈́iTTC�W��JT9960�ɋK��j���} 2‑40�Ɏ����B
�Ȃ��A2009�N1���Ɋ��������ꂽG.9970�́A�z�[���l�b�g���[�N�̓`���T�O�iG.hnta: home network transport architecture�j���K�肷����̂ŁA���̑Ώۂ́AG.hn�݂̂Ȃ炸�AHome PNA 3.1�iG.9954�j�����HD-PLC�iIEEE 1901�j���܂ށB
�\ 2‑15�@G.hn�֘A�����Q
|
���� |
���C�� |
�������莞�� (�ŐV��) |
�K����e |
|
G.9970 |
�l�b�g���[�N�w |
2009.1 |
�z�[���l�b�g���[�N�`���T�O�K��(G.hnta) |
|
G.9961 |
�f�[�^�����N�w |
2015.7 |
�f�[�^�����N�w�K�� |
|
G.9962 |
2014.10 |
�Ǘ��K�� |
|
|
G.9960 |
�����w |
2015.7 |
�V�X�e���A�[�L�e�N�`���ƕ����w |
|
G.9964 |
2011.12 |
�X�y�N�g���Ǘ��K�� |
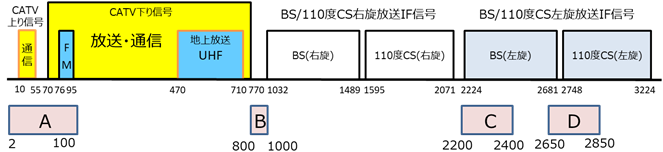
�} 2‑40�@G.hn�p���g���сiTTC�W��JT-9960�j
��L4�̑ш�iA�AB�AC�AD�j�̈ꕔ��BS-IF��`�����̖ړI�ŗ��p����Ă��邽�߁A�P�[�u���e���r�ŗ��p����ꍇ�ɂ́A���ꂼ��̋ǂɂ�������g�����p�ɍ��킹�Ċ����̃T�[�r�X�Ɗ����Ȃ����g����I������K�v������B
Home PNA 3.1�����G.hn���P�[�u����ŗ��p����ꍇ�̕����w�K��T�v���\ 2‑16�Ɏ����B
�\ 2‑16�@�����P�[�u����p����Home PNA 3.1�����G.hn�iITU-T G.9960�j
|
�K�荀�� |
Home PNA 3.1 (����) |
G.hn (����) |
|
���g���͈� |
4�`36MHz (���[�hD) (�}4-26�Q��) |
2�`100MHz�A���@�@(�}4-27�Q��) |
|
�ő�`�����x |
320Mbps (32MHz�A10bit/Symbol) |
1Gbps (100MHz�ш敝) 2Gbps (200MHz�ATDD) |
|
�ϒ����� |
FDQAM/QAM |
OFDM(QAM) |
|
������ |
CRC-8 |
LDPC-BC (Low Density Parity Check Code-Block Code) |
|
�ő�ڑ��䐔 |
|
32 (�I�v�V������250)�� |
�B Home PNA 3.1/G.hn�Ή����i�iHCNA�j
�W���Z����̊����̓����P�[�u���𗘗p����MDF�`�e�����ґ��ڑ����鐻�i�ŁAHome PNA 3.1 over Coax/G.hn�ɏ���������̂Ƃ���HNCA�ƌĂ�鐻�i������B�����i��C-6�ƌĂ�郂�f����Home PNA 3.1�����AC-7�AC-8��G.hn�����ł���B�\ 2‑17�ɍŐV��C-8�̐��i�d�l�������B
�\ 2‑17�@HCNA���i�d�l�iG.hn�����j
|
���i���f�� |
CEM-837(�e�@)�ACEM-831(�q�@) |
|
�q�@�ő�ڑ��䐔 |
30��ȉ� (����) |
|
���[�J |
SENDTEK(��p) |
|
�ϒ����� |
OFDM |
|
�g�p���g���� |
6-76MHz |
|
�`�����x |
1Gbps(���_�l)�A750MHz+(�����l) |
|
�o�͒l/���e���� |
6dBm / 70dB |
|
�ő�ڑ�MAC�� |
1024 |
|
�e�@�ڑ��|�[�g |
SFP x 1 & GbE x 2 |
|
�q�@�|�[�g(LAN��) |
GbE x 2 (�C���^�[�l�b�g�A�d�b) |
|
IP |
IPv4/IPv6 |
|
�d��(�e�@) |
12VDC�ALine Power�APoE |
|
DHCP Support |
Client�ARelay Option 82�ASnooping |
|
�F�ؕ��� |
PPPoE�ARADIUS�AEAP-TLS |
|
Auto Configuration |
�i�e�@�A�q�@�j |
�g�p���g���ш�̏����FM�ĕ����ш�Ƌߐڂ��邽�߁A�������g��̗��p���K�v�ƂȂ�BHCNA Master�@��͍������g���������Ă���AV-ONU�̏o�͂��hTV�h�[�q�ɓ��͂��邱�Ƃɂ��{�@�\�����p�ł��邪�AHCNA�̏��TV����~���邱�Ƃ�h�����߁A�} 2‑41�Ɏ����@��ڑ���ł́AV-ONU�����RF�����g�o�͂�BS�p�X�X���[�M����HCNA�̏o�͐M�����O���̍������g��ō������Ă���B���̏ꍇ�AHCNA�̏o�͐M�����]���ɃJ�b�g����邽�߁A�{���̎��g�������ׂĒʂ��ɂ́AHCNA�i�e�@�j���ɂč������邩�A�����t�B���^��������������퓙���K�v�ɂȂ�B
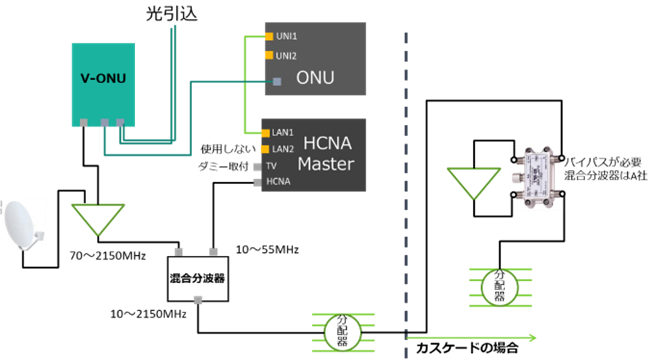
�} 2‑41�@HCNA�ڑ���
G.hn�̗̍p�ɂ������Ă͈ȉ��̓_�ɒ��ӂ�v����B
ž �P�[�u���e���r�̏��ш��TDD�ŗ��p���邽�߁A�����ݔ��ɏ������̃A���v�����݂���ꍇ�ɂ͗��p�ł��Ȃ��i��������̐M�����ʂ�Ȃ��j
C-DOCSIS�ɔ�אe�@�̉��i���������ʁA�q�@�̉��i��DOCSIS�P�[�u�����f��(CM�j�Ɣ�r���č��z�ł���B���̂��߁A�����Ґ��ɂ���ẮA�����I�ȃR�X�g��C-DOCSIS������ꍇ������B
2.3.1.4�@ �����P�[�u�����p�ɂ��ʐM�������Z�p�Ƃ��̒ʐM���x�̔�r
�\ 2‑18�ɏW���Z��̒ʐM�������̌������_�I�T�Z�l�������B�u����HFC�v�ł́A�P�[�u���ǂɐݒu����DOCSIS 3.0�𗘗p���A�W���Z���CMTS��1Port�������Ă�B�W���Z����̊��������P�[�u���i���10�`55MHz/����70�`770MHz�j�𗘗p����ꍇ�̒ʐM���x�́A���20Mbps�i16QAM��6.4MHz�j/����160Mbps�i256QAM��6MHz�~4ch�j�ƂȂ�B
�܂��A�u�W���Z��������P�[�u���v�̗��p�P�[�X�ł́A�W���Z��܂Ō�������āu�����P�[�u�����ɏ��M���Ȃ��A����ʐM�M���Ȃ��v�Ƃ�����ŁA�����ݔ��i����j�ł͏��/������g���ύX�Ȃ��ŗ��p�A�o�����A���v���C1�Ƒo�����A���v���C2�ł́A�X�Ȃ鍂��������Ƃ��āu���/������g���ύX�Ƒш�g���v���s���Ɖ��肵���B
�Ȃ��ABS-IF�ш�i1032�`1489MHz�j�͏W���Z��ł̗��p�������A�ʐM�ł͗��p���Ȃ����̂Ƃ���B
�\ 2‑18�@�W���Z��̒ʐM�������̌����i�ʐM���x�͗��_�I�T�Z�l�j
|
|
����HFC |
�W���Z��������P�[�u���i���M���Ȃ�/����ʐM�M���Ȃ��j |
||
|
����HFC�ݔ� ���10�`55MHz ����70�`770MHz |
�����ݔ��i����j ���10�`55MHz ����70�`770MHz |
�o�����A���v���C1 ���10�`85MHz ����108�`1002MHz |
�o�����A���v���C2 ���10�`204MHz ����258�`1032MHz |
|
|
DOCSIS 3.0 |
���20Mbps 16QAM ��6.4MHz�~1ch ����160Mbps 256QAM ��6MHz�~4ch |
���210Mbps 64QAM ��6.4MHz�~7ch ����320Mbps 256QAM ��6MHz�~8ch |
���330Mbps 64QAM ��6.4MHz�~11ch ����1280Mbps 256QAM ��6MHz�~32ch |
���� |
|
C-DOCSIS |
|
|||
|
DOCSIS 3.1 |
���300Mbps 256QAM ��45MHz�~1ch ����800Mbps 1024QAM ��96MHz�~1ch*** |
���300Mbps 256QAM ��45MHz�~1ch ����800Mbps 1024QAM ��96MHz***�~1ch |
���500Mbps 256QAM ��75MHz�~1ch ����1600Mbps 1024QAM ��192MHz�~1ch |
���1280Mbps 256QAM ��96MHz�~2ch ����3200Mbps 1024QAM ��192MHz�~2ch |
|
�T�[�r�X���� |
FM�Ȃǒ�
BS-IF�� |
�����Ɠ����� FM�Ȃǒ�
BS-IF�� |
FM��VHF1�`3ch �s��
BS-IF�� |
FM��VHF1�`3ch�AMIDc13�`21ch�A VHF4�`12ch�A SHBc22�`27ch �s�� BS-IF�� |
�y���z���g���ш�
�EDOCSIS 3.0/C-DOCSIS�F���5�`85MHz/����108�`1002MHz
�EDOCSIS 3.1�F���5�`204MHz/����108�`258MHz�iSHOULD�j�A
258�`1218MHz�iMUST�j�A1218�`1794MHz�iMAY�j
***6MHz�~16ch���̑ш�𗘗p����ꍇ
�y���zC-DOCSIS
�EC-DOCSIS�FType1�iMini-CMTS�j�̕����̐��i��������
2.3.1.5�@ �d�b�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p
�W���Z���MDF�`�e�����̊Ԃɂ́A�ʏ�A�d�b�T�[�r�X�ւ̗��p��O��Ƃ������^�����i�c�C�X�g�y�A�j���~�݂���Ă���A���̓d�b�T�[�r�X�Ƌ�������`�ŃC���^�[�l�b�g�A�N�Z�X�p�̓`���Z�p���p�����Ă���B���^�����𗘗p�����\�I�ȗL���A�N�Z�X�Z�p�Ƃ���ADSL�iAsymmetric Digital Subscriber Line: ITU-T G.992.1�AG.992.2�AG.992.3�AG.992.4�AG.992.5�j�����邪�A�W���Z����ł͏�艺��Ώ̒ʐM�ɗ��p�����VDSL�iVery high bit rate DSL: ITU-T G.993.1�AG.993.2�AG.993.5�j�����p������Ă���BVDSL�W�������ŋ߂̃��^���A�N�Z�X�Z�p��G.fast�ƌĂ�AITU-T SG.15�Ŋ���������Ă���B�܂��A���̍������̋K�i��MGfast�ƌĂ�A2020�N�ɕ����w�����肳�ꂽ�B
�\ 2‑19��ADSL����n�܂������^���n�A�N�Z�X�Z�p�̐i�W�������B
�\ 2‑19�@���^���n�A�N�Z�X�Z�p�̐i�W
|
�K�i���� |
ITU-T����(�����w) |
�������莞��* |
���x(����/���)(bps) |
|
ADSL |
G.992.1 |
1999.7 |
6M/640k |
|
ADSL 2+ |
G.992.5 |
2003.5 |
16M/800k |
|
VDSL |
G.993.1 |
2004.6 |
52M/2.3M |
|
VDSL 2 |
G.993.2 |
2006.2 |
100Mbps |
|
G.fast |
G.9701 |
2014.12 |
��艺�荇�v1G (106MHz) |
|
MGfast |
G.9710 |
2020.2 |
��艺�荇�v5G (424MHz) |
*�������莞���͏��ł̐���N��
2.3.1.6�@ G.fast
�@ G.fast�d�l�T�v
G.fast��VDSL2�ɑ������^�����A�N�Z�X�Z�p�Ƃ��āAITU-T SG15�ɂ����Ċ���G.9700�i�d�̓X�y�N�g�����x�d�l�j����ъ���G.9701�i�������C���d�l�j�Ƃ���2014�N�ɏ��F���ꂽ�BG.fast�֘A��ITU-T�����Q�̈ꗗ���\ 2‑20�Ɏ����B
�\ 2‑20�@G.fast�֘A�����Q
|
���� |
���C�� |
�������莞�� |
�K����e |
|
G.997.2 |
�ێ�E�^�p�E�Ǘ��w |
2015.5 |
OAM (Operation, Administration, Maintenance)�K�� |
|
G.994.1 Amd4 |
�f�[�^�����N�w |
2014.12 |
G.fast�����R���|�[�l���g�̋K�� (�n���h�V�F�[�N�K��) |
|
G.9701 |
�����w |
2014/5 |
�����w�K�� |
|
G.9700 |
2014/12 |
���g�������PSD�K�� |
G.fast�́A�} 2‑42�Ɏ����悤��2�`106MHz�܂ł̑ш�𗘗p���A�����I�ɂ�212MHz�܂Ŋg�������\��ł���BG.fast�̓d�̓X�y�N�g�����x�iPSD�j�́A������VDSL���Ƃ̋������l���������̂ƂȂ��Ă��邪�A�������S�ɔ����邽�߂ɂ�VDSL�����p����30MHz�܂ł̑ш�ŃT�u�L�����A���I�t�Ƃ���^�p���s���B���̏ꍇ�A�`���e�ʂ��ő��30%�����邱�ƂɂȂ�B
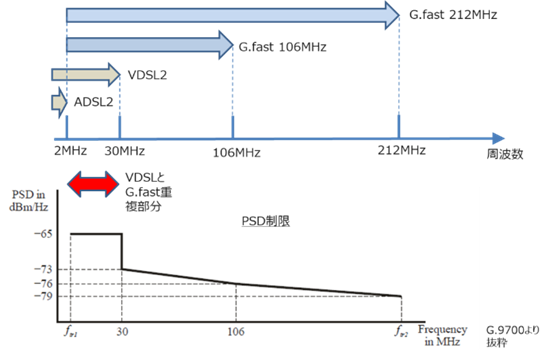
�} 2‑42�@G.fast�̗��p���g����PSD
VDSL��G.fast�̎d�l��r���\ 2‑21�Ɏ����B
G.fast�̕����w�̕ϒ������́ADMT�idiscrete multi-tone�j�ɕ��ނ��������ł���AITU-T����G.993.2��VDSL2�Ɨގ����Ă��邪�A��������}�邽�߂�1�L�����A�Ɋ��蓖�Ă�r�b�g����12�r�b�g�Ƃ��Ă���B���݂̊���G.9701�ɂ����ẮAVDSL2�̍ō�30MHz������ō�106MHz�܂���212MHz�܂Ŏg�p����v���t�@�C�����K�肳��Ă���B�������A��҂͑����̍��ڂ��p�������ƂȂ��Ă���A���ݏ��p������Ă��鐻�i�͍ō�106MHz�̃v���t�@�C�����g�p���Ă���B�܂��AVDSL2�Ƃ̋������������邽�߂ɁA�Œ���g����2.2�A8.5�A17.664��������30MHz�ɐݒ�\�Ȏd�l�ƂȂ��Ă���B
G.fast�̕��M�����́AVDSL��VDSL2��FDD�ifrequency-division duplexing�j�Ƃ͈قȂ�TDD�itime-division duplexing�j���̗p���Ă���B�㉺�����̑��x��i����/���j�́A90/10����30/70�܂Őݒ�\�ƂȂ��Ă���B
�����������́A�g�����X�����ƃ��[�h�E�\�������������̗p����Ă���B����ɁA�N���X�g�[�N�ɂ�鐫�\��}�����邽�߂ɁA���[�R�b�������I�ɃL�����Z������x�N�^�����O�Z�p�i���̃G�R�[�L�����Z���j���̗p����Ă���B�Ȃ��A�x�N�^�����O�͑��˂�ꂽ���^���P�[�u���S�̂�Ώۂɍs�����߁A�������H�i���j�𗘗p�����Ԃŕ�����G.fast�e�@���ɗ��p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����������ƁA���łɐ�s���Ǝ҂�G.fast���ς̏W���Z��ɂ����ẮA�㔭�̎��Ǝ҂�G.fast�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
ITU-T�ɂ�����G.fast�̉���R�c�ł́A�`���}�̂Ƃ��ē����P�[�u�����g�p���ď��1GHz�܂őш�g�����邱�Ƃ���������Ă���B
�\ 2‑21�@VDSL��G.fast�̎d�l��r
|
|
VDSL |
G.fast |
|
�d�l����(������) |
VDSL (17a) (ITU-T 993.1) VDSL2 (30a) (ITU-T 993.2) |
G.fast (ITU-T G.9701) |
|
�g�p���g���� |
�`12MHz (17a) �`30MHz (30a) |
2~106MHz (2~212MHz:�������i��) |
|
�ő�`�����[�g �i��艺�葍�a�j |
����30-80Mbps 150Mbps (17a) 250Mbps (30a) |
1Gbps (100m����)* 500Mbps (100m�����H) |
|
�ϒ����� |
OFDM |
OFDM |
|
�T�u�L�����A�� |
4K |
2K (106MHz�v���t�@�C��) |
|
���d������ |
FDD |
TDD |
|
����/���䗦 |
�Œ� |
��(90:10~30:70) |
|
�V���{�����[�g |
~250��s (17a) |
~20��s |
|
�x�N�^�����O |
ITU-T G.993.5 |
ITU-T G.9701 |
|
���M�o�� |
14.5dBm |
4dBm (a)�A8dBm (b) |
|
FEC |
RS + Trellis |
RS + Trellis |
���F VDSL��17/30�͑ш�̈Ⴂ�AG.fast��a/b�͑��M�o�͂̈Ⴂ
��G.9701�Ń^�[�Q�b�g�Ƃ�����E����`�����x�i���v�j�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
���� ���\�ڕW�i���{����j
100 m���� 500�`1000 Mbps
100 m 500 Mbps
200 m 200 Mbps
250 m 150 Mbps
500 m 100 Mbps
�A G.fast�̐ݒu��
G.fast��VDSL�Ɠ��l�ɁA�W���Z��̓������邢�͉��O�L���r�l�b�g����DSLAM�iDigital Subscriber Line Access Multiplexer�j�ɑ������镪�z�_���j�b�gDPU�iDistribution Point Unit�j��ݒu���ă��[�U�����e����B��{�I�ȍ\�����} 2‑43�Ɏ����B
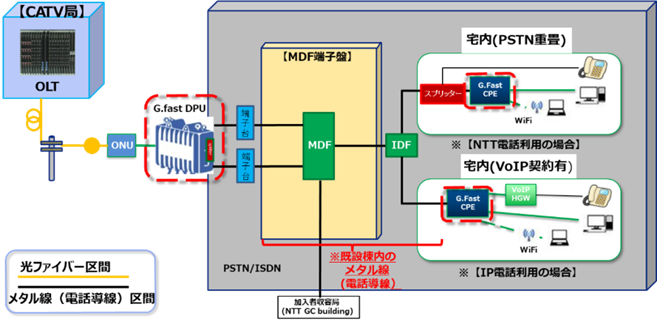
�} 2‑43�@G.fast�𗘗p���铏���ڑ��\���}
G.fast��VDSL�̌�p�����Ɩڂ���A���̓�����VDSL�����łɓ������Ă��鎖�Ǝ҂ɂ����Đe�a���������B��̓I�ɂ́AG.fast�e�@��VDSL�q�@�Ƃ��ڑ��\�ŁA�i�K�I�Ȉڍs���\�Ȃ��ƁA���i��VDSL�Ɠ��z���x�ł��邱�ƁA�v��ݒu�H����VDSL�Ƒ傫���ς��Ȃ����Ɠ�����������B
2.4�@ �V����FTTH�\�z�\�����[�V����
����܂ł̕��z�X�v���b�^��p����FTTH�\�z�Ƃ͈قȂ�A�C�O�ŃV�X�e���̒�����Ȃǂ�ړI�Ƃ����������s���A���ꕔ�̍��ł��łɓ������Ă���A���C�[�u���X�v���b�^��p����FTTH�V�X�e���̍\�z���͂��߂Ƃ���A�V���ȃ\�����[�V�����ɂ��Đ�������B
�������A����Љ��\�����[�V�����́A�P���Ɏ��@�ނ̃R�X�g���r����ƍ����Ȃ邩������Ȃ����A����FTTH�ւ̐�ւ�����������ꍇ�A����ł̌��t�@�C�o�̗Z�����팸�ł���Ȃǂ̘J���ϓ_�̃R�X�g�����b�g�����邽�߁A�P�[�X�o�C�P�[�X�ő����I�ɔ��f����K�v������B
2.4.1�@ �R�l�N�^�\�����[�V����
����܂œ��{�ł́AFTTH�V�X�e���\�z�ɂ�������t�@�C�o�P�[�u���̐ڑ��́A�ق�100���Z���ōs���Ă����B����C�O�ł́A�Z���̃X�L������������Ǝ҂��m�ۂ���̂�����A�v���O���v���C�Ŏ{�H�̃X�s�[�h���グ��R�l�N�^�\�����[�V���������Ă��āA�R�l�N�^�̂݁A���邢�̓R�l�N�^�{�Z���i�����n�̃��X�����炷�ȂǖړI�����肵�����p�j�Ƃ����g�ݍ��킹���A���X�Ɏg���͂��߂Ă���B�������A�������C��������t�@�C�o�[�̎��o���ʒu�i�h���b�v�ӏ��j�����O�ɒ������Ċm�肷��K�v������B�R�l�N�^�\�����[�V�����Ɏg�p�����^�[�~�i���̗���ȉ��Ɏ����B

�} 2‑44 �^�[�~�i���̎d�g��
�o�T�F�R���X�R�[�v�Ё@Leveraging fiber indexing technology
�} 2‑44 �ł́A��\�I�ȗ�Ƃ���12�c�̏ꍇ�������A���̎��̎d�g�݂��ȉ��ɋL�ڂ���B
�@ �O�i�i�����j�ɐݒu����Ă���t�@�C�o���z�n�u�i�}���ɋL�ڂȂ��j����12�c��
���t�@�C�o�P�[�u�����^�[�~�i���ɓ���Ƃ��납��n�܂�B
�A �^�[�~�i�������Ńt�@�C�o�����A�擪�̃t�@�C�o1����̐M����1:4�܂���
1:8�X�v���b�^�i���[�q�j�ɑ����A�n��̌ڋq�ɃT�[�r�X�����B
�B �c��̌��t�@�C�o�i2�`12�j�́u�C���f�b�N�X�v�i���Ԃ�1�i�߂邱�Ɓj����A
12���t�@�C�o��MFOC�iMulti-Fiber Optical Connector�F���c���R�l�N�^�j ���g�����������B
�C 12�c�̌��t�@�C�o�P�[�u���́A���̒[���i��2�C���f�N�V���O�^�[�~�i���j�ɐڑ�����A�C���f�N�V���O�v���Z�X���J��Ԃ����B
�����ŁA�h��MPO�iMulti-Fiber Push On�j�R�l�N�^�t���^�[�~�i����p�����f�C�W�[�`�F�[���̍\�����} 4-32�Ɏ����B�ő��12��̃C���f�N�V���O�^�[�~�i����Ƀ`�F�[���ڑ����\�ŁA�h��MPO�R�l�N�^�t���̑��c�P�[�u���ɂ��A�v���O���v���C�̐ڑ������S�h���ōs�����Ƃ��ł���B
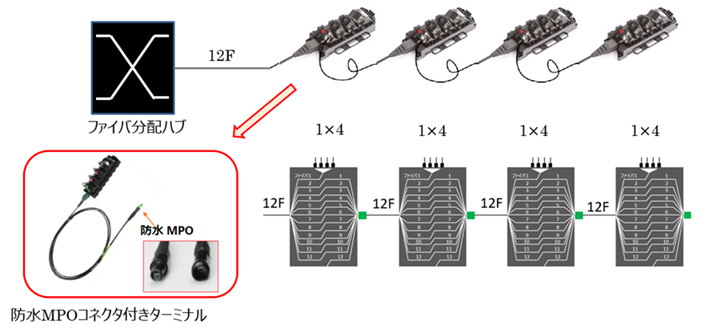
�} 2‑45 �h��MPO�R�l�N�^�t���f�C�W�[�`�F�[��
�o�T�F�R���X�R�[�v�Ё@FTTH �v���O���v���C�\�����[�V����
�{�R�l�N�^�\�����[�V�����̓W�J�R���Z�v�g��} 2‑46�Ɏ����B���ʓI�Ȑv���s�����߂̍ŏ��̃X�e�b�v�Ƃ��āA�ݒu�V�i���I�̊�{�I�ȍ\���v�f�A����у^�[�~�i���̍\�������肷��p�����[�^���`���邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�B�} 2‑46�̃^�[�~�i���i1�`12�j�̔z�u�ƃ^�[�~�i������̔z�M����Z��̌ː����A����ɊY������B�����̃p�����[�^���ݒ肳��邱�ƂŁA�����S������v�`�[���́A��`���ꂽ�r���f�B���O�u���b�N���J��Ԃ������ŁA�v���O���v���C�ł̃l�b�g���[�N���\�z���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B

�} 2‑46�@�R�l�N�^�\�����[�V�����̓W�J�R���Z�v�g
2.4.2�@ ���z���^�b�v��p�����A���C�[�u���A�[�L�e�N�`���R�l�N�^�\�����[�V����
�]����FTTH�\�z�ł́A1�c�̃X�v���b�^���͂ɑ��āA�������̃p���[�ŕ���o�����X�X�v���b�^�������̗p���Ă���B(�} 2‑47)
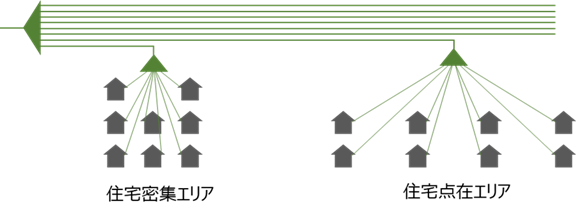
�} 2‑47 �]����FTTH�\�z
����A�V����FTTH�\�z�\�����[�V�����Ƃ��ďЉ�镪�z���^�b�v(�A���o�����X�X�v���b�^)�����ɂ��FTTH�\�z�́A1�c�̌��t�@�C�o�݂̂Ŋ����̃l�b�g���[�N���\������A�K�v�Ȋe�|�C���g�Ō��p���[��L���Ƀ^�b�v���āA���X�o�W�F�b�g���g���ʂ������܂Ń^�b�v���\�ƂȂ�����ł���B(�}4-35)�@���̃A���C�[�u���A�[�L�e�N�`���́AHFC�V�X�e���̃^�b�v�I�t��p�����z�M�`�Ԃɑ�������B�܂��A���z���^�b�v�Ԃ�Z��ւ�Drop�P�[�u���ɂ��Ă��R�l�N�^�t���P�[�u�����g�p����B
�{�\�z���@�ɂ��A�Z���Ȃ��ŒZ���Ԃ̎{�H���\�ƂȂ�A�]��������菭�Ȃ����c����FTTH���\�z�ł���B
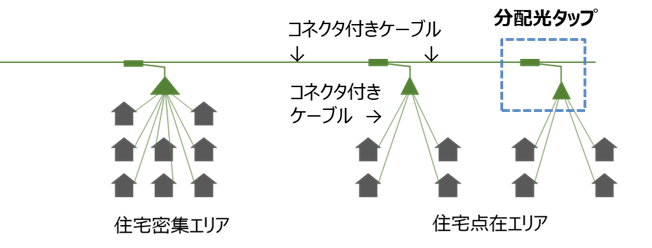
�} 2‑48 ���z���^�b�v��p����FTTH�\�z
�g�p����镪�z���^�b�v�̓��e��}4-36�Ɏ����B�����ł́A9:1�̔�Ώ̂Ō��p���[�z�����ł���B9��Thru�p��1��Drop�p�ł���B�Ȃ��A���z���^�b�v�͕����̕��z�䗦�ɑΉ��������i������B�i�\ 2‑22�j
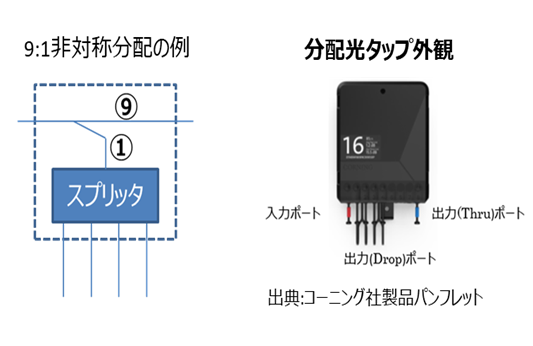
�} 2‑49�@���z���^�b�v
�\ 2‑22 ���z���^�b�v�̕��z�䗦��
�o�T�F�R���X�R�[�v�Ё@Application
Guide_ Leveraging fiber optical tap technology
2.4.3�@ MDU�ł̃R�l�N�^�\�����[�V�������p
�C�O�ł́AMDU�ɂ����Ă��Z���ڑ��ł͂Ȃ��A�R�l�N�^�\�����[�V�������̗p����Ă���B���̔w�i�Ƃ��āA�r���̃I�[�i�[��e�i���g�͓��퐶���ւ̎x����ŏ����ɗ}���A�ł��邾���Z���Ԃł̐ݒu��]��ł��āAFTTH�����ɍ��ӂ��Ă���T�[�r�X�܂ŁA���Ԃ����Ɍ����Ă��邱�Ƃ���A���Ԃ̂�����Z���ڑ������A�Z���ԂŊm���Ɏ{�H�ł���R�l�N�^�ڑ����̗p���邱�ƂŁA�Z�[����FTTH�C���t�����\�z�ł���B
�R�l�N�^�\�����[�V�����𗘗p��������MDU�ɑ���C���t���̍\�z�Ƃ��āA�}4-37�ɗ�������B�����̊ǘH�����p�ł��Ȃ��ꍇ�A���O�ǖʂɂ��̃R�l�N�^�t���P�[�u����~�݂��邱�ƂŁA�c�n�̔z���Ƃ��Ďg�p�ł���B���̃R�l�N�^�t���P�[�u���́A�H��o���Ɋ����ƂȂ�P�[�u������w�肵���Ԋu�ŕ��z�P�[�u�����}�����ꂵ�Ă����ԂŔ[�i����邽�߁A�C���t���v�i�K�Ɋe�K�̃t���A���i����Ԋu�j��A�O�ǂ���̓���������FDT(Fiber Distribution Terminal)�@�܂ł̋����i���z�P�[�u�����j���v�Z���I�[�_�[���邱�Ƃɂ��A�����ɂ҂����荇�������ނƂ��Ĕ[�i����A�������{�H���s�����Ƃ��ł���B
���n�P�[�u���Ƃ��āA�e�����ւ̈������݁A���ɖڗ����ɂ����\�����[�V����(�����ȃP�[�u���O��)�Ŕ��ς˂Ȃ����p���\�ł���B

�} 2‑50�@MDU�C���t����
2.5�@ �����`���Z�p
2.5.1�@ BWA�iBroadband Wireless Access�j�F
BWA��2008�N�ɐ��x�����ꂽ�L�ш斳���A�N�Z�X�V�X�e�����w���A�����̂ɂ�����ꕔ�̒n����J�o�[����u�n��BWA�v�ƑS�����J�o�[����u�S��BWA�v������B��̓I�ȃV�X�e���Ƃ��Ă�AXGP��WiMAX�����邪�A�������x���ɂ����TDD-LTE�Ƃ̌݊������m�ۂ���Ă���B�} 2‑51�Ɏ��g�����蓖�Ă̏������B�S��BWA��Wireless City Planning�Ђ�UQ�R�~���j�P�[�V�����Y�Ђ��^�p���Ă���B�n��BWA�͒n��P�[�u��TV���Ǝ҂Ȃ�99�Ђ��^�p���Ă��邪�A����93�Ђ�TDD-LTE�ƌ݊����̂��鍂�x���������̗p���Ă���i�\ 2‑23�j�B
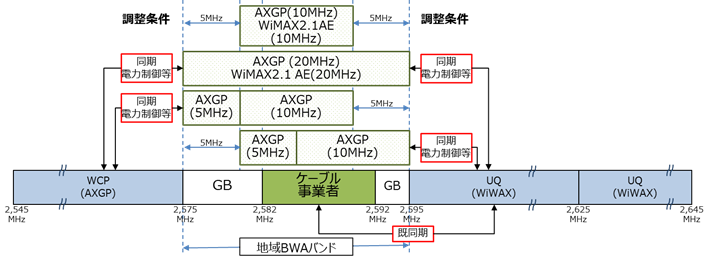
�} 2‑51�@BWA�̎��g�����蓖�ď�
�\ 2‑23�@�n��BWA�V�X�e���̖����NJJ�ݏ�
(https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/system/ml/area_bwa/002.pdf���)
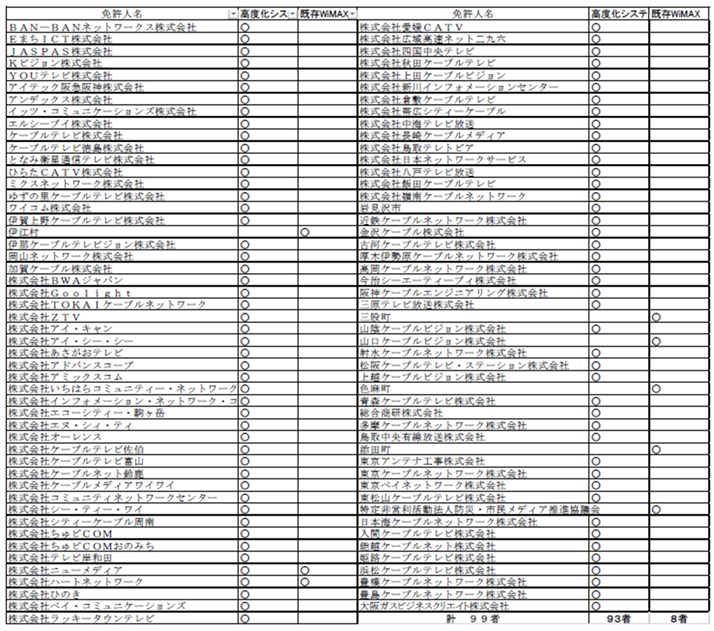
�n��BWA�̗p�r�́A�s�����ւ̉͐�Ď��f���̒�ЊQ���ً̋}�C���t������̒��邢�͉����Ҍ����̍��������ʐM�T�[�r�X�Ȃǂł���i�} 2‑52���Q�Ɓj�B
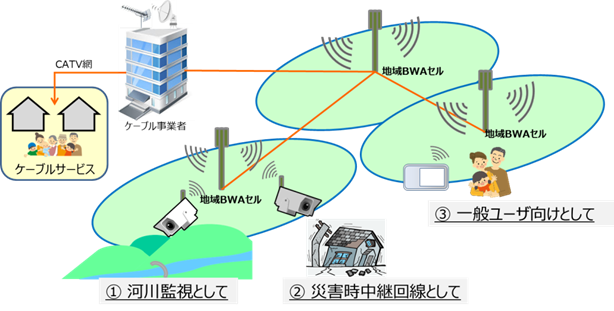
�} 2‑52�@�n��BWA�̗p�r��
2.5.2�@ 5G, ���[�J��5G, B5G/6G
2.5.2.1�@ 5G�@�@�@�`LTE����5G���`
4G(LTE)�ł͌��t�@�C�o���݂̍����`��(����1Gbps���x)��ڕW�Ƃ��C�ړ����̓��掋���������\�ȃV�X�e�������������D5G�ł́C���̐��\������Ɉ����グ��eMBB(enhanced Mobile Broadband)�Ȃ�����ɉ����C���M���D����x��(URLLC�GUltra Reliable & Low Latency Communications)�ƁC��ʂ̃f�o�C�X�Ɛڑ��ł���mMTC(massive Machine Type Communications)��3������Ƃ���V�X�e���ł���D��̓I�ɂ́C�\ 2‑24�Ɏ����悤�ȗv���������ŋK�i�����肳��Ă���D����5G�̗��p�V�[���́C3�̓����܂��Đ} 2‑53�̂悤�ȃC���X�g�ł����Ύ�����C�Љ��DX��ՂƂ��Ċ��҂���Ă���D
�\ 2‑24�@5G�̗v������
|
���� |
�v�������i4G��j |
���l |
|
���[�U�̒ʐM���x |
1000�{ |
����20Gbps�C���10Gbps���x |
|
�ڑ��f�o�C�X�� |
10�`100�{ |
1��n�ǂ����� |
|
�x������ |
1/5�`1/10 |
������Ԃ�1ms�ȉ� |
|
�f�[�^�ʐM�e�� |
1000�{ |
|
|
�����d�̓f�o�C�X�� |
10�{ |
|
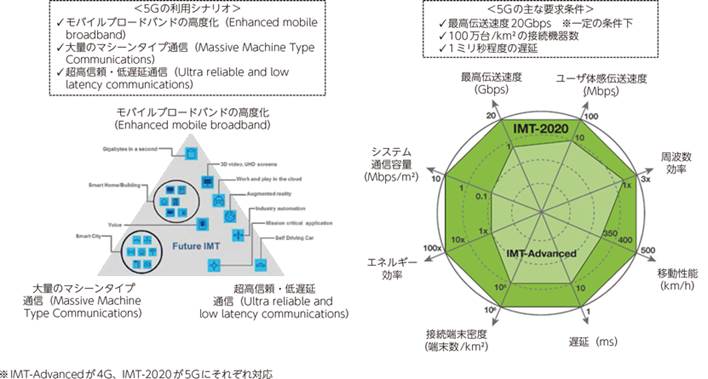
�}
2‑53�@IMT�r�W���������ɂ�����5G�̗��p�V�i���I�y�їv������
�i������ �ߘa2�N ���ʐM�������j
�@ ������
�@5G�̏��p�T�[�r�X�́A2018�N����2019�N�ɂ����Ďn�܂����B�ŏ���5G���p�T�[�r�X�́A2018�N10���ɕč�Verizon�Ђ��Œ薳���T�[�r�X�Ƃ��ĉƒ�����ɒ������Ƃ��ŏ��Ƃ���Ă��܂��B12���ɂ͕č���؍��Ń��o�C�����[�^�̒��͂��܂�A2019�N4���ȍ~��5G�Ή��̃X�}�[�g�t�H���ɂ��T�[�r�X���n�܂����B���{�ł�2020�N3��27����NTT�h�R�����ŏ���5G���p�T�[�r�X���J�n�����B�ŏ��̃T�[�r�X�G���A�͓����A���A���É��A�����̈ꕔ�n��Œ���Ă������B���̌�ANTT�h�R�����͂��߂Ƃ��鑼�̒ʐM���Ǝ҂�����5G�̏��p�T�[�r�X��W�J���A�S���I�ɗ��p���g�傳��Ă���B�������C�����_�ł͎��ɏq�ׂ�NSA��NA�̓�̌`�Ԃ����݂��Ă���B
�A NSA��SA
�@�g�ѓd�b�V�X�e���́A�[���Ɗ�n�ǂō\������閳���A�N�Z�X��(RAN�GRadio Access Network)�ƁA�R�A�Ԃō\������Ă���B4G�̃R�A�Ԃ�EPC�A5G�̃R�A�Ԃ�5GC�Ƃ����B�R�A�Ԃ̋@�\�́A���[�U�[�f�[�^���������[�U�[�v���[��(U-Plane)�ƁA�[���F��ړ���������̈ێ��Ǘ��Ȃǂ�S������v���[��(C-Plane)�ō\������Ă���B4G�̃R�A�Ԃ�EPC(Evolved Packet Core)�A5G�̃R�A�Ԃ�5GC(5G Core)�Ƃ����A���̍\����\�͂ɂ͈Ⴂ������B����5G�̓����ł����ʐڑ��imMTC�j�⍂�M����x���iURLLC�j���������邽�߁A����v���[���̍\�����傫���قȂ��Ă���i�\ 2‑25�C�} 2‑54�j�B
�\ 2‑25�@4G��5G�̖ԍ\���̈Ⴂ
|
|
�����A�N�Z�X�Z�p |
��n�� |
�R�A�� |
|
4G |
LTE |
eNodeB |
EPC |
|
5G (NSA) |
NR |
gNodeB |
NSA�Ή�EPC |
|
5G (SA) |
NR |
gNodeB |
5GC |
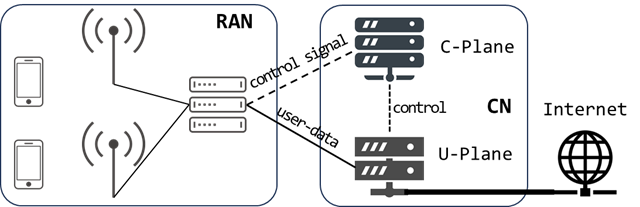
�} 2‑54�@�g�ѓd�b�V�X�e���̃l�b�g���[�N�\���T��
�@�����RAN�ɂ����ẮA4G�̖����A�N�Z�X�Z�p��LTE�A���̊�n�ǂ�eNodeB�ƌĂԂ̂ɑ��A5G�̖����A�N�Z�X�Z�p��NR(New Radio)�A���̊�n�ǂ�gNodeB�ƌĂԁB���łɊ�������Ă���4G�Ԃ�5G��n��gNodeB�����X�ɓ�������ɂ�����ANSA(Non Standalone)�Ƃ����\�����Ƃ��Ă���B����́AC-Plane��LTE�AU-Plane�ɂ�NR��LTE�p������̂ł���AgNodeB��eNodeB�ō\�����ꂽRAN��EPC�x�[�X�̃R�A�Ԃō\�������i�} 2‑55���j�B���̍\���̏ꍇ�A���M��n���h�I�[�o�[�Ȃǂ̐����LTE�ōs���A���[�U�̃f�[�^�]����NR�ɂ�鍂����e�ʓ`��(eMBB)�����������B����ɑ���SA (Stand Alone)�ł̓R�A�Ԃ�5GC�Ƃ��邱�Ƃ�5G�{�̂̔\�͂����������i�} 2‑55�E�j�B
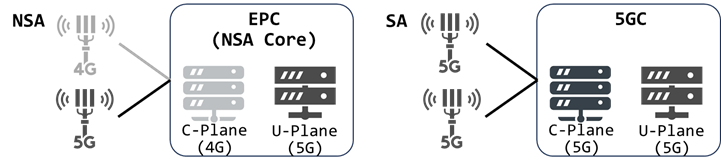
�} 2‑55�@NSA��SA�̈Ⴂ
�B ���g����
������5G�����p������g���тƂ��āA�} 2‑56�Ɏ����悤�ɁASub6�i6GHz�ȉ��j��3.7GHz�т�4.5GHz�сA����я��~���g�т�28GHz�т����蓖�Ă��Ă���B�����͏������Ɖ�������œ������g����p����TDD�iTime Division Duplex�j�ŗ��p�����B5G�̎��g���т�n�Ŏn�܂�ԍ��ŋ�ʂ���Ă���A�����ł�n77�`79��n258�ł���B

�} 2‑56�@5G�̎��g����(���l�̒P�ʂ�GHz)
�܂��A4G�����p������g���т̓o���h�ԍ��ŋ�ʂ���A�����ł͐} 2‑57�Ɏ����ш悪���p����Ă���B���̂����o���h42�̂�TDD�A����ȊO��FDD�iFrequency Division Duplex�j�Ŏg�p����Ă���B����4G/BWA�ŗp�����Ă���A3.6GHz�ȉ��̎��g���тɂ�����5G�̓����iBWA�ɂ��Ă�5G�ɑΉ��������x���j���ł���悤��2020�N8���ɐ��x�������s��ꂽ�B���̌�A�g�ѓd�b���Ǝ҂�̐\���ɉ�����5G�ւ̍��x�����i�߂��Ă���[3]�B
���E���g����c�iWRC-19�j�ɂ�����5G�ɐV���ɗ��p�ł�����g���̋c�_���s��ꂽ�B���̌��ʂ܂��A���{�����ł́A4.9�`5.0GHz�сA26.6�`27.0GHz�ыy��39.5�`43.5GHz �т�3�̑ш�ɂ����Ċ��������V�X�e���Ƃ̋��p��������������{���邱�ƂɂȂ��Ă���B�܂��A���E���g����c�iWRC-23�j�Ō����\���7025�`7125MHz �ɂ��āA���蓖�Ẳ\�������������\��ł���B���{�ł�4.9�`5.0GHz�т�802.11j�i�o�^���̖���LAN�j�Ɏg���Ă��邽�߁A5G�̓����ɂ������ẮA���݂̃V�X�e���ɉe����^���Ȃ����Ƃ����߂��Ă���[4]�B
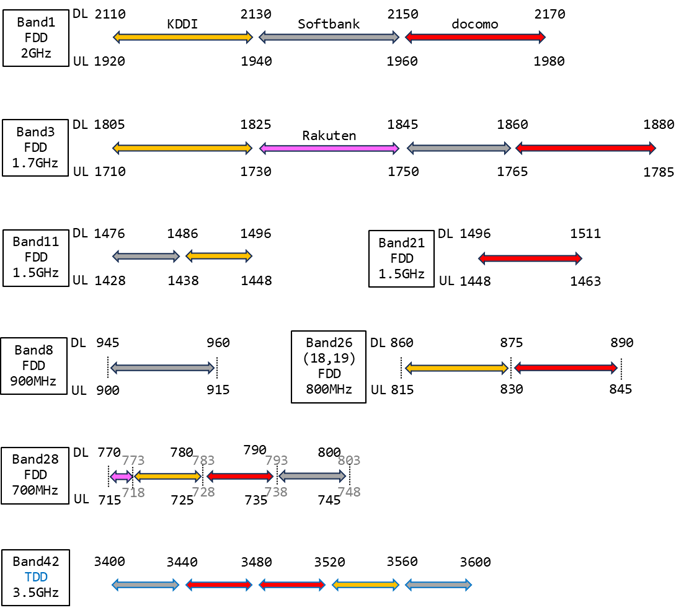
�} 2‑57�@4G�̎��g����(���l�̒P�ʂ�MHz)
2.5.2.2�@ ���[�J��5G
5G�V�X�e���͌g�ѓd�b���Ǝ҂�������O�Ԃɂ������p�������̂ł͂Ȃ��A��Ƃ�y�n�̏��L�҂�����ꂽ�͈͂œƎ���5G�l�b�g���[�N���\�z���邱�Ƃ��ł���B�����ł́A���̂悤�ȖړI�̂��߂̎��g���т��p�ӂ���A�����Ƌ��Ɋ�Â����p���F�߂���B���̂悤��5G�̗��p�`�Ԃ����[�J��5G�Ƃ����B�A�����C�Z���X�o���h��p����Wi-Fi�ɔ�ׂ�5G�̓��������������ʐM����������Ƃ���Ă���B�Ⴆ�A��x���⍂���ʐM�����āA�g�D���̃f�o�C�X��V�X�e�������A���^�C���ŘA�g���A�������v���ȃf�[�^�̓`���⏈�����������܂��B����ɂ��A��������A���^�C���Ď��A����V�X�e���̌������Ȃǂ����҂����B�܂��A��e�ʒʐM�����āA�g�D���̑����̃f�o�C�X��Z���T�[���l�b�g���[�N�ɐڑ�����A��ʂ̃f�[�^�����A���^�C���ő���M���邱�Ƃ�IoT�iInternet of Things�j�f�o�C�X�̊Ǘ���r�b�O�f�[�^�̏����ȂǁA�f�[�^�쓮�^�̃A�v���P�[�V������T�[�r�X���l������B
���[�J��5G�͑g�D���Ǝ��ɏ��L���^�p����l�b�g���[�N�ƂȂ邽�߁A�g�D�͎��g�̃j�[�Y�ɍ��킹�ăl�b�g���[�N��v�E�Ǘ����邱�Ƃ��ł���B����ɂ��A�Z�L�����e�B��v���C�o�V�[�̊Ǘ��A�J�X�^�}�C�Y���ꂽ�T�[�r�X�̒Ȃǂ��\�ɂȂ�B����̗̈��v���ɉ������J�o���b�W�G���A�̐ݒ��A�l�b�g���[�N�\���A�Z�L�����e�B�|���V�[�̒�`�Ȃǂ����R�ɍs����B����ɂ��A�g�D�̓Ǝ��̗v�������ɑΉ�����_�������B
���[�J��5G�̗p�r�Ƃ��āA�H���q�ɂł̃l�b�g���[�N�\�z�ɂ��H��@�B��^���@�B�Ȃǂ̉��u�����^�p�̎������A���邢�͕����Ǘ��≓�u�Ď��Ȃǂ����҂���Ă���B�܂��A�W���Z���L�����p�X��X�^�W�A���ł̃u���[�h�o���h�T�[�r�X�A�L�����p�X���ł̊w�K�x���V�X�e���A�C�x���g���ł̍����ʐM�ȂǁA���܂��܂ȉ��p���l�����Ă���B
���[�J��5G�̖����Ƌ�������̂͊�Ƃ�y�n�̏��L�҂Ȃǂł��邪�A�l�b�g���[�N�̍\�z��^�p�̓l�b�g���[�N���Ǝ҂�V�X�e���C���e�O���[�^�Ȃǂ��T�|�[�g���Ă悢���ƂɂȂ��Ă���B
�@ ���[�J��5G���g����
���[�J��5G��p�̎��g���тƂ��āA2020�N��4.6�`4.9GHz�y��28.3�`29.1GHz���V���ɒlj����ꂽ�B����܂�28.2�`28.3GHz��100MHz���������p�ł��Ȃ������Ƃ���ł��邪�A28GHz�т͊����ƍ��킹��900MHz���Ɋg�債�A�V���ȃT�u�U�i6GHz�шȉ��j��300MHz���ƍ��킹��1200MHz�����p�ӂ���Ă���B���̒lj��ɂ��A����܂ł�28GHz��SA�iStand Alone�j���A2.5GHz���̃v���C�x�[�gLTE�o���h�Ƒg�ݍ��킹��NSA�iNon Stand Alone�j�����ł��Ȃ������̂��A�T�u�U��SA��T�u�U��28GHz��g�ݍ��킹��NSA���ł���悤�ɂȂ���[5]�B
2.5.2.3�@ B5G/6G
�g�ѓd�b�V�X�e���i�����͎����ԓd�b�V�X�e���j��1980�N�ɓo��i�d�d���Ђ�1979�N12���ɓ����n��ŃT�[�r�X���J�n�j���A�Ȍ�A�����ނ�10�N���ɐV���Ȑ���̃V�X�e�����o�ꂵ�Ă���B���̊ϓ_�ł́AB5G/6G�̓�����2030�N���������܂�Ă���A����Ɍ��������g�݂��n�܂��Ă���B�����ł́ABeyond
5G���i�R���\�[�V�A����2020�N�ɐݗ�����ABeyond
5G���i�Ɍ����������I�Ȑ헪�̌����Ȃǂ��J�n���ꂽ�B2023�N3���ɔ��s���ꂽB5G�z���C�g�y�[�p�[��2�ł͎��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���B
�E�g���q�b�N�g�����h�F2030�N���ɗ\�z����郂�o�C���A�v���P�[�V������[�X�P�[�X����g���q�b�N�̌X���������Ă���
�E�ʐM�ƊE�̃}�[�P�b�g�g�����h�F�ړ��ʐM����̃}�[�P�b�g�����A���ɁA�X�}�[�g�t�H�����n�Ǔ��̒ʐM�C���t���ݔ��̃V�F�A�\���̕ω��ƁA�X�}�[�g�t�H���֘A�̍\�����i�̋Z�p�����������Ă���
�E���ƊE���瓾��ꂽ�g�����h�F�����_�Ő��̒��ɑ��݂��邷�ׂĂ̋ƊE�ɂ�����ۑ��o���A�ۑ�����āA�ƊE�Ƃ��Ă���ׂ��p�▲�A����ɂ́ABeyond 5G�Ɋ��҂��鐫�\��@�\���܂Ƃ߂Ă���
�EBeyond 5G�ŋ��߂���Capability��KPI�F4�͂̓��e����A�l�X�ȋƊE�ł̓����I�ȃ��[�X�P�[�X��o���A���ꂼ��̃��[�X�P�[�X�ŋ��߂���Beyond 5G�̐��\���܂Ƃ߂�Ƌ��ɁABeyond 5G���ے�����}�A6�̗��p�V�i���I�A�ڕWKPI�i��ʓI�A�萫�I�j�������Ă���
�E�Z�p�g�����h�FBeyond 5G�ɋ��߂���Z�p�̓����ɂ��Č������A����炪���p�҂�s��ɒ���@�\�E���l�E�ʂ��������E���҂Ȃǂ𖾂炩�ɂ��܂Ƃ߂Ă���
�܂��ANTT�h�R���ł́A2020�N�Ƀz���C�g�y�[�p�[�u5G�̍��x����6G�v���ł������[�X���A2022�N11���ɑ�5�ł֍X�V���ꂽ�BKDDI��2021�N��Beyond 5G/6G �z���C�g�y�[�p�[���A�\�t�g�o���N��2021�N7���ɁuBeyond 5G�^6G�̃R���Z�v�g����ю����Ɍ�������������J�v�Ƒ肵���v���X�����[�X�̒���2030�N��B5G/6G�̐��E�ςƂ���Ɍ�����12�̒���\���Ă���B
2.5.3�@ FWA
2.5.3.1�@ 22/26/38GHz��FWA
FWA�͈�ʂɂ͌Œ薳���ǂɂ��A�N�Z�X�i�����ڑ��j�V�X�e�����w���B�������Ȃ��狷�`�̈Ӗ������ł́A22/26/38GHz�т𗘗p��������Ҍn�����V�X�e����FWA�i�Œ薳���A�N�Z�X�V�X�e���j�ɖ��̕ύX����Ă��āA���ɂ�����w���ꍇ������B���`��FWA�ł́A�d�C�ʐM���Ǝґ��̊�n�ǂƕ����̗��p�ґ��̉����ҋǂƂ����ԂP�Α������^�i�o�|�l�o�GPoint to Multipoint�j�ƁA�d�C�ʐM���Ǝґ��Ɨ��p�ґ��Ƃ��P�P�Ō��ԑΌ��^�i�o�|�o�GPoint to point�j����`����Ă���B�\ 2‑26�ɂ��̊T�v�������B���݁C22GHz��FWA�̍��x����}��C26GHz��FWA���ڍs��������g���ĕ҂��i�߂��Ă���[6]�B
�\ 2‑26�@22/26/38GHz��FWA
|
|
22GHz�� FWA |
26GHz��FWA |
38GHz��FWA |
|
���g���� |
22.0-22.4/22.6-23.0 |
25.25 - 27.0 |
38.05-38.5/39.05-39.5 |
|
��L���g���ѕ� |
58.5 MHz |
|
|
|
�ő�`�����x |
156 Mbps�iP-P�j�C10�lbps(P-MP�j |
||
|
�`������ |
�ő�4km���x(P-P)�C���a1km���x(P-MP) |
||
2.5.3.2�@ ���̑���FWA
�Œ�������͔��Œ�i�m�}�f�B�b�N�j�ŗ��p���閳���A�N�Z�X�V�X�e���Ƃ��ẮA22/26/38GHz�т𗘗p����FWA�̑��ɁA5�fHz�і����A�N�Z�X�V�X�e����18�fHz�і����A�N�Z�X�V�X�e��������B���̊T�v��\ 2‑24�\ 2‑27�Ɏ����B
�\ 2‑27�@5GHz��/18GHz�� �����A�N�Z�X
|
|
5GHz�і����A�N�Z�X |
18GHz�і����A�N�Z�X |
|
���g���� |
4.9 – 5.0 GHz |
17.7-19.7GHz (17.7-18.72 / 19.22-19.7 ) �d�C�ʐM�C�����Ɩ��p 17.7-17.85 / 17.97-18.60 / 19.22-19.7�@����ړ��Ɩ��̖����� 17.7-17.85 / 17.85-18.72 / 19.22-19.7 �Œ�� |
|
��L���g���ѕ� |
5,10,20,40 MHz |
36.5 MHz |
|
�ϒ����� |
OFDM |
|
|
�ő�`�����x |
150Mbps���x |
156Mbps���x |
|
�`������ |
�`3km���x |
�`10km���x(�Ό�����) �`2km���x(1�Α���������) |
|
�ő���d�� |
0.25W ���� |
0.5 / 1.0 W |
|
�ő������ |
13dBi |
|
2.5.3.3�@ �Œ�n�����V�X�e��
�@�Œ�n�����V�X�e���̓A�N�Z�X������Ȃ��`���V�X�e���ł���A���̐ڑ��`�Ԃ͒ʏ�1��1�Ɍ�����B���������p����i�Œ�}�C�N���j��G���g�����X����̗p�r�Ŏg�p����Ă���B�\ 2‑28�ɂ��̊T�v�������B
�\ 2‑28�@�Œ�n�����V�X�e��
|
|
6 GHz�� �Œ�ʐM |
11/15/18 GHz�� �Œ�ʐM |
|
���g���� |
5925 – 6425, |
10.7 – 11.7 /
14.4 – 15.35 / |
|
�`���l���� |
|
36.5, 53.5 MHz (11/15GHz��) |
|
�`������ |
�`60km���x |
�`�\��km���x |
|
�ő�`�����x |
150Mbps���x |
150Mbps |
|
�����ǐ� |
NTT�����Ȃǖ�400�� |
��12000�� |
|
���l |
|
�����̍��x�������\����Ă���i2021�j |
2.5.3.4�@ 23GHz�і����V�X�e��
CATV���Ƃɗp�����閳���V�X�e���Ƃ���23GHz�і����`���V�X�e��������B����̓P�[�u���e���r�̎��g���z������̂܂�23GHz �т̓d�g�ɕϊ�����U���ϒ������iFDM-SSB �����j��p���A�P�[�u���~�݂�����ȉӏ��ɗp����BCATV���Ǝ҂����p�\�Ȗ����`���V�X�e���͕\ 2‑29�Ɏ���3���g���т�����B18GHz �т̖����`���V�X�e���́A�P�[�u���e���r���Ǝ҂����p����ꍇ�ɂ́A�d�C�ʐM�Ɩ��p�����ǂ̖����ݔ������p������̂Ɍ��肳��A��艺�肻�ꂼ��60MHz ���̂P�u���b�N�𗘗p���čő�9ch ��`�����邱�Ƃ��ł���B����A60GHz �т̓`���V�X�e���́A���菬�d�͖����ǂƂ��ČʖƋ��͕s�v�ł�����̂́A�o�͂�10mW �ȉ��ł��邱�Ƃ���`��������200m ���x�Ɍ����Ă���B23GHz �і����`���V�X�e���́A400MHz �̑ш悪���邽�߁A18GHz �ɔ�ׂĂ�葽���̃`�����l���`�����\�ł���A�܂��A60GHz �ɔ�ׂĒ������ł̓`�����\�ł���B
�\ 2‑29�@�P�[�u���e���r���Ǝ҂����p�\�Ȗ����`���V�X�e��
|
|
23GHz�� |
18GHz�� |
60GHz�� |
|
���ȖړI |
�L���e���r�W�����@�������Ɨp |
�d�C�ʐM�Ɩ��p |
���菬�d�͖����� |
|
���g���ш敝 |
400MHz |
��艺��e60MHz |
9GHz |
|
�ő�`�� |
65CH |
9CH |
|
|
���� |
CATV���`�����l�������̖����`�� |
����/�ʐM�����`�� |
�~���g�摜�`���p�y�у~���g�f�[�^�`���p |
|
���p�V�[�� |
������R�ԕ�����CATV�l�b�g���[�N�G���A�̊g�� |
�E�n�f�W��M�_���狤���{�݂܂ł̒��p�`�� �E������R��翂ւ̒n��C���g���l�b�g�̉������[�g |
�z�[�������N(�z���̖�����) |
|
�����b�g |
�E60GHz�тƔ�r���āA�`������������ �18GHz�тƔ�r����Ƥ�`��CH�������Ƃ���B |
�60GHz�тƔ�r���ē`�������������B �E�o�����ʐM���\�B |
�ʖƋ����s�v�B |
|
�f�����b�g |
�P�[�u���e���r�̏�����̓`�����ł��Ȃ��B |
�E23GHz�тƔ�r����ƁA�`��CH�������Ƃ�Ȃ��C �E�d�C�ʐM�Ɩ��p�����ǂ̖����ݔ��Ƌ��p������̂Ɍ����B |
�E�����ǖƋ����Ă��Ȃ��̂ŁA���M����\��������B �18GHz�ыy��23GHz�тƔ�r����Ƥ�`���������Z���B |
�@23 GHz�і����V�X�e���̊�{�\����\ 2‑30�Ɏ����B�����ǖƋ��l��NHK��P�[�u���r�W�����Ȃ�33�ǂ���i���M���j�B���݁A��e�ʉ���o�������ȂǃV�X�e���̍��x������������Ă���B
�\ 2‑30�@23GHz�і����V�X�e���̊�{�\��
|
�����ǎ�� |
�Œ�� |
�ėp���^�ړ��� |
�Ӓn�p���^�ړ��� |
|
���g�� |
23.2GHz – 23.6GHz |
23.28GHz – 23.52GHz |
23.2GHz – 23.6GHz |
|
���d�� |
1W�ȉ� |
0.5W�ȉ� |
0.005W�ȉ� |
|
�`���l���� |
65 |
40 |
65 |
|
�`������ |
�p���{���A���e�i�Ό���5�`10km 1�Α��F30cm�p���{���A���e�i�ƃZ�N�^�[�A���e�i�̑Ό���90����2km���x |
�p���{���A���e�i�Ό���5km���x |
�p���{���A���e�i�Ό���100m���x |
|
�A���e�i |
�Ό��^�F���a30cm�ȏ�̃p���{���A���e�i���� �������F�Z�N�^�[�A���e�i |
���a30�`60cm�̃p���{���A���e�i���� |
���a10�`30cm�̃p���{���A���e�i���� |
|
��ȗp�r |
�L���`���H�̕~�݂�����Ȓn��ւ̒��p��� |
�ЊQ���ɂ����鉞�}�����p�`���H �C�x���g���̔ԑg�f�ޒ��p�`�� |
�n��f�W�^�������̓������ |
2.5.4�@ LPWA
LPWA�iLow Power Wide Area�j�͒����d�͂ōL����J�o�[���閳���V�X�e���̑��̂ł���B�[���̃f�[�^�]�����x��Ԍ���M�̕p�x��}���邱�ƂŒ����Ԃ̃o�b�e���[�^�p���\�ƂȂ�A�d���ݔ��̂Ȃ����ł̉��u�Ď���@�퐧��ɗp����IoT�iInternet of Things�j��M2M�iMachine-to-Machine�j�ɓK���Ă���B���LPWA�V�X�e����\ 2‑31�y�ѕ\ 2‑32�Ɏ����B
�\ 2‑31�@���LPWA��p�V�X�e��
|
|
LoRaWAN |
Sigfox |
ELTRES |
ZETA |
|
�d�l |
LoRa Alliance����߂����J�d�l |
��Sigfox�Ђ̓Ǝ��d�l�B��ɃV���K�|�[���E��p��UnaBiz SAS�Ђ������B |
�\�j�[���J�������d�l |
ZiFiSense�Ђ��� |
|
�Ԍ`�� |
���O�A���c |
���O |
���O |
���c |
|
���Ǝ� |
������Ѓ\���R���A�� |
KCCS�i���Z���R�~���j�P�[�V�����V�X�e��������Ёj |
SNC�i�\�j�[�l�b�g���[�N�R�~���j�P�[�V�����Y������Ёj |
|
|
���g���� |
920�lHz�� |
�� |
�� |
��+429MHz? |
|
���g�����H |
125kHz |
100kHz |
200kHz |
|
|
�ʐM���x |
0.3�`50kbps / |
600 bps / |
�ő�80bit/��
|
0.3�`2.4kbps / |
|
�ϒ����� |
CSS |
|
�`���[�v�M�� |
|
|
��M���x |
|
|
-142dBm |
|
|
�M���� |
���� |
�J�Ԃ����M |
4��J�Ԃ����M |
���� |
|
�y�C���[�h |
59�`230 Byte |
���� 8 Byte |
128bit (48bit��GNSS���) |
8, 50 Byte |
|
�ʐM�����ڈ� |
��km�`�\��km |
�ő吔�\km |
���ʂ�100km |
|
|
|
|
���ۃ��[�~���O�\ |
GNSS�W������ |
���p���p�����}���`�z�b�v�ʐM���\ |
�\ 2‑32�@3GPP�����IEEE802.11�n��LPWA�V�X�e��
|
|
NB-IoT |
LTE-M |
NR-RedCap |
IEEE802.11ah |
|
�Ԍ`�� |
���O |
���O |
���O |
���c |
|
���g���� |
(�kTE�o���h) |
�� |
(5G�o���h) |
920 MHz�� |
|
���g���� |
200kHz |
1.4MHz |
20MHz(FR1[7]) 100MHz(FR2) |
1 MHz /4 MHz |
|
�ʐM���x |
21.25kbps(DL) 62.5kbps(UL) |
800kbps(DL) 1Mbps(UL) |
150Mbps(DL) 50Mbps(UL) |
150kbps�`3.3Mbps(1MHz��) / 15Mbps(4MHz��) |
|
�ő�o�� |
200mW |
200mW |
200mW |
20mW |
|
�ʐM�����ڈ� |
(�Z�����[) |
�� |
�� |
1 km (20mW) |
|
���l |
�J�o���b�W�g���@�\[8](23dB) |
�J�o���b�W�g���@�\(15dB) |
����dFDD(�I�v�V����) |
MIMO�A�}���`�z�b�v�Ή��B |
�\ 2‑31�Ɍf�ڂ��Ă���ȊO��LPWA��p�V�X�e���Ƃ��āARPMA��Flexnet������BRPMA�iRandom Phase Multiple Access�j�͕č��T���f�B�G�S��Ingenu�i�A���W�F�k�j�Ђɂ���ĊJ�����ꂽ�Ǝ������ł���DIngenu�Ђ�Qualcomm�Ђ̃G���W�j�A�ō\������C2008�N��On-Ramp Wireless�ЂƂ��đn�݂������C2016�N�ɍ��̎Ж��ɕύX�����DRPMA�͐��E���ʂ�ISM�тł���2.4GHz�т�p���C���p���g������1MHz�ŁC���ڃX�y�N�g���g�U�iDirect-Sequence Spread Spectrum�j��p���Ă���D�ʐM���x��31kbps(UL) / 15.6kbps(DL)�C�ʐM�����͂��悻20�L�����[�g���Ƃ���Ă���D�����͎��c�Ԃł̗��p�݂̂ł��������C2016�N���Ingenu�Ђ����O�ԃT�[�r�X��k�ĂŎ�|���C�Ȍ�CMachine Network ™�Ƃ��Ėk�Ă̎�v30�s�s�ȏ���J�o�[���Ă���D�����ł�2016�N���ɒ��J�H�O���[�v�������ꊇ��d���Ƃœ�������GE���̃X�}�[�g���[�^�[�����̋Z�p���̗p���Ă��������̎��Ƃ�2018�N��Next Power�Ђ֎��ƌp�����Ă���[9]�D
�@FlexNet��Sensus�Ђ̓Ǝ������ł���C2016�N8���ɐ��Z�p��Ƒ��̕�Xylem�ɔ�������A���݂�Xylem�̃u�����h���Œ���Ă���D�č��ł͊�{�I�ɂ�901�`960 MHz�̎��g���т�p���邱�ƂɂȂ��Ă��邪�C901�`902MHz�т�ISM�o���h�̑���928�`960MHz�т̃��C�Z���X�o���h�������ė��p���邱�ƂŊm���ȒʐM��ڎw�����Ƃ��\�ł���DFlexNet��2016�N8���A���Z�p��Ƒ��̕�Xylem�ɔ�������A���݂�Xylem�̃u�����h���ƂȂ��Ă���D�`�����x�͑o������100kbps���x�C�ʐM������5�`20km�ł���D�č��Ɖp���Ő����E�K�X��Ђ̃X�}�[�g���[�^�[���Ȃ��r�W�l�X�ɐ������C���{�ł��W�J���悤�Ƃ��Ă���[10]�D
2.5.5�@ Wi-Fi
Wi-Fi�́AIEEE 802 LAN/MAN Standards Committee �z����802.11 Wireless LAN ��Ɣǂ����肵���K�i�Ɋ�Â������V�X�e���ł���A���ݐڑ����i�x���_�[���قȂ�@��ł����Ă����݂ɐڑ��ł����Ɓj��S�ۂ��邽�߂ɐݗ����ꂽ�ƊE�c�̂ł���Wi-Fi Alliance���F�肵�������@��ɂ���č\�������B�ŋ߂̎��Wi-Fi�K�i��\ 2‑33�ɂ܂Ƃ߂�[11]�B�Ԏ��͑O�̐��ォ��X�V���ꂽ�p�����[�^��\���Ă���B
�\ 2‑33�@Wi-Fi�t���X�y�b�N�K�i�iWi-Fi HaLow™������Sub6�Ή��̂݁j
|
���� |
Wi-Fi4 |
Wi-Fi5 |
Wi-Fi6/6E |
Wi-Fi7 |
|
�K�i�� |
IEEE802.11n |
IEEE802.11ac |
IEEE802.11ax |
IEEE802.11be |
|
�K�i����N |
2009 |
Wave1: 2013, Wave2: 2016 |
2019 |
2024 |
|
���g����(GHz) |
2.4/5 |
5 |
2.4/5/6(6E) |
2.4/5/6 |
|
�`���l���� |
20/40 |
20/40/80, 80+80/160 |
�� |
20/40/80/ |
|
�ϒ����� |
64QAM |
256QAM |
1024QAM |
4096QAM |
|
OFDMA |
�~ |
�� |
�Z |
�� |
|
MIMO(�ő�) |
4�~4 |
8�~8 |
�� |
16�~16 |
|
MU-MIMO |
�~ |
����̂� |
�Z |
�� |
|
�s�[�N�`�����[�g(���[�U) |
600 Mbps |
3.5Gbps 6.9 Gbps |
9.6 Gbps |
46 Gbps |
|
�����E�V�Z�p |
HT �Echannel bonding �ESU-MIMO �EMAC������ |
VHT �EMU-MIMO |
HE �EOFDMA �EBSS-Color �EDSC�Ɠd�͐��� �ETWT |
�EMLO �ERestricted TWT �EMulti-RU |
2.5.5.1�@ Wi-Fi 4��Wi-Fi 5
Wi-Fi4�́A1���[�U(STA)������54Mbps���s�[�N�`�����[�g�Ƃ���O����(802.11a�A802.11g)�ɑ��āA600Mbps��HT(High Throughput)����������BWi-Fi4�ō̗p���ꂽ��v�Z�p�́A��{�`���l��2�`���l�����̑ш敝40MHz��1�`���l���Ŏg�p����`���l���{���f�B���O�ƁA�ő�4�X�g���[������ԑ��d�ł���MIMO�̗̍p�ł���AMAC�t���[���̃I�[�o�[�w�b�h�팸�Ƃ��킹�Ė�11�{�̃s�[�N�`�����[�g��B�����Ă���B������SU(Single User)-MIMO�݂̗̂̍p�ł��邽�߁A�����ɕ����̃��[�U(STA)�ɑ��ċ�ԑ��d��ł��Ȃ��B�Ⴆ��STA��2�{�̃A���e�i���������Ă��Ȃ��ꍇ�AAP��4�A���e�i�ł����Ă��ő�̋�ԑ��d����2�ƂȂ邽�߁A�`�����[�g�͋�ԑ��d���Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׂ�2�{�ǂ܂�ł���B�������AMU(Multi User)-MIMO�ł���A�����ɕ����̃��[�U�̋�ԑ��d���\�ƂȂ�B�Ⴆ�A2�A���e�i��STA��2�䂠��A����炪������4�A���e�i��AP�Ɛڑ�����ꍇ�ɂ͋�ԑ��d���̓g�[�^����4�ƂȂ邽�߁A�S�̂̃X���[�v�b�g��SU-MIMO�Ɣ�ׂČ��シ��B
�@Wi-Fi5��VHT (Very High Throughput)��W�Ԃ��AWi-Fi�K�i�ŏ��߂�MU-MIMO���̗p�����B��������������iAP��STA�j�݂̂ł���B�\ 2‑33�Ɏ������悤�ɁAWave1��Wave2�̋K�i������A�`���l���������̍ő�ш敝��2�{����Ă���BWave2�ł͍ő�Ŋ�{�`���l��4���̃`���l���{���f�B���O���ł���BMIMO�̍ő�A���e�i���g����256QAM�̗̍p�Ƒ��܂��āAWi-Fi4�ɔ�ׂĖ�11�{�̃s�[�N�`�����[�g��B�����Ă���B�܂��AMU-MIMO�̗̍p�ɂ���đS�̂̎����I�ȃX���[�v�b�g�����サ�Ă���B
2.5.5.2�@ Wi-Fi 6/6E
�@Wi-Fi6�́A�s�[�N�`�����[�g�̂���Ȃ��������A�ǂ��炩�Ƃ�����HE (High Efficiency)�A���Ȃ킿�������\�[�X�̗��p���������シ��Z�p�ɏœ_�������A�����ł̎����I�ȃX���[�v�b�g���P��_���Ă���B�A�����C�Z���X�o���h�̖������\�[�X�𗘗p����Wi-Fi��CSMA/CA����{�Ƃ��銱����̎d�g�݂�����邪�AWi-Fi�̕��y�ɔ������̑���ɂ���ĉ��P�̗]�n���萶���Ă����B
�@Wi-Fi6�œ������ꂽBSS-Color[12]��BSS (Basic Service Set)����ʂ���6�r�b�g�̎��ʎq�ł���BBSS-Color�͖����t���[���̎n�܂�������v���A���u�����ɂ���A��������m���邱�ƂŖ����ǂ�MAC�t���[��������O�Ɏ��炪������BSS����̐M�����ۂ���f�������f�ł���B���̃����b�g�̈�́A�f�����X���[�v��Ԃɓ��邱�Ƃŏȓd�͂ɂȂ��邱�Ƃł���B�܂��A�V���ɓ������ꂽDSC(Dynamic Sensitivity Control)�E���M�d�͐����BSS-Color��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�قȂ�AP���אڂ���i���Ɏg�p�`���l������������j�Ō��ʂ�����B���A����STA��������BSS�̃G���A�ɂ�����̂Ƃ���BWi-Fi6�̐����ɂ����āA��BSS�ȊO��BSS��OBSS (Overlapping BSS)�Ɨ������B�]���̈�ʓI�ȃL�����A�Z���X�ł́A�M�������m�̏ꍇ��-62dBm�AIEEE802.11�̏ꍇ��-82dBm��臒l�Ƃ��A����������M�d�͂�����ꍇ��STA�̓`���l��busy�Ɣ��肵�A���M�������ɑҋ@����BDSC�ł͂���臒l��BSS-Color�ɉ����ĕύX����B��̓I�ɂ́A��BSS�̏ꍇ��臒l��Ⴍ�iOBSS�̏ꍇ��臒l�������j�ݒ肷�邱�ƂŁAOBSS����̊��ɂ����STA�̑��M�@����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�������x�h���B��������A���M�����킴�Ɓu�������ɂ����v���đ��M����@��𑝂₷�̂ł���B����A��������ɋ��e����AOBSS�ɂƂ��Ă͋t��STA����̊��ɂ���ĒʐM��W������B�����ŁASTA�̓I�[�v�����[�v����ő��M�d�͂����AOBSS�ɗ^���銱�d�͂���背�x���ȉ��ɗ}����悤�ɂ���B��̓I�ɂ́AOBSS����̐M���������iRSSI���傫���j�ꍇ��STA�̋߂���OBSS������Ɣ��f���Ă���STA�͑��M�d�͂�Ⴍ���A�t��RSSI���������ꍇ�͑��M�d�͂�傫������B���̐���́ABSS-Color�ɂ���Ď�BSS��OBSS��f������ʂł��邩����ʓI�ɍs����B�܂�A�v���A���u���������̎�M�łnBSS����ʂł��邩��A�K�v�̂Ȃ�MAC�t���[���S�̂����X�Ǝ�M���鎞�ԁi�Ə���d�́j�̖��ʂ��Ȃ���̂ł���BDSC�ɂ��S�̂̃X���[�v�b�g���P�ʂ͏����ɂ��قȂ邪�A����[13]�ł�10%�O��̌��ʂ�������Ă���B�Ȃ��ABSS-Color��1����63�܂ł̒l�ł���A���ꂽ�ꏊ�ł͍ė��p�����BOBSS�œ����BSS-Color���g�p����Ă���ꍇ�́ASTA��AP�ɕ��Ď����I�ɒ�������d�g�݂��p�ӂ���Ă���[14]�B
Wi-Fi6�œ������ꂽOFDMA��1��OFDM�V���{��(�����̃T�u�L�����A�ō\������Ă���)���̃��[�U(STA)�ŋ��L����A�N�Z�X�����ł���A4G�ȍ~�̃Z�����[�V�X�e���ł��̗p����Ă���BOFDMA�ł́AOFDM�V���{�����\�����镡���̃T�u�L�����A��RU(Resource Unit)�ƌĂԒP�ʂɕ������A���ꂼ���RU��d�g��Ԃ��ł��K�������[�U�Ɋ��蓖�Ă�B����ɂ��A�e�T�u�L�����A�̗��p�����i�ш敝������̎����X���[�v�b�g�j�����サ�ATDMA�ɔ�ׂăV�X�e���S�̂̕��σX���[�v�b�g�����P���邱�Ƃ��ł���B
Wi-Fi6��HE�̑���IoT���ӎ������@�\����������Ă���BBSS-Color�����͂Ƃ�����STA�̏ȓd�͉���ړI�Ƃ���802.11ah�ōŏ��ɓ������ꂽ���̂ł���B���ɂ�802.11ah�ɂ���ȓd�͋@�\������TWT (Target Wake Time)��Wi-Fi6�ɍ̗p����Ă���AAP��STA���ɃX���[�v��Ԃ��Ǘ����Ă��ߍׂ����d�͊Ǘ����s�����Ƃ��ł���B����܂ł̏ȓd�͋@�\��AP��STA����ĂɃX���[�v��������d�g�݂ł�����[15]�B
2.5.5.3�@ Wi-Fi 7
������AP���אڂ���OBSS �� (�܂�dense operation�Ȋ�)���ł̌����^�p�Ɏ���������Wi-Fi 6�ɑ��āAWi-Fi 7�ł͓`�����[�g�̌���ɏd�_����A�����Ă���B���̔w�i�ɂ́A���ɍL���ш敝��L����6GHz�т̊��p�ƁA16K����X�g���[�~���O�⍂����VR�EAR�ł̗��p���z�肳��Ă���B����ɑo�����A�v���Ő[���v�����邽�߂ɂ͒�x���������K�v�ł���A�܂��e�[���̍����`�����V�X�e���S�̂ŃT�|�[�g���邽�߂Ɏ��g�����p�����̂���Ȃ���P�����߂���ł��낤�BWi-Fi7�͎��ɏq�ׂ�Z�p�����Ă����̗v���ɑΏ�����B
�܂��\ 2‑33�} 2‑58�Ɏ����悤�ɁAWi-Fi7�ł́A�ő�Ŋ�{�`���l��16���̃`���l���{���f�B���O���s�����Ƃ��ł���B����͏]����2�{�ł���A���݂̎��g���v�����ł�6GHz�тł̂ݗ��p�ł���B�܂��A�ϒ������͍ő��4096QAM���K�p����A����ɂ��r�b�g���[�g�̌����1.2�{�ł���BMIMO�ɂ���ԑ��d�����ő�16�ƁA�]����2�{�ł���B�����ɂ��s�[�N�`�����[�g(�K�i��̍ő�l)�͖�4.8�{��46Gbps�ƂȂ����B
Wi-Fi7�̐V���ȋ@�\�Ƃ���MLO(Multi-Link Operation)������B����͈��AP-STA�Ԃɂ����āA�����ɕ����̎��g����(2.4GHz / 5GHz / 6GHz)�̕����`���l���𗘗p���ăf�[�^�̑���M���s�����̂ł���B�����ɗ��p���镡���̃����N�ňقȂ�f�[�^�����`�����č����`�����������A���邢�́A�����f�[�^���d���`�����邱�ƂŐM������������B��҂̏ꍇ�A�����`���l����������busy�ƂȂ�p�x�͒P��̃`���l����busy�ƂȂ�p�x����ʂɂ͒Ⴍ�A����Ēx�������̉��P�����҂����BSTR���[�h�ł͕��������N��p���ē����ɑ���M���\�ƂȂ�A����M�����݂ɍs���ꍇ�Ɣ�ׂđ��M�܂ł̑҂����Ԃ��������A����ē`���x��������ɒጸ����B�܂��AWi-Fi 6�œ������ꂽTWT��`���x���̒ጸ�Ɋ��p����Restricted TWT���V���ɓ������ꂽ�BTWT�ł�STA����SP (Service Period;�T�[�r�X����)��݂��A����ȊO�̊��Ԃł͂���STA�̓X���[�v��ԂƂȂ�BSP�̊��Ԃ́ASP���قȂ鑼��STA�Ƌ������邱�ƂȂ����̃`���l���𗘗p�ł���̂ŁARestricted TWT�ł͂�����time-sensitive�ȃg���q�b�N�����蓖�āA�x���W�b�^�[�̒ጸ��}��B
�@�܂��A���g�����p�����̌����}��V���ȋZ�p�Ƃ��āAMulti-RU��preamble puncturing������BWi-Fi6�œ������ꂽOFDMA�́A���[�U(STA)���Ɉ��RU�𗘗p������̂ł������B���̕��Q�͗Ⴆ�ΐڑ����[�U�����Ȃ��ꍇ�ɂ��ׂẴ`���l���ш悪���p����Ȃ����Ƃł���BWi-Fi7�ł͕�����RU�����p�ł���Multi-RU���������ꂽ�B���g������̗��ꂽRU�����p���邱�Ƃ��ł��邽�߁A���g���_�C�o�V�`���ʂ����邱�Ƃ��ł���Bpreamble puncturing��Wi-Fi6�ŃI�v�V������������Ă�����Wi-Fi7�ŕK�{�@�\�ƂȂ����B�Ⴆ���[�_�[�Ȃǂɂ���ē���̎��g���ш悪�������Ƃ��ɁA���̑ш�݂̂����O���ė��p����@�\�ł���Bpuncturing�̒P�ʂ�20MHz���ł���B�]����80MHz�ȏ�̃`���l���{���f�B���O�̍ۂɊ�����ƁA20�lHz����Primary�`���l���������g�p���A����ȊO�̃`���l��(�ш敝60MHz �ȏ�)�͎g�p�ł��Ȃ������B
2.5.5.4�@ ������K�i�����iWi-Fi 8�j
�@Wi-Fi 7�̎��̐���ƂȂ�Wi-Fi 8��S���K�i�̌����ǂƂ��āAIEEE802.11bn UHR (Ultra High Reliability)-SG(Study Group)��2022�N7���ɐݗ�����A�oAR(Project Authorization Request)�̈ψ���F���o��2023�N11���܂ł�UHR-TG(Task Group)�𗧂��グ�A2028�N�����[�X�̗\��ƂȂ��Ă���B���̊�b�ƂȂ�l�����́AWi-Fi 7�œ�������MLO(Multi Link Operation)�������ɂ߂č����M�����̎����ł���B���̔w�i�Ƃ��āA�l��̗̂��p����@��Ԃ̖����ʐM�̎��v����荞�ޑ_��������BWi-Fi 7�ɑ��錻���_�ł̓����i�����ۑ�j�́A�@ ��SINR�ł̓`�����[�g�A�A�ړ�����G���A���܂����ӏ��ł̒x����W�b�^�[�A�B�`���l�������[�X�A�C�d�͏����peer-to-peer (1��1)�̒ʐM�`�ԁA�ƂȂ��Ă���B
2.5.5.5�@ ���g���сiWi-Fi�j
Wi-Fi���g�p�ł�����g���т͒i�K�I�Ɋg�傳��Ă����BWi-Fi�̓��������痘�p����Ă���2.4GHz�т�ISM�o���h�ł����邪�A�} 2‑58�Ɏ����ʂ�A�ш敝83.5�lHz(2.4GHz�`2.4835GHz)�̒���20�lHz���̊e�`���l�����I�[�o�[���b�v����`��13�`���l������`����A����ɓ��{�ł̓`���l��14��2.484GHz�ɒ�`����Ă���B2.4�fHz�т�Wi-Fi�`���l�����݂��Ɋ����Ȃ��悤��(�I�[�o�[���b�v���Ȃ��悤��)�ő���ɗ��p����ꍇ�́A�`���l��1�A6�A11�����14�̂ݗ��p����B�������A�`���l��14��IEEE 802.11g�ȍ~�g�p����Ȃ�[16]�B
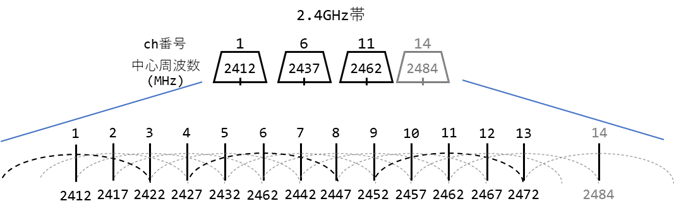
�} 2‑58�@Wi-Fi���g�p������g���i2.4GHz�сj
Wi-Fi���g�p����5�fHz�т́AW52(5.2GHz��)�AW53(5.3GHz��)�AW56(5.6GHz��)�ɕ��ނ����B�} 2‑59�Ɏ����悤�ɁA2005�N5���̑����ȗ߉����ɂ��AW52��4�`���l��(#34,#38,#42,#46)�̒��S���g�����ύX����A�����W53��4�`���l��(#52,#56,#60,#64)���lj����ꂽ�BW53��W52�Ɠ��l�ɉ����ł̎g�p�Ɍ��肳���B�܂��AW53�𗘗p����A�N�Z�X�|�C���g��DFS (Dynamic Frequency Selection)��TPC (Transmit Power Control)�̋@�\�������K�v������iDFS��TPC�͌�ɏq�ׂ�j�B
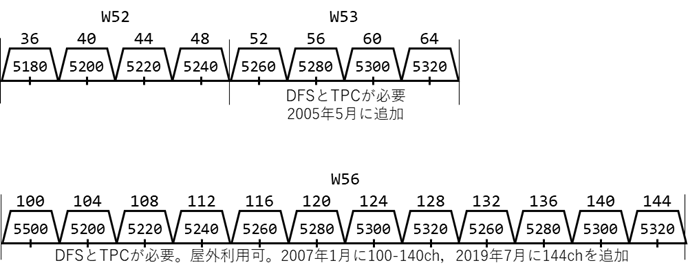
�} 2‑59�@Wi-Fi���g�p������g���i5GHz�сj
����2007�N1���̑����ȗ߉����ɂ��AW56��11�`���l��(#100, #104, #108, #112, #106, #120, #124, #128, #132, #136, #140)���lj�����A2019�N7���ɂ����1�`���l��(#144)���lj����ꂽ�BW56��W53���l��DFS��TPC�̋@�\��K�v�Ƃ��邪�A���M���ׂ��́A���O�ł̗��p���\�ŁA���o�͓d�͂̋��e�l��W52/W53(eirp200mW�ȉ�)�ɔ�ׂ�5�{�i��1W�ȉ��j�ɂȂ��Ă���_�ł���B
������2022�N9���̉����ɂ��AW52�̎����ԓ����p�ƁA6GHz�т̗��p���F�߂�ꂽ�BW52�͂���܂őD���ƍq��@���܂މ������p�����F�߂��Ă��Ȃ������B6GHz�тɂ��ẮA5.925GHz����6.425GHz�܂ł�500MHz���͈̔͂�24�`���l�����������ꂽ�B���̗��p�́A�\ 2‑34�Ɏ����悤�ɁAW52�̎����ԓ����p�ł͏]����1/5(eirp=40mW�ȉ�)�A6GHz�т̍������p�ɂ��ẮA�����Ɍ��肳���LPI�N���X�ƁA�����O�ŗ��p�ł���VLP�N���X��2��ނ��K�肳��Ă���BLPI�̑��M�o�͂�W52,W53(��200mW)�Ɠ����AVLP�͂���1/8(��25mW)�ł���B6L�ł�DFS���s�v�ł���D
Wi-Fi6E�ɂ́C������̃N���X�ł���SP (Standard Power)���K�肳��Ă���D���̃N���X�ł́CDFS�ɑւ����g�����p�̎d�g�݂ł���AFC (Automated Frequency Coordination )�@�\�̉��ōő�PW�̏o�͂����e�����D���������{�����ł͎g�p���F�肳��Ă��Ȃ��D���̃N���X��AP��AFC System�ɐڑ�����Ă���C�g�p���������g���тƑ��M�o�͂�AP��ID����шʒu���ƂƂ��Ƀ��N�G�X�g����ƁC���p�ł���`���l���Ƒ��M�o�͂��m�炳���d�g�݂ɂȂ��Ă���[17]�D
�\ 2‑34�@Wi-Fi���g�p�ł���5GHz�т�6GHz�т̕���
|
���� |
W52 |
W53 |
W56 |
6L |
|
���g���͈� |
5150-5250 |
5250-5350 |
5470-5725 |
5925-6425 |
|
�`���l���� |
4 |
4 |
12 |
24 |
|
DFS |
�s�v |
�K�v |
�K�v |
�s�v |
|
���O���p*1 |
�~*2 |
�~ |
�Z |
VLP�̂݁Z |
|
�ő�o��(eirp, 20MHz������) |
�����F23dBm �ԓ��F40mW |
23dBm*3 |
30dBm*3 |
LPI�F 23dBm VLP�F14dBm |
(*1�F��ԓ��E�D�����E�q��@���͉��O�ł͂Ȃ���������)�i*2�F�����ԓ��͗��p�\�j�i*3�FTPC�������ꍇ�͂��̔����j�Ȃ��A�@�����������ł̗��p��2.4GHz�шȊO�F�߂��Ă��Ȃ��B
2.5.5.6�@ DFS�iDynamic Frequency Selection�j
5GHz�т͋C�ۃ��[�_�[���g�p���Ă���AWi-Fi������������邽�߂̋@�\�Ƃ���IEEE802.11h ��DFS���K�肳��Ă���BDFS�ł͂܂��A�g�p����`���l���Ƀ��[�_�[�d�g�����Ȃ����ǂ����������ԁi�ʏ��60�b�j�T��B���̊m�F��CAC (Channel Availability Check) �ƌĂԁBCAC���N���A���ă`���l���g�p���n�߂Ă��A��Ƀ��[�_�[�d�g�̌��o�͍s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����In-Service Monitoring�Ƃ����BIn-Service Monitoring �̊��ԂɃ��[�_�[�d�g�����o�������݂₩�Ɂi10�b�ȓ��j�d�g�̔��M���~���Ȃ���Ȃ炸�A���̃`���l���͈�莞�ԁi30���ȏ�j�g�p�ł��Ȃ��iCAC�ł̌��o�̍ۂ����l�j[18]�B
2.5.5.7�@ TPC (Transmission Power Control)
TPC�͉q���ʐM�Ƃ̊������炷���߂ɁA�A�N�Z�X�|�C���g�ƒ[���̑o���ő��M�d�͂�������@�\�ł���BDFS�Ɠ��l�AIEEE 802.11h�ŋK�肳��Ă���B�������A�K�{�@�\�͎���5���ڂł���A��̓I�ȓd�͒l�̋K��͂Ȃ��BTPC�@�\�Ƃ��Ă͑��M�d�͂�ύX����i�K�Ȓl�ɒ�������j���Ƃ��ł���Ηǂ��Ƃ���Ă���悤�ł���[19]�B
Ÿ DFS/TPC ����������Ă��� STA ����� AP �́A���M�t���[���� Capability Bit �� Spectrum Management ���Z�b�g���邱�ƁB
Ÿ AP ����� AdHoc ���[�h�� STA �̓r�[�R������� Probe-Response �� Country IE ����� Power Constraint IE ���܂߁A�n�斈�̍ő呗�M�o�͒l�ƒጸ�v���l(Mitigation Requirement)��ʒm���邱�ƁB
Ÿ STA �� AP �ɑ��鑗�M�t���[���� Power Capability IE ���܂߁A���M�o�͒����\�͈͂�ʒm���邱�ƁB
Ÿ STA ����� AP �̑��M�o�͂� �n��ɂ���Ē�߂�ꂽ�ő�o�͋K��ɏ]�����ƁBSTA �� AP ���� Mitigation Requirement �l���w�����ꂽ�ꍇ�A�X�ɂ��̂ԂM�o�͂������邱�ƁB
Ÿ AP ����� AdHoc ���[�h�� STA �̓r�[�R������� Probe-Response �� TPC Report IE ���܂߁ALink Margin=0, Transmit Power=���g�̑��M�o�͂�ʒm���邱�ƁB
�Ȃ��A�[��STA�̓A�N�Z�X�|�C���g�̋��Ȃ�W53�AW56�̓d�g���g�p�ł��Ȃ����߁AW53�AW56�т̃`���l����AP���A�N�e�B�u�X�L�����ł��Ȃ��i�v���[�u�v�����o���Ȃ��̂Łj�B
2.5.5.8�@ IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow ™)
IEEE 802.11ah�iWi-Fi HaLow™�j�́A�g�ѓd�b�̕���ł̓v���`�i�o���h�ƌĂ��1GHz������ISM Band�𗘗p����Wi-Fi�̋K�i�ł���D�ʏ��Wi-Fi�ɔ�ׂē`�����[�g�͒Ⴂ�i�ő�15Mbps�j���̂́C��Z�����[�nLPWA��p�V�X�e��(�\ 2‑31�Q��)�ɔ�ׂ�Δ�r�I�����CIP�e�a���������B�������̒ʐM�i1�`��km���x�j���\�ŁC�[���̏���d�͂�}���邱�Ƃ��ł���B������\ 2‑35�Ɏ����B
�@���{�ł�2022�N9����11ah�̗��p���\�ƂȂ����B���Y11ah�Ή��f�o�C�X���o�ꂵ�A�R�ԕ��ł̒��b�Q��̂��߂̃J�����f����A���ݕ��ł̊C�m�Ď��Ȃǂ̏��p�@�ɂ����؎������s���Ă���B�X�}�[�g�_�Ƃ⋙�ƁA��K�͍H��⏤�Ǝ{�݂Ȃǂŗ��p�����IoT�f�o�C�X��X�}�[�g�V�e�B�Ƃ���������ł̗��p�����҂���Ă���B���ݎg�p�ł�����g����920.5�`928.1MHz�ł��邪�A����AMCA�V�X�e���̎��g���ڍs�ɔ������p�\�ƂȂ�850�`860�lHz��930�`940MHz�̈ꕔ���lj������\��������[20]
�\ 2‑35�@IEEE802.11ah ��v�p�����[�^
|
|
IEEE802.11ah (Wi-Fi HaLow TM) |
|
�Ԍ`�� |
���c |
|
���g���� |
920 MHz��(920.5 – 928.1)�A�����C�Z���X |
|
�`���l���� |
1 MHz /4 MHz |
|
�ʐM���x |
150kbps�`3.3Mbps(1MHz��) / 15Mbps(4MHz��) |
|
�ő�o�� |
20mW |
2.5.5.9�@ 60GHz��FWA�@�~���g�iWiGig�j
�M�K�r�b�g���̍����`�����������邽�߁A�L�����g���т����p�ł���~���g�i���60GHz�сj��p���閳���ʐM�K�i�Ƃ���WiGig (Wireless Gigabit)��2009�N�Ƀ����[�X���ꂽ�B���̊��͍ő�`�����x7Gbps��B��������̂ŁA���N5���Ɍ������ꂽ�ƊE�c��WiGig�A���C�A���X���p�\�R���₻�̎��Ӌ@��ł̗��p��z�肵�č��肵�����̂ł���B������Wi-Fi�̍ŐV�K�i(Wi-Fi 4)�ł́A�ő�`�����[�g��600Mbps�ł������B����AIEEE802.11�W������Ɣǔz����ad�^�X�N�O���[�v�ɂ����Ė���LAN�̃~���g���p����������A������WiGig���̗p�����`��2012�N��IEEE802.11ad�����肳�ꂽ�B�Ȃ�WiGig�A���C�A���X��2013�N��Wi-Fi�A���C�A���X�ɓ�������Ă���B
802.11ad��PHY�d�l�͕\ 2‑36�Ɏ����悤��4����BOFDM PHY�̓I�v�V�����ł���V���O���L�����A(SC) PHY��K�{�Ƃ���B�ϒ�������QPSK�ȏ�̓I�v�V�����ƂȂ�A�V���O���L�����A�ł�16QAM�܂ŁAOFDM PHY�ł�64QAM�܂łƂł���B�K�{�d�l�ɂ�����ő�`�����[�g��1155Mbps�A�V���O���L�����A�d�l�ł�4620Mbps (16QAM�A��������3/4)�AOFDM PHY�ł�6756.75Mbps�i64QAM�A��������13/16�j�Ƒ傫���قȂ�B
�@802.11ay�ł́A�ő�4�`���l���܂ł̃A�O���Q�[�V������8�X�g���[���܂ł�MIMO��ԑ��d���\�ł���B�ő原���̕ϒ������̓V���O���L�����A�̏ꍇ��64QAM�AOFDM�̏ꍇ��256QAM�ɂȂ����B�܂��Ashort GI�i�K�[�h�C���^�[�o���j�̓����ɂ��A�����`�����[�g�����シ��B�Ⴆ�A�V���O���L�����A�̏ꍇ�A�ő�`�����[�g��11ad��4620Mbps (16QAM�A��������3/4)����A8662.5Mbps(64QAM�C��������7/8)�ɂȂ�B����ɑO�q�̃`���l���A�O���Q�[�V�����Ƌ�ԑ��d���K�p�����ƁA�K�i��̃s�[�N�`�����[�g��277.2Gbps�ɂȂ�B
�\ 2‑36�@�~���g�Ή�Wi-Fi�̏���
|
�K�i�� |
IEEE802.11ad / WiGig |
IEEE802.11ay |
|
�K�i����N |
2009/2011 (WiGig 1.0/1.1) 2012 (802.11ad) |
2021 |
|
���g���� |
60 GHz (57-66GHz) |
�� |
|
�`���l���� |
2.16 GHz |
2.16/4.32/6.48/8.64 GHz (�A�O���Q�[�V����) |
|
�ϒ�����(�ő原��) |
16QAM (SC PHY) 64QAM�iOFDM PHY�j |
64QAM (SC PHY) 256QAM�iOFDM PHY�j |
|
MIMO��ԑ��d |
�Ȃ��i�r�[���t�H�[���̂݁j |
�ő�8�X�g���[�� |
|
�ʐM�����ڈ� |
|
�� |
2.5.6�@ ���̑�����
2.5.6.1�@ LAA�FLicensed Assisted Access�ALTE-U (Unlicensed)
LAA�iLicensed Assisted Access�j�Ƃ́A���C�Z���X�o���h��p����Z�����[�V�X�e�����A����LAN�������͖���LAN�����p����A�����C�Z���X�o���h�����p���ăX���[�v�b�g�����コ������̂ł���B���̋Z�p��LTE-Advanced (�����[�X10)�œ������ꂽ�L�����A�A�O���Q�[�V����(CA)�ƁA2015�N�ɐݗ������ƊE�c��LTE-U Forum�����肵��LTE-U�iLTE-Unlicensed�j���x�[�X�ɂȂ��Ă���B
�L�����A�A�O���Q�[�V�����͕����̃L�����A�𑩂˂č����`������������Z�p�ł���A��ƂȂ�L�����A�iPrimary cell�j�ɕʂ̃L�����A�iSecond cell�j���������Ĉ�̃����N���\������B�܂�LTE-U�́AWi-Fi�Ȃǂ̑��̖����V�X�e���V�X�e�������p����A�����C�Z���X�o���h�œ��삷��悤�ɁALTE�̋K�i�����ς������̂ł���A�ƊE�c�̂ł���LTE-U Forum��2015�N�ɍ��肵���B������LTE-U�̓L�����A�Z���X�̎d�g�݂�����Ă��炸�A5GHz�тł̃L�����A�Z���X���`���t�����Ă��郈�[���b�p����{�ł͗��p���ł��Ȃ������B
LAA�ł́A���C�Z���X�o���h�̃L�����A��Primary cell���A�A�����C�Z���X�o���h�̃L�����A��Secondary cell���g�p���A�ǂ���̃Z���ł�LTE�̖����K�i��p����B������LTE-U�ƈقȂ�A�A�����C�Z���X�o���h�ɂ����Ă̓L�����A�Z���X�iLBT�GListen Before Talk�j���K�p�����BPrimary cell�̊�n�ǂ̓f�[�^�̕����E������S���ASecondary cell�ƘA�g����B�����[�X13�i2016�N�j�ɂĉ�������̃L�����A�A�O���Q�[�V�������K�肳��A�����[�X14�i2017�N�j�ɂď��������K�肳�ꂽ�BCA��LAA�̈Ⴂ��}�Ɏ����B�Ȃ������[�X13�ł́ALAA�̑��ɁALTE�Ɩ���LAN���A�O���Q�[�g����LWA (LTE/WLAN aggregation)���K�肳��Ă���B
2.5.6.2�@ NR-U�F(New Radio - Unlicensed)
3GPP�����[�X16�ł́A5�f�V�X�e���ɂ����ăA�����C�Z���X�o���h�𗘗p����NR-U���K�肳�ꂽ�BLAA�Ɠ��l�ɁAPrimary cell�ł�NR�����C�Z���X�o���h�Ŏg�p���ASecondary cell��NR-U�𗘗p����`�ԁi�A���J�[�^�j�ɉ����āANR-U�݂̂ł̉^�p�ɂ��A�����C�Z���X�o���h�̗��p�`�ԁi�X�^���h�A���[���^�j���T�|�[�g����Ă���BNR-U���z�肷����g���т�5GHz�т�6GHz�тł���A���胊���N�ōő�320MHz���A���ōő�80MHz���ł���B���{�ł�NR-U���p�͌����_�ŔF�߂��Ă��Ȃ��B
2.5.6.3�@ FPU
Field Pick-up Unit�Ƃ́A�����ԑg�̉f���≹�������ꂩ��X�^�W�I�֓`������V�X�e���ł���B�����ł́A�\ 2‑37�Ɏ������g���т��g�p����Ă���B
|
���g���ď� |
���g���� |
�ǐ� |
���g���� |
�`�� |
�Œ� |
�ړ� |
���l |
|
1.2/2.3GHz�� |
1240-1300MHz[60]/ 2330-2370MHz[40] |
117 |
18MHz |
145Mbps 10Mbps |
|
|
TDD�o���� |
|
B�o���h |
5.850-5.925GHz |
322 |
18MHz |
300Mbps |
50 |
4 |
�ΔgMIMO |
|
C�o���h |
6.425-6.570GHz |
2,492 |
|
|
|
|
|
|
D�o���h |
6.870-7.125GHz |
3,064 |
|
|
|
|
|
|
E�o���h |
10.25-10.45GHz |
2,191 |
|
|
7 |
3 |
|
|
F�o���h |
10.55-10.68GHz |
1,299 |
�� |
�� |
�� |
�� |
|
|
G�o���h |
12.95-13.25GHz |
5 |
�� |
�� |
5 |
3 |
�� |
|
42GHz�� |
41-42GHz |
4 |
125MHz |
210Mbps |
3-5 |
0.05 |
HD�̔k�`�� |
|
55GHz�� |
54.27-55.27GHz |
3 |
�� |
�� |
�� |
�� |
�� |
|
120GHz�� |
116-134GHz |
0 |
18GHz |
12Gbps |
0.5-1 |
-- |
4K�E8K�k�`�� |
2.5.6.4�@ �ߐږ����iUWB�j
UWB�iUltra-Wideband�j�́A���ɍL�����g���ш敝�i�ʏ�500MHz�ȏ�j�����ϒ��g��p���閳���ʐM�����̑��̂ł���B�ߋ����ł̍����ʐM�⍂���x���ʂ��\�Ƃ���B��\�I�ȋK�i�́A�\ 2‑38�Ɏ���IEEE802.15�V���[�Y�ł���B
�\ 2‑38�@UWB�V�X�e���̎�ȋK�i
|
�K�i�� |
���� |
���g���� |
|
IEEE802.15.4-2020 |
�����x������_���������w�K�i�ƁA�V���v���ȕϒ�������p����y�ʂȋ@��\����1Mbps�ȉ��̒ᑬ�ʐM��_�����d�l�B�`���l������499.2MHz |
Low band : 3.1 – 4.9 GHz High band: 6.0 – 10.6 GHz |
|
IEEE802.15.6 |
�̂���̃o�C�^���f�[�^���`�����邽�߂̒ʐM�K�i�BUWB�����e���邱�ƂŃV���v���ȉ�H�\���ƒ����d�͂�_���Ă���B |
|
|
IEEE802.15.8 |
�[���ԒʐM�̂��߂�PHY�EMAC�w�K�i |
4.20 – 4.80 GHz 7.25 –10.25 GHz |
�@UWB��2002�N�ɕĘA�M�ʐM�ψ���iFCC�j�̔F������A�������p���J�n�����B���{�ł́A2006�N�ɒʐM�p�r�i3.4�`4.8GHz�сA7.25�`10.25GHz�сj�A2010�N�ɏՓ˖h�~�p�ԍڃ��[�_�[�p�r�i22�`29GHz�сj�A2013�N�ɃZ���T�[�p�r�i7.25�`10.25GHz�сj�ł̗��p�����x�����ꂽ�B�ʐM�p�r�ƃZ���T�[�p�r�͉����Ɍ��肳��Ă������A2019�N�ɐ��x�������s���A7.587�`8.4GHz�т̉��O���p���\�ɂȂ����BApple��2019�N�ɔ�������iPhone11�V���[�Y��UWB�ɑΉ����A�Ȍ�UWB�͍L���g����悤�ɂȂ����B���Ђ��̔�����AirTag��UWB�ɂ���ăZ���`���[�g���I�[�_�[�ł̑������\�Ƃ��A�������Ǘ��Ȃǂɗp������B�܂������Ԃ̖����L�[�V�X�e���ł�UWB�̗̍p���i��ł���B�V�����V�X�e���͖����L�[�̏��L�҂��ԗ��̋߂��ɂ��邱�Ƃ�UWB�̑����@�\�Ŋm�F���A�d�g�̕s���Ȓ��p�ɂ������i�����[�A�^�b�N�Ƃ����j��h���d�g�݂����Ă���B
2.5.6.5�@ �ߐږ����iNFC�j
�@NFC�iNear Field Communication�j��UWB��������ɋ߂������ł̒ʐM��z�肷��B��ڐGIC�J�[�h��d�q�^�O��NFC�̑�\��ł���B���x��̖��̂́u�U�����ǂݏ����ʐM�ݔ��v�ł���A13.56MHz�}6.78kHz�̎��g���т�p����B13.56MHz�𗘗p�����ڐG�C���^�t�F�[�X�̍��ەW���K�i�Ƃ��āA�ߐ�(Proximity)�^��ISO/IEC 14443�n�ƋߖT(Vicinity)�^��ISO/IEC 15693�n������B�O�҂̒ʐM�����͍Œ�10cm���x�ł����ɔ�ڐGIC�J�[�h�ɗ��p����Ă���B��҂̒ʐM������70cm���x�ł��蕨���̏��i�^�O�ɗ��p����Ă���B�\ 2‑39�ɋߐڌ^�̍��ەW���K�i�̊T�v�������B
�\ 2‑39�@�ߐڌ^NFC�̍��ەW���K�i
|
���� |
�������� |
�ʐM�v���g�R���� |
�T�v |
|
Type A (NFC-A) |
ISO/IEC 14443 |
ISO/IEC 18092 |
• ��@�\�A���e�ʂ̃J�[�h�B�I�����_�̃t�B���b�v�X�Ђ��J������MIFARE���N���B�P�@�\�̃J�[�h�Ƃ��ČÂ�����̗p����Ă���B • ���ގ���p�J�[�h�A�����w���p���l�F�J�[�htaspo�A�ꕔ�̔�ڐG�N���W�b�g�J�[�h����(�}�X�^�[�J�[�h PayPass)�Ȃǂɍ̗p����Ă���BNTT��IC�e���t�H���J�[�h��ꕔ�̃o�X��ԗp�J�[�h�ɂ��̗p����Ă����B |
|
Type B (NFC-B) |
ISO/IEC 14443 (Type B) |
• ���@�\�A���Z�L�����e�B�̃J�[�h�BPKI�ɑΉ��������̂������A�������n�̃J�[�h�ɍL���̗p����Ă���B • �l�ԍ�(�}�C�i���o�[)�J�[�h�A�Z����{�䒠(�Z��)�J�[�h�A�p�X�|�[�g�A�^�]�Ƌ��A�ݗ��J�[�h�ɍ̗p����Ă���B |
|
|
Felica (NFC-F) |
(ISO/IEC 14443 �Ɠ���ASK�ϒ�) |
ISO/IEC 18092 |
• ��@�\�A���e�ʂ̃J�[�h�B�\�j�[���J���B���i�����������������ł���B���{�ł͌�ʌn��d�q�}�l�[�ōL���̗p����Ă���B • Suica�APASMO�AQUICPay/QUICPay+�A���T�C�t�P�[�^�C�A�y�VEdy�Ananaco�A�Ȃǂɍ̗p����Ă���B |