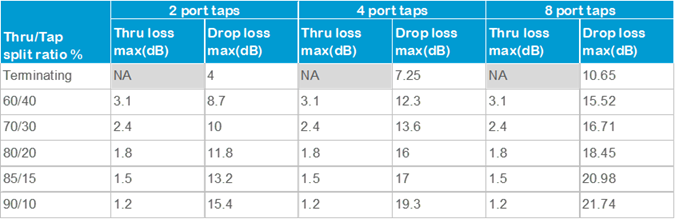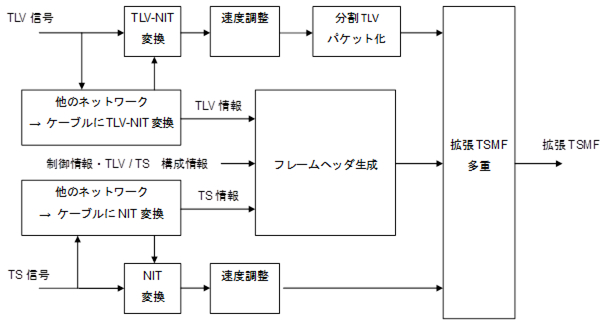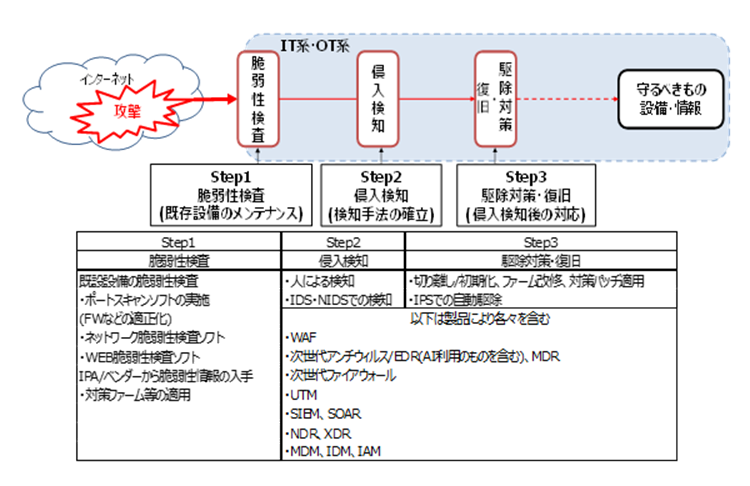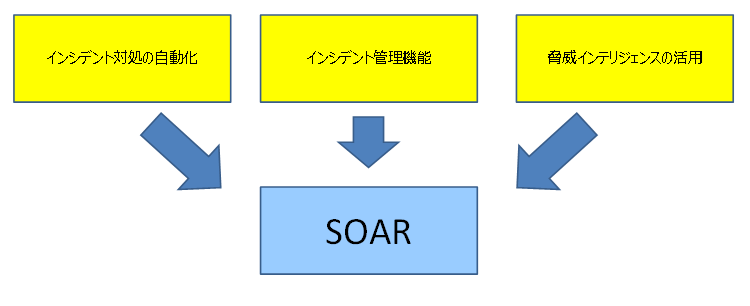�P�[�u���e���r���j�Ղ́A�O��̉���(2018)����6�N�o�߂��܂����B���̊Ԃɐ��E�I�ɗ��s�����V�^�R���i�E�B���X�����ǁi�ȉ��A�R���i�j�ɂ��Љ�I�E�o�ϓI���̑傫�ȕω�������A��X�̃��C�t�X�^�C���̓R���i�ȑO�Ɋ��S�ɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ����l��������܂��B���̃��C�t�X�^�C���̕ω��ɍ��킹�āA�P�[�u���e���r�̃T�[�r�X�����l�����i�݁A�֘A����Z�p���������i���E���l�����Ă��܂����B
���̓x�̉����́A���̋Z�p�̐i���ɂ��ă^�C�����[�ɃL���b�`�A�b�v���邱�Ƃ���ȖړI�ł���܂��B�Ƃ͌������̂́A�`���̒ʂ�A���N�ɓn��R���i�ɂ��e�����͂��߉�X����芪���Љ�����傫���ω����A�P�[�u���e���r�ƊE���u�����A�������傫���ω����Ă��܂����B�����ŁA�{���́w�Z�p�x�̗��j�Ղł͂���܂����A�P�Ȃ�Z�p�̃A�b�v�f�[�g�����ł͖����A����̃P�[�u���e���r���Ƃ��w�Ĕ�������x���߂́w�����̑I�����x���������Ƃ��ӎ����ĉ������邱�ƂƂ��܂����B
�w�����̑I�����x�̐i���͎����̂��̂ł͖����A�����̐i���}�̂悤�Ɏ��ԂƋ��ɕω����āA�����ⓝ��������̂�����A�܂������Ă������̂�����܂��B����Ƌ��ɁA�P�[�u���e���r�Z�p�͈̔͂�����Ɋg�債�A���̐i���̃X�s�[�h���܂��܂��������Ă����ł��傤�B���̕������̕ω��ɂ����A���^�C���őΉ����邽�߁A���̕ω��E�����ɂ��ă^�C�����[�ɏC���E�lj����Ă����\���ɂ����ӂ��܂����B
��P�͂ŁA�P�[�u���e���r�ƊE�̏ƑΏ����ׂ��ω��ɂ��Đ���������ŁA��Q�͈ȍ~�Ŋe����ɂ�����w�����̑I�����x��R�����Ă����܂��B
���e
��1�� �P�[�u���e���r�ƊE�̏� �Ώ����ׂ��ω�
1.2 �P�[�u���e���r�T�[�r�X�̐i���E���l��
1.6 �P�[�u���e���r�̍Ĕ����Ɍ�����
2.1.1 HFC�P�[�u���`���Z�p�̍��x��
2.1.2 DVB-C2�i���x�ȃf�W�^���L���e���r�W�������������j
2.2.3 ���`���ւ̃}�C�O���[�V����
2.3.1 �����P�[�u�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p
2.4 �V����FTTH�\�z�\�����[�V����
2.4.2 ���z���^�b�v��p�����A���C�[�u���A�[�L�e�N�`���R�l�N�^�\�����[�V����
2.4.3 MDU�ł̃R�l�N�^�\�����[�V�������p
2.5.1 BWA�iBroadband Wireless Access�j�F
��3�� �T�[�r�X�E�R���e���c�Z�p
3.1.1 �����̍��x���i4K�E8K�Ή��j
3.1.4 HDR�i�n�C�_�C�i�~�b�N�����W�j
3.1.7 22.2ch �O�����}���`�`�����l����������
3.2.4 �����O�ɂ�����IoT���c��A�W�����@�ւȂ�
3.2.5 IoT�̃r�W�l�X���Ƃ���ɂƂ��Ȃ��ۑ�
3.2.7 Federated Learning�i�A���w�K�j
4.1.2 CATV���Ǝ҂ւ̃T�C�o�[�U���̎��
��1��
�P�[�u���e���r�ƊE�̏�
�Ώ����ׂ��ω�
1.1�@ �Љ���̕ω�
�V�^�R���i�E�B���X��2023�N�x�ɑ�5�ނɕ��ޕύX����A�������̐����͗������������߂��Ă�������A�e�����[�N��I�����C����c�̕��y�Ȃ��V�^�R���i�E�B���X�Ƌ��ɐ�����j���[�m�[�}���Ɍ������傫���ω����Ă����B����A�Ē��f�Ֆ��C�A�����̋����s���A�E�N���C�i��ɂ��G�l���M�[�����ۑ��C���t���A�p���X�`�i�����ȂǍ��ۓI�ȕs���v�f�͑��X�p�����Ă���B�܂��A�n�����g����Ƃ��Ă�CO2�r�o�ʍ팸��z�^�o�ςȂNJ��ւ̔z�������߂��Ă���B
�����ł́A2024�N1��1���̔\�o�����n�k�̔����ɂ��A�����EICT�̃��C�t���C���Ƃ��Ă̏d�v�������߂ĔF������Ă���B
���̂悤�ȏ̒��ŁA�P�[�u���ƊE����芪�����́ANetflix�ADisney�AAmazon�AYoutube�ȂNJC�OOTT�iOver The Top�j���Ǝ҂ɂ�铮��z�M�T�[�r�X�̎s��K�͂�����Ɋg�債�Ă���B�܂��A�������e�Ђɂ�� TVer ��NHK�v���X�ɂ��l�b�g�����z�M�ȂǁA�C���^�[�l�b�g�ɂ�铮��z�M���Ƃ��������Ă���B����ɁA�����Ȃł́A�u�f�W�^������ɂ�����������x�݂̍���Ɋւ��錟����v�ɂ����āA�u���[�h�o���h�ɂ���֕����������ۑ�Ƃ��Ď��グ�A��ƃ`�[���ɂďW���I�ȋc�_���p�����Ă���B
2024�N1���ɂ�����A�P�[�u���e���r�ƊE���猩��PEST���͂��\ 1‑1�ɂ܂Ƃ߂��B
�\ 1‑1�P�[�u���e���r�ƊE���猩��PEST���́i2024�N1���j
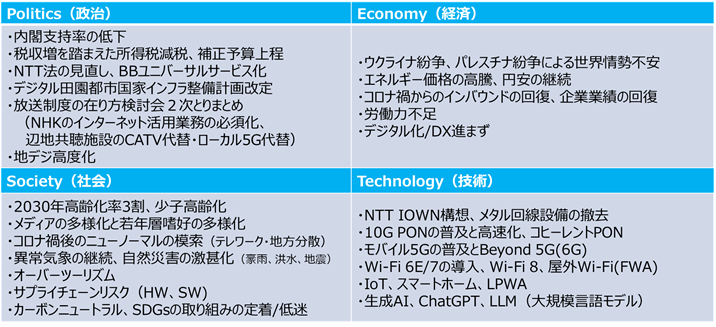
1.2�@ �P�[�u���e���r�T�[�r�X�̐i���E���l��
��L�̊��ω��ɑΉ����āA�P�[�u���e���r���Ƃɂ����Ă��Љ�v���Ƌ������Ɣ͈͂̊g��E���l���������ɐi��ł���B�����ʼn��߂āA2024�N1���ɂ�����P�[�u���e���r�ƊE��SWOT���͂��\ 1‑2�ɂ܂Ƃ߂��B���ƌ����Ă��A�P�[�u���e���r���Ƃ̍ő�̋��݂͒n�斧�����ł���A���̋��݂��ő���Ɋ��������Ƃ����߂���B
�\ 1‑2�@�P�[�u���e���r�ƊE���猩��SWOT���́i2024�N1���j

�} 1‑1�ɑ���ɂ킽��P�[�u���T�[�r�X�̑��l���ɂ��Ď��̂R�w�\���Ő�������B (a)�����҂ɂƂ��Ắu�G���h�T�[�r�X�v���C���A(b)�ǂ̂悤�Ȓ[���i�����ҏ��L���܂ށj�ɃT�[�r�X����邩�Ƃ����u�[���v���C���A�����(c)�ǂ̂悤�ȃl�b�g���[�N�i���Ǝ��Ǝ҂��܂ށj��ʂ��ăT�[�r�X����邩�Ƃ����u�`���T�[�r�X�v���C���̂R�w�\����z�肵�A�P�[�u���T�[�r�X�́A���ꂼ��̑g�ݍ��킹�i�|���Z�j�ł���ƍl����ƃT�[�r�X�S�̘��Ղ��邱�Ƃ��ł���B
(a) �u�G���h�T�[�r�X�v���C���@�} 1‑1 (a)�F�@�P�[�u���e���r���Ƃ̏o���_�ł�������T�[�r�X�i���F�j���j�Ƃ��āA�ʐM�C���t���ɂ��u���[�h�o���h�T�[�r�X�����킹�Ē��A���̏�Œn��̃R���e���c�^��f�B�A�T�[�r�X�i�I�����W�j�Ɏ��Ƃ��g�債�Ă����B�����č���́A�n��Ɋ��Y�����l�X�Ȑ����x���T�[�r�X�i�����j�̒Ɋg�����A����ɂ͒n��r�W�l�X�iBtoB�j�^�s���iBtoG�j��ICT�T�[�r�X�Ŏx����n��DX�i�����j�̐��i�������҂���Ă���B�����̂��ꂼ��̃T�[�r�X�̈�ɂ����āA���ƊE�Ƃ̋����E���������Ȃ���i�����Ă���A����܂ł̃r�W�l�X���f�����傫���ω����Ă����Ƒz�肳��A���܂��ɓ]���_���}���Ă���B
(b) �u�[���v���C���@�} 1‑1 (b)�F�u�G���h�T�[�r�X�v�Ɓu���q�l�v�̐ړ_�ƂȂ�[���^�f�o�C�X�́A�����T�[�r�X�ł�STB�^(RF)�e���r�i���F�j�����S�ł��������A�ŋ߂̓e���r�������l�b�g�ڑ��\�ȃR�l�N�e�b�h�e���r��IP�h���O���AIP-STB�ɂ�鎋���ւƑ��l�����i��ł���B�ʐM�T�[�r�X�ł�PC�A�X�}�[�g�t�H���A�^�u���b�g�Ȃǂ��ΏۂɂȂ�B����ɐ����x���T�[�r�X�ł̓E�F�A���u���A�Ɠd�AIoT�A�J�����Ȃǂ��Ώے[���̑��l������w�i��ł���i�j�B
(c) �u�`���T�[�r�X�v���C���@�} 1‑1(c)�F�u�[���v���C���ɐڑ�����l�b�g���[�N�T�[�r�X�ɒ��ڂ���ƁA�����T�[�r�X�i�]����RF�G���F�j����ђʐM�T�[�r�X�iIP�G�����j���x����Œ�l�b�g���[�N�iHFC�AFTTH�j�A�����l�b�g���[�N�iBWA�A���[�J��5G�AFWA�ALPWA�j�A����ɍL�͈͂ł��ЊQ�ɂ������q���ʐM�A����l�b�g���[�N�iWi-Fi�j�������ƑΏۂɂȂ�B
�@���ꂩ��̃P�[�u���e���r���Ƃɂ����āA����瑽�l�������T�[�r�X�S�Ă̑g�ݍ��킹�i�|���Z�j���ɑS�Ď������邱�Ƃ͓���B�����璅�肷��̂��A�ǂ������I�ɔ��W�����Ă����̂��A����ɂǂ����W�J�����Ă����̂��A�܂��A�����̐ݔ������܂Ŋ��p���āA���V�K�ݔ��Ƀ}�C�O���[�g���Ă����̂��A�����̌o�c���f�͊e�Ђ̎��Ɗ��ɂ��ˑ�����B�܂��A�������Ɨ̈�ɂ����Ă͂��q�l�̃j�[�Y�ω��Ƀ^�C�����[�ɑΉ����邱�Ƃ����ʉ��Ƃ��ďd�v�ɂȂ�B�P�[�u���ƊE�͍��܂��ɂ��̓]���_�ɂ���A���̂悤�ȑ��l�Ȏ��Ɖۑ�����������������u�P�[�u���e���r�̍Ĕ����v���n�������ƍl���Ă���B
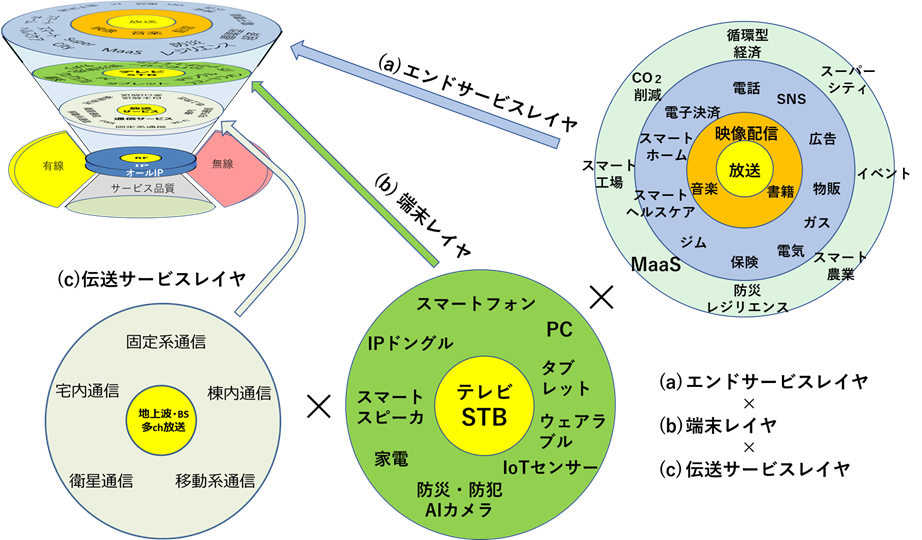
�} 1‑1�@�P�[�u���T�[�r�X�̐i���Ƒ��l��
1.3�@ �������A���Ɗ��̕ω�
�P�[�u���e���r�T�[�r�X�̐i���E���l���ɔ��Ȃ��āA�ƊE�O�Ƃ̋���������ы��������ω����Ă���B
�@�E�����T�[�r�X�ł́AIP�����ɂ���āA2022�N7���ɂm�s�s�h�R�����m�s�s�Ղ����z���������u�Ђ���TV�v���Ƃ��^�c���Ă���A�t���b�c�������p���Ă̕����T�[�r�X��f���z�M�T�[�r�X���Ƃ��Ē��Ă���B�S���ł̉����҂�83������ �ƂȂ��Ă���B
�܂��ARF�����ł́A�X�J�p�[JSAT���t���b�c�����̌������p���āA�u������e���r�v�Ƃ������̂ŁA�n��g�e���r��BS���̍ĕ����T�[�r�X�⑽�`�����l���T�[�r�X����Ă���A�ĕ����T�[�r�X�̐ڑ����т�273������ �ƂȂ��Ă���B
������e���r�́ANTT����������u�t���b�c�e���r�v����n�܂������ANTT�������u������v����������p����ISP���Ǝ҂��A�X�J�p�[JSAT�́u������e���r�v�����P�[�X�i�X�J�p�[���R���{���[�V�����j�������Ă��Ă���B
�ŋ߂ł́A�P�[�u���e���r���Ǝ҂ɂ����Ă��ANTT�����̌�����𗘗p���A�X�J�p�[JSAT���ƘA�g���Ēn��g��BS���̍ĕ����T�[�r�X���s�����Ƃ��n�܂����B���ɁA����̃T�[�r�X�G���A���̌�������������ȃP�[�u���e���r���Ǝ҂�A�T�[�r�X�G���A�̊g����}���ŁANTT�����̌�����𗘗p���悤�Ƃ���P�[�u���e���r���Ǝ҂ɂƂ��ẮA����������������Ȃ��_�����ڂ���Ă���B
�܂��A�P�[�u���e���r���Ǝ҂��d�͌n�ʐM���Ǝ҂̌�������g���āA�ĕ����T�[�r�X�⑽�`�����l���T�[�r�X�����n����o�Ă��Ă���B
�@�E�u���[�h�o���h�T�[�r�X�ł́A�Œ�n�ł́ANTT�������������Ȃ̕⏕�������p���s�̎Z�n��̌��t�@�C�o�̕~�݂�i�߂Ă���A�S���Ǝ҂ł̌��t�@�C�o�̐��уJ�o�[����99.7% �ƂȂ��Ă���B�P�[�u���e���r���Ǝ҂ɂƂ��ẮA���ʐM���ƎҁA�\�j�[�̃j���[���Ђ���A�d�͌n�̒ʐM���Ǝ҂Ƃ͋����W�ł��邪�A��L�̕����T�[�r�X���l�ANTT������d�͌n�ʐM���Ǝ҂̌�����𗘗p���ĒʐM���x�̍�������}�鋦�ƃP�[�X����������B�P�[�u���e���r���Ǝ҂ɂƂ��ẮA�������Ȃ��Ƌ����͂̒ቺ�ɂȂ���B
�@�����n�ł́A�g�ѓd�b���Ǝ҂ɂ��TG�T�[�r�X�̐l���J�o�[����96.6�� �ƂȂ��Ă���B�����̌g�ѓd�b���Ǝ҂�5G���g�����e�v�`�T�[�r�X�i�����u���^�z�[�����[�^�[�j����Ă���A����E�����̍H�����s�v�ȏ�A�T�f�̒������T�[�r�X�����p�\�ł��邱�Ƃ���A�����҂𑝂₵����B���[�J���T�f�T�[�r�X���J�n���Ă���P�[�u���e���r���Ǝ҂����X�ɑ������邪�A�g�ѓd�b���Ǝ҂Ƃ�BtoC�����ł͂Ȃ��A�����̂�n��Ƃ̘A�g�ɂ��BtoG�ABtoB�̃r�W�l�X��͍����Ă���P�[�X�������B
�@�E�R���e���c�r�W�l�X�ɂ��ẮA���`�����l���T�[�r�X������ŁA�ԑg�����Ǝ҂Ƃ̋��Ƃ͈��������d�v�ł��邪�AIP�z�M����������ƁA���쌠�����̑Ή����ۑ�ł���BNetflix��YouTube����OTT�Ƃ̊W�́A�����͉f���z�M�̃g���t�B�b�N�ɂ��C���^�[�l�b�g�ш�̐�L��A�L����OTT�����ɔ����P�[�u���e���r���`�����l���T�[�r�X�̉��Ȃǂ̉ۑ��������ꂽ���A���݂ł́A�P�[�u���e���r���Ǝ҂�OTT�T�[�r�X���掟������A���[�U�[�i��������ʉ���g���t�B�b�N�̍팸�̂��߂ɃP�[�u���e���r�̃Z���^�[�ɃL���b�V���T�[�o�[��ݒu����Ƃ�����������������B
�E�L���r�W�l�X�ɂ��ẮA���E�I�ɃC���^�[�l�b�g�L���̎s�ꂪ�L�тĂ���A�䂪���ɂ����Ă����Ƀe���r�����̍L���s��������Ă��� �B�l�̋����E�S�����l�����钆�ŁA�P�[�u���e���r���Ǝ҂��R�~�`���������ł̍L�������ł͂Ȃ��A�l���^�[�Q�b�g�Ƃ���f���z�M�T�[�r�X�ɂ�����L���r�W�l�X���f������������K�v�����邪�A���̂��߂ɂ́A�]���̐��ђP�ʂł̏��ɉ����A���[�U�[�P�ʂ̌l���̒~�ς��d�v�ɂȂ낤�B
ICT��IoT��p���������x���T�[�r�X�A�n��DX�ɂ��ẮA�ʐM���Ǝ҂�Sier�A�x���_�[�Ƃ̋����̈�iRed Ocean�j�ł��邪�A�P�[�u���e���r���Ƃ̋��݂ł���n�斧�����A�����̂Ƃ̘A�g������D�ʐ���ێ����Ă���T�[�r�X���痧���グ�Ă������Ƃ��d�v�ł���B�����ł��A�T�[�r�X���Ǝ҂Ƃ̋��������Ƃɓ]�����Ă������Ƃ��I�����ɓ����ׂ��ł���B
[1] �����Ȍ��\�����u�P�[�u���e���r�̌���vp.4���
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000504511.pdf)
[1] �X�J�p�[���\�������ihttps://www.skyperfectjsat.space/news/detail/202312.html�j
[1] �����Ȍ��\�������ihttps://www.soumu.go.jp/main_content/000864083.pdf�j
[1] �����Ȍ��\�������ihttps://www.soumu.go.jp/main_content/000894733.pdf�j
[1] �����ȗߘa�T�N�ŏ��ʐM�������
�ihttps://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd243220.html�j
1.4�@ �Z�p�̐i���E���l��
�Z�p�I�Ȋϓ_����́A�P�[�u���e���r�ɓ��������ŗL�Z�p�ɉ����āA�ʐM�ƊE�Ő�s���Ă���I�[�v���ȃO���[�o���W���ɂ��ICT�Z�p����荞�ނ��Ƃ��܂��܂��d�v�ɂȂ�B���ɍŋ߂ł́AAI�ɂ�鎩�R���ꏈ����摜�����AXR�E���^�o�[�X�E�f�W�^���c�C���ȂǁA�S���V�����Z�p���o�����A�����x�I�ɐi�����Ă��Ă��邱�Ƃ̓P�[�u���ƊE�ɂ����Ă��T�[�r�X�̐i���E���l���ɔ����āA�����̊��p��͍�����K�v���o�Ă����B�@
�܂��A�P�[�u���e���r�����Z�p�ɖڂ�������ƁA���悢��S�Ă̕����̃I�[��IP���������̂��̂ƂȂ�ARF��IP�̍œK�ȋ���������ɓ���AIP���ɂ��V�Z�p�Ƃ̗Z���T�[�r�X�̎������}�����B
�C���t���Z�p�ʂł́A�L������ɂ����Ă�FTTH 10G-PON�T�[�r�X���p�\�G���A���L�܂�B��������ɂ����Ă̓��[�J��5G�Ƌ���MEC�iMulti-access Edge Computing�j��l�b�g���[�N�X���C�X�@�\�̊��p���V�T�[�r�X�C���t���Ƃ��Ċ��҂���AWi-Fi6/6E�̕��y��AWi-Fi7�̓o��A����ɂ�60GHz���̃~���g�і�����p����FWA�V�X�e���̏��p���p�������Ă����B����́AFTTH�Ɩ����̃V�[�����X�ȗZ���Z�p�����҂����B�܂��AIoT�T�[�r�X�Ɍ������Ȃ�LPWA�̗��p���i��ł���B
�T�[�r�X�Z�p�ʂł́A�Z�L�����e�B������ʐM�i���̊m�ۂ����߂��鎞��ƂȂ�B���̂��߁A�l�b�g���[�N�@�\��R���e���c�z�M�V�X�e���̉��z���E�N���E�h���EAI���p�i�݁A���G������C���t���̉^�p�������ɂ�鋣���͋����^�R�X�g�_�E�����d�v�ƂȂ�B�܂��AIP�ɂ��f���z�M�A�L���t���T�[�r�X�A���R�����h�Ȃǂ̋����ɉ����A���ƎҎ��g��IP�h���O���Ȃǂ̐V�[����IoT�Z�p�������g���邱�ƂŁA�n��DX��f�W�^���c���s�s���ƍ\�z���x���钆�S�v���[���ƂȂ邱�Ƃ����҂����B
�����č���́A����炷�ׂĂ̕���ɐZ�����Ă����ƒ��ڂ���Ă���AI�̐ϋɓI�Ȋ��p���d�v�ȉۑ�ƂȂ�B
1.5�@ 5�̏d�_����
���̂悤�ɑ��l�ɐi���E�g�債�Ă���Z�p���R�ꖳ�������E�������Ă������߂̑S�̘��Ւn�}�Ƃ��āA5�̏d�_����F�u�I�[��IP�v�u�L���v�u�����v�u�T�[�r�X�i���v�u�V�T�[�r�X�v���ȉ��Ɏ����ʂ��`�����B�u�I�[��IP�v�𒆐S�ɁA�������C���t���Z�p���i�L���̃I�[��IP�̖����j�A�c�����T�[�r�X�Z�p���i�V�T�[�r�X�̃I�[��IP�̃T�[�r�X�i���j�ƒu�����ƂŁA�����Z�p����Ԃ̘A�g���m�������B����́A�P�[�u���e���r���Ƃ��x���鑽�l�ȐV�����Z�p��P�Ɓi�_�j�Ƃ��đ����邾���łȂ��A���Ƃɂ�����Ӗ��i�X�g�[���[�j�Ƃ��đ��Z�p�̊W�����ʂő������邱�Ƃ��ӎ��������̂ł���B�����āA���ׂĂ̕���Ɋ֘A����Z�p�Ƃ��Ă�����AI�̊��p���l�����Ă����B�i�} 1‑2�j
�{�P�[�u���Z�p���j�Ղ̖{�_�ł́A���̂T�̏d�_����ɉ����Đ������Ă����B
�@ �u�I�[��IP�v:�@�f���T�[�r�X��IP�ɂ������E�z�M�݂̂Ȃ炸�A�e���r�T�[�r�X�̍��x���A�^�p���x���A�T�[�r�X�ԘA�g�ɂ��t�����l�n�o�Ȃ�IP�Z�p�͌��������Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��A�O�q�����C���t���Z�p���A�T�[�r�X�Z�p���ŕ\�����悤�ɑ�4�̏d�_����Ɩ��ڂɊ֘A�������Ă���A�P�ƂŊ���������̂ł͂Ȃ��B�u�I�[��IP�v�ł́A��������IP�Z�p����g����������P�[�u���T�[�r�X�����Ē���B���{�P�[�u�����{�ł̓I�[��IP��5�̏d�_����̒��j�ɐ����������������𐄐i����B
�A �u�L���v:�@�C���^�[�l�b�g�ɂ��f���T�[�r�X�̕��y�⍂�����A�e�����[�N�������ւ̑Ή��ȂǁA�l�b�g���[�N�T�[�r�X�̍L�ш扻�ւ̗v�]�����܂��Ă���B�܂��ATV�T�[�r�X�ɂ����Ă�FTTH�ւ̈ڍs���i��ł���BFTTH��������������ɂ������ẮA�PGbps/10Gbps�Ȃǂ̃T�[�r�X���x���j���[�ɂƂǂ܂炸�^�p���A�ێ琫�������܂߂��{�H�̗e�Ղ��Ȃǂ��d�v�Ȍ����|�C���g�ł���A�u�L���v���d�_����̈�ƈʒu�t��������i�߂�B
�B �u�����v�F�@���q�l����ł̍Ō�̃A�N�Z�X�Ƃ��Ă�Wi-Fi��[�J��5G�Ȃǂ̖����͏d�v�ȋZ�p�ł���B�P�[�u�����Ǝ҂Ƃ��č��i����TV�T�[�r�X���͂��߃u���[�h�o���h�T�[�r�X�AIoT�T�[�r�X���C���t������Ē���ꍇ�A����̌�萧��A�ш�Ǘ��Ȃnj������ڂ͑����B�܂��܂����l������u�����v���d�_����̈�ƈʒu�t��������i�߂�B
�C �u�T�[�r�X�i���v�F�@���q�l�ɃT�[�r�X�����ɂ�����A���̕i�����ێ��E�Ď����A��ɓK�ɊǗ����邱�Ƃ̓T�[�r�X���Ǝ҂Ƃ��Ă̕K�{�v���ƍl����B�T�[�r�X�i�����ێ����シ�邽�߂ɂ̓T�[�r�X�^�p�A�ݔ��^�p�A�Z�L�����e�B�^�p�A�ݔ��ۑS�ȂǑ���ɂ킽�錟�����K�v�ł���B�܂��A���G������ݔ����^�p�Ɩ��̃R�X�g�_�E���Ɍ������^�p���x���Z�p���}���ɐi�����Ă���B�����u�T�[�r�X�i���v���d�_����̈�ƈʒu�t��������i�߂�B
�D �u�V�T�[�r�X�v�F�@�u�L���v�u�����v�Ȃǂ̍��i���ȃC���t���ɉ����āA���͓I�ȃT�[�r�X�̓P�[�u�����Ǝ҂Ƃ��Č��������Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����BTV�T�[�r�X�ɂ����ẮA���q�l�Ƃ̐ړ_�ł��������u�Ƃ��Ă�STB�̍��@�\����R���e���c�z�M���ł̏_��ȃT�[�r�X�Ή����]�܂��B�܂��A�V�������f�B�A�Ƃ��Ă�XR�A�n�斧���̃P�[�u���e���r�Ȃ�ł͂�IoT�ȂǐV�T�[�r�X�̈�ł͌������s���邱�Ƃ͂Ȃ��BB-C, B-B, B-G���邢�͒n��DX�ő��l������u�V�T�[�r�X�v���d�_����̈�ƈʒu�t���A�X�̋Z�p�ɂƂ��ꂸ�ɍL������Ō�����i�߂�B
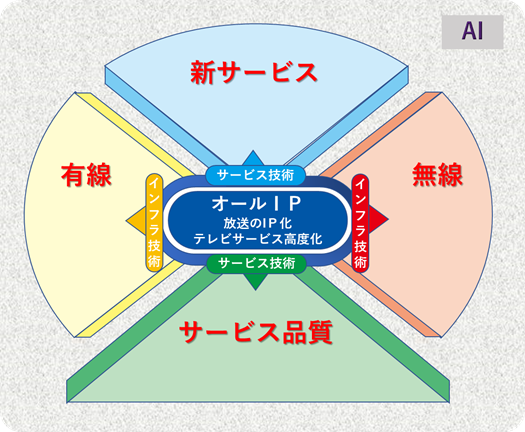
�} 1‑2�@5�̏d�_����
1.6�@ �P�[�u���e���r�̍Ĕ����Ɍ�����
��P�͂ł́A�P�[�u���e���r�ƊE�Ƃ��āA�P�[�u���e���r�ɕ����Z�p�����̍��x���E�W�������s�������łȂ��A�ƊE���Đ₦���ω����Ă������푽�l�ȐV�Z�p���悭�������A��̑I�����A���p���邱�Ƃ��܂��܂��d�v�ƂȂ邱�Ƃ��q�ׂĂ����B
��Q�͈ȍ~�ł́A���̂��߂̗��j�ՂƂȂ�Z�p�̉���ƃP�[�u���e���r���ƂɂƂ��Ắw�����̑I�����x�������B���̌��ʂƂ��āA���{�P�[�u�����{�͎��Ǝҗl�Ƌ��Ɂw�P�[�u���e���r�̍Ĕ����x��n�����Ă�����K�r�ł���B
��2�� �C���t���Z�p
2.1�@ HFC�`���Z�p
2.1.1�@ HFC�P�[�u���`���Z�p�̍��x��
�ʐM���x�̍������̂��߂ɕK�v�ȋZ�p�Ƃ��āAHFC�`���H�̍��x���A�ϒ��E�������Z�p�̍��x���A�����̋Z�p���̗p����DVB-C2�i���x�ȃf�W�^���L���e���r�W�������������j��DOCSIS 3.1�ADOCSIS4.0�ɂ��ċL�q����B
2.1.1.1�@ HFC�`���H�̍��x��
(1) HFC���x���i������HFC�j
HFC���x���́A������HFC�Ƃ��Ă�A���Z�����i1�Z�����̉ƒ��100�����x�܂Ō��炷�j�Ɠ����`���ш��1GHz���x�܂ōL�ш扻���邱�Ƃł���B�������Z�����E�L�ш扻��HFC���\������o�����A���v�̌����ɂ��A�ʐM���x�̌����CN�䓙�̓`�����\�̌��オ���҂ł���B
���Z�������s�����߂ɁA���m�[�h�ȉ��̑o�����A���v��0���邢��1�Ƃ��iNODE 0/NODE+1�Ƃ��Ă��j�A���P�[�u���̋����������A�����P�[�u���̋��������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���Fiber Deep�Ƃ��Ă��B�܂��A�����P�[�u���i���g����1/2��ɔ�Ⴕ�Č����ʂ���������j�̋������Z���Ȃ邽�߁A1GHz�ȏ�̎��g���܂ŒʐM�Ɏg����悤�ɂȂ�BDOCSIS 3.0�̉�����g����108�`1002MHz�ADOCSIS 3.1�̉�����g����258�`1218MHz�iMUST/�K�{�j���邢��108�`1794MHz�iSHOULD/�����EMAY/�C�ӂ��܂ށj�ƂȂ��Ă���i�ڍׂ�2.1.3�@DOCSIS 3.1�Q�Ɓj�B
2.1.1.2�@ �ϒ��E�������Z�p�̍��x��
�]���A�P�[�u���̕����ƒʐM�iDOCSIS 3.0�ȑO�j�̕����w�́AITU-T����J.83�ɏ�������QAM�ƒZ�k�����[�h�E�\����������RS�i204�A188�j�������Z�p��p���Ă����B�ŋ߁A�������Z�p�ɂ�BCH�u���b�N�����ƒᖧ�x�p���e�B�`�F�b�N�����iLDPC�j���p�����Ă���B���̌������Z�p��p����ƁACN��Ŗ�7dB�̉��P���ʂ�����A���݂�64QAM�̏��vCN���256QAM�����p�ł��邱�Ƃ���A��1.33�{�̓`�����\�ƂȂ�B����ɁADVB-C2�����DOCSIS 3.1�ł́A4096QAM���̑��l�ϒ����K�肳��Ă���B
�܂��A�ʐM�̍������iDOCSIS 3.0�j������̓`���e�ʊg��̂��߂ɁA�V���O���L�����AQAM�̕����̃`���l�����{���f�B���O������@�����邪�A�ŐV��Wi-Fi��DVB-C2�ADOCSIS 3.1�ł�OFDM���g���āA�A������`���l���̊Ԃ̋ш�ɂ������g�ߍ��ނ��Ƃœ`���e�ʂ̊g�傪�s���Ă���B
�����OFDM��BCH�{LDPC�������������̗p���A�ϒ��̑��l���ɂ�鍂�����`���\�Ƃ����B����BCH�{LDPC�����������́A���B�̕����K�i�iDVB�FDigital Video Broadcasting�j�̉q���E�n��E�P�[�u���̑��ł���DVB-S2�EDVB-T2�EDVB-C2����{�̉q�������̍��x�������ɍ̗p����A�ʐM�ł�DOCSIS 3.1�ɍ̗p����Ă���B�܂��AOFDM�ɂ��`���́ADVB-C2�ADOCSIS 3.1��EPoC�ō̗p����AOFDM�̃}���`�L�����A�����̓��������āA6MHz�ш�̘g���ĔC�ӂ̑ш�����R�Ɏg�p�\�ȋK�i�E�d�l�ƂȂ��Ă���B
�@ OFDM
���s�̃V���O���L�����AQAM�����ł́A6MHz�Ȃǂ̕����ш敝�ɐM���ш�𐧌����邽�߂Ƀ��[���I�t���Ɉˑ����Ă������AOFDM�ł͒��������T�u�L�����A�𖧂ɓ`�����邽�߁A�K�[�h�o���h���}�s�ȓ����������A�ш�d�l�������ǂ��Ȃ�B�܂��A�`���H�̔��˂���g�������̕�ɍۂ��Ď�M���ŗp������g�`�����ɂ����āA�V���O���L�����AQAM�����ł͊�M�����Ȃ��u���C���h�����̂��߂�1024QAM�ȏ�̑��lQAM�͎�������ł��邪�AOFDM�ł̓p�C���b�g�M���iContinual pilot��Scattered pilot�j����Ƃ����g�`�����ɂ����4096QAM�ȏ�̑��lQAM�������\�ƂȂ��Ă���B
����ɁAOFDM�̃T�u�L�����A��6MHz�ш�̘g���ĔC�ӂ̑ш�܂Ŋg��i�ш�A���j�ł��i6MHz�ш�Ԃ̃K�[�h�o���h���s�v�j�A����Ȃ�ш�d�l�������ǂ��Ȃ�B�܂��A6MHz�ш���Ɋ��g�������݂���ꍇ�A���s�̃V���O���L�����AQAM�����ł͂��̃`�����l���͎g�p�ł��Ȃ��������i��������`�����l���j�AOFDM�ł͂��̊��g�������݂�����g�������݂̂�����āA����ȊO�̕����ŃT�u�L�����A��p���ă`�����l�����̈ꕔ��L�����p�ł���B
DOCSIS 3.1��EPoC�ł́A6MHz�ш�̘g���ĔC�ӂ̑ш�i1MHz�P�ʁj�ŁA�����̕�����ʐM�Ŏg�p����Ă���ш������ė��p�\�ƂȂ��Ă���B�܂��A���Ɖ���̑o�����̒ʐM���p�ш���A����ш�i���10�`55MHz�A����70�`770MHz�j����A�V�K�ш�1�i���5�`65MHz�Ɖ���76�`1000MHz�j��V�K�ш�2�i���5�`204MHz�A����268�`1218MHz�j�Ȃǂ̎��R�ȑш�ŕύX�\�ƂȂ��Ă���B�������A���p�ш�̕ύX�ł́AHFC���\�����Ă���o�����A���v�̏��/���蕪�����g����ύX����K�v������B
�A BCH�{LDPC�������Z�p
���݂̃f�W�^�������ł́A�Z�k�����[�h�E�\����������RS�i204�A188�j��p���Ă��邪�A�ŋ߂ł�BCH�������p�u���b�N�����ƒᖧ�x�p���e�B�`�F�b�N�����iLDPC�j���p�����Ă���B
BCH�������p�u���b�N�����Ƃ́A�J���ҁiBose�EChaudhuri�EHocqenghem�G�{�[�Y�A�`���h�[���A�{�b�P���W�F���j�̖��ɗR������u���b�N�����������iBCH�̂ق��A�n�~���O������[�h�E�\����������������j�ł���A�u���b�N�P�ʂɓ���̐������������g���ē����p���e�B�r�b�g��t�����ē`������B�Ⴆ�ABCH�i15�A11�j�ł͐�����������G(x) = x4 + x + 1 ��p���āA�f�[�^���i���r�b�g���j��11�r�b�g�A�璷�r�b�g����4�r�b�g��1�r�b�g�̌��������ł���B�ᖧ�x�p���e�B�`�F�b�N�����iLDPC�FLow-Density Parity-Check�j�́A�p���e�B�`�F�b�N�����̈��ł���BLow-Density�i�ᖧ�x�j�Ƃ́A�������ɑ���1�����r�b�g�������Ȃ��Ƃ������Ƃł���AParity-Check�ł́A�r�b�g��̈��P�ʂ̒��ɂ���1�̐����A������������`�F�b�N���邱�ƂŌ��肷�邱�Ƃɂ���BLDPC�́A���ɑa�Ȍ����s��ɂ���`���ꂽ���`�����ł���B�a�ȍs��Ƃ́A�s�����1�̐������ɏ��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�����s�����1�̐������Ȃ����Ƃ́A���Z�ʂ����Ȃ����Ƃ��Ӗ������������邱�Ƃ��e�ՂɂȂ��Ă���B
���̋Z�p��p����ƁA��q�iDVB-C2���} 2‑1���邢��2.1.3�@DOCSIS 3.1���} 2‑8�j�Ŏ����悤�ɁA�����`�����x�ŏ��vCN�䂪��7dB���Ȃ�Shannon���E�l�܂�2dB�Ɣ����Ă���B
DVB-C2�ł́A�������̃u���b�N��������2��ޗp�ӂ���Ă���A������������Normal Code�i�������\�͂��������x���ʑ�j�ƕ��������Z��Short Code�i�������\�͂����܂荂���Ȃ����x���ʏ��j����������Ă��邪�A�ʏ�Nomal Code���g�p����B
DOCSIS 3.1�i����j�ł́A�ʐM�ŗ��p����ۂ̒x���ʍ팸�̂��߂�DVB-C2�ɂ�����Short code�݂̂�p���ALDPC����������8/9�݂̂Ƃ��āA�n�[�h�E�F�A�̕��G����������Ă���i��q���} 2‑6�Q�Ɓj�B
2.1.2�@ DVB-C2�i���x�ȃf�W�^���L���e���r�W�������������j
DVB�́A���B�̃f�W�^�����������̕W�����g�D�A����т����ō��肳�ꂽ�W���K�i���w���ADVB�K�i�Ă͉��B�ʐM�W��������iETSI�FEuropean Telecommunications Standards Institute�j�ɒ�o����A���B����̋K�i�ƂȂ�BDVB�W���K�i�́A���B�ȊO���܂ߑ����̍��ō̗p����Ă���A�����K�iDVB-C�́A�O�N1993�N�ɐ��肳�ꂽDVB-S����ɁA1994�N�ɐ��肳�ꂽ�B���{�̃P�[�u���d�l�ł�������Q�Ƃ��AJ.83�gAnnex C�h�Ƃ��ċK�i������Ă���B���Ȃ݂�DVB-C�͓�����J.83�gAnnex A�h�Ƃ��ċK�i������Ă���B
DVB-C2�́A��2����f�W�^���P�[�u���K�i�Ƃ���2009�N�ɋK�i�����������A���N2010�N�Ɏ��p�������ɒ��肵���B2011�N11���ɂ́A����LSI�̏o�ׂ��J�n����Ă���B�܂�2013�N2���ɕ]�����������{���A���̌��ʂ������ċK�i�����ŏI�łƂȂ��Ă���B���̌�2013�N6���ɂ́A���B�̎��ƎҁiKabel Deutschland�j�ɂ����āADVB-C2�ł̎����������J�n���ꂽ�i�����F1024QAM�A��������3/4�j�B
DVB-C2�̑傫�ȓ����Ƃ��āA�L�����A�`��������OFDM���̗p�������ƂƁA������������LDPC���̗p�������Ƃ���������B�����́A�q���K�i��DVB-S2/�n��g�K�i��DVB-T2�ō̗p���ꂽ���̂����̂܂܁ADVB-C2�ł��̗p�������̂ł���B
�������s�K�i�ł́A�ϒ������̓V���O���L�����A��64QAM/256QAM�ł��邪�ADVB-C2�̓}���`�L�����A��OFDM�����ł���A�ш���ɕ����̃T�u�L�����A�𗧂āA���ꂼ��16QAM����4096QAM�܂ł̑��lQAM��I���\�ł���B�������́A�]����Reed-Solomon�����ɑւ��ADVB-C2�ł͓������Ƃ���LDPC�A�O�����ɂ�BCH���̗p���Ă���BLDPC����������2/3����9/10�܂ł�5��ނ�����B
�M���ш敝�́A�ő�l�Ƃ���8MHz��6MHz����I���ł���悤�ɂȂ��Ă���B���̍ő�ш敝�ɂ�����L�����A���̍ő�l��8MHz��6MHz�Ƃœ���3408�Ƃ��Ă���A�L�����A�������炷���Ƃɂ��ш敝��C�ӂɌ��炷���Ƃ��\�ł���B�L�����A���̍ő�l��8MHz��6MHz�Ƃœ����ł���̂ŁA�L�����A�Ԋu��8MHz�̏ꍇ��2.23kHz�A6MHz��1.67kHz�ŌŒ�ƂȂ�B
DVB-C2�̓`��������DVB-C����ь��s�����K���K�i�ł���J.83 Annex C�Ɣ�r�����\ 2‑1�Ɏ����A���\��r�Ƃ��ď��vCN��Ɠ`�����x���} 2‑1�Ɏ����B
�\ 2‑1�@DVB-C2��DVB-C�̕�����r
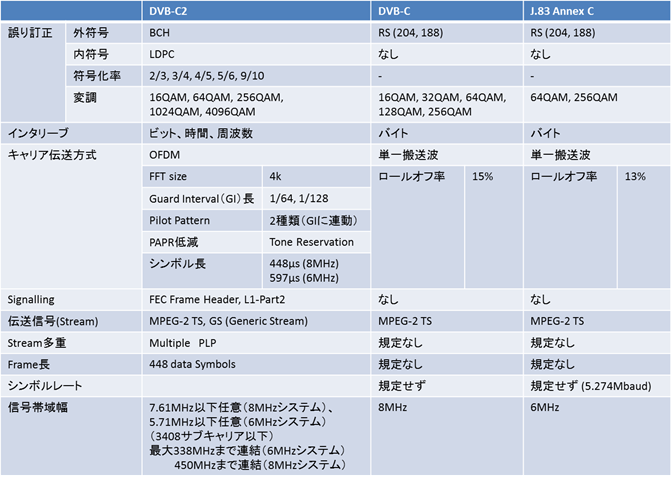
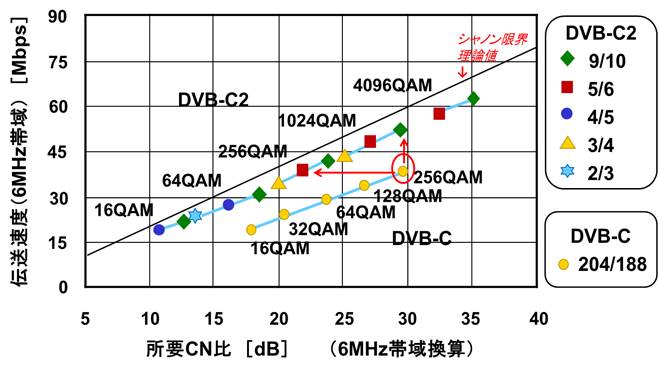
�} 2‑1�@DVB-C2��DVB-C�Ƃ̐��\��r
�} 2‑1�́ADVB-C2�̓������悭�\�����̂Ƃ��ėp��������̂ł���B�����Ŏ������V���m�����E�́AShannon�������ʐM�ɂ�����`���e�ʂ̗��_���E�l�ł���A���s��DVB-C�i6MHz���Z�j�͗��_�l�ɑ��Ă܂��u���肪���邪�ADVB-C2�͗��_���E�ɂ��Ȃ�߂Â������`��������B�����Ă���B
����̉^�p�ŗp�����Ă���64QAM�Ə��vCN�䂪�����ꍇ�A3�����̓`�����x��������B���s��256QAM�̓`�����x���g���������A���vCN�䂪���������^�p�ł��Ȃ��ꍇ�ł��ADVB-C2�ɂ����Ă�256QAM/��������4/5�ł�7dB�ႢCN��ł��\�ł���B�܂�����256QAM�^�p���\�ȏꍇ�AC2�ł�1024QAM/��������9/10���g�p�ł���B
ITU-T���ەW�����ɂ����ẮA������P�[�u���`�������̗v������J.381�Ɋ�Â��`�������̎d�l�K��Ƃ��āADVB-C2�ɏ�������V�K����J.382��2013�N12���Ɋ��������ꂽ�B�Ȃ�2017�N10���̎��_�ɂ����ẮA�{�������̗p�������i�͓��{�����ł͎s�̂���Ă��Ȃ��B
2.1.3�@ DOCSIS 3.1
DOCSIS�iData Over Cable System Interface Specification�j��HFC��ō����f�[�^�T�[�r�X����邽�߂̃V�X�e���d�l�ŁA���̏��Łi1.0�Łj�͕č��P�[�u�����{��1997�N3���ɍ��肵���B���̌�AQoS�@�\�̒lj��i1.1�ŁA1999�N4���j�A���ϒ������̒lj��ɂ����g�����p�����ib/s/Hz�j�̉��P�i2.0�ŁA2001�N12���j�A�`���l���{���f�B���O�@�\�̒lj��i3.0�ŁA2006�N8���j�Ƃ������������d�ˁA2013�N10���ɂ͍ŐV��3.1�ł������[�X����Ă���B
DOCSIS 3.1�́AOFDM��LDPC�̗̍p�ɂ��DOCSIS 3.0�ɔ�ׂĎ��g�����p������3���ȏ���シ��Ƌ��ɁAHFC�̏�����g�����ő�1.8GHz�܂Ŋg�����邱�Ƃɂ��`���e�ʂ̔���I�Ȋg���}���Ă���B���Ȃ킿�A�W���I�Ȑݔ��\���ʼn���5Gbps�A���1Gbps�̓`���e�ʂ̎������������Ă���B�܂��A�]���̃V���O���L�����AQAM�ϕ��������萔�����邱�Ƃɂ��DOCSIS 3.0�Ƃ̋������\�Ƃ��Ă���̂������ł���ADOCSIS 3.0�Ƃ͐���̈قȂ�Z�p���̗p���Ă���ɂ��ւ�炸DOCSIS 3.1�ƌď̂��Ă��鏊�Ȃł���B[1]
DOCSIS 3.0��3.1�ł̑傫�ȈႢ�́A�\ 2‑2�Ɏ����悤�ɁA�`���������V���O���L�����AQAM����OFDM�ɂȂ������ƁA���͂Ȍ����������ł���LDPC�̓����ɂ��ő命�l�ϒ�������4096QAM�i�I�v�V�����ł�16384QAM�܂Łj�Ƃ������ƁA�܂��AOFDM�̗̍p�ɔ�����6MHz�̃`�����l���T�O��P�p���A�ő�192MHz�i����j�A96MHz�i���j���V�X�e��������̍ő���g���ш敝�Ƃ����_���ł���B
�\ 2‑2�@DOCSIS 3.0/3.1��r
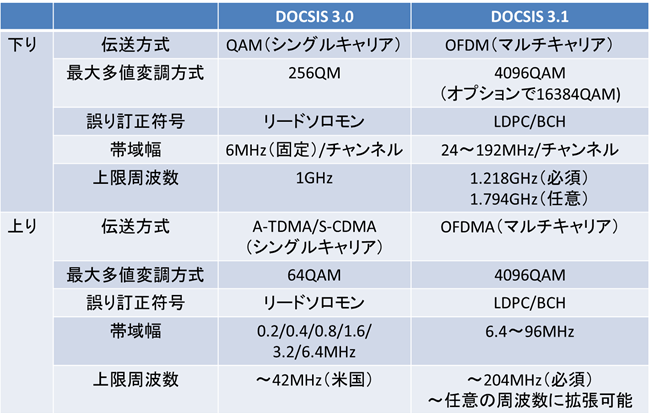
DOCSIS 3.1���p������g�����Ɏ����B����ш�́A3.0���p����108�`258MHz���g���ш�i�����j�A258�`1218MHz��K�{�Ƃ��A�����1218�`1794MHz���g���ш�i�C�Ӂj�Ƃ��Ă���B����5�`204MHz��K�{�Ƃ�����ŁA204MHz�ȏ�̑ш�͏�������߂��ɔC�ӂɊg���\�Ƃ��Ă���B
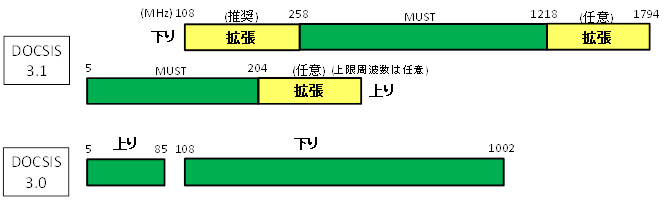
�} 2‑2 �@DOCSIS 3.1/3.0�̎��g��
DOCSIS 3.1�ɂ���e�ʉ��́A�`�������̍��x���ɉ����A���̂悤��HFC�ш�̊g����O��Ƃ��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���A�ȉ��̉ۑ�ւ̑Ή����K�v�ƂȂ�B
�E�g���ш�ʼn^�p���̖����V�X�e���Ƃ̊Ԃ̔튱�E�^���ւ̑Ή�
�E���E����̑ш�ύX�ɔ������p������̒u��
�܂��A���l�ϒ���p���邽�߂ɂ͎�M�[�ɂ�����CN��̉��P���K�v�ƂȂ�A���̂��߂ɃP�[�u�����f���iCM�j�������ґ���̋��E�_�ɒu������iGateway Architecture�Ə̂���j�AHFC�̏��Z����������������̊g��iFiber Deep���ƌď́j���̕���ɂ��`���HCN������P���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
DOCSIS 3.1�̉��肨��я��d�l�T�v�����ꂼ���\ 2‑3�A�\ 2‑4�Ɏ����B
�\ 2‑3�@DOCSIS 3.1�d�l�T�v�i����j
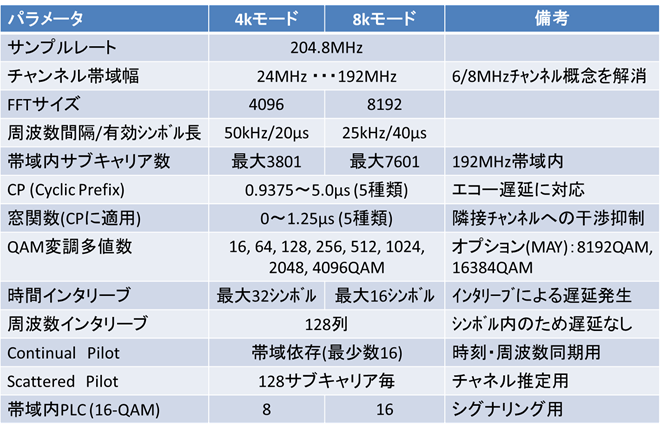
�\ 2‑4�@DOCSIS 3.1�d�l�T�v�i���j
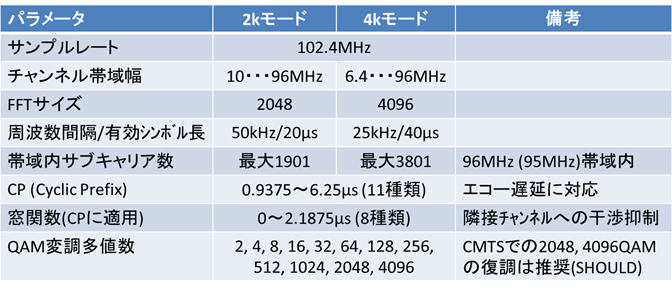
�\ 2‑3�A�\ 2‑4��2k/4k/8k���[�h��FFT�T�C�Y�������A���E���肻�ꂼ���2��ނ�FFT�T�C�Y���K�肳��Ă��邪�A���ۂ̉^�p���ɍ��킹�ēK��FFT�T�C�Y��I�����邱�Ƃ����߂���B�Ⴆ�A����8k���[�h�ł̓T�u�L�����A�̎��g���Ԋu��25kHz�ƂȂ�A4k���[�h��50kHz�ɔ�ׂĂ�肫�ߍׂ������g���̉�����\�ƂȂ�B�܂��A�V���{�����͒���������ɏq�ׂ�K�[�h�C���^�[�o���iCyclic Prefix�FCP�j�̕t�^�ɂ��`���e�ʒቺ�̉e�������Ȃ��ł��邪�A���̔��ʃC���p���X���̃m�C�Y�̉e�����₷���Ȃ�A�����l�����ׂ��_�ł���B
�Ȃ��A����4k���[�h�ł�4096�{�̃T�u�L�����A����������邪�A192MHz�̑ш���ɔz�u�����͍̂ő��3801�{�ŁA���[��295�{�͓d�͂�^����ꂸ�A���p����Ȃ��i�} 2‑3�j�B���̏�Ԃ̃T�u�L�����A��Excluded�i���O�j�T�u�L�����A�ƌĂԁB�ш����QAM�`�����l����z�u������A����̑ш�ɑ��݂��銱�g�������ꍇ�ɂ��Y������T�u�L�����A��Excluded��Ԃɂ���B
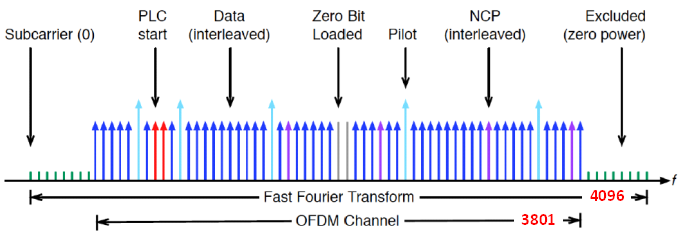
�} 2‑3�@DOCSIS 3.1�̃X�y�N�g����
DOCSIS 3.1�̃V�X�e���v�����} 2‑4�Ɏ����B���E���苤�ɁA��Ɏ�����OFDM�e2�`�����l���Ƌ��ɁA����͏]����QAM�`�����l��24�A����QAM�`�����l��8���������邱�ƂƂ��Ă���B�����āACMTS�iCable Modem Termination System�j��S-CDMA���[�h�̏�������T�|�[�g���邱�Ƃ𐄏����Ă���B
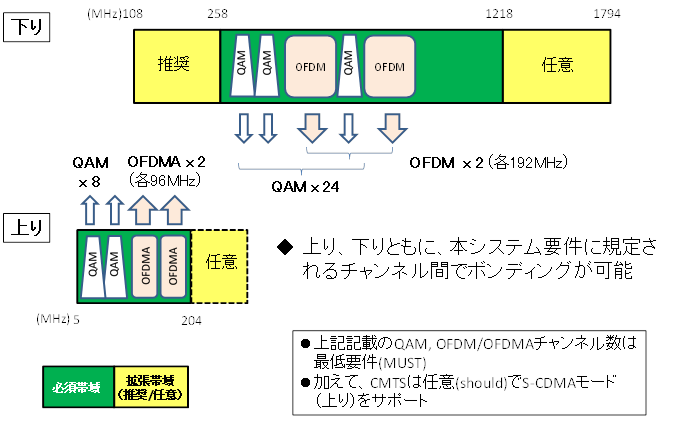
�} 2‑4�@DOCSIS 3.1�̃V�X�e���v��
2.1.3.1�@ DOCSIS 3.1��PHY�i����j
DOCSIS 3.1�̉���PHY�@�\�̃u���b�N�}���} 2‑5�Ɏ����B
�M���̓f�[�^��i���j�ƃV�O�i�����O�@�\��S��PLC�iPhysical Layer Signaling Channel�j�ɕ������A���ꂼ�ꂪ�������iFEC�j�AI/Q�A�X�N�����u���A�C���^�[���[�u���̏������o�č������ꂽ��A�t�t�[���G�ϊ��iIDFT/IFFT�j�ɂ����OFDM�T�u�L�����A����������A�K�[�h�C���^�[�o���iCP�j����ё������t�������B
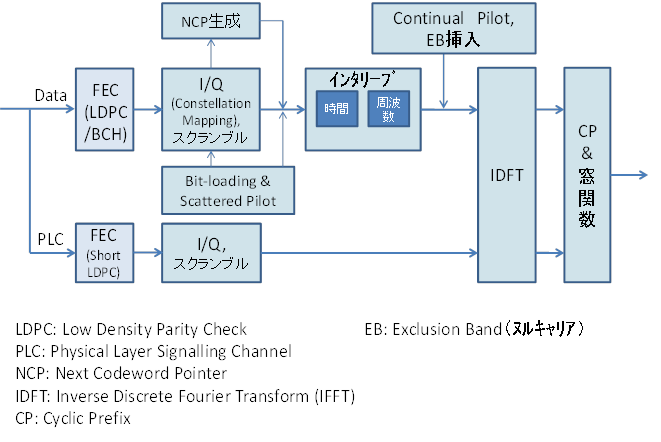
�} 2‑5�@DOCSIS 3.1����PHY�@�\�u���b�N�}
�ȉ��A�e�@�\�ɂ��ĊT������B
(1) FEC�i����j
DOCSIS 3.1�̉���ł��} 2‑6�Ɏ����悤�ɁA�����������iFEC�j�Ƃ��ĊO����BCH�A������LDPC��p���Ă���B����͊�{�I�ɂ�DVB-C2�d�l��6.1��[2]�Ɠ��l�ł��邪�ADVB-C2�ł�64800�r�b�g�̕�������Normal Code�Ƃ��ėp����̂ɑ��āADOCSIS 3.1�ɂ����ẮADVB-C2�ł�Short code�ƌĂ��16200�r�b�g�̕������݂̂�p���ALDPC����������8/9�݂̂Ƃ��āA�ʐM���p���̒x���팸�ƂƂ��Ƀn�[�h�E�F�A�̕��G����������Ă���B
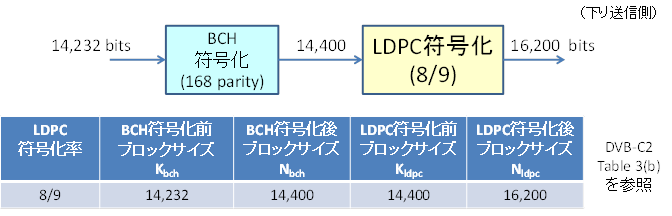
�} 2‑6�@DOCSIS 3.1����FEC
(2) ���l�ϒ������i����j
�`���V�X�e���ł́A�ʏ�A�`���H��CN��ɍ��킹�Č������̕��������Ƒ��l�ϒ��̑g���������邱�Ƃɂ��`�����\�̍œK����}�邱�Ƃ��������ADOCSIS 3.1�ł͕����������Œ肵�A���̑���ɔ��`�ϒ��i128QAM�A512QAM�A2048QAM�j����э����ϒ��imixed modulation�j��p���邱�Ƃɂ��`���HCN�ւ̑Ή����s���Ă���B���̓_��DVB-C2�ɂ͂Ȃ�DOCSIS 3.1�̓����ł���B
���`�ϒ��̗�Ƃ���512QAM�̃R���X�e���[�V�������} 2‑7�Ɏ����B
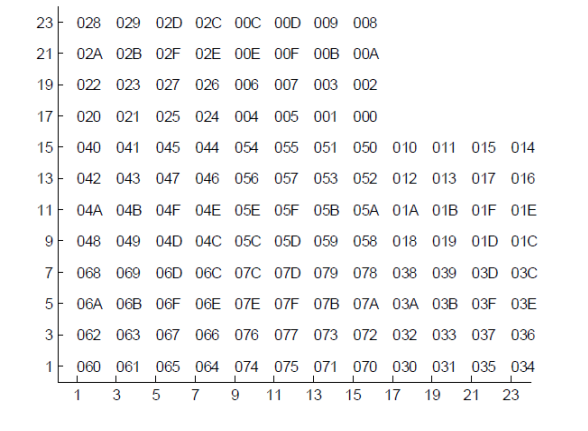
�} 2‑7�@���`�ϒ��̗�i512QAM�j
�����ϒ��́A512/1024QAM�A1024/2048QAM�A2048/4096QAM�̂悤�ɈقȂ鑽�l�ϒ������g������A���Ԏ���ō��݂����ėp���邱�Ƃɂ��A���ԓI�ȏ��vCN���m�ۂ���Z�p�ł���B
DOCSIS 3.1�ł́A�ʏ�̑��l�ϒ��ɔ��`�ϒ�����э����ϒ��������邱�Ƃɂ�菊�vCN��̗��x�igranuality�j��1.5dB���݂Ŏ������Ă���B
�} 2‑8�ɕϒ������i�`���e�ʁj�Ə��vCN��̊W�������B
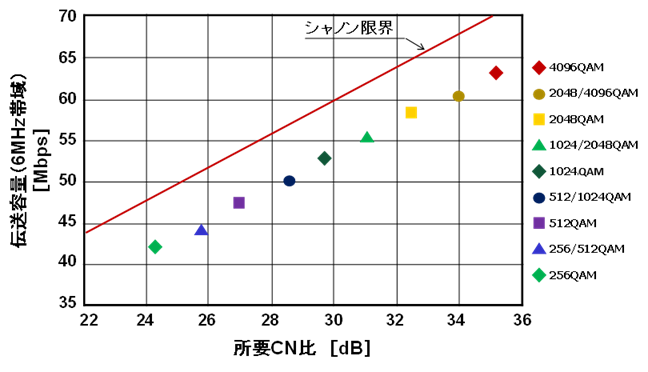
�} 2‑8�@�ϒ����l���Ə��vCN��̊W
(3) �ϒ��v���t�@�C��
DOCISIS 3.1�ł́A��M�_�œ�����CN��ɍ��킹��OFDM�T�u�L�����A�̕ϒ����l�����w��ł���B�����ϒ����l����L����T�u�L�����A�̏W�܂��ϒ��v���t�@�C���iprofile�j�ƌĂсAA����P�܂ł�16��ނ��K�肳���BProfile A��CM�����������o�^����ۂɗp����boot profile�ł���B
�v���t�@�C�����} 2‑9�̂悤�Ɏ��g���i�T�u�L�����A�j�����Ǝ��Ԏ������Ƀu���b�N������AA���珇�Ԃɑ��M�����i�}�ł�A����D�܂ł̃v���t�@�C�����L�ځj�B��M����CM����M���ׂ��T�u�L�����A�͂����ꂩ�̃v���t�@�C���Ɋ܂܂�A�v���t�@�C�����ꏄ����܂ł͎��̃f�[�^�͎�M�ł��Ȃ��B����āA�v���t�@�C���̌J��Ԃ��������`���x���ilatency�j�ƂȂ�B
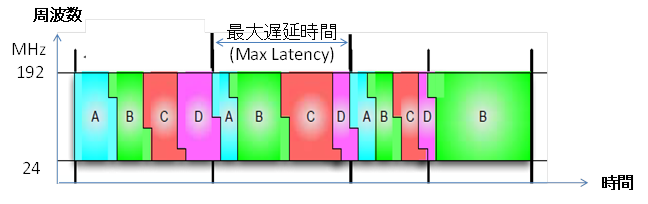
�} 2‑9�@�ϒ��v���t�@�C��
(4) PLC
PLC�iPhysical Layer Link Channel�j�́ACMTS����CM��OFDM�`�����l���̕ϒ����l�����̃p�����[�^��ʒm����V�O�i�����O�`�����l���ł���B
PLC���} 2‑10�Ɏ����悤�ɘA������6MHz�ȏ�̑ш悪�m�ۂł�����g���т�4k���[�h��8�{�A8k���[�h��16�{�̃T�u�L�����A�Ƃ��Ĕz�u�����i���ɑS�ш敝��400kHz�j�BPLC�̍ł����g���̒Ⴂ�T�u�L�����A��1MHz�̐����{�̎��g���ɔz�u���邱�ƂƂȂ��Ă���A�C�j�V�����C�Y����CM��1MHz���Ƃɑш���X�L��������PLC��T���B
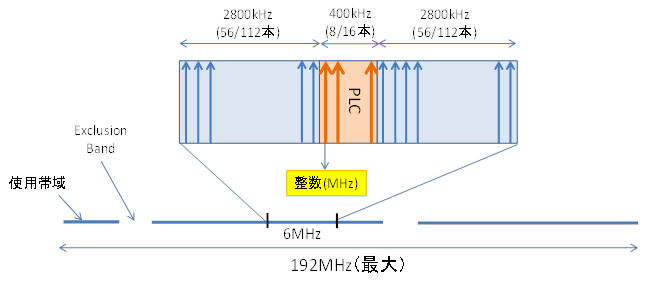
�} 2‑10�@PLC�z�u�}
�} 2‑11�Ɏ����悤�ɁAPLC�̓v���A���u��8�V���{���ƃf�[�^120�V���{���i���v128�V���{���j�̌J��Ԃ��ō\������A�v���A���u������BPSK�A�f�[�^������16QAM�ϒ��Ɛ�p��LDPC�i384�A288�j��p����B
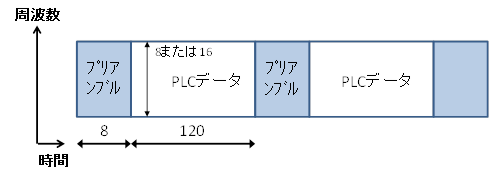
�} 2‑11�@PLC�̍\��
(5) CP����ё���
DOCSIS 3.1�ł́A�x���g�ɂ�銱��ጸ����CP�A����ё��M�X�y�N�g�����̑ш�O�������������P���鑋�����d�l������Ă���B
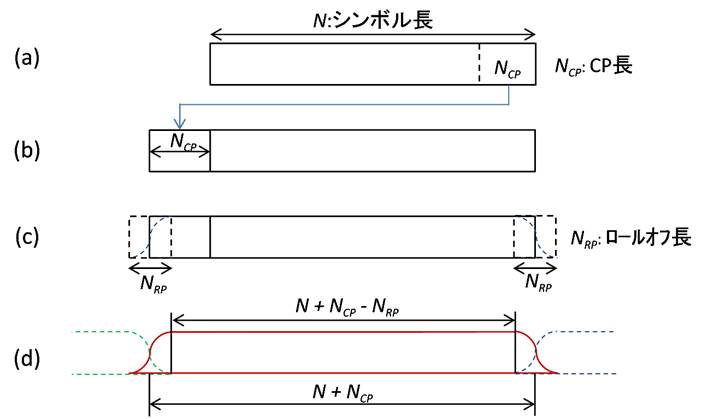
�} 2‑12�@CP�Ƒ���
CP�̓K�[�h�C���^�[�o���iG/I�j�Ƃ��Ă�A�} 2‑12 (a)(b)�Ɏ������悤�ɁA����`������V���{���ɕt������邽�ߓ`���e�ʂ��������邪�AHFC���̔��˓��ɂ���Đ�����x���g�̉e���y���ɗL���ł���BDOCSIS 3.1�̉���ł�CP���iNCP�j�Ƃ���0.9375�A1.25�A2.5�A3.75�A5.0µs��5��ނ��K�肳��Ă���BCP�l���傫���قǁA�����x���ɑΉ��\�����A�`���e�ʂւ̉e�����傫���Ȃ�BCP�Ɠ`���e�ʂ̊W���} 2‑13�Ɏ����B����4k���[�h�ł̓V���{������20µs�ƒZ�����߁ACP�̒l�ɂ���Ă͗e�ʂ��傫���ቺ���邱�Ƃ��킩��B
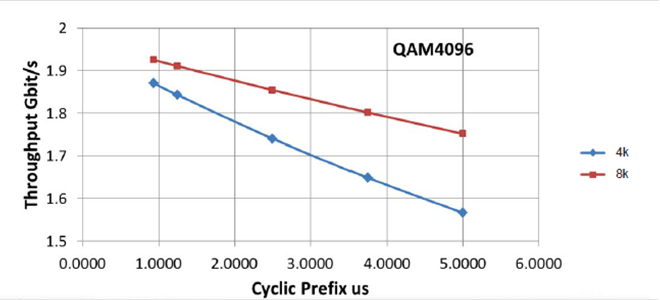
�} 2‑13�@CP�Ɠ`���e�ʂ̊W
����̑����́A�} 2‑12 (c)�Ɏ����悤�ɁA��`�V���{���̗��[��raised cosine�����|�����킹�A���Ԏ���łȂ��炩�Ȍ`��ɂ�����̂ŁA���[���I�t���iNRP�j�ɂ��K�肳���BNRP�͉�������ł�0�i�����Ȃ��j�A0.3125�A0.625�A0.9375�A1.25µs��5��ނ����p�\�ł���i�������ANCP��NRP�j�B���[���I�t�����ݒ肷��قǁA�V�X�e������я��O�ш�iexclusion band�j�̗��[�ɂ����Ď��g���̈�ŋ}�s�ȑш�O���������������邽�߁A�אڂ�QAM�M�����ւ̉e����ጸ���A��葽����OFDM�T�u�L�����A���^�p�\�ƂȂ�B�������A�} 2‑12 (d)�Ɏ������悤�Ƀ��[���I�t���̔����͗אڂ̃V���{���Əd�Ȃ邽�߁A�V���{���Ԋ����������錇�_������B
DOCSIS 3.1�̓`���e�ʂ��ő剻���邽�߂ɂ́A�^�p����HFC�̓�����אڂ̑��̃T�[�r�X�̉^�p�ɍ��킹��NCP��NRP�̒l���œK�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
2.1.3.2�@ DOCSIS 3.1��PHY�@�\�i���j
(1) �~�j�X���b�g
DOCSIS�̏��ɂ����āACM�Ɋ����Ă��鑗�M�g���~�j�X���b�g�iMinislot�j�ƌĂԁB�eCM�́A1��̑��M�^�C�~���O���Ƃ�1�܂��͕����̃~�j�X���b�g�������Ă��A�o�[�X�g��̑��M�g�𑗐M����BDOCSIS 3.1�̃~�j�X���b�g�́A���Ԏ�K�V���{���A���g����Q�T�u�L�����A���\�������i�} 2‑14�j�B�\ 2‑5�Ɏ����悤�ɁA�V���{����K�̓��[�h�iFFT�T�C�Y�j����уV�X�e���̑ш敝�ɂ��ő�l���K�肳��A�T�u�L�����A��Q�̓��[�h�ɂ����i8�܂���16�j�ł���B
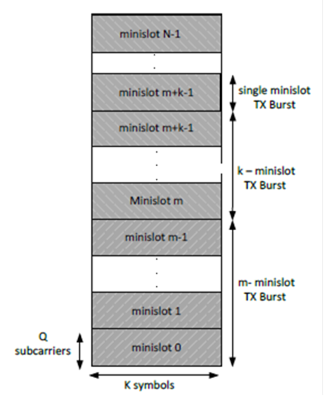
�} 2‑14�@DOCSIS 3.1�̃~�j�X���b�g�\���}
�\ 2‑5�@DOCSIS 3.1�~�j�X���b�g�p�����[�^
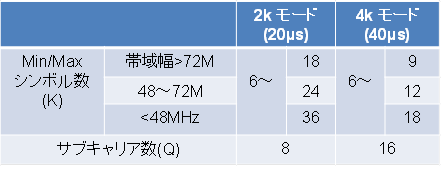
�~�j�X���b�g���̃T�u�L�����A�͂��ׂē����ϒ���p���邪�A���M�^�C�~���O���Ƃɕϒ����l����ύX�\�ł���B
(2) FEC�i���j
DOCSIS 3.1���FEC�́A����ƈقȂ�AQC-LDPC�iQuasi-Cyclic LDPC�j��p����BQC-LDPC�͊ȈՂȌJ��Ԃ��s��𗘗p������̂ŁACM�̃n�[�h�E�F�A���ȑf�����邱�Ƃ��\�ł���B���FEC�̃p�����[�^���\ 2‑6�Ɏ����B
�\ 2‑6�@DOCSIS 3.1���FEC
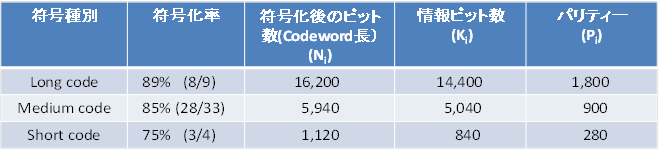
CM��CMTS����ʒm�����grant�i���M���j�Ɋ�Â��A�~�j�X���b�g�߂Ă������A���̎��A�ŏ���Long�R�[�h���g���A�c��r�b�g��Long�R�[�h������Ȃ�����Medium�R�[�h��p���A�Ō��Short�R�[�h�Ń~�j�X���b�g�����B
2.1.3.3�@ �`�����l���{���f�B���O
�} 2‑4��DOCSIS 3.1�̃V�X�e���v���Ɏ�����OFDM�`�����l���ԁAQAM�`�����l���ԁA�����OFDM/QAM�`�����l���ԂŃ{���f�B���O���\�ł���B
����Ń`�����l���{���f�B���O���s�������̍ő�e�ʁiMAC�e�ʁj���\ 2‑7�Ɏ����B�������AOFDM��4�V�X�e���i192MHz�~4�j�ȏ�^�p���邽�߂ɂ͈�ʂ�HFC�ш�̊g�����O��ƂȂ�B
�\ 2‑7�@����`�����l���{���f�B���O���̍ő�e�ʁiMAC�e�ʁj
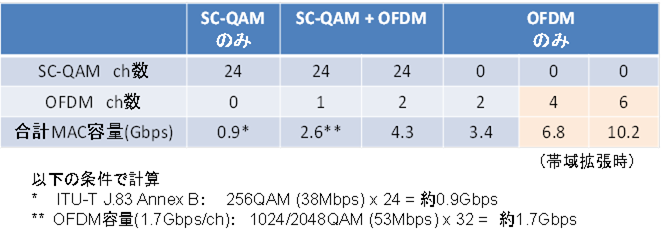
���ł��AOFDMA��QAM�`�����l���Ԃ̃{���f�B���O���\�ł���B
���̏ꍇ�ATaFDM�iTime and Frequency Divising Multiplexing�F���Ԏ��g���������d�j��p����OFDMA/QAM�`�����l���������ш�����p����B����́A�} 2‑15�Ɏ����悤�ɁAQAM�`�����l���̑��M�~�j�X���b�g��OFDMA�̃t���[���������A�����QAM�`�����l�������p���Ȃ����g����OFDMA�~�j�X���b�g�������Ă邱�Ƃɂ�莞�Ԏ�����ю��g�����őш�����p����Z�p�ł���B
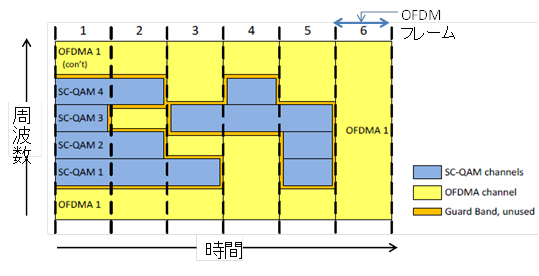
�} 2‑15�@���`�����l���{���f�B���O��TaFDM
2.1.4�@ DOCSIS 4.0
HFC�l�b�g���[�N�W�����A��Gbps�̏㉺�Ώ̑��x�̃T�[�r�X�����������@�Ƃ��āA�C�O�̃P�[�u���ƊE�ł�2�̈قȂ�A�v���[�`���o�������B
ž Full Duplex�iFDX�jDOCSIS�iNode + 0 �̍\���ł̂ݑΉ��\�j
ž ���g�����d�iFDD�jDOCSIS��1.8GHz�܂ŃX�y�N�g���g���iESD�j
�iNode + 0 �ȊO�̍\���ł��Ή��\�j
���̎�@�̑��ႪCATV�֘A�x���_�̍����������A�����̗̂v����s�ꉻ�����̕s�m��������ݔ��������S�O�����鎖�Ԃɔ��W���Ă������B���̎��Ԃ����������邽�߁A�č�CableLabs�ł̓x���_����щ���e�ЂƂƂ��ɑI�����̖��m���Ɠ����i�߁ADOCSIS 4.0�̎d�l��V���ɍ��肵�Ă���B
DOCSIS 4.0�ɂ����ẮA���Ɏ����悤�ɋZ�p�I��{�����s����B
ž FDX �� 1.8GHz FDD�̗��@�\���T�|�[�g
ž ����MAC (�� D4.0 MAC) �v����P��d�l��
ž ����PHY (�� D4.0 PHY) �v����P��d�l��
ž DOCSIS 4.0�����̂́A���ׂĂ̗v�����T�|�[�g
ž �P�[�u�����f���iCM�j�p�����̂̐v�ɉe����^����v����`������
Ø ����: OFDM 5ch�A �P��L�����AQAM�@32ch
Ø ���: OFDMA 7ch�A A-TDMA 4ch�i�I�v�V������8ch)
Ø FDX�� 1.8GHz FDD�̗��v����`���T�|�[�g
2.1.4.1�@ FDX�iFull Duplex�j�V�X�e��
DOCSIS 3.1�ł͉���10Gbps�A���1Gbps�����E�Ƃ���邪�A�č�CableLabs�ł͏��E����Ώ̂�10Gbps�T�[�r�X���\�Ƃ���FDX�iFull Duplex�j����������ADOCSIS 4.0�ŋK�i�����ꂽ�B����܂ł�DOCSIS 3.1�Ƃ͈قȂ�A����ш�͂��̂܂܂ɁA���ш�g�����\�ł���BFDX�ł�108�`684MHz�Ԃŏ��E�����OFDM�M�����Ɏg�p����B���̂��߁A�M���Ԋ����L�����Z������Z�p�i�G�R�[�L�����Z�����O�j���K�{�ƂȂ�B���͓���CM�������CM�ɑ��Ă����łȂ��A�m�[�h�o�R�����邽�߃G�R�[�L�����Z�����O��FDX�ɂƂ��ĕK�{�̋Z�p�ł���B
�} 2‑16��CMTS�ACM���ꂼ�ꂩ�猩��FDX�`�����l���̎g�����ƐM���Ԋ��̊T�O���A�} 2‑17��FDX�V�X�e���ԁA�����V�X�e���ւ̊��������B
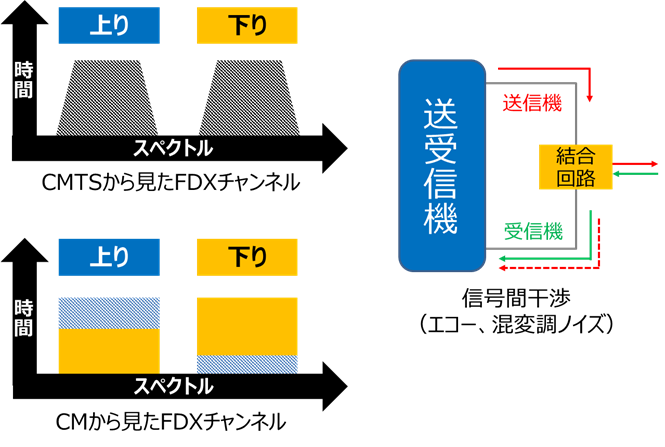
�} 2‑16�@FDX�ł�TDD�Z�p�̎g�����ƐM���Ԋ��̊T�O
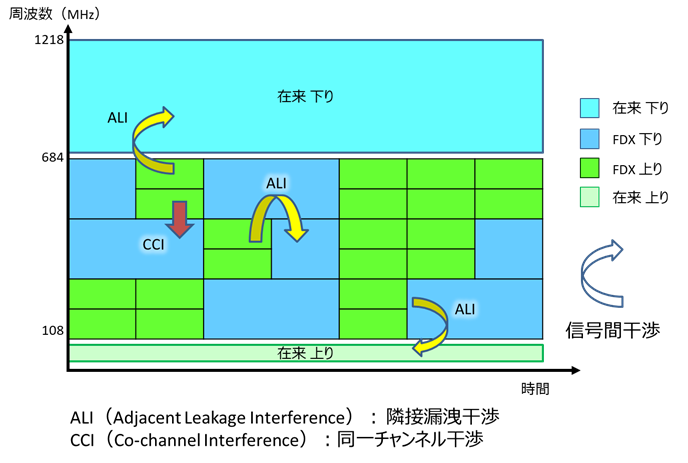
�} 2‑17�@FDX�V�X�e���ԁA�����V�X�e���ւ̊���
�} 2‑18��FDX�P�[�u�����f���iCM�j�ɂ����銱�̏������B
���̏܂��ADOCSIS 4.0�ł͈ȉ��̎菇�ɂ��FDX�̎��g�������Ɗ��������s���B
i) ����CM�̏��Ɖ����FDX�ш�i108�`684MHz�j���̈قȂ���g���������Ă�B
ii) CM�̏�著�M�M���ɕt������ш�O�X�v���A�X�M���̎��g�̎�M�@�ւ̉�荞�݁i�אڃ`�����l���ւ̘R��E���j�̓G�R�[�L�����Z���ŏ�������B
iii) CM�̏��M��������CM�̉���M����M�Ɋ����邩�ۂ������O�Ɍ����A������CM�̃O���[�v�����O���[�v�iIG�j�ƒ�`����B����CM�����M���́A����CM��������IG���̑���CM�ɁA�������g��������p�Ɋ����ĂȂ��B
iv) CMTS���} 2‑16�ɂ������悤�ɏ펞�A�S�ш�����E���蓯���ɗ��p����̂ŁA�G�R�[�L�����Z���Ŋ�����������B
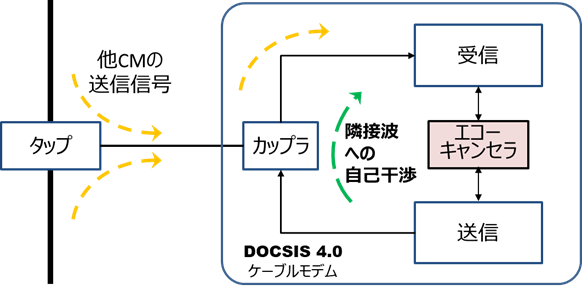
�} 2‑18�@FDX CM�ɂ����銱��
FDX��CM�͔�FDX��DOCSIS 3.1 CM�Ƃ̍��݉^�p���\�ƂȂ��Ă���B�} 2‑19��DOCSIS 3.1�V�X�e����FDX�̕��p�������B���̐}�́AFDX�m�[�h�ɂ�����108MHz�`204MHz�őS��d�ʐM���ł��邱�Ƃ������Ă���B
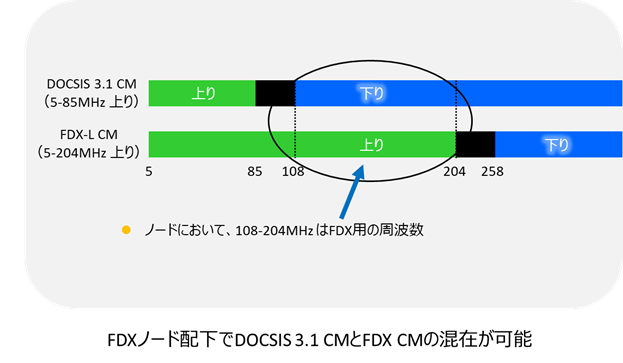
�} 2‑19�@DOCSIS 3.1�V�X�e����FDX�̕��p
2.1.4.2�@ FDD�iFrequency Division Duplexing�j�V�X�e��
�} 2‑20��DOCSIS 4.0�ɂ�����1.8GHz �ш�g��FDD�ɂ�����㉺�������g���������B
�����g����684MHz�܂Ŋg���\�ŁA684�`834MHz�̃K�[�h�o���h������ŁA834�`1218MHz�܂ł�384MHz��1794MHz�܂ł�576MHz�A���v960MHz�ш敝��������g���Ƃ��ė��p����B
�Ȃ��������g��������������A�K�[�h�o���h�ш敝���傫���Ȃ�_�ɒ��ӂ��K�v�ł���B
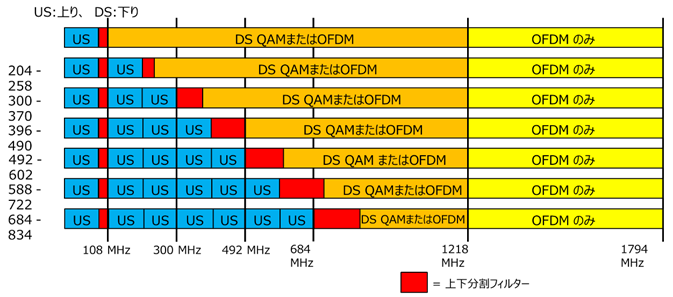
�} 2‑20�@DOCSIS 4.0�ɂ�����1.8GHz�ш�g�� FDD�pCM�̏㉺�������g���̗�
2.2�@ ���`���Z�p
2.2.1�@ ���`���̎d�g��
���`���̌`�Ԃ́A���t�@�C�o���w�b�h�G���h����ǂ��܂ŕ~�݂��邩�ɂ���đ傫��4�ɕ�������B�} 2‑21�̂悤�Ɍ��m�[�h�܂ł�HFC�iHybrid Fiber Coaxial�j�A���o�̓~�j�m�[�h�܂ł�FTTC�iFiber To The Curb�j�A�e�Z�˂܂ł�FTTH�iFiber To The Home�j�A�W���Z��̋��p���܂ł�FTTB�iFiber To The Building�j�ƌĂԁB
HFC�́A���O�`���H�����P�[�u���Ɠ����P�[�u���ō\�������B�����P�[�u����Ԃɂ�5�`7�i�̑����킪�ڑ������BFTTC�́A���O�`���H�����P�[�u���Ɠ����P�[�u���ō\������AHFC�̃l�b�g���[�N�`�ԂƂ̍��͏��Ȃ����A�����ґ�̋߂��ɍ��o�̓~�j�m�[�h��ݒu���A�����P�[�u����Ԃɑ������u���Ȃ������ł���BFTTH�́A���O�`���H�����ׂČ��P�[�u���ō\������A�ˌ��Z�˂̂悤�ɂ��ꂪ�_��Z�˂ւ̕~�݂ƂȂ�����ł���BFTTB�́A���O�`���H�����ׂČ��P�[�u���ō\������邪�A�W���Z��̂悤�Ɍ����ւ̈�������_��Z�˂܂ł͌����̓����P�[�u�����̊��ݔz���œ`����������ł���B
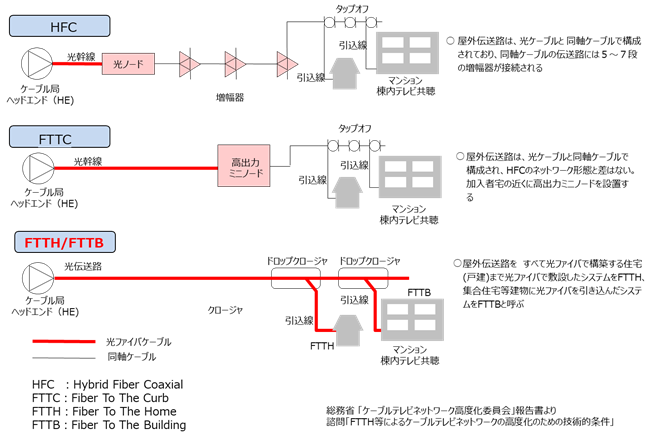
�} 2‑21�@���`���̌`��
���`���ɂ����ẮA�} 2‑22�Ɏ����Ƃ�����t�@�C�o1�c�̏�ɁA�Е����̕����Ƒo�����ʐM��g�����d���ē`������B�g�p����g���͕�����1,555nm�A�ʐM������1,490nm�A���1,310nm�ł���B�P�[�u���e���r�ǂł͕����ƒʐM��ʂɂ���2�c��p���邱�Ƃ��������A���̏ꍇ�ł��g���͓����ł���B
�����̐M���́A�d�g�Ɠ������ϒ��g�ł���A���̓_�͓����P�[�u���ł̓`���M���Ɠ����ł��邪�AFTTH�ł͓`�����g���ш悪2~3GHz�ƍL���ABS��110�xCS��IF�`�����\�ł���B�ʐM�̐M���́A�g1�h�g0�h�̃f�W�^���f�[�^�ł���B
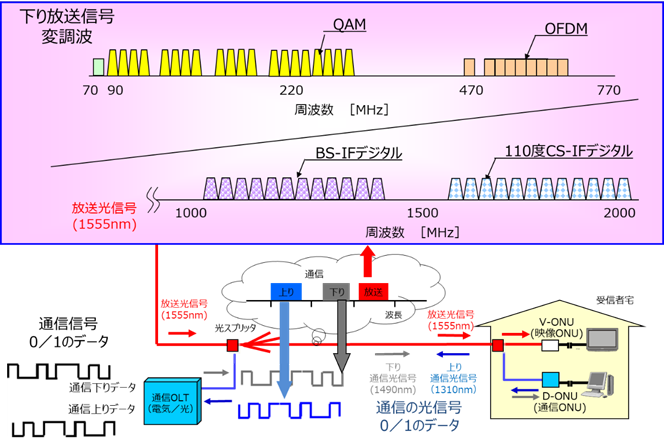
�} 2‑22�@FTTH�ɂ���������ƒʐM�̑��d��
���`�����\������@��́A�Ǔ����u�̒ʐMOLT�iOptical Line Terminal�j�ƁA������u��D-ONU�iData-Optical Network Unit�j�ł���B
�܂��A�����p�ɂ́A�Ǔ����u�Ƃ��ēd�C�E���ϊ����u�iRF���ϒ���j���A������u�Ƃ���V-ONU�iVideo-Optical Network Unit�j������B���`���͂����@���PON�iPassive Optical Network�j�����̓`���Z�p���g���čs����i�} 2‑22�Q�Ɓj�B
OLT����ONU�ւ̉�������ʐM�ɂ́ATDM�iTime Division Multiplexing�F���������d���j�Z�p���p������BTDM�͕�����ONU�ւ̐M�����A���ԓI�ɏd�Ȃ�Ȃ��悤�ɑ��d�����ē`������Z�p�ł���B����M���͌��X�v���b�^�ŕ��ꓯ���PON�Ɍq���邷�ׂĂ�ONU�ɓ����M�����]�������B���̂��ߊeONU�ւ͑���ONU���̃f�[�^���]�������B�eONU�͎��Ȉ��Ẵf�[�^�����𒊏o���A����ONU���f�[�^�͔p������B
ONU����OLT�ւ̏������ʐM�ɂ́ATDMA�iTime Division Multiple Access�F�����������ڑ��j�Z�p���p������B����ONU����̏��M�������X�v���b�^�ō��g����邽�߁A�eONU����̐M�����������ɑ��M���ꂽ�ꍇ�A�`���H��ŏՓ˂��N�����\��������BTDMA��ONU�̃f�[�^���M�^�C�~���O�Ƒ��M�ʂ𐧌䂵���M���̏Փ˂�������鑽�d���Z�p�ł���i�} 2‑24�Q�Ɓj�B
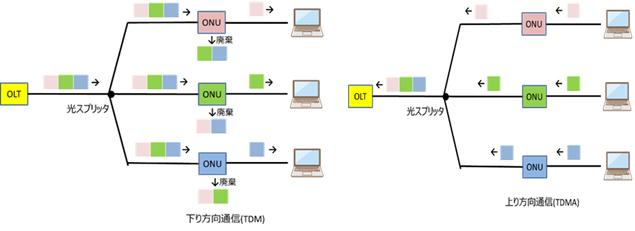
�} 2‑23�@PON�ɂ��o�����ʐM
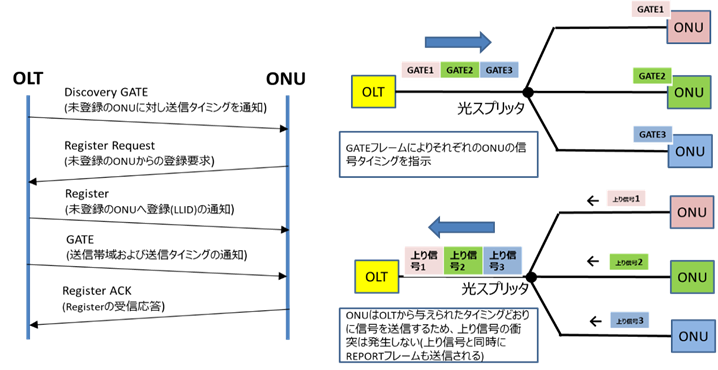
�} 2‑24�@���M���Փˉ��
E-PON�iEthernet-PON�j�ł́AONU��PON�ɐڑ�������OLT�͂���ONU�������I�ɔ������AONU��LLID�iLogical Link ID�j��t�^���ĒʐM�����N�������I�Ɋm������B���̋@�\��P2MP�f�B�X�J�o���ƌĂԁBP2MP�f�B�X�J�o�����ɁAOLT�͊Y��ONU�Ƃ̊Ԃ�RTT�iRound Trip Time�F�t���[���������ԁj������s���A�܂�ONU��OLT�Ƃ̎����������s���BRTT���肨��ю��������͂��̌������I�ɍs���A���H�����̕ω��Ȃǂɂ��Y�����������ꍇ�ɂ͐���������B
�Ȃ��A�V�X�e�����ł���20km�ȓ���ONU�����݂��邽�߁A����20km�̌����B���Ԃ͌��t�@�C�o���̔g���Z�k���ɂ���Ė�0.1ms�ɂȂ�A���̉������Ԃ���RTT��0.2ms���x�ȉ��Ɛ��������B
������ONU����̏��M�������X�v���b�^�ō������Փ˂��Ȃ��悤��E-PON�ł�OLT���i�ߓ��̖����߁A�eONU�ɑ��đ��M����ʒm����B����ɂ��eONU����̏��M�������ԓI�ɕ������Փ˂��������B�i�} 2‑24�Q�Ɓj
���M���̒ʒm�́A��̓I�ɂ́uGATE�v�ƌĂ�鐧��t���[����OLT����eONU�֑��邱�Ƃɂ���������BGATE�t���[���ɂ́A����ONU�ɑ��鑗�M�J�n�����Ƒ��M�ʁi���̎��_����ǂꂾ���̏��M���𑗂��Ă悢�Ƃ������j�����e����Ă���ONU�͂��̎w���ɂ��������ď��M���̑��M���s���B
�Ȃ��AIEEE802.3ah�ł͊eONU�ւ̏��M�����M�����@�͋K�肳��Ă��邪�A�eONU�ւ̑ш�̊����i���M�J�n�����Ƒ��M�p�����Ԃ̌v�Z�j���@�ɂ��Ă͋K�肳��Ă��Ȃ��B
2.2.2�@ ���`���̍��x��
PON�̒ʐM�����͕W��������Ă���A����܂ŁAITU-T�ɂ��G-PON�iGigabit PON�j��IEEE�ɂ��E-PON�iEthernet PON�j�̕W�������i�߂��Ă������A�����ɉ����V���Ȓc��(25GS-PON MSA, �č�CableLabs, Open XR optics Forum)�ł��W�������s����悤�ɂȂ����B
ITU-T�͍��ۓd�C�ʐM�A���̒ʐM����̕W�������肷��@�ւł���BIEEE�ithe Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.�j�͓d�C�H�w�E�d�q�H�w�Z�p�̊w��ł���AIEEE802.3��ŃC�[�T�l�b�g�i���`�����܂ށj�̕W�������肵���B25GS-PON MSA(Multi-Source Agreement)�́AITU-T���W��������������25Gbps�̋K�i�����肷�邽�߂ɑn�݂��ꂽ�c�̂ł���BOpen XR optics Forum�ƕč� CableLabs �̓R�q�[�����gPON�̕W�������s���Ă���B
���`���K�i�̐i�����} 2‑25�Ɏ����B
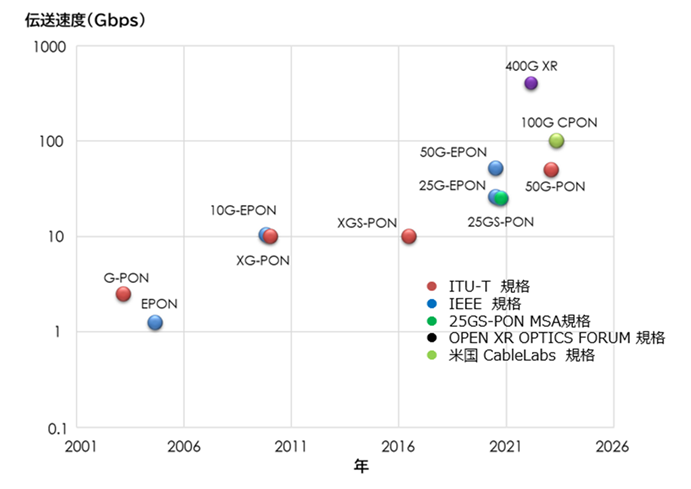
�} 2‑25�@���`���K�i�̐i��
2.2.2.1�@ ITU�W��G-PON��IEEE�W��E-PON
G-PON�́AG-PON�ȑO��B-PON�iBroadband PON�j�Ƃ̐�������ۂ��������������̂ł���A���܂ł̒ʐM�̊�{�ł���d�b�ԂƂ̐���������8kHz�œ��������Ă���B�܂��A�ϒ�GEM�iG-PON Encapsulation Method�j�t���[����ATM�Z�����܂Ƃ߂�GTC�iG-PON Transmission Convergence�j�t���[���i125��s�F8kHz�Œ�j�ō\������A�d�b�A�f�[�^�A��p���Ȃǂ̒ʐM�T�[�r�X�����e���邱�Ƃ��ł���B
E-PON�́A���܂ł̓d�b�ԂƂ̐��������IP�ԂƂ̐��������Ƃ�A�C�[�T�l�b�g�iEthernet�j�t���[���̂܂܂œ`������B���݂͍��������ꂽGE-PON�iGigabit Ethernet-PON�j�����p����Ă���B
���`���K�iG-PON��GE-PON�Ȃ�тɂ��̍������ł���10G-EPON��XG-PON�̓`���t���[���Ȃǂ̊T�v��\ 2‑8�Ɏ����B�X��10Gbps���̕W�����T�v��\ 2‑9�Ɏ����B
�\ 2‑8�@G-PON��E-PON�̊T�v
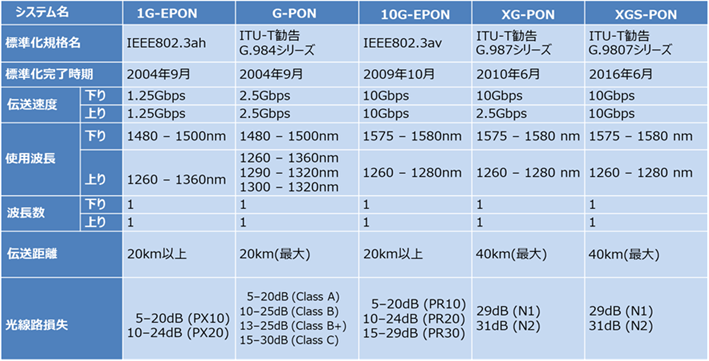
����AIEEE�ł́A2004�N��1G-EPON�iIEEE802.3ah�A����1Gbps�^���1Gbps�j�A2009�N��10G-EPON�iIEEE802.3av�A����10Gbps�^���10Gbps�j���W�������ꂽ�B�܂��A2020�N��25G-EPON(IEEE802.3ca�A����25Gbps�^���25Gbps)��50G-EPON�iIEEE802.3ca�A����50Gbps�^���50Gbps�j���W�������ꂽ�B
�\ 2‑9�@Over10G PON�̕W�����T�v
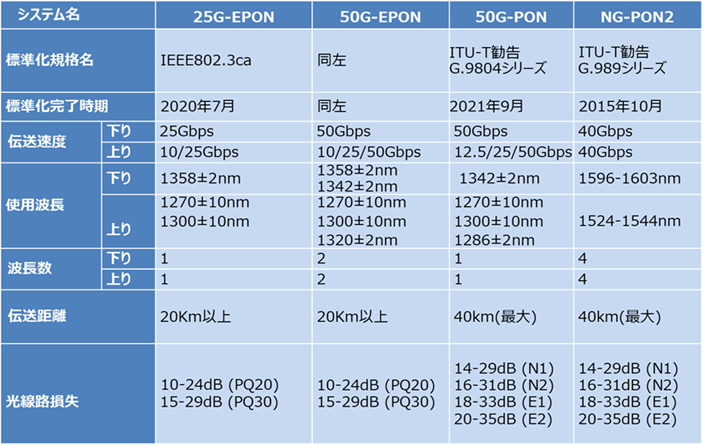
�`�����x�ɂ��āAE-PON�ł́A�����x�ϒ��œ`���\�Ȃ悤�ɃC�[�T�l�b�g�t���[���̒��������i�g1�h�Ɓg0�h�����p�x�Ɉˑ��j��ጸ����8-10�ϊ���p�����B���̂��߁A���`�����x�͋K�i�i����1.25Gbps/���1.25Gbps�j��0.8�{�i����1Gbps/���1Gbps�j�ƂȂ��Ă���BG-PON�̓`�����x�́A����/���̑g�����i����/���F1244.16Mbps/155.52Mbps�A1244.16Mbps/622.08Mbps�A1244.16Mbps/1244.16Mbps�A2488.32Mbps/155.52Mbps�A2488.32Mbps/622.08Mbps�A2488.32Mbps/1244.16Mbps�A2488.32Mbps/2488.32Mbps�j�ƂȂ��Ă���i�Q�ƁFTable 1/G.984.2 – Relation between parameter categories and tables�j�B������GEM�t���[����GTC�t���[���̃w�b�_�[�����̃��X�͊܂܂Ȃ��������x���L�ڂ��Ă��邪�ACTC�_�E���X�g���[��38880Byte�ŁAGTC�t���[���w�b�_�[�iONU���ʼnρFONU��64�Ɖ���j548Byte��CEM�t���[���w�b�_�[5Byte���l�����Ă��A�e�t���[���w�b�_�[�͖�1.4%�ł���B�܂��AG-PON�̓C�[�T�l�b�g�A���O�����ATM�iAsynchronous Transfer Mode�j�Ԃ��p�������p�ł���ȂǑ����̋@�\��L���Ă���B
���̂悤��G-PON�̓C�[�T�l�b�g�t���[���̂܂܂œ`������E-PON�Ɣ�r����ƁA�ʐM���x�E�������E���Ƃ��ɗD��AE-PON�Ɠ���2004�N�ɕW��������Ă���ɂ�������炸�A�����̒ʐM���Ǝ҂ɂ͍̗p����Ȃ������B���̗��R�Ƃ��āA��L�̂悤�ȋ@�\�̑�������J�����Ԃ��������Ƃ�A���i�������ƂȂ�Ɨ\������h�����ꂽ�ƌ�����B
2.2.2.2�@ PON�̌��g���ɂ���
���t�@�C�o�̌��g���́A�`���������ጸ�ł���悤�Z�p�J������A1980�N�ɖ�1300�`1700nm�Ł|0.5dB/km�ȉ����K�i������č����Ɏ����Ă���B���̓��A�ʐM�p�iPON�j�ɂ͏��1310nm�i1260�`1360�j�A����1490nm�i1480�`1500�j���A�����p�i����̂݁j�ɂ�1555nm�i1550�`1560�j�������Ă�ꂽ�B���ɁAONU�ɓ������锼���̃��[�U�ł́A���i�����\�ȃt�@�u���E�y���[�E���[�U�iFabry-Perot lasers�F�t�@�u���E�y���[���U��i���ˋ��̊ԁj�ɕ����߂��Ĕ������錴���j�������̔g���Ŕ�������Ƃ����������l���A1260�`1360 nm�ƍL���g���̈悪�ݒ肳�ꂽ�B
���̌�A�������iG-PON��10Gbps�j�����ɍۂ��āA�uEnhancement band�v���lj��K�肳�ꂽ�B����ɂ��A��L��1260�`1360nm��Regular�Ƃ��ADFB lasers�iDistributed Feedback lasers�F���z�A�Ҍ^���[�U�F�����̃��[�U���\������N�^��P�^�����̂̂���N�^�����̂̉�܊i�q�ɂ���ĒP��g���݂̂��������錴���j��ΏۂƂ���Reduce�g���i1290�`1330nm�j��CWDM���̔g���I�����[�U��Ώۂɂ���Narrow�g���i1300�`1320nm�j�������Ă�ꂽ�B���̌��ʁA1Gbps��G-PON�ŏ���DFB laser���g�p����A10Gbps��XG-PON�ŏ��g����1270nm�i1260�`1280�j���g���ē`�����邱�Ƃ��ł��AOLT���ł�G-PON Reduce�g����XG-PON�ŏ��g���Ƃ�WDM�t�B���^�ŕ����ł��邱�ƂƂȂ����BE-PON��Fabry-Perot laser���g�p����G-PON�ł�1260�`1360nm�Ɠ����g���ш���g���\�������邽�߁AOLT����̎w����ONU�̏�蔭�������ԕ������䂷��TDM���K�v�ƂȂ�B
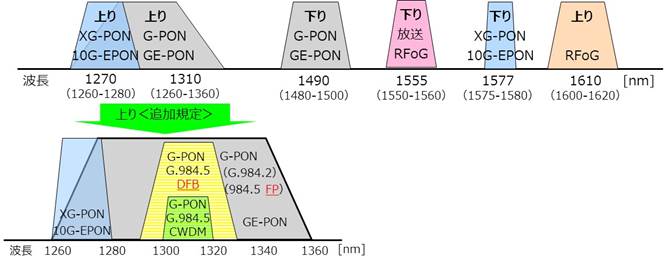
�} 2‑26�@G-PON��E-PON�̌��g��
2.2.2.3�@ PON�@��̑��ݐڑ����ɂ���
��L�̂Ƃ���PON�̒ʐM�����́A�`���t���[���`���Ȃǂ̃f�[�^�����N�w�ƌ��g���̕����w�Ȃǂ̕W�������i�߂��e�퐻�i�����p����Ă������A�@��\�����菇�Ȃǂ̎d�g�݂����߂Ă����ʑw�̕W�������ڍׂɂ͍s���Ă��Ȃ��������߁A���А��i�Ƃ̑��ݐڑ����ł��Ă��Ȃ��B������������ׂ��AITU-T��IEEE�ł���Ȃ�W���������Ƒ��ݐڑ��������i�߂��Ă���B���̗����\ 2‑10�Ɏ����B
�\ 2‑10�@ PON�W��������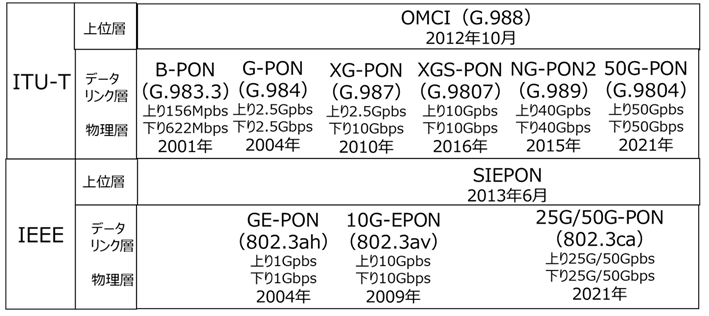 �@
�@
G-PON�ł́AG.984.4�ŁAOLT��ONU�̓�����Ǘ����䂷�邽�߂̃C���^�t�F�[�X���K�肳��Ă͂������A�v�Ɏg���郌�x���ŊǗ�����菇�Ȃǂ��ׂ����K�肵���K�C�h���C��G.Imp.984.4�iImplementer�fs Guide for ITU-T Rec. G.984.4�j�����肳�ꂽ���Ƃɂ�葊�ݐڑ����\�ƂȂ����B�܂��AG-PON��XG-PON�̗��W����ΏۂƂ���G.988�iONU management and control interface (OMCI) specification�j�����肳��A���̗��W���̉ƒ�[���ł���ONU������\�ƂȂ����B�܂��A���̑��ݐڑ����̊m�F�̂��߂ɁABroadband Forum�iBBF�j�ő��ݐڑ��������s���Ă���ABBF�̃z�[���y�[�W�ɂ͂��̔F�v���O������A���ݐڑ��ł������i�iONU�j������Ă���BBBF�̐ڑ������͈ȉ��̎d�l���K�肳��Ă��邪�A���ݐڑ������d�l�Ɋ�Â��F��̎��т͂Ȃ��B
Ø �K���������d�l�iBBF.247 G-PON ONU Certified Products�j
ITU�W���d�l�ɑ���ONU�̓K������F�肷�鎎��
Ø ���ݐڑ������d�l�iTR.255 GPON Interoperability Test Plan�j
�قȂ�x���_��OLT-ONU�Ԃ̑��ݐڑ������m�F���鎎�����K��
GE-PON�ł́AIEEE��P1904.1 Working Group���ݒu����ASIEPON�iStandard for Service Interoperability in Ethernet Passive Optical Networks�j�ƌĂ��GE-PON�̑��ݐڑ����̂��߂̌������i�߂��A2013�N6���ɕč��ł̃P�[�u���e���r���p��ΏۂƂ���Package A�i�P�[�u���j�A���{��NTT�d�l����{�Ƃ���Package B�i���{�j�A�����s����ӎ�����Package C�i�����j���d�l�����ꂽ�B���݂�Package���ƂɔF�v���O�������������Ă���BPackage A���������Ă����č��ł́ADOCSIS�P�[�u�����f���^�p�̃o�b�N�I�t�B�X�̊e��T�[�o�Ȃǂ�PON�ł����p�ł���DPoE�iDOCSIS Provisioning of EPON�j���č��P�[�u�����{�Ŏd�l�����ꂽ�B���̐���R�}���h��Package A�Ɛ������Ă���B�����DPoG�iDOCSIS Provisioning of GPON�j���d�l�����ꂽ�BDPoE�́A�e��@�킪�F����āA�č��P�[�u�����{�̃z�[���y�[�W�Ō��\����Ă���B�܂��APackage B�i���{�j�́ANTT�𒆐S�Ƃ����ʎВc�@�l���ʐM�l�b�g���[�N�Y�Ƌ���iCIAJ�j�������ǂƂȂ��ĕ������[�J�[��10G-EPON�@��̑��ݐڑ�������i�߂Ă���B
���{�P�[�u�����{�ł́A�كx���_��OLT-ONU�Ԃ̑��ݐڑ����������邽�߁A�����̃P�[�u�����ƎҌ�����E-PON���ݐڑ��^�p�d�l�iJLabs SPEC-027 1.1�Łj�����肵���i�} 2‑27�j�B�܂����d�l�ɑΉ������F�莎�����A2017�N8�����J�n�����B
PON���ݐڑ��̊K�w�ł���A�����w�ƃf�[�^�����N�w�ɂ��ẮAIEEE 802.3ah�AIEEE 802.3av�̋K�����������B��ʑw�ł���^�p/�Ǘ�/�����e�i���X�w�ł�DPoE/SIEPON Package A���瑊�ݐڑ��ɕK�v�ȃR�}���h���K�肵�Ă���B
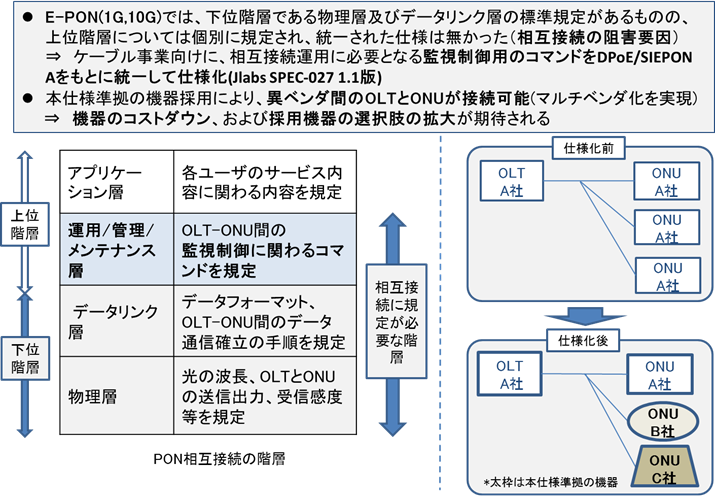
�} 2‑27�@E-PON���ݐڑ��^�p�d�l
�܂��AG-PON�ɂ��Ă����ݐڑ��^�p�d�l�ɂ��Č������s�����B
G-PON�����ʊK�w�ɂ͍��ەW��������A�����@��Ԃ̐ڑ����͍����������̃��[�����͕K�v�ł���B��ʊK�w�ɂ����ʋK�i�͂��邪�A�ʂ̍��ڂ̗̍p�ۂ̓x���_�̎d�l�ɂ�邽�߁A���ݐڑ��͎��Ǝ҂̗v�]�ɂ��A���Ǝ҂ƃx���_���������ČʂɑΉ����Ă����B�]���āA��ʊK�w�̓��A�^�p/�Ǘ�/�����e�i���X�w�̕K�v�ȊĎ�����p�R�}���h�ꂷ�邱�Ƃ��L�v�ł���B
G-PON���ݐڑ��̊K�w�ł���A�����w��TC�w�ɂ��ẮAG.984�A G.987�A G.9807�A G.989�̋K�����������B��ʑw�ł���^�p/�Ǘ�/�����e�i���X�w�ł�OMCI�iG.988�j���瑊�ݐڑ��ɕK�v�ȃR�}���h���K�肷��BE-PON���ݐڑ��d�l�Ƃ̑傫�ȑ���̓��C��3�Ɋւ���Ď��@�\���lj�����Ă��邱�Ƃł���B�Ȃ�G-PON���ݐڑ��^�p�d�l�iJLabs SPEC-036 1.0�Łj��2017�N12��21���Ɋ������A�F���t��2018�N1�����J�n�����B
2.2.2.4�@ GE-PON��10G-EPON�̍��݉^�p
EPON��1G��10G�̍��݉^�p�̂��߂̃C���[�W��} 2‑28�Ɏ����B���[�U1��1Gbps�̑o�����ʐM�A���[�U2��10Gbps�̑o�����ʐM�A���[�U3�͏��1Gbps�A����10Gbps�Ƃ��Ă���B�w�b�h�G���h�ɂ͏��1Gbps�Ɖ���10Gbps�̐M���𐧌䂷��OLT�������āA����͕ʔg���i1Gbps��1490nm�A10Gbps��1577nm�j�Ń��[�U���ONU�ցA����1Gbps��10Gbps�Ƃ������g���ƂȂ邽�߃��[�U1����3�̏��M����ʂ̎��ԂŊ��蓖�Ă鎞����������s���B���̎���������͓������l�b�g���[�N���[�U���X�v���b�^�j�ɐڑ����Ă��郆���[�U��Ɠ����ł���B
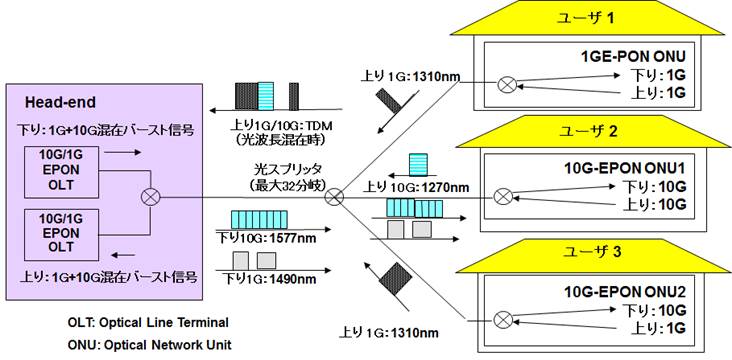
�} 2‑28�@GE-PON��10GE-PON�̍��݉^�p
2.2.2.5�@ ����Ȃ鍂�����ɂ���
NG-PON1�iNext Generation-PON 1�j��GE-PON�Ƃ̋����i���X�v���b�^���x�[�X�Ƃ��������l�b�g���[�N�p����j��v�������Ƃ��Č�������AXG-PON�iITU-T G.987�j�ƂȂ��Ă���B
����Ȃ鍂�����i40Gbps���x�j��ڎw��NG-PON2�iNext Generation-PON 2�j�ł́A���������Ƃ̋�����v�������Ƃ����V�Z�p�𗘗p����B2014�N12��ITU-T G989.2��TWDM-PON�iTime and Wavelength Division Multiplex - PON�j��PtP WDM-PON�iPoint-to-Point Wavelength Division Multiplexing – PON�j��2�������K�肳�ꂽ�B
TWDM-PON�iTime and Wavelength Division Multiplex - PON�j�̌��g���̈�́A��肪1500-1550nm�A���肪1580-1600nm�ŁA�e�g����10Gbps��4�g�������Ă�i�} 2‑29�Q�Ɓj�B
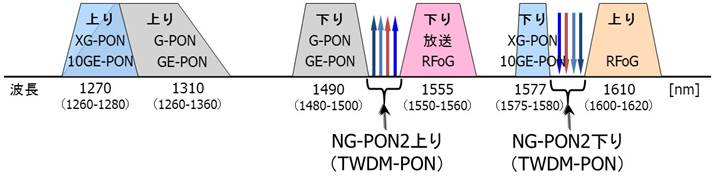
�} 2‑29�@����Ȃ鍂�����i40Gbps�jNG-PON2�̌��g��
���̌��`���ɂ����Ĕg�����d�`��������̔g���Ԋu�́ADWDM�ł͌����g�����ƂɋK�肳��Ă���A193.1[THz]�𒆐S��12.5GHz�A25.0GHz�A50.0GHz�A100GHz�E�E�E�Ԋu�̎��g���i1�A600nm�t�߂̔g���ł́A50GHz�Ԋu�͖�0.4nm�Ԋu�A100GHz�Ԋu�͖�0.85nm�Ԋu�A200GHz�Ԋu�͖�1.7nm�Ԋu�j�ł���BCWDM�ł͔g���𑽏d�E��������t�B���^�̒��S�g����20nm�Ԋu�ŋK�肳��Ă���B�Ȃ��ADWDM��ITU-T G.694.1�ŁACWDM��ITU-T G.694.2�ŋK�肳��Ă���B
2.2.3�@ ���`���ւ̃}�C�O���[�V����
2020�`30�N�ɂ͓����P�[�u���ł̒ʐM���x�����E�ɒB���A�ʐM�T�[�r�X��HFC��DOCSIS����FTTH��PON�Ɉڍs����ƌ����Ă��邪�A�����i�K�I�ɍs�����߂ɗL���ȕ����Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�@HFC���x���i������HFC�Ƃ��Ă�鏬�Z�����E1GHz���x�ւ̑ш�g��j
�A�@RF�{PON�i�ʐM�T�[�r�X�����P�[�u����GE-PON�ɐ�ւ���j
�B�@RFoG�i�`���l�b�g���[�N�݂̂���������j
�C�@PON��HFC�̍��݁i����j�^�p
������g�ݍ��킹�ē`���ݔ��̓����������邱�Ƃ��\�ł���B
���̂ق��č��ł́ADPoE�iDOCSIS Provisioning of EPON�j���d�l������Ă��邪�A�����ł͇@�`�C���ꂼ��̕����ɂ��Đ�������B
2.2.3.1�@ HFC���x��
HFC���x����DOCSIS3.1���厲�Ƃ�����̂ł���B�iDOCSIS�̋L�q�Q�Ɓj
�} 2‑30�̂Ƃ���AHFC���x�������̐ݔ��\�z�ɂ́A�ʐM�p�ǐݔ���CMTS����щƒ�[����CM���A����DOCSIS��3.0����3.1�ɕύX����K�v������B
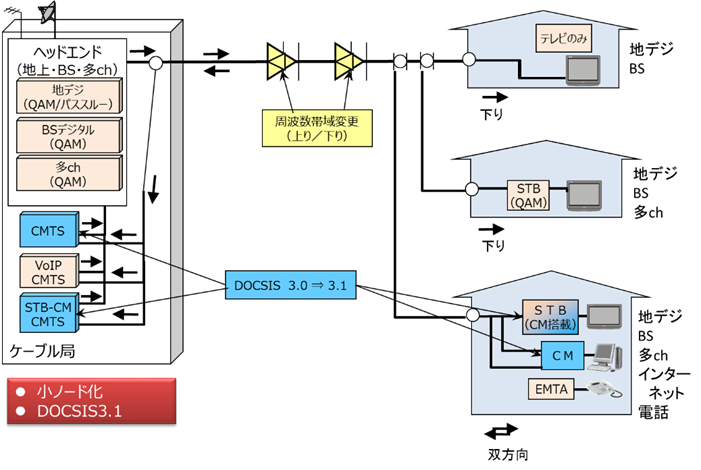
�} 2‑30�@HFC���x�������iDOCSIS 3.1�j
2.2.3.2�@ RF�{PON
RF�{PON�V�X�e�����} 2‑31�Ɏ����悤�ɁA���t�@�C�o�P�[�u����V���ɕ~�݂��ADOCSIS�̃Z���^�[�ݔ������[���ݔ��͎g�킸�ɁAGE-PON�ɂ��ʐM�T�[�r�X���s�������ł���B�ʐM�T�[�r�X�ɂ́A����M���Ɍ��g��1490nm���A���M���Ɍ��g��1310nm��p���A�ǂɐݒu�����OLT�Ɖƒ�ɐݒu�����ONU�Ƃ̊Ԃł́AEthernet�t���[���`���̐M����ONU����Ȃǂ̏���t�����A���̋���ŒʐM����B�������AHFC�l�b�g���[�N�ł���܂Ŏg�p���Ă�������[���iCM����STB�ACM�AEMTA�j�����p�ł��Ȃ��Ȃ�B
�����T�[�r�X�i����M���j�ɂ͌��g��1555nm��p����B���`���̎��g���ш悪�L�����Ƃ���BS-IF�M���̃p�X�X���[�ɂ��ĕ������\�ł���B�f���͍��܂łǂ���W���Z����̓����P�[�u�����g����B
RF�{PON�����iFTTH�j�̒lj��ݔ��Ƃ��ẮA�ǐݔ��̒ʐM�pOLT�ƕ����p�����M�@�EFTTH�`���H�i���t�@�C�o�j�E�ƒ�p�̒ʐM�pD-ONU�ƕ����pV-ONU��lj�����K�v������B
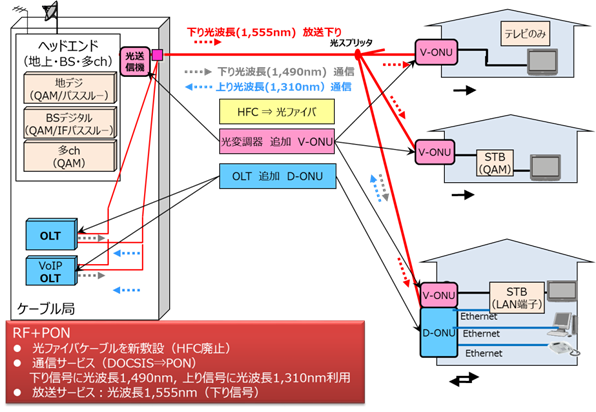
�} 2‑31�@RF�{PON�V�X�e��
2.2.3.3�@ RFoG
RFoG�V�X�e���́A���t�@�C�o�P�[�u����V���ɕ~�݂��邪�ADOCSIS�̃Z���^�[�ݔ������[���ݔ������̂܂܊��p����B���������ĒʐM�ݔ��̓�����������FTTH����i�߂邱�Ƃ��ł����߁ARF�{PON�V�X�e���ւ̈�̈ڍs��i�ƈʒu�t���邱�Ƃ��ł���B
�������A�ʐM�T�[�r�X�̍���̍��������v�ɑΉ�����ɂ́A�o������100Mbps���邢�͂���ȏ�̓`�����x���K�v�ł���A����ɂ�RFoG�͓K���Ă��Ȃ��BPON�̒ʐM���ŏ����瓱������K�v������B
RFoG�V�X�e�����} 2‑32�Ɏ����悤�ɁA�����P�[�u���̉�����̐M�����e�X���Ɋ��蓖�Ă�B����M���ɂ͌��g��1555nm���A���M���ɂ͌��g��1610nm���g���B
RFoG�����i�`���HFTTH�j�ɕK�v�Ȑݔ��Ƃ��ẮA�ǐݔ��̌�����M�@�AFTTH�`���H�i���t�@�C�o�j�A�ƒ�[����R-ONU�ł��肷�ׂĒlj�����K�v������B
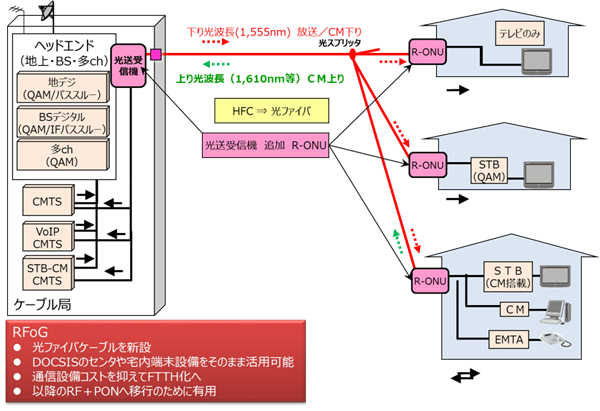
�} 2‑32�@RFoG�V�X�e��
2.2.3.4�@ HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h
HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h�V�X�e���́A�����T�[�r�X��HFC�ŁA�ʐM�T�[�r�X��FTTH�iPON�j�Œ���V�X�e���ł���B
�Ȃ��AHFC�̓����A���v�ւ̋��d�@�\���c�邱�Ƃɕt�����ăP�[�u��Wi-Fi�̉��O�A�N�Z�X�|�C���g�ւ̋��d�@�\���c�邱�ƂɂȂ�B
HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h�V�X�e����} 2‑33�Ɏ����B
HFC�{PON�i�f���A���t�B�[�h�j�����ɕK�v�Ȑݔ��́A�����p�ɂ͊����̃w�b�h�G���h�ݔ��AHFC�`���H����щƒ���̃e���r�ł���lj���v���Ȃ����A�ʐM�p�ɂ͋Ǒ���OLT�AFTTH�`���H�i���t�@�C�o�j�A�ƒ�[����D-ONU�ł��肷�ׂĒlj�����K�v������B
PON�ɂ���ĒʐM����������������ł��邽�߁A�o����STB��CM�����^����LAN�[�q�Ή��^�ɕύX����K�v������B�������A������DOCSIS�ɂ��o����STB�ւ̒��p������ꍇ�ɂ́A�o����STB�̕ύX�͕K�v�Ƃ��Ȃ��B
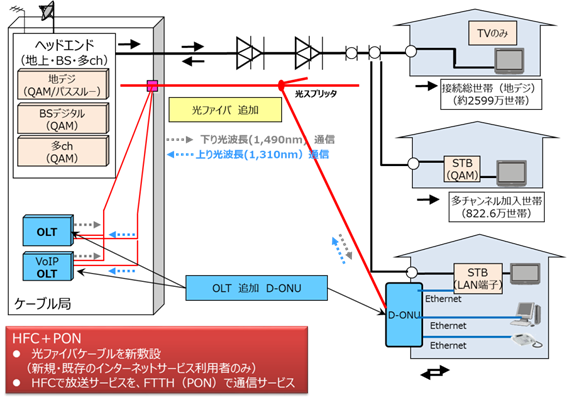
�} 2‑33�@HFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h
�f���A���t�B�[�h�����́AHFC�̍��x���i���Z�����j�p����ꍇ�ƕ��p���Ȃ��ꍇ�ƂňႢ������̂ŁA���ꂼ���} 2‑34����ѐ} 2‑35�Ɏ����B
���Z�����p�����ꍇ�ɂ́A���m�[�h��OLT������Ȃǂ��Ē���ݒu���\�ɂȂ�AOLT�����e���邽�߂̃T�u�Z���^�������炷���Ƃ��ł���B�܂��AOLT-ONU�Ԃ̋������Z���Ȃ���t�@�C�o�ɂ�鑹��������i���g��1,310nm�ɂ�����10km�Ŗ�5dB�j�B�������AOLT�̒���ݒu�ɂ��Ă͓d�����ˏ����ɂ��B
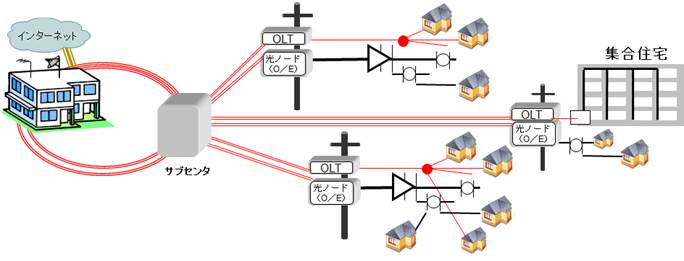
�} 2‑34�@���Z�������p�̃f���A���t�B�[�h
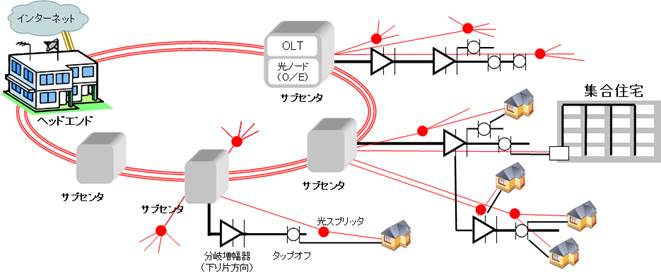
�} 2‑35�@���Z�������p�̂Ȃ��f���A���t�B�[�h
2.2.3.5�@ HFC����FTTH�ւ̍��x�������̑I��
HFC�ARFoG�AHFC�EFTTH�f���A���t�B�[�h�ȂǁAHFC����FTTH�ւ̍��x�������̑I���ɍۂ��l�����ׂ��v�_��\ 2‑11�Ɏ����B
�\ 2‑11�@HFC����FTTH�ւ̍��x�������̑I��
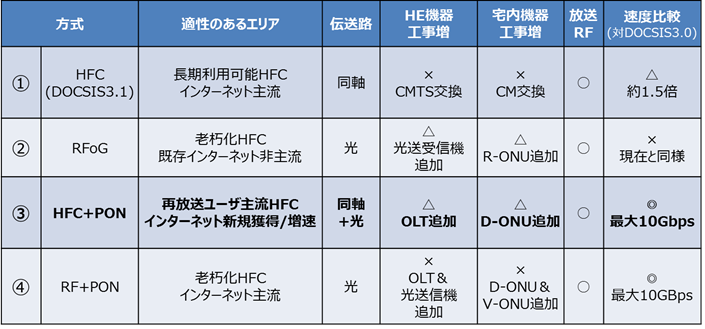
![]()
��\�̓K���̂���G���A�Ɋւ��⑫����B
�@ HFC�����iDOCSIS 3.1�j�͊����̕����iRF�j�ɍ��킹�ĒʐM��DOCSIS 3.1�ɍ��x����������ł���ADOCSIS�̋ǐݔ�CMTS�Ɗe�ƒ���ɂ���CM�̌������K�v�ł���B�ʐM�̍��������}��邽�߁A�������p�\��HFC�n�悩�C���^�[�l�b�g���嗬�̒n��ɂ����ēK����L����B
�A RFoG�����i�`���HFTTH�j�͓`���H�݂̂�FTTH����������ł���A�����̕����iRF�j�ƒʐM��DOCSIS�͂��̂܂܂Ƃ��A�ǐݔ��̖��[�iFTTH�`���H�̋��E�j�Ɍ�����M�@���A�e�ƒ�[�iFTTH�`���H�̋��E�j��R-ONU��lj�����݂̂ł���̂ŒʐM�̍������͐}��Ȃ��B�V��������HFC�n��ł��C���^�[�l�b�g���嗬�ł͂Ȃ��n��ɂ����ēK����L����B
�B HFC�{PON�i�f���A���t�B�[�h�j�����͕�����������HFC�Œ��ʐM��PON�iFTTH�j�ŐV�K�\�z��������ł���A�ǐݔ���OLT���A�`���H��FTTH���A�e�ƒ�[�iFTTH�`���H�̋��E�j��D-ONU��lj�����K�v������BPON�ɂ��ʐM�̍��������}��邽�߁A�ĕ������[�U���嗬��HFC�n��ł����ĐV�K�C���^�[�l�b�g���[�U�̊l�����邢�̓C���^�[�l�b�g������]�̍����n��ɂ����ēK����L����B
�C RF�{PON�����iFTTH�j�͈�ʓI��FTTH�����ł���A�ǐݔ���OLT�ƕ����p�����M�@���A�`���H��FTTH���A�e�ƒ�[�iFTTH�`���H�̋��E�j��D-ONU��V-ONU��lj�����BPON�ɂ��ʐM�̍������ƕ����iRF�j�̒��}��邽�߁A�V��������HFC�n��ł��C���^�[�l�b�g���嗬�̒n��ɂ����ēK����L����B
2.3�@ �W���Z��ɂ����铏���`���Z�p
2.3.1�@ �����P�[�u�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p
��ˌ��ďZ��ɂ��ẮAHFC�`���H�̑ш�g����PON���ɂ��1Gbps�̍���������������悤�Ƃ��Ă��邪�A�W���Z��̒ʐM�������ɂ��Ă͌��ߎ�ƂȂ��@���Ȃ��A���ꂪ�W���Z��䗦�̍����n��ɂ����������x�点��v���ƂȂ��Ă����B
�P�[�u���`���H�̒ʐM���x�̍������̂��߂ɂ��AHFC�`���H�ł́A������DOCSIS 3.0��ϒ��E�������Z�p�����x������DOCSIS 3.1������AFTTH�`���H�ł�ITU-T�W����G-PON��IEEE�W����E-PON�����邱�Ƃ͐�q�̂Ƃ���ł���B
FTTH�ɂ��`���H�̍������́A�W���Z����ɂ����Ă���Ɍ��������������������邱�Ƃ����z�ł���A���̂��߂ɂ͊e�ƒ�܂Ō��t�@�C�o�Œ��ڐڑ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�����̏W���Z����ɂ͓����P�[�u�����z������Ă��錻����A���݂̔z�Ǔ�����Ċe�˂܂Ō��t�@�C�o��z������͍̂���ł���B�܂��A�W���Z����ł̓c�C�X�g�y�A�P�[�u���i�d�b���j�̗��p���\�����A�P�[�u�����Ǝ҂�����e����ł��铯���P�[�u���ɂ�鍂�����̉\��������A�����L�����p���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B���܂ł̋Z�p�ŁA�W���Z����̔z���ɂ��̗p�ł���W���Z����̒ʐM�Z�p��r��
�\ 2‑12�Ɏ����B
�Ȃ��������̗��R�œ����P�[�u���𗘗p�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�d�b���ɂ�鍂���ȓ����ʐM���������p�\�ł���B
�\ 2‑12 �@�W���Z����̍ݗ��ʐM�Z�p��r
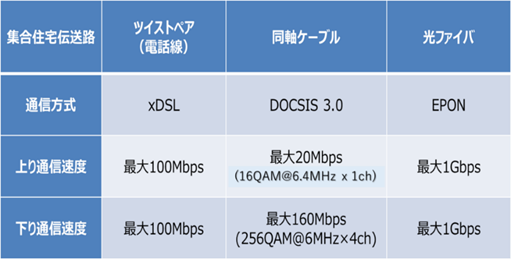
���܂ł̓����P�[�u���𗘗p����DOCSIS 3.0�́A�����`���A�o�����`���A����`���A���������P�[�u���𗬗p�\�Ȃǂ̗��_�͂��邪�A�ш�̊m�ہi���ɏ��ш�̊m�ہj����/���葬�x�̋ϓ����ɓ�_������B
�����ŁA�Ώۂ̏W���Z����ł�HFC���ɂ��o����������Ă���O��ŁA�܂��A�W���Z��܂ł�PON���p���Ȃǂœ`�����邱�ƁA�W���Z��ŏ��/����M�����I�[�i��藬���G�����팸�j���邱�ƁA��������M���ȊO�̐M���͂Ȃ����ƁA���ш�͑S�ш�W���Z����ŗ��p�\�ł��邱�Ƃ�O��ɁADOCSIS 3.0�ADOCSIS 3.1�AC-DOCSIS���p��EoC�iEthernet over Coax�A�����P�[�u�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p�j�ȂǏW���Z������Z�p�ɂ��Ă��̓K�ۂ�����������������B
���̌��ʁAC-DOCSIS���p��EoC�͊����[���i�P�[�u�����f���j�����p�\�ł��邱�Ƃ�A����ш�i���10�`55MHz/����70�`770MHz�j�ł��A���100Mbps�i64QAM�~4ch@6.4MHz�j�A����300Mbps�i256QAM�~8ch@6MHz�j���\�ł��邱�Ƃ͕��������B�ڍׂ��ȉ��ɐ�������B
2.3.1.1�@ C-DOCSIS
EoC�́A�L�`�ɂ�Ethernet�M�����P�[�u�����ɓ`������Z�p���Ӗ����A�d�͐����p��HP AV��d�b�����p��Home PNA������̔h���Z�p������Ɋ܂܂�邪�A�{�߂ł͏�艺��̎��g���ш���Ďg�p���A�P�[�u���e���r�Ƃ̐e�a��������C-DOCSIS�ɂ��ďq�ׂ�B
C-DOCSIS�́A2014�N8��29����C-DOCSIS System Specification�gcm�|SP�|CDOCSIS- I01-140829�h�Ƃ��ĕč��P�[�u�����{�ɂ�菉�ł����J���ꂽ�B���̌�A��2�ŁiI02�j��2015�N3��5���Ɍ��J����Ă���B�܂��ADOCSIS 3.0 Operations Support System Interface Specification�iCM-SP-OSSIv3.0�j�̍ŐV�ŁiI25�j���������s����AAnnex S Additions and Modifications for Chinese Specification���lj�����Ă���B
C-DOCSIS�́gChina DOCSIS�h��gCabinet DOCSIS�h�Ƃ��Ă�A�W���Z��̒ʐM�������̂��߁A�W���Z���MDF�����ɐݒu����CMTS�ƁA�����̓����P�[�u���o�R�Ŋe�ƒ�̃P�[�u�����f���Ƃ��ʐM���s�������ł���BCMTS�����^���������ɂ������̂�CMC�iCable Media Converter�j�ł���A�P�[�u���ǂɐݒu�����CMC�𐧌䂷�鑕�u��CMC�R���g���[���ƌĂԁB���̗��p����} 2‑36�Ɏ����B
C-DOCSIS�ł́A�P�[�u�����f���ƊǗ����u�i�v���r�W���j���O�j���͌��݂̂��̂����̂܂ܗ��p���Ȃ���A�W���Z��ɐV����CMC��ݒu�E�������邱�Ƃɂ�荂�������\�ƂȂ邽�߁A�^�p���S�����Ȃ��B�W���Z��̓��������łȂ����㓙�ɂ��ݒu�\�ȋ@�킪���i���i���FHuawei MA5633�j����Ă���B�����M���́A���ϒ��킩����t�@�C�o�ɂ���ē`�����A�W���Z����⒌��̑��u��CMC�o�͂�DOCSIS�M���ƍ������邱�Ƃ��\�ł���B
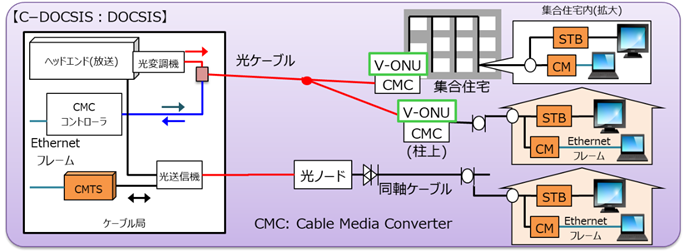
�} 2‑36�@C-DOCSIS�̗��p��
�����ɂ́ACMC�R���g���[����CMC�̋@�\���ǂ̂悤�ɕ��S�E�������邩�ɂ��AC-DOCSIS�ɂ͎���3��ނ�����B���̃A�[�L�e�N�`���̊T�O���} 2‑37�Ɏ����B
Type 1�iMini CMTS�j CMTS�̂قڂ��ׂĂ̋@�\�������[�g���ɒu���B
Type 2�iRemote MAC-PHY�j CMTS��MAC�w�ȉ��̋@�\�������[�g���ɒu���B
Type 3�iRemote PHY�j CMTS��PHY�w�̋@�\�݂̂������[�g���ɒu���B
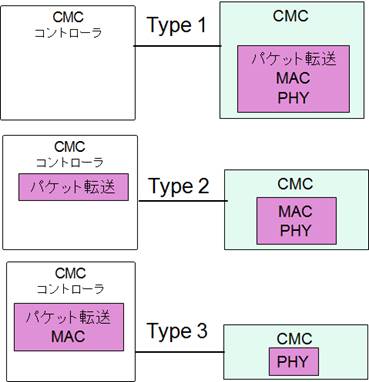
�} 2‑37�@C-DOCSIS��3��ނ̃A�[�L�e�N�`��
�����[�g����CMC�́AType 1���ł����G�ō����AType 3���ł��ȈՂň����ɂȂ邱�Ƃ��z�肳��邪�A�ێ�E�^�p���܂߂Ă̑������f���K�v�ł���B
2.3.1.2�@ C-DOCSIS�̃P�[�u���ǂł̎��؎���
���{�P�[�u�����{�̏W���Z��ʐM����������WG��CNCI�Ő��i����@�iHuawei MA5633�j��p����C-DOCSIS�̎��؎������s�����B�����œ���ꂽ�ʐM���x�̑��茋�ʂ��\ 2‑13�ɁA�����n���}���} 2‑38�Ɏ����B���̎����ł͏��65�`80Mbps�A����280�`360Mbps�������Ă���B
�\ 2‑13�@�W���Z��i���Z�҂Ȃ��A�������ȂǂƂ��ė��p�j�ł̒ʐM���x���茋��
|
|
�M������ |
���茋��:�ʐM���x |
|
���M�� |
SCDMA�F6.4MHz�~3�g�{3.2MHz�~1�g�@�S64QAM |
80Mbps |
|
ATDMA�F6.4MHz�~2�g�{3.2MHz�~2�g�@�S64QAM |
65Mbps |
|
|
����M�� |
8MHz�iAnnex A�j�~8�g�@�S256QAM |
360Mbps |
|
6MHz�iAnnex B�j�~8�g�@�S256QAM |
280Mbps |
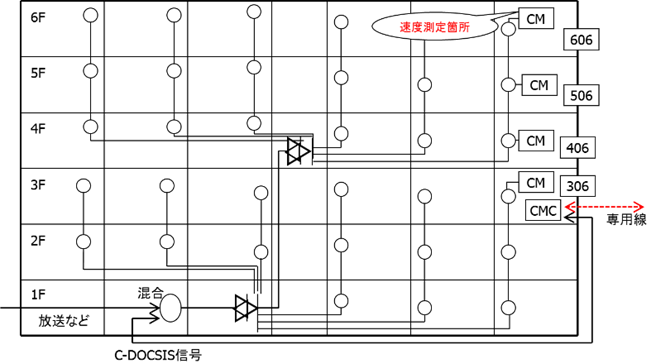
�} 2‑38�@�W���Z��i���Z�҂Ȃ��A�������ȂǂƂ��ė��p�j�ł̎������v�}
���p�����i�߂��Ă���C-DOCSIS�ȊO�ɂ��A�W���Z��ɂ�����`���ɂ͗��p�\�Ȍ�����������������̂ŁA�������Љ��B
2.3.1.3�@ Home PNA over Coax/G.hn
Home PNA�́A���X�͉ƒ���̓d�b�����𗘗p���郁�K�r�b�g�N���X�̓`�������Ƃ��ĊJ������A���̌�J�����ꂽG.hn���M�K�r�b�g�N���X�̑��x�ɑΉ����Ă���B�`���}�̂Ƃ��Ă͓����P�[�u�������p�\�ł���A�W���Z������\�����[�V�����Ƃ��Đ��i����������Ă���B
�{���ł͗������̊T�v����яW���Z������\�����[�V�����ɂ��ĉ������B
�@ Home PNA 3.1 over Coax
Home PNA�iHome Phoneline Networking Alliance�j�͉ƒ���̓d�b���𗘗p��������`���𐄐i����c�̂Ƃ��Đݗ�����A2001�N��ITU-T����G.989.1�����肳�ꂽ�i���̌�A2005�N��G.9951�ɉ��́j�B�����P�[�u���𗘗p�\�ȋZ�p�K�i��Home PNA 3.1 over Coax�ƌĂ�A2007�N1����ITU-T G.9954��v2�Ƃ��Ċ��������ꂽ�B�ϒ������Ƃ���QAM�������͒�V���{�����[�g�ł�FDQAM�iFrequency Diversity QAM�j���̗p���A�ő�`�����x320Mbps��������B
�\ 2‑14��Home PNA�̐i�W�A�܂��} 2‑39��Home PNA 3.1�iG.9951�j�̃X�y�N�g�����[�h�������B
�\ 2‑14�@Home PNA�̐i�W
|
�K�i |
ITU-T���� |
���莞�� |
�����w���x |
���l |
|
Home PNA 1.0 |
- |
1998�N |
1Mbps |
|
|
Home PNA 2.0 |
G.9951 |
2001.2 |
32Mbps |
������G.989.1 |
|
Home PNA 3.0 |
G.9954 |
2005.2 |
128Mbps |
|
|
Home PNA 3.1 |
G.9954 |
2007.1 |
320Mbps |
�����ɑΉ� |
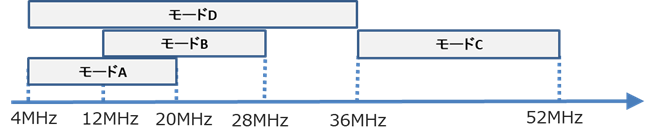
�} 2‑39�@Home PNA 3.1�iG.9954�j�̃X�y�N�g�����[�h
�A G.hn
G.hn�ihn: home network�j�́AHome PNA�̃M�K�r�b�g�ł̈ʒu�t���ŁA�������̓����P�[�u���A�d�b���A�d�͐��Ƃ���3�̊����z���𗘗p�ł��铝��I�ȓ`�������̊m����ړI�ɍ��肳�ꂽ�Z�p�d�l�iITU-T�����Q�j�̑��̂ł���B���̂��������w��ITU-T G.9960�iUnified high-speed wireline-based home networking transceivers - System architecture and physical layer specification�j�ɋK�肳��Ă���BG.hn�������w���x�͍ő�2Gbps���x�i200MHz�ш���g�p�����ꍇ�j�ł���A����d�ʐM�iTDD�j���s���B
G.hn�֘A��ITU-T�����Q�̈ꗗ���\ 2‑15�ɁA�܂��A�����P�[�u���𗘗p����ꍇ�̎g�p���g���͈́iTTC�W��JT9960�ɋK��j���} 2‑40�Ɏ����B
�Ȃ��A2009�N1���Ɋ��������ꂽG.9970�́A�z�[���l�b�g���[�N�̓`���T�O�iG.hnta: home network transport architecture�j���K�肷����̂ŁA���̑Ώۂ́AG.hn�݂̂Ȃ炸�AHome PNA 3.1�iG.9954�j�����HD-PLC�iIEEE 1901�j���܂ށB
�\ 2‑15�@G.hn�֘A�����Q
|
���� |
���C�� |
�������莞�� (�ŐV��) |
�K����e |
|
G.9970 |
�l�b�g���[�N�w |
2009.1 |
�z�[���l�b�g���[�N�`���T�O�K��(G.hnta) |
|
G.9961 |
�f�[�^�����N�w |
2015.7 |
�f�[�^�����N�w�K�� |
|
G.9962 |
2014.10 |
�Ǘ��K�� |
|
|
G.9960 |
�����w |
2015.7 |
�V�X�e���A�[�L�e�N�`���ƕ����w |
|
G.9964 |
2011.12 |
�X�y�N�g���Ǘ��K�� |
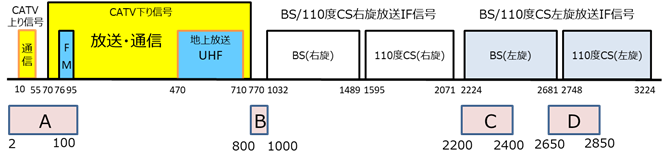
�} 2‑40�@G.hn�p���g���сiTTC�W��JT-9960�j
��L4�̑ш�iA�AB�AC�AD�j�̈ꕔ��BS-IF��`�����̖ړI�ŗ��p����Ă��邽�߁A�P�[�u���e���r�ŗ��p����ꍇ�ɂ́A���ꂼ��̋ǂɂ�������g�����p�ɍ��킹�Ċ����̃T�[�r�X�Ɗ����Ȃ����g����I������K�v������B
Home PNA 3.1�����G.hn���P�[�u����ŗ��p����ꍇ�̕����w�K��T�v���\ 2‑16�Ɏ����B
�\ 2‑16�@�����P�[�u����p����Home PNA 3.1�����G.hn�iITU-T G.9960�j
|
�K�荀�� |
Home PNA 3.1 (����) |
G.hn (����) |
|
���g���͈� |
4�`36MHz (���[�hD) (�}4-26�Q��) |
2�`100MHz�A���@�@(�}4-27�Q��) |
|
�ő�`�����x |
320Mbps (32MHz�A10bit/Symbol) |
1Gbps (100MHz�ш敝) 2Gbps (200MHz�ATDD) |
|
�ϒ����� |
FDQAM/QAM |
OFDM(QAM) |
|
������ |
CRC-8 |
LDPC-BC (Low Density Parity Check Code-Block Code) |
|
�ő�ڑ��䐔 |
|
32 (�I�v�V������250)�� |
�B Home PNA 3.1/G.hn�Ή����i�iHCNA�j
�W���Z����̊����̓����P�[�u���𗘗p����MDF�`�e�����ґ��ڑ����鐻�i�ŁAHome PNA 3.1 over Coax/G.hn�ɏ���������̂Ƃ���HNCA�ƌĂ�鐻�i������B�����i��C-6�ƌĂ�郂�f����Home PNA 3.1�����AC-7�AC-8��G.hn�����ł���B�\ 2‑17�ɍŐV��C-8�̐��i�d�l�������B
�\ 2‑17�@HCNA���i�d�l�iG.hn�����j
|
���i���f�� |
CEM-837(�e�@)�ACEM-831(�q�@) |
|
�q�@�ő�ڑ��䐔 |
30��ȉ� (����) |
|
���[�J |
SENDTEK(��p) |
|
�ϒ����� |
OFDM |
|
�g�p���g���� |
6-76MHz |
|
�`�����x |
1Gbps(���_�l)�A750MHz+(�����l) |
|
�o�͒l/���e���� |
6dBm / 70dB |
|
�ő�ڑ�MAC�� |
1024 |
|
�e�@�ڑ��|�[�g |
SFP x 1 & GbE x 2 |
|
�q�@�|�[�g(LAN��) |
GbE x 2 (�C���^�[�l�b�g�A�d�b) |
|
IP |
IPv4/IPv6 |
|
�d��(�e�@) |
12VDC�ALine Power�APoE |
|
DHCP Support |
Client�ARelay Option 82�ASnooping |
|
�F�ؕ��� |
PPPoE�ARADIUS�AEAP-TLS |
|
Auto Configuration |
�i�e�@�A�q�@�j |
�g�p���g���ш�̏����FM�ĕ����ш�Ƌߐڂ��邽�߁A�������g��̗��p���K�v�ƂȂ�BHCNA Master�@��͍������g���������Ă���AV-ONU�̏o�͂��hTV�h�[�q�ɓ��͂��邱�Ƃɂ��{�@�\�����p�ł��邪�AHCNA�̏��TV����~���邱�Ƃ�h�����߁A�} 2‑41�Ɏ����@��ڑ���ł́AV-ONU�����RF�����g�o�͂�BS�p�X�X���[�M����HCNA�̏o�͐M�����O���̍������g��ō������Ă���B���̏ꍇ�AHCNA�̏o�͐M�����]���ɃJ�b�g����邽�߁A�{���̎��g�������ׂĒʂ��ɂ́AHCNA�i�e�@�j���ɂč������邩�A�����t�B���^��������������퓙���K�v�ɂȂ�B
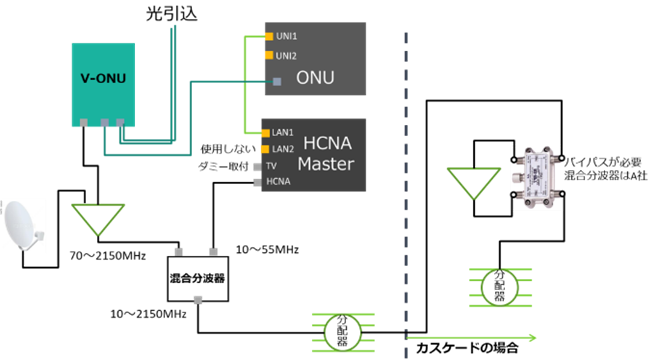
�} 2‑41�@HCNA�ڑ���
G.hn�̗̍p�ɂ������Ă͈ȉ��̓_�ɒ��ӂ�v����B
ž �P�[�u���e���r�̏��ш��TDD�ŗ��p���邽�߁A�����ݔ��ɏ������̃A���v�����݂���ꍇ�ɂ͗��p�ł��Ȃ��i��������̐M�����ʂ�Ȃ��j
C-DOCSIS�ɔ�אe�@�̉��i���������ʁA�q�@�̉��i��DOCSIS�P�[�u�����f��(CM�j�Ɣ�r���č��z�ł���B���̂��߁A�����Ґ��ɂ���ẮA�����I�ȃR�X�g��C-DOCSIS������ꍇ������B
2.3.1.4�@ �����P�[�u�����p�ɂ��ʐM�������Z�p�Ƃ��̒ʐM���x�̔�r
�\ 2‑18�ɏW���Z��̒ʐM�������̌������_�I�T�Z�l�������B�u����HFC�v�ł́A�P�[�u���ǂɐݒu����DOCSIS 3.0�𗘗p���A�W���Z���CMTS��1Port�������Ă�B�W���Z����̊��������P�[�u���i���10�`55MHz/����70�`770MHz�j�𗘗p����ꍇ�̒ʐM���x�́A���20Mbps�i16QAM��6.4MHz�j/����160Mbps�i256QAM��6MHz�~4ch�j�ƂȂ�B
�܂��A�u�W���Z��������P�[�u���v�̗��p�P�[�X�ł́A�W���Z��܂Ō�������āu�����P�[�u�����ɏ��M���Ȃ��A����ʐM�M���Ȃ��v�Ƃ�����ŁA�����ݔ��i����j�ł͏��/������g���ύX�Ȃ��ŗ��p�A�o�����A���v���C1�Ƒo�����A���v���C2�ł́A�X�Ȃ鍂��������Ƃ��āu���/������g���ύX�Ƒш�g���v���s���Ɖ��肵���B
�Ȃ��ABS-IF�ш�i1032�`1489MHz�j�͏W���Z��ł̗��p�������A�ʐM�ł͗��p���Ȃ����̂Ƃ���B
�\ 2‑18�@�W���Z��̒ʐM�������̌����i�ʐM���x�͗��_�I�T�Z�l�j
|
|
����HFC |
�W���Z��������P�[�u���i���M���Ȃ�/����ʐM�M���Ȃ��j |
||
|
����HFC�ݔ� ���10�`55MHz ����70�`770MHz |
�����ݔ��i����j ���10�`55MHz ����70�`770MHz |
�o�����A���v���C1 ���10�`85MHz ����108�`1002MHz |
�o�����A���v���C2 ���10�`204MHz ����258�`1032MHz |
|
|
DOCSIS 3.0 |
���20Mbps 16QAM ��6.4MHz�~1ch ����160Mbps 256QAM ��6MHz�~4ch |
���210Mbps 64QAM ��6.4MHz�~7ch ����320Mbps 256QAM ��6MHz�~8ch |
���330Mbps 64QAM ��6.4MHz�~11ch ����1280Mbps 256QAM ��6MHz�~32ch |
���� |
|
C-DOCSIS |
|
|||
|
DOCSIS 3.1 |
���300Mbps 256QAM ��45MHz�~1ch ����800Mbps 1024QAM ��96MHz�~1ch*** |
���300Mbps 256QAM ��45MHz�~1ch ����800Mbps 1024QAM ��96MHz***�~1ch |
���500Mbps 256QAM ��75MHz�~1ch ����1600Mbps 1024QAM ��192MHz�~1ch |
���1280Mbps 256QAM ��96MHz�~2ch ����3200Mbps 1024QAM ��192MHz�~2ch |
|
�T�[�r�X���� |
FM�Ȃǒ�
BS-IF�� |
�����Ɠ����� FM�Ȃǒ�
BS-IF�� |
FM��VHF1�`3ch �s��
BS-IF�� |
FM��VHF1�`3ch�AMIDc13�`21ch�A VHF4�`12ch�A SHBc22�`27ch �s�� BS-IF�� |
�y���z���g���ш�
�EDOCSIS 3.0/C-DOCSIS�F���5�`85MHz/����108�`1002MHz
�EDOCSIS 3.1�F���5�`204MHz/����108�`258MHz�iSHOULD�j�A
258�`1218MHz�iMUST�j�A1218�`1794MHz�iMAY�j
***6MHz�~16ch���̑ш�𗘗p����ꍇ
�y���zC-DOCSIS
�EC-DOCSIS�FType1�iMini-CMTS�j�̕����̐��i��������
2.3.1.5�@ �d�b�����p�ɂ��ʐM���x�������Z�p
�W���Z���MDF�`�e�����̊Ԃɂ́A�ʏ�A�d�b�T�[�r�X�ւ̗��p��O��Ƃ������^�����i�c�C�X�g�y�A�j���~�݂���Ă���A���̓d�b�T�[�r�X�Ƌ�������`�ŃC���^�[�l�b�g�A�N�Z�X�p�̓`���Z�p���p�����Ă���B���^�����𗘗p�����\�I�ȗL���A�N�Z�X�Z�p�Ƃ���ADSL�iAsymmetric Digital Subscriber Line: ITU-T G.992.1�AG.992.2�AG.992.3�AG.992.4�AG.992.5�j�����邪�A�W���Z����ł͏�艺��Ώ̒ʐM�ɗ��p�����VDSL�iVery high bit rate DSL: ITU-T G.993.1�AG.993.2�AG.993.5�j�����p������Ă���BVDSL�W�������ŋ߂̃��^���A�N�Z�X�Z�p��G.fast�ƌĂ�AITU-T SG.15�Ŋ���������Ă���B�܂��A���̍������̋K�i��MGfast�ƌĂ�A2020�N�ɕ����w�����肳�ꂽ�B
�\ 2‑19��ADSL����n�܂������^���n�A�N�Z�X�Z�p�̐i�W�������B
�\ 2‑19�@���^���n�A�N�Z�X�Z�p�̐i�W
|
�K�i���� |
ITU-T����(�����w) |
�������莞��* |
���x(����/���)(bps) |
|
ADSL |
G.992.1 |
1999.7 |
6M/640k |
|
ADSL 2+ |
G.992.5 |
2003.5 |
16M/800k |
|
VDSL |
G.993.1 |
2004.6 |
52M/2.3M |
|
VDSL 2 |
G.993.2 |
2006.2 |
100Mbps |
|
G.fast |
G.9701 |
2014.12 |
��艺�荇�v1G (106MHz) |
|
MGfast |
G.9710 |
2020.2 |
��艺�荇�v5G (424MHz) |
*�������莞���͏��ł̐���N��
2.3.1.6�@ G.fast
�@ G.fast�d�l�T�v
G.fast��VDSL2�ɑ������^�����A�N�Z�X�Z�p�Ƃ��āAITU-T SG15�ɂ����Ċ���G.9700�i�d�̓X�y�N�g�����x�d�l�j����ъ���G.9701�i�������C���d�l�j�Ƃ���2014�N�ɏ��F���ꂽ�BG.fast�֘A��ITU-T�����Q�̈ꗗ���\ 2‑20�Ɏ����B
�\ 2‑20�@G.fast�֘A�����Q
|
���� |
���C�� |
�������莞�� |
�K����e |
|
G.997.2 |
�ێ�E�^�p�E�Ǘ��w |
2015.5 |
OAM (Operation, Administration, Maintenance)�K�� |
|
G.994.1 Amd4 |
�f�[�^�����N�w |
2014.12 |
G.fast�����R���|�[�l���g�̋K�� (�n���h�V�F�[�N�K��) |
|
G.9701 |
�����w |
2014/5 |
�����w�K�� |
|
G.9700 |
2014/12 |
���g�������PSD�K�� |
G.fast�́A�} 2‑42�Ɏ����悤��2�`106MHz�܂ł̑ш�𗘗p���A�����I�ɂ�212MHz�܂Ŋg�������\��ł���BG.fast�̓d�̓X�y�N�g�����x�iPSD�j�́A������VDSL���Ƃ̋������l���������̂ƂȂ��Ă��邪�A�������S�ɔ����邽�߂ɂ�VDSL�����p����30MHz�܂ł̑ш�ŃT�u�L�����A���I�t�Ƃ���^�p���s���B���̏ꍇ�A�`���e�ʂ��ő��30%�����邱�ƂɂȂ�B
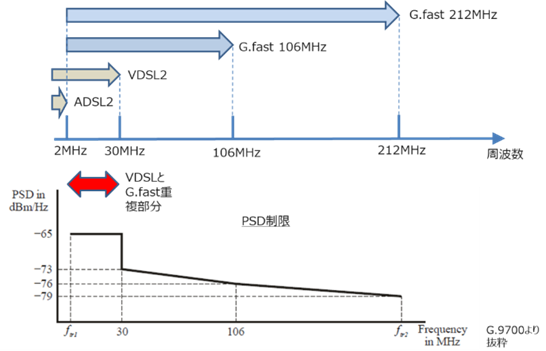
�} 2‑42�@G.fast�̗��p���g����PSD
VDSL��G.fast�̎d�l��r���\ 2‑21�Ɏ����B
G.fast�̕����w�̕ϒ������́ADMT�idiscrete multi-tone�j�ɕ��ނ��������ł���AITU-T����G.993.2��VDSL2�Ɨގ����Ă��邪�A��������}�邽�߂�1�L�����A�Ɋ��蓖�Ă�r�b�g����12�r�b�g�Ƃ��Ă���B���݂̊���G.9701�ɂ����ẮAVDSL2�̍ō�30MHz������ō�106MHz�܂���212MHz�܂Ŏg�p����v���t�@�C�����K�肳��Ă���B�������A��҂͑����̍��ڂ��p�������ƂȂ��Ă���A���ݏ��p������Ă��鐻�i�͍ō�106MHz�̃v���t�@�C�����g�p���Ă���B�܂��AVDSL2�Ƃ̋������������邽�߂ɁA�Œ���g����2.2�A8.5�A17.664��������30MHz�ɐݒ�\�Ȏd�l�ƂȂ��Ă���B
G.fast�̕��M�����́AVDSL��VDSL2��FDD�ifrequency-division duplexing�j�Ƃ͈قȂ�TDD�itime-division duplexing�j���̗p���Ă���B�㉺�����̑��x��i����/���j�́A90/10����30/70�܂Őݒ�\�ƂȂ��Ă���B
�����������́A�g�����X�����ƃ��[�h�E�\�������������̗p����Ă���B����ɁA�N���X�g�[�N�ɂ�鐫�\��}�����邽�߂ɁA���[�R�b�������I�ɃL�����Z������x�N�^�����O�Z�p�i���̃G�R�[�L�����Z���j���̗p����Ă���B�Ȃ��A�x�N�^�����O�͑��˂�ꂽ���^���P�[�u���S�̂�Ώۂɍs�����߁A�������H�i���j�𗘗p�����Ԃŕ�����G.fast�e�@���ɗ��p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����������ƁA���łɐ�s���Ǝ҂�G.fast���ς̏W���Z��ɂ����ẮA�㔭�̎��Ǝ҂�G.fast�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
ITU-T�ɂ�����G.fast�̉���R�c�ł́A�`���}�̂Ƃ��ē����P�[�u�����g�p���ď��1GHz�܂őш�g�����邱�Ƃ���������Ă���B
�\ 2‑21�@VDSL��G.fast�̎d�l��r
|
|
VDSL |
G.fast |
|
�d�l����(������) |
VDSL (17a) (ITU-T 993.1) VDSL2 (30a) (ITU-T 993.2) |
G.fast (ITU-T G.9701) |
|
�g�p���g���� |
�`12MHz (17a) �`30MHz (30a) |
2~106MHz (2~212MHz:�������i��) |
|
�ő�`�����[�g �i��艺�葍�a�j |
����30-80Mbps 150Mbps (17a) 250Mbps (30a) |
1Gbps (100m����)* 500Mbps (100m�����H) |
|
�ϒ����� |
OFDM |
OFDM |
|
�T�u�L�����A�� |
4K |
2K (106MHz�v���t�@�C��) |
|
���d������ |
FDD |
TDD |
|
����/���䗦 |
�Œ� |
��(90:10~30:70) |
|
�V���{�����[�g |
~250��s (17a) |
~20��s |
|
�x�N�^�����O |
ITU-T G.993.5 |
ITU-T G.9701 |
|
���M�o�� |
14.5dBm |
4dBm (a)�A8dBm (b) |
|
FEC |
RS + Trellis |
RS + Trellis |
���F VDSL��17/30�͑ш�̈Ⴂ�AG.fast��a/b�͑��M�o�͂̈Ⴂ
��G.9701�Ń^�[�Q�b�g�Ƃ�����E����`�����x�i���v�j�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
���� ���\�ڕW�i���{����j
100 m���� 500�`1000 Mbps
100 m 500 Mbps
200 m 200 Mbps
250 m 150 Mbps
500 m 100 Mbps
�A G.fast�̐ݒu��
G.fast��VDSL�Ɠ��l�ɁA�W���Z��̓������邢�͉��O�L���r�l�b�g����DSLAM�iDigital Subscriber Line Access Multiplexer�j�ɑ������镪�z�_���j�b�gDPU�iDistribution Point Unit�j��ݒu���ă��[�U�����e����B��{�I�ȍ\�����} 2‑43�Ɏ����B
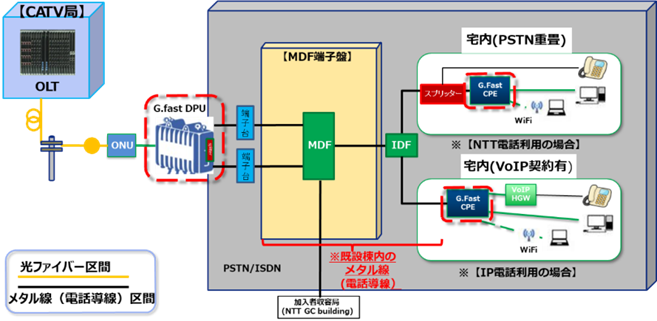
�} 2‑43�@G.fast�𗘗p���铏���ڑ��\���}
G.fast��VDSL�̌�p�����Ɩڂ���A���̓�����VDSL�����łɓ������Ă��鎖�Ǝ҂ɂ����Đe�a���������B��̓I�ɂ́AG.fast�e�@��VDSL�q�@�Ƃ��ڑ��\�ŁA�i�K�I�Ȉڍs���\�Ȃ��ƁA���i��VDSL�Ɠ��z���x�ł��邱�ƁA�v��ݒu�H����VDSL�Ƒ傫���ς��Ȃ����Ɠ�����������B
2.4�@ �V����FTTH�\�z�\�����[�V����
����܂ł̕��z�X�v���b�^��p����FTTH�\�z�Ƃ͈قȂ�A�C�O�ŃV�X�e���̒�����Ȃǂ�ړI�Ƃ����������s���A���ꕔ�̍��ł��łɓ������Ă���A���C�[�u���X�v���b�^��p����FTTH�V�X�e���̍\�z���͂��߂Ƃ���A�V���ȃ\�����[�V�����ɂ��Đ�������B
�������A����Љ��\�����[�V�����́A�P���Ɏ��@�ނ̃R�X�g���r����ƍ����Ȃ邩������Ȃ����A����FTTH�ւ̐�ւ�����������ꍇ�A����ł̌��t�@�C�o�̗Z�����팸�ł���Ȃǂ̘J���ϓ_�̃R�X�g�����b�g�����邽�߁A�P�[�X�o�C�P�[�X�ő����I�ɔ��f����K�v������B
2.4.1�@ �R�l�N�^�\�����[�V����
����܂œ��{�ł́AFTTH�V�X�e���\�z�ɂ�������t�@�C�o�P�[�u���̐ڑ��́A�ق�100���Z���ōs���Ă����B����C�O�ł́A�Z���̃X�L������������Ǝ҂��m�ۂ���̂�����A�v���O���v���C�Ŏ{�H�̃X�s�[�h���グ��R�l�N�^�\�����[�V���������Ă��āA�R�l�N�^�̂݁A���邢�̓R�l�N�^�{�Z���i�����n�̃��X�����炷�ȂǖړI�����肵�����p�j�Ƃ����g�ݍ��킹���A���X�Ɏg���͂��߂Ă���B�������A�������C��������t�@�C�o�[�̎��o���ʒu�i�h���b�v�ӏ��j�����O�ɒ������Ċm�肷��K�v������B�R�l�N�^�\�����[�V�����Ɏg�p�����^�[�~�i���̗���ȉ��Ɏ����B
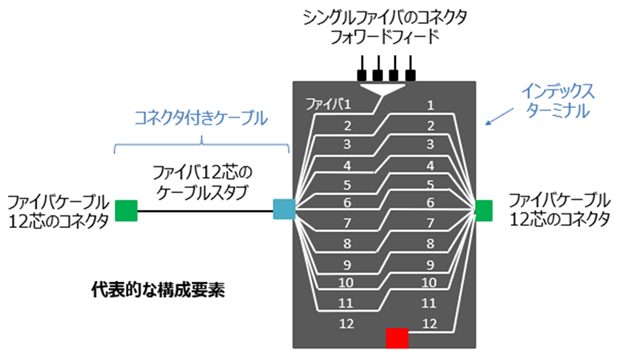
�} 2‑44 �^�[�~�i���̎d�g��
�o�T�F�R���X�R�[�v�Ё@Leveraging fiber indexing technology
�} 2‑44 �ł́A��\�I�ȗ�Ƃ���12�c�̏ꍇ�������A���̎��̎d�g�݂��ȉ��ɋL�ڂ���B
�@ �O�i�i�����j�ɐݒu����Ă���t�@�C�o���z�n�u�i�}���ɋL�ڂȂ��j����12�c��
���t�@�C�o�P�[�u�����^�[�~�i���ɓ���Ƃ��납��n�܂�B
�A �^�[�~�i�������Ńt�@�C�o�����A�擪�̃t�@�C�o1����̐M����1:4�܂���
1:8�X�v���b�^�i���[�q�j�ɑ����A�n��̌ڋq�ɃT�[�r�X�����B
�B �c��̌��t�@�C�o�i2�`12�j�́u�C���f�b�N�X�v�i���Ԃ�1�i�߂邱�Ɓj����A
12���t�@�C�o��MFOC�iMulti-Fiber Optical Connector�F���c���R�l�N�^�j ���g�����������B
�C 12�c�̌��t�@�C�o�P�[�u���́A���̒[���i��2�C���f�N�V���O�^�[�~�i���j�ɐڑ�����A�C���f�N�V���O�v���Z�X���J��Ԃ����B
�����ŁA�h��MPO�iMulti-Fiber Push On�j�R�l�N�^�t���^�[�~�i����p�����f�C�W�[�`�F�[���̍\�����} 4-32�Ɏ����B�ő��12��̃C���f�N�V���O�^�[�~�i����Ƀ`�F�[���ڑ����\�ŁA�h��MPO�R�l�N�^�t���̑��c�P�[�u���ɂ��A�v���O���v���C�̐ڑ������S�h���ōs�����Ƃ��ł���B
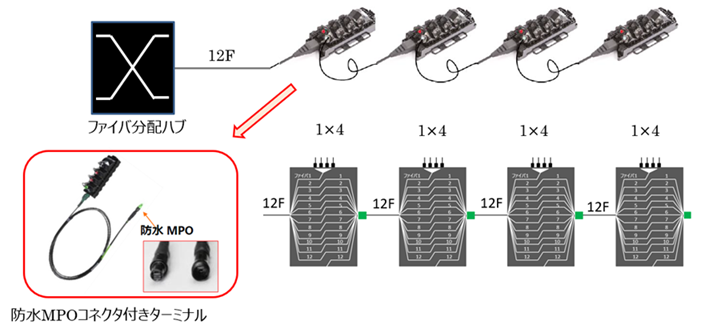
�} 2‑45 �h��MPO�R�l�N�^�t���f�C�W�[�`�F�[��
�o�T�F�R���X�R�[�v�Ё@FTTH �v���O���v���C�\�����[�V����
�{�R�l�N�^�\�����[�V�����̓W�J�R���Z�v�g��} 2‑46�Ɏ����B���ʓI�Ȑv���s�����߂̍ŏ��̃X�e�b�v�Ƃ��āA�ݒu�V�i���I�̊�{�I�ȍ\���v�f�A����у^�[�~�i���̍\�������肷��p�����[�^���`���邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�B�} 2‑46�̃^�[�~�i���i1�`12�j�̔z�u�ƃ^�[�~�i������̔z�M����Z��̌ː����A����ɊY������B�����̃p�����[�^���ݒ肳��邱�ƂŁA�����S������v�`�[���́A��`���ꂽ�r���f�B���O�u���b�N���J��Ԃ������ŁA�v���O���v���C�ł̃l�b�g���[�N���\�z���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B
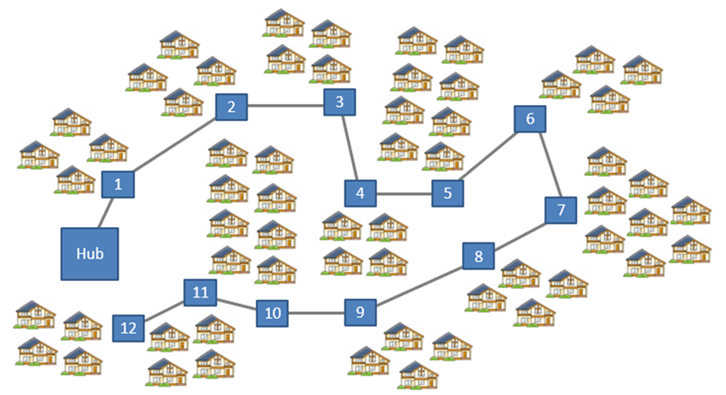
�} 2‑46�@�R�l�N�^�\�����[�V�����̓W�J�R���Z�v�g
2.4.2�@ ���z���^�b�v��p�����A���C�[�u���A�[�L�e�N�`���R�l�N�^�\�����[�V����
�]����FTTH�\�z�ł́A1�c�̃X�v���b�^���͂ɑ��āA�������̃p���[�ŕ���o�����X�X�v���b�^�������̗p���Ă���B(�} 2‑47)
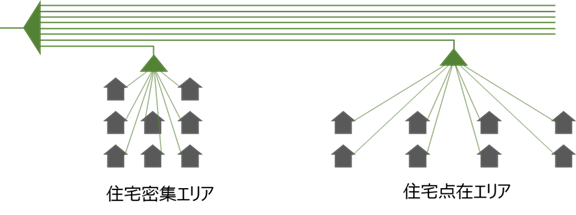
�} 2‑47 �]����FTTH�\�z
����A�V����FTTH�\�z�\�����[�V�����Ƃ��ďЉ�镪�z���^�b�v(�A���o�����X�X�v���b�^)�����ɂ��FTTH�\�z�́A1�c�̌��t�@�C�o�݂̂Ŋ����̃l�b�g���[�N���\������A�K�v�Ȋe�|�C���g�Ō��p���[��L���Ƀ^�b�v���āA���X�o�W�F�b�g���g���ʂ������܂Ń^�b�v���\�ƂȂ�����ł���B(�}4-35)�@���̃A���C�[�u���A�[�L�e�N�`���́AHFC�V�X�e���̃^�b�v�I�t��p�����z�M�`�Ԃɑ�������B�܂��A���z���^�b�v�Ԃ�Z��ւ�Drop�P�[�u���ɂ��Ă��R�l�N�^�t���P�[�u�����g�p����B
�{�\�z���@�ɂ��A�Z���Ȃ��ŒZ���Ԃ̎{�H���\�ƂȂ�A�]��������菭�Ȃ����c����FTTH���\�z�ł���B
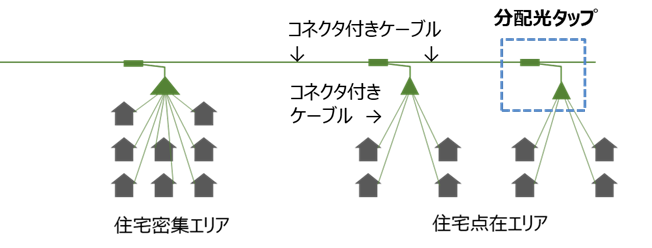
�} 2‑48 ���z���^�b�v��p����FTTH�\�z
�g�p����镪�z���^�b�v�̓��e��}4-36�Ɏ����B�����ł́A9:1�̔�Ώ̂Ō��p���[�z�����ł���B9��Thru�p��1��Drop�p�ł���B�Ȃ��A���z���^�b�v�͕����̕��z�䗦�ɑΉ��������i������B�i�\ 2‑22�j
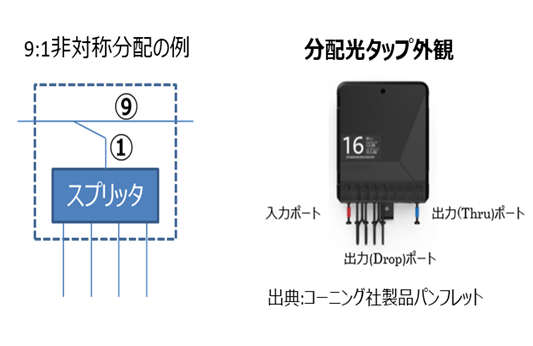
�} 2‑49�@���z���^�b�v
�\ 2‑22 ���z���^�b�v�̕��z�䗦��
�o�T�F�R���X�R�[�v�Ё@Application
Guide_ Leveraging fiber optical tap technology
2.4.3�@ MDU�ł̃R�l�N�^�\�����[�V�������p
�C�O�ł́AMDU�ɂ����Ă��Z���ڑ��ł͂Ȃ��A�R�l�N�^�\�����[�V�������̗p����Ă���B���̔w�i�Ƃ��āA�r���̃I�[�i�[��e�i���g�͓��퐶���ւ̎x����ŏ����ɗ}���A�ł��邾���Z���Ԃł̐ݒu��]��ł��āAFTTH�����ɍ��ӂ��Ă���T�[�r�X�܂ŁA���Ԃ����Ɍ����Ă��邱�Ƃ���A���Ԃ̂�����Z���ڑ������A�Z���ԂŊm���Ɏ{�H�ł���R�l�N�^�ڑ����̗p���邱�ƂŁA�Z�[����FTTH�C���t�����\�z�ł���B
�R�l�N�^�\�����[�V�����𗘗p��������MDU�ɑ���C���t���̍\�z�Ƃ��āA�}4-37�ɗ�������B�����̊ǘH�����p�ł��Ȃ��ꍇ�A���O�ǖʂɂ��̃R�l�N�^�t���P�[�u����~�݂��邱�ƂŁA�c�n�̔z���Ƃ��Ďg�p�ł���B���̃R�l�N�^�t���P�[�u���́A�H��o���Ɋ����ƂȂ�P�[�u������w�肵���Ԋu�ŕ��z�P�[�u�����}�����ꂵ�Ă����ԂŔ[�i����邽�߁A�C���t���v�i�K�Ɋe�K�̃t���A���i����Ԋu�j��A�O�ǂ���̓���������FDT(Fiber Distribution Terminal)�@�܂ł̋����i���z�P�[�u�����j���v�Z���I�[�_�[���邱�Ƃɂ��A�����ɂ҂����荇�������ނƂ��Ĕ[�i����A�������{�H���s�����Ƃ��ł���B
���n�P�[�u���Ƃ��āA�e�����ւ̈������݁A���ɖڗ����ɂ����\�����[�V����(�����ȃP�[�u���O��)�Ŕ��ς˂Ȃ����p���\�ł���B
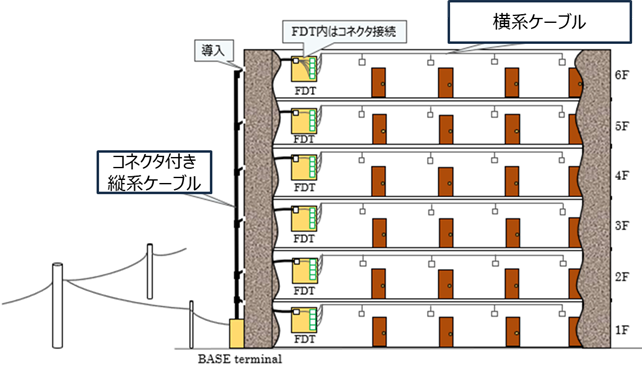
�} 2‑50�@MDU�C���t����
2.5�@ �����`���Z�p
2.5.1�@ BWA�iBroadband Wireless Access�j�F
BWA��2008�N�ɐ��x�����ꂽ�L�ш斳���A�N�Z�X�V�X�e�����w���A�����̂ɂ�����ꕔ�̒n����J�o�[����u�n��BWA�v�ƑS�����J�o�[����u�S��BWA�v������B��̓I�ȃV�X�e���Ƃ��Ă�AXGP��WiMAX�����邪�A�������x���ɂ����TDD-LTE�Ƃ̌݊������m�ۂ���Ă���B�} 2‑51�Ɏ��g�����蓖�Ă̏������B�S��BWA��Wireless City Planning�Ђ�UQ�R�~���j�P�[�V�����Y�Ђ��^�p���Ă���B�n��BWA�͒n��P�[�u��TV���Ǝ҂Ȃ�99�Ђ��^�p���Ă��邪�A����93�Ђ�TDD-LTE�ƌ݊����̂��鍂�x���������̗p���Ă���i�\ 2‑23�j�B
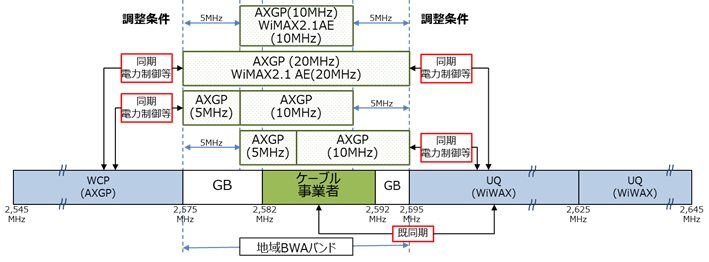
�} 2‑51�@BWA�̎��g�����蓖�ď�
�\ 2‑23�@�n��BWA�V�X�e���̖����NJJ�ݏ�
(https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/system/ml/area_bwa/002.pdf���)
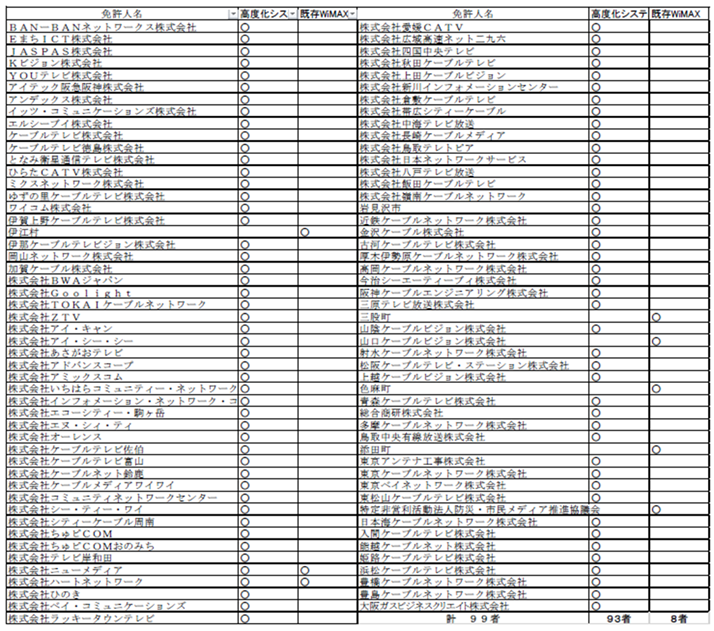
�n��BWA�̗p�r�́A�s�����ւ̉͐�Ď��f���̒�ЊQ���ً̋}�C���t������̒��邢�͉����Ҍ����̍��������ʐM�T�[�r�X�Ȃǂł���i�} 2‑52���Q�Ɓj�B
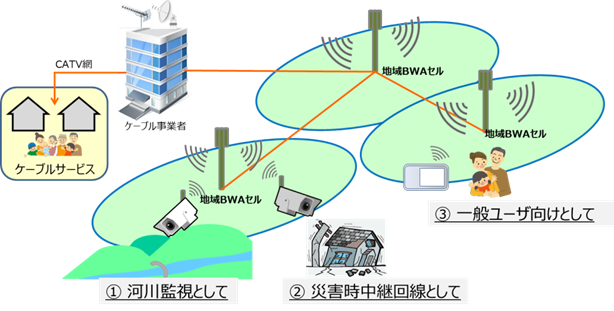
�} 2‑52�@�n��BWA�̗p�r��
2.5.2�@ 5G, ���[�J��5G, B5G/6G
2.5.2.1�@ 5G�@�@�@�`LTE����5G���`
4G(LTE)�ł͌��t�@�C�o���݂̍����`��(����1Gbps���x)��ڕW�Ƃ��C�ړ����̓��掋���������\�ȃV�X�e�������������D5G�ł́C���̐��\������Ɉ����グ��eMBB(enhanced Mobile Broadband)�Ȃ�����ɉ����C���M���D����x��(URLLC�GUltra Reliable & Low Latency Communications)�ƁC��ʂ̃f�o�C�X�Ɛڑ��ł���mMTC(massive Machine Type Communications)��3������Ƃ���V�X�e���ł���D��̓I�ɂ́C�\ 2‑24�Ɏ����悤�ȗv���������ŋK�i�����肳��Ă���D����5G�̗��p�V�[���́C3�̓����܂��Đ} 2‑53�̂悤�ȃC���X�g�ł����Ύ�����C�Љ��DX��ՂƂ��Ċ��҂���Ă���D
�\ 2‑24�@5G�̗v������
|
���� |
�v�������i4G��j |
���l |
|
���[�U�̒ʐM���x |
1000�{ |
����20Gbps�C���10Gbps���x |
|
�ڑ��f�o�C�X�� |
10�`100�{ |
1��n�ǂ����� |
|
�x������ |
1/5�`1/10 |
������Ԃ�1ms�ȉ� |
|
�f�[�^�ʐM�e�� |
1000�{ |
|
|
�����d�̓f�o�C�X�� |
10�{ |
|
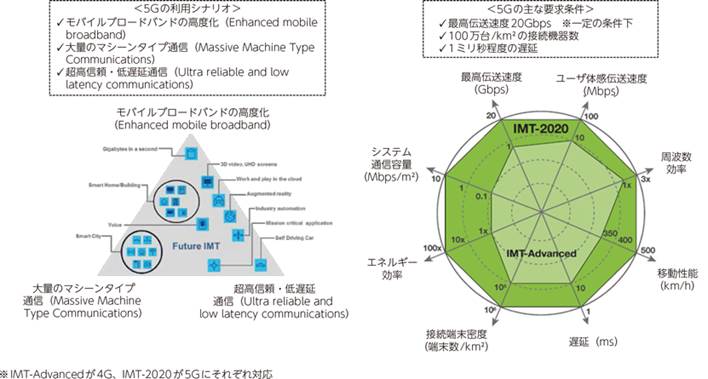
�}
2‑53�@IMT�r�W���������ɂ�����5G�̗��p�V�i���I�y�їv������
�i������ �ߘa2�N ���ʐM�������j
�@ ������
�@5G�̏��p�T�[�r�X�́A2018�N����2019�N�ɂ����Ďn�܂����B�ŏ���5G���p�T�[�r�X�́A2018�N10���ɕč�Verizon�Ђ��Œ薳���T�[�r�X�Ƃ��ĉƒ�����ɒ������Ƃ��ŏ��Ƃ���Ă��܂��B12���ɂ͕č���؍��Ń��o�C�����[�^�̒��͂��܂�A2019�N4���ȍ~��5G�Ή��̃X�}�[�g�t�H���ɂ��T�[�r�X���n�܂����B���{�ł�2020�N3��27����NTT�h�R�����ŏ���5G���p�T�[�r�X���J�n�����B�ŏ��̃T�[�r�X�G���A�͓����A���A���É��A�����̈ꕔ�n��Œ���Ă������B���̌�ANTT�h�R�����͂��߂Ƃ��鑼�̒ʐM���Ǝ҂�����5G�̏��p�T�[�r�X��W�J���A�S���I�ɗ��p���g�傳��Ă���B�������C�����_�ł͎��ɏq�ׂ�NSA��NA�̓�̌`�Ԃ����݂��Ă���B
�A NSA��SA
�@�g�ѓd�b�V�X�e���́A�[���Ɗ�n�ǂō\������閳���A�N�Z�X��(RAN�GRadio Access Network)�ƁA�R�A�Ԃō\������Ă���B4G�̃R�A�Ԃ�EPC�A5G�̃R�A�Ԃ�5GC�Ƃ����B�R�A�Ԃ̋@�\�́A���[�U�[�f�[�^���������[�U�[�v���[��(U-Plane)�ƁA�[���F��ړ���������̈ێ��Ǘ��Ȃǂ�S������v���[��(C-Plane)�ō\������Ă���B4G�̃R�A�Ԃ�EPC(Evolved Packet Core)�A5G�̃R�A�Ԃ�5GC(5G Core)�Ƃ����A���̍\����\�͂ɂ͈Ⴂ������B����5G�̓����ł����ʐڑ��imMTC�j�⍂�M����x���iURLLC�j���������邽�߁A����v���[���̍\�����傫���قȂ��Ă���i�\ 2‑25�C�} 2‑54�j�B
�\ 2‑25�@4G��5G�̖ԍ\���̈Ⴂ
|
|
�����A�N�Z�X�Z�p |
��n�� |
�R�A�� |
|
4G |
LTE |
eNodeB |
EPC |
|
5G (NSA) |
NR |
gNodeB |
NSA�Ή�EPC |
|
5G (SA) |
NR |
gNodeB |
5GC |
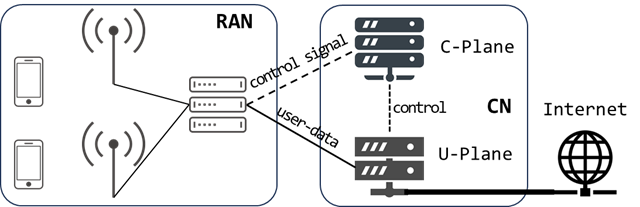
�} 2‑54�@�g�ѓd�b�V�X�e���̃l�b�g���[�N�\���T��
�@�����RAN�ɂ����ẮA4G�̖����A�N�Z�X�Z�p��LTE�A���̊�n�ǂ�eNodeB�ƌĂԂ̂ɑ��A5G�̖����A�N�Z�X�Z�p��NR(New Radio)�A���̊�n�ǂ�gNodeB�ƌĂԁB���łɊ�������Ă���4G�Ԃ�5G��n��gNodeB�����X�ɓ�������ɂ�����ANSA(Non Standalone)�Ƃ����\�����Ƃ��Ă���B����́AC-Plane��LTE�AU-Plane�ɂ�NR��LTE�p������̂ł���AgNodeB��eNodeB�ō\�����ꂽRAN��EPC�x�[�X�̃R�A�Ԃō\�������i�} 2‑55���j�B���̍\���̏ꍇ�A���M��n���h�I�[�o�[�Ȃǂ̐����LTE�ōs���A���[�U�̃f�[�^�]����NR�ɂ�鍂����e�ʓ`��(eMBB)�����������B����ɑ���SA (Stand Alone)�ł̓R�A�Ԃ�5GC�Ƃ��邱�Ƃ�5G�{�̂̔\�͂����������i�} 2‑55�E�j�B
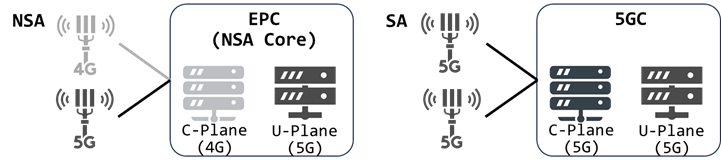
�} 2‑55�@NSA��SA�̈Ⴂ
�B ���g����
������5G�����p������g���тƂ��āA�} 2‑56�Ɏ����悤�ɁASub6�i6GHz�ȉ��j��3.7GHz�т�4.5GHz�сA����я��~���g�т�28GHz�т����蓖�Ă��Ă���B�����͏������Ɖ�������œ������g����p����TDD�iTime Division Duplex�j�ŗ��p�����B5G�̎��g���т�n�Ŏn�܂�ԍ��ŋ�ʂ���Ă���A�����ł�n77�`79��n258�ł���B
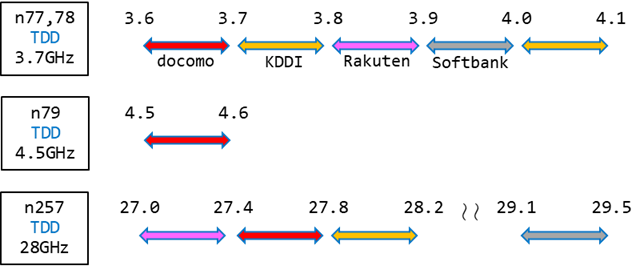
�} 2‑56�@5G�̎��g����(���l�̒P�ʂ�GHz)
�܂��A4G�����p������g���т̓o���h�ԍ��ŋ�ʂ���A�����ł͐} 2‑57�Ɏ����ш悪���p����Ă���B���̂����o���h42�̂�TDD�A����ȊO��FDD�iFrequency Division Duplex�j�Ŏg�p����Ă���B����4G/BWA�ŗp�����Ă���A3.6GHz�ȉ��̎��g���тɂ�����5G�̓����iBWA�ɂ��Ă�5G�ɑΉ��������x���j���ł���悤��2020�N8���ɐ��x�������s��ꂽ�B���̌�A�g�ѓd�b���Ǝ҂�̐\���ɉ�����5G�ւ̍��x�����i�߂��Ă���[3]�B
���E���g����c�iWRC-19�j�ɂ�����5G�ɐV���ɗ��p�ł�����g���̋c�_���s��ꂽ�B���̌��ʂ܂��A���{�����ł́A4.9�`5.0GHz�сA26.6�`27.0GHz�ыy��39.5�`43.5GHz �т�3�̑ш�ɂ����Ċ��������V�X�e���Ƃ̋��p��������������{���邱�ƂɂȂ��Ă���B�܂��A���E���g����c�iWRC-23�j�Ō����\���7025�`7125MHz �ɂ��āA���蓖�Ẳ\�������������\��ł���B���{�ł�4.9�`5.0GHz�т�802.11j�i�o�^���̖���LAN�j�Ɏg���Ă��邽�߁A5G�̓����ɂ������ẮA���݂̃V�X�e���ɉe����^���Ȃ����Ƃ����߂��Ă���[4]�B
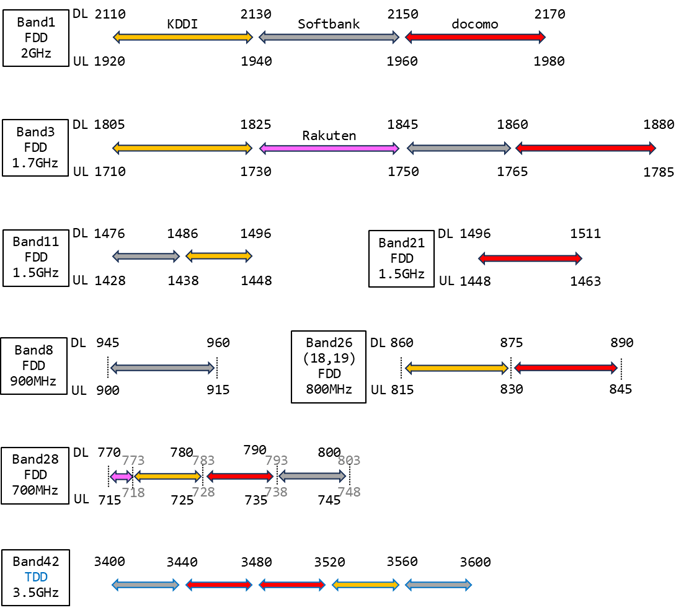
�} 2‑57�@4G�̎��g����(���l�̒P�ʂ�MHz)
2.5.2.2�@ ���[�J��5G
5G�V�X�e���͌g�ѓd�b���Ǝ҂�������O�Ԃɂ������p�������̂ł͂Ȃ��A��Ƃ�y�n�̏��L�҂�����ꂽ�͈͂œƎ���5G�l�b�g���[�N���\�z���邱�Ƃ��ł���B�����ł́A���̂悤�ȖړI�̂��߂̎��g���т��p�ӂ���A�����Ƌ��Ɋ�Â����p���F�߂���B���̂悤��5G�̗��p�`�Ԃ����[�J��5G�Ƃ����B�A�����C�Z���X�o���h��p����Wi-Fi�ɔ�ׂ�5G�̓��������������ʐM����������Ƃ���Ă���B�Ⴆ�A��x���⍂���ʐM�����āA�g�D���̃f�o�C�X��V�X�e�������A���^�C���ŘA�g���A�������v���ȃf�[�^�̓`���⏈�����������܂��B����ɂ��A��������A���^�C���Ď��A����V�X�e���̌������Ȃǂ����҂����B�܂��A��e�ʒʐM�����āA�g�D���̑����̃f�o�C�X��Z���T�[���l�b�g���[�N�ɐڑ�����A��ʂ̃f�[�^�����A���^�C���ő���M���邱�Ƃ�IoT�iInternet of Things�j�f�o�C�X�̊Ǘ���r�b�O�f�[�^�̏����ȂǁA�f�[�^�쓮�^�̃A�v���P�[�V������T�[�r�X���l������B
���[�J��5G�͑g�D���Ǝ��ɏ��L���^�p����l�b�g���[�N�ƂȂ邽�߁A�g�D�͎��g�̃j�[�Y�ɍ��킹�ăl�b�g���[�N��v�E�Ǘ����邱�Ƃ��ł���B����ɂ��A�Z�L�����e�B��v���C�o�V�[�̊Ǘ��A�J�X�^�}�C�Y���ꂽ�T�[�r�X�̒Ȃǂ��\�ɂȂ�B����̗̈��v���ɉ������J�o���b�W�G���A�̐ݒ��A�l�b�g���[�N�\���A�Z�L�����e�B�|���V�[�̒�`�Ȃǂ����R�ɍs����B����ɂ��A�g�D�̓Ǝ��̗v�������ɑΉ�����_�������B
���[�J��5G�̗p�r�Ƃ��āA�H���q�ɂł̃l�b�g���[�N�\�z�ɂ��H��@�B��^���@�B�Ȃǂ̉��u�����^�p�̎������A���邢�͕����Ǘ��≓�u�Ď��Ȃǂ����҂���Ă���B�܂��A�W���Z���L�����p�X��X�^�W�A���ł̃u���[�h�o���h�T�[�r�X�A�L�����p�X���ł̊w�K�x���V�X�e���A�C�x���g���ł̍����ʐM�ȂǁA���܂��܂ȉ��p���l�����Ă���B
���[�J��5G�̖����Ƌ�������̂͊�Ƃ�y�n�̏��L�҂Ȃǂł��邪�A�l�b�g���[�N�̍\�z��^�p�̓l�b�g���[�N���Ǝ҂�V�X�e���C���e�O���[�^�Ȃǂ��T�|�[�g���Ă悢���ƂɂȂ��Ă���B
�@ ���[�J��5G���g����
���[�J��5G��p�̎��g���тƂ��āA2020�N��4.6�`4.9GHz�y��28.3�`29.1GHz���V���ɒlj����ꂽ�B����܂�28.2�`28.3GHz��100MHz���������p�ł��Ȃ������Ƃ���ł��邪�A28GHz�т͊����ƍ��킹��900MHz���Ɋg�債�A�V���ȃT�u�U�i6GHz�шȉ��j��300MHz���ƍ��킹��1200MHz�����p�ӂ���Ă���B���̒lj��ɂ��A����܂ł�28GHz��SA�iStand Alone�j���A2.5GHz���̃v���C�x�[�gLTE�o���h�Ƒg�ݍ��킹��NSA�iNon Stand Alone�j�����ł��Ȃ������̂��A�T�u�U��SA��T�u�U��28GHz��g�ݍ��킹��NSA���ł���悤�ɂȂ���[5]�B
2.5.2.3�@ B5G/6G
�g�ѓd�b�V�X�e���i�����͎����ԓd�b�V�X�e���j��1980�N�ɓo��i�d�d���Ђ�1979�N12���ɓ����n��ŃT�[�r�X���J�n�j���A�Ȍ�A�����ނ�10�N���ɐV���Ȑ���̃V�X�e�����o�ꂵ�Ă���B���̊ϓ_�ł́AB5G/6G�̓�����2030�N���������܂�Ă���A����Ɍ��������g�݂��n�܂��Ă���B�����ł́ABeyond
5G���i�R���\�[�V�A����2020�N�ɐݗ�����ABeyond
5G���i�Ɍ����������I�Ȑ헪�̌����Ȃǂ��J�n���ꂽ�B2023�N3���ɔ��s���ꂽB5G�z���C�g�y�[�p�[��2�ł͎��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���B
�E�g���q�b�N�g�����h�F2030�N���ɗ\�z����郂�o�C���A�v���P�[�V������[�X�P�[�X����g���q�b�N�̌X���������Ă���
�E�ʐM�ƊE�̃}�[�P�b�g�g�����h�F�ړ��ʐM����̃}�[�P�b�g�����A���ɁA�X�}�[�g�t�H�����n�Ǔ��̒ʐM�C���t���ݔ��̃V�F�A�\���̕ω��ƁA�X�}�[�g�t�H���֘A�̍\�����i�̋Z�p�����������Ă���
�E���ƊE���瓾��ꂽ�g�����h�F�����_�Ő��̒��ɑ��݂��邷�ׂĂ̋ƊE�ɂ�����ۑ��o���A�ۑ�����āA�ƊE�Ƃ��Ă���ׂ��p�▲�A����ɂ́ABeyond 5G�Ɋ��҂��鐫�\��@�\���܂Ƃ߂Ă���
�EBeyond 5G�ŋ��߂���Capability��KPI�F4�͂̓��e����A�l�X�ȋƊE�ł̓����I�ȃ��[�X�P�[�X��o���A���ꂼ��̃��[�X�P�[�X�ŋ��߂���Beyond 5G�̐��\���܂Ƃ߂�Ƌ��ɁABeyond 5G���ے�����}�A6�̗��p�V�i���I�A�ڕWKPI�i��ʓI�A�萫�I�j�������Ă���
�E�Z�p�g�����h�FBeyond 5G�ɋ��߂���Z�p�̓����ɂ��Č������A����炪���p�҂�s��ɒ���@�\�E���l�E�ʂ��������E���҂Ȃǂ𖾂炩�ɂ��܂Ƃ߂Ă���
�܂��ANTT�h�R���ł́A2020�N�Ƀz���C�g�y�[�p�[�u5G�̍��x����6G�v���ł������[�X���A2022�N11���ɑ�5�ł֍X�V���ꂽ�BKDDI��2021�N��Beyond 5G/6G �z���C�g�y�[�p�[���A�\�t�g�o���N��2021�N7���ɁuBeyond 5G�^6G�̃R���Z�v�g����ю����Ɍ�������������J�v�Ƒ肵���v���X�����[�X�̒���2030�N��B5G/6G�̐��E�ςƂ���Ɍ�����12�̒���\���Ă���B
2.5.3�@ FWA
2.5.3.1�@ 22/26/38GHz��FWA
FWA�͈�ʂɂ͌Œ薳���ǂɂ��A�N�Z�X�i�����ڑ��j�V�X�e�����w���B�������Ȃ��狷�`�̈Ӗ������ł́A22/26/38GHz�т𗘗p��������Ҍn�����V�X�e����FWA�i�Œ薳���A�N�Z�X�V�X�e���j�ɖ��̕ύX����Ă��āA���ɂ�����w���ꍇ������B���`��FWA�ł́A�d�C�ʐM���Ǝґ��̊�n�ǂƕ����̗��p�ґ��̉����ҋǂƂ����ԂP�Α������^�i�o�|�l�o�GPoint to Multipoint�j�ƁA�d�C�ʐM���Ǝґ��Ɨ��p�ґ��Ƃ��P�P�Ō��ԑΌ��^�i�o�|�o�GPoint to point�j����`����Ă���B�\ 2‑26�ɂ��̊T�v�������B���݁C22GHz��FWA�̍��x����}��C26GHz��FWA���ڍs��������g���ĕ҂��i�߂��Ă���[6]�B
�\ 2‑26�@22/26/38GHz��FWA
|
|
22GHz�� FWA |
26GHz��FWA |
38GHz��FWA |
|
���g���� |
22.0-22.4/22.6-23.0 |
25.25 - 27.0 |
38.05-38.5/39.05-39.5 |
|
��L���g���ѕ� |
58.5 MHz |
|
|
|
�ő�`�����x |
156 Mbps�iP-P�j�C10�lbps(P-MP�j |
||
|
�`������ |
�ő�4km���x(P-P)�C���a1km���x(P-MP) |
||
2.5.3.2�@ ���̑���FWA
�Œ�������͔��Œ�i�m�}�f�B�b�N�j�ŗ��p���閳���A�N�Z�X�V�X�e���Ƃ��ẮA22/26/38GHz�т𗘗p����FWA�̑��ɁA5�fHz�і����A�N�Z�X�V�X�e����18�fHz�і����A�N�Z�X�V�X�e��������B���̊T�v��\ 2‑24�\ 2‑27�Ɏ����B
�\ 2‑27�@5GHz��/18GHz�� �����A�N�Z�X
|
|
5GHz�і����A�N�Z�X |
18GHz�і����A�N�Z�X |
|
���g���� |
4.9 – 5.0 GHz |
17.7-19.7GHz (17.7-18.72 / 19.22-19.7 ) �d�C�ʐM�C�����Ɩ��p 17.7-17.85 / 17.97-18.60 / 19.22-19.7�@����ړ��Ɩ��̖����� 17.7-17.85 / 17.85-18.72 / 19.22-19.7 �Œ�� |
|
��L���g���ѕ� |
5,10,20,40 MHz |
36.5 MHz |
|
�ϒ����� |
OFDM |
|
|
�ő�`�����x |
150Mbps���x |
156Mbps���x |
|
�`������ |
�`3km���x |
�`10km���x(�Ό�����) �`2km���x(1�Α���������) |
|
�ő���d�� |
0.25W ���� |
0.5 / 1.0 W |
|
�ő������ |
13dBi |
|
2.5.3.3�@ �Œ�n�����V�X�e��
�@�Œ�n�����V�X�e���̓A�N�Z�X������Ȃ��`���V�X�e���ł���A���̐ڑ��`�Ԃ͒ʏ�1��1�Ɍ�����B���������p����i�Œ�}�C�N���j��G���g�����X����̗p�r�Ŏg�p����Ă���B�\ 2‑28�ɂ��̊T�v�������B
�\ 2‑28�@�Œ�n�����V�X�e��
|
|
6 GHz�� �Œ�ʐM |
11/15/18 GHz�� �Œ�ʐM |
|
���g���� |
5925 – 6425, |
10.7 – 11.7 /
14.4 – 15.35 / |
|
�`���l���� |
|
36.5, 53.5 MHz (11/15GHz��) |
|
�`������ |
�`60km���x |
�`�\��km���x |
|
�ő�`�����x |
150Mbps���x |
150Mbps |
|
�����ǐ� |
NTT�����Ȃǖ�400�� |
��12000�� |
|
���l |
|
�����̍��x�������\����Ă���i2021�j |
2.5.3.4�@ 23GHz�і����V�X�e��
CATV���Ƃɗp�����閳���V�X�e���Ƃ���23GHz�і����`���V�X�e��������B����̓P�[�u���e���r�̎��g���z������̂܂�23GHz �т̓d�g�ɕϊ�����U���ϒ������iFDM-SSB �����j��p���A�P�[�u���~�݂�����ȉӏ��ɗp����BCATV���Ǝ҂����p�\�Ȗ����`���V�X�e���͕\ 2‑29�Ɏ���3���g���т�����B18GHz �т̖����`���V�X�e���́A�P�[�u���e���r���Ǝ҂����p����ꍇ�ɂ́A�d�C�ʐM�Ɩ��p�����ǂ̖����ݔ������p������̂Ɍ��肳��A��艺�肻�ꂼ��60MHz ���̂P�u���b�N�𗘗p���čő�9ch ��`�����邱�Ƃ��ł���B����A60GHz �т̓`���V�X�e���́A���菬�d�͖����ǂƂ��ČʖƋ��͕s�v�ł�����̂́A�o�͂�10mW �ȉ��ł��邱�Ƃ���`��������200m ���x�Ɍ����Ă���B23GHz �і����`���V�X�e���́A400MHz �̑ш悪���邽�߁A18GHz �ɔ�ׂĂ�葽���̃`�����l���`�����\�ł���A�܂��A60GHz �ɔ�ׂĒ������ł̓`�����\�ł���B
�\ 2‑29�@�P�[�u���e���r���Ǝ҂����p�\�Ȗ����`���V�X�e��
|
|
23GHz�� |
18GHz�� |
60GHz�� |
|
���ȖړI |
�L���e���r�W�����@�������Ɨp |
�d�C�ʐM�Ɩ��p |
���菬�d�͖����� |
|
���g���ш敝 |
400MHz |
��艺��e60MHz |
9GHz |
|
�ő�`�� |
65CH |
9CH |
|
|
���� |
CATV���`�����l�������̖����`�� |
����/�ʐM�����`�� |
�~���g�摜�`���p�y�у~���g�f�[�^�`���p |
|
���p�V�[�� |
������R�ԕ�����CATV�l�b�g���[�N�G���A�̊g�� |
�E�n�f�W��M�_���狤���{�݂܂ł̒��p�`�� �E������R��翂ւ̒n��C���g���l�b�g�̉������[�g |
�z�[�������N(�z���̖�����) |
|
�����b�g |
�E60GHz�тƔ�r���āA�`������������ �18GHz�тƔ�r����Ƥ�`��CH�������Ƃ���B |
�60GHz�тƔ�r���ē`�������������B �E�o�����ʐM���\�B |
�ʖƋ����s�v�B |
|
�f�����b�g |
�P�[�u���e���r�̏�����̓`�����ł��Ȃ��B |
�E23GHz�тƔ�r����ƁA�`��CH�������Ƃ�Ȃ��C �E�d�C�ʐM�Ɩ��p�����ǂ̖����ݔ��Ƌ��p������̂Ɍ����B |
�E�����ǖƋ����Ă��Ȃ��̂ŁA���M����\��������B �18GHz�ыy��23GHz�тƔ�r����Ƥ�`���������Z���B |
�@23 GHz�і����V�X�e���̊�{�\����\ 2‑30�Ɏ����B�����ǖƋ��l��NHK��P�[�u���r�W�����Ȃ�33�ǂ���i���M���j�B���݁A��e�ʉ���o�������ȂǃV�X�e���̍��x������������Ă���B
�\ 2‑30�@23GHz�і����V�X�e���̊�{�\��
|
�����ǎ�� |
�Œ�� |
�ėp���^�ړ��� |
�Ӓn�p���^�ړ��� |
|
���g�� |
23.2GHz – 23.6GHz |
23.28GHz – 23.52GHz |
23.2GHz – 23.6GHz |
|
���d�� |
1W�ȉ� |
0.5W�ȉ� |
0.005W�ȉ� |
|
�`���l���� |
65 |
40 |
65 |
|
�`������ |
�p���{���A���e�i�Ό���5�`10km 1�Α��F30cm�p���{���A���e�i�ƃZ�N�^�[�A���e�i�̑Ό���90����2km���x |
�p���{���A���e�i�Ό���5km���x |
�p���{���A���e�i�Ό���100m���x |
|
�A���e�i |
�Ό��^�F���a30cm�ȏ�̃p���{���A���e�i���� �������F�Z�N�^�[�A���e�i |
���a30�`60cm�̃p���{���A���e�i���� |
���a10�`30cm�̃p���{���A���e�i���� |
|
��ȗp�r |
�L���`���H�̕~�݂�����Ȓn��ւ̒��p��� |
�ЊQ���ɂ����鉞�}�����p�`���H �C�x���g���̔ԑg�f�ޒ��p�`�� |
�n��f�W�^�������̓������ |
2.5.4�@ LPWA
LPWA�iLow Power Wide Area�j�͒����d�͂ōL����J�o�[���閳���V�X�e���̑��̂ł���B�[���̃f�[�^�]�����x��Ԍ���M�̕p�x��}���邱�ƂŒ����Ԃ̃o�b�e���[�^�p���\�ƂȂ�A�d���ݔ��̂Ȃ����ł̉��u�Ď���@�퐧��ɗp����IoT�iInternet of Things�j��M2M�iMachine-to-Machine�j�ɓK���Ă���B���LPWA�V�X�e����\ 2‑31�y�ѕ\ 2‑32�Ɏ����B
�\ 2‑31�@���LPWA��p�V�X�e��
|
|
LoRaWAN |
Sigfox |
ELTRES |
ZETA |
|
�d�l |
LoRa Alliance����߂����J�d�l |
��Sigfox�Ђ̓Ǝ��d�l�B��ɃV���K�|�[���E��p��UnaBiz SAS�Ђ������B |
�\�j�[���J�������d�l |
ZiFiSense�Ђ��� |
|
�Ԍ`�� |
���O�A���c |
���O |
���O |
���c |
|
���Ǝ� |
������Ѓ\���R���A�� |
KCCS�i���Z���R�~���j�P�[�V�����V�X�e��������Ёj |
SNC�i�\�j�[�l�b�g���[�N�R�~���j�P�[�V�����Y������Ёj |
|
|
���g���� |
920�lHz�� |
�� |
�� |
��+429MHz? |
|
���g�����H |
125kHz |
100kHz |
200kHz |
|
|
�ʐM���x |
0.3�`50kbps / |
600 bps / |
�ő�80bit/��
|
0.3�`2.4kbps / |
|
�ϒ����� |
CSS |
|
�`���[�v�M�� |
|
|
��M���x |
|
|
-142dBm |
|
|
�M���� |
���� |
�J�Ԃ����M |
4��J�Ԃ����M |
���� |
|
�y�C���[�h |
59�`230 Byte |
���� 8 Byte |
128bit (48bit��GNSS���) |
8, 50 Byte |
|
�ʐM�����ڈ� |
��km�`�\��km |
�ő吔�\km |
���ʂ�100km |
|
|
|
|
���ۃ��[�~���O�\ |
GNSS�W������ |
���p���p�����}���`�z�b�v�ʐM���\ |
�\ 2‑32�@3GPP�����IEEE802.11�n��LPWA�V�X�e��
|
|
NB-IoT |
LTE-M |
NR-RedCap |
IEEE802.11ah |
|
�Ԍ`�� |
���O |
���O |
���O |
���c |
|
���g���� |
(�kTE�o���h) |
�� |
(5G�o���h) |
920 MHz�� |
|
���g���� |
200kHz |
1.4MHz |
20MHz(FR1[7]) 100MHz(FR2) |
1 MHz /4 MHz |
|
�ʐM���x |
21.25kbps(DL) 62.5kbps(UL) |
800kbps(DL) 1Mbps(UL) |
150Mbps(DL) 50Mbps(UL) |
150kbps�`3.3Mbps(1MHz��) / 15Mbps(4MHz��) |
|
�ő�o�� |
200mW |
200mW |
200mW |
20mW |
|
�ʐM�����ڈ� |
(�Z�����[) |
�� |
�� |
1 km (20mW) |
|
���l |
�J�o���b�W�g���@�\[8](23dB) |
�J�o���b�W�g���@�\(15dB) |
����dFDD(�I�v�V����) |
MIMO�A�}���`�z�b�v�Ή��B |
�\ 2‑31�Ɍf�ڂ��Ă���ȊO��LPWA��p�V�X�e���Ƃ��āARPMA��Flexnet������BRPMA�iRandom Phase Multiple Access�j�͕č��T���f�B�G�S��Ingenu�i�A���W�F�k�j�Ђɂ���ĊJ�����ꂽ�Ǝ������ł���DIngenu�Ђ�Qualcomm�Ђ̃G���W�j�A�ō\������C2008�N��On-Ramp Wireless�ЂƂ��đn�݂������C2016�N�ɍ��̎Ж��ɕύX�����DRPMA�͐��E���ʂ�ISM�тł���2.4GHz�т�p���C���p���g������1MHz�ŁC���ڃX�y�N�g���g�U�iDirect-Sequence Spread Spectrum�j��p���Ă���D�ʐM���x��31kbps(UL) / 15.6kbps(DL)�C�ʐM�����͂��悻20�L�����[�g���Ƃ���Ă���D�����͎��c�Ԃł̗��p�݂̂ł��������C2016�N���Ingenu�Ђ����O�ԃT�[�r�X��k�ĂŎ�|���C�Ȍ�CMachine Network ™�Ƃ��Ėk�Ă̎�v30�s�s�ȏ���J�o�[���Ă���D�����ł�2016�N���ɒ��J�H�O���[�v�������ꊇ��d���Ƃœ�������GE���̃X�}�[�g���[�^�[�����̋Z�p���̗p���Ă��������̎��Ƃ�2018�N��Next Power�Ђ֎��ƌp�����Ă���[9]�D
�@FlexNet��Sensus�Ђ̓Ǝ������ł���C2016�N8���ɐ��Z�p��Ƒ��̕�Xylem�ɔ�������A���݂�Xylem�̃u�����h���Œ���Ă���D�č��ł͊�{�I�ɂ�901�`960 MHz�̎��g���т�p���邱�ƂɂȂ��Ă��邪�C901�`902MHz�т�ISM�o���h�̑���928�`960MHz�т̃��C�Z���X�o���h�������ė��p���邱�ƂŊm���ȒʐM��ڎw�����Ƃ��\�ł���DFlexNet��2016�N8���A���Z�p��Ƒ��̕�Xylem�ɔ�������A���݂�Xylem�̃u�����h���ƂȂ��Ă���D�`�����x�͑o������100kbps���x�C�ʐM������5�`20km�ł���D�č��Ɖp���Ő����E�K�X��Ђ̃X�}�[�g���[�^�[���Ȃ��r�W�l�X�ɐ������C���{�ł��W�J���悤�Ƃ��Ă���[10]�D
2.5.5�@ Wi-Fi
Wi-Fi�́AIEEE 802 LAN/MAN Standards Committee �z����802.11 Wireless LAN ��Ɣǂ����肵���K�i�Ɋ�Â������V�X�e���ł���A���ݐڑ����i�x���_�[���قȂ�@��ł����Ă����݂ɐڑ��ł����Ɓj��S�ۂ��邽�߂ɐݗ����ꂽ�ƊE�c�̂ł���Wi-Fi Alliance���F�肵�������@��ɂ���č\�������B�ŋ߂̎��Wi-Fi�K�i��\ 2‑33�ɂ܂Ƃ߂�[11]�B�Ԏ��͑O�̐��ォ��X�V���ꂽ�p�����[�^��\���Ă���B
�\ 2‑33�@Wi-Fi�t���X�y�b�N�K�i�iWi-Fi HaLow™������Sub6�Ή��̂݁j
|
���� |
Wi-Fi4 |
Wi-Fi5 |
Wi-Fi6/6E |
Wi-Fi7 |
|
�K�i�� |
IEEE802.11n |
IEEE802.11ac |
IEEE802.11ax |
IEEE802.11be |
|
�K�i����N |
2009 |
Wave1: 2013, Wave2: 2016 |
2019 |
2024 |
|
���g����(GHz) |
2.4/5 |
5 |
2.4/5/6(6E) |
2.4/5/6 |
|
�`���l���� |
20/40 |
20/40/80, 80+80/160 |
�� |
20/40/80/ |
|
�ϒ����� |
64QAM |
256QAM |
1024QAM |
4096QAM |
|
OFDMA |
�~ |
�� |
�Z |
�� |
|
MIMO(�ő�) |
4�~4 |
8�~8 |
�� |
16�~16 |
|
MU-MIMO |
�~ |
����̂� |
�Z |
�� |
|
�s�[�N�`�����[�g(���[�U) |
600 Mbps |
3.5Gbps 6.9 Gbps |
9.6 Gbps |
46 Gbps |
|
�����E�V�Z�p |
HT �Echannel bonding �ESU-MIMO �EMAC������ |
VHT �EMU-MIMO |
HE �EOFDMA �EBSS-Color �EDSC�Ɠd�͐��� �ETWT |
�EMLO �ERestricted TWT �EMulti-RU |
2.5.5.1�@ Wi-Fi 4��Wi-Fi 5
Wi-Fi4�́A1���[�U(STA)������54Mbps���s�[�N�`�����[�g�Ƃ���O����(802.11a�A802.11g)�ɑ��āA600Mbps��HT(High Throughput)����������BWi-Fi4�ō̗p���ꂽ��v�Z�p�́A��{�`���l��2�`���l�����̑ш敝40MHz��1�`���l���Ŏg�p����`���l���{���f�B���O�ƁA�ő�4�X�g���[������ԑ��d�ł���MIMO�̗̍p�ł���AMAC�t���[���̃I�[�o�[�w�b�h�팸�Ƃ��킹�Ė�11�{�̃s�[�N�`�����[�g��B�����Ă���B������SU(Single User)-MIMO�݂̗̂̍p�ł��邽�߁A�����ɕ����̃��[�U(STA)�ɑ��ċ�ԑ��d��ł��Ȃ��B�Ⴆ��STA��2�{�̃A���e�i���������Ă��Ȃ��ꍇ�AAP��4�A���e�i�ł����Ă��ő�̋�ԑ��d����2�ƂȂ邽�߁A�`�����[�g�͋�ԑ��d���Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׂ�2�{�ǂ܂�ł���B�������AMU(Multi User)-MIMO�ł���A�����ɕ����̃��[�U�̋�ԑ��d���\�ƂȂ�B�Ⴆ�A2�A���e�i��STA��2�䂠��A����炪������4�A���e�i��AP�Ɛڑ�����ꍇ�ɂ͋�ԑ��d���̓g�[�^����4�ƂȂ邽�߁A�S�̂̃X���[�v�b�g��SU-MIMO�Ɣ�ׂČ��シ��B
�@Wi-Fi5��VHT (Very High Throughput)��W�Ԃ��AWi-Fi�K�i�ŏ��߂�MU-MIMO���̗p�����B��������������iAP��STA�j�݂̂ł���B�\ 2‑33�Ɏ������悤�ɁAWave1��Wave2�̋K�i������A�`���l���������̍ő�ш敝��2�{����Ă���BWave2�ł͍ő�Ŋ�{�`���l��4���̃`���l���{���f�B���O���ł���BMIMO�̍ő�A���e�i���g����256QAM�̗̍p�Ƒ��܂��āAWi-Fi4�ɔ�ׂĖ�11�{�̃s�[�N�`�����[�g��B�����Ă���B�܂��AMU-MIMO�̗̍p�ɂ���đS�̂̎����I�ȃX���[�v�b�g�����サ�Ă���B
2.5.5.2�@ Wi-Fi 6/6E
�@Wi-Fi6�́A�s�[�N�`�����[�g�̂���Ȃ��������A�ǂ��炩�Ƃ�����HE (High Efficiency)�A���Ȃ킿�������\�[�X�̗��p���������シ��Z�p�ɏœ_�������A�����ł̎����I�ȃX���[�v�b�g���P��_���Ă���B�A�����C�Z���X�o���h�̖������\�[�X�𗘗p����Wi-Fi��CSMA/CA����{�Ƃ��銱����̎d�g�݂�����邪�AWi-Fi�̕��y�ɔ������̑���ɂ���ĉ��P�̗]�n���萶���Ă����B
�@Wi-Fi6�œ������ꂽBSS-Color[12]��BSS (Basic Service Set)����ʂ���6�r�b�g�̎��ʎq�ł���BBSS-Color�͖����t���[���̎n�܂�������v���A���u�����ɂ���A��������m���邱�ƂŖ����ǂ�MAC�t���[��������O�Ɏ��炪������BSS����̐M�����ۂ���f�������f�ł���B���̃����b�g�̈�́A�f�����X���[�v��Ԃɓ��邱�Ƃŏȓd�͂ɂȂ��邱�Ƃł���B�܂��A�V���ɓ������ꂽDSC(Dynamic Sensitivity Control)�E���M�d�͐����BSS-Color��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�قȂ�AP���אڂ���i���Ɏg�p�`���l������������j�Ō��ʂ�����B���A����STA��������BSS�̃G���A�ɂ�����̂Ƃ���BWi-Fi6�̐����ɂ����āA��BSS�ȊO��BSS��OBSS (Overlapping BSS)�Ɨ������B�]���̈�ʓI�ȃL�����A�Z���X�ł́A�M�������m�̏ꍇ��-62dBm�AIEEE802.11�̏ꍇ��-82dBm��臒l�Ƃ��A����������M�d�͂�����ꍇ��STA�̓`���l��busy�Ɣ��肵�A���M�������ɑҋ@����BDSC�ł͂���臒l��BSS-Color�ɉ����ĕύX����B��̓I�ɂ́A��BSS�̏ꍇ��臒l��Ⴍ�iOBSS�̏ꍇ��臒l�������j�ݒ肷�邱�ƂŁAOBSS����̊��ɂ����STA�̑��M�@����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�������x�h���B��������A���M�����킴�Ɓu�������ɂ����v���đ��M����@��𑝂₷�̂ł���B����A��������ɋ��e����AOBSS�ɂƂ��Ă͋t��STA����̊��ɂ���ĒʐM��W������B�����ŁASTA�̓I�[�v�����[�v����ő��M�d�͂����AOBSS�ɗ^���銱�d�͂���背�x���ȉ��ɗ}����悤�ɂ���B��̓I�ɂ́AOBSS����̐M���������iRSSI���傫���j�ꍇ��STA�̋߂���OBSS������Ɣ��f���Ă���STA�͑��M�d�͂�Ⴍ���A�t��RSSI���������ꍇ�͑��M�d�͂�傫������B���̐���́ABSS-Color�ɂ���Ď�BSS��OBSS��f������ʂł��邩����ʓI�ɍs����B�܂�A�v���A���u���������̎�M�łnBSS����ʂł��邩��A�K�v�̂Ȃ�MAC�t���[���S�̂����X�Ǝ�M���鎞�ԁi�Ə���d�́j�̖��ʂ��Ȃ���̂ł���BDSC�ɂ��S�̂̃X���[�v�b�g���P�ʂ͏����ɂ��قȂ邪�A����[13]�ł�10%�O��̌��ʂ�������Ă���B�Ȃ��ABSS-Color��1����63�܂ł̒l�ł���A���ꂽ�ꏊ�ł͍ė��p�����BOBSS�œ����BSS-Color���g�p����Ă���ꍇ�́ASTA��AP�ɕ��Ď����I�ɒ�������d�g�݂��p�ӂ���Ă���[14]�B
Wi-Fi6�œ������ꂽOFDMA��1��OFDM�V���{��(�����̃T�u�L�����A�ō\������Ă���)���̃��[�U(STA)�ŋ��L����A�N�Z�X�����ł���A4G�ȍ~�̃Z�����[�V�X�e���ł��̗p����Ă���BOFDMA�ł́AOFDM�V���{�����\�����镡���̃T�u�L�����A��RU(Resource Unit)�ƌĂԒP�ʂɕ������A���ꂼ���RU��d�g��Ԃ��ł��K�������[�U�Ɋ��蓖�Ă�B����ɂ��A�e�T�u�L�����A�̗��p�����i�ш敝������̎����X���[�v�b�g�j�����サ�ATDMA�ɔ�ׂăV�X�e���S�̂̕��σX���[�v�b�g�����P���邱�Ƃ��ł���B
Wi-Fi6��HE�̑���IoT���ӎ������@�\����������Ă���BBSS-Color�����͂Ƃ�����STA�̏ȓd�͉���ړI�Ƃ���802.11ah�ōŏ��ɓ������ꂽ���̂ł���B���ɂ�802.11ah�ɂ���ȓd�͋@�\������TWT (Target Wake Time)��Wi-Fi6�ɍ̗p����Ă���AAP��STA���ɃX���[�v��Ԃ��Ǘ����Ă��ߍׂ����d�͊Ǘ����s�����Ƃ��ł���B����܂ł̏ȓd�͋@�\��AP��STA����ĂɃX���[�v��������d�g�݂ł�����[15]�B
2.5.5.3�@ Wi-Fi 7
������AP���אڂ���OBSS �� (�܂�dense operation�Ȋ�)���ł̌����^�p�Ɏ���������Wi-Fi 6�ɑ��āAWi-Fi 7�ł͓`�����[�g�̌���ɏd�_����A�����Ă���B���̔w�i�ɂ́A���ɍL���ш敝��L����6GHz�т̊��p�ƁA16K����X�g���[�~���O�⍂����VR�EAR�ł̗��p���z�肳��Ă���B����ɑo�����A�v���Ő[���v�����邽�߂ɂ͒�x���������K�v�ł���A�܂��e�[���̍����`�����V�X�e���S�̂ŃT�|�[�g���邽�߂Ɏ��g�����p�����̂���Ȃ���P�����߂���ł��낤�BWi-Fi7�͎��ɏq�ׂ�Z�p�����Ă����̗v���ɑΏ�����B
�܂��\ 2‑33�} 2‑58�Ɏ����悤�ɁAWi-Fi7�ł́A�ő�Ŋ�{�`���l��16���̃`���l���{���f�B���O���s�����Ƃ��ł���B����͏]����2�{�ł���A���݂̎��g���v�����ł�6GHz�тł̂ݗ��p�ł���B�܂��A�ϒ������͍ő��4096QAM���K�p����A����ɂ��r�b�g���[�g�̌����1.2�{�ł���BMIMO�ɂ���ԑ��d�����ő�16�ƁA�]����2�{�ł���B�����ɂ��s�[�N�`�����[�g(�K�i��̍ő�l)�͖�4.8�{��46Gbps�ƂȂ����B
Wi-Fi7�̐V���ȋ@�\�Ƃ���MLO(Multi-Link Operation)������B����͈��AP-STA�Ԃɂ����āA�����ɕ����̎��g����(2.4GHz / 5GHz / 6GHz)�̕����`���l���𗘗p���ăf�[�^�̑���M���s�����̂ł���B�����ɗ��p���镡���̃����N�ňقȂ�f�[�^�����`�����č����`�����������A���邢�́A�����f�[�^���d���`�����邱�ƂŐM������������B��҂̏ꍇ�A�����`���l����������busy�ƂȂ�p�x�͒P��̃`���l����busy�ƂȂ�p�x����ʂɂ͒Ⴍ�A����Ēx�������̉��P�����҂����BSTR���[�h�ł͕��������N��p���ē����ɑ���M���\�ƂȂ�A����M�����݂ɍs���ꍇ�Ɣ�ׂđ��M�܂ł̑҂����Ԃ��������A����ē`���x��������ɒጸ����B�܂��AWi-Fi 6�œ������ꂽTWT��`���x���̒ጸ�Ɋ��p����Restricted TWT���V���ɓ������ꂽ�BTWT�ł�STA����SP (Service Period;�T�[�r�X����)��݂��A����ȊO�̊��Ԃł͂���STA�̓X���[�v��ԂƂȂ�BSP�̊��Ԃ́ASP���قȂ鑼��STA�Ƌ������邱�ƂȂ����̃`���l���𗘗p�ł���̂ŁARestricted TWT�ł͂�����time-sensitive�ȃg���q�b�N�����蓖�āA�x���W�b�^�[�̒ጸ��}��B
�@�܂��A���g�����p�����̌����}��V���ȋZ�p�Ƃ��āAMulti-RU��preamble puncturing������BWi-Fi6�œ������ꂽOFDMA�́A���[�U(STA)���Ɉ��RU�𗘗p������̂ł������B���̕��Q�͗Ⴆ�ΐڑ����[�U�����Ȃ��ꍇ�ɂ��ׂẴ`���l���ш悪���p����Ȃ����Ƃł���BWi-Fi7�ł͕�����RU�����p�ł���Multi-RU���������ꂽ�B���g������̗��ꂽRU�����p���邱�Ƃ��ł��邽�߁A���g���_�C�o�V�`���ʂ����邱�Ƃ��ł���Bpreamble puncturing��Wi-Fi6�ŃI�v�V������������Ă�����Wi-Fi7�ŕK�{�@�\�ƂȂ����B�Ⴆ���[�_�[�Ȃǂɂ���ē���̎��g���ш悪�������Ƃ��ɁA���̑ш�݂̂����O���ė��p����@�\�ł���Bpuncturing�̒P�ʂ�20MHz���ł���B�]����80MHz�ȏ�̃`���l���{���f�B���O�̍ۂɊ�����ƁA20�lHz����Primary�`���l���������g�p���A����ȊO�̃`���l��(�ш敝60MHz �ȏ�)�͎g�p�ł��Ȃ������B
2.5.5.4�@ ������K�i�����iWi-Fi 8�j
�@Wi-Fi 7�̎��̐���ƂȂ�Wi-Fi 8��S���K�i�̌����ǂƂ��āAIEEE802.11bn UHR (Ultra High Reliability)-SG(Study Group)��2022�N7���ɐݗ�����A�oAR(Project Authorization Request)�̈ψ���F���o��2023�N11���܂ł�UHR-TG(Task Group)�𗧂��グ�A2028�N�����[�X�̗\��ƂȂ��Ă���B���̊�b�ƂȂ�l�����́AWi-Fi 7�œ�������MLO(Multi Link Operation)�������ɂ߂č����M�����̎����ł���B���̔w�i�Ƃ��āA�l��̗̂��p����@��Ԃ̖����ʐM�̎��v����荞�ޑ_��������BWi-Fi 7�ɑ��錻���_�ł̓����i�����ۑ�j�́A�@ ��SINR�ł̓`�����[�g�A�A�ړ�����G���A���܂����ӏ��ł̒x����W�b�^�[�A�B�`���l�������[�X�A�C�d�͏����peer-to-peer (1��1)�̒ʐM�`�ԁA�ƂȂ��Ă���B
2.5.5.5�@ ���g���сiWi-Fi�j
Wi-Fi���g�p�ł�����g���т͒i�K�I�Ɋg�傳��Ă����BWi-Fi�̓��������痘�p����Ă���2.4GHz�т�ISM�o���h�ł����邪�A�} 2‑58�Ɏ����ʂ�A�ш敝83.5�lHz(2.4GHz�`2.4835GHz)�̒���20�lHz���̊e�`���l�����I�[�o�[���b�v����`��13�`���l������`����A����ɓ��{�ł̓`���l��14��2.484GHz�ɒ�`����Ă���B2.4�fHz�т�Wi-Fi�`���l�����݂��Ɋ����Ȃ��悤��(�I�[�o�[���b�v���Ȃ��悤��)�ő���ɗ��p����ꍇ�́A�`���l��1�A6�A11�����14�̂ݗ��p����B�������A�`���l��14��IEEE 802.11g�ȍ~�g�p����Ȃ�[16]�B
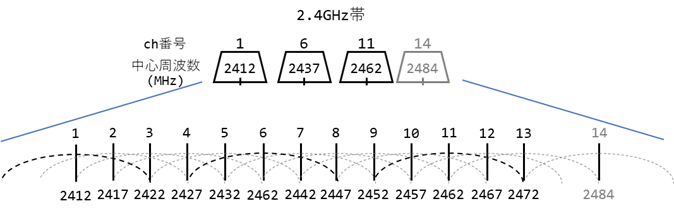
�} 2‑58�@Wi-Fi���g�p������g���i2.4GHz�сj
Wi-Fi���g�p����5�fHz�т́AW52(5.2GHz��)�AW53(5.3GHz��)�AW56(5.6GHz��)�ɕ��ނ����B�} 2‑59�Ɏ����悤�ɁA2005�N5���̑����ȗ߉����ɂ��AW52��4�`���l��(#34,#38,#42,#46)�̒��S���g�����ύX����A�����W53��4�`���l��(#52,#56,#60,#64)���lj����ꂽ�BW53��W52�Ɠ��l�ɉ����ł̎g�p�Ɍ��肳���B�܂��AW53�𗘗p����A�N�Z�X�|�C���g��DFS (Dynamic Frequency Selection)��TPC (Transmit Power Control)�̋@�\�������K�v������iDFS��TPC�͌�ɏq�ׂ�j�B
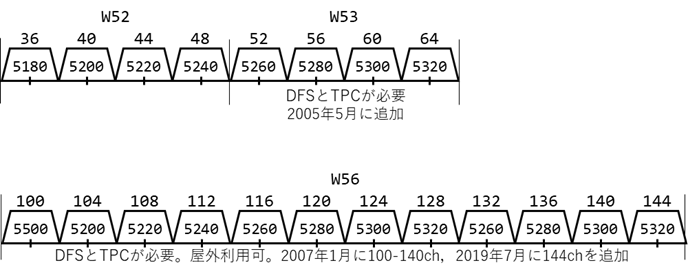
�} 2‑59�@Wi-Fi���g�p������g���i5GHz�сj
����2007�N1���̑����ȗ߉����ɂ��AW56��11�`���l��(#100, #104, #108, #112, #106, #120, #124, #128, #132, #136, #140)���lj�����A2019�N7���ɂ����1�`���l��(#144)���lj����ꂽ�BW56��W53���l��DFS��TPC�̋@�\��K�v�Ƃ��邪�A���M���ׂ��́A���O�ł̗��p���\�ŁA���o�͓d�͂̋��e�l��W52/W53(eirp200mW�ȉ�)�ɔ�ׂ�5�{�i��1W�ȉ��j�ɂȂ��Ă���_�ł���B
������2022�N9���̉����ɂ��AW52�̎����ԓ����p�ƁA6GHz�т̗��p���F�߂�ꂽ�BW52�͂���܂őD���ƍq��@���܂މ������p�����F�߂��Ă��Ȃ������B6GHz�тɂ��ẮA5.925GHz����6.425GHz�܂ł�500MHz���͈̔͂�24�`���l�����������ꂽ�B���̗��p�́A�\ 2‑34�Ɏ����悤�ɁAW52�̎����ԓ����p�ł͏]����1/5(eirp=40mW�ȉ�)�A6GHz�т̍������p�ɂ��ẮA�����Ɍ��肳���LPI�N���X�ƁA�����O�ŗ��p�ł���VLP�N���X��2��ނ��K�肳��Ă���BLPI�̑��M�o�͂�W52,W53(��200mW)�Ɠ����AVLP�͂���1/8(��25mW)�ł���B6L�ł�DFS���s�v�ł���D
Wi-Fi6E�ɂ́C������̃N���X�ł���SP (Standard Power)���K�肳��Ă���D���̃N���X�ł́CDFS�ɑւ����g�����p�̎d�g�݂ł���AFC (Automated Frequency Coordination )�@�\�̉��ōő�PW�̏o�͂����e�����D���������{�����ł͎g�p���F�肳��Ă��Ȃ��D���̃N���X��AP��AFC System�ɐڑ�����Ă���C�g�p���������g���тƑ��M�o�͂�AP��ID����шʒu���ƂƂ��Ƀ��N�G�X�g����ƁC���p�ł���`���l���Ƒ��M�o�͂��m�炳���d�g�݂ɂȂ��Ă���[17]�D
�\ 2‑34�@Wi-Fi���g�p�ł���5GHz�т�6GHz�т̕���
|
���� |
W52 |
W53 |
W56 |
6L |
|
���g���͈� |
5150-5250 |
5250-5350 |
5470-5725 |
5925-6425 |
|
�`���l���� |
4 |
4 |
12 |
24 |
|
DFS |
�s�v |
�K�v |
�K�v |
�s�v |
|
���O���p*1 |
�~*2 |
�~ |
�Z |
VLP�̂݁Z |
|
�ő�o��(eirp, 20MHz������) |
�����F23dBm �ԓ��F40mW |
23dBm*3 |
30dBm*3 |
LPI�F 23dBm VLP�F14dBm |
(*1�F��ԓ��E�D�����E�q��@���͉��O�ł͂Ȃ���������)�i*2�F�����ԓ��͗��p�\�j�i*3�FTPC�������ꍇ�͂��̔����j�Ȃ��A�@�����������ł̗��p��2.4GHz�шȊO�F�߂��Ă��Ȃ��B
2.5.5.6�@ DFS�iDynamic Frequency Selection�j
5GHz�т͋C�ۃ��[�_�[���g�p���Ă���AWi-Fi������������邽�߂̋@�\�Ƃ���IEEE802.11h ��DFS���K�肳��Ă���BDFS�ł͂܂��A�g�p����`���l���Ƀ��[�_�[�d�g�����Ȃ����ǂ����������ԁi�ʏ��60�b�j�T��B���̊m�F��CAC (Channel Availability Check) �ƌĂԁBCAC���N���A���ă`���l���g�p���n�߂Ă��A��Ƀ��[�_�[�d�g�̌��o�͍s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����In-Service Monitoring�Ƃ����BIn-Service Monitoring �̊��ԂɃ��[�_�[�d�g�����o�������݂₩�Ɂi10�b�ȓ��j�d�g�̔��M���~���Ȃ���Ȃ炸�A���̃`���l���͈�莞�ԁi30���ȏ�j�g�p�ł��Ȃ��iCAC�ł̌��o�̍ۂ����l�j[18]�B
2.5.5.7�@ TPC (Transmission Power Control)
TPC�͉q���ʐM�Ƃ̊������炷���߂ɁA�A�N�Z�X�|�C���g�ƒ[���̑o���ő��M�d�͂�������@�\�ł���BDFS�Ɠ��l�AIEEE 802.11h�ŋK�肳��Ă���B�������A�K�{�@�\�͎���5���ڂł���A��̓I�ȓd�͒l�̋K��͂Ȃ��BTPC�@�\�Ƃ��Ă͑��M�d�͂�ύX����i�K�Ȓl�ɒ�������j���Ƃ��ł���Ηǂ��Ƃ���Ă���悤�ł���[19]�B
Ÿ DFS/TPC ����������Ă��� STA ����� AP �́A���M�t���[���� Capability Bit �� Spectrum Management ���Z�b�g���邱�ƁB
Ÿ AP ����� AdHoc ���[�h�� STA �̓r�[�R������� Probe-Response �� Country IE ����� Power Constraint IE ���܂߁A�n�斈�̍ő呗�M�o�͒l�ƒጸ�v���l(Mitigation Requirement)��ʒm���邱�ƁB
Ÿ STA �� AP �ɑ��鑗�M�t���[���� Power Capability IE ���܂߁A���M�o�͒����\�͈͂�ʒm���邱�ƁB
Ÿ STA ����� AP �̑��M�o�͂� �n��ɂ���Ē�߂�ꂽ�ő�o�͋K��ɏ]�����ƁBSTA �� AP ���� Mitigation Requirement �l���w�����ꂽ�ꍇ�A�X�ɂ��̂ԂM�o�͂������邱�ƁB
Ÿ AP ����� AdHoc ���[�h�� STA �̓r�[�R������� Probe-Response �� TPC Report IE ���܂߁ALink Margin=0, Transmit Power=���g�̑��M�o�͂�ʒm���邱�ƁB
�Ȃ��A�[��STA�̓A�N�Z�X�|�C���g�̋��Ȃ�W53�AW56�̓d�g���g�p�ł��Ȃ����߁AW53�AW56�т̃`���l����AP���A�N�e�B�u�X�L�����ł��Ȃ��i�v���[�u�v�����o���Ȃ��̂Łj�B
2.5.5.8�@ IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow ™)
IEEE 802.11ah�iWi-Fi HaLow™�j�́A�g�ѓd�b�̕���ł̓v���`�i�o���h�ƌĂ��1GHz������ISM Band�𗘗p����Wi-Fi�̋K�i�ł���D�ʏ��Wi-Fi�ɔ�ׂē`�����[�g�͒Ⴂ�i�ő�15Mbps�j���̂́C��Z�����[�nLPWA��p�V�X�e��(�\ 2‑31�Q��)�ɔ�ׂ�Δ�r�I�����CIP�e�a���������B�������̒ʐM�i1�`��km���x�j���\�ŁC�[���̏���d�͂�}���邱�Ƃ��ł���B������\ 2‑35�Ɏ����B
�@���{�ł�2022�N9����11ah�̗��p���\�ƂȂ����B���Y11ah�Ή��f�o�C�X���o�ꂵ�A�R�ԕ��ł̒��b�Q��̂��߂̃J�����f����A���ݕ��ł̊C�m�Ď��Ȃǂ̏��p�@�ɂ����؎������s���Ă���B�X�}�[�g�_�Ƃ⋙�ƁA��K�͍H��⏤�Ǝ{�݂Ȃǂŗ��p�����IoT�f�o�C�X��X�}�[�g�V�e�B�Ƃ���������ł̗��p�����҂���Ă���B���ݎg�p�ł�����g����920.5�`928.1MHz�ł��邪�A����AMCA�V�X�e���̎��g���ڍs�ɔ������p�\�ƂȂ�850�`860�lHz��930�`940MHz�̈ꕔ���lj������\��������[20]
�\ 2‑35�@IEEE802.11ah ��v�p�����[�^
|
|
IEEE802.11ah (Wi-Fi HaLow TM) |
|
�Ԍ`�� |
���c |
|
���g���� |
920 MHz��(920.5 – 928.1)�A�����C�Z���X |
|
�`���l���� |
1 MHz /4 MHz |
|
�ʐM���x |
150kbps�`3.3Mbps(1MHz��) / 15Mbps(4MHz��) |
|
�ő�o�� |
20mW |
2.5.5.9�@ 60GHz��FWA�@�~���g�iWiGig�j
�M�K�r�b�g���̍����`�����������邽�߁A�L�����g���т����p�ł���~���g�i���60GHz�сj��p���閳���ʐM�K�i�Ƃ���WiGig (Wireless Gigabit)��2009�N�Ƀ����[�X���ꂽ�B���̊��͍ő�`�����x7Gbps��B��������̂ŁA���N5���Ɍ������ꂽ�ƊE�c��WiGig�A���C�A���X���p�\�R���₻�̎��Ӌ@��ł̗��p��z�肵�č��肵�����̂ł���B������Wi-Fi�̍ŐV�K�i(Wi-Fi 4)�ł́A�ő�`�����[�g��600Mbps�ł������B����AIEEE802.11�W������Ɣǔz����ad�^�X�N�O���[�v�ɂ����Ė���LAN�̃~���g���p����������A������WiGig���̗p�����`��2012�N��IEEE802.11ad�����肳�ꂽ�B�Ȃ�WiGig�A���C�A���X��2013�N��Wi-Fi�A���C�A���X�ɓ�������Ă���B
802.11ad��PHY�d�l�͕\ 2‑36�Ɏ����悤��4����BOFDM PHY�̓I�v�V�����ł���V���O���L�����A(SC) PHY��K�{�Ƃ���B�ϒ�������QPSK�ȏ�̓I�v�V�����ƂȂ�A�V���O���L�����A�ł�16QAM�܂ŁAOFDM PHY�ł�64QAM�܂łƂł���B�K�{�d�l�ɂ�����ő�`�����[�g��1155Mbps�A�V���O���L�����A�d�l�ł�4620Mbps (16QAM�A��������3/4)�AOFDM PHY�ł�6756.75Mbps�i64QAM�A��������13/16�j�Ƒ傫���قȂ�B
�@802.11ay�ł́A�ő�4�`���l���܂ł̃A�O���Q�[�V������8�X�g���[���܂ł�MIMO��ԑ��d���\�ł���B�ő原���̕ϒ������̓V���O���L�����A�̏ꍇ��64QAM�AOFDM�̏ꍇ��256QAM�ɂȂ����B�܂��Ashort GI�i�K�[�h�C���^�[�o���j�̓����ɂ��A�����`�����[�g�����シ��B�Ⴆ�A�V���O���L�����A�̏ꍇ�A�ő�`�����[�g��11ad��4620Mbps (16QAM�A��������3/4)����A8662.5Mbps(64QAM�C��������7/8)�ɂȂ�B����ɑO�q�̃`���l���A�O���Q�[�V�����Ƌ�ԑ��d���K�p�����ƁA�K�i��̃s�[�N�`�����[�g��277.2Gbps�ɂȂ�B
�\ 2‑36�@�~���g�Ή�Wi-Fi�̏���
|
�K�i�� |
IEEE802.11ad / WiGig |
IEEE802.11ay |
|
�K�i����N |
2009/2011 (WiGig 1.0/1.1) 2012 (802.11ad) |
2021 |
|
���g���� |
60 GHz (57-66GHz) |
�� |
|
�`���l���� |
2.16 GHz |
2.16/4.32/6.48/8.64 GHz (�A�O���Q�[�V����) |
|
�ϒ�����(�ő原��) |
16QAM (SC PHY) 64QAM�iOFDM PHY�j |
64QAM (SC PHY) 256QAM�iOFDM PHY�j |
|
MIMO��ԑ��d |
�Ȃ��i�r�[���t�H�[���̂݁j |
�ő�8�X�g���[�� |
|
�ʐM�����ڈ� |
|
�� |
2.5.6�@ ���̑�����
2.5.6.1�@ LAA�FLicensed Assisted Access�ALTE-U (Unlicensed)
LAA�iLicensed Assisted Access�j�Ƃ́A���C�Z���X�o���h��p����Z�����[�V�X�e�����A����LAN�������͖���LAN�����p����A�����C�Z���X�o���h�����p���ăX���[�v�b�g�����コ������̂ł���B���̋Z�p��LTE-Advanced (�����[�X10)�œ������ꂽ�L�����A�A�O���Q�[�V����(CA)�ƁA2015�N�ɐݗ������ƊE�c��LTE-U Forum�����肵��LTE-U�iLTE-Unlicensed�j���x�[�X�ɂȂ��Ă���B
�L�����A�A�O���Q�[�V�����͕����̃L�����A�𑩂˂č����`������������Z�p�ł���A��ƂȂ�L�����A�iPrimary cell�j�ɕʂ̃L�����A�iSecond cell�j���������Ĉ�̃����N���\������B�܂�LTE-U�́AWi-Fi�Ȃǂ̑��̖����V�X�e���V�X�e�������p����A�����C�Z���X�o���h�œ��삷��悤�ɁALTE�̋K�i�����ς������̂ł���A�ƊE�c�̂ł���LTE-U Forum��2015�N�ɍ��肵���B������LTE-U�̓L�����A�Z���X�̎d�g�݂�����Ă��炸�A5GHz�тł̃L�����A�Z���X���`���t�����Ă��郈�[���b�p����{�ł͗��p���ł��Ȃ������B
LAA�ł́A���C�Z���X�o���h�̃L�����A��Primary cell���A�A�����C�Z���X�o���h�̃L�����A��Secondary cell���g�p���A�ǂ���̃Z���ł�LTE�̖����K�i��p����B������LTE-U�ƈقȂ�A�A�����C�Z���X�o���h�ɂ����Ă̓L�����A�Z���X�iLBT�GListen Before Talk�j���K�p�����BPrimary cell�̊�n�ǂ̓f�[�^�̕����E������S���ASecondary cell�ƘA�g����B�����[�X13�i2016�N�j�ɂĉ�������̃L�����A�A�O���Q�[�V�������K�肳��A�����[�X14�i2017�N�j�ɂď��������K�肳�ꂽ�BCA��LAA�̈Ⴂ��}�Ɏ����B�Ȃ������[�X13�ł́ALAA�̑��ɁALTE�Ɩ���LAN���A�O���Q�[�g����LWA (LTE/WLAN aggregation)���K�肳��Ă���B
2.5.6.2�@ NR-U�F(New Radio - Unlicensed)
3GPP�����[�X16�ł́A5�f�V�X�e���ɂ����ăA�����C�Z���X�o���h�𗘗p����NR-U���K�肳�ꂽ�BLAA�Ɠ��l�ɁAPrimary cell�ł�NR�����C�Z���X�o���h�Ŏg�p���ASecondary cell��NR-U�𗘗p����`�ԁi�A���J�[�^�j�ɉ����āANR-U�݂̂ł̉^�p�ɂ��A�����C�Z���X�o���h�̗��p�`�ԁi�X�^���h�A���[���^�j���T�|�[�g����Ă���BNR-U���z�肷����g���т�5GHz�т�6GHz�тł���A���胊���N�ōő�320MHz���A���ōő�80MHz���ł���B���{�ł�NR-U���p�͌����_�ŔF�߂��Ă��Ȃ��B
2.5.6.3�@ FPU
Field Pick-up Unit�Ƃ́A�����ԑg�̉f���≹�������ꂩ��X�^�W�I�֓`������V�X�e���ł���B�����ł́A�\ 2‑37�Ɏ������g���т��g�p����Ă���B
|
���g���ď� |
���g���� |
�ǐ� |
���g���� |
�`�� |
�Œ� |
�ړ� |
���l |
|
1.2/2.3GHz�� |
1240-1300MHz[60]/ 2330-2370MHz[40] |
117 |
18MHz |
145Mbps 10Mbps |
|
|
TDD�o���� |
|
B�o���h |
5.850-5.925GHz |
322 |
18MHz |
300Mbps |
50 |
4 |
�ΔgMIMO |
|
C�o���h |
6.425-6.570GHz |
2,492 |
|
|
|
|
|
|
D�o���h |
6.870-7.125GHz |
3,064 |
|
|
|
|
|
|
E�o���h |
10.25-10.45GHz |
2,191 |
|
|
7 |
3 |
|
|
F�o���h |
10.55-10.68GHz |
1,299 |
�� |
�� |
�� |
�� |
|
|
G�o���h |
12.95-13.25GHz |
5 |
�� |
�� |
5 |
3 |
�� |
|
42GHz�� |
41-42GHz |
4 |
125MHz |
210Mbps |
3-5 |
0.05 |
HD�̔k�`�� |
|
55GHz�� |
54.27-55.27GHz |
3 |
�� |
�� |
�� |
�� |
�� |
|
120GHz�� |
116-134GHz |
0 |
18GHz |
12Gbps |
0.5-1 |
-- |
4K�E8K�k�`�� |
2.5.6.4�@ �ߐږ����iUWB�j
UWB�iUltra-Wideband�j�́A���ɍL�����g���ш敝�i�ʏ�500MHz�ȏ�j�����ϒ��g��p���閳���ʐM�����̑��̂ł���B�ߋ����ł̍����ʐM�⍂���x���ʂ��\�Ƃ���B��\�I�ȋK�i�́A�\ 2‑38�Ɏ���IEEE802.15�V���[�Y�ł���B
�\ 2‑38�@UWB�V�X�e���̎�ȋK�i
|
�K�i�� |
���� |
���g���� |
|
IEEE802.15.4-2020 |
�����x������_���������w�K�i�ƁA�V���v���ȕϒ�������p����y�ʂȋ@��\����1Mbps�ȉ��̒ᑬ�ʐM��_�����d�l�B�`���l������499.2MHz |
Low band : 3.1 – 4.9 GHz High band: 6.0 – 10.6 GHz |
|
IEEE802.15.6 |
�̂���̃o�C�^���f�[�^���`�����邽�߂̒ʐM�K�i�BUWB�����e���邱�ƂŃV���v���ȉ�H�\���ƒ����d�͂�_���Ă���B |
|
|
IEEE802.15.8 |
�[���ԒʐM�̂��߂�PHY�EMAC�w�K�i |
4.20 – 4.80 GHz 7.25 –10.25 GHz |
�@UWB��2002�N�ɕĘA�M�ʐM�ψ���iFCC�j�̔F������A�������p���J�n�����B���{�ł́A2006�N�ɒʐM�p�r�i3.4�`4.8GHz�сA7.25�`10.25GHz�сj�A2010�N�ɏՓ˖h�~�p�ԍڃ��[�_�[�p�r�i22�`29GHz�сj�A2013�N�ɃZ���T�[�p�r�i7.25�`10.25GHz�сj�ł̗��p�����x�����ꂽ�B�ʐM�p�r�ƃZ���T�[�p�r�͉����Ɍ��肳��Ă������A2019�N�ɐ��x�������s���A7.587�`8.4GHz�т̉��O���p���\�ɂȂ����BApple��2019�N�ɔ�������iPhone11�V���[�Y��UWB�ɑΉ����A�Ȍ�UWB�͍L���g����悤�ɂȂ����B���Ђ��̔�����AirTag��UWB�ɂ���ăZ���`���[�g���I�[�_�[�ł̑������\�Ƃ��A�������Ǘ��Ȃǂɗp������B�܂������Ԃ̖����L�[�V�X�e���ł�UWB�̗̍p���i��ł���B�V�����V�X�e���͖����L�[�̏��L�҂��ԗ��̋߂��ɂ��邱�Ƃ�UWB�̑����@�\�Ŋm�F���A�d�g�̕s���Ȓ��p�ɂ������i�����[�A�^�b�N�Ƃ����j��h���d�g�݂����Ă���B
2.5.6.5�@ �ߐږ����iNFC�j
�@NFC�iNear Field Communication�j��UWB��������ɋ߂������ł̒ʐM��z�肷��B��ڐGIC�J�[�h��d�q�^�O��NFC�̑�\��ł���B���x��̖��̂́u�U�����ǂݏ����ʐM�ݔ��v�ł���A13.56MHz�}6.78kHz�̎��g���т�p����B13.56MHz�𗘗p�����ڐG�C���^�t�F�[�X�̍��ەW���K�i�Ƃ��āA�ߐ�(Proximity)�^��ISO/IEC 14443�n�ƋߖT(Vicinity)�^��ISO/IEC 15693�n������B�O�҂̒ʐM�����͍Œ�10cm���x�ł����ɔ�ڐGIC�J�[�h�ɗ��p����Ă���B��҂̒ʐM������70cm���x�ł��蕨���̏��i�^�O�ɗ��p����Ă���B�\ 2‑39�ɋߐڌ^�̍��ەW���K�i�̊T�v�������B
�\ 2‑39�@�ߐڌ^NFC�̍��ەW���K�i
|
���� |
�������� |
�ʐM�v���g�R���� |
�T�v |
|
Type A (NFC-A) |
ISO/IEC 14443 |
ISO/IEC 18092 |
• ��@�\�A���e�ʂ̃J�[�h�B�I�����_�̃t�B���b�v�X�Ђ��J������MIFARE���N���B�P�@�\�̃J�[�h�Ƃ��ČÂ�����̗p����Ă���B • ���ގ���p�J�[�h�A�����w���p���l�F�J�[�htaspo�A�ꕔ�̔�ڐG�N���W�b�g�J�[�h����(�}�X�^�[�J�[�h PayPass)�Ȃǂɍ̗p����Ă���BNTT��IC�e���t�H���J�[�h��ꕔ�̃o�X��ԗp�J�[�h�ɂ��̗p����Ă����B |
|
Type B (NFC-B) |
ISO/IEC 14443 (Type B) |
• ���@�\�A���Z�L�����e�B�̃J�[�h�BPKI�ɑΉ��������̂������A�������n�̃J�[�h�ɍL���̗p����Ă���B • �l�ԍ�(�}�C�i���o�[)�J�[�h�A�Z����{�䒠(�Z��)�J�[�h�A�p�X�|�[�g�A�^�]�Ƌ��A�ݗ��J�[�h�ɍ̗p����Ă���B |
|
|
Felica (NFC-F) |
(ISO/IEC 14443 �Ɠ���ASK�ϒ�) |
ISO/IEC 18092 |
• ��@�\�A���e�ʂ̃J�[�h�B�\�j�[���J���B���i�����������������ł���B���{�ł͌�ʌn��d�q�}�l�[�ōL���̗p����Ă���B • Suica�APASMO�AQUICPay/QUICPay+�A���T�C�t�P�[�^�C�A�y�VEdy�Ananaco�A�Ȃǂɍ̗p����Ă���B |
��3�� �T�[�r�X�E�R���e���c�Z�p
3.1�@ �����T�[�r�X
3.1.1�@ �����̍��x���i4K�E8K�Ή��j
�{�͂ł́A�����̍��x���Ƃ��āA�������דx�ł���4K�E8K�t�H�[�}�b�g�A���P�x���̋Z�p�ł���HDR�iHigh Dynamic Range�j�A�ŐV�̕����E�ʐM�T�[�r�X�ɑΉ����邱�Ƃ��\�Ƃ���MMT�iMPEG Media Transport�j���d�������A�������ꂽ�X�N�����u�������ɑΉ��\��ACAS�A�܂�4K�E8K�����̂��߂̓`���Z�p�Ƃ��āA�q���f�W�^�������ƃP�[�u���f�W�^�������̗�ɂ��Đ�������B����ɁAVR�iVirtual Reality�j�f���̑�\�I�Ȍ`�Ԃł���360�xVR�f���ɂ��Ă���������B
�q���f�W�^�������ł́A���o124/128�xCS�f�W�^�������ł̓X�J�p�[JSAT��2015�N3������4K���p�������J�n���ABS�f�W�^�������ł�4K�E8K�̎���������NHK��2016�N8���ɁAA-PAB��2016�N12���ɊJ�n���A2018�N12���ɂ�4K�E8K�̎��p�������J�n���ꂽ�B����ɁA���o110�xCS�f�W�^�������ł�2017�N��4K�̎����������J�n���A2018�N��4K���p�������J�n���ꂽ�B
IP�ɂ������iIPTV�j�Ƃ��ẮANTT�Ղ�炪2015�N12������4K�̎��p�������J�n�����B
�P�[�u���e���r�ł́ARF�ɂ�鎩�������2015�N12���ɃP�[�u��4K�Ƃ��Ď��p�������J�n���AIP�ɂ��P�[�u��4K������2016�N4������J�n���Ă���B
�����Ȃ������Ă���u4K�E8K���i�̂��߂̃��[�h�}�b�v�v���} 3‑1�Ɏ����B
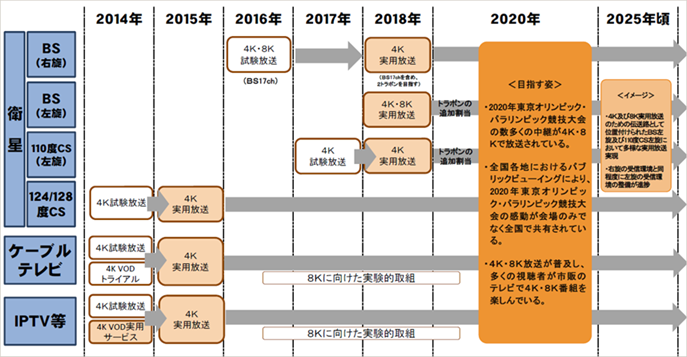
�} 3‑1�����Ȃ�4K�E8K���i�̂��߂̃��[�h�}�b�v
3.1.2�@ 4K�E8K�����̂��߂̍��x��
�{�߂ł́A4K�E8K�����̍��x���ƁA�֘A�������x���Z�p�Ƃ��āAHDR�iHigh Dynamic Range�j�AMMT�iMPEG Media Transport�j���d�������AACAS�ɂ��Đ�������B�����̋Z�p���W���鑗�M���Ǝ�M���̕������} 3‑2�Ɏ����B
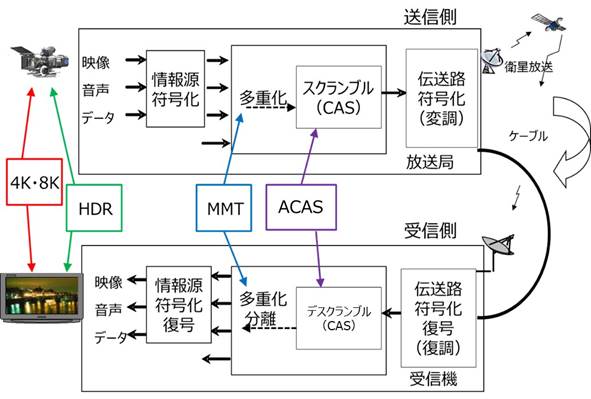
�} 3‑2�@4K�E8K�AHDR�AMMT�AACAS�̊W����
3.1.3�@ 4K�E8K�Ƃ�
4K�E8K�͉f���t�H�[�}�b�g�̉𑜓x���Ӗ����Ă���A4K�t�H�[�}�b�g���Ƃ����\ 3‑1�Ɏ����B
�������̉�f���́AITU����߂��K�i�Ɖf�搧���Ђ̉����c��DCI�iDigital Cinema Initiatives�j����߂��K�i��2�ʂ肪����A4K�ƌĂ�鍪����4,096��4�~1,024�ł��邱�ƂɈ���i�L���������̗e�ʕ\����2��10��ł���1,024��啶����K�ŕ\�����A1,000��\����������k�ƕ\�L���\�L���Ă���j�B
���\�Ɏ���4K�e���r�̓e���r�����p�ŁADCI 4K�͉f���J�����p�ł���B��f����4K�e���r�i�A�X�y�N�g��16:9�j��3,840�ŁADCI 4K�i�A�X�y�N�g��17.1:9�j��4,096�ł���B�t���[�����[�g�͌�q���邪�A4K�e���r�͖��b50�t���[����50p�i���B�Ȃǁj�Ɩ��b60�t���[����60p�i���{�A�č��Ȃǁj��DCI 4K�͖��b24�t���[����24p�ƈقȂ��Ă���B
�\ 3‑1�@�f���t�H�[�}�b�g�̉𑜓x��i4K�j

�܂��A8K�E4K�E2K�Ȃ�тɌ��sHDTV�i2K�j���r���āA�\ 3‑2���f���t�H�[�}�b�g�̉𑜓x�������B
�\ 3‑2�@�f���t�H�[�}�b�g�̉𑜓x�i8K�E4K�E2K �j
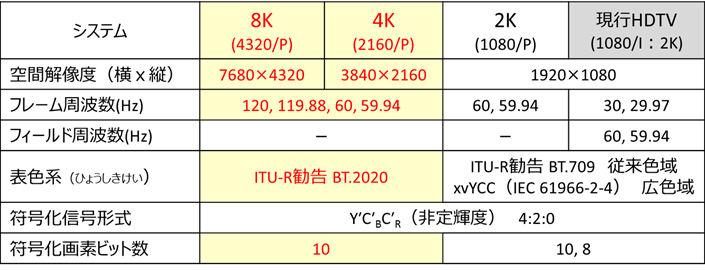
4K�E8K�Ɖ𑜓x�������Ă���Ƃ��̏��r�b�g�����}�����邽�߁A�R�[�f�b�N�Z�p�̐i�����K�v�ł���A���̊W���\ 3‑3�Ɏ����B
�\ 3‑3�@�摜���f�B�A�ƃR�[�f�b�N�Z�p�̐i���ɂ��`�����x��r��i�T���j
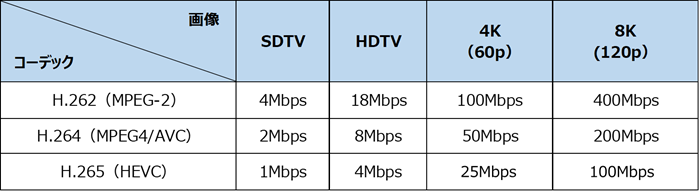
3.1.4�@ HDR�i�n�C�_�C�i�~�b�N�����W�j
HDR�iHigh Dynamic Range�j�́A���掿���̂��߂̋P�x�\���̊g���Z�p�ł���A�P�x�̃_�C�i�~�b�N�����W���L���邱�Ƃł���B
3.1.4.1�@ �Î~���HDR�Ɠ����HDR
HDR�͋P�x�̃_�C�i�~�b�N�����W���L�����邱�Ƃ��w�����A�Î~��Ɠ���ł͂��̎�@���قȂ��Ă���B�Î~��i�ʐ^�j�̕��̐��E�ł̓X�}�[�g�t�H���̃J�����ɂ�HDR�@�\�����ڂ����ȂNJ��ɕ��y���i��ł���BHDR�ʐ^�Ƃ́A�} 3‑3�Ɏ����悤�ɃJ�����̃_�C�i�~�b�N�����W�̋�����₤���߂ɃV���b�^�[�X�s�[�h��ς��ĈقȂ�I�o�ŘA�����ĕ������̎ʐ^���B�e���A�ꖇ�̉摜�ɍ������邱�Ƃɂ���ĉ摜�̎��_�C�i�~�b�N�����W�̕����ő���Ɉ����o�����Ƃ������̂ŁA�����E�̉摜�����̂܂܋L�^������̂ł͂Ȃ��A�l�H�I�ȉ摜�����Z�p�̈�ł���B
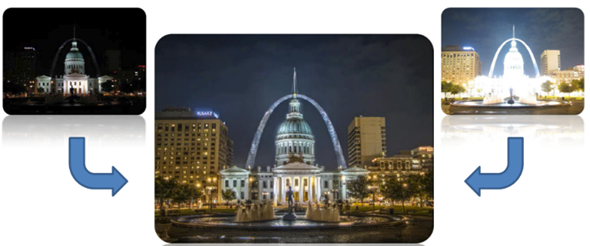
�} 3‑3�@�I�����Ԃ̈قȂ�摜����������HDR�ʐ^�̗�
�i�o�T�F https://www.digitaltrends.com/photography/what-is-hdr-photography/�j
����ɑ��āA�e���r������l�b�g�z�M�A���f�B�X�N�ɂ��p�b�P�[�W���f�B�A�ł̉掿���P�Ƃ��Ęb��ƂȂ��Ă��铮���HDR�Ƃ́A�f������荞�ގB���Z���T�������Ă���L���_�C�i�~�b�N�����W�̐M�������̂܂ܗʎq���i�f�W�^�����j���ċL�^���A���̐M�����e���r���Ńf�B�X�v���C�̋P�x���\�ɍ��킹�āA�g�����ꂽ�_�C�i�~�b�N�����W�̉f���M���𒉎��ɍĐ��\�����悤�Ƃ���Z�p�ł���A�ʐ^�ł���HDR�Ƃ͍l�������قȂ�B
���R�E�̋P�x�����W�́A�} 3‑4�Ɏ����悤�ɁA���̏o�Ă��Ȃ����̐��Ƃ炷�n�ʂ̖��邳��100������1nit�icd/m2�j���x�ŁA���z�̒��ڌ���10��nit�ƌ����Ă���A�c��ȕ��������Ă���B
�l�Ԃ̖ڂ����ɗD�ꂽ���o�����������Ă���A100������1nit����1��nit���x�܂Ŏ��F�ł��A����10��14��i140dB�j�߂��_�C�i�~�b�N�����W�������Ă��邪�ACRT����Ƃ���RT.709�̃_�C�i�~�b�N�����W�͂��܂�ɂ������A�����̏�����Ă����B�ߔN�̉t���e���r�́ACRT�ɔ�ׂăs�[�N�P�x��R���g���X�g�ɉ����Ċi�i�̐i���𐋂��Ă��邽�߁A�����̐��\���\�������o���āA�]���摜�̔���I���P���������錟��������Ă����B
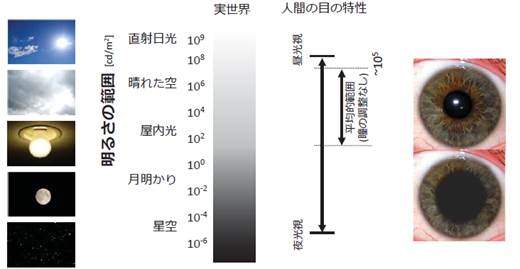
�} 3‑4�@���R�E�̋P�x vs �l�Ԃ̎��o�\�͈�
�i�o�T�F�����ȕ����V�X�e���ψ���HDR��Ɣǎ����@HDR��1�|3�uHDR�Z�p�Ɋւ��铮���v�j
�} 3‑5��HDR���܂ލ��掿���̂��߂̋Z�p�������B
CRT�̃e���r�ł͍��P�x�̂��̂ł���������200nit���x�ł������̂ɑ��A�t���e���r�͕W���̂��̂ł�400nit���x�̃s�[�N�P�x������A�����^LED�o�b�N���C�g�V�X�e���̂��̂ł����1,000nit����s�[�N�P�x��������̂ŁA�����K�i�ōČ��ł��Ȃ��������P�x�����̊K�������R�E�ɋ߂��P���Ńe���r��ʏ�ɕ\������̂�HDR�ł���B
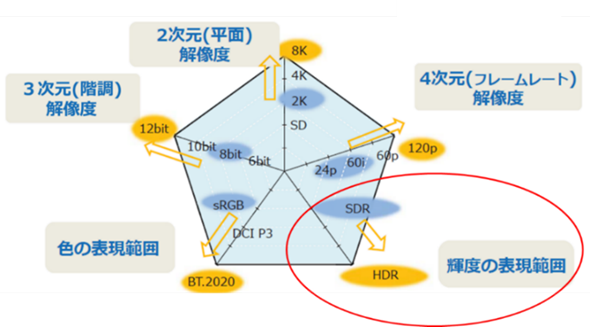
�} 3‑5�@HDR�ȂǍ��掿���̂��߂̋Z�p
�i�o�T�F�����ȕ����V�X�e���ψ���HDR��Ɣǎ����@HDR��1�|3�uHDR�Z�p�Ɋւ��铮���v��JLabs�C���j
3.1.4.2�@ HDR�̌���
4K�E8K����̓`���ɍۂ��āAHDR�Ɗ����̕����ł���SDR�Ƃ��r���A�} 3‑6�����掿���̂��߂�HDR����舵�����邳�͈̔͂������B
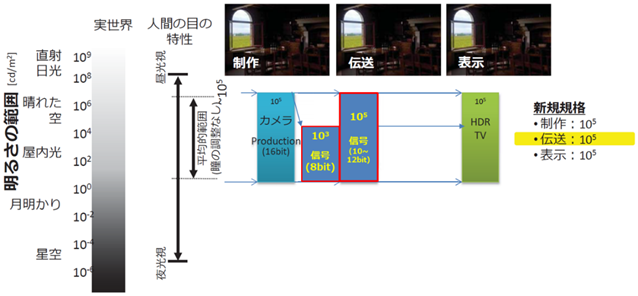
�} 3‑6�@���掿���̂��߂�HDR����舵�����邳�͈̔�
�i�o�T�F�����ȕ����V�X�e���ψ���HDR��Ɣǎ����@HDR��1�|3�uHDR�Z�p�Ɋւ��铮���v�j
HDR�ł̓J�����ŎB�e���ꂽ105�̋P�x�͈͂�`���H�ł�105�̋P�x�͈͂��ێ����AHDR�Ή��e���r��105�̋P�x�͈͂��Č�����B
���s��SDR�ł̓e���r�̃s�[�N�P�x��100 nit���W���ł��������߁A��������103���x�����`�����Ă��Ȃ������B
HDR�M����SDR�M���i����̓`���j�̔�r���} 3‑7�Ɏ����B���̊O�������SDR�ł͖��邢�Ƃ��낪�\���ł��Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B
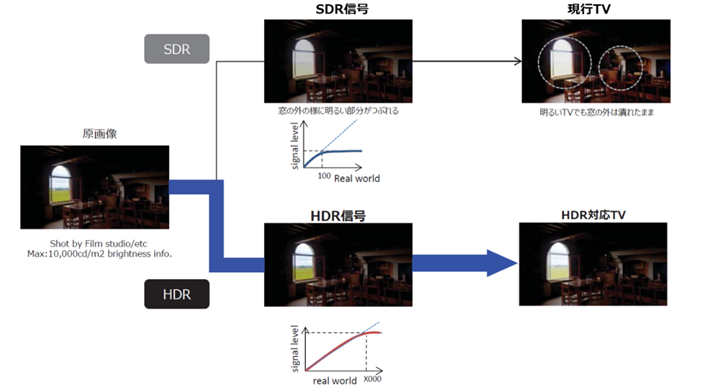
�} 3‑7�@HDR�ɂȂ����ۂ̉摜��
�i�o�T�F�����ȕ����V�X�e���ψ���HDR��Ɣǎ����@HDR��1�|3�uHDR�Z�p�Ɋւ��铮���v�j
3.1.4.3�@ ITU-R�ɂ�����HDR�W��������
ITU-R WP6C�i�ԑg���삨��ѕi���]���jSWG6C-4�i�f���jSWG4�@DG-1�i�n�C�_�C�i�~�b�N�����W�e���r�j��HDR��R�c���Ă���A������EIDRTV�iExtended Image Dynamic Range TV: �f���_�C�i�~�b�N�����W�g���e���r�j�ƌĂ�ł����B
2016�N7���A�č���PQ�iPerceptual Quantization�j�����Ɠ��{�^�p���Ăł���HLG�iHybrid Log-Gamma�j������2�������L�ڂ����V�����āuBT.2100�v�i�ԑg����ƍ��۔ԑg���ʂŎg�p����HDR�e���r�̉f���p�����[�^�l�j��ITU-R�����F���ꂽ�B�������̔�r���\ 3‑4�Ɏ����B
�\ 3‑4�@HDR�����̔�r
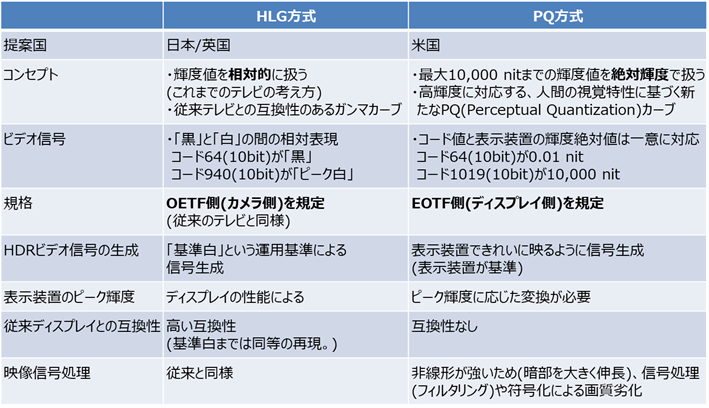
�@ �n�C�u���b�h�@���O-�K���}�iHLG�j����
�n�C�u���b�h�@���O-�K���}�iHLG�j�����́A�Õ��ɏ]���̃K���}�J�[�u�A�����Ƀ��O�J�[�u���̗p����n�C�u���b�h�����ŁA�u����v�Ƃ̑��Βl�ɂ��ϊ������g�p���邽�ߏ]���̃e���r�Ƃ̌݊����������̂������ł���B
�J�������Ō��̋P�x��d�C�M���ɕϊ������-�d�C�`�B���iOETF�FOpto-Electronic Transfer Function�j���K�肵�Ă���A�J�������̃t�B���^�̂悤�ɗp���邽�߁A�����̂悤�ɐ��̉f����͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�ɓK���Ă���B�t�ɁA�f�B�X�v���C�����d�C�M�������̋P�x�ɕϊ���������́A�d�C-���`�B���iEOTF�FElectro-Optical Transfer Function�j�ƌĂԁB
�{�����́A���^�f�[�^�𗘗p�����ɈقȂ�P�x�̉�ʊԂ�قȂ郁�[�J�̑��݉^�p����S�ۂ���B
HLG������OETF��EOTF�̃J�[�u���} 3‑8�Ɏ����B
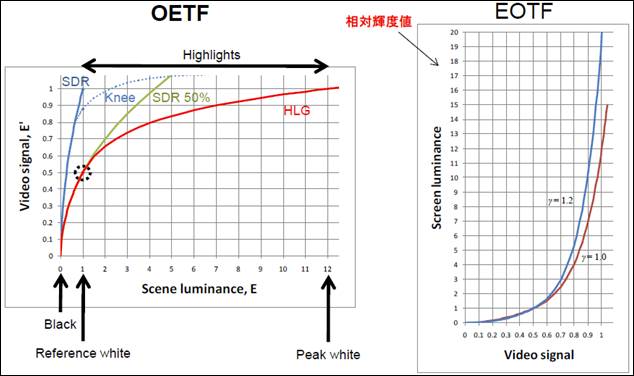
�} 3‑8�@OETF/EOTF�iHLG�j
�i�o�T�F�����ȕ����V�X�e���ψ���HDR��Ɣǎ���
HDR��2-3�ʎ��uHDR���������̒�āv���������j
�A PQ����
�ő�10,000nit�܂ł̋P�x�l���P�x�ň����A�l�Ԃ̎��o�����Ɋ�Â��V���ȃK���}�J�[�u�iPQ�FPerceptual Quantization�j���̗p����BPQ�J�[�u���} 3‑9�Ɏ����B
�d�C�M�����C�R���C�W���O����O���[�f�B���O��Ƃŗ\�ߌ��߂�ꂽ��Βl�ɂ����́^�o�͂̊W�����g�p���邽�߁A����Ɏ��ԂƃR�X�g���|������f��Ȃǂ̍�i�������R���e���c�ɓK���Ă���B
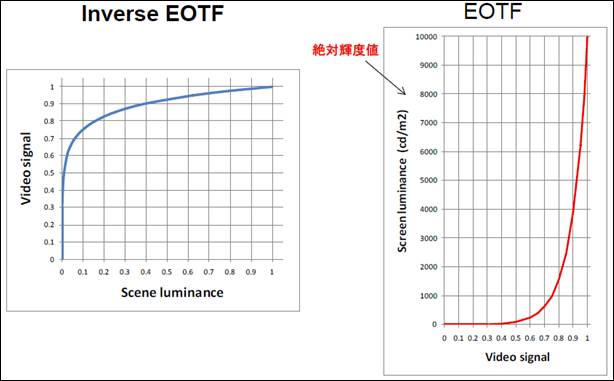
�} 3‑9�@EOTF�iPQ�j
�i�o�T�F�����ȕ����V�X�e���ψ���
HDR��Ɣǎ���HDR��2-3�ʎ��uHDR���������̒�āv�j
3.1.4.4�@ ������HDR�K�i������
���{�����ŕ��������Ƃ���HDR�������K�i�����邽�߂ɂ͑����Ȃ̏ȗߍ������Ȃĕ����@�����肷��K�v�����������AARIB�i��ʎВc�@�l�d�g�Y�Ɖ��j�ł�2015�N7����ARIB STD-B67 1.0�Łu�gEssential Parameter Values for the Extended Image Dynamic Range Television (EIDRTV) System�v�����肵���B
���̌�AHDR��K�p����f���̋�ԓ����Ǝ��ԓ������܂߂����ۓI�ȍ��ӂ������A����ITU-R BT.2100��2017�N6���ɉ������ꂽ���Ƃ��A2018�N1����2.0�ł����肵�A�K�i�����uParameter Values for the Hybrid Log-Gamma(HLG) High Dynamic Range Television (HDR-TV) System�v�ɕύX�����B
ITU-R�̊��������ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 �iMPEG�j�̕W���K�i����Q�Ƃ���邱�Ƃ�z�肷�邽���A�p���ł����{�ƂȂ��Ă���B���e��HLG�������߂����̂ŁA�ȉ���4���ڂɂ��ċK�肵�Ă���B
(1) OETF�ɂ�����V�X�e���p�����[�^���K��i���o���̋K��j
(1) ���F�p�����[�^ (���F�A����F�̍��W�j�FITU-R BT.2020���̗p
(2) �M���t�H�[�}�b�g�i����`���j�FGamma�{Log�̃n�C�u���b�h����
(3) �f�W�^���l�F����Peak�l�A������x���l�A���i0%�j���x���l���̃f�W�^���l�i10bit/12bit�j���K��
HDR���������S�ʂɂ��ẮA���ʐM�R�c�� ���ʐM�Z�p���ȉ� �����V�X�e���ψ���HDR��Ɣǂ��A2016�N3����HLG��PQ�o���ւ̑Ή���A���d���X�g���[���ɂ�����`�B���̎��ʓ��ɂ��ĕ��ɂ܂Ƃ߂Ă���B���̊T�v���\ 3‑5�Ɏ����B
�\ 3‑5�@HDR���������̊T�v
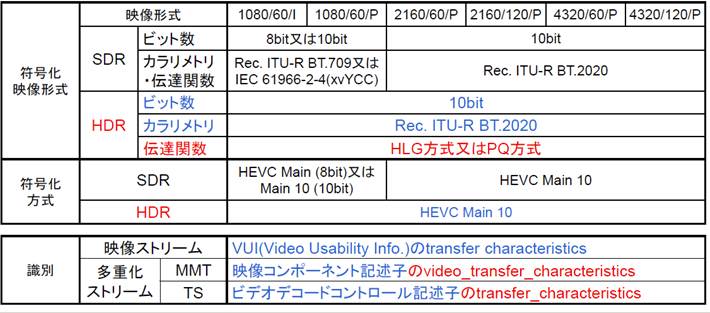
3.1.4.5�@ �u���[���C�f�B�X�N�ɂ�����HDR�K�i������
�������4K�ɑΉ������u���[���C�̋K�i�Ƃ��ĕW�����c��BDA�iBlu-ray Disc Association�j���uUltra HD Blu‒Ray�v�K�i�𐧒肵���B�} 3‑10�Ɏ����悤�ɁA���̒��ɂ�HDR���W���d�l�Ƃ��ċK�肳��Ă���AEOTF�Ƃ���SMPTE�iSociety of Motion Picture and Television Engineers�F�č��f��e���r�Z�p�ҋ���j���K�i������ITU-R�ɕč��ĂƂ��Ē�Ă��Ă���ST2084�iPQ�j���̗p�����B�܂��ASMPTE�͍��P�x�A�L�F��̃��^�f�[�^�K�iST2086���K�肵�Ă���A������ɂ��Ă��̗p���ꂽ�B���̂��߁ABD�v���C���[��HDR�Ή��e���r���̔�����CTA�iConsumer Technology Association�j�́AHDR�̂��߂�ST2086���^�f�[�^��K�p�����C���^�t�F�[�X�d�lCTA-861.3�i���^�f�[�^�g���K�i�j�𐧒肵���B
����ɑ��AHDMI�t�H�[������HDMI�C���^�t�F�[�X�́ACTA���C���^�t�F�[�X�d�l���Q�Ƃ��Ă���K�i�̂��߁A2.0�ł�2.0a�łɉ��肵��CTA-861.3�ւ̑Ή����s�����B
SMPTE ST2084��EOTF�́A���Ƃ��ƃh���r�[�Ђ�HDR���������邽�߂̕\�����u�ŁA�l�Ԃ̎��o�����ɍ��킹���f�����Č����邱�Ƃ��R���Z�v�g�ɒ������̂ł��邪�A�h���r�[�Ђ̓h���r�[�r�W�����Ƃ������W�ŁA���R�E�ɋ߂��f�������P�x�f�B�X�v���C��ōČ����邽�߂Ƀ��^�f�[�^���܂�12�r�b�g���f���A�����C���[�ő��o����V�X�e�����J�����Ă���AUHD BD�̃I�v�V�����Ƃ��č̗p����Ă���B

�} 3‑10�@Ultra HD Blu-ray
3.1.4.6�@ �P�[�u���ƊE�ւ̉e��
HDR��4K�̎��ɗ��閣�͓I�ȍ��掿���̋Z�p�ł���A����ɍL�F��iITU-R BT.2020�j�̗v�f���g�ݍ��킳�邱�Ƃɂ��A�啝�ɉf���\���̉\�����L����A���܂��܂ȓW�������J�������̃C�x���g�ł����̉掿���P�̌��ʂ��F�߂��Ă���B
2018�N12��1���ɊJ�n���ꂽ�V4K�E8K�q�������ɂ�HLG�������̗p����Ă��邱�Ƃ���A���������ĕ���������{�P�[�u�����{�u���xBS�f�W�^�������@�g�����X���W�����[�V�����^�p�d�l�v�iSPEC-033/034�j�ł́ASTB��HLG�����ւ̑Ή���K�{�Ƃ��A�܂�4K����������s���u���x�P�[�u����������v�iSPEC-035�j�ł�HLG�ւ̑Ή���K�{�Ƃ��Ă���B
HDR�̉^�p�ɂ����ďd�v�Ȃ̂́A�V����TV/STB�����݂�������ł̃n�C�_�C�i�~�b�N�����W�iHDR�j�Ə]�������iSDR�j�̎��ʂƁA�ؑւ��ł���B���̂����A�f���X�g���[���̓`�B���̎��ʂɂ��ẮAVUI�iVideo Usability Information�j��transfer characteristics���h18�h�Ƃ��邱�Ƃ�HLG�����ʂ���BVUI�́AMPEG-2 TS�ł̓r�f�I�f�R�[�h�R���g���[���L�q�q�iARIB STD-B10�j�Ɋ܂܂�AMMT�ł͉f���R���|�[�l���g�L�q�q�iARIB STD-B60�j�Ɋ܂܂��B
����AHLG�iHDR�j�f������M����STB�́A�ڑ�����Ă���TV�i�e���r���j�^�[�j��HDR�Ή����ۂ����ʂ���K�v������BSTB��TV�Ԃ�HDMI 2.0b�Őڑ�����Ă���ꍇ�́AHDR�iHLG�j�Ή����ۂ���ł���BTV��HDR�iHLG�j�Ή��̏ꍇ�́AHDR�̂܂܉f�����o�͂��A�����łȂ��ꍇ�̓���͓��{�P�[�u�����{�^�p�d�l�ł͏��i���Ƃ��Ă��邪�A�ŐV��STB�ł�HDR��SDR�ɕύX���ďo�͂��邱�Ƃ����҂����B
�} 3‑11�Ɏ�M�ɂ������STB��TV�̓���������B�܂��A�} 3‑12�ɂ͔ԑg���삩���M�܂ł̐M�������Ɗ֘A����@��������B
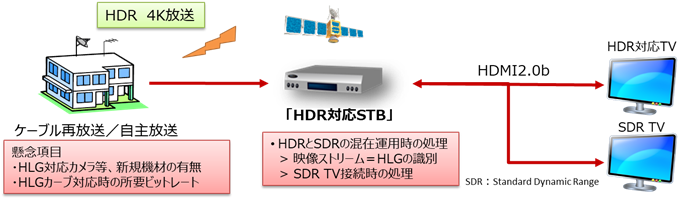
�} 3‑11�@HDR�Ή�STB�̓���
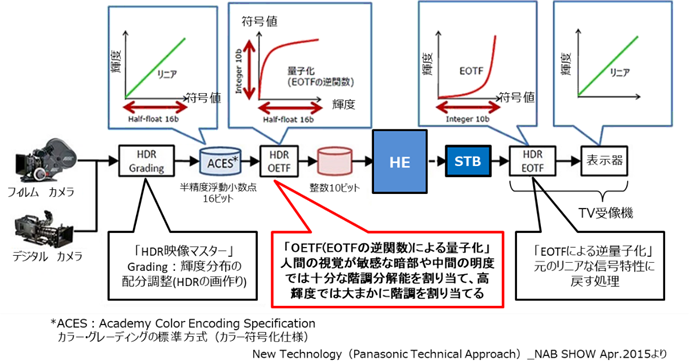
�} 3‑12�@HDR�Ή���STB��TV�Ȃǎ��Ӌ@��
3.1.4.5�@���ɂ����āACTA�K�i��HDMI�K�i�ɂ�����HDR�iPQ�����j�ւ̑Ή����q�ׂ����A�ŐV�̗��K�i�́A�ȉ��ɂ��HLG�����ɂ��Ή����Ă���B
ž 2016�N11���FCTA-861-G�u�k�����f�W�^���C���^�t�F�[�X�pDTV�v���t�@�C���v������B�O�ł�CTA-861-F��CTA-861.3�Ŋg������PQ������HDR�iHDR10�����j���T�|�[�g���Ă������ACTA-861-G��HLG�����̃T�|�[�g��lj�
ž 2016�N12���FHDMI 2.0b������B2.0b�͍ŐV�łł��������ACTA-861-G�ɑΉ�����HLG������HDR���T�|�[�g���邽�߂�HLG�`�B���̃V�O�i�����O��lj��i�Ŕԍ�2.0b�͕ύX�����j
ž 2017�N11���FHDMI 2.1�K�i���������[�X
- �ш敝�g��F18Gbps�iHDMI2.0�n�j��48Gbps
- 10K�𑜓x�܂őΉ�
- ���t���[�����[�g4K p100/120�A 8K p100/120�A10K p100/120���T�|�[�g
- �P�[�u���͐V�K�i��������݊���������A�R�l�N�^�͏]���ǂ���
- PQ�AHLG�̃V�O�i�����O�ɉ�����SMPTE ST2094�̓��I���^�f�[�^���T�|�[�g���A���I���^�f�[�^���g���ăV�[��/�t���[�����ƂɐF�[�x��f�B�e�[���A���邳�A�R���g���X�g�A�F����œK������_�C�i�~�b�NHDR������
3.1.5�@ MMT���d������
�} 3‑13�A�} 3‑14�ɐV4K8K�q�������ɗ��p�����MMT�iMPEG Media Transport�j���̑��d�������������BMMT-TLV�iType Length Value�j��������{�Ƃ��A���s��MPEG-2 TS�����ɂ��Ă��K�肪�lj�����A�^�p���邱�Ƃ��\�ł���B
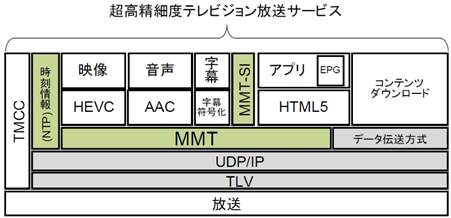
�i�V�K�FNTP�EMMT�EMMT-SI�A�����K��F�f�[�^�`���EUDP/IP�ETLV�j

�} 3‑13�@MMT�ETLV���d������
�i�o�T�F������ �������דx�e���r�W���������V�X�e���T�v�j
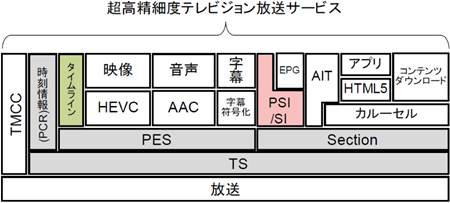
�i�V�K�ɋK�肷�镔���F�^�C�����C���A�K�i���C�����镔���FPSI/SI�A
���łɋK�肳��Ă��镔���FPCR�EPES�ESection�ETS�j

�} 3‑14�@MPEG-2 TS����
�i�o�T�F������ �������דx�e���r�W���������V�X�e�� �T�v�j
���s�̃f�W�^�������V�X�e�����J�����ꂽ�����ɔ�ׁA��������芪���R���e���c�z�M�̊����傫���ω������B�u���E�U�Ō��邱�Ƃ̂ł���}���`���f�B�A�R���e���c���������A�f���t�H�[�}�b�g�A�R���e���c�𗘗p����[���A�`���H�����l�����Ă��Ă���B������MPEG�ł́A����������V�X�e���ł̃T�[�r�X���\�Ƃ���A���܂��܂ȃl�b�g���[�N�ł̃��f�B�A�`���ɑΉ�����V�����`���K�i�Ƃ���MMT�̌������i�߂��A High Efficiency Video Coding �iHEVC�j��3D Audio��g�ݍ��킹���V���ȕW���K�i�ł���MPEG-H�V�X�e���̈ꕔ���iMPEG-H�@Part1�APart10�APart11�APart12�j�ƂȂ�A�W�������ꂽ�B
4K/8K�̎��p�����ɂ�����^�p�d�l�́AARIB TR-B39���x�L�ш�q���f�W�^�������^�p�K�� 1.2�ł����肳��A���d�������̋Z�p�W���Ƃ��Ă�ARIB STD-B60 �f�W�^�������ɂ�����MMT�ɂ�郁�f�B�A�g�����X�|�[�g���� 1.8�ł����肳��Ă���B
�܂��A�P�[�u���e���r�ł́AMPEG-2 TS�ɑ���V���d������MMT�𗘗p������3����STB�����̍��xBS�ĕ����̉^�p�d�l�Ƃ��āAJLabs SPEC-033 ���xBS�f�W�^�������g�����X���W�����[�V�����^�p�d�l�i�P��QAM�ϒ������j��JLabs SPEC-034 ���xBS�f�W�^�������g�����X���W�����[�V�����^�p�d�l�i����QAM�ϒ������j�����肵�Ă���B
3.1.5.1�@ MPEG-2 TS�̌��E��MMT
MPEG-2 TS�́A����M����N���b�N���܂߂Ċe�R���|�[�l���g��1�̃X�g���[���Ƃ��Ĉ������߁A�P��̓`���H�ɂ������̎d�g�݂�z�肵�������ł���B���������݂ł͑��l�ȃR���e���c�����݂��A�܂�����𗘗p����[�������l�����Ă���A�����ƒʐM�Ƃ̘A�g�ɂ��R���e���c�z�M�ȂǁA�����̍����T�[�r�X�����҂����悤�ɂȂ��Ă����B���̂悤�Ȋ��ω��ɑ��AMPEG-2 TS�ōŐV�̕����E�ʐM�T�[�r�X�ɑΉ�����ɂ͈ȉ��̓_�Ő�����B
ž �X�g���[�����ő��d�����������A���̃X�g���[���Ƃ̑��d�����ł��Ȃ��i��F�����X�g���[���ƒʐM�X�g���[���𑽏d�j
ž �قȂ�X�g���[���ԂŎ����������ł��Ȃ��i��F�����ƒʐM�̎��������j
ž �p�P�b�g�����Œ�i188�o�C�g�j�ŁA��e�ʃR���e���c�̓`���ł͔����
ž ��e�ʃt�@�C���̓`��������
MPEG-2 TS�ŏ�L�̐���ɑΉ�����ɂ͌��E�����邽�߁A�V���Ɏ���������V�X�e���ŗ��p�\�ȃ��f�B�A�g�����X�|�[�g�����Ƃ��Ĉȉ��̂悤�ȑΉ���}��AIP�`�����l������MMT���W�������ꂽ�B
ž �قȂ�X�g���[���𑩂˂邽�߂̃��^�f�[�^���K��
ž �قȂ�`���}�̂��o�R�����X�g���[���Ԃ̎����������\
ž �ϒ��p�P�b�g�𗘗p���A��e�ʃR���e���c�iUHDTV�Ȃǁj�̓`����������
ž �t�@�C���`����������
3.1.5.2�@ MMT�̓���
MMT�̋@�\�̓����́A�ʐM�����̎Q�Ɛ���w�肵�āA�T�[�o����擾�����ԑg�֘A���Ȃǂ��ɕ\������Ƃ��������ƒʐM�̘A�g�ɂ��n�C�u���b�h�z�M�ł��邱�Ƃł���A���̃C���[�W���} 3‑15�Ɏ����B
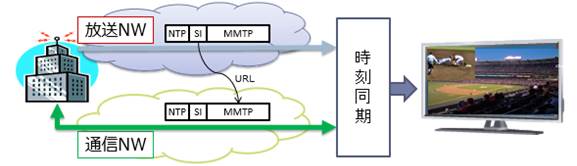
�} 3‑15�@�X�|�[�c���p�ɂ����Ď�f��������g�œ`�����A
�A���O���̈قȂ�f�����ʐM�œ`������ꍇ�̃C���[�W
�n�C�u���b�h�z�M�̎�ȋ@�\�v�f�Ƃ��āA�ȉ��̓��e����������B
ž �`���H���V�[�����X�ɐ�ւ���@�\��L���A���Ƃ��đ��M���ł͑����_�f�����̓`���H�Ŕz�M���l������B�܂���M���ł́A���Ƃ��Ήq�������ł̍~�J�����Ȃǂ̍ۂɂ͒ʐM�Ŕz�M����������M���邱�ƂŁA�p���������\�Ƃ���T�[�r�X�����B���邢�͊K�w�iScalable�j�������ɑΉ������X�g���[����z�M���邱�Ƃɂ��A�x�[�X���C��������œ`�����A�g�����C����ʐM�œ`������T�[�r�X�Ȃǂ��l�����A���̈����} 3‑16�Ɏ����B
ž ����������NTP�iNetwork Time Protocol�j�𗘗p���邱�ƂŁA�]����MPEG-2 TS���d�������ł͍�����������^�ʐM�R���e���c�Ԃ̐�Ύ����������������A�قȂ�`���H���o�R�����X�g���[���Ԃ̓������\�ɂȂ�B�܂����萢�E��UTC�iCoordinated Universal Time�j�`���œ��ꂳ�ꂽ�v���[���e�[�V�����^�C���X�^���v�iPresentation Time Stamp�j���f���≹���Ȃǂ̃R���|�[�l���g�i�A�Z�b�g�j�ɕt�^����邱�Ƃɂ��A�����x�ɓ��������T�[�r�X���ł���B
ž �A�Z�b�g���ƂɁA�����M�[���ɍ��킹�Ă��̉�ʏ�ł̕\���̈���w�肷�邱�Ƃ��ł���B
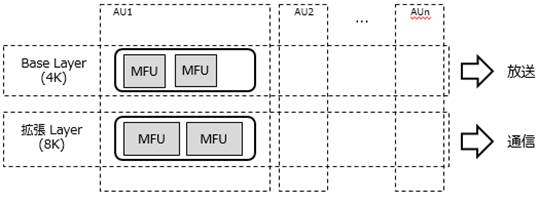
�} 3‑16�@MMT�ɂ��K�w�`���̗�
3.1.5.3�@ MMT�̍\��
���s�̕����V�X�e���ł͑��d�������i���f�B�A�g�����X�|�[�g�����j�Ƃ���MPEG�ŕW�������ꂽMPEG-2 TS�������p�����Ă���BMPEG-2 TS�ł͒P��̓`���H�ɂ�������z�肵�A����M����N���b�N���܂߂Ċe�R���|�[�l���g����̃X�g���[���Ƃ��Ĉ����Ă��邪�A���l�ȓ`���H��e���r�݂̂Ȃ炸�^�u���b�g��X�}�z���̃f�o�C�X�����݂�������ō��x�ȃT�[�r�X�����ɂ͌��E������B
���̂悤�ȍ��݊����ɂ����郁�f�B�A�z�M�ɗp�������A�̋K�i�Ƃ���2014�N3���ɍ��ەW�������ꂽ�̂��AISO/IEC 23008 MPEG-H�iHigh efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments�j�ł���AMMT�͂���Part 1�ƂȂ��Ă���B
���Ȃ݂ɁAPart 2��4K/8K�̉f���������ɗp������HEVC�iH.265�j�ł���A����3D Audio�iPart 3�j�AForward Error Correcting Codes for MMT�iPart 10�j�AComposition coding for MMT�iPart 11�j�����K�肳��Ă���B
MMT�ɂ����镄�����M���̍\����MPEG-2 TS�Ɣ�r�����} 3‑17�Ɏ����B
�}�̍ŏ�ʂɂ���l�b�g���[�N���ۉ����C���iNAL�FNetwork Abstraction Layer�j���j�b�g�́AHEVC�iH.265�j�G���R�[�_�[���o�͂��镄�����M���ŁA���܂��܂Ȑ�������܂ޔ�VCL-NAL�ƁA���k���ꂽ�f���X���C�X�f�[�^�ł���VCL�iVideo Coding Layer�j-NAL���j�b�g������B��VCL-NAL���j�b�g�ƍŒ�1��VCL-NAL��A���������̂̓A�N�Z�X���j�b�g�iAU�j�ƌĂ�A1���̃t���[���iPicture�j�ɑ�������B
����MFU�iMedia Fragment Unit�j��MMT�ɂ�����ŏ��̏����P�ʂŁAHEVC�iH.265�j�f���M���̏ꍇ��VCL-NAL���j�b�g��p����B���̏ꍇ��MFU��MPEG-2 TS��PES�ɑ�������B�܂��A�P��܂��͕����̔�VCL-NAL��MFU�ƂȂ�B
MPU�iMedia Processing Unit�j���} 3‑18�Ɏ����悤�ɁA���^�f�[�^�ƕ����̃T���v���f�[�^�iVCL-NAL���j�b�g�^MFU�j���A���������̂ł���AHEVC�iH.265�j�̂悤�ȃt���[���ԗ\����p���镄�����M����p����ꍇ�ɂ́AGOP�iGroup of Picture�j�Ɠ����P�ʂł���K�v������BMPU�͓Ɨ����ĕ������\�ȕ������P�ʂł���A�����╜��������MPU�P�ʂŎw��\�ł���B
MMTP�y�C���[�h��MPU�^MFU���琶��������@��2����B1�ڂ́AMPU��������@�A2�ڂ�MFU����MPU���\�����鏈�����ȗ����AMFU��MMTP�y�C���[�h�Ƃ�����@�ł���A�����ł͒x�����팸����ړI�����2�ڂ̕��@���p������B���̏ꍇ�AMPU�Ɋ܂܂��ׂ����^�f�[�^�́A������iMMT-SI�j�Ƃ��đ��M�����BMMTP�y�C���[�h�͉ϒ������A�T�C�Y�ɂ�蕡����NAL���j�b�g���i�[����ꍇ��ANAL���j�b�g�����Ċi�[����ꍇ������B
�Ō�ɁAMMTP�y�C���[�h�Ƀw�b�_�[��t������MMTP�p�P�b�g�ƂȂ�B�w�b�_�[�ɂ̓y�C���[�h�^�C�v�A�z�M�^�C���X�^���v�A�p�b�P�[�W�V�[�P���X���̏�܂܂��B
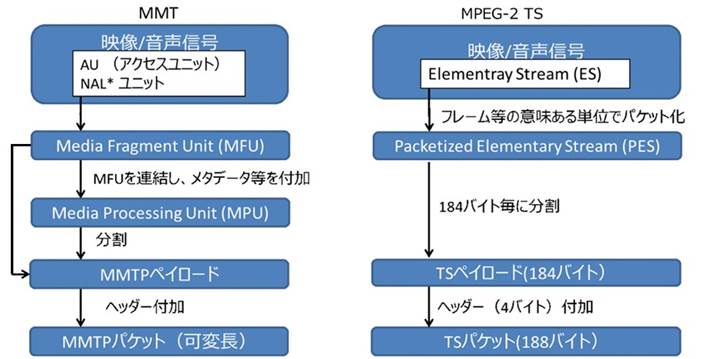
�} 3‑17�@MMT�ɂ����镄�����M���̍\����MPEG-2 TS�Ƃ̔�r
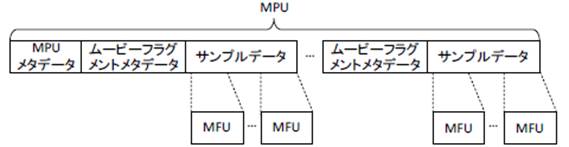
�} 3‑18�@MPU�̈�ʓI�ȍ\��
�i�o�T�FARIB STD-B60�j
3.1.5.4�@ �v���g�R���X�^�b�N
MMT�ɂ���������̃v���g�R���X�^�b�N���} 3‑19�ɁA�܂��ʐM�ł̃v���g�R���X�^�b�N���} 3‑20�Ɏ����BMMT�ł́AIP�̏�ʑw�ƂȂ�UDP��TCP�œ`�������AMMTP�iMMT Protocol�j�p�P�b�g�A����т��̃p�P�b�g���ɕ��������ꂽ���f�B�A���i�[����MMT�y�C���[�h���K�肵�Ă���B
�܂��A���f�B�A�̊e�R���|�[�l�b�g�������`���Ƃ��āAMFU�^MPU���`���Ă���B
MMTP�p�P�b�g�́A�ʐM�ŗ��p����ꍇ��IP�p�P�b�g�����ē`������B�����̓`���H�œ`�����邽�߂ɂ́AIP�p�P�b�g������MMTP�p�P�b�g���ATLV���d��������K�p���ē`������BTLV�ł́A������MMT�̃T�[�r�X�𑽏d���āATLV�X�g���[���Ƃ��ē`�����邱�Ƃ��ł���B�iMMT�ETLV�����j
���̂悤�ɗ��҂̏�ʃ��C�������ʍ\���ł��邽�߁A�����ƒʐM�Ƃl�Ɉ������Ƃ��ł���̂������ł���B
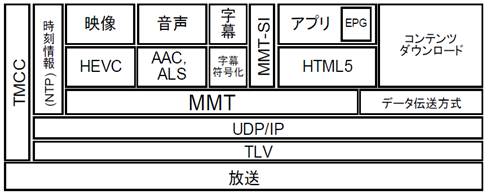
�} 3‑19�@MMT��p��������V�X�e���̃v���g�R���X�^�b�N
�i�o�T�FARIB STD-B60�u�f�W�^�������ɂ����郁�f�B�A�g�����X�|�[�g�����v�j
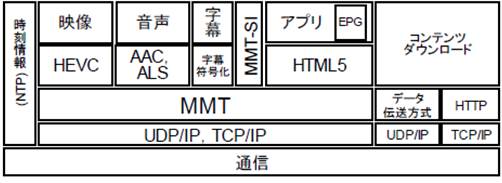
�} 3‑20�@�ʐM����ɂ�����v���g�R���X�^�b�N
�i�o�T�FARIB STD-B60�j
3.1.5.5�@ MMT�p�b�P�[�W
�O���ŋL�ڂ���2�̃v���g�R���X�^�b�N�͔��ɗގ����Ă���A�����MMT�������`���H�ƒʐM�`���H���悤�Ɉ������Ƃ��ł���Ƃ��������ɂ����̂ł���B
�} 3‑21�ɕ����`���H�ƒʐM�`���H�̗�����p����T�[�r�X�̍\���������B�} 3‑21�́A�f���R���|�[�l���g1�A�����R���|�[�l���g1�A�f�[�^1������`���H�ŁA�f���R���|�\�l���g2�A�����R���|�[�l���g2�A�f�[�^2��ʐM�`���H�œ`������`�Ԃ������Ă���B�����`���H�ł͉f���A�����A�f�[�^��3�̃R���|�[�l���g��1��IP�f�[�^�t���[�ɑ��d���A�����TLV�X�g���[���œ`�����Ă���B����́A���M��������ׂĂ̒[���ɓ`������邽�߂ł���B
�܂��A�ʐM�`���H�œ`������R���|�[�l���g�́A�[�����Ƃ̌ʂ̗v���ɉ����邽�߁A�R���|�[�l���g���ƂɈقȂ�IP�f�[�^�t���[�œ`������B
�����ŁA�����T�[�r�X�i�R���e���c�j�ɑΉ����銇����u�p�b�P�[�W�v�ƌĂсA1�̃T�[�r�X�ɂ����ĊJ�n����яI�������ɂ���ʂ����ԑg���u�C�x���g�v�ƌĂԁB
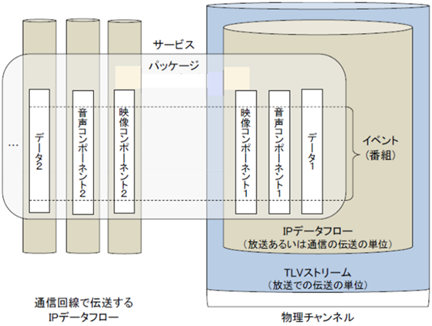
�} 3‑21�@�����E�ʐM���f�ɂ�����T�[�r�X�̍\��
�i�o�T�FARIB STD-B60�j
3.1.5.6�@ MMT���䃁�b�Z�[�W�iMMT-SI�FMMT-Signaling Information�j
MMT-SI�́A�����ԑg�̍\���Ȃǂ������`������M���Ń��b�Z�[�W�E�e�[�u���E�L�q�q��3��ނ���Ȃ�B���b�Z�[�W�̓e�[�u����L�q�q��`�����Ɋi�[���邽�߂̐���M���A�e�[�u���͓���̏��������v�f�⑮�����L�ڂ���������A�L�q�q�͂��ڍׂȏ�������������ł���BMMT�̐��䃁�b�Z�[�W�̌`���Ƃ��AMMTP�y�C���[�h�Ɋi�[��MMTP�p�P�b�g�Ƃ���IP�p�P�b�g�����ē`������B
���b�Z�[�W�̈��PA�iPackage Access�j���b�Z�[�W������A���̒���MPT�iMMT Package Table�j�ŌX�̔ԑg���\������A�Z�b�g�̃��X�g�AURL�����L�q����B
�����̃p�b�P�[�W�i�����R���e���c�j�𑽏d����ꍇ�ɂ́A�} 3‑22�Ɏ����悤��PA���b�Z�[�W�̒��Ƀp�b�P�[�W���X�g�e�[�u�����܂܂�A���̃p�b�P�[�W���X�g�e�[�u���ɑ��̃p�b�P�[�W��MPT���܂�PA���b�Z�[�W��`������MMTP�p�P�b�g�̃��X�g���܂܂��B
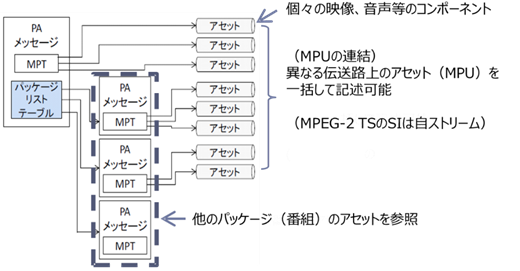
�} 3‑22�@�p�b�P�[�W���X�g�e�[�u���ɂ��p�b�P�[�W��MPT�̎Q��
�i�o�T�FARIB STD-B60�u�f�W�^�������ɂ����郁�f�B�A�g�����X�|�[�g�����v�j
3.1.6�@ ACAS
�����Ȃ̓��\�Ŏ�����Ă���VCAS�����̊T�v�ɂ����\ 3‑6�Ɏ����B
�\ 3‑6�@���x�L�ш�q�������iBS/110�xCS�j�̃X�N�����u���T�u�V�X�e��

�P�[�u���e���r�ƊE�ł́A2.10���̑�3����STB��4K�^�p�d�l�Ŋ��ɏq�ׂ��悤�ɁA���xBS�ĕ����⍂�x�P�[�u����������ɂ����āA�VCAS�����Ƃ���ACAS��p����B
ACAS�͎��̂悤�ȓ��������B
ž ARIB STD-B61���҂̃A�N�Z�X��������i��2����j�ɏ���
ž �X�N�����u��������AES128�𗘗p���A�Z�L�����e�B������
ž STD-B61���ҋK��̃_�E�����[�_�u��CAS�iD-CAS�j�ɂ͊Y�����Ȃ����ACAS�\�t�g�E�F�A�����S�ɍX�V����d�g�݂�L����
�����ŁAARIB STD-B61���҂ɏ�������ACAS�́A�Z�L�����e�B����̂��߂̏��K�͂ȃ\�t�g�E�F�A�X�V�@�\��L���邪�A���҂ɋK�肳���CAS�v���O�����̑S�ʓI�ȃA�b�v�f�[�g�@�\(D-CAS)�ɂ͑Ή����Ă��Ȃ����Ƃɒ��ӂ��K�v�ł���B
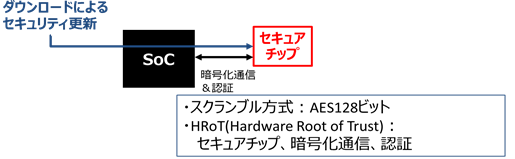
�} 3‑23�@ACAS
�P�[�u���e���r���Ǝ҂�ACAS�𗘗p���邽�߂ɂ́A���p�p�r�ɉ������\ 3‑7�Ɏ���2�̋敪����I�����ē��{�P�[�u���e���r�A����ACAS�X�L�[���ɎQ������B�������A�p�X�X���[�ɂ��ĕ����ɂ�����STB���g�p�����A�����e���r�Ŏ�M����ꍇ�́A�{�X�L�[���̑ΏۊO�ƂȂ�A�X�L�[���ւ̎Q���͕K�v�Ƃ��Ȃ��B
�\ 3‑7�@�A��ACAS���p�X�L�[��
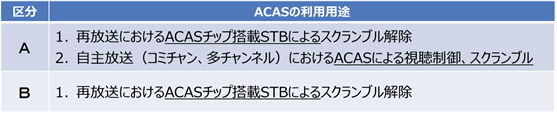
�{�X�L�[���ł́AJ:COM�AJDS�AJCC���VCAS���c��Ƃ̊Ԃ�EMM�iEntitlement Management Message�j���p�ݔ���L����B
J:COM�����JDS�AJCC�P���̎��Ǝ҂́A���̒��p�������āAACAS�V�X�e���Ƃ̊Ԃ�EMM���̂������s���A�VCAS���c��ɑ���EMM�̈Í������˗�����Ƌ��ɁA�A���o�R�ňÍ�����p���x�����B
3.1.7�@ 22.2ch �O�����}���`�`�����l����������
���������ł́A�X�e���I��5.1ch�T���E���h�ɂ���ĉf��ق̂悤�ȗՏꊴ���鉹�������Ɏ�������Ă��邪�A8K�����ł́A22.2ch�O�����}���`�`�����l�������������K�i������A5.1ch�T���E���h�������Տꊴ�̂��鉹�����v�悳��Ă���B
���̕����́A��ԓI�ɔz�u���ꂽ22�`�����l���ƒቹ���ʗp��2�`�����l������\������A3�����I�ȋ�ԉ������Đ�������̂ł���B
5.1ch�����̃X�s�[�J�z�u��
�} 3‑24�ɁA22.2ch�����̃X�s�[�J�z�u���} 3‑25�Ɏ����B����22.2ch������24�̃X�s�[�J�ɂ�鉹����5.1ch�T���E���h�������Տꊴ������A�p�u���b�N�r���[�C���O��V�A�^�[�ȂǂɗL���ł���B
�܂��A�ƒ�ł̂��܂��܂�4K/8K�e���r�������ɑΉ����邽�߂ɁA22.2�}���`�`�����l����������菭�Ȃ��X�s�[�J���ōĐ�����Đ��@�̊J����NHK�����Z�p�������Ői�߂��Ă���A�t���b�g�p�l���f�B�X�v���[�Ɉ�̉����ꂽ12�̃X�s�[�J�ɂ��o�C�m�[�����Đ��@������Ă���Ă���B���̕��@�ł́A24�̃X�s�[�J��ݒu���邱�ƂȂ��A22.2ch�}���`�`�����l��������̌����邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B
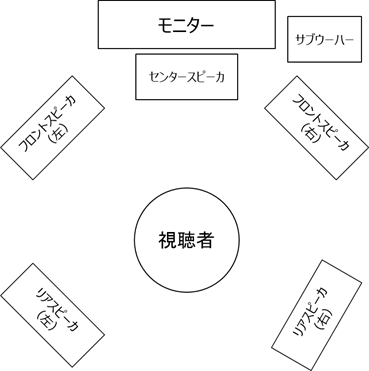
�} 3‑24�@5.1ch�T���E���h�̃X�s�[�J�z�u
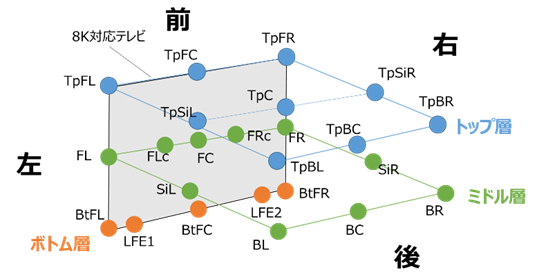
�} 3‑25�@22.2ch�����̃`�����l���z�u�}
3.1.7.1�@ 22.2ch���������̕������K�i
���{�����ɂ�����22.2ch���������ɂ��8K�������������邽�߂ɁA�����ȗߑ�87���u�W���e���r�W�����������̂����f�W�^�������Ɋւ��鑗�M�̕W�������v�̉��肪�s���Ă���B
���xBS�f�W�^�������A���x���ш�CS�f�W�^����������э��x�L�ш�CS�f�W�^�������ɂ�����ő���͉����`�����l�����́A�u22�`�����l������ђ�����������2�`�����l���Ƃ���v���ƁA�����������́A�uMPEG-4 AAC�K�i�����MPEG-4 ALS�K�i�ɏ�����������Ƃ���v���Ƃ��K�肳��Ă���B
�܂��A�����ȗ߁E�����ɑΉ����āAARIB STD-B32�u�f�W�^�������ɂ�����f���������A�����������y�ё��d�������v�̉��肪�s���A�ő�22.2�`�����l���̃}���`�`�����l���������[�h�ɑΉ�����MPEG-4 AAC���������������̂��ڍׂȎd�l�Ɋւ���lj��K�肪�s���Ă���B��ARIB�K�i�ł́A22.2ch������p����Ƃ��ɁA2ch�A5.1ch�����������ɑ���d�g�݂��K�肳��Ă���B
�\ 3‑8�Ɏ����Ƃ���A�ȗ߁E���������ARIB�W���K�i�ɂ����āA8K�����ɗp����T���v�����O���g����48kHz�A�ʎq���r�b�g����16�r�b�g�ȏ�ƋK�肳��Ă���AMPEG-4 AAC������������AAC-LC�iLow Complexity�j�v���t�@�C����p���邱�Ƃ���߂��Ă���B
�\ 3‑8�@22.2ch�����̃f�W�^�������M���K��
|
�T���v�����O���g�� |
48kHz�A96kHz�i�I�v�V�����j |
|
�ʎq���r�b�g�� |
16�r�b�g�A20�r�b�g�A24�r�b�g |
3.1.8�@ 4K�E8K�����̂��߂̓`���Z�p
�q���f�W�^�������ƃP�[�u���f�W�^�������ɂ��Đ�������B���ɁA�P�[�u���f�W�^�������`���Z�p�Ƃ��āA�f�W�^���L���e���r�W�������������iITU-T����J.83 Annex C��64/256QAM�j�A���������g�`�������A�q���f�W�^�������̒��Ԏ��g���iIF�j�p�X�X���[�`�������A����э��x�P�[�u����������ɂ��Ď����B
3.1.8.1�@ �q���f�W�^������
�q���f�W�^�������ɂ́A���x���ш�`�������i���o124/128�xCS�f�W�^�������F�X�J�p�[JSAT�j�ƍ��x�L�ш�`�������iBS/���o110�xCS�f�W�^�������j������A4K�E8K�f�������������ɂ�H.265�iHEVC�j�����������p����邪�A���d��������`���H�������͈قȂ��Ă���B�q���f�W�^�������̍��x���`���Z�p�̊T�v�ɂ��đ����ȃz�[���y�[�W�f�ڎ������Q�Ƃ����\ 3‑9�Ɏ����B
���x�L�ш�q���f�W�^�������̓`���H�����������ł́A���[���I�t����0.1����0.03�ɒጸ���邱�ƂŁA�V���{�����[�g��32.5941Mbaud����33.7561Mbaud�ւƍ��������Ă���A8PSK�i3/4�j�̏ꍇ�A���s�q�������Ɠ����ȏ�̃T�[�r�X���ԗ��Ŗ�72Mbps�̓`�����\�ƂȂ��Ă���B�܂��A�V���������Ƃ���7/9��lj����A16APSK�i7/9�j���̗p���邱�ƂŃg�����X�|���_�������100Mbps�̓`�����\�ł���B�����ʐM�K���̏o�͏���l�i60dBW�j�Ƃ����ꍇ�A16APSK�i7/9�j�ōň����T�[�r�X���ԗ�99.7%�ȏ���m�ۂł���B
�\7-9�ɂ͋K�i��̕����̃p�����[�^��������L�ڂ���Ă��邪�A���xBS�q�������̎��ۂ̉^�p�ɂ�����ϒ�������16APSK�A����������7/9�A�X�N�����u��������AES128�A���d��������MMT�ETLV�A���ƂȂ��Ă���B
�Ȃ��A���o110�xCS�����͉q�������ɔ�׃_�E�������N�d��(e.i.r.p.)�����������߁A��������2/3���g�p���A�g�����X�|���_�������66Mbs�̓`�����\�ƂȂ��Ă���B
�\ 3‑9�@�q���f�W�^�������̍��x���`���Z�p
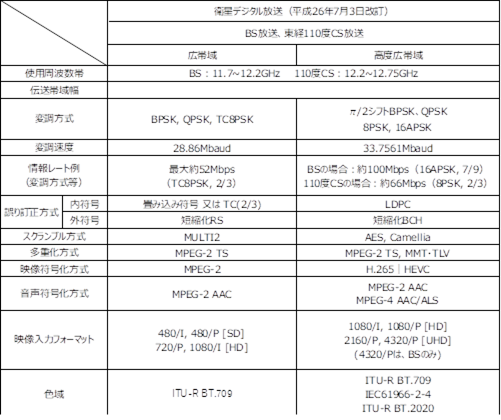
3.1.8.2�@ �P�[�u���f�W�^������
�f�W�^���L���e���r�W�������������iITU-T����J.83 Annex C��64/256QAM�j�A���������g�`�������A�q��������̃p�X�X���[�`�������i�q���f�W�^��������IF�p�X�X���[�����j�A����э��x�P�[�u����������ɂ��Ď����B
3.1.8.3�@ �����̃f�W�^���L���e���r�W������������
�����̃f�W�^���L���e���r�W�������������iITU-T����J.83 Annex C��64/256QAM�j�ł́AH.265 (HEVC)�AMPEG-2 TS���d���A256QAM��p����4K���p�����i��������j���\�ł���B���̗���} 3‑26�Ɏ����B���̕�����4K�t�H�[�}�b�g�܂ł���{�Ƃ��āA���s�̃P�[�u���e���r�̕����T�[�r�X�Ƃ̑��݉^�p�����ł������m�ۂ��A�����̐ݔ������ő�����p���邱�ƂŁA�P�[�u��UHD TV�����T�[�r�X�̑����̓�������щ^�p���\�Ƃ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
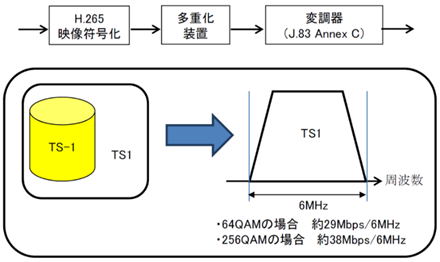
�} 3‑26�@�����̃f�W�^���L���e���r�W�������������ł�4K����
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
�@ ���������g�`������
J.83 Annex C����{�ɑ�e�ʂ̃f�[�^�𑗂邽�߂̋Z�p�Ƃ��āA����TS�`�������̂P�����g�i64 QAM/256 QAM�j�̓`���e�ʂ���X�g���[���iTS��������TLV�j���̔����g��p���ĕ����`�����A��M�@�ō�����������ł���B����������e�ʃX�g���[���̈ꕔ�Ɗ����̃f�W�^��������TS�p�P�b�g����ʂ��ē���t���[�����ɑ��d�����邱�Ƃ��\�ł���B
���̕����ɂ����p���Ƃ��Ă̓������ȉ��Ɏ����B
(1) �q�������Ɠ����T�[�r�X���P�[�u���e���r�Œ�
ž 64QAM(��30Mbps)��256QAM(��40Mbps)��C�ӂ̕������g���ɐݒ肵�ĕ����`��
ž MMT�ETLV�����MPEG-2 TS�̑o���ɑΉ���
(2) ���s�̃P�[�u���{�݂̐��\��8K UHD TV�`���\
ž ITU-T J.83 Annex C���x�[�X
ž �����g�𑩂˂�����ɂ���e�ʓ`��������
ž ���������g�`�������AITU-T����J.183�𗘗p
ž �����T�[�r�X�̋X���b�g��L�����p�\
�Ⴆ�Βn�f�W�i�g�����X���W�����[�V�����j�̋X���b�g�𑩂˂�4K�`���ȂǁA���s�����ƌ���݊�����L����
(3) ���ۂ̃P�[�u���e���r�{�݂Ŏ��؎����ɐ���
ž ���{�l�b�g���[�N�T�[�r�X�A�R�����@2013�N2��
ž �W���s�^�[�e���R���i���FJCOM�j�A�����s�@2014�N5��
���̕������������邽�߁A�����̕���TS���d�t���[���iTSMF: Transport Stream Multiplexing Frame �j���g������B�ȉ��̐����ł́A�g�����镡��TS���d�t���[�����u�g��TSMF�iExtended TSMF�j�v�Ə̂���B
�܂��A���������g�`�������̐M������M���邽�߁A�V���ɗL�����������g�`�����z�V�X�e���L�q�q�ichannel_bonding_cable_delivery_system_descriptor�j����`���ꂽ�B
�} 3‑27�ɕ��������g�`�������̊T�v�������B
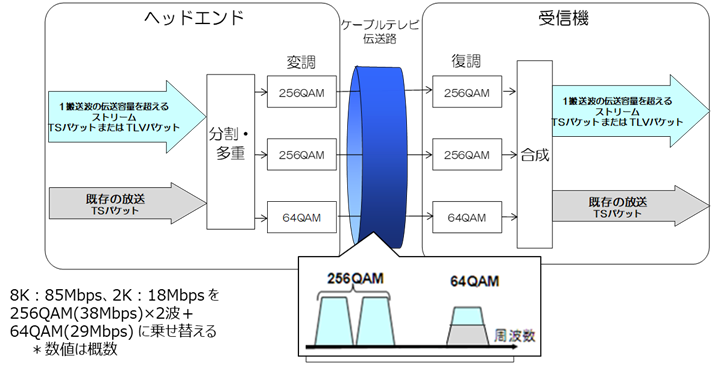
�} 3‑27�@���������g�`�������̊T�v
�i�g��TSMF��K�p����2��256 QAM��1��64 QAM����`�������j
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�
�����V�X�e���ψ���P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
�A �ϒ���������ѓ`���H����������
���������g�`�������ő��M���镪�������X�g���[���̓`���H�����������́A�����̃f�W�^���L���e���r�W�������������̓`���H�����������Ɠ���Ƃ���B�V���{���N���b�N�͔����g�Q���\������e�����g�œ������Ă�����̂Ƃ���B
���������g�`�������̊e�����g�́A�����̃f�W�^���L���e���r�W�������������Ɠ���̓`���H�����������i�ϒ������A���[���I�t���A�G�l���M�[�g�U�����A�����������A�C���^�[���[�u�����A�t���[�������M���A�t���[���\���j��p����B����ɂ��A�} 3‑28�Ɏ����悤�ɁA�����̃f�W�^���L���e���r�W�������������Ɠ����M���`���Ƃ��ď������邱�Ƃ��\�ł���A����܂łɊJ�����Ă����Z�p��K�i�����p���邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��A���؎����ɂ��m�F����Ă���B
�擪�o�C�g�̒l��0x47��188�o�C�g�̃f�[�^����̗p���邱�Ƃɂ��A�P��TS�`�������╡��TS�`�������Ɠ��l�ɁA���������g�`�������������̓`���H�����������ň������Ƃ��\�ł���B�����g�Q���\������e�����g�̃V���{���N���b�N�������邱�Ƃő���M�@�̍\�����ȑf���ł���B

�} 3‑28�@���������g�`������
�i��e�ʂ̃X�g���[����1��64 QAM��2��256 QAM�ɕ������ē`�������j
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
(1) 4K�A8K�T�[�r�X�̓`����
4K 8K�����������悭�������鉞�p��Ƃ��āA�} 3‑29��4K��2K���ꂼ��1�`�����l����`���������A�܂��} 3‑30��8K��2K�����ꂼ��1�`�����l���`�������������B
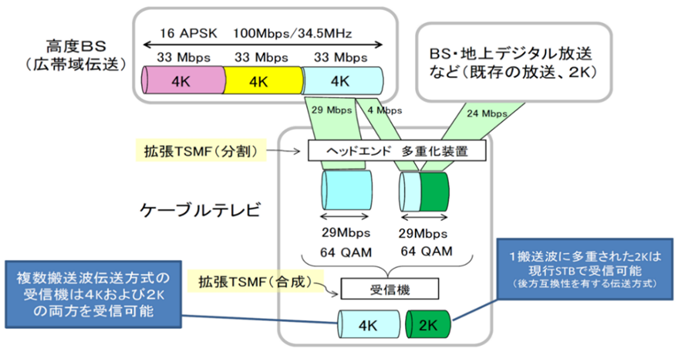
�} 3‑29�@4K��2K���ꂼ��1�`�����l����`��������{��
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
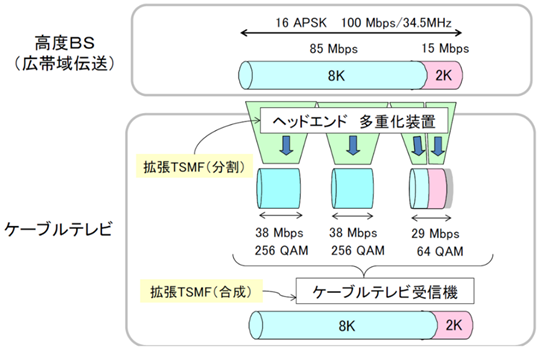
�} 3‑30�@8K��2K���ꂼ��1�`�����l����`��������{��
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
(2) ��e�ʂ�TS�p�P�b�g��`������Z�p
4K�A8K�Ȃǂ̑�e�ʂ�TS�p�P�b�g�܂���TLV�����p�P�b�g��`�����邽�߂ɕ��������g�ɕ������ē`�����鉞�p��Ƃ��Ĕ����g�Q�ɑ���������g�̕ϒ��������������ꍇ�̃X���b�g�̔z�𑗐M���M���A���d�����u�A��M�@���M���ɕ����Ă��ꂼ���} 3‑31�A�} 3‑32�A�} 3‑33�Ɏ����B
|
���M��TS�@ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�} 3‑31�@���M��TS�M���𑗐M�O�̃X���b�g�̔z�C���[�W�i100Mbps�j
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�@�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
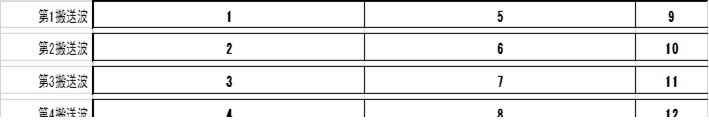
![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�} 3‑32�@�����g�Q�ɕ��������X���b�g�̔z�C���[�W�i25Mbps�~4ch�j
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�@�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
|
��M������TS�@ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�} 3‑33�@��M��TS�M���𑗐M�O�̃X���b�g�̔z�C���[�W�C���[�W�i100Mbps�j
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�@�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
(3) TLV�M���̊g��TSMF�ւ̑��d��
�g��TSMF���d�����u�́ATS�M�����̓|�[�g�ɓ��͂���TS�M����������TLV�M�����̓|�[�g�ɓ��͂���TLV�M�����A�g��TSMF��̃X���b�g�ɁA����TS�M���������͓���TLV�M���̓Ɨ�����ۂ��Ȃ��瑽�d�����A�o�͂�����̂ł���B
���d������TLV�M���Ɋ܂܂��TLV-NIT���P�[�u���e���r�l�b�g���[�N�i���l�b�g���[�N�j�p�̂��̂łȂ��Ƃ��́A�P�[�u���e���r�l�b�g���[�N�i���l�b�g���[�N�j�p�ɏ���������TLV-NIT��TLV�M���ɑ}�����ďo�͂���B
TLV�M���́A�ϒ���TLV�p�P�b�g�̏W���ł���B�g��TSMF���d�����u�ł́ATLV�p�P�b�g���Œ蒷�i188�o�C�g�j�̕���TLV�p�P�b�g�ɕϊ����A�X���b�g�ɑ��d����B����TLV�p�P�b�g�́A�擪��3�o�C�g���w�b�_�[�Ƃ��A����ɑ���185�o�C�g���y�C���[�h�Ƃ���B
�} 3‑34��TLV�p�P�b�g�����āA����TLV�p�P�b�g������������������B�y�C���[�h�ɂ́A�������ꂽ������TLV�p�P�b�g���܂܂�邱�Ƃ�����B
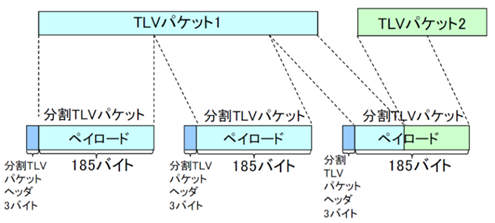
�} 3‑34�@����TLV�p�P�b�g�̗�
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�@�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
�Q�l�Ƃ��āA�g��TSMF���d���̋@�\�u���b�N�\������} 3‑35�Ɏ����B�g��TSMF���d�����u�ł́A����TLV�M���̓`�����x�ɑ��āA����������Ȃ����o�\�Ƃ���X���b�g�������炩���ߊm�ۂ��Ă����B���Z���ꂽ�`�����x������TLV�M���̓`�����x������ꍇ�ɂ́A�k��TLV�p�P�b�g��}�����đ��x�������s���A�m�ۂ��ꂽ�X���b�g�̂��ׂĂ�TLV�p�P�b�g�Ŗ��߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�} 3‑35�@TS�M�������TLV�M�����g��TSMF���d����\����
�B IF�p�X�X���[�`������
FTTH�����Ă���V�X�e���ɂ����ẮAIF�p�X�X���[�����ɂ��4K�E8K�̕�����`�����邱�Ƃ��\�ł���B���x�L�ш�q���f�W�^������������16APSK�ϒ������ɂ����ẮA��������������9/10�̎��ɗv��������M�Ғ[�q�ɂ�����C/N�́A17dB�ȏ�ŁA���̐M�����P�[�u�����Ǝ҂���M���āAIF�p�X�X���[�����ɂ��ĕ����T�[�r�X���s�����߂ɂ́A���s�K�i�̕W���q���f�W�^���e���r�W����������IF �p�X�X���[�K�i11dB����6dB����C/N���m�ۂ���K�v������B�} 3‑36�ɉq��������̃p�X�X���[�`�������ɂ�����T�[�r�X��������B
IF�̍ō����g���́AND-23��`������Ɩ�3224MHz�ƂȂ�B�S�Ă�IF���g���́A�\ 3‑10�ɋL�ڂ���Ă���B
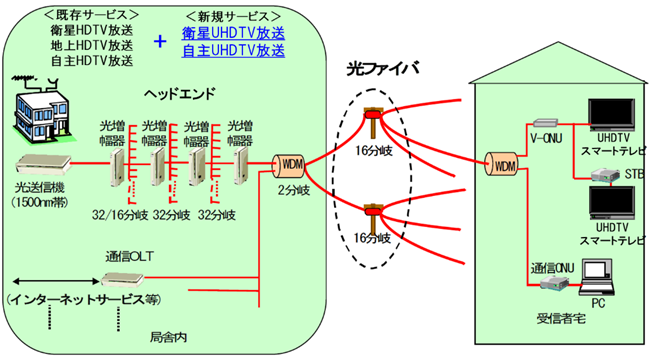
�} 3‑36�@�q��������̃p�X�X���[�`�������ɂ�����T�[�r�X��
�i�o�T�F���ʐM�R�c��@���ʐM�Z�p���ȉ�@�����V�X�e���ψ���
�@�P�[�u���e���rUHDTV��Ɣǁ@�i�āj�j
�ȉ��ɁA�A���e�i�ɂ��q�������g�̎�M��q��������̃p�X�X���[�`���Ɋ֘A�����Q�l���������B
�q�������g�̉~�Δg�Ƃ́A�}7-37�Ɏ����悤�ɕΔg�ʂ���]���Ă�����̂������B�����Δg�␂���Δg�����A�q���̎p���ɂ��Δg�����̕ω�����̉e�����ɂ����B
�~�Δg�ɂ��ẮA�d�g�̐i�s�����Ɍ������Ď��v���̉E���~�Δg�Ɣ����v���̍����~�Δg������B�E���ƍ����̓d�g�݂͌��Ɋ����Ȃ����߁A�q�������g�ɂ����Ă͓������g���т����p���邱�Ƃ��\�ł���B���݂̕����Ɏg���Ă���͉̂E���݂̂ł��邪�A�������g�p���J�n���ꂽ�B�P�[�u����ɂ����ẮA�������g���т̋��p�͕s�\�ł��邽�߁A�݂��ɈقȂ���g���ɕϊ����ē`�������B
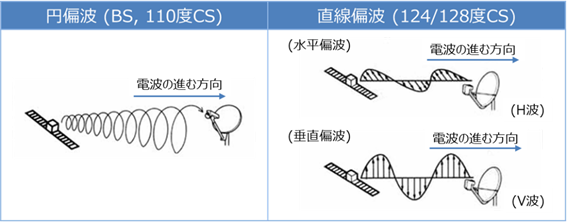
�} 3‑37�@�q�������g�̕Δg���i�o�T�F�q����������j
�} 3‑38�̓P�[�u����Ŏg�p����IF�ւ̎��g���ϊ��̌����������Ă���B�q�������g�ƉE���p���邢�͍����p�̋Ǖ����M���g���Ƃ��������A�����g���������t�B���^�őI�ʂ���IF�����o���B�Ȃ��A�����p�̋Ǖ����U���g����ARIB STD-B63�ɂ����ĉ��肳��Ă���A�]����ARIB STD-B21�����̃A���e�i�Ƃ͌݊����������̂Œ��ӂ��K�v�ł���B
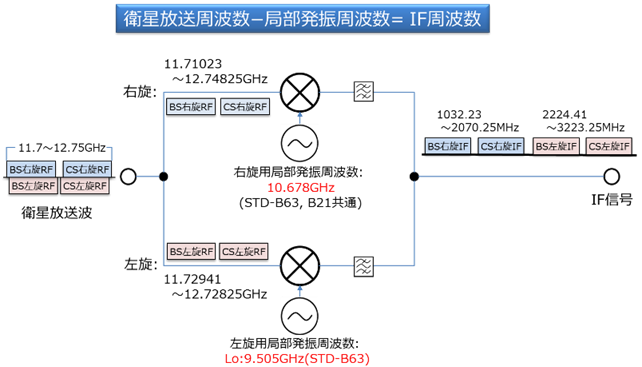
�} 3‑38�@BS/110�xCS�@IF�ւ̎��g���ϊ� �i�o�T�FARIB STD����}�j
�\ 3‑10�́ABS/110�xCS-IF�̎��g���ꗗ�ł���B���̕\�Ɏ����悤�ɁA�����~�Δg�̗��p�ɂ�葽����IF���lj�����Ă���A�P�[�u����ɂ�����ō��`�����g����3223.25MHz�ƂȂ����B���̂悤�ȍ������g���ɂ�����M�����x����C/N���m�ۂ��邽�߂ɁA����E�����̓����P�[�u���A�u�[�X�^�A���z��A�e���r�[�q�Ȃǂ̌�����Ƃ��K�v�ƂȂ�ꍇ������B
�\ 3‑10�@BS/110�xCS-IF���g���ꗗ
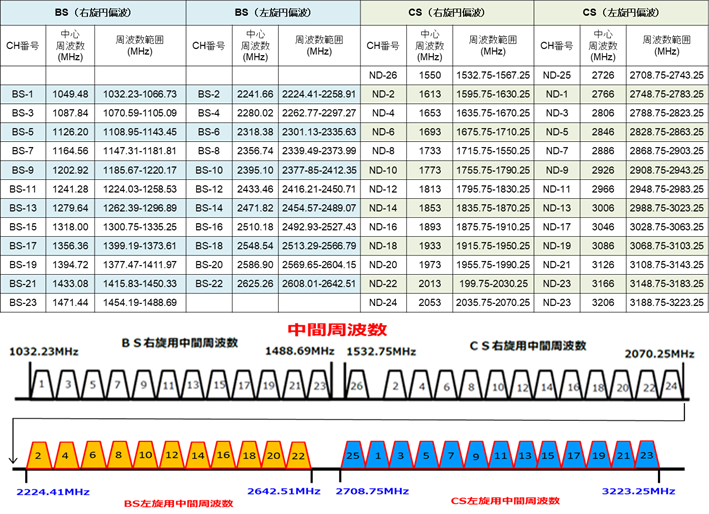
�\ 3‑11�́A���̂悤��IF���p�X�X���[�`�����邽�߂ɒ�߂�ꂽ�Z�p��ł���B
�\ 3‑11�@�q��������̃p�X�X���[�`�������̎�ȋZ�p�
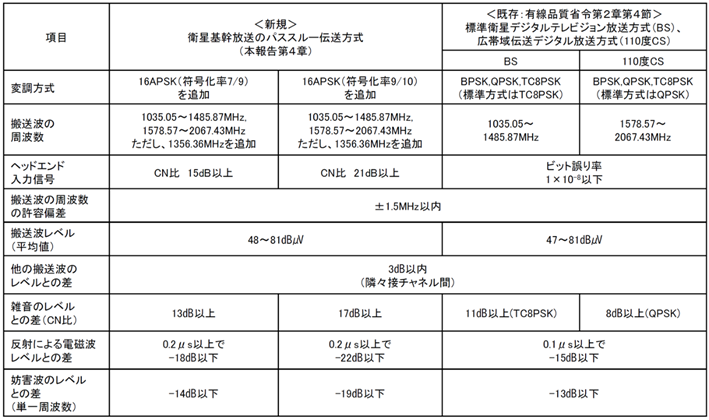
3.2�@ IoT�T�[�r�X
3.2.1�@ �C���g���_�N�V����
IoT�iInternet of Things�j�Ƃ́A�قȂ��ނ̕����I�ȃf�o�C�X��I�u�W�F�N�g���C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����A���݂ɒʐM���A�f�[�^����������Z�p��T�O�łł���BIoT�́u���m�̃C���^�[�l�b�g�v�Ƃ��Ă�A���퐶����Y�Ɗ����ɂ����āA�l�X�ȕ��i���C���^�[�l�b�g����đ��݂ɘA�g���A�������L���邱�Ƃ��\�ɂ��Ă���B
��̓I�ɂ́A�Z���T��A�N�`���G�[�^�[�𓋍ڂ����f�o�C�X���A�l�b�g���[�N�ɐڑ�����A���A���^�C���Ńf�[�^�����W���A�������A������s���B����ɂ��A���Y���̌���A�������A�������A�T�[�r�X�̉��P�Ȃǂ̗l�X�ȗ��_�����҂����B
IoT�̊�ՂƂȂ�Z�p�ɂ́A�Z���T�Z�p�A�l�b�g���[�N�Z�p�A�N���E�h�R���s���[�e�B���O�A�r�b�O�f�[�^�����A�l�H�m�\�Ȃǂ��܂܂��B�����̋Z�p����������邱�ƂŁAIoT�V�X�e������������A�V���ȃr�W�l�X���f����T�[�r�X�̐��������҂���Ă���
IoT�̗��j�͌Â��B�C���^�[�l�b�g���l�̃R�~���j�P�[�V�����݂̂��痣��͂��߂��̂́A1990�N�㏉���Ƀ}�[�N�E���C�U�[�iMark Weiser�j�ɂ���Ē��ꂽ�h���r�L�^�X�R���s���[�e�B���O�h�����[�Ǝv����B�ނ́A1991�N�ɔ��\�����_���ŁA�R���s���[�^���l�X�̓��퐶���ɐZ�����A�ڂɌ����Ȃ��`�Ől�X�̎��͂ɗn������Ŏg����悤�ɂȂ邱�Ƃ��N�����B
1990�N��㔼����2000�N�㏉���ɂ����ẮA���r�L�^�X�R���s���[�e�B���O�̎����ƌ����̐i�W������ꂽ�B���ɓ��{�ł̓��r�L�^�X�l�b�g���[�N�Ƃ������ōL���m��킽��A���ɂ�鐔�����̌����J�����J�Ԃ����B����ɂ́A�Z���T�e�N�m���W�[�̐i���A���o�C���R���s���[�e�B���O�̕��y�A3G�g�ѓd�b�V�X�e�����͂��߂Ƃ��郏�C�����X�ʐM�Z�p�̔��W�̍v�����傫��
IoT�̗p�ꂪ���Ɍ��ꂽ�̂́A�����炭IUT-T�ɂ��hThe Internet of Things�h(ITU INTERNET REPORTS2005)[1]����ł͂Ȃ����A�Ǝv����B���̒��ł͒ʐM�̑Ώۂ��@�B��Z���T�܂Ŋg�傳��A��������̂��l�b�g���[�N�Ɍq����֘A����R���e���c�������p���_�C��������B
2000�N�㒆������́A�Z���T�Z�p�̐i����4G/Wi-Fi�ʐM�Z�p�̔��W�Ɏx�����A�l�X��IoT�f�o�C�X���J������A���y���݂����B���ɁA�X�}�[�g�Ɠd�A�X�}�[�g���[�^�A�����Ԃ̃e���}�e�B�N�X�ȂǁA������Y�Ƃ̂��܂��܂ȕ����IoT�����p����n�܂����̂����̍�����ł���B
2010�N�㒆���ȍ~�AIoT�̓f�[�^�쓮����|�ɐi�����n�߂�BIoT�f�o�C�X�����W����f�[�^�ʂ͋}���ɑ������A�C���^�[�l�b�g��ɑ�ʂɗ���n�߂�B������r�b�O�f�[�^�Z�p��N���E�h�R���s���[�e�B���O���x���A�f�[�^���͂�@�B�w�K�����p�������l�n�����s����悤�ɂȂ��Ă������B�������̗����̍����f�[�^������Ղ��o�����A�f�[�^�����r�����i��ł������B����ł́A�Z�L�����e�B�̏d�v���������AIoT�f�o�C�X��l�b�g���[�N�̃Z�L�����e�B��������Ă������B
����́AIoT�̏�����Ղ͂قڊm�����A�G���h�̃Z���T���m�I�Ȑi�����i��ł���B�N���E�h�݂̂ɗ��炸�A�Z���T�߂��ł̏������d������G�b�W�R���s���[�e�B���O��l�H�m�\�iAI�j�Ȃǂ̐V���ȋZ�p������IoT�ɓ�������A���A���^�C���ł̃f�[�^�����⓴�@�̒����҂���悤�B
3.2.2�@ IoT�̊�ՋZ�p
IoT���\�������ȋ@�\�v�f�Ƃ��ẮAIoT���x�����ՂƂ��ẮA�傫�������āA�Z���T/�G���h�f�o�C�X�A�Z���T�m�[�h�A�ʐM�l�b�g���[�N�A�N���E�h�v���b�g�t�H�[���A�����ăf�[�^���͏����A�A�v���P�[�V����/���[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�A�Z�L�����e�B�A����/�A�N�`���G�[�V���@�\�ɂȂ�ƍl������B�ȉ������ɂ��ĊT������B
3.2.2.1�@ �Z���T
IoT�ŗ��p�����Z���T�́A���܂��܂Ȏ�ނ�����A�l�X�ȗp�r�ɉ����ăf�[�^�����W����B�ȉ��ɁA��ʓI��IoT�Z���T�̎�ނƂ��̗p�r��������������B
���x�Z���T:
���x�𑪒肵�A���̉��x�ω����Ď�����B�ƒ��Y�Ɨp�r�ł̋C��Ǘ��A�①�ɂ�Ⓚ�ɂ̉��x�Ǘ��ȂǂɎg�p�����B
���x�Z���T:
���x�𑪒肵�A���C�⊣���̏�Ԃ��Ď�����B�ƒ��Y�Ɨp�r�ł̎��x�Ǘ���A�A���͔|�̃��j�^�����O�ȂǂɎg�p�����B
���Z���T:
���̗ʂ𑪒肵�A�Ɩ�����̖��邳������B�܂��A�����̗ʂ𑪒肵�āA���z�����d�V�X�e���̍œK�Ȕz�u�����肷��̂ɂ��g�p�����B
�����x�Z���T:
���̂̉����x�𑪒肵�A�U���⓮�������o����B�X�}�[�g�t�H����E�F�A���u���f�o�C�X�Ȃǂ̓��쌟�o��A�n�k�̃��j�^�����O�ȂǂɎg�p�����B
���̓Z���T:
���͂𑪒肵�A�C���␅���̕ω����Ď�����B�V��\���⍂�x�̌v���A�����̃��j�^�����O�ȂǂɎg�p�����B
�����Z���T:
���̂܂ł̋����𑪒肵�A��Q�����m��ʒu����ȂǂɎg�p�����B�����Ԃ̒��Ԏx���V�X�e����{�b�g�̏�Q������Ȃǂɗ��p�����B
�K�X�Z���T:
����̃K�X�̔Z�x�𑪒肵�A�K�X�R���������̊Ď����s���B�R���K�X���m����C�i���Z���T�Ȃǂ�����B
�����Z���T:
���͂̉��𑪒肵�A���ʂ���g���͂���B�����F���V�X�e������Ď��ȂǂɎg�p�����B
3.2.2.2�@ �Z���T�m�[�h
IoT�Ŏg����Z���T�m�[�h�Ƃ́A�Z���T�ƒʐM�@�\��g�ݍ��킹�����^�̃f�o�C�X���w���B�Z���T�m�[�h�́A�Z���T�ߖT�ɔz������A��ɃZ���T�Ƃ̃C���^�t�F�[�X�A�}�C�N���R���g���[���A�ʐM���W���[���Ȃǂ���\������A�Z���V���O�����f�[�^��K�ɃN���E�h�ɑ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�Z���T�m�[�h�̑�\�I�ȗ�Ƃ��ẮAArduino����������BArduino�́A�I�[�v���\�[�X�v���b�g�t�H�[���ŁA�}�C�N���R���g���[���[�𒆐S�Ƃ����n�[�h�E�F�A�ƁA������v���O�������邽�߂�Arduino IDE�ƌĂ��\�t�g�E�F�A�J��������\�������BArduino�{�[�h�́A�Z���T��A�N�`���G�[�^�Ȃǂ̎��Ӌ@���ڑ����A���䂷�邽�߂̃v���g�^�C�s���O��n�[�h�E�F�A�J���ɍL���g�p����Ă���B�} 3‑39��Adruino UNO�̎ʐ^�ł���B

�} 3‑39�@Arduino�{�[�h(WikiPedia�����p).
Arduino�ƕ���ōL�����p����Ă���Z���T�m�[�h����R�X�g�ŏ��^�̃V���O���{�[�h�R���s���[�^Raspberry Pi�ł���BRaspberry Pi�́A�L�x��GPIO�iGeneral Purpose Input/Output�j�s����USB�|�[�g������A���܂��܂ȃZ���T��f�o�C�X��ڑ����Ďg�p���邱�Ƃ��\�ł���BLinux�x�[�X�̃I�y���[�e�B���O�V�X�e��(e.g., Raspberry Pi OS)�����s���APython�₻�̑��̃v���O���~���O����ŊJ�����邱�Ƃ��\�ł���B������Raspberry Pi�͊ȒP��IoT�����p�ƍl�����Ă������A�p�t�H�[�}���X���o�[�W�������オ�閈�ɐi�����AGPU�����ڂ����Ɏ����Ă���(2024�N1�����_�ł�Raspberry Pi 5�����\����Ă���)�B�܂�Raspberry Pi OS�ɂ͐��������\�t�g�E�F�A�ł���Wolfram�Ђ�Mathematica�������Ńo���h������Ă��邱�Ƃ����M�����B
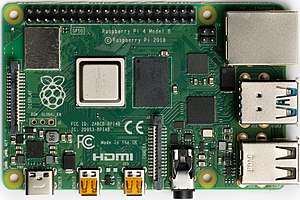
�} 3‑40�@Raspbery Pi 4 Model B�iWikiPedia�����p�j
��y��IoT�p�̃Z���T�m�[�h�Ƃ��ė��p�\�ȃ}�C�N���R���g���[���{�[�h�Ƃ��ẮAESP8266�����ESP32������B������WiFi��Bluetooth������AArduino IDE�Ńv���O���~���O���邱�Ƃ��ł��A�����̊J���҂�R�~���j�e�B�Ɏx������Ă���B
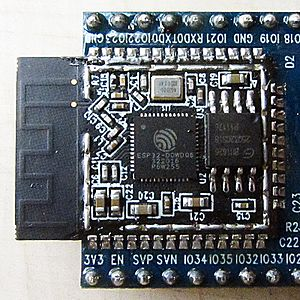
�} 3‑41�@ESP32���W���[���̗�iWikiPedia���j
�@�܂��ŋ߂ł�NVIDIA�Ђ��GPU�𓋍ڂ����g�ݍ���IoT�A�v���P�[�V�����ɂēK�p�\��Jetson Nano����������A��q����悤�ȃZ���T�m�[�h�ł�AI�������\�ɂ��Ă��Ă���B
3.2.2.3�@ �X�}�[�g�f�o�C�X
�@IoT�A�v���P�[�V�����ł͂��܂��܂ȃZ���T�@�\��A�N�`���G�[�^�@�\��������X�}�[�g�f�o�C�X���悭���p�����B�����ł͂��̗��������B
�X�}�[�g�z��
���͂�R���f�B�e�B�Ƃ��āA����K�v���Ȃ����AiPhone��Android�[���̂悤�ȃX�}�[�g�z���́A�^���Ȃ�����̑�\�I�ȃX�}�[�g�f�o�C�X�ł���B�@�\�I�ȃ��[�U�C���^�t�F�[�X�A�l�b�g���[�N�T�[�r�X�@�\�AGPS�A�ʐM�@�\�A�Z�L�����e�B�@�\��������A�l�X�̐������x����K�{�̃c�[���ƂȂ����BIoT�̊ϓ_����́A���[�U�ւ̃��[�`���x����Ӗ��ŕK�{�f�o�C�X�ł���B
�X�}�[�g�X�s�[�J
Amazon Echo�AGoogle Home�AApple HomePod�Ȃǂ̃X�}�[�g�X�s�[�J�[�́A�����A�V�X�^���g�𓋍ڂ��A�����R�}���h���t���A���[�U���v��������̒�ƒ���̋@���T�[�r�X�̐�����s�����Ƃ��ł���B
�X�}�[�g�Ɩ�
Philips Hue�ATP-Link�Ȃǂ̃X�}�[�g�d���́A�X�}�[�g�t�H���≹���A�V�X�^���g����āA���邳��F���x��������A�^�C�}�[��ݒ肵���肷�邱�Ƃ��\�ł���B
�X�}�[�g�R���Z���g
SwitchBot��TP-Link�Ȃǂ̃X�}�[�g�R���Z���g�́A�Ɠd���i�������[�g�ŃI��/�I�t������A����d�͂����j�^�����O�����肷�邱�Ƃ��\�ł���B
�X�}�[�g�J����
TP-Link���e�Ђ������Ă���X�}�[�g�J�����́A�l�b�g���[�N�@�\��L���Ă���A���A���^�C���ʼnƂ̒���O�̏����j�^�����O������A���������m���ăA���[�g�𑗐M������ł��A������h�ƂɍL�����p����Ă���B
�G�A�^�O
�u�G�A�^�O�v�́AApple���J���������^�y�ʂ̒ǐՃf�o�C�X�ŁA�����ɂ́uAirTag�v�ƌĂ�A���������茩���ɂ������i��ǐՂ��邽�߂ɗp������B�ʐM��i�Ƃ��Ă�Bluetooth��Ultra Wideband�iUWB�j�̋Z�p��g�ݍ��킹�ē��삳����BBluetooth�ŋߋ����Ń��[�U�[��iPhone�ƃy�A�����O���AUWB���g�p���āA�G�A�^�O�̐��m�Ȉʒu����肷��B
3.2.2.4�@ �E�F�A���u���f�o�C�X
�X�}�[�g�f�o�C�X�̈��ł��邪�B���ɐl�ɑ������ėp��������̂̓E�F�A���u���f�o�C�X�ƌĂ��B��\�I�ȃf�o�C�X������������B
�@ �X�}�[�g�E�H�b�`
�X�}�[�g�E�H�b�`�́A�r�ɑ�������f�o�C�X�ŁA���v�̋@�\�����łȂ��A���N��t�B�b�g�l�X�̃g���b�L���O�A�ʒm�̎�M�A���y�̍Đ��A���ϓ��̋@�\�����B��\�I�Ȃ��̂�Apple Watch������B
�A �t�B�b�g�l�X�o���h
�t�B�b�g�l�X�o���h�́A����r�ɑ�������f�o�C�X�ŁA�^���⊈���ʁA�����Ȃǂ̌��N�����g���b�L���O���A���[�U�[�̌��N�Ǘ���t�B�b�g�l�X�ڕW�̒B�����x������B��\�I�Ȃ��̂�Google��Fitbit������B
�B �X�}�[�g�O���X
�X�}�[�g�O���X�́A���K�l�̂悤�Ȍ`��̃f�o�C�X�ŁA�f�B�X�v���C��J�����A�Z���T�𓋍ڂ��A���̕\����AR�i�g�������j�̌������B��Ƃ��Ă̓Z�C�R�[�G�v�\������������MOVERIO�����Ă���B
�C �E�F�A���u���J����
�E�F�A���u���J�����́A�g�ɒ����邱�Ƃ��ł���J�����ŁA�A�N�e�B�r�e�B��C�x���g���L�^���A�n���Y�t���[�ł̎B�e�⓮��z�M���s����BGoPro���L���ł���B
�D �E�F�A���u���w�b�h�Z�b�g
�E�F�A���u���w�b�h�Z�b�g�́A�����ɑ�������f�o�C�X�ŁA�����̎�M��M�A���z�����iVR�j��g�������iAR�j�̌������BMeta������Meta Quest��Microsoft������HoloLens���L���ł���B
3.2.2.5�@ �ʐM�Z�p
IoT�ł̓Z���T�������U���Ĕz������邱�Ƃ������A������萶����������K�ɏW�邽�߂ɒʐM�Z�p�͂قڕK�{�ƂȂ��Ă���BIoT�A�v���P�[�V�����̏ꍇ�A�ʐM�����͂��قǒ����Ȃ��Ă��悭�A�`�����x���ᑬ�ŗǂ�����ɒ����d�͂������v������邱�Ƃ������B�����ł͂�������\�I�ȋZ�p�����B
�@ Wi-Fi
Wi-Fi�́A����LAN�𗘗p�����ʐM�Z�p�ł���A�ƒ��I�t�B�X�Ȃǂ̉������ł悭�g�p����A���������肵���ʐM�����B�ŋ߂ł�Wi-Fi6��Wi-Fi6E�Ȃǂ̍L�ш�ȕ������o�����Ă����B
�A Bluetooth
Bluetooth�́A�ߋ��������ʐM�Z�p�ł���A�X�}�[�g�t�H����X�}�[�g�E�H�b�`�Ȃǂ̃f�o�C�X�Ԃł̐ڑ��ɍL���g�p����Ă���B�ȓd�͒ʐM��ړI�Ƃ���Bluetooth Low Energy�iBLE�j�Ȃǂ̋K�i���o�ꂵ�Ă���B
�B Zigbee
Zigbee�́A�����d�͂̃f�o�C�X�Ԃł̒ʐM�ɓ������������ʐM�K�i�ł���A�X�}�[�g�z�[����Y�Ɨp�r�ōL���g�p����Ă���B���b�V���l�b�g���[�N�̍\�z���\�ł���B�Ȃ��ߋ���/�����d�͂���������ʐM�����Ƃ��ẮAZ-Wave��ANT�Ȃǂ�����B
�C LPWA
LPWA(Low Power Wide Area)�͒������ł̒ʐM���\�ɂ�������d�̖͂����ʐM�Z�p�ł���A�L��̃Z���T�l�b�g���[�N�̍\�z�Ɏg�p�����B�Y�Ɨp�r��_�ƁA�s�s�C���t���̃��j�^�����O�Ȃǂŗ��p����邱�Ƃ������BLPWA�ɂ͊e��̃V�X�e��������ALoRa, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, ELTRES, ZETA�Ȃǂ��m���Ă���B
3.2.2.6�@ �ʐM�v���g�R��
IoT�ł́A�`��������͑��̃A�v���P�[�V�����ɔ�ׂ����Ώ��ʂł��邱�Ƃ������B���̂��߁A�ʐM�ɗp������v���g�R���͌y�ʂł����ʂ̃f�[�^�p�ɃI�[�o�[�w�b�h�̏��Ȃ����̂��p������B��\�I�ȒʐM�v���g�R���Ƃ��Ă͉��L�̂悤�Ȃ��̂�����B
�@ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
���Ƃ���IBM�ɂ���ĊJ�����ꂽ�y�ʂȃ��b�Z�[�W���O�v���g�R���ŁAIoT�f�o�C�X�Ԃ̒ʐM�ɍL���g�p����Ă���B��ш敝��s����ȃl�b�g���[�N���ł������I�ɓ��삵�A������p�u�T�u�iPublish/Subscribe�j�ƌĂ��A�ԂɃu���[�J����郂�f�����̗p���Ă���B
�A HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
�E�F�u�A�v���P�[�V�����ōL���g�p�����W���I�ȃv���g�R���ł����ARESTful�ȍl���������邱�ƂŁA�Z���T�̒l��₢���킹�ē���Ȃ�IoT�f�o�C�X�Ԃ̒ʐM�ɂ��L�����p����Ă���BRESTful API���������邱�ƂŁA�f�o�C�X�Ԃ̃f�[�^��������p�ӂɍs�����Ƃ��ł��܂��B
�B CoAP (Constrained Application Protocol)
HTTP�͔�r�I�d���v���g�R���ł��邽�߁A�@�\���y�ʉ������v���g�R���ł���BIoT�f�o�C�X��Z���T�l�b�g���[�N�ł̒ʐM�ɓK���Ă���BUDP��œ��삵�ARESTful�ȃC���^�t�F�[�X����Ă���B
�C AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)
���b�Z�[�W�w���~�h���E�F�A�V�X�e�������ɁAMQTT�Ɠ��lPublish/Subscribe ������p�����v���g�R���ł���B��{�͋��Z�@�ւł̃V�X�e���̂悤�ȃ��b�Z�[�W�L���[�̈��S�ȓ]����z�M���s�����߂Ɏg�p����邪�AIoT�V�X�e���ɂ����Ă��A�M�����̍����ʐM����������ۂɗ��p�����B
3.2.2.7�@ IoT�Ɏg����f�[�^�t�H�[�}�b�g
IoT�ŗp������f�[�^�t�H�[�}�b�g�Ƃ��ẮA�y�ʂł��ǐ��ɗD�ꂽ�t�H�[�}�b�g���]�܂��B��\�I�Ȃ��̂Ƃ��ĉ��L����������B
�@ JSON (JavaScript Object Notation)
�y�ʂŐl�Ԃɂ��ǐ��������f�[�^�t�H�[�}�b�g�ŁA�L�[�ƒl�̃y�A����Ȃ�e�L�X�g�x�[�X�̌`���ł���BWeb�A�v���P�[�V������RESTful API�ȂǂōL���g�p����Ă���B
�A XML (eXtensible Markup Language)
�\�������ꂽ�f�[�^��\�����邽�߂̃}�[�N�A�b�v����ŁA�^�O�Ɨv�f����Ȃ�e�L�X�g�x�[�X�̌`���ł���B�E�F�u�T�[�r�X��f�[�^�̌����t�H�[�}�b�g�Ƃ��čL���g�p����Ă������A�ߔN��JSON�Ɏ���đ����邱�Ƃ������Ă���B
�B Protocol Buffers (protobuf)
Google���J�������o�C�i���`���̃f�[�^�t�H�[�}�b�g�ŁA�v���g�R���o�b�t�@�Ƃ��Ă��B�����I�ȃf�[�^�̒���(�K�w�������Ȃ��t���b�g�Ȉ�Ȃ���̃f�[�^�ɕϊ�����)��t�����������A�v���g�R���o�[�W�����Ǘ���f�[�^�\���̊g��������Ă���B
�C RDF(Resource Description Framework)
�@RDF�̓f�[�^���O���t�\���ŕ\�����߂̕\�L�@�ŁA�g���v���b�g�Ƃ��ĕ\�����ꂽ����p���ăf�[�^���f����\������B�Ӗ���\���ł���Z�}���e�B�b�NWeb���x����Z�p�ƌ����Ă��邪�AIoT�̗̈�ŗp�����邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��B
3.2.2.8�@ �f�[�^�����ƕ��͋Z�p
IoT�ɂ���ē���ꂽ�f�[�^�ɑ��Ă͓K�ɏ������͂��s�����Ƃɂ���āA���܂��܂ȉ��߂⓴�@�A�X���邱�Ƃ��ł���B�����ł͈�ʓI�ȋZ�p������������B
�@ �f�[�^�}�C�j���O
�f�[�^�}�C�j���O�́A��ʂ̃f�[�^����p�^�[����W�������邽�߂̎�@�ł���B�W�߂�ꂽ�f�[�^�ɑ��āA�N���X�^�����O�A���ށA��A�A�ُ팟�o�ȂǓ��v�Z�p��AI�Z�p���K�p�����B
�A �N���X�^�����O
�������������f�[�^�|�C���g���O���[�v�������@�ŁA�f�[�^�̍\����W���𗝉�����̂ɖ𗧂B��\�I�Ȏ�@�ɂ́AK-means�@�A�K�w�I�N���X�^�����O�ADBSCAN�Ȃǂ�����B
�B �@�B�w�K
�@�B�w�K�́A�f�[�^����w�K���A�p�^�[����\�����f�����\�z����Z�p�ł���B���t����w�K�A���t�Ȃ��w�K�A�����w�K�Ȃǂ̃A�v���[�`������A���ݍł��i�����������̈�ƂȂ��Ă���B��\�I�Ȏ�@�Ƃ��āA��A���́A����A�����_���t�H���X�g�A�j���[�����l�b�g���[�N�Ȃǂ�����B
�C ���v���
���v��͂́A���v�I��@��p���ăf�[�^�Z�b�g�̓�����W���𗝉����邽�߂ɗp������B���ρA�W�����A���ցA��A�Ȃǂ̓��v�ʂ��g�p����A�W���I�ȉ�͋Z�p�̂ЂƂł���B
�D �r�b�O�f�[�^����
�r�b�O�f�[�^�����Z�p�͑�e�ʂ̃f�[�^�������I�ɏ������邽�߂̎�@�ŁA�N���E�h�R���s���[�e�B���O���s�����߂ɂ͕K�{�̋Z�p�ƂȂ��Ă���BHadoop�Ȃǂ̕��U�����t���[�����[�N���g�p�����B
�E ���A���^�C������
���A���^�C�������Z�p�́A�f�[�^���ɏ������ă��A���^�C���̓��@�邽�߂̎�@�ł��B���ɍ����ő�ʂ̃f�[�^�ɑ��u���ɔ����ł���悤�A�X�g���[�������A���G�C�x���g�����iCEP: Complex Event Processing�j�A���A���^�C�����͂Ȃǂ��p������B
3.2.2.9�@ �N���E�h�R���s���[�e�B���O�Z�p
�Z���T�œ���ꂽ�f�[�^�̓l�b�g���[�N����ďW��A�K�ȏ���/���͂��s���ĉ��������̂��ʏ�ł���B���̈�A�̏������s���v���b�g�t�H�[���͒ʏ�N���E�h�̒��Ŏ�������邱�Ƃ������B
�����̃v���b�g�t�H�[���Ƃ��Ă�2007�N�ɏo������Pachube������AIoT�̃A�[���A�_�v�^�ɂ悭�p����ꂽ�B2011�N�̓����{��k�Ђł�Pachube��p�������˔\�g�U��L���{�����ꂽ�B���T�[�r�X�͂��̌�2011�N��Xively�ɖ���ς�����A2018�N�ɂ�Google IoT �N���E�h�̈ꕔ�ƂȂ����B
���݂ł͑��̃N���E�h�v���b�g�t�H�[��(AWS, Google, Azure�Ȃ�)�͂������IoT�����̃T�[�r�X���܂Ƃ߂Ē��Ă���B�����ł�AWS(Amazon Web Services)���ɂƂ���IoT�����̃N���E�h�R���s���[�e�B���O�T�[�r�X�ɐG���B
�@ �N���E�h�v���b�g�t�H�[��
AWS IoT�́AIoT�f�o�C�X����̃f�[�^�����W���A�f�o�C�X�̊Ǘ���A���^�C�����́A�\�����͂Ȃǂ̋@�\����Ă���B
�A �N���E�h�X�g���[�W
Amazon S3�́A�N���E�h�X�g���[�W�Ƃ��đ�e�ʂ̃f�[�^��ۑ����A�K�v�Ȏ��ɃA�N�Z�X�\�ł���B
�B �N���E�h�f�[�^�x�[�X
Amazon DynamoDB�͑�K�͂ȃN���E�h�f�[�^�x�[�X�ŁA��K�͂ȃf�[�^�Z�b�g���Ǘ����A�����ŃX�P�[���u���ȃf�[�^���������s����B
�C �N���E�h�R���s���[�e�B���O
Amazon EC2�́A���z�T�[�o���N���E�h��œ��I�Ɋ��蓖�āAIoT�f�o�C�X����̃f�[�^�̏������x������N���E�h�R���s���[�e�B���O�T�[�r�X�ł���B�����\�͂��_��Ɋ��蓖�Ă邱�Ƃ��ł���B
�D �T�[�o�[���X�R���s���[�e�B���O
AWS Lambda�́A�́A�K�v�ɉ����ăR�[�h�����s���A���\�[�X�̊Ǘ�������������T�[�o�[���X�R���s���[�e�B���O�T�[�r�X�ł���BIoT�Z���T�Ȃǂ���̃g���K���x�[�X�Ƃ����C�x���g�h���u���ȃR���s���[�e�B���O���e�ՂɎ����\�ł���B
3.2.3�@ IoT�̑�\�I�ȃT�[�r�X��
�{�͂ł́AIoT�̑�\�I�ȃT�[�r�X����������B
3.2.3.1�@ �X�}�[�g�z�[��
�ƒ���̗l�X�ȃf�o�C�X�i�Ɩ��A�Z���T�A�Ɠd�Ȃǁj�����o�C���A�v���≹���A�V�X�^���g�ɂ���āA���u����f�o�C�X�𐧌䂵����A�����������肷�邱�Ƃ��s���B�Ɠd�����Ɩ�����A�G�A�R���̐���ɂ�鉷�x�Ǘ��A�Z�L�����e�B�J�����A�X�}�[�g���b�N�A�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���Ȃǂ��܂܂��B2022�N�ɂ̓A�}�]���A�O�[�O���A�A�b�v���Ȃǂ����S�ƂȂ����X�}�[�g�z�[���̂��߂̋��ʋK�iMatter�i�}�^�[�A�ȉ��}�^�[�j�������[�X����A����ɏ������邱�ƂŁA���l�ȉƓd�̐���Ǘ����\�ɂȂ낤�Ƃ��Ă���B
3.2.3.2�@ �X�}�[�g�V�e�B
������ʃV�X�e���̊Ď��A�S�~���̃t����Ԃ̃��j�^�����O�A���H��ʂ̗���̍œK���A�����Ɩ��̐���ȂǁA�s�s�C���t���̌���������P�Ɋ��p���ꂦ��B
3.2.3.3�@ �_��
�y��Z���T�A�C�ۃZ���T�A���V�X�e���Ȃǂ̃f�o�C�X���g�p���āA�_�앨�̐�������j�^�����O���A���ʓI�Ȕ_�ƊǗ����s���B
3.2.3.4�@ �Y�Ɨp IoT
�����v���Z�X�̊Ď��ƍœK���A�@��̕ۑS�Ǘ��A�����`�F�[���̉����ȂǁA�H���q�ɂł̌�������Y������Ɋ��p�����B
3.2.3.5�@ �w���X�P�A
�g�ɂ���f�o�C�X�i�E�F�A���u���j��Z���T��p���āA�l�̌��N��Ԃ����A���^�C���Ń��j�^�����O���A��Ë@�ւ���҂Ƌ��L����B
3.2.3.6�@ ���r���e�B
�����^�]�Ԃ̊J����A�ԗ��̃����[�g�Ď��A�^�]�f�[�^�̎��W�A��ʏ��̃��A���^�C���X�V�Ȃǂɗ��p�����B
3.2.3.7�@ ������
�ɊǗ��A�̔��f�[�^�̎��W�A�ڋq�s���̕��́A�X�}�[�g�V���b�s���O�̌��̒ȂǁA�����ƊE�ɂ������������ڋq�T�[�r�X����ɉ��p�����B
3.2.3.8�@ �G�l���M�[�Ǘ�
�X�}�[�g���[�^�[�̓����ɂ��d�͎g�p�ʂ̃��A���^�C���Ď���œK���A�Đ��\�G�l���M�[�̌����I�ȗ��p�Ȃǂ��܂܂��B
3.2.4�@ �����O�ɂ�����IoT���c��A�W�����@�ւȂ�
�{�͂ł́A�����O�ɂ�����IoT�Ɋ֘A�����W�����@�ւ�t�H�[�����A���c��ɂ��ĐG���B
3.2.4.1�@ ���ۓI��IoT�W�����g�D
�@ ITU-T SG20 https://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sg20.aspx
�O���[�o���ȕW�����@�ւƂ��ẮA���ۋ@��ITU-T�̃O���[�v�̈�ł���ITU-T SG20 ����������BSG20�̓X�}�[�g�V�e�B�Ƃ��̒ʐM�Ɋւ���IoT�A�v���P�[�V�����ɏœ_�ĂČ������s���Ă���B
�A IEEE Internet of Things�iIoT�jTechnical Community https://iot.ieee.org/
IEEE�ɂ����ẮAIoT�S�ʂ̋Z�p�̔��W�A�W�����A����щ��p���T�|�[�g���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�B OneM2M https://www.onem2m.org/
OneM2M�́A2012�N�ɐݗ����ꂽ�قȂ�ƊE��IoT�f�o�C�X��A�v���P�[�V�����Ԃ̑��݉^�p���ƌ��������m�ۂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����A�O���[�o���ȑg�D�ł���B�W�����A�Z�L�����e�B�A���݉^�p���̊m�ۂɊւ��Č�������Ă���B
3.2.4.2�@ �����ɂ�����IoT�֘A�g�D
�����ɂ����ẮAIoT��ړI�Ƃ��Ċe��̋��c���t�H�[�������ݗ����ꊈ�����s���Ă���B�����ł͎�ȑg�D���Љ��B
�@ �X�}�[�gIoT�t�H�[����<https://smartiot-forum.jp/about>
�X�}�[�gIoT�t�H�[�����́A2015�N10���ɐݗ�����AIoT���Ɋւ���A�Z�p�J���A�W�����A����уX�}�[�gIoT�\�����[�V�����̎��p�����x�����邽�߂ɁA�Y�ƊE�A�w�p�E�A���{�@�ւ����͂��Ċ������Ă���B
�A
�X�}�[�g�V�e�B�����A�g�v���b�g�t�H�[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��https://www.mlit.go.jp/scpf/about/index.html>
���v���b�g�t�H�[���́A���{�@�ցA���Ԋ�ƁA�s���Ƃ̋��͂�ʂ��ăX�}�[�g�V�e�B�̊J���𑣐i���邽�߂̎��g�݂ł���B���̃v���b�g�t�H�[���́AIoT�₻�̑��̐�i�Z�p���g�p���āA���܂��܂ȓs�s�@�\��T�[�r�X�����A�������I�Ŏ����\�A�����ďZ�݂₷���s�s��n�����邱�Ƃ�ڎw���Ă���B�{�v���b�g�t�H�[���ɂ́A���t�{�A�����ȁA�o�ώY�ƏȁA���y��ʏȁA�f�W�^�����炪����A�˂Ă���B
�B �n��DX���i���{�^�n����IoT���i���{https://local-iot-lab.ipa.go.jp/
���{�ɂ�����n��DX���i���{��n����IoT���i���{�́A�f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V�����iDX�j��IoT�Z�p�̒n��ւ̓����ƕ��y��ړI�Ƃ��Ċ������s���Ă���BIPA���劲�ł���B�{���{�́A���ɒn�������̂�n��o�ς̊������ɏœ_�āA��i�Z�p�����p���Ēn��ŗL�̉ۑ���������A�V���ȉ��l�n�o��ڎw���Ă���B
�C
�Z�L���A IoT �v���b�g�t�H�[�����c��
�@�@�@�@�@�@<https://www.secureiotplatform.org/about>
�����c��́AIoT�f�o�C�X��T�[�r�X�̃Z�L�����e�B���������A�M���ł���IoT���̍\�z��ڎw���c�̂ł���BIoT�̕��y�ɔ����Z�L�����e�B�̊m�ۂ͋ɂ߂ďd�v�ȉۑ�ł���A���c��́A�Z�L�����e�B���X�N�ɑΏ����A���S��IoT�G�R�V�X�e���𐄐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�D
IoT�T�[�r�X�A�g���c��
�@�@�@�@�@�@�@<https://www.aiots.org/about/establishment/>
IoT�T�[�r�X�A�g���c��́A�قȂ�IoT�T�[�r�X��v���b�g�t�H�[���Ԃ̘A�g�𑣐i���A���ꂳ�ꂽIoT�G�R�V�X�e���̍\�z��ڎw���c�̂ł���B���̋��c��̎�ȖړI�́A�@���v���b�g�t�H�[���̑��݊����E���݉^�p�������コ���邱�Ƃɂ���B
3.2.5�@ IoT�̃r�W�l�X���Ƃ���ɂƂ��Ȃ��ۑ�
3.2.5.1�@ IoT�̃r�W�l�X�̈�
3.�ł͊e���IoT�T�[�r�X�ɂ��ĐG�ꂽ�������ł͂����̃r�W�l�X���Ƃ���ɂƂ��Ȃ��ۑ�ɂ��ďq�ׂ�
�r�W�l�X�̈�ł�B2B��B2C�̗�����ɂ�����IoT�r�W�l�X�̎��g�݂����{����Ă���B
B2B�̈�ł͐�̃X�}�[�gIoT�t�H�[�����ɑ����̎��Ⴊ�f�ڂ���Ă���ʂ�A�����Ƃ��\��Ƃ��āA���Y���C���̍œK����@�B�̉��u�Ď��A�\�h�ۑS�A�G�l���M�[�Ǘ��A�T�v���C�`�F�[���̌������Ȃǂ��s���Ă���B�܂��A�����ƂɌ��炸�����A�_�ƁA���݂ȂǑ��̎Y�Ƃł������ȗ��p�̋@�^������B
���B2C�̈�ł̓X�}�[�g�z�[���f�o�C�X�A�E�F�A���u���Z�p�A���N�Ǘ��A�v���P�[�V�����ȂǁA����Ҍ�����IoT���i�̕��y���n�܂��Ă���B�܂��A�����ԋƊE�ɂ�����i�r�Q�[�V������ԗ��Ǘ����s���R�l�N�e�b�h�J�[���A��ʏ���Ҍ���IoT�Z�p�Ƃ��ďd�v�ł���B
�r�W�l�X���́A�s��̃j�[�Y��ƊE�̐��n�x�ɂ���Ĉق�BB2B�\�����[�V�����́A�R�X�g�팸���������}��ړI�ŁA��r�I��������i��ł������A����҂ɒ��ڊւ��B2C�Ɋւ��ẮA��w�̏���҂̎���̈ӎ��g�傪���҂����B
���{�ł́A�X�}�[�g�V�e�B��Љ�ۑ�̉�����ڎw�����v���W�F�N�g�A�܂����[�J��5G�̗��p���i�ȂǁA���{����̐ϋɓI�Ȏx���������AB2B�����B2C�̗�����IoT�̃r�W�l�X�����i�݂���ƌ����悤�B
3.2.5.2�@ ���E�ɂ�������{��IoT�r�W�l�X
���E�I�Ɍ����Ƃ����{��IoT�r�W�l�X�̌���͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��낤���H
�} 3‑42�́A������ �gIoT���ۋ����͎w�W -2021�N���� [�T�v]- ���甲������IoT�s��̍��E�n��ʃV�F�A�Ɛ����������������̂ł���B���������ƁAIoT�s��S�̂ł͒����̃V�F�A���ł������A�č��Ɠ��{�������ł��邪���{�̃V�F�A��2016�N����2021�N�ɂ���
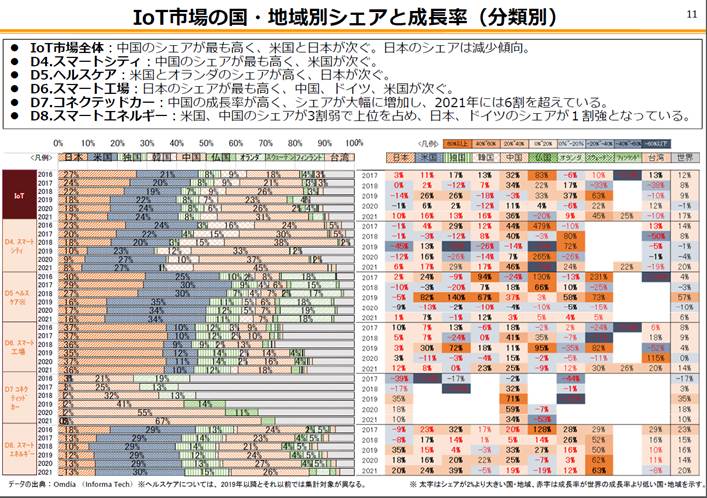
�} 3‑42�@IoT�s��̍��E�n��ʎЂƐ������i������ �gIoT���ۋ����͎w�W -2021�N���� [�T�v]- �j���甲���h
��27%����17%�ɂ܂ʼn��~���Ă��邱�Ƃ��킩��B���E�I�ɂ�IoT�s��͐����𑱂������A���{�̋����͂͑��ΓI�ɒቺ���Ă��邱�Ƃ��킩��B���̌����͂����炭����20�N����ICT���������E�̑����ɔ�ׂē��{�������x��Ă����̂ƒʂ���_�ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���H
�����ɋL�����Ƃ��A���{��DX���̒x��AICT�ւ̓����͒P�Ȃ�������E�ȗ͉���ړI�Ƃ����P�[�X�������A�V���ȃr�W�l�X�𗧂��グ��悤�ȐV���l�n���ɂȂ����Ă��Ȃ��Ƃ̎w�E�����邪�A�����ɂ����Ă͂܂邩�Ǝv����BIoT�ɂ��V�r�W�l�X�n�o�����҂����B
���{�ŃO���[�o�������ꂽIoT�r�W�l�X��j�Q���Ă��錴���̂ЂƂɃO���[�o���ȕW������i�߂�\�͂Ɍ����Ă���_���������悤�B����o���A�������ɂǂ����Ă��I�[���W���p���Ƃ��ē������[�����^��������A�N���X�{�[�_�ŕW�����A�Ђ��Ă̓r�W�l�X����������Ƃ���܂ōs���ĂȂ���������B
3.2.5.3�@ �P�[�u���e���r�ƊE�ɂ�����IoT
�T�_
�G���h���[�U�̉ƒ�ڌڋq�Ƃ��Ċm�ۂ��Ă���P�[�u���e���r���Ǝ҂́AIoT�����p���ėl�X�ȕ���ŐV���ȃT�[�r�X��r�W�l�X���f���̍\�z��ڎw���͔̂��ɖ]�܂������Ƃł���B�P�[�u��TV���Ǝ҂́A�G���h���[�U�ւ̃��[�`�ɉ����āA�n��ڋq�u���̃X���[���N���E�h�I�ȋ@�\�����邱�Ƃł������̃T�[�r�X�̉\�����J������Ǝv����B
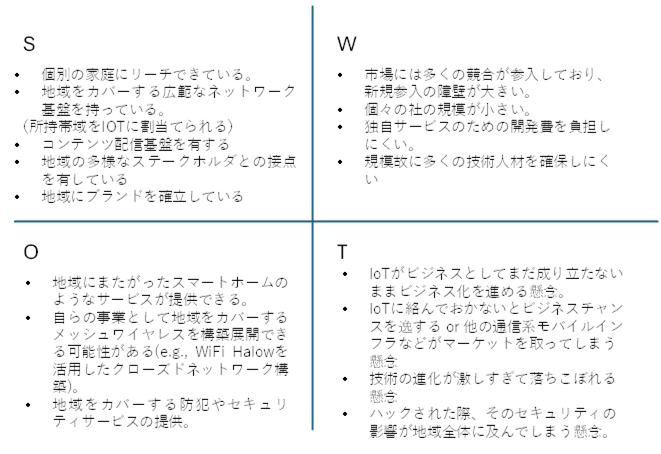
�} 3‑43�@�P�[�u�����Ǝ҂�IoT�T�[�r�X����������ۂ�SWOT��
��ʓI�ł͂��邪�A���{�̃P�[�u��TV��Ђ�IoT�r�W�l�X����������ɍۂ��Ă�SWOT�������Ă݂��B�����} 3‑43�Ɏ����B���݂͊��ɑ����̉ƒ�Ƀ��[�`���Ă���l�b�g���[�N��ՂȂ�тɑш��L���Ă��邱�ƂŁA���R���e���c�z�M���\�ȋ@�\�����ɂ���_�ł���B�����݂͋ƊE�ł̌X�̎Ђ̋K�͂����������߁A�v������������S���I�ȃX�y�b�N���ꂪ�e�Ղł͂Ȃ��_���������悤�B�@��Ƃ��Ă͒n��S�̂��J�o�[���Ă���̂ŁA��������ėႦ�Βn��S�̂��J�o�[����悤�Ȗh�Ƃ�A���R�ЊQ�Ď��Ȃǂ����������L���ɂȂ�Ǝv����B�Ō�Ɏ�_��������Ƃ���A�n����J�o�[���Ă��邪�̂ɁA�����C���V�f���g�����������ۂɂ͂��̉e�����n��S�̂ɋy�т���_��������Ȃ��B
3.2.5.4�@ 6.2 �P�[�u�����Ǝ҂ɂ��IoT�T�[�r�X
������āA���ɐ��X�̃P�[�u��TV�ł̓T�[�r�X���s���Ă��邪�A��\�I�ȃr�W�l�X�Ƃ��Ă͎��̂悤�ȍ��ڂ���Ƃ��ċ������悤�B
���̓X�}�[�g�z�[���T�[�r�X�ł���B��ɏq�ׂ��X�}�[�g�z�[���f�o�C�X��l�b�g���[�N�ڑ����ꂽ�Ɠd����A�ڋq�̉ƒ���X�}�[�g�z�[�������邽�߂̃T�[�r�X�̓W�J�ł���B
���̌��Ƃ��ẮA�Z�L�����e�B�T�[�r�X�̒ł��낤�B �P�[�u��TV���Ǝ҂��Z�L�����e�B�J������z�[���Z�L�����e�B�V�X�e������AIoT�Z�p�����p���Čڋq�̉ƒ��r�W�l�X�̃Z�L�����e�B�����コ����T�[�r�X�̓W�J�����蓾�悤�B�P�[�u��TV���Ǝ҂̏ꍇ�A�n��ɖʓI�ɓW�J���邱�Ƃ��\�Ȃ̂ŁA�ʌڋq�̃Z�L�����e�B�݂̂Ȃ炸�G���A�Ƃ��ẴZ�L�����e�B�����@���������`�����X������Ǝv����B
����Ɍ��ƂȂ�̂͒n��S�̂ŊǗ��\�ȃG�l���M�[�Ǘ��T�[�r�X����������B �P�[�u��TV���Ǝ҂��G�l���M�[���j�^�����O�V�X�e����X�}�[�g���[�^�[����A�ڋq�̃G�l���M�[�g�p�ʂ��Ď����A�ߖ����������x������T�[�r�X��W�J����T�[�r�X���l������B���̏ꍇ�A�n��Ƃ��Ă̋C����d�͋����̓x���������v�炢�A�œK�Ȑ�����g�[�^���ŕ]��������A�e�ƒ��I�t�B�X�ւ̐�����s���V�i���I���l������B�����B2C�ւ̓K�p�ł������AB2B�Ƃ��ẴG�l���M�[�}�l�[�W�����g�ł���Ƃ�������B
3.2.6�@ IoT�̓W�]
�{�͂ł́A���܌��J�I�Ȃ���A�����IoT�ɂƂ��đ傫�����W�𐋂����|����ɂȂ肻���ȍ��ڂɂ��Đ����������B
3.2.6.1�@ AI��IoT
�^���]�n���Ȃ��AAI��IoT�f�o�C�X����������c��ȃf�[�^����Ӗ��̂��铴�@�𒊏o���A�X�}�[�g�Ȉӎv������T�|�[�g���邱�ƂŁAIoT�̉\����傫���L���悤�B����IoT�ł�xx�����o�������A�Ƃ������悤�Ȓ�^�I�ȗv�����������߁A�@�B�w�K�ɂ���Đl�Ԃ��ւ�邱�ƂȂ��A�܂�������f�����N���s�v�ŕK�v�ȏ������s����\��������B�ł���@�\��Ƃ��ẮA
• ���A���^�C���f�[�^����: �Z���T����̃��A���^�C���f�[�^��v���ɕ��͂��A�����̃t�B�[�h�o�b�N��A�N�V���������{����B
• �p�^�[���F��: �@�B�w�K�������邱�ƂŁA�擾�f�[�^�̒�����p�^�[����F�����A�ُ팟�m��\�����͂����{�B
• �\���ێ�: �̏�\����@��̃����e�i���X���K�v�ȃ^�C�~���O��\�����A�_�E���^�C���������B
• �p�[�\�i���C�[�[�V����: ���[�U�̏K����D�݂��w�K���A�J�X�^�}�C�Y���ꂽ���[�U�[�G�N�X�y���G���X�����B
• �Z�L�����e�B�Ď�: �ُ�ȃl�b�g���[�N�g���t�B�b�N��s�R�ȍs�������o���āA�Z�L�����e�B�N�Q��h�����߂̑����x���V�X�e�������B
�@�B�w�K��IoT�̑g�ݍ��킹�́A�P�Ƀf�[�^�����W���邾���łȂ��A���̃f�[�^�����p���ĐV���ȉ��l��n��������B
3.2.6.2�@ �G�b�W�R���s���[�e�B���O
�@IoT�ɂ�����G�b�W�R���s���[�e�B���O�́A�f�[�^���W���f�[�^�Z���^�[��N���E�h�ł͂Ȃ��A�f�[�^�̔������ɋ߂��u�G�b�W�v�A�T�^�I�ɂ͌��n�Ńf�[�^���W��m�[�h�ŏ�������A�v���[�`�ł���B����ɂ��A�������Ԃ̒Z�k�A�ʐM�ш敝�̐ߖ�A�v���C�o�V�ƃZ�L�����e�B�̌��オ�\�ƂȂ�B���̓����Ƃ��āA���M�ɂ����鎞�Ԃ��ȗ����A���A���^�C���ɋ߂��������\�ɂ����x�����A�K�v�܂��͏d�v�ȃf�[�^�݂̂��G�b�W�őI�����đ��M���邱�Ƃɂ��l�b�g���[�N�̑ш�ߖ�A�s�v�ȃ��[�U�f�[�^�̓t�B���^���đ���Ȃ����Ƃɂ��v���C�o�V�[�ƃZ�L�����e�B�̊m�ہA���Ƀl�b�g���[�N����Q�ƂȂ��Ă����[�J���œ���p�������錘�S���Ȃǂ������b�g�Ƃ��ċ�������B
�G�b�W�R���s���[�e�B���O�́A�����^�]�ԁA�X�}�[�g�t�@�N�g���[�A�s�s�C���t���Ǘ��A�H����̐��Y���Ǘ��ȂǁA�x����������Ȃ����ł�IoT�A�v���P�[�V�����ɓ��ɏd�v�ł���B
3.2.7�@ Federated Learning�i�A���w�K�j
���Ƀf�o�C�X�����U�z�u�����P�[�X������IoT�\�����[�V�����Œ��ڂ����@�B�w�K�Z�p�̂ЂƂ�Federated Learning�ł��낤�A�f�[�^�̃v���C�o�V�[��ی삵�Ȃ���@�B�w�K���f�����g���[�j���O���邽�߂̃A�v���[�`�ŁA2017�NGoogle�ɂ���Ē�Ă��ꂽ�B�Ⴆ�Όl�l�̃X�}�[�g�z���̕������͂ɂ��āA�S�Ă̓��͂��N���E�h�ɏW�߂��X�̃X�}�[�g�z���ŕ��U�w�K�������ʂ݂̂��A�b�v���[�h���Ė߂����ƂŌl�f�[�^�̃v���C�o�V�����A�w�K�����{�ł��邽�߁A������ɁA��ÁA���Z�A�X�}�[�g�V�e�B�ȂǁA�f�[�^�̋@���������ɏd�v��IoT�A�v���P�[�V�����ŘA���w�K�͏d�v�ɂȂ�ƍl������B
3.2.8�@ FIWARE
FIWARE�́A���[���b�p�Ŏn�܂����C�j�V�A�e�B�u�ŁA�W�������ꂽ�X�}�[�g�\�����[�V�����̊J���̂��߂̃v���b�g�t�H�[���ł���B�X�}�[�g�V�e�B�A�X�}�[�g�C���_�X�g���[�A�X�}�[�g�A�O���J���`���[�ȂǁA���܂��܂ȕ���̃f�W�^���ϊv���x�����邽�߂�API��f�[�^���f������`�������Ă���B
FIWARE�̎�v�ȃR���|�[�l���g�Ƃ��ẮA�f�o�C�X��Z���T����̏����W�A�f�[�^�����A���^�C���ŏ�������I���I���R���e�L�X�g�u���[�J�[�A�قȂ�IoT�v���g�R���ƃR���e�L�X�g�u���[�J�[�Ƃ̊Ԃŏ���ϊ�����IoT�G�[�W�F���g�A�A�v���P�[�V�������e�ՂɃf�[�^�ɃA�N�Z�X�ł��邽�߂̃f�[�^/�R���e�L�X�gAPI�A�A�v���P�[�V�����Ԃŋ��ʂ̗����𑣐i���邽�߂̕W�������ꂽ�f�[�^���f������������B
�@FIWARE�͓��ɁA���݉^�p���̖����������邱�Ƃɏœ_�āA�R���e�L�X�g�������ɕ\���ł���X�L�[��������Ă���B���̂��ߌ����̃C���t���Ǘ��A��ʊǗ��A�G�l���M�[�Ǘ��ȂǑ���ɂ킽��p�r�ɓK�p����Ă���B����ŁA�L�@���I���g���W�I�ł���̂ŁA�p������L���̈�Ō�b�̍��v���K�v���Ǝv����B
3.2.9�@ ������
IoT�́A���ꂩ����{�ɂƂ��ĊԈႢ�̂Ȃ��ۑ�ƂȂ鏭�q����A�h�ЁE���Б�A�C���t���ێ��A�l�X�̌��N�ێ��A�e��Y�Ƃ̔��W�ɂƂ��ăG�b�Z���V�����Ȗ������ʂ������ƂɂȂ�B�������A���̑��x�͌����Ĉ�C�ɐi�ނ킯�ł͂Ȃ��A�������̃g���C�A���̃x�X�g�v���N�e�B�X�̒�����B2B�̃r�W�l�X�����܂�A����҂������̃f�o�C�X�ɐG��A���̗�������������A�����ē�����O�̓���̃R���f�B�e�B�ƂȂ�Ƃ���B2C�̃r�W�l�X���������W���Ă䂭�ł��낤�B
�@�n�߂͕��y���͂��������Ȃ���������Ō��݂͍L�����y���Ă����Ƃ���IPv6������B2000�N�����ɓ��{��IPv6�Z�p�ɏG�łĂ���ƌ����Ȃ���A���y�͑S���i��ł��Ȃ������B�������Ȃ���IPv4���͊����A�A�b�v����}�C�N���\�t�g�AGoogle�炪��������IPv6�̃T�|�[�g/�ڍs��i�߂�ƁA�����Ƃ����Ԃɐ��E�ɂƂ��ē�����O�̑��݂ɂȂ����BIoT���܂����y���Ȃ����Ȃ��A�ƌ����Ȃ���A���̂܂ɂ��C��������g�̉��ɂ����ē�����O�ŒN�������s�v�c�Ǝv��Ȃ����E�ɂȂ��Ă���ƕM�҂͑z������B
3.3�@ �V�����f���T�[�r�X�^�Z�p�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
3.3.1�@ XR
3.3.1.1�@ XR�̖���
Society 5.0�̎����Ɍ����āA�t�B�W�J����ԂƃT�C�o�[��Ԃ���̉�����\�z�ł���CPS�i�T�C�o�[�E�t�B�W�J���E�V�X�e���j���f�����Ă���B���̍\�z��������邽�߂̋Z�p�̂ЂƂ�XR�ł���BXR�́AVR (Virtual Reality) ��AR (Augmented Reality) �AMR (Mixed Reality) �ȂǁA�T�C�o�[��Ԃƃt�B�W�J����Ԃ�Z�����������ʂ�l�Ԃ̒m�o�Ƀt�B�[�h�o�b�N����Z�p�̑��̂ł���B�T�C�o�[��Ԃɂ�����AI�Ȃǂŕ��͂������ʂ��A�t�B�W�J����Ԃɓ`�B���邱�ƂŁA�l�̍s���Ȃǂ�ϗe�����������S���BXR�Z�p�����p�����R���e���c�́A�܊����~�b�N�X���ꂽ����܂łɂȂ��Տꊴ���̌����A�����鐶���V�[���̒��őn�o���邱�Ƃ��ł���B
3.3.1.2�@ XR���ڎw���p
2030�N�ɂ́A������ꏊ�ɐݒu���ꂽIoT�f�o�C�X��Z���T�ɂ��A�t�B�W�J����Ԃ̏��̓X�L��������A�T�C�o�[��ԏ�Ńt�B�W�J����Ԃ��Č��ł���悤�ɂȂ�A�����ɉˋ�̕��i��m�܂ŏd�ˍ��킹��悤�Ȋg������������邱�Ƃ����҂����B
�����́A�T�C�o�[��ԏ�ō\�z���ꂽ���E�ł��郁�^�o�[�X�Ȃǂ̃v���b�g�t�H�[�������XR�Z�p�ɂ�胆�[�U�ɒ����B���o�I�ɂ́A���ʓI�ȉf���\���ɗ��܂炸�AVR�^AR�O���X�ł̒͂������A���̉f����\������z���O���t�B�ɂ������ƌ��������t���Ȃ����̕\�������������B�܂��A��̍L����܂ł��������闧�̉�����m�ɐG�ꂽ���o����t�H�[�X�t�B�[�h�o�b�N�Ȃǂ̗l�X�Ȓm�o�\����g�ݍ��킹�Č܊��ɓ`�B����}���`���[�_���A�g�����������B����ɂ́A�T�C�o�[��Ԃƃt�B�W�J����Ԃ��Ȃ��A�����̖c��ȃf�[�^���u���Ɏn�����\�ȍ������`�������������B
��������XR�Z�p�̐i�����R�~���j�P�[�V�����X�^�C���ɑ���ȕϊv�������炷�B��̓I�ɂ́A�����̕����ɂ��Ȃ���A�ߋ��ɖK�ꂽ�ꏊ���Č����A���̎v���o�����u�̉Ƒ���F�l�Ƌ��L����B�e�����l�̌��ɐG��A�����Ǝ���d�˂�B����Ȍ��t�����ł͓`���Ȃ��@�ׂȃj���A���X�̕\���܂ł��\�Ƃ���B
�t�B�W�J����Ԃ��Z���V���O�������̓T�C�o�[��ԂŊg������A�܊��ɓ���������XR�R���e���c�Ƃ��āA�������Ƀf�[�^���k���ꂽ�`�ŁA�^�C�����O�����������邱�ƂȂ��݂��̋�Ԃ��s��������B���̌��ʁACPS�ɂ����ăV�[�����X��XR�̌��������炷�B
3.3.1.3�@ ���̒��̓���
COVID-19�̊����g��ɔ��������[�g���[�N��o�[�`�����C�x���g�̋}���ȕ��y�ɔ����A���^�o�[�X�𒆐S�Ƃ��āAXR�Z�p�����p�������u�ł̃R�~���j�P�[�V������R���{���[�V����������ʓI�ƂȂ����B�G���^�[�e�C�������g����r�W�l�X�̗̈�܂ŕ��L���p�r�Ŋ��p����Ă���B�G���^�[�e�C�������g�̗̈�ɂ����ẮA�I�����C���łȂ������Q���҂ƈꏏ�ɗV�Ԃ��Ƃ��\�ȃQ�[���A���y�p�t�H�[�}���X�Ȃǂ̃C�x���g�ӏ܁A�o�[�`�������[�����ł̃V���b�s���O�Ƃ��������[�X�P�[�X���l������B�r�W�l�X�̗̈�ɂ����ẮA3D��ԓ��ł̌��C�E�g���[�j���O�Ȃǂ̋����A�Q���ғ��m�ŏ�����L���Ȃ���f�B�X�J�b�V�������s����c��ړI�Ƃ������p���l������B
���ۂɁAVR�O���X����������̌��ƁA�A�o�^�[�ɂ�鎩�ȕ\������g�����o�[�`������c��W��������Ă��Ă���[1]�B���l�̋Z�p�����p���āA�o�[�`�����L�����p�X��o�[�`�����I�t�B�X��{�i��������č��̑�w���Ƃ��o�ꂵ�Ă���[2][3]�B�����f�o�C�X�̐i�����i��ł���AVR�^AR�O���X�Ɋւ��āA�č��⒆���Ȃǂ̑��IT��Ƃ𒆐S�ɍ��掿�E�L����p�E���^�E�y�ʂƂ��������\���オ�����ɐi�߂��Ă���A���p�V�[�����g�債�Ă���B
���̂悤�ɁAXR�Z�p�̕��y�͒����ɐi��ł�����̂́A�]���͓���̏��i�E�T�[�r�X�݂̂��f�W�^��������A�T�C�o�[��Ԃ̃t�B�[�h�o�b�N������̌��͒f�ГI�Ȃ��̂ɗ��܂��Ă����B
�����ŁA�G���^�[�e�C�������g�̗̈�ɂ����郆�[�X�P�[�X�̈��Ƃ��āAKDDI�����\�����o�[�`�����a�J���Љ��B���̃o�[�`�����a�J�ł́A�T�C�o�[��ԓ��ł͏a�J�̊X���݂��f�W�^���c�C���Ƃ��čČ�����A24���ԁA���E���ǂ�����ł��A���g���A�o�^�[�ƂȂ��ĎQ�����邱�Ƃ��\�ł���[4]�B�܂��A�a�J��ɂ����ẮA�X�}�[�g�t�H����X�}�[�g�O���X�ɓ��ڂ��ꂽ�J�����z���̉f�������Ԃ�F������VPS (Visual Positioning Service)�����p���āA���ۂ̏a�J�̌i�F�Ɉ��H�X���Ȃǂ�AR�ŕ\�������T�[�r�X�̎��؎������s��ꂽ�i�} 3‑44�j[5]�B

�} 3‑44�@�a�J�X�N�����u�������_�ɂ�������؎����ł̑̌��C���[�W
3.3.1.4�@ �ۑ�
���̂悤�ɁAXR�Z�p�����p�����V�̌��̑n�o����͏��X�ɏo�Ă��Ă��邪�A�X�Ȃ郆�[�X�P�[�X�̊g���[���ɂ����Ă͉������ׂ��ۑ������B�����ł́A�{�e�ŏЉ�郁�^�o�[�X�A�_�Q�f�[�^��z���O���t�B�Ȃǂ̗��̕\���̊ϓ_�ł̉ۑ�ɂ��ďq�ׂ�B
�܂����^�o�[�X�Ɋւ���ۑ�ɂ��ďq�ׂ�B���^�o�[�X�ł́A�������ꂽ�l�Ɠ�����Ԃ����L���Ȃ���A�����̕��g�Ƃ��ẴA�o�^�[����ăR�~���j�P�[�V�����Ȃǂ��s�����Ƃ��\�ł���B�} 3‑45�̓��^�o�[�X���ŕ\��������Ԃ�A�o�^�[�̃C���[�W�ł��邪�A������CG�iComputer Graphics�j�ŕ\�������[6]�B���[�X�P�[�X�ɂ���ẮA��������蒉���ɍČ����邱�Ƃ����߂���B���o�̊ϓ_�ł́A�Ⴆ�A���^�o�[�X���ł̃V���b�s���O��X�|�[�c�ϐ�Ȃǂ�z�肷��ƁA�l����ߕ��Ȃǂ̎����܂ōČ�����邱�Ƃ����҂����B

�} 3‑45�@���^�o�[�X��ɍ\�z���ꂽ��ԂƃA�o�^�[�ɂ��\��
�܂��A�} 3‑46�̓��^�o�[�X���ŕ\������鉹���\���̃C���[�W�ł���[7]�B���^�o�[�X���̃��[�U��I�u�W�F�N�g�̈ʒu������Ȃǂɂ���āA���̕���������ω������闧�̉����̕\��������B���̉����́A�V�A�^�[�ӏܗp�r�ł́A�}���`�`�����l���̃T���E���h�I�[�f�B�I�V�X�e���𗘗p���Ă��Տꊴ�̍����\�����\�ƂȂ��Ă��Ă���[8]�B����ŁA���^�o�[�X�Ȃǂł̗��p�ɂ����ẮA�X�}�[�g�t�H���̃X�s�[�J�[��w�b�h�t�H���Ȃǂɂ��X�e���I�Đ�����ʓI�ł���B�X�e���I�Đ��ɂ����闧�̉����̕\�����s���A�v���[�`����������Ă���[9]�B���^�o�[�X���ł̉��y���t��R�~���j�P�[�V�����Ȃǂ�z�肷��ƁA�����̐l�����t������A���b�����肷��ۂ́A��ԓ��̉��̍L�����͋[�ł��邱�Ƃ����҂����B
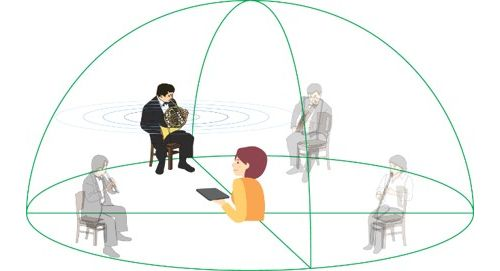
�} 3‑46�@���^�o�[�X���ł̉����\���̃C���[�W
�G�o�ɂ����Ă��A���^�o�[�X���̐l��I�u�W�F�N�g�ɐG�ꂽ�ۂ̊��o��ł��邱�Ƃ��]�܂����B�Q�[���̃R���g���[���[��O���[�u�^�̃f�o�C�X�Ȃǂ�����U���ɂ��t�B�[�h�o�b�N�Ȃǂ���������Ă��邪[10][11]�A���[�X�P�[�X�ɓK�����f�o�C�X�ɂ����āA��y�ɑ@�ׂȃt�B�[�h�o�b�N���s���邱�Ƃ͗L�p�ł���ƍl������B���̑��A�k�o�□�o�̍Č��ɂ��ẮA�G��I�Ȏ��Ⴊ�������o�Ă����i�K�ł͂��邪�A���^�o�[�X���̗Տꊴ�̂���̌�������Ɍ㉟������t�B�[�h�o�b�N�����҂����[12][13]�B
���ɗ��̕\���Ɋւ���ۑ�ɂ��ďq�ׂ�B�]���̃T�C�o�[��Ԃ���̎��o�I�ȃt�B�[�h�o�b�N�̌��́A���2D�f�B�X�v���C�����`�Ԃɐ�������Ă������A3D�Ɋg�����邱�ƂŁA�} 3‑47�̂悤�Ȃ��Տꊴ�̂���̌��������ł���ƍl������B

�} 3‑47�@���̕\�������p�������o�I�ȃt�B�[�h�o�b�N�̃C���[�W
3D�f���̃f�[�^�\���`���Ƃ��āA��Ԃɂ��镨�̂�_�̏W���Ƃ��ĕ\������_�Q������B�_�Q�͋�Ԃ�_�̈ʒu�Ƃ��̐F�ŕ\������V���v���ȃf�[�^�\���ł���A�l�X�ȃ��[�X�P�[�X�ŗ��p�����B����ŁA3D���������߁A���̃f�[�^�ʂ͖c��ƂȂ�B���̂��߁A�_�Q�f�[�^�����k����Z�p�͕K�v�s���ƌ�����ł��낤�B3D�R���e���c�̕��y�ƂƂ��ɁA�l�b�g���[�N�ɗ��ʂ���f�[�^�ʂ͍���v�X���傷��ƍl�����邽�߁A�X�Ȃ鍂�����Ȉ��k�����߂���B
�܂��A3D�f���̕\���Z�p�Ƃ��āA���ߌ^�f�B�X�v���C��n�[�t�~���[�Ȃǂɂ����3D��Ԓ���2D�̍��掿CG�𓊉e����A�v���[�`����������Ă���[14]�B����ŁA�����ƌ������邱�Ƃ������I�ɕs�\�ȉf���\�����������ׂ��A�����̂̕\�ʂ��甽�˂��ē�������g���L�^�E�Đ�����z���O���t�B�����p�������̕\���f�B�X�v���C�Z�p[15]�̌����J�����i�߂��Ă��邪�A�\���p�f�o�C�X�Ȃǂ̐���A���掿�E�L����p�̉f���\���͎�������Ă��Ȃ��ł���B
���̂悤�ȏ̒��ŁA�X�Ȃ郆�[�X�P�[�X�̒T����ۑ�����Ɍ��������g�݂��o�Ă��Ă���B���߈ȍ~�ɂ����āAXR���ڎw�����E����������\���v�f�Ƃ��āA���^�o�[�X�A�_�Q�f�[�^�A�z���O���t�B�ɏœ_�����ĂāA���ꂼ��̏ڍׂɂ��ďq�ׂ�B
3.3.2�@ ���^�o�[�X
3.3.2.1�@ ���^�o�[�X�̓���
�܂����^�o�[�X�̓����ɂ��ďq�ׂ�B���^�o�[�X�ɂ��ẮA���m�Ȓ�`�͂Ȃ����A���[�U�ԂŃR�~���j�P�[�V�������\�ȁA�C���^�[�l�b�g���̃l�b�g���[�N��ʂ��ăA�N�Z�X�ł���A���z�I�ȃf�W�^����Ԃƌ����Ă���[16]�B
��q�̂悤�ȑ̌������T�[�r�X���������Љ��B���E�ő勉�̃��^�o�[�X�Ƃ��āAVRChat [17]�ƌĂ��T�[�r�X������Ă���A���E������Q�����郆�[�U�ƃA�o�^�[�������b��C�x���g�ւ̎Q���Ȃǂ��y���ނ��Ƃ��ł���B�܂��AEpic Games�Ђ�����Fortnite [18]�Ȃǂ̂悤�ɁA�Q�[���@�\���������킹���T�[�r�X�����݂���BFortnite�ł́A���[�U����Ԃ��f�U�C�����邱�Ƃ��ł��A���̋�Ԃ𑼂̃��[�U�ƈꏏ�Ɋy���ނ��Ƃ��\�ł���B�܂��A�r�W�l�X�����̃R���{���[�V�����c�[���Ƃ��āAMicrosoft Mesh�Ȃǂ�����Ă���[19]�B�܂��AMeta�Ђ̓��^�o�[�X�T�[�r�X�̒ɉ����āA���v�����̍����̌����\�Ƃ��邽�߂�XR�f�o�C�X�̊J������s���Ă���[20]�B���{���̃��^�o�[�X�Ƃ��ẮA�N���X�^�[�Ђ̃��^�o�[�X�v���b�g�t�H�[���ł���cluster[21]������Ă���A�X�}�[�g�t�H���APC�AVR�w�b�h�Z�b�g�Ȃǂ̑��l�ȃf�o�C�X����Q�����邱�Ƃ��ł���B�܂��A���݂���s�s���Č�������ԓ����U��ł���s�s�A���^���^�o�[�X�ł���KDDI�炪���i����o�[�`�����a�J�Ȃǂ�����Ă���[4]�B
���̂悤�ɁA���^�o�[�X�Ƃ��ėl�X�ȃT�[�r�X������Ă��邪�A����������ɍ��x��������g�݂��o�Ă��Ă���B�����ł́A���^�o�[�X�̐i���Ɍ��������g�݂̈��Ƃ��āA�A�o�^�[�̃t�H�g���A���\���ƃ}���`���[�_���A�g�ɂ��ďЉ��B
3.3.2.2�@ ���^�o�[�X��i��������A�o�^�[�̃t�H�g���A���\��
���^�o�[�X�̍��x���̂ЂƂƂ��āA�������������Ɠ����悤�Ɋ������Ԃ̎ʎ��I�ȍČ�������B��q�̓s�s�A���^���^�o�[�X�̂悤�ɁA���݂���ꏊ���T�C�o�[��ԂɍČ�������g�݂��i�߂��Ă���B���̏�ŁA���^�o�[�X�ł̎��g�̃A�o�^�[���A�l�Ԃ�������ɕ\���\�ȃo�[�`�����q���[�}������Ă���Ă���[22]�B�X�܂ł̐ڋq��ē��A����E���Ȃǂœ���I�Ɋ��p����A�l�Ɋ��Y�����݂Ƃ��ĎЉ�I�Ɏ�e�����悤�ɂȂ�B�o�[�`�����q���[�}���̃C���[�W��} 3‑48�Ɏ���[23]�B�o�[�`�����q���[�}���͐l�Ƃ̃C���^�t�F�[�X�Ƃ��Ă̖����݂̂ɗ��܂炸�A���i�̊��E�f�U�C���i�K�ɂ�����T���v������̃o�[�`���������A�T�v���C�`�F�[����DX���̎�i�Ƃ��Ă����L�����p�����悤�ɂȂ�[24]�B�܂��A�T�C�o�[��Ԃɂ����Ă͎��g�̃G�[�W�F���g���f�W�^���c�C���Ƃ��đ��݂��A�e�p�╞���͂������A�d����\������V�`���G�[�V�����ɉ����čœK�ɐ��䂳��A���Ƀr�W�l�X�V�[���ɂ����Ă͑Ζʈȏ�̃R�~���j�P�[�V������i�Ƃ��ē���I�Ɋ��p�����悤�ɂȂ�B

�} 3‑48�@�o�[�`�����q���[�}���̃C���[�W
���̂悤�Ȏʎ��I�ɕ\�����ꂽ�o�[�`�����q���[�}���́A���^�o�[�X�Ȃǂŗ��p�����X�}�[�g�t�H���ŕ\������ꍇ�A���̃f�o�C�X�̕`�揈���\�͂̐���A�T�[�o��CG�̕`�揈�����s���A���̌��ʂ�2D�f���Ƃ��ăX�g���[�~���O�z�M�����@����ʓI�ł���B���̍ۂɁA�f�[�^�ʐM�ʂ���ђ[���������ׂ��ۑ�ƂȂ邪�A�T�[�o�ƃX�}�[�g�t�H�����̕`�揈����K�ɕ��U���邱�Ƃɂ��A�X�}�[�g�t�H���ł̃t�H�g���A���ȃ����_�����O���\�Ƃ���Z�p����Ă���Ă���[22]�B����ɂ��A�ʐM�ʂ�}���X�}�[�g�t�H���ł̕\���i�����ێ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
3.3.2.3�@ ���^�o�[�X��i��������}���`���[�_���A�g
���^�o�[�X�̍��x�����������邽�߂ɂ́A���o�I�ȕ\���͂̌��ゾ���łȂ��A���̓I�ȉ���ɂ�鎋���̌��A�l��m�ɐG��銴�o�Ȃǂ��Č����邱�Ƃ͏d�v�ł���B
�Ⴆ�A���^�o�[�X���ł̉��y���C�u�����̃��[�X�P�[�X�ɂ����ẮA�����I�ɗ��ꂽ��Ԃ�������܂߂ă��A���^�C���ɐڑ�����A�������������̏�ɂ��邩�̂悤�ȁA���C�u�����z�����v���̌����\�ɂȂ�Ƒz�肳���B
���̂悤�ȉ��̗��̓I�ȕ\������������Z�p�Ƃ��āAKDDI�́u����VR�v�Ƃ������̉����Z�p���Ă��Ă���B��Ԓ��̔C�ӂ͈̔͂ɃY�[��������������A���^�C���ɍ������邱�ƂŁA360�x�f�����̌������A�������������Ɏ��R���݂Ƀt�H�[�J�X�ł���C���^���N�e�B�u�����̌����\�ƂȂ��Ă���[25]�B�} 3‑49�́A���̉����Z�p�����p�����o�[�`�����R���T�[�g�̗�ł���B

�} 3‑49�@���̉����Z�p�����p�����o�[�`�����R���T�[�g�̗�
���o�⒮�o�ɉ����āA�G�o�A�k�o�A���o�̍Č��Z�p�Ƃ��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA���^�o�[�X��ʂ��āA����̐�����āA���[�U�ɑ��Č܊��t�B�[�h�o�b�N������A���̌��Ƒ��F�̂Ȃ��A���R�ŖL���ȑ̌��A���邢�͌�����������̑̌��������邱�Ƃ����҂����B
3.3.3�@ �_�Q�f�[�^
3.3.3.1�@ �_�Q�f�[�^�Ƃ�
�ߔN�A3�����f�[�^�̐����E�����E�Ɋւ���Z�p�̔��W�ɔ����A�l�X�ȕ���ɂ�����3�����f�[�^�̗����p���i�߂��Ă���B�ł���\�I��3�����f�[�^�̂ЂƂɓ_�Q�f�[�^������B�_�Q�f�[�^�Ƃ́A3������ԓ��̕����̓_����Ȃ�f�[�^�̏W���ł���B�e�_�͍��W�ix,y,z�j�̊��ƐF�ir,g,b�j�┽�˗��Ȃǂ̑����������B�_�Q�f�[�^�͔��ɔėp���̍����\���`���ł��邽�߁A���L���p�r�ŗ��p�����B�Ⴆ�A���Ƃł͌�������n�`��LiDAR�Ȃǂ̃Z���T�ŃX�L�������A����ꂽ�_�Q�f�[�^���{�H����e�i���X�̉ߒ��ŗ��p����BAR/VR/MR�ȂǂɌ������R���e���c����ł́A�t�H�g�O�����g���Ȃǂ�p���Đ��������_�Q�f�[�^��3�����V�[���̕\���ɗ��p����B�܂��APC��^�u���b�g�A�X�}�[�g�t�H���A�w�b�h�}�E���g�f�B�X�v���C�ȂǁA�_�Q�f�[�^�������[�����p�r�ɉ����đ��l�����Ă���B���̂悤�ȏŁA��ʂɖc��ȃf�[�^�ʂƂȂ�_�Q�f�[�^�ɂ��X�g���[�W��ʐM�ւ̕��ׂ��팸���邽�߁A�_�Q���k�Z�p�ւ̊��҂����܂����B
���������w�i����A�}���`���f�B�A���������ەW�����c�̂ł���MPEG (Moving Picture Experts Group) �́A�_�Q���k�Z�p�ł���PCC (Point Cloud Compression) �̋K�i�����s���Ă���BPCC�͌��̓_�Q�̕i�����ێ����Ȃ���啝�Ȉ��k���\��B�����Ă���A�f�[�^�ʂ̑傫�ȓ_�Q�f�[�^�����k���ă��o�C������o�R�ň���I�ɓ`�����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B����A�_�Q�̃G���R�[�h���̏������ׂɂ͉ۑ肪���������A�ŋ߂̊J������ł͍������Z�p�Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ�胊�A���^�C���������������Ă���B
�Ȃ��A���ەW���Ƃ��ċK�肳��Ă���͕̂��������݂̂ł���A�����������ɂ͖ړI�ɉ����čœK������]�n���c����Ă���B�܂�A�p�r�ɉ������p�t�H�[�}���X���������邽�߁A�_��Ȏ������\�ł���A�Ⴆ���A���^�C��������ڎw���ꍇ�́A�������̎d�g�݂Ƒg�ݍ��킹���G���R�[�_�̎������s����B
3.3.3.2�@ MPEG�ɂ��ŐV�̓_�Q���k�Z�p�̍��ەW������
MPEG���K�i������PCC�ł́A�_�Q�f�[�^�̕��L���A�v���P�[�V�������l�����A�_�Q�f�[�^�̓����ɉ����āAV-PCC (Video-based�@Point Cloud Compression)��G-PCC (Geometry-based�@Point Cloud Compression)��2��������߂��Ă���B�ȉ��ɂ��ꂼ��ɂ��āA�����̊T���A�Ȃ�тɃ��A���^�C���G���R�[�_�̊J��������������B
�@ V-PCC (Video-based�@Point Cloud Compression)
V-PCC (Video-based�@Point Cloud Compression)[26] �́A���ەW�����@�ւ�ISO/IEC��2020�N10���ɋK�i�����ꂽ�B���O�ɁuVideo-based�v�Ƃ���ʂ�A�_�Q�f�[�^��̂悤�ɕϊ����āA�����̉f���������Z�p�ł���VVC (Versatile Video Coding)��HEVC (High Efficiency Video Coding)�𗘗p����_�������ł���B�_�Q�f�[�^�扻���鏈���̓s���ɂ��A�����̂���l���Ȃǂ̕��̂̓_�Q�̏����ɓK���Ă���B
V-PCC�͓����̂���l���Ȃǂ̕��̂̓_�Q�������悭���k�ł��邱�Ƃ���A�Ⴆ�A�t�H�g���A���Ȑl���\���ɂ�郉�C�u�R�}�[�X��V���[�ȂǁA��ɃR���e���c�z�M�ł̗��p�����҂����B���̂悤�ȃ��[�X�P�[�X�ł̓��A���^�C�������d�v�ƂȂ邪�A�_�Q�̃G���R�[�h���̏������ׂɂ͉ۑ肪�������B����ɑ��AV-PCC���A���^�C���G���R�[�_ [28],[29] �ł�MPEG�����J���Ă���Q�ƃ\�t�g�E�F�A [30] ���x�[�X�ɃG���R�[�_�ɑ��č������̎d�g�݂����A���A���^�C������\�ȃV�X�e�����J�������B
V-PCC�̃G���R�[�_�̏����̊T�v��} 3‑50�Ɏ����BV-PCC�̃G���R�[�_�́A�_�Q�t���[���QGOF (Group of Frames)�����͂����ƁA�e�_�Q�t���[�����p�b�`�ƌĂ��P�ʂɕ������A�_�Q�̎��͂ɉ��肵�������̖̂ʂɃp�b�`�𓊉e����B�p�b�`�ւ̕����Ɗe�p�b�`�̓��e�ʂ̔���́A�e�_�̖@�������Ȃǂ̏��Ɋ�Â����������B�p�b�`�̓��e�ɂ�蕡����ނ̉摜�����A���ꂼ��̉摜��GOF�P�ʂł܂Ƃ߂Ċ����̉f���������Z�p�ɂ�蕄��������B
����ɑ��AV-PCC���A���^�C���G���R�[�_�ł́A�p�b�`�ւ̕����Ɗe�p�b�`�̓��e�ʂ̔��菈���Ɋւ�����P���s�����B��̓I�ɂ́A�Q�ƃ\�t�g�E�F�A�ł͐��_���Ƃɂ��̔��菈�����s��ꂨ��A�c��ȏ������Ԃ���₳��Ă����̂ɑ��A3������Ԃ��p�b�`��������ɏ����ȏ���Ԃɕ������A���̏���Ԃ��Ƃɔ��菈�����s�����Ƃō����������B�����āAV-PCC�ɓK�����^�X�N�X�P�W���[�����O�����ɂ��CPU�g�p�������P�����B
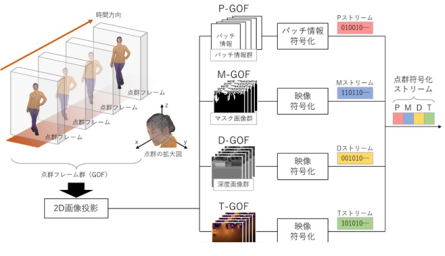
�} 3‑50�@V-PCC�̃G���R�[�_����
����V-PCC���A���^�C���G���R�[�_��p�����V�X�e���Ŏ��ۂ̃��[�X�P�[�X��z�肵���`���������s�����B�V�X�e���̍\���C���[�W��} 3‑51�Ɏ����B���O�ɃX�^�W�I�ŎB�e�����l���̍����x�_�Q�i��2000���_/�b�j��V-PCC���A���^�C���R�[�f�b�N�ɂ���ĕ��������A5G���o�R���ĉ��u�̎������_�܂Ń��C�u�z�M�����B���u�n�ł̓z���O���t�B�b�N�X�e�[�W��X�}�[�g�t�H���ŃR���e���c������I�ɍĐ��ł��邱�Ƃ��m�F�����B

�} 3‑51�@V-PCC���A���^�C���`�������̃V�X�e���\��
V-PCC��p���ă��A���^�C���ɓ_�Q�f�[�^�̓`�����ł��邱�Ƃɂ��A�Ⴆ�Ή��y��t�@�b�V�����Ȃǂ̃V���[�C�x���g��ΏۂɁA�{�������g���b�N�X�^�W�I�ŎB�e�����f�������̂܂܃��^�o�[�X�ɎQ��������Ƃ������V�����C�x���g�̌��̑n�o�����҂ł���B
�A G-PCC (Geometry-based Point Cloud Compression)
G-PCC (Geometry-based Point Cloud Compression)[27] �́A���ەW�����@�ւ�ISO/IEC��2023�N3���ɋK�i�����ꂽ�BV-PCC�Ƃ͈قȂ�_�Q��3�����f�[�^�̂܂ܕ��������A�ǂ̂悤�ȓ_�Q�f�[�^�ɑ��Ă��g�p�\�ł���_�������ł���B�������Ȃǂ̐Î~�������̂��Ԃ�\���_�Q��ALiDAR�Ŏ擾�����_�Q�Ȃǂ̕��̂��Ԃ�\���a�ȓ_�Q�ɓK���Ă���B
G-PCC�́AV-PCC�ƈقȂ�L���3�����V�[���̓_�Q��LiDAR�Ŏ擾�����a�ȓ_�Q�ɑ��ē_�Q�̕i���Ȃ킸�����悭���k�ł��邱�Ƃ���A������x����ЊQ��ȂǕ��L�����p�����҂���Ă���B���̂悤�ȃ��[�X�P�[�X�ł́A���O�ɂ�����^�@��Ŏ擾�����_�Q���A���o�C��������o�R���đ����ɉ��u�n�ɓ`�����Ċm�F�ł��邱�Ƃ��]�܂����B�������Ȃ���AG-PCC�̏ꍇ�ɂ����Ă��_�Q�̃G���R�[�h���̏������ׂɂ͉ۑ肪�������B����ɑ��AG-PCC���A���^�C���G���R�[�_ [29] �ł�MPEG�����J���Ă���Q�ƃ\�t�g�E�F�A [31] ���x�[�X�ɃG���R�[�_�������Ƌ@�\�lj������{���A���A���^�C������\�ȃV�X�e�����J�������B
�����_�ŋK�i�����������Ă���G-PCC�́A�t���[�����̏������Ɨ����Ă���B���̂��߁A���͂������t���[������ꍇ�ɂ̓}���`�X���b�h�����ŕ���ɃG���R�[�h���邱�ƂŁA�V���O���X���b�h�̓��쎞�Ɠ������ʂ������ɓ��邱�Ƃ��ł���B������G-PCC���A���^�C���G���R�[�_�ł́A�t���[���P�ʂ̕������s�����Ƃō����������������B�܂��A�@�\�lj��Ƃ��āA�_�Q�f�[�^�̃X�g���[�~���O���o�͋@�\�ƃl�b�g���[�N����M�@�\�����������B����ɂ��m�[�gPC��8�����Ƃ����ꍇ��200���_/�b���鏈�����\�ɂȂ����B����́A�����̍����\LiDAR�Ŏ擾�ł���_�Q�����A���^�C���ŏ������邱�Ƃ��ł��鐫�\�ł���B
����G-PCC���A���^�C���G���R�[�_��p���ăV�X�e�����\�����A���ۂ̃��[�X�P�[�X��z�肵���`���������s�����B�V�X�e���̍\���C���[�W��} 3‑52�Ɏ����BLiDAR��RGB�J�����Ń��A���^�C���Ɏ擾���Ă���_�Q�f�[�^���m�[�gPC�ŃG���R�[�h���A5G���o�R���ĉ��u�n�ɓ`�������BLiDAR �́A��32 ���_/�b (3.2 ���_/�t���[���A10�t���[��/�b) �� �_�Q�f�[�^���擾���Ă����B���u�n�ł́A��M�����_�Q�f�[�^��PC��ʂɕ\�������B��M���ł́A�_�Q�f�[�^�擾�����500�~���b�̒x���ŁA�_�Q������I�ɍĐ��ł��邱�Ƃ��m�F�����B
G-PCC��p���ă��A���^�C���ɓ_�Q�f�[�^�̓`�����ł��邱�Ƃɂ��A�Ⴆ�h���[���𗘗p���Č���̗l�q�����C�u�z�M���A�ЊQ���̋~��������C���t���\�z���̉��u��Ǝx���̉~���������҂ł���B
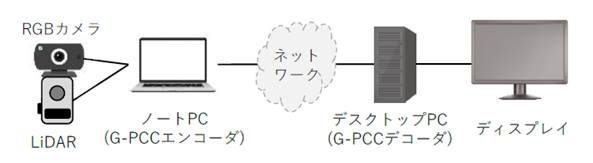
�} 3‑52�@G-PCC���A���^�C���`�������̃V�X�e���\��
3.3.4�@ �z���O���t�B
3.3.4.1�@ �z���O���t�B�Ƃ�
�z���O���t�B�Ƃ́A����Ԃɂ����Ėڂɓ͂����̔g���Č����邱�ƂŁu�������������������ɂ��邩�̂悤�Ɍ�����v���̉f���\�����\�Ƃ���Z�p�ł���A�u���ɂ̗��̉f���Z�p�v�Ƃ��Ă�Ă���B���̂���̌����Č����鐫������A�ዾ�Ȃǂ̃f�o�C�X���p��Ȃ����ᗧ�̉f���ӏ܂��\�ł���B�܂��A�z���O���t�B�͐l�Ԃ̗��̒m�o��4�v���i���ᎋ���E�^�������E�t�s�E�œ_���߁j�����ׂĖ������Z�p�Ƃ���Ă���A�]���̗��̉f���Z�p�Ƃ͈قȂ�A�u�t�s���ߖ����i�ӏ҂̓��鉜�s�����Ǝ��ۂ̃f�B�X�v���C�ʂƂ̋������ɖ����������邱�Ɓj���N����Ȃ��v�Ƃ�����������A�ᐸ��J��s�����Ȃǂ̊ӏ҂̐g�̓I���S�̏��Ȃ��f���Z�p�Ƃ��Ă����҂���Ă��� [32]�D��L���\��Ƃ��āA�z���O���t�B�͏]���̗��̉f���ɂ͂Ȃ�����������Ă���A���Y���̉f���ɂ���Ă����炳��郆�[�U�ϓ_�̃����b�g�͈ȉ��̒ʂ�ł���D
1. �����̂悤�ȗ��̊�����
2. �t�s���ߖ����ɂ��g�̓I���S���N����Ȃ�
3. �[�����m�ȉ��s�\�����\
4. ���[�U�̎��͂ɉ������Đ����̕���\
5. ���ߕ\���ɂ�����ԂƂ̏d�\
6. ���ᗧ�̉f���ӏ܂��\
�����̓�������A�z���O���t�B�̓��[�U���S�̏��Ȃ������Ԋӏ܉\�ȗ��ᗧ�̉f���ł���A����I�ȗ��p�������Ԃł̗��p�A���m�ȉ��s�������߂郆�[�X�P�[�X�ɓK���Ă���Ƃ����A��̓I��Ƃ��ẮA�ȉ��̃��[�X�P�[�X����������B
�i�P�j���̉f���L���E����
�@�z���O���t�B�́A�����̂悤�ȗ��̊�����f���\�����\�Ƃ��A�܂��[�����m�ȉ��s�\�����\�ł���Ƃ�����������A���̉f���L���ɉ��p���邱�ƂŃ��[�U�ւ̍����A�s�[�����ʂ����҂����B�܂��A������Ԃɂ����ė��̉f���ł̈ē��W���Ȃǂ̏����s�����ƂŁA��蒼���I�ȏ���̑��i�����҂����B
�i�Q�j���u�R�~���j�P�[�V����
�@�z���O���t�B�́A�����̂悤�ȗ��̊�����f���\���Ƃ�����������A���u�R�~���j�P�[�V�����ɂ�����f���\���ɗ��p���邱�ƂŁA�u��葊���g�߂Ɋ����鉓�u�R�~���j�P�[�V�����̎����v�����҂����B�e���r��c�Ȃǂɗ��p���邱�ƂŖȖ��ȃR�~���j�P�[�V�������������A�����I�ȓ������̎����ɂ���^����B
�i�R�j���u����
�z���O���t�B�ɂ������̂悤�ȗ��̊�����f���\���ɂ��A��蒼���I�ȋ�ԏ��̗����ɂȂ���B��̓I�ɂ́A�X�|�[�c�ɂ����鉓�u�w���Ȃǂɂ����āA�w���҂̓����𐳊m�ɗ����ł��邱�Ƃ���Ζʂł̎w���Ɠ����̎w�����ʂ̎��������҂����B�܂��A�g�̓I���S���N����Ȃ��Ƃ�����������A�q�������̋��狳�ނւ̉��p���\�ł���A���ʓI�ȉ��u����ɂ��n��i���̉����Ȃǂ����҂����B�@
�i�S�j���u���
�z���O���t�B�́A�[�����m�ȉ��s�\�����\�ł���Ƃ�����������A��荂�x�ȉ��u��Â̎��������҂����B��̓I�ɂ́A���u�n�ɂ����Ă������̏�Ԃ𗧑̓I�����m�Ɍ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�ΖʂƂ���F�̂Ȃ��f�f���\�ƂȂ�B�܂��A���{�b�g����Z�p�ȂǂƑg�ݍ��킹�邱�ƂŁA���u�ł̎����Ȃǂ��\�ƂȂ邱�Ƃ����҂���A�����ɂ��A��Â̂���Ȃ鍂�x����n��i���̉��������҂����B
3.3.4.2�@ �z���O���t�B�̍Đ�
�z���O���t�B�̍Đ��ɂ������āA�ߔN�ł̓R���s���[�^��Ő��������f�B�W�^���f�[�^�u�v�Z�@�����z���O�����icomputer-generated hologram: CGH�j�v���u��Ԍ��ϒ���ispatial light modulator: SLM�j�v��ŕ\�����A���̉f�����Đ������@���L����������Ă���[33]�B�R���s���[�^���3D��ԏ�ɔz�u���ꂽ���̂���̌����V�~�����[�g����CGH��Ƃ�����������A�u�����ɑ��݂��Ȃ����z�I�ȕ��̂��ʑ̂Ƃ��邱�Ƃ��ł���v�A�u�f�B�W�^���f�[�^�Ƃ��ĉ��u�n�ւ̓`�������\�ƂȂ�v�Ƃ��������_������BCGH��p�������̉f���̍Đ��͎�Ɏ���3�̃v���Z�X����Ȃ�A���̃v���Z�X�̊T�v��} 3‑53�Ɏ����B
�i1�j���̌��f�[�^�̐���
�R���s���[�^�̉��z�I��3D��ԏ��3D���f���f�[�^�i���́j��z�u���A�ӏܑΏۂƂȂ�V�[���i�ӏܑΏۃV�[���j���\������B���̊ӏܑΏۃV�[���ɑ��āASLM�̈ʒu�ɑ������镽�ʁi�z���O�����ʁj��ݒ肷��B�ӏܑΏۃV�[���̕��̂���z���O�����ʂ��̓`���v�Z���s���A�z���O�����ʏ�̌��̐U���ʑ����z�i���̌��f�[�^�j��B���̂Ƃ��A���̌��f�[�^��2�������ʏ�ɕ��z����U���ƈʑ����i�������͂��̕��f���\���j�ƂȂ�B
�i2�jCGH�̐���
�@�z���O�����ʂɐ������ꂽ���̌��f�[�^�Ƃ͕ʂ̌����ł���Q�ƌ���ݒ肵�A���Y�Q�ƌ��ƕ��̌��f�[�^�̊��p�^�[�����Z�o����B���̊��p�^�[����CGH�ł���B���ۂ�SLM�ɂĕ\������ۂɂ́ACGH��2bit��8bit�̃r�b�g�[�x�����摜�ւƕϊ������B
�i3�jCGH��p�������̑��̍Đ�
�@CGH��SLM�ɕ\�����������ŁA�Q�ƌ��Ɠ��l�̈ʒu���瓯�l�̔g���������i�Đ��Ɩ����j���Ǝ˂���BCGH�̃p�^�[���ɏ]���čĐ��Ɩ�����SLM��ʼn�܂��邱�Ƃɂ���āA�ӏܑΏۃV�[���̗��̑����Đ������B
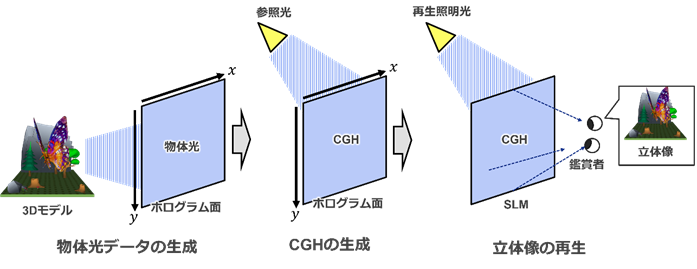
�} 3‑53�@�z���O���t�B�̍Đ��v���Z�X
3.3.4.3�@ �z���O���t�B�̋Z�p�ۑ�Ɠ���
�z���O���t�B�ɂ�闧�̉f���̎����ɂ͑傫���ȉ��̋Z�p�ۑ肪����B
�i1�j�f�B�X�v���C�̑�^���ƍL���扻
���̉f���ɂ����Ă̓f�B�X�v���C�T�C�Y�ƃ��[�U�̊ӏ܉\�͈́i����j�͏d�v�ȗv�f�̈�ł���B�z���O���t�B�̌�������A���[�U�̊ӏ܂���Đ����̎���́A�z���O�����̉�f�Ԃ̋����i��f�s�b�`�j�ɂ���Č��肳���B�Ⴆ�ΐԐF���̔g����620�`750nm�Ƃ���ƁA�����悻����30���ƂȂ闧�̉f�����������邽�߂ɂ́ACGH�̉�f�s�b�`�����Ȃ��Ƃ�1��m�i=1,000nm�j�ȉ��ł���K�v�����邱�Ƃ��킩��B����͋ɂ߂č���f���x�ȃf�B�X�v���C���K�v�ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B����SLM�ɂ��ẮA�ŐV�̌����Z�p�ɂ����Ă��A�����I�ɉf���ӏܗp�r�Ƃ��ĉf�����\���y���߂�f�o�C�X�͎�������Ă��Ȃ�[33]�B
�@���̉ۑ�ɑ��āAKDDI�ł�SLM�ł͂Ȃ����[�U�[���\�O���t�B��p����CGH�����p���邱�ƂŁA��^���L�����CGH�A�j���[�V�������������Ă���[34]�B
�i2�j�f�[�^�T�C�Y�̈��k
��L(1)�̉ۑ�ɋL�ڂ��������x�ȃf�B�X�v���C�ɂ����ẮA�\�������f�[�^�̉�f�����c��ƂȂ�B�Ⴆ�A�c��10cm�~10cm�̃f�B�X�v���C�T�C�Y�ł́A��L1��m��f�s�b�`�����f�B�X�v���C�̉�f����10����f�ɂ��̂ڂ�B�����ɁA���̂悤�ȃf�B�X�v���C�����ɐ��������z���O�����̃f�[�^�T�C�Y���傫�Ȃ��̂ƂȂ�B�z���O������2�������ʂɂ�������̐U���ʑ��Ȃǂ̕��z�ŕ\������邽�߁A��ʂ̉摜�E�f���t�H�[�}�b�g�Ɛe�a���������A�����̉f���������Z�p��K�p���邱�Ƃ��\�ł���B����ŁACGH�̂��M�������͎��R�摜�Ƃ͑傫���قȂ�B���̂��߁A�����̉f���������Z�p��P����CGH�ɓK�p���������ł̓C���^�[�\���A�C���g���\���Ƃ������@�\�����ʓI�ɓ������A�����I�Ȉ��k�͓���B������āA���̌����L�^����ʒu�̋ߖT�ɐݒ肵����ŕ��������A�������Ńz���O�����ʂ��g��`������Ƃ������A�v���[�`����Ă���Ă��� [35]�B���Y�A�v���[�`�ɂ��ACGH�̐M�����������R�摜�ɋ߂Â����߁A�����̉f���������Z�p�����ʓI�ɓ������Ƃ�����Ă���B
�y�Q�l�����z
[1] �T����, �g�w��I�����C�����EVR�J�Â̖��J���h, ���{�o�[�`�������A���e�B�w�, 2020, 25��, 2��, p.35-43, 2020.
[2] https://universitybusiness.com/how-about-using-a-digital-avatar-on-a-virtual-campus/
[3] https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60130810Z00C20A6I00000/
[4] https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/05/15/4437.html
[5] https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2019/08/28/3979.html
[6] https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/03/07/6588.html
[7] https://www.kddi-research.jp/newsrelease/2019/100702.html
[8] https://www.dolbyjapan.com/dolby-cinema
[9] https://www.sony.jp/feature/contents/220606/
[10] https://article.murata.com/ja-jp/article/miraisens-3d-haptics-technology-1
[11] https://www.senseglove.com/
[12] https://aromajoin.com/ja
[13] https://www.meiji.ac.jp/koho/press/6t5h7p0000342664.html
[14] https://group.ntt/jp/newsrelease/2018/11/26/181126d.html
[15] Yoneyama��, �gHolographic head-mounted display with correct accommodation and vergence stimuli, �gOpt. Eng. 57(6), 061619, 2018.
[16] https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd131210.html
[17] https://hello.vrchat.com/
[18] https://www.fortnite.com/
[19] https://adoption.microsoft.com/ja-jp/microsoft-mesh/
[20] https://about.meta.com/ja/
[21] https://cluster.mu/
[22] https://www.kddi-research.jp/newsrelease/2021/021801.html
[23] https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2021/03/10/5006.html
[24] https://news.kddi.com/kddi/corporate/topic/2021/09/10/5401.html
[25] �x����, �g�����҂��Ƃ̌������E�����������������鉹���f�B�A�Z�p�h, �M�w��, Vol.104, No.1, pp.22-26, 2021�N1��
[26] "V-PCC codec description", ISO/IEC JTC1/SC29/WG7 N0100 (June2020)
[27] "G-PCC codec description", ISO/IEC JTC1/SC29/WG7 N0217 (Apr.2022)
[28] https://www.kddi-research.jp/newsrelease/2022/102401.html
[29] https://www.kddi-research.jp/newsrelease/2023/012401.html
[30] https://github.com/MPEGGroup/mpeg-pcc-tmc2
[31] https://github.com/MPEGGroup/mpeg-pcc-tmc13
[32] D. M. Hoffman, A. R. Girshick, K. Akeley, and M. S. Banks, �gVergence–accommodation conflicts hinder visual performance and cause visual fatigue,�h J. Vis. 8(3), 33, 2008.
[33] ���c ���i�C��ԑ��Đ��p�\���f�o�C�X�̌����J�������CNHK�Z��R&D �H���CNo.187, 2021.
[34] https://www.kddi-research.jp/newsrelease/2022/050901.html
[35] ������,"VVC�ɂ��v�Z�@�����z���O�����̓��摜�������̈ꌟ��," 2024�N�d�q���ʐM�w������u���_���W, No.D-11A-34, 2024�N3��.
3.4�@ AI�ɂ��R���e���c�����Z�p
3.4.1�@ ����AI�Ƃ�
3.4.1.1�@ ����AI�̒�`
����AI�iGenerative Artificial Intelligence�j�́A�f�[�^�̊w�K��ʂ��ĐV�����A���m�̃f�[�^������\�͂����l�H�m�\�̈ꕪ��ł���B�]����AI�������̏��͂��A���ނ��邱�Ƃɏd�_��u���Ă����̂ɑ��A����AI�́A�w�K�����f�[�^����V���ȃR���e���c���u���ݏo���v�B���̃v���Z�X�́A�l�Ԃ��o����m������V�����A�C�f�A�ݏo�����@�Ƃ�����x�ގ����Ă���B
����AI�̊j�S�́u���f���v�ɂ���B����̓f�[�^�Z�b�g�͂��A���̃f�[�^�Z�b�g�ɐ��ރp�^�[���╪�z�𗝉�����\���ł���B���̗�������ɁA���f���͐V���ȃf�[�^�|�C���g�����邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�A�����̔L�̉摜����w�K�����������f���́A���݂��Ȃ������A���Ɍ�����L�̉摜�����邱�Ƃ��\�ł���B
����AI�́A����Generative Adversarial Networks�iGANs�j��Variational Autoencoders�iVAEs�j�Ƃ������Z�p�̐i���ɂ��A���ڂ��W�߂Ă���B�����̋Z�p�́A���A���e�B�̂���摜�A�����A�e�L�X�g�����邾���łȂ��A�f�[�^�g���A���z���̃V�~�����[�V�����A���������ꂽ�f�[�^�Z�b�g�̍쐬�ȂǁA����ɂ킽�鉞�p���\�ɂ��Ă���B
�������A����AI�̔\�͂͑n���Ɍ��肳��Ȃ��B���̋Z�p�́A�f�[�^�̗�����[�߁A��������p����V�������@����邱�ƂŁA�Ȋw�A��ÁA�|�p�Ȃǂ̕���Ɋv�V�������炷���Ƃ����҂���Ă���B����AI���J���\���͑傫���A���̉e���͉�X�̐����̂����鑤�ʂɋy�Ԃ��낤�B
3.4.1.2�@ ����AI�����j�Ɣ��W
����AI�̗��j�́A�l�H�m�\�����̏����ɑk�邱�Ƃ��ł���B�ŏ��̐l�H�m�\�v���O�����̈ꕔ�́A�ȒP�Ȍ���p�^�[���̐����␔�w�I�ؖ��̐����Ȃǂ����s���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B�������A�����̏����̎��g�݂͌���I�Ȃ��̂ł���A����AI�̉\�������S�Ɉ����o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B
����AI�̌����ɂ�����傫�ȓ]���_�́A�[�w�w�K�ƃj���[�����l�b�g���[�N�̐i���ɂ���Ă����炳�ꂽ�B���ɁA2014�N�ɓ������ꂽGenerative Adversarial Networks�iGANs�j�́A����AI�̕���Ɋv���������炵���BGANs�́A������Ǝ��ʊ�̓�̃j���[�����l�b�g���[�N���݂��ɋ������Ȃ���w�K��i�߂�d�g�݂ł���A���Ƀ��A���ȉ摜��r�f�I�A����������\�͂����B
���̌�̔N�����o�āA���l�Ȑ������f�����J������A���ꂼ�ꂪ�قȂ�A�v���[�`�Ńf�[�^�̐������s���悤�ɂȂ����B�Ⴆ�AVariational Autoencoders�iVAEs�j�́A�f�[�^�̊m���I���f�����w�K���A���̃��f������V�����f�[�^���T���v�����O����B����ARecurrent Neural Networks�iRNNs�j�́A���Ƀe�L�X�g�≹�y�̐����ɂ����ėD�ꂽ���\������B�����͌�ɉ������B
����AI�̉��p�͈͂��}���Ɋg�債�Ă���B�����̉摜��������n�܂�A���݂ł͎��R���ꐶ���A3D���f���̐����A��É摜�̍����ȂǁA����ɂ킽�镪��ł̉��p���i��ł���B���̂悤�Ȑi���́A����AI�������E�̖������ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����\���������Ă���B
����AI�̗��j�Ɣ��W�́A�l�H�m�\�Z�p�̐i���ƂƂ��ɁA�������̑n�����ƃC�m�x�[�V�����̌��E���g���������Ă���B
3.4.1.3�@ ����AI�̊�{�T�O
�@ �@�B�w�K�Ɛ���AI�̊W
�@�B�w�K�́A�f�[�^����w�K���A���̊w�K��ʂ��ē���̃^�X�N�����s����\�͂��R���s���[�^�ɗ^����Z�p����ł���B���̍L�͂ȕ���̒��ŁA����AI�͋@�B�w�K�̂����̓��ʂȃJ�e�S���Ɉʒu�Â�����B�@�B�w�K���f�[�^�͂��A�p�^�[����F�����邱�Ƃɒ��͂���̂ɑ��A����AI�͂��̃p�^�[������ɐV���ȃf�[�^�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�@�B�w�K���f���́A��ʂɓ��̓f�[�^�ɑ��ė\���╪�ނ��s�����A����AI�̃��f���́A�^����ꂽ�f�[�^�Z�b�g�Ɋ�Â��ĐV�����f�[�^�C���X�^���X���u�����v����B���̈Ⴂ�́A���҂��Nj�����ړI�̍��{�I�ȈႢ���痈�Ă���B�@�B�w�K�̑����͗\���I�Ȑ����������A����AI�͑n���I�Ȑ��������B
����AI�̃��f���́A�@�B�w�K�̋Z�p�𗘗p���ăf�[�^�̕��z���w�K����B�w�K���ꂽ�f�[�^�̕��z����V�����T���v�������邱�ƂŁA���f���͎��ۂɑ��݂��邩������Ȃ����A�܂��ϑ�����Ă��Ȃ��f�[�^�|�C���g��z�����邱�Ƃ��ł���B���̃v���Z�X�́A�@�B�w�K�ɂ����鋳�t�Ȃ��w�K�̈�`�Ԃƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B
�@�B�w�K�̘g�g�݂̒��ŁA����AI�͐V�����\�����J���B����AI�̃A�v���[�`�́A�]���̋@�B�w�K�����ʂ��Ă����������̖��A�Ⴆ�f�[�^�s����ߏ�K���Ȃǂ��ɘa�����i�����B�܂��A�@�B�w�K�����ݏo�����m�����A���S�ɐV�������@�Ŋ��p���邱�Ƃ��\�ɂ���B
�@�B�w�K�Ɛ���AI�̊W����T��A����AI���@�B�w�K�͈͓̔��łǂ̂悤�ɓ��ʂȈʒu���߂Ă��邩���������B�܂��A����AI�̊�{�I�ȊT�O�Ƃ��̋@�\�ɂ��Ă��ڍׂɐ�������B
3.4.1.4�@ �������f���̎��
�@ ���t����w�K�Ƌ��t�Ȃ��w�K
�@�B�w�K�̎�@�͑傫����ɕ�������B��͋��t����w�K�A������͋��t�Ȃ��w�K�ł���B�����͊w�K����ۂ̃f�[�^�̌`�ԂƁA���f�����ǂ̂悤�Ƀf�[�^����w�K���邩�Ɋ�Â��ċ�ʂ����B
���t����w�K�ł́A���f���͓��̓f�[�^�Ƃ���ɑΉ�����o�̓f�[�^�i���x���j�̗�������w�K����B���̃v���Z�X�ł́A���f�����������o�͂�����悤�ɁA���̓f�[�^�Əo�̓f�[�^�̊W�𗝉����邱�Ƃ��ړI�ł���B���t����w�K�̓T�^�I�ȗ�Ƃ��ẮA�摜�Ɏʂ��Ă��镨�̂����ʂ��镪�ޖ���A�����������Ƃ̉��i��\�������A���Ȃǂ�����B
����A���t�Ȃ��w�K�ł́A�o�̓f�[�^�i���x���j�Ȃ��œ��̓f�[�^�݂̂���w�K���s���B���̏ꍇ�A���f���̓f�[�^���̍\����p�^�[���������I�Ɍ����o���A����Ɋ�Â��ăf�[�^�ނ�����A�V�����f�[�^�������肷��B���t�Ȃ��w�K�́A�f�[�^�̃N���X�^�����O�⎟���팸�A�����Đ���AI�ɂ����鐶�����f���̊w�K�ɗ��p�����B
����AI�ɂ����鋳�t�Ȃ��w�K�̉��p�͓��ɏd�v�ł���B�������f���́A���x���t������Ă��Ȃ���ʂ̃f�[�^���畡�G�ȃf�[�^���z���w�K���A���̕��z�Ɋ�Â��ĐV�����f�[�^�C���X�^���X������B����ɂ��A���t�Ȃ��w�K�́A�V�����R���e���c�̐����A�f�[�^�g���A����ɂ͋��t����w�K���f���̃g���[�j���O�f�[�^�Ƃ��Ă̗��p�ȂǁA����ɂ킽�鉞�p���\�ƂȂ�B
�A GAN(Generative Adversarial Networks)
GAN�A���Ȃ킿Generative Adversarial Networks�́A2014�N�ɃC�A���E�O�b�h�t�F���[��ɂ���Ē�Ă��ꂽ�������f���ł���B���̃��f���́A������iGenerator�j�Ǝ��ʊ�iDiscriminator�j�̓�̃l�b�g���[�N����\�������B������͐V�����f�[�^�T���v������������������A���ʊ�͂��̃T���v�����{���̃f�[�^���������ꂽ�f�[�^�������ʂ�����������B
GAN�̊w�K�v���Z�X�́A������Ǝ��ʊ킪�݂��ɋ�������Q�[���̂悤�Ȍ`�Ői�ށB������͂��{���炵���f�[�^�����悤�Ǝ��݁A���ʊ�͖{���̃f�[�^�Ɛ������ꂽ�f�[�^�𐳊m�Ɏ��ʂ��悤�Ƃ���B���̋�����ʂ��āA������͏��X�ɍ��i���ȃf�[�^������\�͂����コ���A���ʊ�͂�萸�x�������ʂ���\�͂����コ����B
GAN�͓��ɉ摜�����ɂ����Č����Ȑ��ʂ��グ�Ă���A�ʐ^�̂悤�Ƀ��A���ȉ摜�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�܂��A�X�^�C���ϊ��A�摜�⊮�A�摜����摜�ւ̕ϊ��ȂǁA���l�ȉ��p���\�ł���B
�������AGAN�̊w�K�͕s����ł���A���[�h����ƌĂ�錻�ۂ��N���邱�Ƃ�����B����́A�����킪����ꂽ��ނ̃T���v�������������Ȃ��Ȃ��Ԃ��w���B����ɁA���i���Ȑ������邽�߂ɂ́A�T�d�ȃp�����[�^�̒������K�v�ƂȂ�B
GAN�̌����́A���̃|�e���V�����Ɖ��p�̍L����ɂ��A����AI����ɂ����Ċ����ɍs���Ă���B�V�����A�[�L�e�N�`���̊J����A�w�K�v���Z�X�̈��艻�A���p�͈͂̊g��ȂǁA�����̐i����������B
�B VAE(Variational Autoencoders)
VAE�A���Ȃ킿Variational Autoencoders�́A�f�[�^�̊m�����z���w�K���邱�Ƃɂ��A�V�����f�[�^�����鐶�����f���ł���BVAE�̓I�[�g�G���R�[�_�̈�`�Ԃł���A�G���R�[�_�ƃf�R�[�_�̓�̎�v�ȕ�������\�������B�G���R�[�_�͓��̓f�[�^�����̐���ԂɃ}�b�s���O���A�f�R�[�_�͂��̐���Ԃ��猳�̃f�[�^��Ԃւ̃}�b�s���O���w�K����B
VAE�̓����́A����Ԃɂ�����_���L�Ӌ`�ȕ��@�ŘA�����Ă��邱�Ƃł���B����ɂ��A���ݕϐ��𑀍삷�邱�ƂŁA�f�[�^�̊��炩�ȕω������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ⴆ�A��摜�̐����ɂ����āA���ݕϐ���ω������邱�ƂŁA�\��┯�^���A���I�ɕς��摜���ł���B
VAE�̊w�K�v���Z�X�ł́A�G���R�[�_�ɂ���ăf�[�^�̊m�����z���ߎ����A�f�R�[�_�͂��̕��z����T���v�����O���ꂽ���ݕϐ������̃f�[�^�ɍč\������B���̉ߒ��ŁAKL�_�C�o�[�W�F���X�ƌĂ�鑹�������ŏ������邱�Ƃɂ��A�G���R�[�_�̋ߎ����z���f�[�^�̐^�̕��z�ɋ߂Â��悤�Ɋw�K���i�ށB
VAE�͂��̏_��ƌ���������A�摜���������łȂ��A�ُ팟�o�A�f�[�^�̈��k�A����ɂ͋����w�K�ɂ������ԕ\���̊w�K�ȂǁA���L�����p���\�ł���B�܂��A����Ԃ̉��߉\���́A�f�[�^�̗�����[�߂邽�߂̗L�p�Ȏ�i�����B
�������AVAE�ɂ͌��E������B�č\�����ꂽ�f�[�^�����̃f�[�^�ɔ�ׂĂڂ₯�Ă��܂��X��������A����͓��ɉ摜�f�[�^�ɂ����Č����ł���B�܂��A���G�ȃf�[�^�\�������f�[�^�̐����ɂ͓K���Ă��Ȃ��ꍇ������B
VAE�̌����́A��荂�i���Ȑ������邽�߂̐V�����A�[�L�e�N�`����w�K��@�̊J���ɏœ_�ĂĐi�߂��Ă���BVAE�̊T�O�́A����AI�̕���ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ���������ł��낤�B
�C RNN(Recurrent Neural Networks)
RNN�A���Ȃ킿Recurrent Neural Networks�́A���n��f�[�^�⏇���t����ꂽ�f�[�^���������߂̃j���[�����l�b�g���[�N�̈��ł���BRNN�̓����́A�ߋ��̏����L�����A��������݂̓��͂Ƒg�ݍ��킹�ď�������\�͂ɂ���B���̓����ɂ��ARNN�͎��R���ꏈ���≹�y�����ȂǁA�A���I�ȃf�[�^���ւ��^�X�N�ɓK���Ă���B
RNN�̊�{�I�ȍ\���̓V���v���ł��邪�A�����Ƀ��[�v�������ƂŁA���n��̊e���_�ł̓��͂ƂƂ��ɁA��O�̎��_����̏��������p�����Ƃ��ł���B����ɂ��ARNN�͕�����V�[�P���X���̈ˑ��W�����f��������\�͂����B
RNN�͓��ɐ������f���̕����ŗL���ł���B�ߋ��̃f�[�^�|�C���g���l�����Ȃ���V�����f�[�^�|�C���g������������邱�ƂŁA���͂���f�B�Ȃǂ̘A�������f�[�^�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ⴆ�A�^����ꂽ�e�L�X�g�̑�����������A�����Ɋ�Â��ĐV�������y����Ȃ����肷�邱�Ƃ��ł���B
�������ARNN�ɂ͂������̉ۑ�����݂���B���ɁA�����Ԃ̈ˑ��W�𑨂��邱�Ƃ�����ł���Ƃ�����肪����B����͌��z����������z�������Ɗ֘A���Ă���A�w�K�ߒ��ŏd�v�ȏ�����邱�Ƃ������ł���B���̖����������邽�߂ɁALSTM(Long Short-Term Memory)��GRU(Gated Recurrent Unit)�Ȃǂ̉��ǂ��ꂽRNN���J������Ă���B
RNN�Ƃ��̕ώ�́A����AI�̕���ɂ����ďd�v�ȃc�[���ł��葱���Ă���B�������l�������f�[�^�����̔\�͂́A�����̉��p�ɂ����ĉ��l�����BRNN�̌����ƊJ���́A�����ʓI�ŏ_��ȃ��f����ڎw���Đi�߂��Ă���B
3.4.2�@ ����AI�̋Z�p�I�v�f
3.4.2.1�@ �f�B�[�v���[�j���O�Ɛ���AI
�f�B�[�v���[�j���O�́A�[�w�j���[�����l�b�g���[�N��p�����@�B�w�K�̈ꕪ��ł���A�ߔN�A����AI�̐i�W�ɂ����Ē��S�I�Ȗ������ʂ����Ă���B�f�B�[�v���[�j���O�̃��f���́A�����̑w�������ƂŁA���G�ȃf�[�^�̕\�����w�K����\�͂�����B���̔\�͂ɂ��A�f�B�[�v���[�j���O�́A�摜�A�����A�e�L�X�g�ȂǁA���l�ȃf�[�^�̐����ɓK���Ă���B
����AI�ɂ�����f�B�[�v���[�j���O�̉��p�́A��ɐ������f���̍\�z�Ɋւ��B�[�w�j���[�����l�b�g���[�N��p���邱�ƂŁA���x�ɕ��G�ȃf�[�^���z�����f�������A�V�����f�[�^�C���X�^���X�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B����GAN��VAE�Ȃǂ̐������f���́A�f�B�[�v���[�j���O�̘g�g�݂̒��Ŕ��W���Ă���A���A���ȉ摜�⎩�R�Ȍ���e�L�X�g�̐����ɐ������Ă���B
�f�B�[�v���[�j���O�ɂ�鐶��AI�̃A�v���[�`�́A�f�[�^�̊K�w�I�ȕ\�����w�K���邱�ƂɊ�Â��Ă���B�j���[�����l�b�g���[�N�̊e�w�́A���̓f�[�^�̈قȂ�����𑨂��A�����̓�����g�ݍ��킹�邱�Ƃŕ��G�ȃf�[�^�\����͕킷��B���̃v���Z�X�́A�l�Ԃ̔]����������������@�ɗގ����Ă���Ƃ��l�����Ă���B
�f�B�[�v���[�j���O��p��������AI�́A�D�ꂽ���ʂ��グ�Ă������ŁA��ʂ̃g���[�j���O�f�[�^�ƌv�Z������K�v�Ƃ���B�܂��A�������ꂽ�f�[�^�����̃f�[�^�Z�b�g�Ɋ܂܂���f���邱�Ƃ�A���ߐ��̌��@�ȂǁA�������̉ۑ�����݂���B
�f�B�[�v���[�j���O�Ɛ���AI�̊W�́A�����AI�Z�p�̔��W�ɂ����ďd�v�ȃe�[�}�ł��葱����B�����҂����́A�������I�ȃ��f���̊J���A�f�[�^�̕�ւ̑Ώ��A���f���̉��ߐ�����ȂǁA�����̉ۑ�Ɏ��g��ł���B
3.4.2.2�@ �j���[�����l�b�g���[�N�̃A�[�L�e�N�`��
�j���[�����l�b�g���[�N�̃A�[�L�e�N�`���́A����AI�ɂ����钆�j�I�ȗv�f�ł���B����́A�f�[�^���畡�G�ȓ�����p�^�[�����w�K���A�V���ȃf�[�^�����邽�߂̌v�Z���f���̍\�����w���B�j���[�����l�b�g���[�N�́A�P���ȃp�[�Z�v�g�������畡�G�Ȑ[�w�w�K���f���܂ŁA���܂��܂Ȍ`�Ԃ����݂���B
��ʂɁA�j���[�����l�b�g���[�N�͓��͑w�A�B��w�A�o�͑w�̎O�̎�v�ȑw����\�������B���͑w�̓f�[�^�����A�B��w�͕����̃��x���Ńf�[�^�̒��ۉ��Ɠ������o���s���A�o�͑w�͍ŏI�I�Ȍ��ʂ����B�B��w�̐��ƃm�[�h�i�j���[�����j�̐��������قǁA�l�b�g���[�N�͂�蕡�G�Ȋ���\���ł��邪�A�v�Z�R�X�g�Ɖߊw�K�̃��X�N�����傷��B
�j���[�����l�b�g���[�N�̃A�[�L�e�N�`���́A�^�X�N�̐����A�g�p����f�[�^�̎�ށA���߂���o�͂ɂ���đ傫���قȂ�B�[�w�w�K�ɂ�����ŐV�̐i���́A����̃^�X�N�ɍœK�����ꂽ�A�[�L�e�N�`���̊J���ɂ���Ă����炳��Ă���B�Ⴆ�A��ݍ��݃j���[�����l�b�g���[�N�iCNN�j�͉摜�֘A�̃^�X�N�ɁA�g�����X�t�H�[�}�[���f���͎��R���ꏈ���̃^�X�N�ɓ������Ă���B
�j���[�����l�b�g���[�N�̃A�[�L�e�N�`���̐v�ƍœK���́A����AI�̐��\�����肷���ŏd�v�ȗv�f�ł���B�����҂����́A�������I�ŁA�\���͖L���ŁA�w�K�����肷��l�b�g���[�N�A�[�L�e�N�`�������߂āA�p���I�ɐV���ȃ��f���̊J���Ɏ��g��ł���B
3.4.2.3�@ �������ƍœK��
�������́A�j���[�����l�b�g���[�N�̊w�K�ɂ����āA���f���̏o�͂��ڕW�Ƃ���l����ǂꂾ������Ă��邩���ʉ�����w�W�ł���B����AI�ɂ����āA�������̓��f�������������f�[�^���{���̃f�[�^�Ƃǂꂾ�����Ă��邩�A�܂��͓���̖ړI���ǂꂾ���B�����Ă��邩��]�����邽�߂ɗp������B�œK���Ƃ́A���̑������̒l���ŏ�������悤�Ƀ��f���̃p�����[�^������v���Z�X�ł���B
����AI�ɂ����鑹�����͑��푽�l�ł���A����̐������f����^�X�N�ɉ����ĈقȂ�B�Ⴆ�AGAN�ł́A���ʊ킪�{���̃f�[�^�Ɛ������ꂽ�f�[�^���ǂꂾ�����m�Ɏ��ʂł��邩��\���������ƁA�����킪���ʊ���x�����Ƃɂǂꂾ���������Ă��邩��\�����������p������BVAE�ł́A�č\���덷��KL�_�C�o�[�W�F���X���܂ޑ��������g�p����A�f�[�^�̍č\�����x�Ɛ���Ԃ̐��������ɍs���B
�œK���A���S���Y���́A�������̍ŏ����������I�ɍs�����߂̎�@�ł���A���z�~���@�₻�̕ώ킪��ʓI�Ɏg�p�����B���z�~���@�́A�������̌��z�A�܂�p�����[�^�Ɋւ��鑹�����̓������v�Z���A���̌��z�����������Ƀp�����[�^���������X�V���Ă����B���̃v���Z�X���J��Ԃ����ƂŁA�ŏI�I�ɑ��������ŏ��ƂȂ�p�����[�^�̒l�Ɏ���������B
�œK���̉ߒ��ł́A�w�K���̐ݒ肪�d�v�ł���A����͊e�X�e�b�v�Ńp�����[�^���ǂꂾ���X�V���邩�����肷��B�w�K�����傫������ƍœK�ȉ����I�[�o�[�V���[�g���Ă��܂��A����������Ǝ����܂łɎ��Ԃ������肷����B�܂��A�~�j�o�b�`���z�~���@������^����p���邱�ƂŁA�w�K�̈��萫�����コ���A�������x�𑁂߂邱�Ƃ��ł���B
�������ƍœK���́A����AI�ɂ����郂�f���̐��\�Ɗw�K���������肷���ŏd�v�ȗv�f�ł���B�����҂����́A���ǂ��������邽�߂ɁA�V�����������̐v��œK���A���S���Y���̉��ǂɎ��g��ł���B
3.4.3�@ ����AI�̉��p��
3.4.3.1�@ ���R���ꐶ��
���R���ꐶ���́A����AI�����p������\�I�ȗ̈�̈�ł���B����́A�@�B���l�Ԃ������ł��錾��Ńe�L�X�g��������������Z�p�ł���A�f�[�^�̗v��A���̍쐬�A��b�^�G�[�W�F���g�A�X�g�[���[�̑n��ȂǁA����ɂ킽�鉞�p�����݂���B
���R���ꐶ���̃v���Z�X�́A��ʂɃf�[�^��Ӑ}���ꂽ���b�Z�[�W����͂Ƃ��Ď��A��������Ƃɕ��╶�͂��\�z����B���̉ߒ��ł́A���@�I�ɐ��m�ŁA���Ӗ����ʂ���e�L�X�g�����邱�Ƃ����߂���B����AI�Z�p�A����RNN��g�����X�t�H�[�}�[���f���Ȃǂ̐[�w�w�K���f���́A���̃^�X�N�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����B
���R���ꐶ���̉��p��Ƃ��ẮA�V�C�\��A�X�|�[�c�C�x���g�̌��ʁA�����̗v��Ȃǂ�����B�����̉��p�ɂ����āA����AI�͑�ʂ̃f�[�^����֘A���𒊏o���A�����l�Ԃ��������₷���`���̃e�L�X�g�ɕϊ�����B�܂��A�`���b�g�{�b�g�≼�z�A�V�X�^���g�ł́A���[�U�[�̎����v�]�ɑ��鎩�R�ȕԓ������邽�߂ɂ��̋Z�p���p������B
���R���ꐶ���̋Z�p�́A�N���G�C�e�B�u�ȕ��|��i�̑n��ɂ����p����Ă���B�Ⴆ�A�����̕��w��i�̃X�^�C����͕킵�ĐV���ȕ�������邱�Ƃ�A���[�U�[����̃v�����v�g�Ɋ�Â��Ď��⏬����n�삷�邱�Ƃ��\�ł���B
���R���ꐶ���Z�p�̔��W�ɂ��A�e�L�X�g�����̎��������i�݁A�����̎Y�Ƃɂ����č�Ƃ̌��������}���Ă���B�������A�������ꂽ�e�L�X�g�̕i���╶���̓K����ۏ��邱�ƁA�����������e�̗ϗ������m�ۂ��邱�ƂȂǁA�������ׂ��ۑ�������B�����҂�J���҂́A�����̉ۑ�ɑΏ����Ȃ���A��荂�x�Ȏ��R���ꐶ���Z�p�̊J���Ɏ��g��ł���B
3.4.3.2�@ �摜�����ƕҏW
�摜�����ƕҏW�́A����AI�Z�p�������Ȑ��ʂ������Ă��镪��ł���B���̋Z�p�́A�w�K�����摜�f�[�^�̕��z����V�����摜������\�͂Ɋ�Â��Ă���B����GAN��VAE�Ȃǂ̐[�w�w�K���f���́A�ʐ^���A���ȉ摜�̐����ɐ������Ă���A�A�[�g�A�G���^�[�e�C�����g�A�L���ȂǁA���l�ȗ̈�ł̉��p���i��ł���B
�摜�����ɂ����鉞�p��Ƃ��ẮA�L�����N�^�[�f�U�C���A���i�摜�̐����A�t�@�b�V�����A�C�e���̃f�U�C���Ȃǂ�����B�����̉��p�ɂ����āA����AI�͐l�Ԃ̑n�������x�����A�V���ȃr�W���A���R���e���c�̑n�o���\�ɂ���B
�摜�ҏW�ɂ����Ă��A����AI�͑傫�ȉ\�����߂Ă���B�Ⴆ�A�����̉摜�̃X�^�C����ϊ�������A�摜�̈ꕔ�����R�ɏC���E�폜������A���𑜓x�����邱�Ƃ��ł���B����ɂ��A�]���͐��Ƃ̎�ɂ���Ă̂݉\�ł��������x�ȉ摜�ҏW���A����y�ɁA�������I�ɍs����悤�ɂȂ�B
�܂��A�摜�����Z�p�́A���z������g�������Ƃ���������ɂ����Ă��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B���A���Ȋ���I�u�W�F�N�g�����A���������z��Ԃɓ������邱�ƂŁA�v���^�̑̌�����邱�Ƃ��ł���B
�摜�����ƕҏW�Z�p�̔��W�ɂ́A�ϗ��I�ȉۑ�������B���ɁA���A���Ȑl���摜��f��������\�͂́A���U�̏��̊g�U��v���C�o�V�[�̐N�Q�Ɉ��p�����\��������B���̂��߁A�Z�p�̊J���Ɖ��p�ɂ������ẮA���̎Љ�I�ȉe�����\���ɍl�����A�K�ȃK�C�h���C���̂��Ƃōs���K�v������B
�摜�����ƕҏW�́A����AI�̉��p�̒��ł����Ɏ��o�I�ɖ��͓I�ȕ���ł���A������Z�p�̐i���ƂƂ��ɁA����ɑ��l�ȉ��p�����҂���Ă���B�} 3‑54�͑�\�I�ȉ摜�����A�v���P�[�V����Stable Diffusion�Ő����������{�̉���̕��i�̗�ł���B

�} 3‑54�@Stable Diffusion�Ő�����������̕��i
3.4.3.3�@ ���������Ɖ��y����
���������Ɖ��y�����́A����AI�Z�p�����p�����d�v�ȗ̈�ł���B�����̋Z�p�́A�e�L�X�g���玩�R�ȉ�����������A�V�����y�Ȃ�n�삵���肷�邱�Ƃ��\�ɂ���B
���������A���Ȃ킿�e�L�X�g�E�g�D�E�X�s�[�`�iTTS�j�́A�����ꂽ�e�L�X�g��l�Ԃ̐��ɕϊ�����Z�p�ł���B�ߔN�̐���AI�̐i���ɂ��A���������̕i���͑傫�����サ�Ă���A�����A�C���g�l�[�V�����A����\���ȂǁA�l�Ԃ̎��R�Șb������͕킷�邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B���̋Z�p�́A�����A�V�X�^���g�A�I�[�f�B�I�u�b�N�̐����A���o��Q�Ҏx���V�X�e���ȂǁA����ɂ킽�鉞�p������B
���y�����ɂ����Ă��A����AI�͐V���ȉ\�����J���Ă���BAI�́A����̃W��������A�[�e�B�X�g�̃X�^�C�����w�K���A����Ɋ�Â��ăI���W�i���̊y�Ȃ�n�삷�邱�Ƃ��ł���B���̃v���Z�X�ɂ́A�����f�B�A�n�[���j�[�A���Y���ȂǁA�y�Ȃ̂��܂��܂ȗv�f���܂܂��B�������ꂽ���y�́A�f���Q�[���̃T�E���h�g���b�N�A�A�[�e�B�X�g�̑n�슈���A����ɂ͉��y����ɂ����Ă����p�����B
���������Ɖ��y�����̐i�W�́A����AI�̔\�͂������ƂƂ��ɁA�N���G�C�e�B�u�ȕ���ɂ�����AI�̖������Ē�`���Ă���BAI�ɂ�鉹���≹�y�̐����́A�l�Ԃ̑n�������g�����A�V�����A�[�g�t�H�[���̒T���𑣂��Ă���B
�������A�����̋Z�p�̉��p�ɂ́A���쌠��n�앨�̃I���W�i���e�B�Ƃ������ۑ�������BAI���������������≹�y���l�Ԃ̃N���G�C�^�[�̌�����N�Q���Ȃ��悤�A�K�Șg�g�݂̂��ƂŋZ�p���g�p����邱�Ƃ����߂���B
���������Ɖ��y�����́A����AI�̉��p�Ƃ��đ傫�Ȓ��ڂ��W�߂Ă���A������Z�p�̔��W�Ƌ��ɁA���̉��p�͈͍͂L���葱����ł��낤�B
3.4.3.4�@ �f�[�^�g��
�f�[�^�g���́A�����̃f�[�^�Z�b�g����lj��̃g���[�j���O�T���v���������@�ł���A���ɋ@�B�w�K���f���̊w�K�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����B����AI�́A���̃v���Z�X�ɂ����Ē��S�I�ȋZ�p�ƂȂ��Ă���B�f�[�^�g�����s�����ƂŁA���f���̈�ʉ��\�͂����コ���A�ߊw�K��h�����Ƃ��ł���B
�摜�f�[�^�ɂ�����f�[�^�g���ł́A����AI��p���ĐV�����摜�����邱�Ƃ���ʓI�ł���B����ɂ́A�����̉摜����]��������A���]��������A�F����ύX�����肷��P���Ȏ�@����AGAN���g�p���đS���V�����摜�������蕡�G�Ȏ�@�܂ł��܂܂��B����ɂ��A�w�K�f�[�^�Z�b�g�̑��l���������A���f���������E�̂��܂��܂ȏɑΉ��ł���悤�ɂȂ�B
�e�L�X�g�f�[�^�ɂ����Ă��A����AI�𗘗p�����f�[�^�g�����s���Ă���B���R���ꏈ�����f���̃g���[�j���O�̂��߂ɁA�����̃e�L�X�g�f�[�^����V���ȕ��╶�͂����A�f�[�^�Z�b�g���g�[����B���̃v���Z�X�ɂ́A�P��̒u���A���̍č\���A�V�������̐����Ȃǂ��܂܂��B
�����f�[�^�̏ꍇ�A�f�[�^�g���͉����̃s�b�`�⑬�x��ύX������A�w�i�m�C�Y��lj����邱�Ƃɂ��s���邱�Ƃ������B����AI��p���邱�ƂŁA�����̕ϊ������������ꂽ���@�ōs���A��茻���I�ȃg���[�j���O�f�[�^�����邱�Ƃ��ł���B
�f�[�^�g���́A����ꂽ�ʂ̃g���[�j���O�f�[�^�������p�ł��Ȃ��ꍇ��A���f������茘�S�ɂ���K�v������ꍇ�ɓ��ɗL�p�ł���B����AI�����p���邱�ƂŁA�]���̎�@�ł͎����ł��Ȃ��������x���̃f�[�^�g�����\�ƂȂ�A�@�B�w�K���f���̐��\����ɍv�����Ă���B
3.4.4�@ ���p����ւ̓K�p
3.4.4.1�@ �}�[�P�e�B���O��L���ƊE�ł̊��p
�}�[�P�e�B���O��L���ƊE�ɂ����鐶��AI�̊��p�́A�ߔN�A�傫�Ȓ��ڂ��W�߂Ă���B����AI�́A�p�[�\�i���C�Y���ꂽ�L���R���e���c�̍쐬�A����҂̊S�������r�W���A���R���e���c�̐����A���ʓI�ȃ}�[�P�e�B���O�헪�̍���ȂǁA���܂��܂Ȍ`�Ŋ��p����Ă���B
�p�[�\�i���C�Y���ꂽ�L���R���e���c�̐����́A����AI�̏d�v�ȉ��p��ł���B����҂̉ߋ��̍w��������I�����C���ł̍s���p�^�[���͂��A���̏�����ɂ��ČX�̏���҂ɍ��킹���J�X�^�}�C�Y���ꂽ�L�����b�Z�[�W��摜������B����ɂ��A�L���̊֘A�������܂�A����҂̊S�������ʓI�Ɉ������邱�Ƃ��ł���B
�܂��A�r�W���A���R���e���c�̐����ɂ����Ă��A����AI�͑傫�Ȗ������ʂ����Ă���B�V���i�̃v�����[�V�����r�W���A����ASNS�p�̃N���G�C�e�B�u�ȉ摜�A�o�i�[�L���ȂǁA���͓I�Ŗڂ������r�W���A���R���e���c�̐������A����AI�ɂ��e�ՂɂȂ��Ă���B����GAN�̋Z�p�́A�ʐ^�̂悤�Ƀ��A���ȉ摜�����邱�Ƃ��\�ł���A�L���r�W���A���̕i�������コ����B
����ɁA����AI�̓}�[�P�e�B���O�헪�̍���ɂ����Ă����p����Ă���B����҂̍s����n�D�Ɋւ���f�[�^����C���T�C�g�𒊏o���A����Ɋ�Â��ă}�[�P�e�B���O�L�����y�[���̃R���Z�v�g��b�Z�[�W������B����ɂ��A���^�[�Q�b�g�ɍ��v�����A���ʓI�ȃ}�[�P�e�B���O�헪�̍��肪�\�ƂȂ�B
�}�[�P�e�B���O��L���ƊE�ɂ����鐶��AI�̊��p�́A��ƂɂƂ��ċ����͂����߂�d�v�ȗv�f�ƂȂ��Ă���B�������A�l�̃v���C�o�V�[�ی��ϗ��I�ȍL�����H�Ɋւ���ۑ�ɗ��ӂ��A�K�ȗ��p�����߂���B
3.4.4.2�@ �G���^�[�e�C�����g�ƊE�ł̗��p
�G���^�[�e�C�����g�ƊE�ɂ����鐶��AI�̗��p�́A�n�����ƋZ�p�̗Z���ɂ���ĐV���ȉ��l�ݏo���Ă���B�f��A���y�A�r�f�I�Q�[���A�����ăA�[�g�Ƃ���������ŁA����AI�̓R���e���c����̃v���Z�X��ϊv���A�ϋq�ɖ��̌��̃G���^�[�e�C�����g����Ă���B
�f��ƊE�ɂ����āA����AI�͓�����ʂ�w�i�̐����ɗ��p����邱�Ƃ������Ă���B���A����CG�L�����N�^�[�╗�i�����邱�ƂŁA����R�X�g�̍팸�ƂƂ��ɁA�f���\���̉\�����L���Ă���B�܂��A�r�{�̎���������A�����̉f���f�ނ���V���ȃV�[����n�o����������s���Ă���A�f�搧��̖����Ɋv�V�������炷�\�����߂Ă���B
���y����ł́A����AI��p�����y�Ȑ��삪���ڂ��W�߂Ă���BAI���w�K�����������̊y�Ȃ̃X�^�C������ɁA�I���W�i���̃����f�B��n�[���j�[������B����ɂ��A�A�[�e�B�X�g�͐V���ȃC���X�s���[�V�����邱�Ƃ��ł��A�n�슈���̕����L����B����ɁA����AI�ɂ�郉�C�u�p�t�H�[�}���X��A�C���^���N�e�B�u�ȉ��y�̌��̒��\�ƂȂ��Ă���B
�r�f�I�Q�[���ƊE�ɂ����ẮA����AI���Q�[�����̗v�f�������������邽�߂ɗp�����Ă���B�L�����N�^�[�A�A�C�e���A����ɂ̓Q�[���̃��x������܂ŁAAI���v���C���[�̍s����D�݂ɉ����ē��I�ɃR���e���c�����A���j�[�N�ȃQ�[���̌������B
�A�[�g�̗̈�ł́A����AI�����p�����V���ȃA�[�g��i�̑n�o���i��ł���BAI���w�K�������j�I�ȃA�[�g�X�^�C�������ɁA�Ǝ��̃r�W���A���A�[�g�����邱�ƂŁA�]���̃A�[�g����̘g������i�����ݏo����Ă���B
�G���^�[�e�C�����g�ƊE�ł̐���AI�̗��p�́A�ϋq�ɐV������������������ƂƂ��ɁA�N���G�C�^�[�̕\���̕����g���Ă���B�������AAI�ɂ��n�앨�̒��쌠��A�l�Ԃ̃N���G�C�^�[�̖����Ƃ������c�_�������N�����Ă���A�Z�p�̐i�W�ƂƂ��ɁA�����̉ۑ�ɑ����������͍�����Ă���B
3.4.4.3�@ �P�[�u���ƊE�ł̗��p��
�P�[�u��TV�ƊE�ɂ����鐶��AI�̗��p�́A�R���e���c�̐��E�V�X�e���̋����A�����҃f�[�^�̕��́A�p�[�\�i���C�Y���ꂽ�L���̒ȂǁA�����ʂɂ킽��B�����̋Z�p�́A�����̌��̌���ƋƊE�̃r�W�l�X���f���̊v�V��ڎw���Ă���B
���E�V�X�e���́A�P�[�u��TV�ƊE�ɂ����鐶��AI�̑�\�I�ȉ��p��ł���B����AI��p�������E�V�X�e���́A�����҂̉ߋ��̎���������D�݂͂��A����Ɋ�Â��ČX�̎����҂ɍœK�Ȕԑg��f��𐄑E����B����ɂ��A�����҂͎��g�̊S�ɍ������R���e���c��e�ՂɌ����邱�Ƃ��ł��A�����̌������シ��B
�����҃f�[�^�̕��͂ɂ����Ă��A����AI�͏d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B�����҂̍s���p�^�[����n�D��[���������邱�ƂŁA�P�[�u��TV���Ǝ҂͂�薣�͓I�ȃR���e���c�����E���삷�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�܂��A�������̗\����ԑg�̍œK�ȕ����X�P�W���[���̍���ȂǁA�^�c�̌������ɂ��v�����Ă���B
�p�[�\�i���C�Y���ꂽ�L���̒́A�P�[�u��TV�ƊE�ɂ����鐶��AI�̉��p�̒��ł����ɒ��ڂ���Ă��镪��ł���B����AI�����p���邱�ƂŁA�����҈�l�ЂƂ�̋�����j�[�Y�ɍ��킹���L�������A���^�C���Ő������A�������邱�Ƃ��ł���B����ɂ��A�L���̌��ʂ����サ�A�L����ɂƂ��Ă����͓I�ȍL���v���b�g�t�H�[���ƂȂ�B
�P�[�u��TV�ƊE�ɂ����鐶��AI�̗��p�́A�����҂̃j�[�Y�ɉ����邾���łȂ��A�V���ȃr�W�l�X�`�����X��n�o����\���������Ă���B�������A�l�̃v���C�o�V�[�ی��f�[�^�̈��S���Ƃ������ۑ�ɑ���z�����K�v�ł���A�Z�p�̐i���ƂƂ��ɁA�����̖��ɑ��������̊J�����i�߂��Ă���B
3.4.5�@ ����AI�̎Љ�I�e��
����AI�̔��W�́A�Љ�S�̂ɑ���ȉe����^���Ă���B���̋Z�p�́A�N���G�C�e�B�u�Y�Ƃ̕ϊv�A�l�̃v���C�o�V�[�ƃZ�L�����e�B�̖��A�J���s��ւ̉e���ȂǁA�l�X�ȑ��ʂŎЉ�ɉe�����y�ڂ��Ă���B
�N���G�C�e�B�u�Y�Ƃɂ����鐶��AI�̗��p�́A�A�[�g�A���y�A���w�ȂǁA�l�Ԃ̑n�����̗̈�ɐV���ȉ\���������炵�Ă���BAI�ɂ���Đ������ꂽ��i�́A�]���̃N���G�C�e�B�u�ȃv���Z�X��⊮���A�V�����`���̃A�[�g��n�o����B�������A�����̋Z�p���l�Ԃ̃A�[�e�B�X�g�ɑ�����̂ƂȂ�̂��A���邢�͋���������̂ƂȂ�̂��ɂ��ẮA���������c�_���K�v�ł���B
�l�̃v���C�o�V�[�ƃZ�L�����e�B�ɑ��鐶��AI�̉e�����d�v�Ȍ��O�����ł���B���ɁA���A���ȉ摜��f���A����������\�͂́A�U���̊g�U�⍼�\�A�v���C�o�V�[�̐N�Q�Ƃ��������X�N�����߂�B����ɑΏ����邽�߂ɂ́A�Z�p�I�ȉ�����̊J���ƂƂ��ɁA�K�Ȗ@�I�g�g�݂̐��������߂���B
�J���s��ɂ����ẮA����AI�͈ꕔ�̐E���^�X�N�̎��������\�ɂ��A�J���̐�����ς���\��������B����ŁA�V���ȐE�Ƃ�X�L���̎��v�ݏo�����Ƃ��\�z�����B���̕ω��ɓK�����邽�߂ɂ́A�����P���̃V�X�e�����čl���A�����̘J���s��ɔ�����K�v������B
����AI�̎Љ�I�e���́A�Z�p�̗��p���@���̎d���ɑ傫���ˑ�����B���̂��߁A�Z�p�ҁA�������ĎҁA�Љ�S�̂����͂��A����AI�̃|�e���V�������ő���Ɋ��p���A���X�N���ŏ����ɗ}����o�����X�������邱�Ƃ��d�v�ł���B����AI�̔��W�́A�ϗ��I�ȃK�C�h���C���ƎЉ�I�ȍ��ӂɊ�Â��ׂ��ł���A���̉ߒ��œ������ƌ��������m�ۂ��邱�Ƃ����߂���B
3.4.6�@ ����AI�̌��������Ɩ���
3.4.6.1�@ ����AI�̌�������
����AI�̌����́A�Z�p�I�Ȑi���ƎЉ�I�Ȏ��v�̗����ɂ���ĉ�������Ă���B���̕���ɂ����錤�������́A�V�����A�[�L�e�N�`���̊J���A�w�K�v���Z�X�̍œK���A���p�͈͂̊g��Ƃ������������ɏW���B
�V�����A�[�L�e�N�`���̊J���ɂ����ẮA��荂�i���Ȑ������邽�߂̐V���ȃl�b�g���[�N�\�����T������Ă���B����ɂ́A�������f���̌����������コ����A���S���Y���̉��ǂ�A�قȂ�^�C�v�̐������f���̓����Ƃ������A�v���[�`���܂܂��B�܂��A�w�K�v���Z�X�̈��萫�����߂邽�߂̌������i�߂��Ă���A����GAN�ɂ����郂�[�h������ւ̑Ώ����d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B
����AI�̉��p�͈͂̊g��ɂ��ẮA�]���̗̈�ɉ����A��ÁA�����ƁA�s�s�v��Ƃ������V���ȕ���ւ̉��p���͍�����Ă���B�Ⴆ�A��É摜�̐����ɂ��f�f�x����A���i�v�̂��߂̐V�f�ނ̐����A�s�s�̃V�~�����[�V�����ɂ�鎝���\�ȓs�s�v��̍���Ȃǂ���������B
�����ɂ����鐶��AI�̌����́A�����̋Z�p�I�Ȑi���ɉ����A�ϗ��I�ȉۑ�ւ̑Ή����d�v�ȃe�[�}�ƂȂ�B�U���̊g�U��v���C�o�V�[�̐N�Q�Ƃ��������X�N�ւ̑�AAI�ɂ��n�앨�̒��쌠��I���W�i���e�B�̖��ւ̎��g�݂����߂��Ă���B�܂��AAI�Z�p�̖��剻�Ɍ������A�N�Z�X�̕�������A�Z�p�̓������Ɛ����ӔC�̊m�ۂ��A�����̌����ɂ����ďd�v�ȗv�f�ƂȂ�B
����AI�̖����́A�Z�p�I�Ȋv�V�ƂƂ��ɁA�Љ�I�ȐӔC�Ɨϗ��I�ȍl�������̂ƂȂ�B�����ҁA�J���ҁA�������ĎҁA�����ĎЉ�S�̂����͂��A����AI�������\�ŗϗ��I�ȕ��@�Ŕ��W������悤�Ɏ��g�ނ��Ƃ��d�v�ł���B
3.4.6.2�@ ����AI�̉\���ƌ��E
����AI�́A���̔��W�ɂ��A�N���G�C�e�B�u�ȍ�i�̐����A�f�[�^�g���A�p�[�\�i���C�Y���ꂽ�R���e���c�̒Ƃ����������̉\�����J���Ă���B�����̋Z�p�́A�G���^�[�e�C�����g�A�}�[�P�e�B���O�A��ÁA�Ȋw�����Ƃ��������L������Ŋv�V�������炵�A�l�Ԃ̑n�����Ɛ��Y����傫���g������B����AI�ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�V�����A�C�f�A��R���e���c�́A�]���̕��@�ł͍l�����Ȃ������`�������������B
�������A����AI�̋Z�p�́A���̗��p���@��ړI�ɂ���ẮA�ϗ��I�Ȗ���Љ�I�Ȍ��O�������N�����\��������B�U���̐�����v���C�o�V�[�̐N�Q�A�m�I���Y���̖��́A���̋Z�p�̐ӔC����g�p�����߂鐺�����߂Ă���B�܂��AAI�ɂ�鎩�������i�ޒ��ŁA�J���s��ւ̉e����l�Ԃ̖����Ɋւ��鍪�{�I�Ȗ₢����N����Ă���B
����AI�̖����́A�����̋Z�p�̉\�����ő���Ɋ��p���A�����Ƀ��X�N���Ǘ����A�ϗ��I�Ȏw�j�ɉ������g�p���m�ۂ��邱�Ƃɂ������Ă���B���̂��߂ɂ́A�Z�p�ҁA�����ҁA�������ĎҁA����ɂ͈�ʂ̐l�X���܂߂��Љ�S�̂ł̑Θb�Ƌ��͂��s���ł���B
�ŏI�I�ɁA����AI�̉\���ƌ��E�́A�l�Ԃ������̋Z�p���ǂ̂悤�Ɏ���A�K�p���A�K�����邩�ɂ���Č`�����B����AI�̎����\�Ȕ��W�́A�Z�p�I�Ȑi�������łȂ��A�ϗ��I�A�Љ�I�ȓ��@�Ɋ�Â������I�ȃA�v���[�`��K�v�Ƃ���B����AI���l�ނɂƂ��Đ^�ɗL�v�ȃc�[���ƂȂ邽�߂ɂ́A���̉\����T�����A���E��F�����A���ɐ������邽�߂̓���͍�����K�v������B
��4�� �T�[�r�X�i��
4.1�@ �Z�L�����e�B
4.1.1�@ ��`
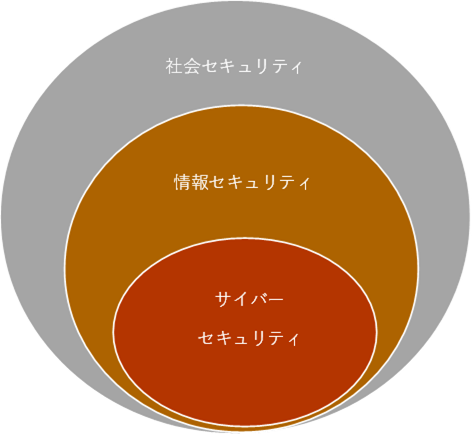
�} 4‑1�@�Z�L�����e�B�֘A�}
�Z�L�����e�B�̒�`�ɂ���JIS�i���{�Y�ƋK�i�j��ISO�AITU�A���̑������@�Ȃǂ̌��I�ȕ����Ȃǂɂ��ƁA�Z�L�����e�B�Ƃ����P��Ɋւ�����I�Ȓ�`�Ƃ��āA�u�Љ�Z�L�����e�B�v�A�u���Z�L�����e�B�v�A�u�T�C�o�[�Z�L�����e�B�v������A�����̊W���A�} 4‑1�Ɏ����B�܂��A�e�X�̒�`�ɂ��Ă͎��߈ȍ~�ɏq�ׂ�B
4.1.1.1�@ �Љ�Z�L�����e�B
�Љ�Z�L�����e�B�̒�`�́AJIS Q22300:2013�ɂ��ƁA�ȉ��̒ʂ�ƂȂ��Ă���B
|
�Ӑ}�I�y�ы����I�ȁA�l�I�s�ׁA���R���ۋy�ыZ�p�I�s��ɂ���Ĕ�������C���V�f���g�A�ً}���ԋy�эЊQ����Љ����邱�ƁA���тɂ����ɑΉ����邱�ƁB |
�����v��ƁA�u�Љ����邱�Ɓv�ł���A���ׂẴC���V�f���g���ΏۂƂ�����B
4.1.1.2�@ ���Z�L�����e�B
���Z�L�����e�B�̒�`�́AJIS Q27000:2019�ł́A�ȉ��̒ʂ�ƂȂ��Ă���B
�w���̋@�����A���S������щp�����ێ����邱�ƁB�x
�܂��A�K�i���ɂ́A�@�����A���S���A�p���ɉ����A�Ǝ㐫�̒�`���L�ڂ���Ă���B
l �@�����iConfidentiality�j
�w�F����Ă��Ȃ��l�A�G���e�B�e�B���̓v���Z�X�ɑ��āA�����g�p�������A�܂��A�J�����Ȃ������B�x
l ���S���iIntegrity�j
�w���m���y�ъ��S���̓����B�x
l �p���iAvailability�j
�w�F���ꂽ�G���e�B�e�B���v�������Ƃ��ɁA�A�N�Z�X�y�юg�p���\�ł�������B�x
l �Ǝ㐫�iVulnerability�j
�w��ȏ�̋��Ђɂ���ĕt�����܂��\���̂���A���Y���͊Ǘ���̎�_�B�x
���������āA�@�����A���S���A�p����3���Ȍ��ɕ\������ƁA�@�����́u��R��Ȃ����Ɓv�A���S���́u��ς��Ȃ����Ɓv�A�p���́u���ł���g���邱�Ɓv�ł���Ƃ�����B�Ȃ��A�@�����A���S���A�p����3�́A���Z�L�����e�B��3�v�f�Ƃ������A�p��̓�����������āACIA�Ƃ��Ă�Ă���A�u����CIA���ێ����邱�Ɓv���A���Z�L�����e�B�Ɠ��`��ɂȂ��Ă���B
�܂��AJIS Q27000�V���[�Y�́AISO 27000�V���[�Y�Ƃ������N���Ă���AISMS�Ƃ������Ă���B
4.1.1.3�@ �T�C�o�[�Z�L�����e�B
�T�C�o�[�Z�L�����e�B�̒�`�ɂ��ẮAJIS Q27000�V���[�Y�ɂ͋L�ڂ��Ȃ����AISO 27000 �V���[�Y��ISO 27032�F2012�ɂ́A�T�C�o�[�Z�L�����e�B�Ƃ��āw�T�C�o�[��Ԃ̏��̋@�����A���S���A����щp���̈ێ��x�ƂȂ��Ă���B
����A�����̌��I�ȕ����ł́A�T�C�o�[�Z�L�����e�B��{�@�̑����i�����O�\�N�\�\������z�j�ŃT�C�o�[�Z�L�����e�B���ȉ��̒ʂ��`���Ă���B
|
�d�q�I�����A���C�I�������̑��l�̒m�o�ɂ���Ă͔F�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������i�ȉ����̏��ɂ����āu�d���I�����v�Ƃ����j�ɂ��L�^����A���͔��M����A�`������A�Ⴕ���͎�M�������̘R�����A�Ŏ����͚ʑ��̖h�~���̑��̓��Y���̈��S�Ǘ��̂��߂ɕK�v�ȑ[�u���тɏ��V�X�e���y�я��ʐM�l�b�g���[�N�̈��S���y�ѐM�����̊m�ۂ̂��߂ɕK�v�ȑ[�u�i���ʐM�l�b�g���[�N���͓d���I�����ō��ꂽ�L�^�ɌW��L�^�}�́i�ȉ��u�d���I�L�^�}�́v�Ƃ����j��ʂ����d�q�v�Z�@�ɑ���s���Ȋ����ɂ���Q�̖h�~�̂��߂ɕK�v�ȑ[�u���܂ށj���u�����A���̏�Ԃ��K�Ɉێ��Ǘ�����Ă��邱�Ƃ������B |
�����v��ƁA�u�d���I�ȏ��Z�L�����e�B����邱�Ɓv�ł���A���ȂǓd���I�ȊO�̕������f�B�A�ɏ�������ł�����́A���Z�L�����e�B�ɂ͊Y��������̂̃T�C�o�[�Z�L�����e�B�ɂ͊Y�����Ȃ��B
�܂��AITU-T��X.1500 (2011)/Amd.12 (03/2018)�ɂ��T�C�o�[�Z�L�����e�B�̒�`������̂ŁA�Q�l�܂łɏЉ��B
|
�T�C�o�[���Ƒg�D�A���[�U�̎��Y����邽�߂Ɏg�p�\�ȃc�[������j�A�Z�L�����e�B�̊T�O�A�Z�L�����e�B�̕ی�A�K�C�h���C���A���X�N�Ǘ��A�v���[�`�A�s���A�g���[�j���O�A�őP��A�ۏA�Z�p�̏W�܂�B�g�D����у��[�U�̎��Y�ɂ́A�ڑ�����Ă���R���s���[�^�f�o�C�X�A�l���A�C���t���A�A�v���A�T�[�r�X�A�ʐM�V�X�e���A����ѓd�q�I�ɑ��M�܂��͕ۑ����ꂽ���̑S�̂��܂܂��B�T�C�o�[�Z�L�����e�B�́A�T�C�o�[��Ԃɂ�����Z�L�����e�B��̊댯����A���[�U�Ƒg�D�̎��Y�̃Z�L���A�ɕۂ������@�\�Ƃ��̕ێ�ɂ��āA���悤�ɓw�߂邱�Ƃł���B��ʓI�ȃZ�L�����e�B�����j�ɂ́A�p���A���S���i�F�Ɣ۔F�h�~���܂ށj�A����ы@�������܂܂��B ���F�����K������і@���̈ꕔ�ł́A�l�����ł������ی삷�邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�ꍇ������B |
4.1.1.4�@ �Z�L�����e�B�̕���
CATV���Ǝ҂̑命����Web�Ŏ��Ђ̃T�[�r�X���e�Ȃǂ����J���A�Ј��p�̃��[���T�[�o��ێ����Ă���A�C���^�[�l�b�g�Ɛڑ�����Ă���BCATV���Ǝ҂Ɍ��炸��ʂ̊�Ƃł��������Ă��邱�̂悤�ȃV�X�e���̂��Ƃ��A�Г��V�X�e���܂���IT�n�ƌĂ�ł���B����ACATV���Ǝ҂��������Ɓi�e���r�Ȃǁj��d�C�ʐM���Ɓi�C���^�[�l�b�g�E�d�b�Ȃǁj�Ƃ��Čڋq�ɃT�[�r�X�����ۂɗp����V�X�e���̂��Ƃ��A�^�p�n���n�V�X�e���܂��́AOT�iOperational Technology�j�n�V�X�e���ƌĂ�ł���BCATV���Ǝ҂�IT�n��OT�n�̃V�X�e����{�\���̗��} 4‑2�Ɏ����B
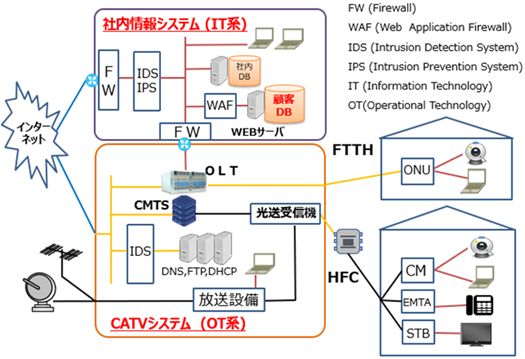
�} 4‑2�@CATV���Ǝ҂̃V�X�e����{�\����
���̗�ł́A�������ƂƓd�C�ʐM���Ƃ̗�������Ă���CATV���Ǝ҂�\���Ă��邪�A�������Ƃ݂̂���Ă��鎖�Ǝ҂ɂ��Ă��ʐM�֘A���u���Ȃ����ƈȊO�͓����ł���B�Ȃ��ACATV���Ǝ҂̋K�͂ɂ��傫�ȍ��ق́A�w�b�h�G���h���̈Ⴂ�ɂ��CMTS��T�[�o�Ȃǂ̒ʐM�@��̐��ł���A�V�X�e���̊�{�\���ɂ͑卷�Ȃ��B�Ȃ��A�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ̒ʐM�T�[�r�X����Ă���OT�n�ł́ACMTS��OLT�̉����Ҍn�̐ݔ���ADNS�iDomain Name System�j��FTP�iFile Transfer Protocol�j�T�[�o�Ȃǂ̃Z���^�[�n�V�X�e���ō\������Ă���̂���{�ł���B�����āA�T�[�r�X�̓�����AFW�i�t�@�C�A�E�H�[���j�𖢑}���̂܂܉^�p���A�����҂փC���^�[�l�b�g������Ă���B�������AOT�n�̃V�X�e���̐ݒ��ύX�ɉ����A�����ғo�^�Ȃǂ����邽�߁AIT�n���OT�n�ւ̒ʐM�o�H�����݂��A���̊Ԃ�FW����Ă���̂����ʂł���B���������āA�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ���Ă��Ȃ������T�[�r�X�݂̂̎��Ǝ҂ɂ��Ă��AIT�o�R��OT�n�i�����@��j�ɂ��A�N�Z�X�ł��邽�߁A�ʐM�T�[�r�X���s���Ă��鎖�Ǝ҂Ɠ��l�ɃT�C�o�[�U���̊댯��������B
IT�n��OT�n�ł͎��ׂ��D��x����ʓI�ɈقȂ��Ă���BIT�n�ł́A�l����@�����������Ă��邱�Ƃ���A�@��������邱�Ƃ��ŗD��ł��邪�A�����̃T�[�r�X��~���������p�����ቺ����V�X�e���̃��X�^�[�g�͔�r�I�e�Ղɉ\�ł���B����AOT�n�ł́A���q�l�ւ̕����E�ʐM�T�[�r�X�Ȃǂ���A24����365���̉ғ������߂��邱�Ƃ���A�p������邱�Ƃ��ŗD��ƂȂ��Ă���B�����ɂ��ĕ��ނ������̂�\ 4‑1�Ɏ����B
�\ 4‑1�@�Z�L�����e�B�̕���

�Ȃ��ACATV���Ǝ҂ɂ����Ĕ������Ă���u���R�k�v�A�u�}���E�F�A�����v�A�uDoS�U���v�ɂ��ẮA���ꂼ��A�u�@�����v�A�u���S���v�A�u�p���v�̐N�Q�ɂ�����A�Z�L�����e�B�̃C���V�f���g�Ƃ��Ĉ�����B
4.1.2�@ CATV���Ǝ҂ւ̃T�C�o�[�U���̎��
�T�C�o�[�U����@�ɂ͕����̃p�^�[�������邪�A�{�͂ł́AIT�n�EOT�n�ŋ��ʂ̃T�[�o�Ȃǂɑ��A�C���^�[�l�b�g�o�R�ōU�����d�|����T�^�I�Ȏ�@�ɂ��ĉ������B
4.1.2.1�@ �T�v
�T�[�o�Ȃǂ�_���T�C�o�[�U���̓T�^�I�Ȏ�@��} 4‑3�Ɏ����B
�U���҂́A�ŏ���IP�A�h���X�̃X�L�����ƃ|�[�g�X�L���������{���čU���Ώۂ�IP�A�h���X��|�[�g���i��i�@�j�B���̌��ʁA�U���ΏۂƂȂ�|�[�g���J���Ă���ꍇ�A�s���N���i�A�j��WEB�Ǝ㐫�U���i�B�j�����s����B�����̍U��������ł��Ȃ���A4.1.1.2�@�߂ʼn���������Z�L�����e�B��3�v�f�ł���u�@�����v�u���S���v�u�p���v���N�Q����Ă��܂��B
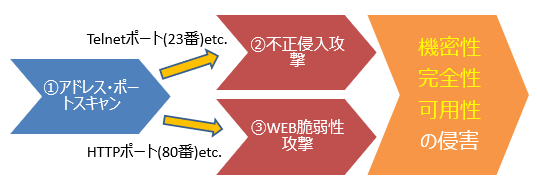
�} 4‑3 �T�C�o�[�U���̓T�^
4.1.2.2�@ CATV���Ƃɂ�����T�C�o�[�U���̈ꗗ
CATV���Ƃɂ�����T�C�o�[�U���̎�@�ƌ����̈ꗗ��\ 4‑2�Ɏ����B
�T�C�o�[�U���Ƃ��̑�ɂ��ẮA���X���l�����Ă������߁A��ɍŐV�̏�����肷�邱�Ƃ��̗v�ł���B��������U���̈ꕔ���Љ��B
�\ 4‑2�@�T�C�o�[�U���̎�ނƌ���
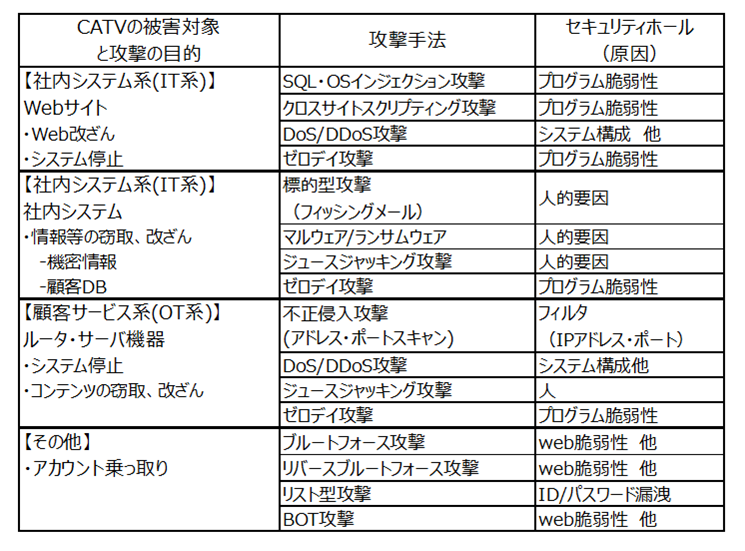
4.1.2.3�@ �A�h���X�E�|�[�g�X�L����
�U���҂́A���E����IP�A�h���X�i��42���j�ƁA65,536�̃|�[�g�̊J���̗L���������i�X�L�����j���_�����߂�B���̑S�A�h���X�ƑS�|�[�g���������鎞�Ԃ́A�킸��6���Ԓ��x�Ƃ����Ă���BIP�A�h���X�́A32�r�b�g�Ŗ�42���̃A�h���X��Ԃ�����IPv4�ƁA128�r�b�g��IPv4�̃A�h���X��4��i42���~42���~42���~42���j�̃A�h���X��Ԃ�����IPv6�����邪�A42����IP�A�h���X��1�b�ԂŌ����ł����Ƃ��Ă��AIPv6�̑S�A�h���X�ƑS�|�[�g����������̂�138���N�i�F���̗��j�j�̖�170���{���̎��Ԃ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A�U���҂������IPv6�A�h���X��m���Ă���ꍇ�������A�X�L������p�����U����IPv4�A�h���X����ȃ^�[�Q�b�g�ɂȂ�B�܂��A���J����Ă���WEB�T�C�g�ŒN�ł��e�ՂɃX�L�����iIPv4�̂݁j���\�ł���A���̑�\��ł���SHODAN��censys�Ń��{�̃h���C���ŃX�L�������s�������ʂ��A���ꂼ��} 4‑4����ѐ} 4‑5�Ɏ����B�����̃T�C�g�̗��p�͊�{�I�ɖ����ł���B������IP�A�h���X�������i250�A�h���X/���j����ꍇ�Ȃǂɂ́A�ʓr��p�i��59�`��999/���j���K�v�ƂȂ邪�A�U���҂��g�p���Ă���Ƃ������Ƃł���B
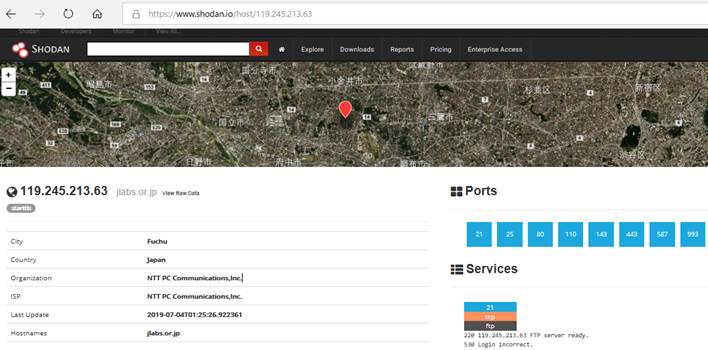
�} 4‑4�@SHODAN�ɂ�郉�{�h���C���̃|�[�g�X�L��������
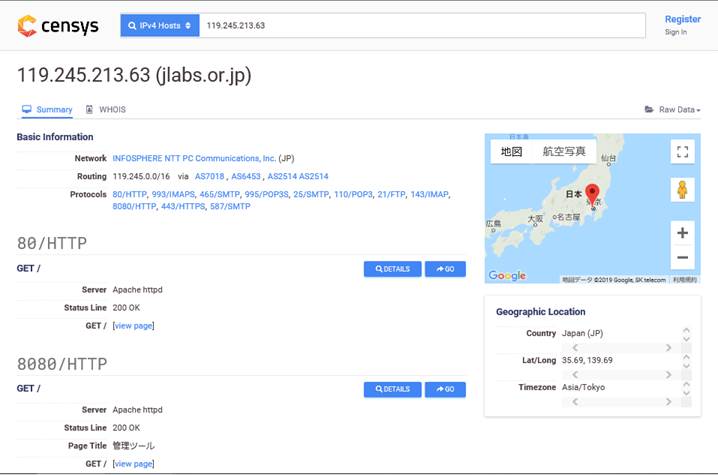
�} 4‑5�@Cencys�ɂ�郉�{�h���C���̃|�[�g�X�L��������
�} 4‑4��Ports�ɕ\������Ă��鐔���́A�|�[�g�ԍ��������Ă���A21�Ԃ�25�ԂȂǂ̕����̃|�[�g���J���Ă��邱�Ƃ��킩��B�|�[�g�ԍ��́A16�r�b�g����Ȃ�0�ԁ`65,535�Ԃ�����A�\ 4‑3�̒ʂ�A�ԍ��ɂ��@�\�����ނ���Ă���B���̔ԍ��́A�ꕔ��IANA�iInternet Assigned Numbers Authority�j�ɂ��Ǘ�����Ă��邪�A���R�Ɏg����|�[�g�ԍ������݂���BIANA�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g�Ɋ֘A����ԍ����Ǘ����Ă���k�Ăɂ���g�D�ł���B
�\ 4‑3�@�|�[�g�ԍ��̕���

��\�I�ȃ|�[�g�ԍ��Ƃ��̋@�\�Ƃ��ẮA�ȉ��̂��̂�����A�����̃|�[�g�ԍ���_���ĕs���N�����s����B���Ƃ��A23�Ԃ�Telnet�ɂ��ẮAID�ƃp�X���[�h�����v����A�Y���̃T�[�o�ɐN���ł��A�t�@�C���̑��삪�ł��Ă��܂����ƂɂȂ�B
21�ԁFFTP 23�ԁFTelnet 25�ԁFSMTP
80�ԁFHTTP 110�ԁFPOP3 443�ԁFHTTPS
�Ȃ��ASHORDAN�́A��ɃX�L�������s���Ă���A���{�̃h���C���������Ƃ���A�قږ����A���̓��e���X�V����Ă���B����������IT�n�AOT�n�Ɋւ�炸�A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����Ă��邷�ׂĂ�CATV���Ǝ҂̃T�[�o�ނ̏�S���E�Ɍ��J����A�Ǝ㐫������A�U���҂̊i�D�̃^�[�Q�b�g�ɂȂ��Ă��܂����A�t�ɂ��̏��Ŏ��Ђ̐Ǝ㐫���m�F���邱�Ƃ��ł���B
4.1.2.4�@ �s���N���U���i�s���A�N�Z�X�j
�U���҂́A�|�[�g�X�L�����œ��肵��IP�A�h���X�ƃ|�[�g�ԍ��̏�����ɁA���L�̕s���N���|�C���g�ɑ��čU�������{����B
�@ �p�X���[�h�s��
�U���҂͈�ʓI�ȃ��O�C�����A�p�X���[�h��Telnet�|�[�g��HTTP�|�[�g�Ȃǂł̕s�����O�C�������݂�B���̃��O�C������p�X���[�h�́A�groot�h��gadmin�h�A�g123456�h�̂悤�ȊȈՂȂ��̂⎖�O�Ɏ擾�������̂������B�܂��A�u���[�g�t�H�[�X�ƌĂ�邷�ׂĂ̕����̑g�ݍ��킹���������̂�A�����邠�肪���ȃp�X���[�h�����ׂĎ��������^�U���Ƃ������U��������B
���̂ق��ɁA���X�g�^�U���ƌĂ�鉽�炩�̎�i�ɂ���ē��肳�ꂽID�ƃp�X���[�h�̑g�ݍ��킹��p���āA���̓��e�ŕ�����̃��O�C�������s������̂�����B�����̋��Ђɂ��ẮA4.1.3�@���ɂďڍׂɉ������B
�A �Ǝ㐫���Ή��@��
���̏ꍇ�̐Ǝ㐫�Ƃ́AOS��\�t�g�E�F�A�v���O�����̋@�\�s���A�܂��͐ݒ��v�~�X�Ȃǂ������Ŕ�������Z�L�����e�B��̌��ׂ̂��Ƃł���B�ʏ픭�����ꂽ�Ǝ㐫�̓\�t�g�E�F�A�A�b�v�f�[�g�ɂ����X���C����邪�A�@��^�p�҂��A�b�v�f�[�g��ӂ�ƍU���Ώۂƌ��Ȃ���A�s���N���U�����鋰�ꂪ����B�L���ȗ�Ƃ��āA2017�N4���ɔ������ꂽ�A�g�����v�����郉���T���E�F�A�uWannaCry�v������i�} 4‑6�Q�Ɓj�B

�} 4‑6�@WannaCry�̐g����v�����
�����T���E�F�A�iRansomware�j�Ƃ́ARansom�i�g����j��Software�i�\�t�g�E�F�A�j��g�ݍ��킹�č��ꂽ���̂ł���A��������ƃp�\�R�����̃f�[�^���Í������Ďg�p�ł��Ȃ���Ԃɂ��āA���̐������������邽�߂̐g�����v�������ʂ�\��������B���̃}���E�F�A�́A���[���ȂǂɓY�t���ꂽ�t�@�C�����N���b�N���Ď��s���邩�A�Ǝ㐫�̈��p�ɂ�芈�����J�n����B��������ƁA�܂���C&C�T�[�o�ڑ����A�s���t�@�C�����_�E�����[�h���Ď��s���A�l�b�g���[�N��ɂ��鑼�̃p�\�R�����������Ă��̐Ǝ㐫�̈��p�ɂ�芴�����g�傳����B�����āA�f�[�^�t�@�C�����Í���������ŁA�g����Ƃ���300�h�����Í��ʉ݁i���z�ʉ݁j�̃r�b�g�R�C���Ŏx�����悤�v������B���̐Ǝ㐫�̈��p�Ƃ́A445�ԃ|�[�g���g���Ă���}�C�N���\�t�g�̃t�@�C�����L�@�\�̐Ǝ㐫��_�������̂ł���B���̃}���E�F�A���^�����e���͂��Ȃ�傫���������߁A�}�C�N���\�t�g�́A���łɃT�|�[�g���I�����Ă���Windows XP�Ȃǂ�OS�ɑ��Ă��C���\�t�g�E�F�A�̒��s���ٗ�̑[�u���s�����قǂł���B�Ȃ��A�g����v���̕��ʂɂ́A3�����o�߂���Ɨv�����z��2�{�ɂȂ�A7���Ԃ��߂��Ă��x����Ȃ���A�Í������ꂽ�t�@�C�����폜����Ƃ�������Ă��邪�A���ۂɐg������x�����ĈÍ�������������邩�ǂ����͕s���ł���B���̃}���E�F�A�ɂ��A���ۂ�CATV���Ǝ҂ɂ���Q���������B
�B WEB�Ǝ㐫�U��
CATV���Ǝ҂̃z�[���y�[�W�p��WEB�T�[�o�́A�ʏ�IT�n�ɐݒu����Ă���B���p�҂̗v���ɂ��A���I�ɉ������邱�Ƃ�A���O�C��������͂��ł��邱�Ƃ�WEB�̓����ł��邪�AWEB�̒��ɂ͂��̓��͑���ɐƎ㐫��������̂�����A�������U���҂��_���Ă���B���̎�̍U���̂ЂƂƂ���SQL�C���W�F�N�V����������A���̐Ǝ㐫���U�������ƁA�l���Ȃǂ̘R�k������s���Ă��܂��B
SQL�C���W�F�N�V�����Ƃ́A�f�[�^�x�[�X�T�[�o�𑀍삷�閽�ߕ��ł���SQL�̐Ǝ㐫�ɑ���U���ł���B�U���҂́A���̐Ǝ㐫������WEB�A�v���P�[�V�����ɑ��āAID��p�X���[�h�̓��̓G���A��SQL�����܂܂�����������͂��āA�Ӑ}�I�Ƀf�[�^�x�[�X�𑀍삵�āA�l���Ȃǂ�ގ悷��B�s���ɓ��肵���f�[�^�́A�_�[�N�E�F�u�ƌĂ�Ă���ŃT�C�g�Ŏ������Ă���B
���̑��AWEB�Ǝ㐫��_�������̂ɁA�N���X�T�C�g�E�X�N���v�e�B���O�iXSS�FCross Site Scripting�j�Ƃ����U��������B����́AHTML�ɂ��e�L�X�g��Java�ɂ��v���O������\��������ꍇ�ɁA���ӂ̂���X�N���v�g�����s���Ă��܂��Ƃ���WEB�̃o�N�𗘗p�������̂ł���AWEB�y�[�W�̉�����Ȃǂ��s���Ă��܂����̂ł���B
4.1.3�@ �T�C�o�[�U���ւ̑�ɂ���
�T�C�o�[�U���ւ̑�ɂ��āA�T�O����@�A�g�D�Ƃ��Ă̑�A�T�v���C�`�F�[���Ƃ��Ă̑���L�ڂ���B
4.1.3.1�@ �T�C�o�[�U���h��̊�{
�T�C�o�[�U�����玩�ЃV�X�e������邽�߂ɂ́A�Ǝ㐫�̌�����U���̌��m���L���ł���B�{�͂ł́ACATV���Ǝ҂ɂ�����T�C�o�[�U���h��̊�{�ɂ��ċL�q����B�������A�����ŋL�q�������i�́A���X�e�b�v�̑���܂ނ��̂����邽�߁A���ӂ��K�v�ł���B
�} 4‑7�ɁA�T�C�o�[�U���h��̊T�v�������B
�} 4‑7�@�T�C�o�[�U���h��̊T�v
����̃T�C�o�[�U����ɂ��āA�ȉ���3�̃X�e�b�v�Œ�`����B
Step1. �Ǝ㐫����
Step2. �N�����m
Step3. �쏜��E����
Step1�ł́A���݃V�X�e���̃����e�i���X����щ��ς��s���\�����������߁A����^�p�̎x��ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��K�v�ł��邱�ƂƓ����ɁA����̉^�p���������Ă�������Ƃ����^�p�̐���z�����Ƃ��̗v�ł���B
Step2�ł́AStep1�ɂĊm�����ꂽ���˔j���ꂽ��̑�Ƃ��č\�z�������̂ŁAFW����ɐݒu���ĕs���ȃg���q�b�N���Ď����A�h��Ȃ����͔�����̂Ȃǂ�����B������U�镑�����m�𒆐S�Ƃ����A���i�V�X�e�����ɗ����g���q�b�N�ƈقȂ���̂����Ĕ���A���Ȃ킿�����I�ɑΉ��ł���V�X�e������\�Ƃ��Ă�������B
Step3�ł́A��Q�ɑ�������̑�ɂ��ċL�q����B��ɂ��ẮA�U�镑�����m�̂悤�Ȏ����h�䂾���łȂ��A���X�̃����e�i���X����l�דI�ɔ������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
�@ �Ǝ㐫�����iStep1�j
�ݒu����Ă���T�[�o�Ȃǂ̐Ǝ㐫���^�p�O��^�p���Ɍ������邽�߁A�} 4‑8�Ɏ����悤�Ɋ�{�I�ɂ́A(1)�|�[�g�X�L�����A(2)�l�b�g���[�N�Ǝ㐫�����A(3)WEB�Ǝ㐫������3�̋@�\���L���ł���B
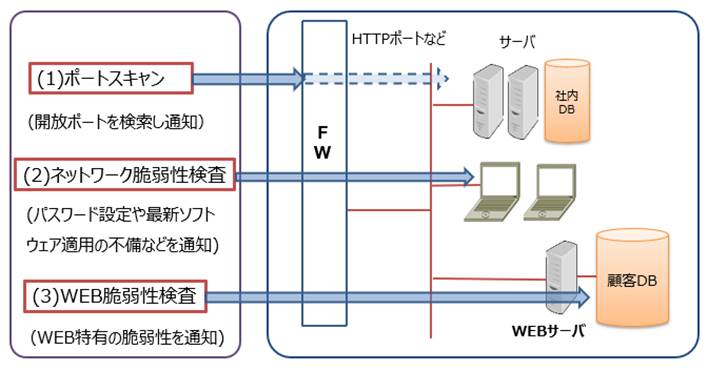
�} 4‑8�@�Ǝ㐫�����@�\
(1)�|�[�g�X�L�����\�t�g
�|�[�g�X�L�����\�t�g�Ƃ́A1��IP�A�h���X���Ƃ�65,536����|�[�g�̊J���̗L�����X�L�������Ē������A�Z�L�����e�B�z�[���Ƃ��Ȃ蓾��|�[�g����������\�t�g�ł���B�|�[�g�X�L����������@�\�ɂ��āA�ʏ��\�I��21�Ԃ�23�ԂȂǂ�1,000���x�̃|�[�g�ԍ��݂̂��������邪�A�ݒ莟��ł��ׂẴ|�[�g�ԍ����������邱�Ƃ��ł���B
(2)�l�b�g���[�N�Ǝ㐫�����\�t�g
�\�t�g�E�F�A�̃p�b�`�K�p�̕s������Ղȃp�X���[�h�ݒ�Ȃǂ��x������@�\������B
(3) WEB�Ǝ㐫�����\�t�g
SQL�C���W�F�N�V�����Ȃǂ�WEB�A�v���P�[�V�����̐Ǝ㐫��f�f���A�x������@�\������B
�����ł́A(1)����(3)�̋@�\����A������CATV���Ǝ҂��̗p���Ă���Nessus�ɂ��ĉ������B
l Nessus
�C���^�[�l�b�g�ڑ��T�[�r�X���S�E���S�}�[�N���i���c��A���S�E���S�}�[�N�擾�ɐ������Ă���\�t�g�ŁA���łɕ�����CATV���Ǝ҂��̗p���Ă���B2019�N6������Nessus Essentials�������Œ���Ă��邪�A�����ł���IP�A�h���X�̏����16�܂łƂȂ��Ă���ȂǁA�ꕔ�@�\�ɐ������݂����Ă���B����A�������Ȃ��L���ł́ANessus Professional�Ƃ������̂Œ���Ă���A���̔N�ԃ��C�Z���X���́A��30���~�i2019�N12�����݁j�ƂȂ��Ă���B�} 4‑9�̃��{�Ŏg�p����Nessus�̃��j���[��ʂ����Ă��킩��悤�ɁA���o�I�ɂ��킩��₷���A�g���₷���\�t�g�ł���B
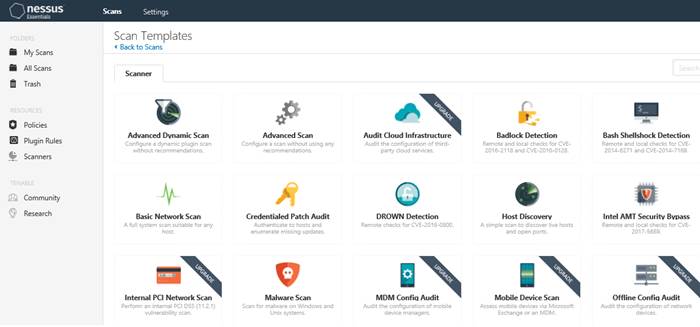
�} 4‑9�@Nessus�̃��j���[���
�A �N�����m�iStep2�j
�T�C�o�[�U������̑Ώ��́ANIST�iNational Institute of Standards and Technology�F�A�����J�����W���Z�p�������j����߂��uNIST SP800-171�v�ɋL�ڂ̃��X�N�Ǘ��t���[�����[�N���Q�l�ɁA��Ƃ��ƂɌ��߂�Ƃ悢�B���̃t���[�����[�N�ł́A����iIdentify�j�A�h��iProtect�j�A���m�iDetect�j�A�Ή��iRespond�j�A�����iRecover�j�ƂȂ��Ă��邪�A�����Ɋւ��ẮA��ʓI�Ƀo�b�N�A�b�v�f�[�^���g���čs����B���������āA�{���ł́A����ȊO�̌��m�ƑΉ��ɂ��āA�l�b�g���[�N����уG���h�|�C���g���ꂼ��ɂ��ďq�ׂ�B
(1)�l�b�g���[�N�̐N�����m
�O������̃|�[�g�X�L�����ɑ��AFW�ŕs�v�ȃ|�[�g�����̂���ʓI�����A���[����Web�ȂNJO���ƒʐM����T�[�o�Ȃǂ́A�֘A�|�[�g�͊J������K�v�����邽�߁A���ꂾ���ł͖h������Ȃ��B���̂��߁AFW�z���Ō�q����IDS�iIntrusion
Detection System�F�s���N�����m�V�X�e���j�ȂǂŌ��m���AIPS�iIntrusion Prevention System�F�s���N���h��V�X�e���j�ȂǂŃT�C�o�[�U���ɑΉ�����B
�T�C�o�[�U���h��̃C���[�W��} 4‑10�Ɏ����B
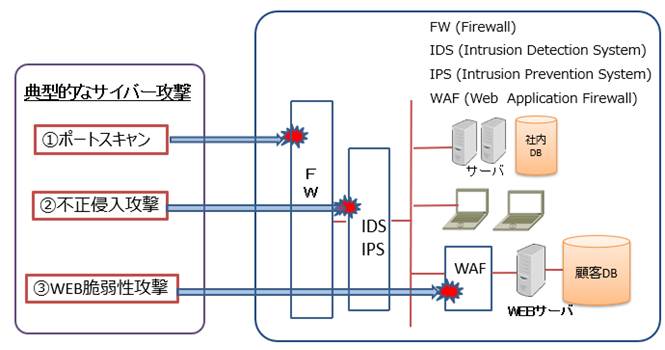
�} 4‑10�@�T�C�o�[�U���h��C���[�W�}
(a) FW
FW�́A�O������̃|�[�g�X�L�����Ȃǂɑ��A�g�p���Ă��Ȃ�IP�A�h���X��|�[�g����ĕs�v�ȃg���q�b�N���Ւf����B
(b) IDS�EIPS
IDS�́A�T�[�o�Ȃǂ̐ݒ�s����p�b�`�K�p�̕s���Ȃǂ̐Ǝ㐫�ɑ��A����łȂ��g���q�b�N�Ȃǂ����m���ăT�C�o�[�U�������m����B���IPS�́A���̌��m���Ă��̒ʐM���~����ȂǍU����h���B
IDS�ɂ́ANIDS�iNetwork-based IDS�F�l�b�g���[�N�^IDS�j�ƁAHIDS�iHost-based IDS�F�z�X�g�^IDS�j������A�Ď�����Ώۂ⓱�����@���قȂ��Ă���BNIDS�́A�����ʂ�l�b�g���[�N��ł̃g���q�b�N���Ď����A���̃p�P�b�g����͂��Ĉُ팟�m����^�C�v�ł���B���HIDS�́A�T�[�o��p�\�R���Ȃǂ̃z�X�g�ɏ풓�����ĕs���N�������m����^�C�v�̂��߁A�Ď��Ώۂ̃z�X�g���ꂼ��Ɍ��m����\�t�g���C���X�g�[������K�v������B���̂��߁ANIDS�̕����������₷���B
IDS��IPS���s���N�������m����d�g�݂́A�s�����o�^�i�~�X���[�X���o�FMisuse Detection�j�ƈُ팟�o�^�i�A�m�}�����o�FAnomaly Detection�j�ɕ��ނ����B�s�����o�^�́A���炩���߃u���b�N���X�g�ɓo�^���ꂽ�V�O�l�`���ƌĂ��p�^�[����[���ƃ}�b�`���O�����ĐN�����o���s���d�g�݂ł���B�܂�A���m�̎�����g�����N���������o�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����A�ʏ�ƈقȂ�g���q�b�N�����o����ُ팟�o�^�ł́A����łȂ��ꍇ���ُ�Ɣ��f���邽�߁A���m�̎�����g�����N���������邱�Ƃ��ł���B���̎d�g�݂́A���O�C�������A�l�b�g���[�N�g���q�b�N�A�g�p����R�}���h�╶���`���Ȃǂ̏����ɑ��āA���펞��臒l��ݒ肵�A�ݒ�ƈقȂ�ꍇ�Ɉُ�Ɣ��f����̂����A����痼���̌��o��@���̗p�������̂����݂���B���ۂ�NIDS�ł́A���K�̓I�t�B�X�p��1Gbps���x�̃g���q�b�N�ɑΉ��������̂���A�ʐM���Ǝ҂ł��g�p�\��100Gbps������̂܂ŁA��p���i�i�I���v���~�X�j�̎�ނ��L�x�ŁA���ɂ̓N���E�h�Œ��Ă�����Ǝ҂����݂��Ă���B�܂��A�p�\�R����T�[�o�Ƀ\�t�g�E�F�A���C���X�g�[������IDS������������@���\�ł���B
(c) WAF�iWeb Application Firewall�j
WAF�̓z�[���y�[�W�A�N�Z�X�ւ̒ʐM���������A�E�F�u�A�v���P�[�V�����ւ̍U����h�䂷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���A4.1.2.4�@�߂ʼn������Web���L�̐Ǝ㐫���U���҂ɓ˂���āA�l���Ȃǂ��܂܂��DB�𑀍삷�邱�Ƃɑ��AWeb�T�[�o�̎�O�Ŗh��ł���BWAF��FW�ł͂�����̂́A�ʐM�ɂ����鑗�M�����Ƒ��M����iIP�A�h���X��|�[�g�ԍ��j����ɃA�N�Z�X�𐧌�����FW�Ƃ͋@�\���قȂ��Ă���B�܂��AFW�͊O�����J����K�v�̂Ȃ��ʐM��ւ̃A�N�Z�X�𐧌����A�s���ȃA�N�Z�X��h�~����̂ɑ��AWAF�́AFW�ł͐������邱�Ƃ��ł��Ȃ�Web�A�v���P�[�V�����ւ̒ʐM���e�����Đ��䂷����̂ł���B��̓I�ɂ��}
4‑11�@WAF�̓���T�v
�o�T�FIPA�wWeb Application Firewall�ǖ{ ������2�Łx�����}
4‑11�Ɏ����悤�ɁA�ʏ�̃z�[���y�[�W�{���ł͐��������Ȃ����̂́A�E�F�u�A�v���P�[�V�����̒ʐM���e�ɊO������f�[�^�x�[�X��s���ɑ��삷��悤�ȒʐM�p�^�[�����܂܂�Ă����ꍇ�A���̒ʐM���Ւf����B
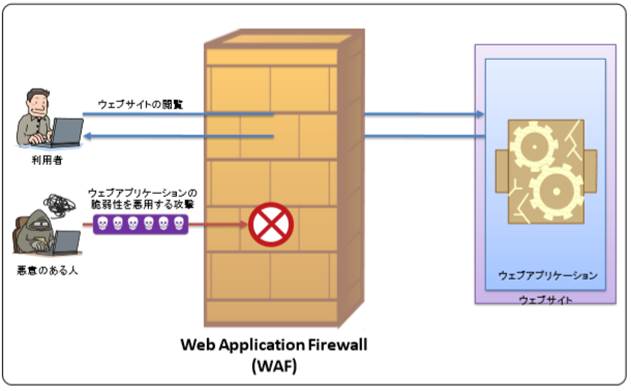
�} 4‑11�@WAF�̓���T�v
�o�T�FIPA�wWeb
Application Firewall�ǖ{ ������2�Łx�����p
WAF�ɂ��Ă�IDS�EIPS�Ɠ��l�A�I���v���~�X�̐�p�@���\�t�g�E�F�A���C���X�g�[�������T�[�o�𗘗p������̂ɉ����A�N���E�h�Ŏ���������̂����݂���B
(d) �����Ǘ�
�Z�L�����e�B�x���_�́AIDS��IPS�AWAF�Ȃǂ�g�ݍ��킹��UTM�iUnified Threat Management�F�������ЊǗ��j�Ƃ��đ����I�ȃZ�L�����e�B�\�����[�V��������Ă���ꍇ������B�����I�ȃZ�L�����e�B�\�����[�V�����Ƃ��ẮANGFW�iNext Generation Firewall�F������t�@�C�A�E�H�[���j�����݂���BUTM��NGFW�̗�������舵���Ă�����Ǝ҂́A��K�͂̃G���^�[�v���C�Y�����ɁuNGFW�v�A������ƌ����ɂ́uUTM�v��̔����Ă���B���̃x���^�̑�K�͂̃G���^�[�v���C�Y�ɂ��ẮA�����_�ł͐�Gbps�ȏ�̃g���q�b�N���������̂��w���Ă���B
�܂��AUTM�Ǝ������̂Ƃ��āASIEM�iSecurity Information and Event Management�F�Z�L�����e�B���C�x���g�Ǘ��j�ƌĂ�Ă���V�X�e��������B�Z�L�����e�B�Ɋ֘A�������O���W�Ƃ����@�\�ł́AUTM��SIEM�����l�ł��邪�AUTM�̓��O���W�߁A�����̃��W�b�N�ŃZ�L�����e�B�ᔽ�⋺�Ђɑ��ău���b�L���O���s���B���SIEM�̓��O���番�͂��s���A�C���V�f���g�\���̔����⎖�̔�����̒����Ȃǂ̎g�p���ړI�ł����āA�u���b�L���O�͍s��Ȃ��B
(2)�G���h�|�C���g�̐N�����m
(a)
NGAV
����܂ł̃p�\�R���Ȃǂ̃G���h�|�C���g�ɑ���Z�L�����e�B��Ƃ��āAAV�iAnti-Virus�F�A���`�E�C���X�j�\�t�g�E�F�A����ʓI���������A�ߔN�ANGAV�iNext Generation Anti-Virus�F������A���`�E�C���X�j�\�t�g�E�F�A�Ƃ������̂��o�ꂵ�Ă���BAV��NGAV�̈Ⴂ�ɂ��ẮAAV�̃}���E�F�A���m�������p�^�[���}�b�`���O�i�V�O�l�`�������Ƃ��Ă��j�ōs����̂ɑ��ANGAV�́A�ÓI�⓮�I�ȃq���[���X�e�B�b�N���m��l���m�\�iAI�j�A�@�B�w�K�Ƃ������V�����Z�p��p���āA�}���E�F�A�Ƌ^�킵�����̂����m���ău���b�N���邽�߁A���m�̃}���E�F�A�ɑ��Ă��Ή����\�ł���B
(b) EDR�iEndpoint Detection and Response�j
�@EDR��ƁA�u�G���h�|�C���g�̌��m�ƑΉ��v�ł���A�G���h�|�C���g�ɐN�������}���E�F�A��v���Ɍ��m�A�����A�����Ċg�U�h�~���邱�Ƃ�ړI�ɂ����\�t�g�E�F�A�̑��̂ł���B������}���E�F�A�Ɋ������Ă��܂����ꍇ�ł���Q���ŏ����ɐH���~�߂邽�߁ANGAV�ƈꏏ�ɉ^�p���Ă����Ƃ��������Ă���BEDR�́A�p�\�R���ȂǂɐN�����Ă��܂����}���E�F�A�̑Ώ�������ł���AV��NGAV�̎�_���J�o�[���A�}���E�F�A�N����̉e�����ŏ����ɐH���~�߁A�Ώۋ@��̐藣���Ȃǂ�v���ɍs���A��Q�g���h�~����B����A�N���h�~�@�\���Ȃ����߁A�ʏ��AV��NGAV�ƕ��p���Ă���B���̑��AEDR�̓����Ƃ��ẮA�G���h�|�C���g���̏������I�Ɏ��W���Ď����s���Ă��邽�߁A�}���E�F�A�̐N���o�H�̓���A�����Nj��̎��ԒZ�k���\�ł���A�Ĕ��h�~�ɂ��L���ł���B������������ɂ�����A�G���h�|�C���g�̏��͂���X�L�����K�v�Ȃ��߁ASOC�i�Z�L�����e�B�I�y���[�V�����Z���^�[�j�̉^�p�Ƃ̃Z�b�g�ōs���̂��]�܂����B
(c) MDR�iManaged Detection and Response�j
�@EDR���}�l�[�W�h�T�[�r�X�Œ���MDR�Ƃ����T�[�r�X������BMDR�́A�O���̐��X�L�������Z�L�����e�B�l�ނ��W�߂�SOC��EDR�̉^�p���ϑ�����T�[�r�X�ŁA�Z�L�����e�B�l�ނ̊m�ۂ�^�p�Ǘ����ȗ͉��ł���B
�@MDR�ɂ́A�C���V�f���g�̏����v���Z�X��S���g�[�^���T�|�[�g�T�[�r�X�ƂȂ�t���}�l�[�W�h�^�A���Ќ��m�ƒʒm����ꎟ�I�ȑΏ��܂ł̈ꕔ�̃C���V�f���g�Ή���S���Z�~�}�l�[�W�h�^�̓��ނ�����BSOC��ێ����Ă��Ȃ�������CATV���Ǝ҂�EDR������ꍇ�ɂ́A�@���p�ȊO���ׂĎ��Ђʼn^�p����̂��AMDR��p���ĊO���ɉ^�p���ϑ�����̂��ŃR�X�g���ς���Ă��邪�A�T�C�o�[�Z�L�����e�B���̂��߂ɂ�EDR�̓����𐄏�����B
�B �쏜��iStep3�j
Step2�ɂđ�\�����Z�L�����e�B��ɂ́A���Ђɑ��Č��m�E����܂ōs�����A�h��܂őΉ��ł��Ȃ����̂�����B������Ή����Ԃɍ���Ȃ��A�������͔�Q���������Ă��܂����ۂ̑Ώ����@���ȉ��ɋL���B
l ��Q���^����[���̐藣��
���ꂽ�ΏۂƂȂ�[������肵�A�X�^���h�A�����������Ƃ��K�v�ƂȂ�B����ɂ��A�[������[���ւ̊������A��Q���ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł���B
l ��Q�̊m�肨��ы��L
��Q��c���E�m�肵�A�Z�L�����e�B�x���_�Ƌ��L���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
�Ώ��\�t�g�Ɋւ��ẮA�O���ɂĉ�������ʂ�AIPS�EWAF����������B
IPS�Ɋւ��ẮAIDS�ƃZ�b�g�ŗ��p���邱�Ƃ����邪�A�����ݔ��Ƃ̌��ˍ������P�̂ŗ��p���邱�Ƃ�����ق��AUTM���̃V�X�e���ɂċ@�\�����ꍇ�����邽�߁A�����ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B
WAF�Ɋւ��ẮAWeb�ɓ��������`��IDS�EIPS�Ƃ��ĔF������Ă���B�@�\���ގ����Ă���AWeb�֘A�̃g���q�b�N���Ď����s���Ȃ��̂������h�䂷��@�\�����B
4.1.3.2�@ �F�،n�s���A�N�Z�X�ւ̑�
Step3�ŏЉ���p�X���[�h�s���ɑ���U���ւ̑�Ƃ��āA���ƎҁE���[�U�[�o���ɑ��钍�ӊ��N���K�v�ł���B
���Ǝ҂̑Ή��Ƃ��ẮAIDS�EIPS�AWAF��p�����ӂ�܂����m�ɂ���Ĉُ�ȃA�N�Z�X�̌��m����ёΉ�����������B���킹�āA���O�C����K�v�Ƃ���T�[�r�X�ւ̑Ή��Ƃ��ē�i�K�F�i��v�f�F�j��O�C���A���[�g�A�A�J�E���g���b�N�V�X�e���̓������͂��߁AIP�A�h���X�ɑ���A�N�Z�X�Ւf�����Ȃǂ���������B
��i�K�F�ɂ��ẮAID�ƃp�X���[�h����́E���������i��i�K�j��ɁA�ʂ̒[���ɑ����Ă��镶�������͂�����́A���邢�͎w��Ȃǂ̐��̏������߂���̂�����B�����̑Ή��ɂ��A���X�g�^�U���Ȃǂɂ��ID�ƃp�X���[�h�̕s�����p�ɑ���\�ɂȂ�Ƃ�����B���̂ق��ɂ��A����ID���畡���O�C���Ɏ��s�����ꍇ�ɊY���A�J�E���g�����b�N����A�J�E���g���b�N�V�X�e���A�����IP�A�h���X���瑽�ʂ̃��O�C�����s���������ꍇ�ɂ���IP�A�h���X����̃A�N�Z�X���Ւf����@�\���s���A�N�Z�X��Ƃ��Ă�������B�����@�\�̓����́A�u���[�g�t�H�[�X�U���A�܂��̓��o�[�X�u���[�g�t�H�[�X�U���ɑ��Ĕ��ɗL���ł���Ƃ�����B�����̋@�\�́AWeb�t�H�[���ւ̖��ߍ��݂�Ǘ����ϑ����Ă���ꍇ�A�_��I�v�V�����Ƃ��ė��p�\�Ȃ��̂Ȃǂ�����B
���[�U�ɑ��Ă����ӊ��N���d�v�ł���B�s���A�N�Z�X�ɂ���ē���ID�ƃp�X���[�h���A����Web�T�[�r�X�ւ̃��O�C����o�^�Ɉ��p����鋰�ꂪ����B���ۂɂ��̕��@�ŕs���ۋ����s��ꂽ���������B���q�l�̐M��������̂��߁A���Ǝ҂���旧���Ē��ӂ𑣂��Ă������Ƃ��K�v�Ƃ����B
���Ǝ҂���[�����Ă�����\�I�Ȏ��ۂƂ��āAID����уp�X���[�h�̎g���܂킵�Ɋւ��钍�ӊ��N�A�K�ȃp�X���[�h�̐ݒ董�i����������B
ID����уp�X���[�h�̎g���܂킵�h�~�Ɋւ��ẮA��q�̃��X�g�^�U�����͂��߂Ƃ���s���ȓǂݎ��̔�Q���y�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
![]() �K�ȃp�X���[�h�̐ݒ董�i�ɂ��ẮA���ݐݒ肳��Ă���p�X���[�h�̎�ނⒷ���i�����j�G�����邱�ƂŁA��O�҂ɂ���͂����ɂ�������˂炢������B�G���h���[�U�ɂ���ẮA�����l�̂܂܃A�J�E���g���^�p����ꍇ��A�����݂̂̃P�[�X���������Ȃ��B�ύX�����p�X���[�h�̕��j�Ƃ��ẮA�����l��P���ȕ�����ȂǓ��肪�e�ՂȂ��͔̂����A�p�啶���E�������E�L��������������10���ȏ�̕�����ō\�����邱�Ƃ��]�܂����B�Ȃ��AIPA�̕��ɂ��ƁA�p�����̑g�ݍ��킹�i62�����j�ʼn�lj\�Ȏ��Ԃ́A4���̏ꍇ����2���ł���̂ɑ��A6���̏ꍇ�ɂ͖�5���A8���̏ꍇ�Ŗ�50�N�A������10���̏ꍇ�ɂ͖�20���N�ƂȂ��Ă���B
�K�ȃp�X���[�h�̐ݒ董�i�ɂ��ẮA���ݐݒ肳��Ă���p�X���[�h�̎�ނⒷ���i�����j�G�����邱�ƂŁA��O�҂ɂ���͂����ɂ�������˂炢������B�G���h���[�U�ɂ���ẮA�����l�̂܂܃A�J�E���g���^�p����ꍇ��A�����݂̂̃P�[�X���������Ȃ��B�ύX�����p�X���[�h�̕��j�Ƃ��ẮA�����l��P���ȕ�����ȂǓ��肪�e�ՂȂ��͔̂����A�p�啶���E�������E�L��������������10���ȏ�̕�����ō\�����邱�Ƃ��]�܂����B�Ȃ��AIPA�̕��ɂ��ƁA�p�����̑g�ݍ��킹�i62�����j�ʼn�lj\�Ȏ��Ԃ́A4���̏ꍇ����2���ł���̂ɑ��A6���̏ꍇ�ɂ͖�5���A8���̏ꍇ�Ŗ�50�N�A������10���̏ꍇ�ɂ͖�20���N�ƂȂ��Ă���B
4.1.3.3�@ �Z�L�����e�B�h���@�̂܂Ƃ߂ƈ��
����܂ł̓��e�܂��āA�Z�L�����e�B��̈���} 4‑12�Ɏ����B
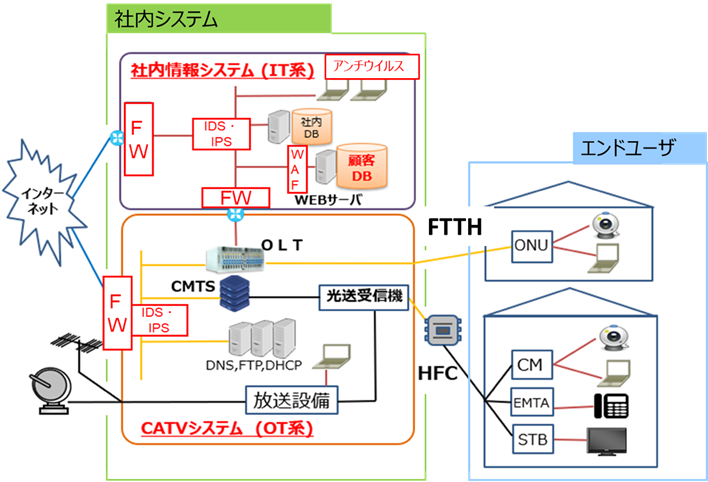
�} 4‑12�@�Z�L�����e�B����
�} 4‑12�́A�e�@�\�̓��������āACATV���Ǝ҂ɓ��Ă͂߂��`�ł̖h��ݔ��̕~�ݗ�������Ă���B
�ݔ����G���h���[�U�ƎГ��V�X�e���ɁA���p�V�X�e���iOT�n�j�ƎГ����V�X�e���iIT�j�n�ɂ��ꂼ�ꕪ�����ĉ������B
(1) �C���^�[�l�b�g�AIT�n�AOT�n�Ƃ̐ڑ��_�ɂ��ĕs�v�ȃA�N�Z�X���Ւf���邽�߁AFW�̐ݒu���L���ł���B
(2) FW����̃g���q�b�N�Ď��ɂ���FW�̒ʉ߂��Ă��܂����s���g���q�b�N��U�������o�E�h�䂷�邽�߂ɁA�����IDS�EIPS��ݒu���邱�Ƃ𐄏�����B
(3) Web�A�v���EWeb�T�C�g�̊Ď��ɂ���
(1)(2)�̑���Ƃ邱�Ƃɂ���Ėh���@�͊m������Ă������A���Г��V�X�e���ɋ߂�Web�T�C�g���ӂ̑���Ƃ邱�ƂŖh��͂���ɋ��łȂ��̂ƂȂ�BWeb�A�v�����ӂɑ��āAWAF�����邱�Ƃ𐄏�����B
�����ɂ��āA�Z�L�����e�B��Ƃ��Ċm�������ݔ���V�X�e���A�����Ėh���@�́A����I�ȃ����e�i���X�ɂ���āA����Ɍ��ʂ�����B�Z�L�����e�B�S���҂ɂ����ẮA�@��ݒu����уV�X�e���̕~�݂����ɗ��炸�A�Z�L�����e�B�̍ŐV���������Ȃ������I�ȃ����e�i���X����ю{�݂̍œK����}��K�v������B
�@ �Z�L�����e�B��ɂ�����R�X�g����ѓ�Փx
�\ 4‑4�ɃZ�L�����e�B��ɂ������R�X�g�ɂ��ďЉ��B
�Z�L�����e�B��ɂ�����R�X�g����ѓ�Փx�͒萫�I�ł���A���ۂ̎��ƎҋK�͂ɍ��킹�đ傫���ϓ����邽�߁A���ۂɓ�������ۂ͒��ӂ��K�v�ł���B
�\ 4‑4�@�Z�L�����e�B��ɂ�����R�X�g����ѓ�Փx
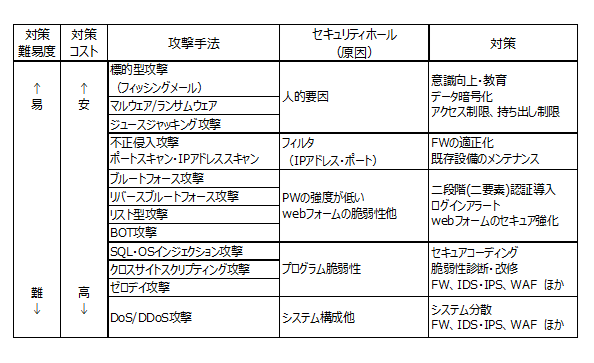
�A �Љ�ƃT�C�o�[���Ђ̕ω�
����܂ŏq�ׂĂ����Z�L�����e�B��͋��E�^�h��Ƃ����A��Y��Ɩ����pPC�����Аݔ��⎩�Ѓl�b�g���[�N�Ȃǂ̕����ꂽ���ɂ��邱�Ƃ�O��ɂ����h���ł���B
�������A�Љ�̕ω��Ƃ���ɔ����T�C�o�[���Ђ̕ω��ɂ���ăZ�L�����e�B��ɂ��V���ȊT�O����ݏo����Ă���B
�P�[�u�����Ǝ҂ɂ����Ă��A�T�[�r�X�i���̌�����������ړI�ɁA�Ɩ��ɗp����@��ɃX�}�[�g�t�H����^�u���b�g���͂��߂Ƃ��郂�o�C���[���̗��p��A������ʐM�@��̃I���v������N���E�h�ւ̈ڍs���s������B�܂��A�������̂��߂ɋƖ��ϑ��̃p�[�g�i�[�ƃf�[�^��V�X�e����A�g���邱�Ƃ�����B�} 4‑12�̖h��ݔ��̕~�ݗ�����Ƃɍl�����P�[�u�����Ǝ҂̎��ƕω��̃C���[�W���} 4‑13�Ɏ����B
�} 4‑13���̕ω��́A�Љ�S�̂ŋN�����Ă�����̂ł���B����܂łƏ��قȂ�A�Ɩ��ɗ��p����@��͑��l�����A��Y��Ɩ��p�@�킪�ЊO�Ɏ����o�����悤�ɂȂ����B2020�N�ɂ́A�V�^�R���i�E�B���X�̗��s���A�e�����[�N�����i����A�V���ȓ������Ƃ��Ē蒅������B�����āA�T�C�o�[�U���͂��̕ω��ɍ��킹�Đi�����A�e�����[�N�̂悤�ȃj���[�m�[�}���ȓ�������_���U����A�T�v���C�`�F�[���̐Ǝ㐫��˂��U���Ȃǂ��������Ă����B�܂��A���̎�����I�������A�N����h�����Ƃ⌟�m���邱�Ƃ�����Ȃ��Ă���B
���̂悤�ȏ��̃Z�L�����e�B��ɂ����Ă��A�V���ȃZ�L�����e�B�̊T�O��d�g�݂��K�v�ƂȂ����B
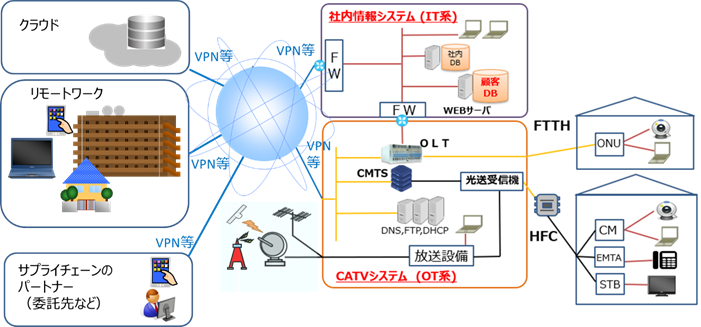
�} 4‑13�@�P�[�u�����Ǝ҂̎��ƕω��̃C���[�W
�B �[���g���X�g�Z�L�����e�B
�[���g���X�g�Ƃ́A�u�����M�p���Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł���A�} 4‑14�Ɏ����Ƃ���Г��E�ЊO���킸�A�l�b�g���[�N��̃g���q�b�N�̈��M�p�����ɃZ�L�����e�B���g�ފT�O�ł���B
�[���g���X�g�Z�L�����e�B�ł́A���ׂ���Y�͋��E�̓��O�ɂ���A���ׂ���Y�ɂ͋��E�̓��O����A�N�Z�X����Ă��āA���Ђ͋��E�����ɂ��ړ����Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���ׂĂ̏�Y�ւ̃A�N�Z�X��M�������Ɋm�F���邱�Ƃ����߂�B
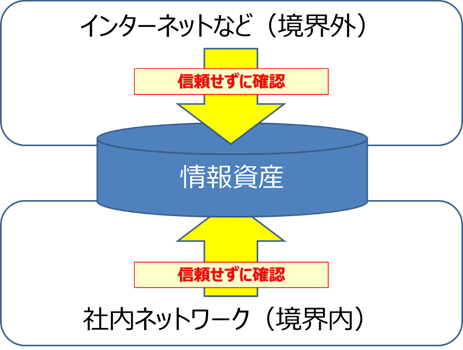
�} 4‑14�@�[���g���X�g�Z�L�����e�B�̊T�O
��ɏq�ׂ��悤�ɁA�]���^�̖h���@�͋��E���h��ɕ��ނ���A������Â��h���@�Ƃ��Ď�舵��ꂪ���ł���B���ɁA�Z�L�����e�B�x���_�̓W�J�ł́A���E���h��̓[���g���X�g�̑Ɛ������݂Ƃ��ĕ\������A�Z�L�����e�B��DX���ɔ������E���h�䂩��̒E�p�𐄏�������̂������B
�C SASE�iSecure Access Service Edge�j
SASE�Ƃ́A�ăK�[�g�i�[�Ђ�2019�N�ɒ��A��Ƃ̋@��^�p�`�Ԃ̕ω��ɑΉ�����`�œo�ꂵ���A�V���ȃZ�L�����e�B�t���[�����[�N�̍l�����ł���B
�]���̃Z�L�����e�B��̌X���́A�O�q�̂Ƃ����ƃl�b�g���[�N�͎Г��̐�p������Ԃŏ����������̂������������A�N���E�h��Ԃ�p�����T�[�r�X�������悤�ɂȂ������Ƃɂ��A�N���E�h���p�ɓK�����Z�L�����e�B��̍\�z���ۑ�ƂȂ����B
�܂��A�e�����[�N�Ȃǂ̐V���ȋΖ��`�ԂȂǂɑΉ������Z�L�����e�B������X�Ɠ������Ă������Ƃ́A�V�X�e���̕��G���ɔ����Ǘ��ҕ��ׂ̑����A�����̒ቺ��闘�p��UX�̒ቺ�����łȂ��A�R�X�g�̑�����ʐM���ׂ��������Ă���B
�����̉ۑ�ɑ��āA�~���ȃl�b�g���[�N�@�\�Ɛڑ��̈��S�����m�ۂ���l�b�g���[�N�Z�L�����e�B����̃t���[�����[�N�ɂ܂Ƃ߂Ē��邱�ƂőΉ����悤�Ƃ���̂�SASE�ł���BSASE�̖ړI�́A�N���E�h����[�g���[�N�ȂNJ�Ƃ̋@��^�p�`�Ԃ̕ω��ɔ����Ǘ��̔����R���h�~����ƂƂ��ɁA�ω��ɔ����Ǘ��R�X�g���̗}���A���p�҂̗����̌���A�N���E�h�̗����p��e�����[�N�̓����ɂ�萶����l�b�g���[�N���p�̕��ׂɑ���������ł���B
SASE�̊T�v��} 4‑15�Ɏ����B
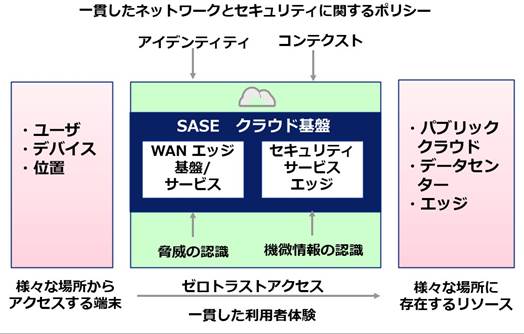
�} 4‑15�@SASE�̊T�v
�o�T�FNeil MacDonald, Nat Smith�F2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence
SASE�ł́ASD-WAN�iSoftware Defined-Wide Area Network�j����ՂƂ��ēW�J����A������SD-WAN�ɂč\�������Z�L���A�ȒʐM��ՁA����уN���E�h���ɂ�����Z�L�����e�B�G�b�W�ɂ����āA��苭�łȃZ�L�����e�B������{������̂ƂȂ�B
�D SOC�^�p�̍��x��
�T�C�o�[���Ђ����x�����҈Ђ�U�邤�ɑ���Z�L�����e�B��Ƃ��ẮA�V���ȐN�����m�̎d�g�݂���邱�Ƃ�����̑Ή������x�����邱�Ƃ�i�߂Ă���B
���̈���ŁA�V�X�e���̕��G����Z�L�����e�B�Ɩ��̔ώG���ɑ��āA�������I�ȉ^�p���\�z���邱�Ƃ����߂��Ă���B
���̍��x�ȑ�ь����I�ȉ^�p�ɂ��Ă̊T�O�Ƃ��āA�K�[�g�i�[�Ђ�SOC Visibility Triad�iSecurity Operation Center Visibility Triad�FSOC�^�p�̍��x���j����Ă���B
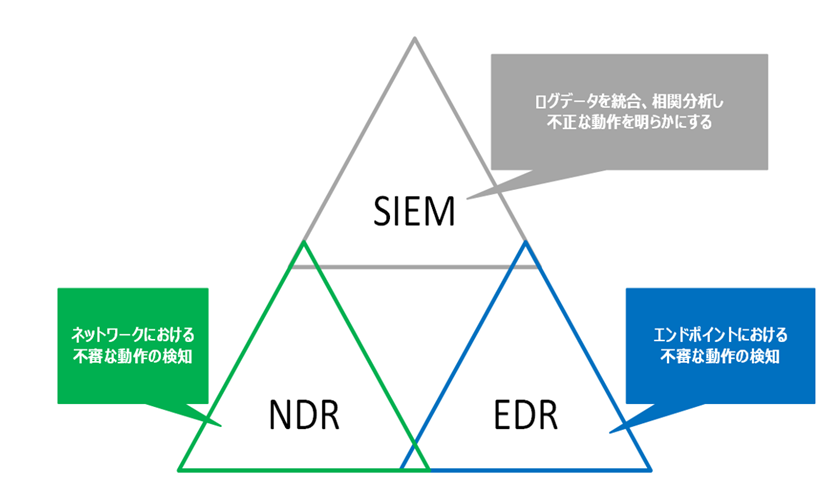
�} 4‑16�@ SOC Visibility
SOC Visibility�́A�{�߃l�b�g���[�N�̐N�����m�̍��ŏq�ׂ�SIEM�����EDR�Ƀl�b�g���[�N�ł̕s�R�ȓ�������m����NDR�iNetwork Detection and Response�j��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA��Ƃւ̃T�C�o�[�U����s���A�N�Z�X���������A���m�����s�����Ƃł���B����ɂ��ASOC��NDR��EDR�Ō��m�����A���[�g��SIEM�ő��֕��͂��邱�ƂŁA�����ɑΉ����K�v�ȃA���[�g�݂̂����Ή����邱�Ƃ��ł��A��ƕ��ׂ��y�����邱�Ƃ��ł���BNDR���͂��߁ASOC�̍��x���Ɍq����V���ȑ�ɂ��Ĉȉ��A�������B
�E NDR
�T�C�o�[���Ђ̍��x���ɔ����A�]���̋��E���h��ł͋��Ђ̐N����h�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B���̂��Ƃ���A���ЂɐN������邱�Ƃ�O��ɂ����Z�L�����e�B�Ή����K�v�ƂȂ��Ă����B���̈��NDR�ł���B
NDR�́A�l�b�g���[�N��̂��܂��܂ȏ��i���O�j�����W�E���͂��A�s�R�ȒʐM���s���Ă��Ȃ��������m������̂ł���B
���Ƃ��A�ŋ߂̃T�C�o�[�U���ł́A�N�������}���E�F�A��C&C�T�[�o�ƒʐM���Ƃ�A�d�v���փA�N�Z�X���A�O���Ɏ����o�����߂̑�e�ʃf�[�^�𑗐M����B
���̂悤�ȎГ��l�b�g���[�N�̒��A���邢�͎ЊO�֔��M����Ă���s�R�ȒʐM���Ȃ�����NDR�Ń��A���^�C���ɊĎ��E���m���邱�ƂŁA��Q��h�����Ƃ��ł���B�܂��A�s�R�ȒʐM�����̏�őj�~���邱�Ƃ�T�C�o�[�U���҂ɂ�郍�O�̉������폜������O�̐��������O���擾���邱�ƂȂǂ��ł���B
�} 4‑17��NDR���J�o�[����̈�������B
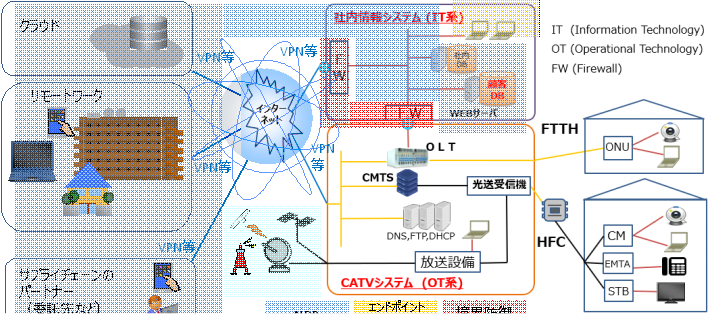
�} 4‑17�@NDR���J�o�[����̈�
�} 4‑17�ł́ACATV�V�X�e����NDR�̈�Ƃ��Ă��Ȃ����A������IP�����i��ł��邱�Ƃ��AOT�n���Z�L�����e�B����������邽�߂�NDR�̈�Ƃ��Ă������Ƃ�����̌����ۑ�ł���B
�F SOAR�iSecurity Orchestration, Automation and Response�j
���ЊǗ��ɂ����ẮA����܂łɉ�����Ă���IPS��IDS�ASIEM�AEDR�Ȃǂ̌��m�c�[���𗘗p���đ�ʂɂ�����̒�����������m����B
���̌��m�̌�ɂ́A���̖�肪���ۂ̋��Ђł���̂��m�F��i�߂Ă����A�ɂ���Ă̓C���V�f���g�ւ̑Ή����K�v�ƂȂ�B
�������A�e���m�c�[�����甭�ꂽ�A���[�g���e����ǁE�������A�ǂ̂悤�ȏ��N�����Ă���̂��́E���f�����āA�Ή���i�߂�ɂ��Ă���Ɨʂ������A�܂��Z�L�����e�B�X�L�������l�ނ������K�v�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ȉۑ����������\�����[�V������SOAR�ł���BSOAR�́A�č��𒆐S�ɔ��W�������Ă���\�����[�V�����ŁA�Z�L�����e�B�^�p�̎����������������������Z�p�ł���A�g�D���̊e��Z�L�����e�B�@�킨��ъO���T�[�r�X������W���ꂽ���Џ�����̃v���b�g�t�H�[���ɓ�������B��ʓI�ɂ͐} 4‑18�̂悤�ȎO�v�f�ō\�������B
�} 4‑18�@SOAR�̍\���v�f
SOAR�ł́A�������z�肳���C���V�f���g�̑Ή��菇���u�v���C�u�b�N�v�ƌĂ��f�W�^�����[�N�t���[�ɑg�ݍ���ł����B�z�肳�ꂽ�C���V�f���g�����������ۂ́A�v���C�u�b�N�ɑg�ݍ��܂ꂽ�菇�őΏ����Ă����B���̂��Ƃ���A�蓮�ł̍�Ɨʂ͌���A�Ή����x���オ��B�܂��A��x���A���[�g��[�z���̏��������Ɏ��Ԃ��₷���Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�Z�L�����e�B�S���҂͓�Փx�E�d�v�x�̍����Z�L�����e�B�C���V�f���g�ւ̑Ή��ɏW�����邱�Ƃ��ł���B
�G IAM�iIdentity and Access Management�j
�P�[�u�����Ǝ҂́A�Ɩ���������T�[�r�X����̂��߂ɂ��܂��܂ȎГ��A�v���P�[�V������N���E�h�T�[�r�X�𗘗p����@������Ă��Ă���B�܂��A�ڋq��Web�T�[�r�X����Ă���P�[�u�����Ǝ҂́A���̃T�[�r�X�𗘗p���邽�߂�ID���ڋq�ɔ��s���Ă���B
���̈��S�ȗ��p�𑣐i�����ՂƂ��āA���p����V�X�e�����Ƃɐݒ肳�ꂽ������ID���Ǘ����A���킹�ăA�N�Z�X�����̓K�ȊǗ����s�����߂̎d�g�݂�IAM�ł���B
IAM�̒��ŁA����ҁiConsumer�j�A�܂�ڋq��ID�ɓ�������IAM�̂��Ƃ��uCIAM�v�A��Ɠ��̏]�ƈ�ID���Ǘ�����IAM��Enterprise�̓�������t���āuEIAM�v�Ƃ��ꂼ��Ă�Ă���B
�\ 4‑5��CIAM��EIAM�̔�r�������B
�\ 4‑5�@CIAM��EIAM�̔�r
|
|
CIAM |
EIAM |
|
ID�Ǘ� |
�ڋq |
�]�ƈ��E�p�[�g�i�[��� |
|
ID�o�^ |
�Z���t�T�[�r�X |
�l��DB��[�N�t���[ |
|
�����F�V�X�e�� |
�O���T�[�r�X�܂� |
���V�X�e�� |
|
ID���� |
��\���f�[�^���܂݊g���\ |
�\�����E�Œ艻 |
|
�����Ǘ� |
�ڋq�̓��ӂɊ�Â� |
�K�w������/���F���[�N�t���[ |
|
�Z�L�����e�B�E���� |
�Z�L�����e�B������ |
�Z�L�����e�B������ |
CIAM�́A�ڋq����Web�T�[�r�X�̌ڋqID���E�Ǘ�����ۂɗp������B���EIAM�́A�Г��A�v���P�[�V������PC�Ƀ��O�C������ۂ̃��[�UID���ꌳ�I�ɊǗ�������̂ŁA�ŋ߂ł̓[���g���X�g�Ή��̃\�����[�V�������o�ꂵ�Ă���B
�H XDR�iExtended Detection and Response�j
�ߔN�A�Z�L�����e�B�x���_���͂����Ă���̂�XDR�ł���B
�K�[�g�i�[�Ђɂ��XDR�̒�`�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
|
�����̃Z�L�����e�B���i���l�C�e�B�u�ɓ������A���C�Z���X���ꂽ���ׂẴR���|�[�l���g�ꂵ����ѐ��̂���Z�L�����e�B�^�p�V�X�e������������A�Z�L�����e�B���Ђ̌��m����уC���V�f���g�Ή��c�[���ł���B |
�} 4‑19�ɃK�[�g�i�[�Ђɂ��XDR�̒�`��}�����������̂������B
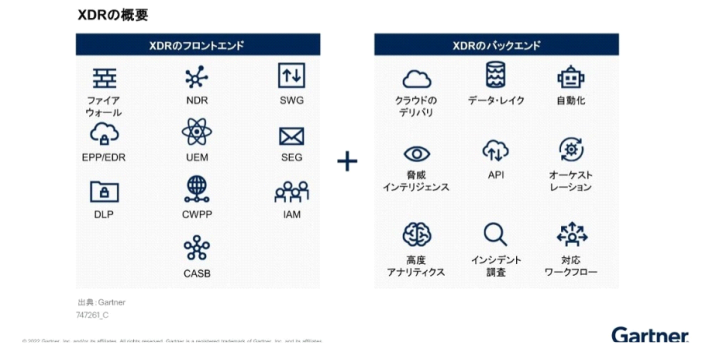
�} 4‑19�@�K�[�g�i�[�Ђɂ��XDR�̒�`
�o�T�FNeil MacDonald, Nat Smith�F2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence
XDR�́A���[����T�[�o�A�C���^�[�l�b�g�A�N�Z�X�ȂǁA�����̗̈�̃f�[�^�����f�I�Ɏ��W�E���o���֘A�t���ĕ��͂��s���B����ɂ��A�l�b�g���[�N����G���h�|�C���g�܂ŕ��L���Ď����ł��A���ՓI�ȑS�̏c�����\�ŁA�L�͈͂̃��O�̑��֕��͂ɂ����Ċ댯�����m���ʒm���邱�Ƃ��ł���B
XDR�́A�l�b�g���[�N�̐N�����m�̍��ŏq�ׂ�SIEM�Ɨގ����Ă���悤�Ɍ����邪�ASIEM���e���Ō��m���ꂽ�C���V�f���g���W����ɓ����ƕ��͂��s�����Ƃɑ��āAXDR�͑S�̂���ՓI�ɊĎ��E��͂��Ď����Ώ����s���Ƃ����Ⴂ������BXDR�̓����́ASOC�^�p��Z�L�����e�B��̌������A�Z�L�����e�B��̓���A�T�C�����̖h�~�Ƃ��������b�g������B
�I ���o�C���[���̊Ǘ�
�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�Ȃǂ̃��o�C���[�������Ƃɗ��p�����Ƃ������Ă��Ă���A���ɂ͌l���L�̃��o�C���[�����Ɩ��ɗ��p����BYOD�iBring Your Own Device�j�������Ƃ�����B�P�[�u�����Ǝ҂ł��Ɩ��Ƀ��o�C���[���𗘗p���Ă��鎖�Ƃ�����B
���̂悤�ɁA�Ɩ��ɗp�����郂�o�C���[�����d�v�ȏ��[���Ƃ��ď��R�k�Ȃǂ̃Z�L�����e�B���X�N�ɔ�����������K�v������B
���o�C���[���̊Ǘ��̎d�g�݂Ƃ��ẮAMDM�iMobile Device Management�j�AMAM�iMobile Application Management�j�AMCM�iMobile Contents Management�j������B
MDM�Ƃ́A��Ɨ��p�̃��o�C���[�����ꌳ�I�ɊĎ��E�Ǘ����邽�߂̃T�[�r�X�E�\�t�g�E�G�A�̂��ƂŁA��ʓI�ɁA�u�ݒ�Ǘ��v�u���u�ł̑��쐧��v�u���p�ҏ����W�v��3�̋@�\��������Ă���B
�ݒ�Ǘ��́AOS�̃A�b�v�f�[�g��A�v���P�[�V�����̃C���X�g�[���E�A���C���X�g�[���A����A�v���P�[�V������J�����Ȃǒ[���@�\�̐����AWi-Fi�ݒ�Ȃǂ̈ꌳ�Ǘ����ł���B
���u�ł̑��쐧��́A�[�������̍ۂ̉��u���b�N�����f�[�^�̈ꕔ�܂��͑S�폜�̑���A���u����̃��b�Z�[�W�\���A�[�����͂̉f���≹�������W���铙�̋@�\�����B
���p�����W�Ƃ́A�[���̈ʒu����ړ����A����A�v���P�[�V�����̎g�p���A���u������W����@�\�ŁA�[�����^�p���[���ɏ]�����������p����Ă��邩���m�F����B
MAM�́A���o�C���ŗ��p����A�v���P�[�V�������Ǘ����邽�߂̃T�[�r�X�E�\�t�g�E�G�A�̂��Ƃł���BMAM�ł́A�[�����̋Ɩ��Ɏg�p���Ă���A�v���P�[�V�����ƃf�[�^�݂̂�藣���ĊǗ����邱�Ƃ���A���R�����h�~��ړI�Ƃ��Čl���L�̒[�����Ɩ��p�Ɏg�p����BYOD�[���ŗ��p����邱�Ƃ������B
MAM�̋@�\�ɂ́A�w��A�v���P�[�V�����ɂ��āA�g�p�֎~����юg�p���A��Ђ����L����f�[�^�̒[���ւ̃R�s�[��ړ��̐����A�[�������ⓐ��ɂ̓A�v���P�[�V���������u����ŏ�������@�\�Ȃǂ�����B
MCM�Ƃ́A���o�C���[���ŋƖ����s���ۂɋƖ��ɕK�v�ȃR���e���c�������Ǘ�����T�[�r�X�E�\�t�g�E�G�A�̂��Ƃł���BMCM��MAM�Ɠ��l�ɁABYOD�[���ŃZ�L�����e�B���m�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ė��p����Ă���B
MCM�̋@�\�ɂ́A����R���e���c�ɑ���A�N�Z�X�����Ǘ��A�R���e���c���p�̍ۂ̋@�\����������B�܂��A���i�ɂ���ẮA�[�����p�҂̓���R���e���c���p���L�^���A���O�͂���Ȃǂ̋@�\��������Ă�����̂�����B
�܂��A��L3�̋@�\���܂Ƃ߂�EMM�iEnterprise Mobility Management�j�Ƃ����d�g�݂��łĂ��Ă���B�} 4‑20��EMM�AMDM�AMAM�AMCM�̋@�\�������B
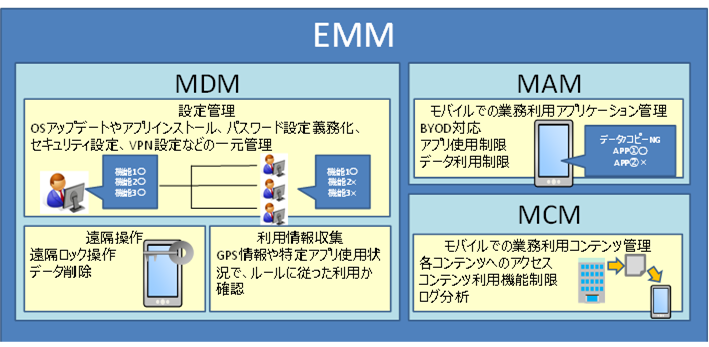
�} 4‑20�@EMM�AMDM�AMAM�AMCM�̋@�\
4.1.3.4�@ �g�D�Ƃ��ẴZ�L�����e�B��
�T�C�o�[���Ђɂ́A����܂ʼn��������ɉ����A�g�D�ʂł̑���d�v�ł���B
�Г��̑g�D�Ƃ��ẮACISO�iChief Information Security Officer�F�ō����Z�L�����e�B�ӔC�ҁj��M���ӔC�҂ɐ����ACSIRT�iComputer Security Incident Response Team�F�Z�L�����e�B�C���V�f���g�Ή����`�[���j��g�D���A�C���V�f���g�������ɔ�����B
�����āA�V�X�e������уl�b�g���[�N��24���ԊĎ�����SOC���\�z���ASIEM�ɂ�铝�����O�Ǘ��E�Ď����瓾����m���Ɋ�Â����^�p���s�����Ƃ���ʓI�ɂȂ����B
����ɁA���g�D���O�Ƃ̃Z�L�����e�B���A�������Ƃ���POC�iPoint of Contact�j��ݒu����B
���������g�D��̐��́A��{�I�ɃC���V�f���g�������i�L���j�̂��߂̂��̂ł��邽�߁A�C���V�f���g�������̖����ɒ��ڂ��W�܂肪�������A�C���V�f���g�������ɐv���ȑΉ�������悤���펞�ɂ�����������ׂ��g�D�ł���B
CISO�ECSIRT�ESOC�EPOC���ꂼ��̖������A�\ 4‑6�Ɏ����B
�\ 4‑6�@�Z�L�����e�B�^�p�Ɋւ��e�g�D�̂��̖���
|
�g�D |
���� |
|
CISO
|
�@�Z�L�����e�B�̐��\�z�Ƃ��̋��� �A�Z�L�����e�B�֘A�\�Z�l���ƌ��ʌ��� �B�s���@�ւƂ̃p�C�v�ێ��i�@�I���ɂ��W���邱�Ƃ����邽�߁j |
|
CSIRT |
�@ �T�C�o�[�Z�L�����e�B�֘A�Г��K���̐���Ɖ^�p �A �Z�L�����e�B�C���V�f���g���̑Ή����� �B �V�X�e����OS��IP�A�h���X�A�g�p�ړI�Ȃǂ̒I���i�A�Z�b�g�Ǘ��j �C �Z�L�����e�B�\�Z�̍���Ǝ��s �D �C���V�f���g���╽�펞�̃��|�[�g�쐬�ƕ� �E ���Z�L�����e�B�̋���A�[���A�P�� |
|
SOC |
�@ 24����365���^�p���A�C���V�f���g�������ɂ́ACSIRT�փG�X�J���[�V���� �A FW��IDS�̃��O�ASIEM�Ȃǂ��Ď����A���Ђ� �B �K�v�ɉ����āACSIRT�Ƌ��Ƀf�W�^���t�H�����W�b�N�i�d�q�ӎ��j�����{ |
|
POC |
�@ ���g�D���E���g�D�O�Ƃ̃Z�L�����e�B���A�g���� �A SOC����̃Z�L�����e�B�����z���グ�A�S�̑��i�f�E���o �B JPCERT��x�@���Ƃ̏��A�g |
����CISO�����POC�Ɋւ��ẮA�Z�L�����e�B�̑S�̍\���𗦂��鑶�݂ł��邽�߁A�l�I�ɂ͏n�����ׂ��ł���B��ʎВc�@�l���{�R���s���[�^�Z�L�����e�B�C���V�f���g�Ή��`�[�����c��i���{�V�[�T�[�g���c��j�ł́APOC�ɋ��߂���X�L�����K�肵�Ă���̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B
�@ ��Ƃɂ�����Z�L�����e�B�g�D����
�{���ł́A�]�ƈ���1,000�l�K�͂̑��Ƃœ�������Ă����ʓI�ȃZ�L�����e�B��̈��ɂ��ĉ������B
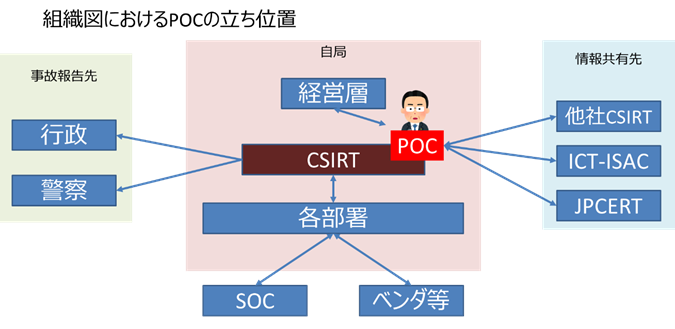
�} 4‑21�@�g�D�ɂ�����POC�̗����ʒu
SOC��ݒu������ŁACSIRT�����Ƃ��đS�̊Ǘ������{���A�A�g�����Ƃ���POC��ݒu����B
�O���ϑ��Ȃǂ̎ЊO������A�Ǝ㐫��C���V�f���g�Ȃǂ̃Z�L�����e�B�f�[�^���z���グ�A���Ђ̌���Ƃ��Đ�������K�v������B
�܂��A�s����x�@�Ƃ̘A�g��A�����Z�L�����e�B�̐��@�ւł���JPCIRT���Ƃ̘A�g�ȂǁA�C���V�f���g�������̘A�����l�����邱�Ƃ��̗v�ł���B
�����́A���ׂ�POC�̋Ɩ��NJ��ƂȂ邪�A�ɉ����Ċe�����Ɋ���U���邱�Ƃ����蓾��B
�A ���ꂩ�狁�߂���Z�L�����e�B�l��
�Z�L�����e�B�l�ނȂ�тɎГ����\�[�X�̕s�����āA�v���X�E�Z�L�����e�B�l�ނ̈琬��������Ƃ��ċ������Ă���B
�v���X�E�Z�L�����e�B�l�ނ́A�]���̃Z�L�����e�B���Ƃ��C�Ƃ��Ċ�Ɠ��̗v���ɐݒu����`�Ƃ͈قȂ�A�e�����ɃZ�L�����e�B�Ɋւ���m���̍����l�ނ�z�u���邱�Ƃɂ��A�O�q�Ɠ����������͂���ȏ�̃Z�L�����e�B���x�����m�ۂ���T�O�ł���B
�v���X�E�Z�L�����e�B�l�ނ����闘�_�͑����A��q�����Z�L�����e�B��C�l�ނ̍팸�����łȂ��A�g�b�v�_�E���ł͌����ɂ����Z�L�����e�B�̐Ǝ㐫�t�H���[��[���Z���̐v�����A���e�����̌���Ɋ��Y�������j����Ȃǂ���������B�܂��A�Ή��l���������������Ƃɂ��g�D�I�ȃZ�L�����e�B�\�ɂȂ����ŁA�g�D�Ƃ��Ă̓�����e�S���̋Ɩ����S�y���Ȃǂ̑Ή����ׂ��ۑ������B��ʎВc�@�l���{�T�C�o�[�Z�L�����e�B�E�C�m�x�[�V�����ψ���iJCIC�j���A�ǂ̒��x�Z�L�����e�B�X�L�������߂�̂��A���傲�Ƃɂ܂Ƃ߂Ă���̂ŁA�����̎Q�l�ɂ��ꂽ���B
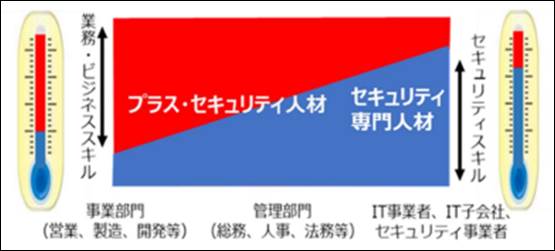
�} 4‑22�@�e����ɋ��߂���Z�L�����e�B�X�L���̃C���[�W
�o�T�F��ʎВc�@�l���{�T�C�o�[�Z�L�����e�B�E�C�m�x�[�V�����ψ���
�����ŁA��L�g�D��ƃv���X�E�Z�L�����e�B�l�ނ�g�ݍ��킹���`�Ƃ��āA���{���l�Ă��郂�f���p�^�[�����ȉ��Ɏ����BCSIRT�̖�����POC�A�L��A����Ƃ�3�ɍi��A�ƊE�S�̂̃��\�[�X�s�����l�������X���[���X�^�[�g�Ƃ��Ă̍\���Ƃ���B
�L��A����Ƃ́A�ɉ����đ��S���̕⏕�����{������̂Ƃ��A��Ƃ̏璷����}����̂Ƃ���B�������܂Ƃ߂����̂��} 4‑23�ł���B
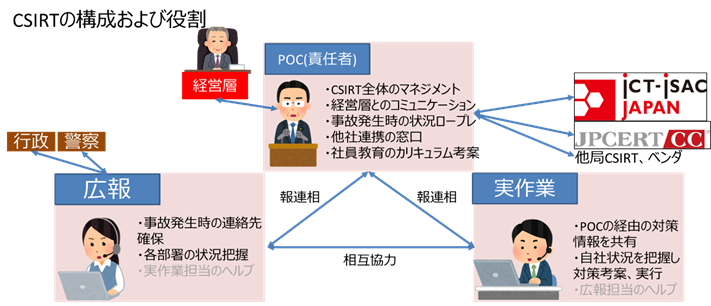
�} 4‑23�@���{�I���W�i�����f���Ƃ��Ă�CSIRT�\������і���
�L��Ǝ���Ƃ̒S���҂����ꂼ��2�����x�C������B�]�ƈ���100�l���̊�Ƃ̏ꍇ�ACSIRT��5���ȏ�ō\�����邱�Ƃ𐄏�����B�e�S���҂�����̖����𗝉����A���ɏ������L���邱�ƂŁA�C���V�f���g������̑Ή��v�������������}�邱�Ƃ��ł���B���킹�āA�e��������ыƖ����e�ɂ��Ă��Ċm�F�A�������͍č\�����邱�Ƃ��̗v�ł���B
4.1.3.5�@ �T�v���C�`�F�[���ւ̃Z�L�����e�B��
�ߔN�̃T�C�o�[�U���ɂ��C���V�f���g�̔����ł́A�V�X�e���A�g���������悪�T�C�o�[�U���������ƂŋƖ�����~���Ă��܂��A���邢�͎����o�R�ŃT�C�o�[�U�����Ă��܂��A������T�v���C�`�F�[���̐Ǝ㐫�𗘗p�����T�C�o�[�U���̔�Q���������Ă���B
2022�N�ɁA��莩���ԃ��[�J�����i���B��̃T�C�o�[�U����Q����Ɩ���~�ɒǂ����܂ꂽ���Ƃ�A�n���Î{�݂������o�R�ɂ��T�C�o�[���АN���ŃV�X�e����~����я��R�����̔�Q�������Ƃ��傫������Ă���B
�P�[�u�����Ǝ҂ł́A�V�X�e���̍\�z��ێ�^�p�������Ɉϑ����邱�Ƃ��͂��߁A�_��l���Ȃǂ̉c�Ɗ�����d�b��t�A�q�擱���H���A�_�������A���������Ȃǂ̌ڋq�ړ_�Ɩ��������Ɉϑ����Ă��邱�Ƃ�����A���ЋƖ��ɂ��ăT�v���C�`�F�[�����\�z���Ă���B�܂��A�n�������̂̕����ʐM�C���t���̍\�z��ێ�^�p��n��R���e���c�̍쐬�A�W�������̕����ʐM�ݔ��̍\�z����ѕێ�A�Z���T�[�r�X�̉^�p�Ȃǂ̎���ȂǁA���҂̃T�v���C�`�F�[���ɑg�ݍ��܂�Ă���ꍇ������B���̂悤�ȏ��ŁA�P�[�u�����Ǝ҂̓T�v���C�`�F�[���̃Z�L�����e�B��ɂ��Ĉӎ������K�v������B
�@ �Ɩ��ϑ���ȂǂƂ̃T�v���C�`�F�[���Z�L�����e�B��
�A������������ɒ��Ă���u�P�[�u���e���r�̂��߂̃T�C�o�[�Z�L�����e�B��K�C�h�v�ł́A�u�o�c�҂��F�����ׂ��i�Z�L�����e�B��́j3�����v�̈�Ƃ��āu���Ђ͖ܘ_�̂��ƁA�r�W�l�X�p�[�g�i�[��ϑ�����܂߂��T�v���C�`�F�[���ɑ���Z�L�����e�B�K�v�v�ł��邱�ƂL���Ă���B�����āA�A���́u�P�[�u���e���r�̂��߂̃T�C�o�[�Z�L�����e�B��X�^�[�g�A�b�v������v�ł́A�T�v���C�`�F�[���̃r�W�l�X�p�[�g�i�[�ɂ�����Z�L�����e�B�v�����_�ɐ��荞�ݐӔC�͈͂m�����邱�ƁA�ϑ���̃Z�L�����e�B��̎��Ԃ����I�Ɋm�F���邱�Ƃ𐄏����Ă���B�܂��A�ϑ���I��ɂ������ẮA�v���C�o�V�[�}�[�N����S�E���S�}�[�N�Ȃǂ̃Z�L�����e�B�F�̎擾�̊m�F���L���ȑ�Ƃ��Ă���B
����ɁA���ЃV�X�e�����ϑ���V�X�e���ƘA�g������ۂȂǂ́A�ϑ����VPN�◘�p�V�X�e���A�l�b�g���[�N���K�ɊǗ�����Ă��邩�A�܂��Z�L�����e�B��̍X�V���K�ɂ���Ă��邩�A����I�Ɋm�F���c�����Ă������Ƃ��T�v���C�`�F�[���̐Ǝ㐫��˂��U����h�����߂ɂ��K�v�ł���B
�܂��A�c�Ɗ�����V�X�e���J���E�ێ�Ή��Ȃǂ̂��߂Ɏ��Ђ̃V�X�e�����ϑ���ɂ����p������ꍇ�ɂ́A�����Ɋւ���_��������킵����ňϑ���̗��p�҂�ID�E�p�X���[�h�ɂ��ĊǗ��ΏۂƂ��A�ݐЏ◘�p�Ȃǂ�c�����Ă������Ƃ��AID�E�p�X���[�h�̕s�����p������s����h�����Ƃɖ𗧂��Ă���B
�T�v���C�`�F�[���̃\�t�g�E�F�A�Ǘ��ɂ��ẮAOSS�iOpen Source Software�j�̊Ǘ����ǂ̂悤�ɂ��邩�����ڂ���Ă���B
���Ƃ��A���܂��܂Ȑ��i��OSS�����W���[���Ƃ��ėp���Ă��邪�A�ŋ߂ł�2021�N12������2022�N1�������Java�x�[�XOSS�̃��M���O���C�u������Apache Log4j�ɐƎ㐫�i���u�̑�O�҂��Ǝ㐫�����p����H�����f�[�^�𑗐M���邱�ƂŁA�C�ӂ̃R�[�h�����s����Ă��܂����ꂪ�������j���m�F�����ȂǁAOSS�ɂ��Ǝ㐫�����݂��Ă���A�K�ȊǗ��Ή����K�v�ł���B�������Ȃ���A��̎���ł�Apache���ǂ��Ŏg���Ă��邩�A��͂Ȃ���Ă��邩�𗘗p�҂��c���ł��Ă��炸�A�ϑ����ł��鎖�Ǝ҂��\�t�g�E�F�A�T�v���C�`�F�[���ւ̑��v�ۂ����f�ł��Ȃ��������Ă��邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă���B
���̂悤�ȉۑ�ɑ��ĕč��ł͑��}�Ȏ�g�݂����Ă���A2021�N5���ɑ哝�̂����������T�C�o�[�Z�L�����e�B�����̂��߂̑哝�̗߂̒��ł́A�\�t�g�E�F�A�T�v���C�`�F�[�������̂��߂ɁAOSS�ɂ��Ď���2�_���s�����Ƃŗ��p�c�����邱�Ƃ����y���Ă���B
l �v���_�N�g�Ŏg�p����Ă���OSS�̊��S���Əo�����\�Ȕ͈͂ŕۏ��A�ؖ����邱��
l �e�v���_�N�g��SBOM�iSoftware Bill Of Materials�F�\�t�g�E�F�A���i�\���\�j���w���҂֒��ڒ��邱�ƁA�������͌��JWeb�T�C�g�ɊJ�����邱��
����SBOM�̊��p�ɂ��ẮA���{�����ł��쐬�Ǘ��̃R�X�g��m�I���Y���o�̌��O�Ȃǂ���莋�Ƃ�����A�o�Y�Ȃ𒆐S�Ɏ��Ȃǂ̊��p���i�ւ̎�g�݂��s���Ă���A�������p����邱�Ƃ����҂���Ă���B
�A �T�[�r�X�ɑ���T�v���C�`�F�[���Z�L�����e�B��
�P�[�u�����Ǝ҂́A�������ʏ���҂ւ̃T�[�r�X�̂ق��ɁA�����{�݂▯�Ԋ�Ƃɂ��T�[�r�X����Ă���B���̏ꍇ�A�T�[�r�X�̓��e�ɂ���Ă͒�̃T�v���C�`�F�[���ɑg�ݍ��܂�邱�Ƃ�����A��̃Z�L�����e�B�v���ɉ������T�[�r�X��ݔ�����邱�Ƃ����߂��邱�Ƃ�����B
���{���{�́A2015�N9���ɃT�C�o�[�Z�L�����e�B�Ɋւ��鍑�Ɛ헪�ł���u�T�C�o�[�Z�L�����e�B�헪�v���t�c���肵���B2016�N8���ɂ́A�T�C�o�[�Z�L�����e�B�헪�{���͐��{�@�֑S�̂̏��Z�L�����e�B���������ړI�Ƃ���u���{�@�ւ̏��Z�L�����e�B��̂��߂̓����v�����肵���B������ĕ{�Ȓ��́A�u�{�Ȓ�������̂��߂̃K�C�h���C���v�����肷��ȂǁA�s���@�ւ�����{�݂ł̓Z�L�����e�B��Ƃ���IT�V�X�e����IT���i�̒��B�ɂ�����v�����������̂ƂȂ��Ă��Ă���B
�܂��AIPA�͏�L�̊�Ȃǂ��Q�Ƃ��A���Ԋ�ƁE�g�D��IT�V�X�e����IT���i�̒��B�҂Ɍ������uIT���i�̒��B�ɂ�����Z�L�����e�B�v�����X�g���p�K�C�h�u�b�N�v�s���Ă���A���B�v���̍��x���͖��Ԋ�Ƃɂ��L����n�߂Ă���B
����ɁA�Ē��̊W�����Ȃǂ̍��ۓI�ȉۑ�ɔ����A�V�X�e�����\�z���Ă���@��̏o�����T�[�r�X�̗p�̗v���ƂȂ�悤�Ȏ�����������Ă���B
�����̏��́A�P�[�u�����Ǝ҂�����T�[�r�X���e�ɂ���ẮA�P�[�u�����ƎҎ��g���@���̓��e���ڋq�ɒ���ق��ɁA�V�X�e���\���⒲�B��Ȃǂɂ��z�����K�v�ƂȂ�\���������Ă���B
4.1.4�@ �ŐV�e�N�m���W�[�g�����h
�@IT�Z�p������ɐi�W���A����l�X�ȃT�[�r�X��Z�p�����ݏo�����ɔ����A�V�K�Z�p��T�[�r�X�ɕt�������V���ȃZ�L�����e�B�̉ۑ���w�E����Ă���B�Ⴆ�A�V�^�R���i�̊����ɔ����A�����[�g���[�N�����y����ɏ]���āA�����[�g���[�N�̗��p�`�Ԃɑ���Z�L�����e�B�K�v�ƂȂ�B�܂��A����ŁA�Z�L�����e�B����Ɋւ���V���ȋZ�p�v�V�ɂ��A����܂ňׂ����Ȃ��������S���E�M�����̍����T�[�r�X����������A����炪�V���Ȏs��ݏo�����Ƃ�����B�����ł́A����AIT�T�[�r�X�ɂ����ē����̉\�������鏫�������������Z�L�����e�B�Ɋւ���e�N�m���W�[�g�����h�Ƃ��āA�ȉ��̂S���Љ��B
l �ϗʎq�Í��F�ʎq�R���s���[�^����������Ă���Ǖs�\�ȁA�����̈Í������ɑ���V���ȈÍ�����
l �ʎq���z���iQKD)�F���`���H��ŁA�ʎq�Z�p�����p�������I�Ɉ��S�ɋ��L����ʎq���z��
l ���@�\�Í��F�f�[�^�̔铽��f�B�W�^�������Ȃǂ́A�����̗p�r�Ƃ͈قȂ�@�\�����V���ȈÍ�����
l AI�̂��߂̃Z�L�����e�B�FAI�V�X�e���̐M�����E���S�����m�ۂ����J���◘���p���������邽�߂̃t���[�����[�N
4.1.4.1�@ �ϗʎq�Í�
�ߔN�A�ʎq�R���s���[�^�����ڂ���Ă���B�ʎq�R���s���[�^�́A�ʎq���ۂ𗘗p���邱�Ƃɂ��A���݁A�L�����p����Ă���R���s���[�^���������Ƃ�����Ȑ��w�����������Ƃ��\�ɂȂ邱�Ƃ��m���Ă���B���̐��w���̈ꕪ��Ƃ��āA�Í��������m���Ă���B���݁A�l�X��ICT�V�X�e���ŗ��p����Ă���Í������́A���݂̃R���s���[�^�̑��x�ł́A�����I�Ȏ��ԁi�Ⴆ�A�����A���T�ԁA���N���j�ʼn�ǂ�������Ƃ��m���Ă��邪�A��K�͂ȗʎq�R���s���[�^����������ƁA�ʎq�̕����̐����𗘗p���āA�����I�Ȏ��Ԃʼn�ǂ��ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�@�����ŁA���݁A�C���^�[�l�b�g�ɂ����āA���p�҂̔F�⌈�ςŃZ�L�����e�B���m�ۂ��邽�߂Ɏg���Ă���Í��Z�p�Ƃ́A�Ⴆ�A���l�Ɍ���ꂽ���Ȃ������A�������̌����g���Ă��̏���ϊ�����Z�p�ł���B�܂��A��ǂƂ́A���̏���m��Ȃ����l���Í������ꂽ�������Ƃ̏��ɋt�ϊ����鎎�݂ł���B���S�ň��S���ăC���^�[�l�b�g��̃T�[�r�X�𗘗p�ł���̂́A�����̈Í��̉�ǂ��ƂĂ�������߂ł���B�����ŁA�Í������̑�\�I�ȕ����Ƃ��āA���J���Í��Ƌ��ʌ��Í��Ƃ�����B���J���Í��Ƃ́A�Í����̌��ƕ����̌����قȂ�ꍇ�A���ʌ��Í��́A�Í����̌��ƕ����̌��������ꍇ�ƂȂ�B��\�I�Ȍ��J���Í���RSA�Í��A���ʌ��Í���AES�����L�����p����Ă���B
�\ 4‑7�Ɏ����悤�ɁA��K�͂ȗʎq�R���s���[�^����������ƁAAES�Ȃǂ̋��ʌ��Í��ł́A�ʎq�T���Ƃ���Z�p�ɂ��A���p����Í��̌��������I�ɐ���ł���悤�ɂȂ邽�߁A�Í��Ɏg�����̒�����2�{���x�ɒ�������K�v������B����ARSA�Ȃǂ̌��J���Í��ɂ��ẮA�Í��̒_�ƂȂ鐔�w���ł���傫�Ȑ��̑f�����������A��K�͂ȗʎq�R���s���[�^�ɂ���ĊȒP�ɉ������Ƃ��ł��邽�߁A���݂̈Í���ʂ̌��J���Í��ɒu��������K�v��������B���ꂪ�A�ϗʎq�Í��ƌĂ��Z�p�ł���B
�\ 4‑7�@�ʎq�R���s���[�^�����ɂ��Í��̊�w���Ƒ�
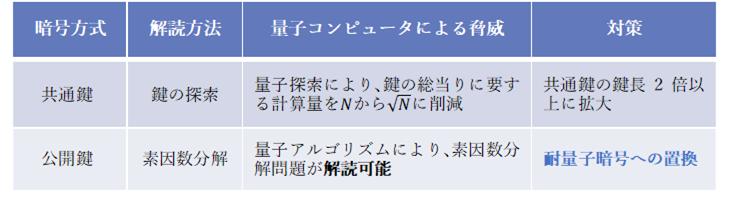
�Í�����ǂł���\�͂�L�����K�͂ȗʎq�R���s���[�^���o�����鎞���́A5�N�ォ10�N�ォ���m�ɗ\�����ł��Ă��Ȃ����A���݂̈Í��Z�p�ňÍ������ꂽ��A�����ԕۊǂ����ۂɂ́A������������Ƃ����Ă����K�͂ȗʎq�R���s���[�^�ʼn�ǂ���鋰�ꂪ����B�]���āA��K�͂ȗʎq�R���s���[�^�̎����ɐ旧���āA�ϗʎq�Í����J������K�v������B
�@ NIST PQC�v���W�F�N�g
���̂悤�Ȕw�i�ɂ��A�č��W���Z�p������NIST�ł́A2016�N�ɑϗʎq�Í��̃r���[�e�B�R���e�X�g�ł���PQC(Post Quantum Cryptography)�v���W�F�N�g���J�n�����BPQC�W�����̃^�C�����C����} 4‑24�Ɏ����B����́A���E���̈Í��w�҂���������W���A���̒�����A�D�ꂽ������NIST�̕W���Z�p�Ƃ��đI�肷��v���W�F�N�g�ł���BNIST�ł́A2027�N�܂łɂ͊����̌��J���Í�����ǂ����Ƃ̑z��̂��ƁA��̓I�ȕ�����I�肷�銈�����s���Ă���B
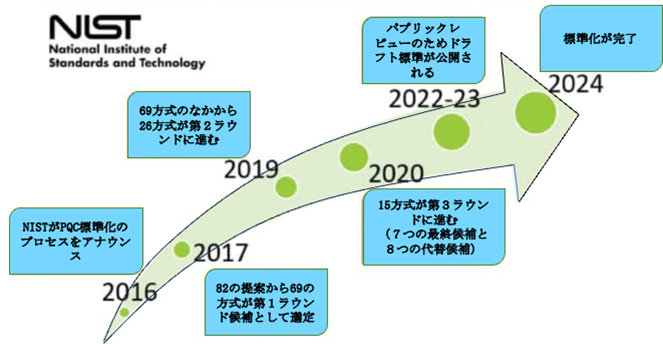
�} 4‑24�@NIST�ɂ�����PQC�W�����̃^�C�����C��
�@����܂ŁANIST�ɂ��R��̃R���e�X�g���o�āA2022�N�V���A���J���Í�/���J�v�Z�������J�j�Y��1�����A�f�B�W�^�������R�����̌v�S�̕������I�肳��A2023�N8���ɁA�����̃h���t�g�W�������J����Ă���B
�ϗʎq�Í��̃h���t�g�W��
FIPS 203, Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard
FIPS 204, Module-Lattice-Based Digital Signature Standard
FIPS 205, Stateless Hash-Based Digital Signature Standard
�����ŁA���J���Í�/���J�v�Z�������J�j�Y���Ƃ́A�ʐM����āA����ɋ��ʌ������S�ɓ`���邽�߂ɁA���J���ŋ��ʌ����Í�������Z�p�ł���B���J���Í�/�����L�A���S���Y���ɂ��ẮA��S��ڂ̃R���e�X�g�ł���ɂP�������lj��I�肳��A2024�N�ɑI�肳�ꂽ�ϗʎq�Í����W���d�l�Ƃ��Č��J�����\��ł���B�����ł́A�\ 4‑8�ɂ���܂őI�肳�ꂽ�S�̑ϗʎq�Í��̊T�v���q�ׂ�B
(1) ���J����/���J�v�Z�������J�j�Y��
CRYSTALS–KYBER
�{�����́AFIPS 203�Ƃ��ăh���t�g���Ă��쐬����Ă���B�{�����́A�i�q�_�T�����ƌĂ�鐔�w���𗘗p�������J���Í�/���J�v�Z�������J�j�Y���ł���B�{�����́A�i�q�_�T�����̒��ł������I��MLWE(Module Learning with Errors)�𗘗p���Ă���AIND-CCA2(Indistinguishability against Chosen Ciphertext Verification Attack)�ƌĂ��q�ϓI�Ȉ��S����S�ۂ��Ă���B�܂��A�{�����́A���J���y�шÍ������ꂽ���1000�o�C�g���x�ƂȂ�B
(2) �f�B�W�^������
CRYSTALS–Dilithium
�@�{�����́AFIPS 204�Ƃ��ăh���t�g���Ă����J����Ă���B�{�����́A�i�q�_�T�����̈��ł���MLWE(Module Learning with Errors)�𗘗p���Ă���ASUF-CMA�iStrong Existential Unforgeability under Chosen Message Attack�j�ƌĂ��q�ϓI�Ȉ��S����S�ۂ��Ă���B�܂��A�{�����́A��q��Falcon�Ɠ��l�Ɍ����I�ȕ����ł���B
FALCON
�{�����́A��\�I�Ȋi�q�Í��ł���NTRU�𗘗p���������ł���A���̉���̂��ƂŁA�U���s�\����S�ۂ��Ă���B�܂��A���J����f�B�W�^�������̃T�C�Y���������A�����̌��������ɏ����ł��闘�_���������A�����쐬��CRYSTALS–Dilithium���x���A���̐����ɔ��Ɏ��Ԃ�v����Ƃ������_������B�܂��A�f�[�^�\����A���������_�𗘗p����K�v������ȂǁA����������_���w�E����Ă���ANIST����́A�œK�Ȏ������@�₻�̎����̌��ؕ��@�Ɋւ����Ƃ����߂��Ă���B2024�N��FIPS�̑��Ă����J�����\��ł���B
SPHINCS+
�@�{�����́AFIPS 205�Ƃ��ăh���t�g���Ă����J����Ă���B�{�����́A�n�b�V�����Ɋ�Â��A�f�B�W�^�����������ł���BSHA-256�Ȃǂ̕W���I�ȃn�b�V������p���Ă���A�n�b�V�����̈��S���Ɉˑ����������ł���B�P�̌��J���ŏ����ł���ɐ���������B�i�q���̈��S���������Ƃ��Ă��鑼�����ƈ��S���̍����Ƃ͖��W�Ȃ��߁A�����̕����̉�ǎ�@���������ꂽ�ꍇ�̃t�H�[���o�b�N�A���S���Y���̈ʒu�t���Ƃ������Ă���B�������⏐�������A�����쐬�ɔ�ׂč����ł���B�����������̕����ɔ�ׂ�CRYSTALS–Dilithium��FALCON�ɔ�ׂĔ��ɒ����B
�\ 4‑8�@NIST PQC�̈Í�����
|
�ړI |
���� |
�����ƂȂ鐔�w��� |
���S�� |
���� |
|
���J����/���J�v�Z�������J�j�Y�� |
CRYSTALS–KYBER |
�i�q�_�T�����
|
IND-CCA�Q |
���J���y�шÍ������ꂽ���o�C�g���x |
|
�f�B�W�^������ |
CRYSTALS–Dilithium |
�i�q�_�T�����(decisional Module-LWE assumption) |
SUF-CMA |
��q��Falcon�Ɠ��l�Ɍ����I�ȕ��� |
|
FALCON |
�i�q�_�T�����iShort Integer Solution Problem over NTRU lattices�j |
Unforgeability in the QROM |
���J����f�B�W�^�������̃T�C�Y���������A�����̌��������ɏ����ł��闘�_�A���̐������x���Ƃ������_ |
|
|
SPHINCS�{ |
�n�b�V�����̏Փ˒T����� |
�n�b�V�����̈��S�������� |
��ʓI�ȃn�b�V���������p�\�A�������⏐�������A�����쐬�ɔ�ׂč����A���������������ɔ�ׂĔ��ɒ����B |
4.1.4.2�@ �ϗʎq�Í��̊����Z�L�����e�B�v���g�R���ւ̓�������
����A�ϗʎq�Í����W���������ɏ]���ARSA���J���Í����A�ϗʎq�Í��ɒu��������K�v��������B���̂��߁A�ȉ��Ɏ����ʂ�A�C���^�[�l�b�g�W�����쐬���Ă���IETF�ł͑ϗʎq�Í��̓����������i�߂��Ă���B
(1) TLSv1.3
TLv1.3�́A�g�����X�|�[�g�w��ŁA�F�A�Í������̃Z�L�����e�B�@�\�����Z�L�����e�B�v���g�R���ŁAWeb�̃Z�L�����e�B���m�ۂ��邽�ߓ��ɍL�����p����Ă���BTLSv1.3�ł́A�������y�єF��ړI�Ƃ��āARSA�AECDH�AECDSA�Ȃǂ̌��J���Í����p�����Ă���A��������ʎq�R���s���[�^�̎����ɂ���w�����邱�Ƃ��m���Ă���B���̂��߁AIETF�ł́A�ϗʎq�Í��ɑΉ�����TLS�̎d�l�̌������i�߂��Ă���iHybrid key exchange in TLS 1.3�j�B�W�������ꂽ�ϗʎq�Í����A���S�ʁA���\�ʂŏ\���Ɏ��p�ɑς�����Ƃ����R���Z���T�X������ڍs����܂ł́A�����̈Í��Ƒϗʎq�Í����I��I�ɗ��p�\�ȃn�C�u���b�h���[�h�̗��p���z�肳���B
(2) OpenSSL
OpenSSL�́ATLS�̃I�[�v���\�[�X�ɂ��\�t�g�E�F�A�����y�т��̃v���W�F�N�g��\���BOpenSSL�v���W�F�N�g�ł́ANIST�̑I��v���Z�X����������܂ŁA���A���S���Y�����܂߂Ȃ��ӌ��������Ă��邪�A��q��Open Quantum Safe�v���W�F�N�g�́A�]����ړI�Ƃ��Č����܂�OpenSSL 3.x�̎������s���Ă���B
(3) Open Quantum Safe
Open Quantum Safe�́A�ϗʎq�Í��̎����y�уv���g�^�C�v���x������I�[�v���\�[�X�v���W�F�N�g�ł���BOpen Quantum Safe�ł́Albops���Ă��C����ŊJ�����ꂽ�ϗʎq�Í��̃I�[�v���\�[�X���C�u���������ƂƂ��ɁA�@OpenSSL�̃��C�u������p���āA�����̃v���g�R����A�v���P�[�V�����Ƀv���g�^�C�v�Ƃ��đϗʎq�Í���g�ݍ��ލ�Ƃ��s�Ȃ��Ă���B
(4) SSH
SSH�́AIETF�ɂ��W�������ꂽRSA, ECDH, ECDSA���J���Í��Ɋ�Â��A���̌����A�F�v���g�R���ł���B���݁ASSH�ɑ��āA�ϗʎq�Í��̑Ή��ɂ��Č�����i�߂Ă��邨��A�C���^�[�l�b�g�h���t�gPost-quantum Hybrid Key Exchange in SSH�̍쐬��Ƃ��i�߂��Ă���B�B
(5) PGP
PGP�́A�d�q���[���̃R���e���c�i�{���j�ɑ���Í����A�f�B�W�^����������������Z�p�ł���B���J�v�Z�������J�j�Y���ƃf�B�W�^�������ɑ��āAECC,ECDSA�Ȃǂ̌��J���Í����p�����Ă���B���݁A�����̌��J���Í��Ƒϗʎq�Í��̑o���̕����p���āA�Í����A�f�B�W�^���������s���R���|�W�b�g���[�h�̌�����i�߂Ă���(Post-Quantum Cryptography in OpenPGP)
4.1.4.3�@ �ʎq���z��
���z���Ƃ́AITC�V�X�e���ɂ����āA���ꂽ�n�_�ɁA�������S�ɔz������Z�p�ł���B�������S�ɔz���ł���A���u�n�Ԃŋ��L���ꂽ����p���āA�����Í������đ��M�ł���B�����ŁA�������S�ɔz�����邽�߂ɂ́A�r���̒ʐM�H�ł̓�����������h�~����K�v������B�ʎq���z���́A�ʎq�̐�����p���āA������������h�~���āA�����I�Ɉ��S�ɔz������Z�p�ł���B���ɁA�ʎq�����s�m�萫�����̐����ɂ��A�r���̒ʐM�H�ł̓����s�ׂ��A���q�̏�Ԃɕω��������炷���Ƃɂ��A�������Ɍ��o�ł���Ƃ����_�́A�]���̈Í��Z�p�ł͎����s�\�Ȉ��S����L���邱�Ƃ�����Ƃ��Ă���B
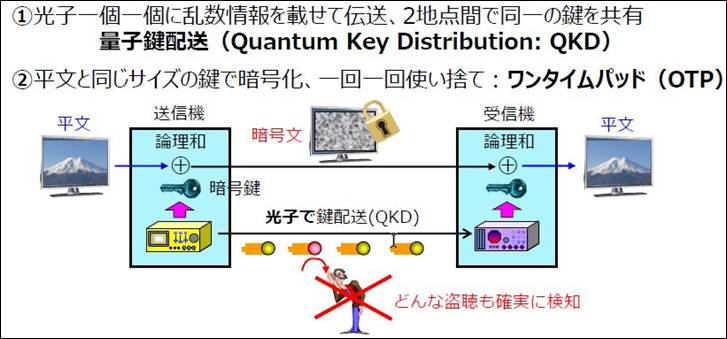
�} 4‑25�@�ʎq�Í��ʐM�̊T�v�}
�i�o�T�@NISC�u�������G�u�ʎq�Í��Z�p�Ɋւ��铮���ƓW�]�v�@NICT���X�؉�p���@(2019.4.26)�j
�@ ��{����
�����ł́A�ʎq���z���Z�p�̒��ł���\�I�ȃv���g�R���ł���BB84���T������i�} 4‑26�j�B���M�҂́A���s����Q��ނ̕Δg�i�����Ό��Ɖ~�Ό��j�̂����ꂩ�������_���ɑI�����āA�h0�h/ �g1�h�̏���\���A���`���H��ʂ��āA��M�҂Ɍ��q�Ƃ��đ��t����B��M�҂͂Q��ނ̕Δg�����o�ł���Δg����������ꂼ��p�ӂ��A�ǂ��炩����̕Δg������Ō��q����M���A���q����M���閈�ɕΔg���g��������_���ɐ�ւ���B���M�������q�̕Δg�Ǝ�M��̕Δg������̕Δg�̎�ނ���v���Ă���ꍇ�́A�������h0�h/ �g1�h�̏�����M���A��v���Ă��Ȃ��ꍇ�́A������������M�ł��Ȃ����ߔj������B���̌��ʁA���M�҂����M�����h0�h/ �g1�h���̂����A�m���I�ɂق�1/2�Ő������h0�h/�g1�h�̏�����M�ł���B�����ŁA�ʐM�H�œ��������������ꍇ�́A�������h0�h/ �g1�h���x��Ȃ����߁A��M������̌��m�����傫���Ȃ邱�Ƃ��m�F�ł��邽�߁A�������s��ꂽ���Ƃ����o�ł���B
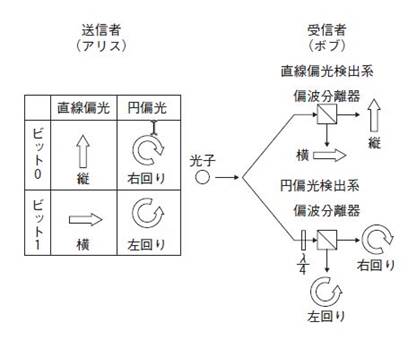
�} 4‑26�@BB84�v���g�R���̊�{�T�O�}
�i�o�T�@NTT�Z�p�W���[�i���@2006.8�j
�A ���p���Ɍ��������g�݂ƕW��������
�ʎq���z���́A���Ɉ��S���̍��������Ƃ����Ă������ŁA���`���̑��x��A�����I�ɓ`���\�ȋ������ۑ�ƂȂ��Ă����B�ŋ߂ł́A�����A�����Z�p�̉��ǂɂ��A�`�����x�̑��ʂ݂̂ł�10Mbps���x�A�`�������̑��ʂ݂̂ł�500km���x���B������A���p�ʂł̉ۑ�������������B�܂��A�ʎq���z���Z�p���l�b�g���[�N�V�X�e���Ƃ��ė��p���錟�����i�߂��Ă���B�ʎq���z��(QKD)�l�b�g���[�N�́A�ʎq���z���̑���M�@���l�b�g���[�N�ڑ����A���S�������I�Ɍ����Ǘ��E�z������Z�p�ł���A�l�b�g���[�N��̔C�ӂ̒n�_�ł̈Í����̋��L���s���A������]���̃l�b�g���[�N�ɒ��邱�ƂŁA���Ɉ��S�ȈÍ������g�����V���ȃZ�L�����e�B�T�[�r�X���\�ƂȂ�B
����ɗʎq���z���l�b�g���[�N�̑��ݐڑ������m�ۂ��邽�߂�ITU-T�ɂ����č��ەW�������i�߂��Ă���B��̓I�ɂ́AITU-T SG13�ɂ����āA�@�\�v�������A�A�[�L�e�N�`���A���Ǘ��A����E�Ǘ��AQoS���AITU-T SG17�ɂ����āA�Z�L�����e�B�v�������A���Ǘ��A�������A�[�L�e�N�`���A�Í��@�\���AITU-T SG11�ɂ����āA�C���^�[�t�F�[�X�d�l�̍�����s���Ă���B����ɁAETSI, ISO/IEC JTC1 SC27�ɂ����ẮA�ʎq���z���̑��u�̕W�������i�߂��Ă���B��̓I�ɂ́A�ʎq���z�����u�̃Z�L�����e�B�F��(CC�F��)�ɕK�v�ȁA�Z�L�����e�B�v���d�l�ƕ]��⼿�@�̕W������⾏���Ă���B
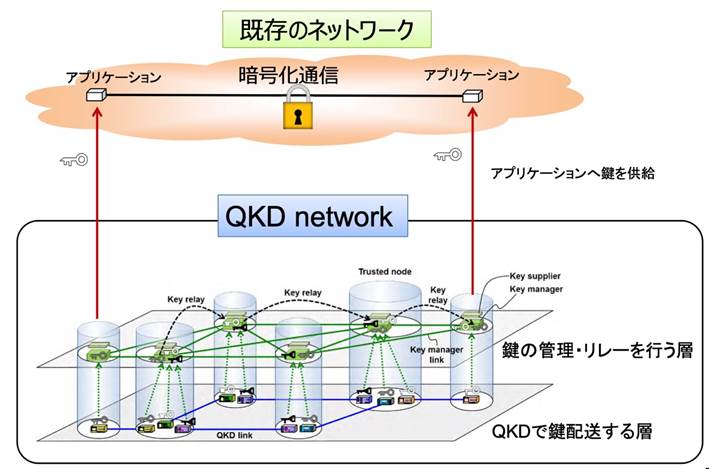
�}
4‑27�@QKD�l�b�g���[�N�̊T�O�}
�o�T�@�u�������G�uTokyo QKD Network: �ʎq�Í��l�b�g���[�N�e�X�g�x�b�g�̍\�z�Ɨ����p�vNICT���� ���T���@(2021.3.28)
4.1.4.4�@ ���@�\��
�@�]���A�Í��Z�p�́A�f�[�^��铽����A�f�B�W�^���������s���ȂǁA��r�I�A�V���v���ȃZ�L�����e�B�@�\�������̂Ƃ��āA�L�����p����Ă������A�ŋ߁A�Í��Z�p�̐i���ɔ����A�Љ�̂��܂��܂ȃj�[�Y�ɑΉ����ł����蕡�G�ō��x�ȈÍ��Z�p�Ƃ��č��@�\�Í����J������Ă���B���@�\�Í��Ƃ́A�]���̈Í��Z�p�ɂ͂Ȃ����x�ȕt���@�\�����Í��Z�p�̑��̂ł���A����̈Í��Z�p�ł͂Ȃ������Ȓ�`�͂Ȃ��B�����ł́A���@�\�Í��ɕ��ނ�����\�I�ȈÍ��Z�p�ɂ��āA���̋@�\�̓����ƁAITC�V�X�e���ɂ����āA�ǂ̂悤�ȗp�r���z�肳��Ă��邩�Ƃ����ϓ_�ŊT������B
�@ �����^��
�@�����^�Í��Ƃ́A�������Í��������܂܉��Z���邢�͏�Z���ł���Í��Z�p�ł���B�]���̈Í��Z�p�͕K���������̂悤�Ȑ�����ۗL���Ȃ��B���ɁA���Z�Ə�Z�o�����\�ȋ@�\�����Í��́A���S�����^�Í��ƌĂ�Ă���B�ŐV�̕����Ƃ��ẮA�Í����̑ΏۂƂȂ鐔���Ɏ������������Ƃ��ł���CKKS��������Ă���Ă���B
�@�����^�Í��̑�\�I�ȗp�r�́A�N���E�h��ł̔铽�v�Z�ł���B�����A�l�X�ȏ������N���E�h��œ��삳����N���E�h�T�[�r�X�����ڂ���Ă���B�N���E�h�T�[�r�X�Ƃ́A�f�[�^��ۊǂ��郁���������y�сA�R���s���[�^�̌v�Z�����������A�N���E�h�ɃA�E�g�\�[�X����T�[�r�X�ł���B�����ŁA�N���E�h�T�[�r�X����鎖�Ǝ҂́A�N���E�h��ň�����{���\�ł��邽�߁A��荂���Z�L�����e�B��v���C�o�V�ی�����߂�V�X�e���ł́A�N���E�h���Ǝ҂ɑ��Ă�����铽�������P�[�X���z�肳���B�����ŁA�f�[�^�̃o�b�N�A�b�v���N���E�h��ōs���݂̂̏ꍇ�ɂ́A�]���̈Í��Z�p��p���āA�f�[�^���Í������ĕۊǂ��邱�Ƃ��\�ł��邪�A����ɁA�N���E�h��ł̌v�Z������铽�������ꍇ�ɁA�{�����^�Í����K�v�ƂȂ�B���̂悤�ɁA�N���E�h�T�[�r�X�𗘗p����ۂ̃Z�L�����e�B�E�v���C�o�V����̂��߂ɏ����^�Í��̗��p���z�肳���B�N���E�h�ł̗��p�C���[�W���} 4‑28�Ɏ����B
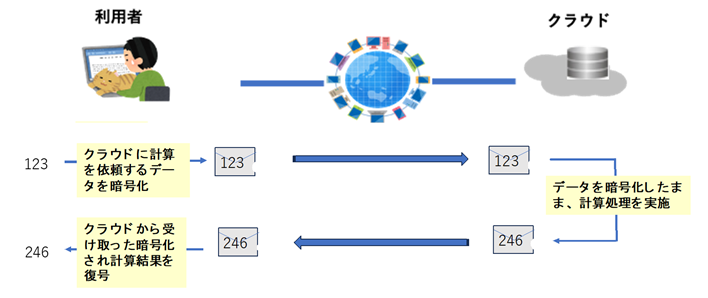
�} 4‑28�@�����^�Í��̗��p�C���[�W
�A �����\��
�@��q�̂Ƃ���A�]���̈Í��Z�p��p���āA�o�b�N�A�b�v�f�[�^���N���E�h��Ɉ��S�ɕۊǂ��邱�Ƃ͉\�ł��邪�A�o�b�N�A�b�v�f�[�^����K�v�ȏ��݂̂������������ꍇ���l������B���̂��߂ɂ́A��U�S�f�[�^�����Ĉ�v���邩���m�F����K�v�������A��N���E�h���Ǝ҂ɘI�悷��ƂƂ��ɁA�������̂�������������ł���B���̉ۑ����������Z�p�Ƃ��Č����\�Í�����Ă���Ă���B�����\�Í��Ƃ́A�����̃t�@�C�����Í�������N���E�h�ɕۊǂ��ꂽ��ԂŁA�N���E�h�ɑ��Č����L�[���[�h��铽���A���A�Í������ꂽ�t�@�C�������邱�ƂȂ������L�[���[�h���܂ރt�@�C���邱�Ƃ��\�ȋZ�p�ł���B�����̎��p�����l�����Ċ��S��v�݂̂ł͂Ȃ������������w��\�Ȋg����������������Ă���B�����\�Í������p�C���[�W���} 4‑29�Ɏ����B
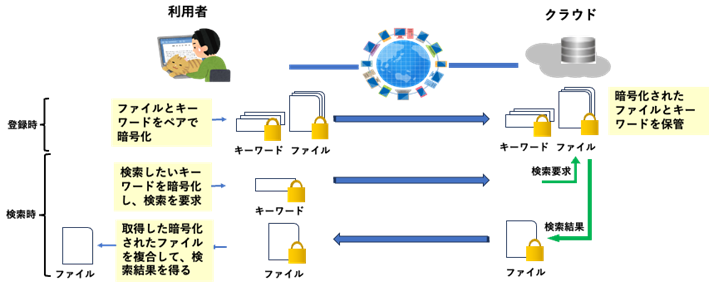
�} 4‑29�@�����\�Í��̗��p�C���[�W
�B ID�x�[�X���iIBE�j
�@ID�x�[�X�Í��Ƃ́A���J���Í��̈��ł���B�]���̌��J���Í��́A�{�l�݂̂��ۗL����閧���ƁA���l�Ɍ��J�ł�����J����p����B�����ŁA���J���́A���J���Í��̌������@�\�ɂ���Đ�����������Ȍ���p���邪�AID�x�[�X�Í��ł́A���J���ɖ��O��[���A�h���X�ȂǁA���炩���ߑ��݂���{�l��ID�i���ʎq�j��p��������ł���B���̂��߁A���J���Í��̉ۑ�Ƃ���Ă�����J���Ɩ{�l�i���J���̏��L�ҁj�̊W��ۏႷ����J���ؖ������s�v�ƂȂ�B�Ⴆ�A�{�l�̓d�q���[���̃A�h���X�����J���Ƃ��āA�f�[�^���Í������āA���̓d�q���[���̈���ɑ��t���邱�ƂŁA�ȒP�ɈÍ��ʐM���ł���BID�x�[�X�Í������p�C���[�W���} 4‑30�Ɏ����B
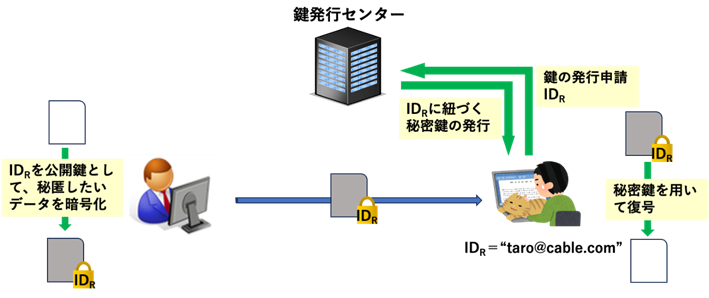
�} 4‑30�@ID�x�[�X�Í��̗��p�C���[�W
�C �����x�[�X���iABE�j
�@�����x�[�X�Í��́AID�x�[�X�Í��̍l����������Ɋg�����������ł���B�����x�[�X�Í��ɂ���ĈÍ������ꂽ�f�[�^���A�قȂ鑮�����������̑���ɑ��A�Í����ɐݒ肵���|���V�[�ɍ��v���鑮���������p�҂݂̂������ł�������ł���B�Ⴆ�A�R���e���c�z�M�T�[�r�X�ɂ����āA���ʉ������ѐ��l�̑����̗��p�҂̂݃v���~�A���R���e���c���{���\�ɂ���ƌ������T�[�r�X���z�肳���B���̂悤�ɁA��̈Í������ꂽ�f�[�^�ɑ��āA�����Ɋ�Â��A�N�Z�X������s�����Ƃ��\�ƂȂ�B�����x�[�X�Í������p�C���[�W���} 4‑31�Ɏ����B
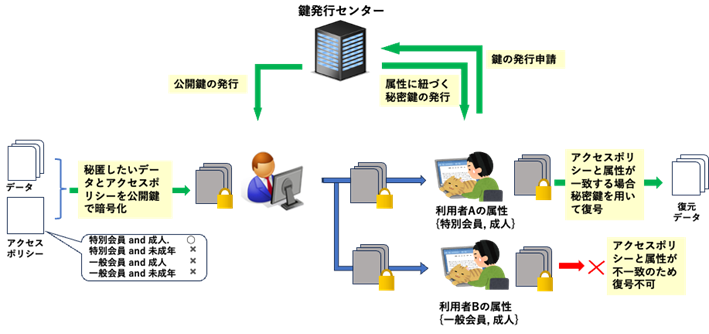
�} 4‑31�@�����x�[�X�Í��̗��p�C���[�W
�D ���^��
�@���^�Í��́A�����x�[�X�Í�������Ɉ�ʉ��������̂ł���B���^�Í��̓����́A����lx���Í��������f�[�^���A����̊�f(x)�ɑΉ�������J���Í��̔閧��sk_f��p���邱�Ƃɂ��Ax�����邱�ƂȂ�����̊���(x)���v�Z�ł���Í��Z�p�ł���B
�����x�[�X�Í��̂悤�ȃf�[�^�A�N�Z�X����ȊO�ŁA�z�肳��郆�[�X�P�[�X�Ƃ��ẮA�Ⴆ�A�Z�L���A�ȃX�p�����[���t�B���^���l������B�Í������ꂽ���[���ɑ��āA�v���L�V�����[�������邱�ƂȂ��X�p�����[�����ǂ����肷�邱�Ƃ��\�ł���B��̓I�ɂ́A�X�p�����胍�W�b�N����f�Ƃ��āA���̈��������[���̃R���e���c�Ƃ���ꍇ�A���^�Í��ɂ��Í������ꂽ���[���R���e���c�ɑ��āA�v���L�V���A�閧����p���ă��[���̃R���e���c�����邱�ƂȂ��A�v�Z���ʁi�܂�A�X�p��/�X�p���łȂ����̔��茋�ʁj�݂̂�m�邱�Ƃ��ł���B�܂��A�ʂ̃��[�X�P�[�X�Ƃ��ẮA�Í������ꂽ��Ï��̃f�[�^�x�[�X�̒�����A�A�W�A�l�̊��̎�ʂƈ�`�q�^�̊W���݂̂𒊏o�������ꍇ�Ȃǂ̃f�[�^�}�C�j���O�ɂ��K�p�\�ł���B���̂悤�Ɋ��^�Í��́A���ɕ��L���T�[�r�X�ւ̓K�p�����҂���Ă���B���^�Í������p�C���[�W���} 4‑32�Ɏ����B
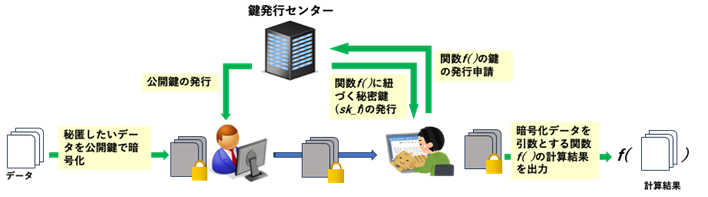
�} 4‑32�@���^�Í��̗��p�C���[�W
4.1.5�@ AI�̂��߂̃Z�L�����e�B
�����AIT�Z�p�̐i�W�ɔ����AAI�̐i�����}���ɐi��ł���B21���I�ɓ���������O���l�H�m�\�u�[���́A�f�B�[�v���[�j���O�̓o��ɂ����������AAI���ꕔ�A�l�Ԃ̎v�l���郌�x���ɒB���Ă���B���ɁAChatGPT�Ȃǂ̍ŋ߁A�o�ꂵ����K�͌��ꃂ�f���iLLM�j�́A���Z�A��ÁA�n��A����ȂǍL�͈͂ȃr�W�l�X�̈�ւ̓K�p���i�߂��Ă���A�Љ�ɗ^����C���p�N�g�͐r��ł���B�]���āA����A���܂��܂Ȉӎv�����AI����������邱�Ƃ͋^���̗]�n���Ȃ��A�d�C�ʐM�ݔ��ɑ��Ă��A��Q�̌��m�╜���Ȃlj^�p�̎�������AI�����p���邱�Ƃ��z�肳���B����A���̂悤��AI�ւ̈ˑ����i�ނɂ�AAI�̐M�����ɑ��郊�X�N�����O����Ă���A���X�N�}�l�W�����g�̑��ʂ�AI�̎Љ�����Ɍ������i�ق̉ۑ�ƍl�����Ă���B�Ⴆ�AAI���o�͂��鐄�_���ʂ�100���������Ƃ͌��炸�A���_���ʂ̍�������������ł��邽�߁AAI����������f�������ꍇ��z�肵�āA���V�X�e���ɏ�L�̃��X�N���ǂ̂悤�ɑΏ����邩���l����K�v������B����ɁA�ŋ߁AAI�ɑ���Z�L�����e�B���X�N�����ڂ���A�w�ە���ł��܂��܂ȋ��Ђ�����Ă���A���̑�̕K�v�����w�E����Ă���B�����ł́AAI�ɑ���Z�L�����e�B����̑�\�I�ȋ��Ђɂ��ďq�ׁA�Љ�����Ɍ�����AI�̃��X�N�}�l�W�����g�̓����ɂ��ďq�ׂ�B
4.1.5.1�@ AI�̃��C�t�T�C�N��
�@AI�̃��C�t�T�C�N���Ƃ��āA�w�K�t�F�[�Y�Ɨ��p�t�F�[�Y������( �} 4‑33)�B�w�K�t�F�[�Y�ł́A�Ⴆ�A��ʐ^����j���𐄘_����A�p�����{��ɖ|��Ȃǂ̃^�X�N���A���ʂ̃T���v���f�[�^���w�K�����邱�Ƃɂ��A���_���s���@�B�w�K���f�����쐬����B���_�t�F�[�Y�ł́A��L�A�w�K�ς݂̋@�B�w�K���f����p���āA�e�X�g�f�[�^����͂��A���_���ʂ�B��q�̐���AI�ł́A���_���f���͐������f���ɒu�������B
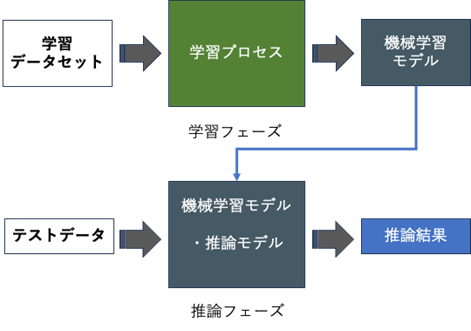
�} 4‑33�@AI�ɂ�����Q�̃t�F�[�Y
4.1.5.2�@ AI�̋���
AI�ɑ���U���́A���X�i�����Ă���A�@�B�w�K���f��������w�K�t�F�[�Y�ł̍U����A���_�t�F�[�Y�ɂ�����A�w�K�ς݂̋@�B�w�K���f���ɑ���U���ȂǁAAI�̊e�X�̃t�F�[�Y�ɑ��鋺�Ђ��w�E����Ă���B�����ł́ANIST.AI.1-00-2e2023�ɂ����Ē�`���ꂽ���Ђ��Љ��B�ȉ��̒ʂ�A�]���̐��_���f���ɑ���AI�ɉ����A�������ڂ���Ă��鐶��AI�ɑ���U������������Ă���B
�@ ���_���f���ɑ��鋺��
�E�|�C�Y�j���O�U��
�@�|�C�Y�j���O�U���́A�@�B�w�K���f�����Ӑ}�I�ɕύX���Č딻�f���N�������Ƃ�ړI�Ƃ��āA�w�K���ɁA�w�K�f�[�^��w�K���f��������������U���ł���A�w�K���Ɋw�K�f�[�^���̂��̂����A���邢�͊w�K�f�[�^�𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ȍU�����f���ł���B
�|�C�Y�j���O�U���́A����ɁA�w�K���f���S�̂ɖ����ʂɉe����^���AAI�V�X�e���̗��p�҂ɑ��ăT�[�r�X���ۍU���������N�����g�p���|�C�Y�j���O�U���h�A�����̕W�I�T���v���ɑ���@�B�w�K���f���̐��_�ɕω���U������g�W�I�^�|�C�Y�j���O�U���h�A�f�[�^�Ƀo�b�N�h�A�ƂȂ�g���K�[�ߍ��ނ��Ƃɂ��A�Ӑ}���锻�f���N�����g�o�b�N�h�A�U���h�A�w�K�ς݂̋@�B�w�K���f���ڕύX���āA���ӂ̂���@�\�����f���ɑ}������g���f���|�C�Y�j���O�U���h�̉\�����w�E����Ă���B
�E����U���i�G�ΓI�T���v���j
����U���́A�f�[�^�ɍŏ����̏���t�����邱�ƂŁA���_�t�F�[�Y���ɍU���҂��I�������C�ӂ̃N���X�ɕ��ށA���Ȃ킿�A���_���ʂ�ύX�ł���G�ΓI�T���v�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B����U���́A�@�B�w�K���f���ɑ�����o�݂͂̂���G�ΓI�T���v��������g�u���b�N�{�b�N�X����U���h��A�@�B�w�K���f���̊w�K�f�[�^�A�\���A�n�C�p�[�p�����[�^�ȂǁA�@�B�w�K�V�X�e���Ɋւ��銮�S�Ȓm�������p���ēG�ΓI�T���v��������g�z���C�g�{�b�N�X����U���h������B�G�ΓI�T���v���ɂ��U���̃C���[�W��} 4‑34�Ɏ����B
�E�v���C�o�V�[�U��
�v���C�o�V�[�U���Ƃ́A�@�B�w�K���f������l����d�v�C���t���̋@���f�[�^�����o�[�X�G���W�j�A�����O���āA���o����U���ł���B�v���C�o�V�[�U���́A�w�K�ɗp�����f�[�^�𐄘_�����g���f���C���o�[�W�����U���h�A���背�R�[�h�܂��̓f�[�^���A���v�A���S���Y���܂��͋@�B�w�K�A���S���Y���Ɏg�p�����w�K�f�[�^�Z�b�g�̈ꕔ�ł��邩�ǂ����f����g�����o�[�V�b�v���_�U���h�A�w�K�ς݂̋@�B�w�K���f���ɖ₢���킹���s�����ƂŁA�@�B�w�K���f���̃A�[�L�e�N�`���ƃp�����[�^�[�Ɋւ�����𒊏o����g���f�����o�U���h�A�@�B�w�K���f���𑀍삷�邱�ƂŁA�w�K�f�[�^�̕��z�Ɋւ�����𐄘_����g�v���p�e�B���_�U���h�ɕ��ނ����B
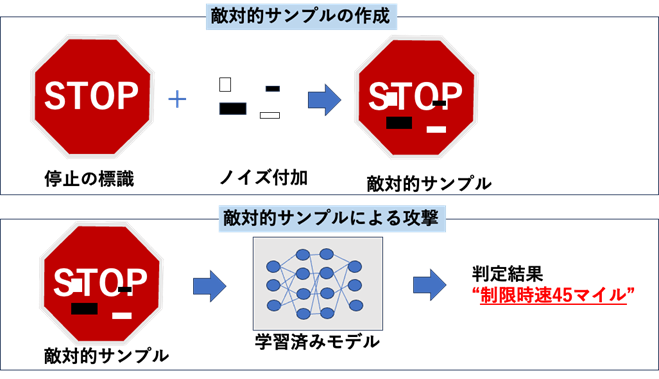
�} 4‑34�@����U���i�G�ΓI�T���v���j�̃C���[�W
�Q�l�@Eykholt �ق� "Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Models", CVPR 2017, arXiv:1707.08945
�A ����AI�ɑ��鋺��
�������ڂ���Ă��鐶��AI�Ƃ́AAI�ɂ��܂��܂ȏ����w�K�����A���p�҂̗v�������ɏ]�����e�L�X�g�A�摜�A�����Ȃǂ̐l�H�I�ȏ������A�o�͂���@�\��L����B�I�[�v��AI�Ђ��J������ChatGPT�AGoogle���J������Bard�ȂNJe��LLM(��K�͌��ꃂ�f��)�𗘗p��������AI���o�����Ă���B���̂悤�Ȑ���AI�ɑ��Ă��ȉ��̂悤�ȁA���܂��܂ȋ��Ђ��w�E����Ă���B
�EAI�T�v���C�`�F�[���U��
�����̎��p�I�Ȑ���AI�́A�I�[�v���\�t�g�E�F�A����J���ꂽ�f�[�^�𗘗p���Ă���A�I�[�v���\�t�g�E�F�A�ɑ��݂���g�f�V���A���C�Y�Ǝ㐫�h�̈��p�A���邢�́A���J���ꂽ�f�[�^����������Ă���g�|�C�Y�j���O�U���h����\��������B�����ŁA�f�V���A���C�Y�Ǝ㐫�Ƃ́A�e�������f�����L�̃f�[�^�t�H�[�}�b�g�Ńp�b�P�[�W�����ꂽ����AP���f�����_�E�����[�h���ė��p����ہA�C�ӂ̃R�[�h�����s�ł���Ǝ㐫�̂��Ƃł���B�܂��A����AI�ɑ���|�C�Y�j���O�U���Ƃ́A��������Ă��Ȃ��L�͂ȃf�[�^�\�[�X����f�[�^�����W���邱�Ƃ���ʓI�Ȑ���AI�̃��f���ł́A�f�[�^�Z�b�g���\������URL�̃��X�g����邽�߁A������URL��̃f�[�^���U���҂ɂ���ĉ��ς����U���ł���B
�E�_�C���N�g�v�����v�g�C���W�F�N�V�����U��
Chat-GPT�Ȃǂ�LLM�i��K�͌��ꃂ�f���j�ɑ��āA�U���҂��A�Ӑ}�I��LLM����s���ȉ�e�L�X�g����͂���U���ł���B�U����v���p�K���_�A���I�ȃR���e���c�A�}���E�F�A�Ȃǂ��o�͂�����A���邢�́A�l����s���ɉ�����Ȃǂ��U���̖ړI�Ƃ��Ă���B����AI�́A��ʓI�ɗϗ��I�ɖ��̂���₢���킹�ɂ͉����Ȃ��Z�[�t�K�[�h�̎d�g�݂���������Ă��邪�A�{�U���͂��̃Z�[�t�K�[�h�����蔲���邽�߃W�F�C���u���[�N�Ƃ��Ă�Ă���B
�E�C���_�C���N�g�v�����v�g�C���W�F�N�V�����U��
�_�C���N�g�v�����v�g�C���W�F�N�V�����U���Ɨގ����Ă��邪�A����AI���O���̃f�[�^��Web�T�C�g���A�N�Z�X����ۂɁA����AI�ɕs���ȓ����������C���W�F�N�V�������N�����f�[�^��API�ɂ��U���ł���B���̍U���́A����AI�̃��\�[�X��Q�����DoS�U���A��������ʂ�����U���A�v���C�o�V�[����D�悷��U���Ȃǂ�ړI�Ƃ���B
�����AI�Ɋւ���e��̍U���ɑ��A�l�X�ȑ�̌������i�߂��Ă���i�K�ł��邪�A�Ⴆ�A���_���f���ɑ������U���Ɋւ��ẮA��ɂ�萄�_���f�����x�̒ቺ�A�������ׂ̑���ȂǁA���S���Ɛ��x�̊Ԃɂ̓g���[�h�I�t������A�������̉��P�����߂���B�]���āA�����ł́AAI�̋��Ђ��ɘa���邽�߂̃��X�N�}�l�W�����g�̃t���[�����[�N��AI�ɑ��鋺�Е��͂Ɋ�Â��Z�L�����e�B�K�C�h���C���̌����ɂ��ďq�ׂ�B
�\ 4‑9�@AI�ɑ���U��
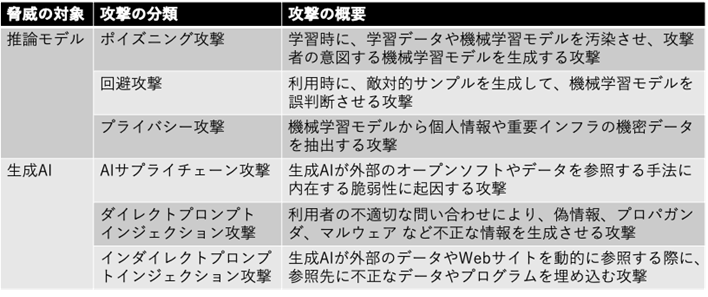
4.1.5.3�@ AI�̃��X�N�}�l�W�����g
�ӔC�̂���AI�V�X�e���̊J���A�����p���s�����߂ɂ́AAI���X�N�}�l�W�����g�́A���ƂȂ�B���̂��߁A�����O�ɂ����āAAI���X�N�}�l�W�����g��Z�L�����e�B�K�C�h���C���̌������i�߂��Ă���B�����ł͂��̑�\�I�Ȏ��g�݂��Љ��B
�č�NIST��2023�N1����AI���X�N�}�l�W�����g�t���[�����[�N�iAI RMF�j�����J�����BAI RMF�́AAI�V�X�e���̐v�E�J���E�z���E���p���s���g�D�e�X���A���g�D�Ɋւ��AI�̃��X�N�́E�]���E�ጸ���A�M���ł���ӔC����AI�V�X�e���̊J���Ɨ����p�̑��i��ړI�Ƃ��Ă���BAI RMF�ɂ��ẮA���߂ʼn������B
2024�N1���ɂ́A���ۋK�iISO/IEC 42001 AI�}�l�W�����g�V�X�e�����K�i�����ꂽ�B�{�K�i�ł́AAI�V�X�e�����J���A�܂��͎g�p����g�D��ΏۂƂ��A�g�D��AI�V�X�e����K�ɗ����p�i�J���E�E�g�p�j���邽�߂ɕK�v�ȃ}�l�W�����g�V�X�e�����\�z����ۂɏ��炷�ׂ��v�������ɂ��āA�g���X�N�x�[�X�A�v���[�`�h�ɂ���ċK�肵�Ă���B�M�����ⓧ�����A�����ӔC�������AI�V�X�e���̗����p���ł���悤�A���̃��X�N����肵�A�y������Ƌ��ɁAAI�̌�������l�̃v���C�o�V�[�Ȃǂւ̔z���ɂ��Ă��v�����Ă���B
�@�����ɂ����ẮA2019�N�ɓ��t�{�̓����C�m�x�[�V�����헪���i��c�ɂ����āA�u�l�Ԓ��S��AI�Љ���v�����J����Ă���A���̂Ȃ��ŁAAI�ɂ�����v���C�o�V�[�m�ۂ�Z�L�����e�B�m�ۂ̌������L�ڂ���Ă���B�܂��A2022�N6���ɂ́A���{�\�t�g�E�F�A�w��@�B�H�w������iMLSE�j�ɂ����āA�u�@�B�w�K�V�X�e���Z�L�����e�B�K�C�h���C���v�����肳��Ă���B�{�K�C�h���C���ł́A�@�B�w�K�V�X�e���̊J���ҁE�T�[�r�X�Ҍ����ɁA�@�B�w�K�V�X�e�����L�̍U���ɑ���Z�L�����e�B��菇���������̂ł���B�Z�L�����e�B��̎��{�ɂ����āA���ׂ����Ƃ̔c����A���{���̊J���ҁE�T�[�r�X�҂Ƌ@�B�w�K�Z�L�����e�B���ƂƂ̈ӎu�a�ʂ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��������ŁA�@�B�w�K�V�X�e�����L�̍U���ɑ���Z�L�����e�B��̎菇�������u�{�ҁv�A�@�B�w�K�Z�L�����e�B�̐��m�����Ȃ��V�X�e���J���Ҏ��g�ŕ��͂����@���L�ڂ����u���X�N���͕ҁv�A�@�B�w�K�V�X�e�����L�̍U���ɑ��錟�m�Z�p�_���ށE���������u�U�����m�Z�p�̊T�v�v�̎O���\���ƂȂ��Ă���B
�t���[�����[�N��K�C�h���C���ɉ����āA2023�N12���ɂ́A���B�A���iEU�j�ɂ��AI�K���@�āuEU AI ACT�v���b�荇�ӂ���Ă���BEU AI ACT�́A�����ɂ��EU�̒P��s��S�̂ň��S�ŐM���ł���AI�̊J���Ɨ����p�𑣐i���邱�Ƃ�ڎw���Ă���A �g���X�N�x�[�X�A�v���[�`�h�ɏ]���ĎЉ�ɊQ���y�ڂ�AI�����̔\�͂Ɋ�Â��ċK������A ������gthe higher the risk, the stricter the rules�h�i���X�N�������قǁA���[���͌������j�̌����Ɋ�Â��Ă���B�܂��AEU�ɂ�����v���C�o�V�[�̖@�K���ł���GDPR�Ɠ��l�Ɉ�O���K�p�ΏۂƂȂ��Ă���AEU�O�̎��Ǝ҂��AEU�ݏZ�҂�ΏۂƂ���AI�V�X�e����T�[�r�X�����ꍇ���K���̑ΏۂƂȂ�B����ɁA�{�K���Ɉᔽ�����ꍇ�A�ő�3500�����[�����邢�͔����7%�̔����K�肪�݂����Ă���B
4.1.5.4�@ AI ���X�N�}�l�W�����g�t���[�����[�N1.0 (AI RMF)
AI�Ɋւ��l�X�ȃ��X�N���I�ɔc�����A�K�ɑΏ����邽�߂̘g�g�݂ł���NIST�����J����AI RMF�͂Q�̃p�[�g�ɕ�����Ă���A��ꕔ�ł́A�g�D��AI�Ɋւ��郊�X�N���ǂ̂悤�ɋK�肷�邩�̘g�g�݂���AAI�̃��X�N�ƐM�����ɂ��ĕ��͂��s�Ȃ��Ă���B��̓I�ɂ́A���X�N���Ǘ����邽�߂ɁAAI�̐M�����ɂ��āA�} 4‑35�Ɏ��������̓������K�肵�Ă���AAI�Ɋւ��g�D���A���̖ړI��[�X�P�[�X�Ɋ�Â��A�����̓�����K�ɍl������g�g�݂��K�肵�Ă���B
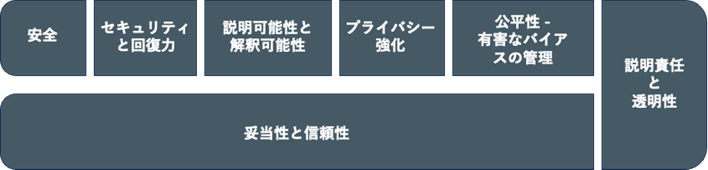
�} 4‑35�@�M���ł���AI�V�X�e���̓���
��ł́A�e�g�D��AI�V�X�e���̃��X�N�͂��A�{�t���[�����[�N�����H���邽�߂́g�R�A�h�ƌĂ��S�̋@�\�A����(Govern), �}�b�v(Map), ��(Measure), �Ǘ�(Manage)���K�肵�Ă���i�} 4‑36�j�B�����ŁA����(Govern)�́A�g�D��AI���X�N�}�l�W�����g�v���Z�X��葱���̑S�ĂɊւ�鉡�f�I�ȋ@�\�ł���B����A�}�b�v(Map), ��(Measure), �Ǘ�(Manage)�́AAI�V�X�e�����L�̊��i�R���e�N�X�g�j��AAI�V�X�e���̃��C�t�T�C�N���ɂ�����e��ʂœK�p�����@�\�ł���B
����(Govern)����у}�b�v(Map)�́A�g�D�̏܂��āA���X�N�}�l�W�����g�Ƒg�D�����Ă����v���Z�X�ƍl�����A���Ƀ}�b�v(Map)�́AAI�̃��C�t�T�C�N���ɂ����āA���l�ȊW�҂��֗^���鑽���̑��݈ˑ��I�Ȋ�������\�������Ȃ��ŁA�R���e�N�X�g�ƌĂ��AI�V�X�e���̖ړI�E�O��E����E�\�z����郊�X�N�Ȃǂm�����A�݂��ɋ��L�A��������ȃv���Z�X�ƂȂ��Ă���B��(Measure)�́A��ʓI�E�萫�I�A�܂��͕����I�Ȏ�@�̃c�[���A�e�N�j�b�N�A���@�_��p���āAAI���X�N�Ɗ֘A����e���́E�]���E�x���`�}�[�N�E���j�^�����O����v���Z�X�ł���A�Ǘ�(Manage)�́A�}�b�s���O����A���肳�ꂽ���X�N�ɑ��āA����I�ɁA����(Govern)�̕��j�ɏ]�����X�N������z������v���Z�X�ƍl������B
�@����AAI�́A�w�K�f�[�^���̂��̂̐M������w�K�f�[�^�̎��ԓI�ȕω����l�������^�p���K�v�ƂȂ�_�AAI�̏o�͂��A�w�K�f�[�^�ɂ�鐳���ȏo�͂Ȃ̂��A���邢�́A��Q��AI�ւ̐N�Q�ɑ���ُ�ȏo�͂��̔��ʂ�����ȂǁA��Q���m�E�ُ팟�m�̍�����w�E����A��ʓI��IT�V�X�e����\�t�g�E�F�A�̃��X�N�}�l�W�����g�Ƃ͈قȂ�_�����X����A��L�̂悤��AI�V�X�e���̓������l�������t���[�����[�N�ƂȂ��Ă���_�����ڂɒl����B

�} 4‑36�@AI�̃��X�N�}�l�W�����g�������\������@�\